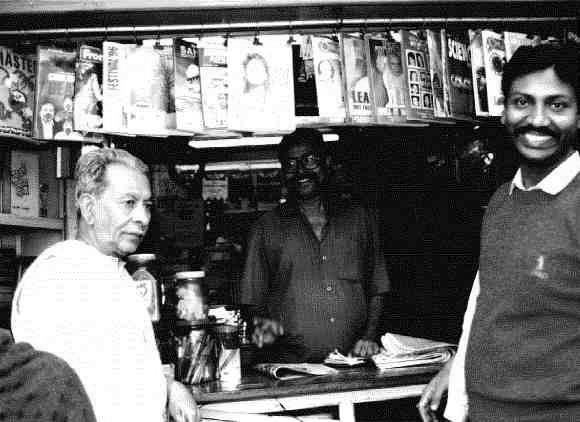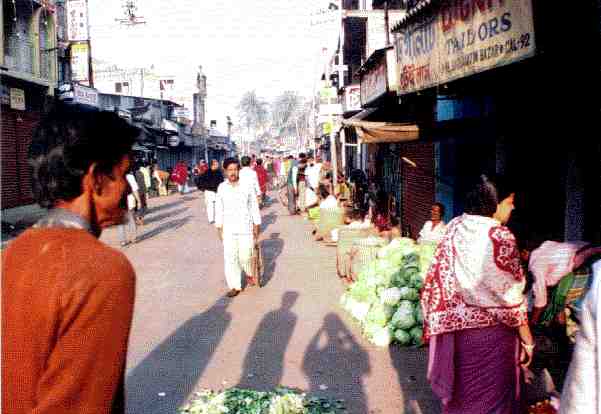| よく見知らぬ人から声をかけられることがあります。「インドの方ですか?」「暑いお国でしょう、インドは?」 「額に付けているものは何というのですか?」「サリーって本当にきれいですね。どのように着られるのですか?」「インドはカレーの本場でしょう?」 等々、実に細かく他愛のない質問ばかりです。 またインドについて、このホームページを通じ多数の質問も寄せられます。なかには「これからインドに旅行するのですが、どのような点に注意すれば好いでしょうか、アドバイスをお願いします」とか「インドの大学に留学したいのですが、どの大学が良いか知りたいのですが…」というものや、あるいは大学で「インド古典舞踊を研究しているので詳しく教えて下さい」といった学生の方からの具体的専門的な質問もあったり内容は多岐に渡り様々です。私はこれらの質問に対し、私の解る範囲内で出来るだけ返事をすることにしています。総じてどの方もインドに対し好ましい印象を抱いて下さっておられるようですが、ただ残念なことはインドは昔から日本と深いつながりを持つ国であるにも関わらず、その情報はきわめて大雑把にすぎるといった印象をうけます。例えば上に記したような「暑いお国でしょう、インドは?」という質問の一般認識がどのていど精確なものであるのか…。インドは国土も日本の約9倍近くあり南北に長く東西に広がっており、山岳地帯もあれば高原もあり砂漠もあれば常夏の地帯もあるわけですから、暑いところもあれば寒いところもあり、とても一括りで「インドは暑い国である」とは言えないわけです。カレーについても、日本のカレーはイギリスから改良されて入ってきた経緯を持ち、全く同じもののように考えられがちですが、インドと日本のカレーにおけるその実質はおおよそ違ったもので、質量ともに日本とは比較にならないくらいインドのカレーはヴァリエイションに富んでいます。要するにインドと日本のカレーは同日には語れないということなのです。また「手を使って食べる」習慣に日本の人は興味をそそられるようですが、手で直接食べる習慣は何もインドばかりではありません。世界史的にみれば手で直接食べる習慣の方が主流でありヨーロッパに於いてさえ18世紀まではナイフもフォークも使ってはいませんでした。当時ヨーロッパの文化先進国であったイタリアでさえ16世紀の段階ではごく一部の貴族階級のみがようやくナイフやフォークを使いはじめた程度であり、他はみな素手で食べていたわけです(箸を使って食べる中国、朝鮮、ベトナム、日本の方が少数派に属していたのです)。またインドの人々も日本に対する認識の誤りが多く見られます。一例を上げれば日本の代表的食文化の「寿司」や「刺身」など食べ方のイメージが湧かず、捕った魚をそのまま包丁も入れず丸ごと食べていると考えている人もいます。インドと日本は心情的には互いに身近なイメージを抱きながら、事実は実に遠い懸隔を持っているようです。過剰な情報競争は刺激的なニュースを生み出し、ただ売らんがための偏向へと突出して走ります。しかし情報の氾濫している現代に於いてさえ、精確且つ客観的な情報というものは少なく、また述べられていることが事実であっても、それは事の一面に過ぎないということを十分考慮に入れ情報を取り入れて頂きたいと思うのです。 |