U.Gallery
王子と乞食 | ||
かつて、王子と呼ばれていた事がある。誇り高き戦闘民族の生き残りとして、どこまでも強さを求めていた事がある。夜空に向かって手を伸ばしながら、いつか自分はあの輝く星をも超える高みに昇る存在になるのだと、信じていた事がある。けれど、いくら手を伸ばしても、ついに夜空の星に手は届かなかった。
夜闇が忍びやかに空を覆い、月が青ざめた姿を露わにする。先程まで天窓から斜めに陽が射し、あれほど赤く燃えていた壁が今はすっかり深い青に塗りつぶされていた。どこからともなく夜露に湿った草の匂い、月夜の匂いがする。
「う…………ぅ…………ん」
一糸まとわぬ無防備な背中に、忌まわしい喜悦を秘めた視線が注がれる。緑色の双眸が放つねっとりとした視線を感じて思わず声が漏れ、曝け出された後ろの穴をひくりと締めてしまい、体が震えた。
そこは広く、殺風景な部屋だった。唯一壁には大きな古鏡が掛けられていて、自分が横たわる寝台は鏡に全貌が写る位置に設置されていたから、少し顔を動かせば視線の主が誰なのか、この目で確認する事もできるだろう。けれど、そんなものに頼らなくともオレは背後の存在をひしひしと感じる事ができた。見なくたって分かる、背後ではオレの同族が……アイツが、ふんぞり返って座っているのだ。整った容貌をした筋骨たくましい男。ほとんど裸に近い軽装だが、その印象は無防備というには程遠い。口元には冷たく尊大な笑みを浮かべ、どっさりと溢れるように豊かな金髪が鎧そのものの盛り上がりを見せる肩や背中までを覆っている。
月の光が増すごとに、オレ達サイヤ人の力も増大する。かつてオレは、この力さえあればできない事など何もないと思っていた。オレが望めば、この世界で手に入らないものなど何一つ無いと思っていた。けれど今は力の昂ぶりがオレを虚しくさせる。オレはとうとう、この世にはいくら望んでも手に入らない物も、越えられない壁もあるのだということを、知ってしまったのだ。
「そら、もっと足開いて、おめえの淫乱な尻穴を良く見せてみろよ」
低く、どこか上機嫌な声がする。毒のように甘い声だ、絶対的な支配者の声。オレが逆らう事は許されず、声に命じられるまま相手に背を向けて四つん這いになり、おずおずと両足を開いた。
「そんなにケツの穴ヒクつかせて、散々オラが挿れてやったのにまだ足りねえのか?本当に食い意地の張った尻だよなあ」
王者の覇気と子供の稚気をはらんだ声に恥ずかしめられても、オレは唇を噛みしめたまま答えられなかった。誇り高きこのオレが、かつてぶっ殺してやろうとした奴を前に、裸で這いつくばって股を開いている。堕ちたものだ、少し前のオレがこのざまを見たら憤死ものだろうな。捨て鉢気味に思いながら、けれどこの頃そんな自棄すら忘れそうになっている事を、薄々感じていた。
「早くこの淫乱な穴にオラのをぶち込んで、塞いでほしいんだよな?」
やつの声がオレの背後に近付いて、太い指が尻の狭間に伸ばされるのを感じた。それからゆっくりと窄まりを撫でられる。濡れそぼり、柔らかくほぐれた襞を伸ばしながら、時々からかうように指先が窄まりに潜り込まされる。
「ふ……ン、ぁ………」
固い指先がぬめりに助けられて深く突き入れられるかと思った瞬間、指は引き抜かれ、お預けを食らったように物欲しげに喘いでしまう。自分の声をどこか遠いもののように聞きながら思う。オレはおかしくなってしまった。かつて貪欲に強さだけを追い求めていた誇り高き王子は、どこへ行ってしまったのか。
時間の移りは本当に早い。この簡素な牢獄に押し込められてヤツに犯され続けながら数日、ずっとそれを思ってきた。…数日?いや、もっとか…
「そうだ、たまには違うものが食いてえんだろ?ちょうど良かったな、こんなのも持ってきたんだ」
何気なく視線を動かして、ヤツが革袋から取り出したものを目にした途端、オレは枯れ果てたはずの叫び声をまた上げそうになった。それは全長が20cm近くもありそうな、長く太い男性器を模したもの……バイブだったからだ。柔らかそうな肉質の本体にはコードの先にコントローラーがあり、摘みをひねるとモーター音と共に全体が細かく震動した。
「早く挿れてみてえだろ。オラのが入っちまうんだから、これくらい余裕だよな」
ちゃんとローションも塗るからさ。やけに明るい声を聞きながら、オレはまた体が震え出すのを感じた。何度もヤツに指を入れられたが、器具を突っ込まれた事は無い。これから無機物で後ろを犯されるのだという恐怖と屈辱に、声が震えるのを止められない。
「止せ、無理だ…やめろ………っ」
「無理じゃねえよ」
震える声での懇願、しかしそんなもので目の前の男が情けを掛ける事は無い。バイブにローションを塗りながらオレに向けられたヤツの目は、平常時の呑気なものでも、交戦時の興奮したものでも無い、もっと威圧的で恐ろしい視線だった。
「おめえの尻はいくらほぐしてもすぐまたキツキツになっちまうからな。こいつで慣らしてやろうっていうんだ、もっと喜べよ」
「嫌だ、いや……!」
圧倒的な力がオレの上体を押さえつけ、尻だけを高く上げさせる。
「力抜け、入れるぞ」
「ぁ………あ!ぁ………ぁああぁ………っ」
狭くぴたりと閉じた穴に冷たい器具が押しあてられ、逆方向からこじ開けられて太い異物で蹂躙された。痛みと圧迫感、続いて奥のいいところを押されて甘くくすぐったいような痺れるような感覚が一気に襲い掛かり、喉から搾り出した声を上げて身を捩る。これまで散々犯され、いたぶられ続けた窄まりは懸命に襞を伸ばして異物を受け入れ、少しでも楽になろうと力を緩めればそこはひくひくと喘いだ。
「ほら、全部入ったじゃねえか」
「……っン、っう………」
奥まで入っているモノを揺さぶられ、痛み以外の感覚にシーツをきつく握って耐える。その途端押しこまれた器具を締めつけてしまい、その全長を否応なく感じてしまう。
「んふぁ…………っ」
「ケツ穴が喘いでる。気持ちいいんだな。いいぞ、もっと遠慮なく食えよ」
「っ…?!」
突っ伏していた上体が思わず跳ね上がる。くぐもったモーター音がして、窄まりに埋め込まれた器具が、体内で細かく震動を始める。
「い、やだ!ぁ……カカッ……ぁああ!あっ!あーっ!」
いやらしい歓喜が尻の奥で弾けて、器具の振動に押し出されて先走りが噴き出してくる。射精する時のような目も眩むような快感にたちまち昇りつめ、けれど吐精はしなかった。刺激が強すぎて射精する事ができない。
「ぁあ、ひっ、やあぁああっ!」
「尻を振りまくって、いやらしいな。おめえのちんちんもヨダレ流して喜んでるぞ」
「あっあぁ、ん!っああっ!」
感じすぎて痛みすら伴う刺激が、止まることなく続いている。快楽の箇所を容赦なく刺激する器具から逃れようと必死の抵抗を試みるが、結果みだらに尻をくねらせてヤツを喜ばせただけだった。
緩急をつけて器具がぬるぬると抜き差しされる。時々振動する先端を内壁に強く押しつけられ、尻全部が性感帯になって大きなうねりのような快感が押し寄せる。苦しい、自分の性器は弾けそうなほどに張りつめているのに、一向に絶頂の気配は来ない。ただ淫靡な悦びだけがオレを満たし、切ない声を絞り出させた。
「あーーーっ…………ぁ……あ………っ」
散々尻穴をいたぶられた後、やっとバイブが止まり、疲労し切ったオレは全身の力を抜いて弛緩した。荒い息をつきながらヤツを睨みつけるオレの目は、きっと潤みきっているに違いない。
「うーん、まだ全然足りねえって顔だな」
目の前の男はオレを見ながらうっすらと笑っていた。いや、笑っているように見えるだけだ。口の端が片方吊りあがってはいるが、緑色の両目は冷たいまま燃え盛り、少しも温もってはいない。突然勢いよくバイブが引き抜かれ、きゅぽんと間抜けた音がした。
「ケツの穴をこんなにぐちゃぐちゃのトロトロにしやがって。やっぱりこんな道具、おめえの尻じゃ全然物足りねえよな」
背後でぐしゃりと何かがへし折られる音、それから器物が無造作に投げ捨てられた音がした。ヤツの声を聞きながら、悔しさに固く閉じた両目から我知らず涙が溢れる。けれどそれが本当に悔しいからなのか、それとも過ぎる快楽のせいなのか、もう良く分からなくなってくる。あざけるような視線を背後に感じながら、ヤツの言う通り淫靡な窄まりは咥え込んだものを奪われて、物欲しげに喘いでいた。もう自分の意思で止める事ができないほどにそこはひくひくと喘ぎ、そのたびにねちねちといやらしい水音が聞こえて、一層オレを絶望的な気分にさせる。
「なあ、やっぱり道具よりもオラに挿れてほしいんだろ?おめえの口から言ってみせろよ」
「誰がキサマなんかに……っひ……っ!!」
思わず息を飲む。オレの背後に重く分厚い体がずしりと圧し掛かる感覚。続いて尻穴に、火傷しそうなほど熱く、圧倒的な質感を持った太いものが押しあてられる感触。
「いいから、言ってみせろよ」
「いや……いやだ………っ」
これからまたオレはこいつに犯されるのだ。重い体に抑え込まれながら、オレはもう情けない事に震えが止まらず、体は委縮し切って完全に力を失っていた。
「いやだ……やめ……」
がくがくと体を震わせながら、見開いた両目からとめどなく涙が溢れる。
「ほら、さっさと言えって」
いっそ優しいとすら思えるような、低い声が耳元で響く。それに合わせてオレの尻穴に押し付けられた太いモノが、入口をこじ開けるように少しずつ窄まりを押しながら、ゆっくりと円を描いて動かされる。思わずそれを弾き返そうと尻に力を入れると、今度は押し入るように窄まりの真ん中を強く押される。
「早く言え。言わねえと…」
「………………」
『早く挿れてくれ』とヤツの思うままの言葉を口にしようとして、拳を握りしめて踏みとどまる。怯えきって震えながら、それでもオレはなけなしのプライドを引っかき集め、情けなく慈悲を乞いそうになる口を固く閉ざした。どれほど無様な姿を晒そうと、完全なる敗北だけはするものか。オレは精一杯の気迫を込めて、背後の男を肩越しに睨み上げた。
「……まったく、おめえの意地っ張りも相当だよな」
溜息のような、呆れた声が肩越しに聞こえた。
「―――ちょっとは優しくしてやろうかと思ったけど、やっぱ止めた」
何が、と聞き返す暇も無かった。尻たぶを掴まれて高く腰を持ち上げられたと思った瞬間、再び灼熱の太いものが押し付けられ、今度は情け容赦無くオレの中に突き入ってきた。
「うぁ…あ、ああああああああああっ!!!」
あまりの衝撃に、背骨が折れるほどに体を仰け反らせ、もはや枯れ切ったと思われた喉から絶叫が迸る。
「ぁああっ、はあ…っ!!……カカ…いや、だ…ああぅ…っ…はっ…ぁ……っ!!」
無理に広げられた体内が悲鳴を上げ、骨盤が軋む。犯される恐怖、全身を覆う激痛、自由を奪われ淫らな格好を強要される屈辱。何度味わっても慣れる事は無かった。けれど、それだけじゃなかった。
「イヤだっ、痛、ぁっ…んっ!!」
「痛えだけじゃねえだろ、感じてるんだろ?」
尻肉と腰が打ち合わされる音と、次第に甘さを帯びていく自分の声。体の奥の奥まで詰め込まれ、広げられ、快楽の源をリズミカルに刺激される。
「んっあ……いた…やだ、あぁあっ!あっはっ……っ!」
屈辱と恐怖、それに快感が混じり合って、どうして良いか分からずただ泣き叫ぶ。顎が外れたかのように開きっぱなしで閉じる事ができなくなった口から、きつく閉じた両目から、そして触れられてもいないはずの自分の性器から、たらたらと熱い何かが溢れ落ちる。
「いいかベジータ、良く覚えておけよ」
耳元でまた、毒のように甘い声がする。真の王者の声だ。オレの体は繋がったまま軽々と抱え上げられ、膝裏を掴んで思いきり股を開かされた。
壁に掛けられた大きな姿見にオレの姿が余すところなく映し出されて、またオレのプライドをズタズタにする。目の前の鏡には、これほど耐えがたい屈辱を受けながら、立ち上がって張りつめ、快楽の涙をたらたらとこぼし続けている自分のいやらしい性器も、はしたない窄まりが襞を目いっぱい広げて太いものを飲み込み、離すまいと貪欲に締めつけている様も、何もかもが隠しようもなく映し出されていた。
「…あ……ぁっ、や…だ……っ…」
あまりの恥辱に顔を背けようとしても許されず、大きな手に顎を掴まれ無理やり正面を向かされる。
「おめえは始めから、オラに負ける運命だったんだ」
太い指が、裂けるほど広げられた窄まりの縁をゆるやかに撫でる感触に、自分が何を咥えこみ、嬉々として飲み込んでいるのかを思い知らされる。その間にも抽出は止む事無く続けられる。
「弱い者は滅ぼされるってのはサイヤ人の信条だったんだよな。おめえは弱いから、負けるんだ」
「あっ、あんっ!…触る…な……はぁっ…あ…ああっ!!」
「言ってみろよ、『イカせてください』って。今日はちゃんと言えるよな?」
目の前に映る、二周りも大きな体に抱え上げられ、深々と刺し貫かれている自分。がくがくと激しく揺すぶられながら、きつくしかめられていたはずの顔から苦痛が消え、喜悦と恍惚に支配されていく。
「ほら、早く言えって」
「ああぁーー……っ……ぁあ!!っあ!」
太いもので体の内側を擦られるたび、ぐちゃぐちゃと卑猥な音が接合部から聞こえ、脳が焼き切れるほどの快感に見舞われる。今にも崩れ落ちそうな自尊心、もう何もかも投げ出して精を吐き出してしまおうにも、その度に後ろからの突き上げは痛みすら伴うほどに激しさを増し、どうしてもイク事が出来ない。あまりにも長い拷問のような快感、頭の中で極彩色が渦を巻き、次いで全てが白くなり何も考えられなくなる。
「…頼む……て」
「ん?何だ、聞こえねえぞ」
揺すぶられ続け、だらしなく開いた自分の口から、うわ言のような呟きが聞こえる。
「もう……イカせ…て…くれ……」
「おいおい、それが人に物を頼む態度かよ」
真っ白に燃え盛る世界が張力の限界に達し、ひび割れて細かな破片を落としながら崩れていく。ずるずると出し入れされる太いものに意識の全てを支配され、もっと深く、もっと強く突いてほしいと願う。この望みが叶えられるなら、オレはもう…
「……イカせて……くださ……い、っ…」
「よし、良く言えたな」
ご褒美だ、と言われたところまでが、意識を保てた限界だった。直後に、これまでよりも一層深く突き入れられ、同時に一度も触れられなかった性器を大きな手で包まれて激しく擦りあげられた。
「あっ、あぁあああああぁああああっ!!」
前と後ろから同時に与えられた、これまでで最も強い圧倒的な快楽。枯れ果てた喉が引きちぎれる程に声を上げ、限界まで張りつめていた性器が遂に白い迸りを噴きこぼす。
「はぁ……ぁ……」
吐精の余韻に体がびくびくと痙攣し、沸点をとっくに超えた意識は目もくらむほど白く輝き、次いで暗転する。体中の力が失われ、自分の腹に吐精したばかりの白濁がゆっくりと流れ落ちるのを感じながら、オレの意識は闇に飲まれた。
「なんだ、もう気絶しちまったのか」
深淵の奈落に向かって、どこまでも落ちていく。吹き付ける冷たい風に引きこまれてこの淵を落ちたら、もう二度と這いあがる事は出来ない。
「まあ、後はオラの好きにさせてもらうとするか」
かつて、王子と呼ばれていた事がある。比類なき強さを誇り、貪欲な程純粋に強さを求めていた事がある。何人にも決して膝を付かず、誇り高く振る舞っていたオレは、ある日突然深い淵に落ち消えてしまった。ここにいるのは自分の非力さ故に敗北した、ただの弱者だ。精を受け入れ、慈悲を乞い、与えられる快楽をむさぼり続ける、堕落した存在だ。

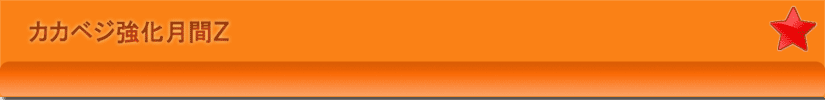
 さめない熱
さめない熱
 U.illust/Novel / イラスト小説
U.illust/Novel / イラスト小説 BBS / 掲示板
BBS / 掲示板