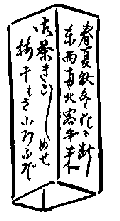|
私ども、茶亭「さはら」では、この行燈を江戸の百花園開設時より掲げてまいりました(勿論、書き換えなどをいたしてはおりますが)。 この行燈について、コピーライトという視点から右記の谷様が考察されたものを、一部抜粋させていただきご紹介申し上げます。
|
「江戸のコピーライター」著書紹介
谷 峯蔵(たにみねぞう)
主な著書
『洒落のデザインー山東京伝「手拭合」-』(共著、岩崎美術社、六十一年)、『写楽はやっぱり京傳だ』(毎日新聞社、六十年)、『遊びのデザイン-山東京傳「小紋雅話」-』(岩崎美術社、五十九年)、『写東新考-写楽は京傳だった-』(文藝春秋、五十六年)、『暖簾考』(日本書籍、五十四年)、『芭蕉堂七世・内海長大』(千人社、五十二年)等がある。
昭和六十一年十二月二十日初刷発行、発行者 佐 藤 文 夫、発行所 ㈱ 岩崎美 術 社
|
実用文型はコピーの原点
「呉服物現金安売り掛値なし」をキャッチフレーズに「一銭にても空値申上げず侯間‥‥‥、一銭にても延金には仕らず侯」とした強い企業哲学を率直に打ち出し、まったく冗語をはさまなかった越後屋三井の天和三年三月の引札は、実用文形式のコピーの最たるものである。
そのビジネスに徹した結果は、越後屋の繁栄をもたらした。
「広告は〔効く〕ためにある」と、田原晋『日本のコピー発想法』は宣言している。越後屋の引札は、その言を明確に証明したと言えるし、マーケッティング活動を支えたコミュニケーション、つまりマーケッティング・コミュニケーションを完全に昇華させたのが、このコピーだったと言えるのである。
(中略)
実用文形式の表記形態はコピーの一つの系譜として三百年を経た今日にもつながっている。
なぜ、このコピー形態が、消耗的回転率の早い広告の世界で絶えることがないのか。それは日本的商風土と感性の中では、社告的な場合に利用されるコピー形態が堅実な印象を与えるからで、今後も絶えることのない軌条に続くであろうことは、十分に想像される。
ところで、『七十一番職人尽歌合』に示された平安期の貴族言葉そっくりと思われるコピーが、今も生きて使われている。
それは向島百花園の茶亭「さはら」の軒先きに掛けられた行灯に、「お茶きこしめせ梅干もさふらうぞ」と書かれているものである。
これは、どう見ても実用文とは言いにくい。
だが、短文で素直に語りかけた貴族言葉は、戯文ではなく、もちろん洒落や地口でもない。完全に貴族言葉を実用におきかえたキャッチ・フレーズであり、優れたコマーシャル・メッセージであり、適切なコピーなのである。
百花園は、文化年間、佐原鞠塢が向島・寺島村の代官屋敷の跡地一町歩(一万平米弱)の地に庭園を開き、これに梅樹三百六十本を植え、かたわら秋草を添えて四時遊観のところとした。
爾来、花屋敷または新梅屋敷と呼ばれ、江東の名勝となり、園内に向島七福神の一つ寿星(福禄寿)を祀っていることから、園中でできた梅干を「寿星梅」と名付けて名物とし、亀田鵬斉(ぼうさい)の碑、大田南畝の額、大窪詩仏の聯(れん)などで飾ったが、橘千蔭(たちばなのちかげ)の筆に成った「お茶きこしめせ梅干もさむらうぞ」とした行灯が茶亭の軒先にかけられている(木村捨三編著『江戸時代商標集』)。
この鞠塢は酒井抱一に愛され、抱一が敬慕した光琳の墓修復のため抱一に代って京都へ出向き、その一切をさばいているほどの男だった。園中の茶亭には、十一代将軍家斉も遊び、いつごろからか百花園と呼ばれ、将軍お成り座敷は今も当時の面影を残したたたずまいであり、ここで一日の歓をつくすことができる。

|
百花園は昭和初年に東京市へ寄付され、現在は都の管理となっているが、茶亭「さはら」の管理と経営は鞠塢の血を継いだ佐原洋子氏があたり、今は氏のやさしい筆で「お茶きこしめせ梅干もさふらうぞ」と、読みよい仮名遣いに書き改めた行灯になっている。
それはそれで結構として、うるさく穿鑿(せんさく)すれは千蔭が書いたという「さむらうぞ」は「侯ぞ」で、『広辞苑』は〔さうらふ・さぷらう・さぷらふ・さむらふ〕は侯(そうろう)と同詞、〔居り・あり〕の謙譲語・丁寧語。鎌倉時代男性はさうらふ(ソウロウ)、女性はさぶらふ(サブロウ)と使い分け、室町時代には女性語として、さむらふが用いられたとし、また「ぞ」の助詞を、平安時代は多く清音の「そ」としたとしている。
鹿児島徳治著『隅田川の今昔』に、
花やしきお茶きこしめせ梅干も
さふらふぞとあり桝行灯に 中原綾子
とあり。明治三十一年発行の『風俗画報』百花園の部には、
千蔭が「御茶きこしめせ梅干もさむらふぞ」の掛行燈を……。
と記している。中原綾子の歌の「さふらふぞ」は、国学者千蔭とすれば、一語の中に同字を二字使ったとは考えられず、濁点をつけずに濁音で読ませ、すなわち清音で読ませて濁音を意識させた古文・雅文の用字例からも、当初、千蔭が書いたのは、茶亭であるだけに室町時代の女性語で「梅干もさむらふそ」だったように思われる。
行灯に筆を執った千蔭(享保二十年-文化五年〔一七三五-一八○八〕)は、江戸町奉行与力で、賀茂真淵に入門、本居宣長に師事した歌人であり国学者で、県居(あがたい・真淵の号)門四天王の一人。彼の『万葉集略解』は万葉集入門書として広く読まれ、書は仮名書にすぐれ千蔭流と称され広く知られている。抱一と深い親交だったことから、行灯に筆を執ったと思われるが、擬古文のこのコピー「お茶きこしめせ梅干もさむらふそ」こそ千蔭の案文だったのに相違ない。
普通なら、正面に屋号、両側は「大入叶」とか「千客万来」とした茶亭の掛け行灯だった。
だが、抱一や南畝の支援と、鵬斎、文晁、手柄岡持らとの親交からも、墨客の遊観をさそう梅屋敷だっただけに、この閑雅な行灯は文人たちの評価を得たのに相違ない。
季節きせつで花を見る会、虫を聞く会、茶会、句会、琴の会など常時行われているが、軒下の行灯は年ごとに張替えられ相変わらず「お茶きこしめせ梅干もさふろうぞ」とある。あらかじめ頼めば、句会や打合せ会のあと「酒(ささ)きこしめせ、田楽もさふろうぞ」で楽しい時をすごすことができる。
そして、この擬古文のコピーは二百年近くを経た今日も生き、百花園に興趣を添えている。これは、さきに述べたとおり秀れたコマーシャル・メッセージであり、適切なコピーだからなのである。
コピーとは、やはり、こうありたいものだ。

|