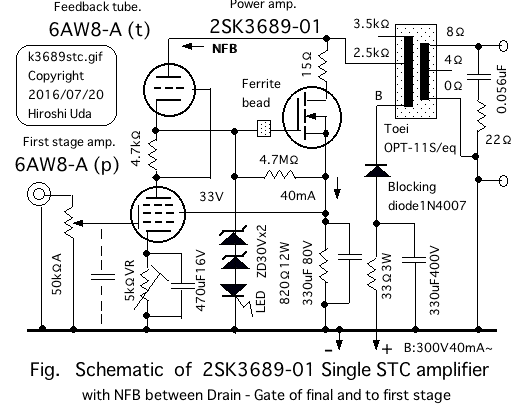1.1 抵抗分割 NFB アンプ試作 (2006/09)
高耐圧 MOSFET 2SK3689-01 を数個頂戴し、別項に示す試験回路 *2SK3689-01 R-div NFB を試作、一応実用になるレベルに調整しました。
まずは既に先行試作した、パワー BJT および電圧増幅三極管をダーリントン構成した、田中安彦氏が考案・実装した「球リントン」回路を、MOSFET にも適用すべく試作してみました。
球リントンでは信号を含む全カソード電流を BJT のベースに吸わせる所を、MOSFET では信号電圧をケードに与えれば良い訳です。 そこで三極管のカソードを抵抗にて接地し、カソード電圧および信号を MOSFET ゲートに入力する「球 MOS リントン」回路としたのですが、ダーリントン構成の NFB が効き過ぎか調整不足か・・・良い結果が得られませんでした。
そこで一旦後退、MOSFET 終段ドレーンから初段の負荷抵抗への動作電圧を供給する「抵抗分割 NFB 兼用 C/R 結合回路」にて、終段出力を初段の負荷抵抗およびその内部抵抗とで配分する、D-K NFB (drain~gate NFB) ・・・真空管回路での所謂 P-G NFB 相当の回路に再構成し直して「とにかく動作する状態」を得ました。 動作結果は若干高音の不足以外には特段の問題が見当らず、ドライバの改良が課題と見るも、次の試作は中断していました。
1.2. D-K NFB アンプ試作 (2012/12)
その後、上記の後{ディスクリート半導体終段による出力トランス付きアンプ}との基本仕様の試作課題が出ました。 その機会には、前記の抵抗分割 NFB アンプより、さらに真空管アンプに近いレベルに完成度を上げるべく、別項に示す試験回路 *2SK3689-01 D-K NFB に示す通り、下記の二項目を条件に構成しました。
(1) MOSFET の確実なドライブ
ダーリントン構成する以前に、カソードフォロワ・ドライブに適合する管種の選択方法を特定しながら、試作して実装にて確認しようと考えました。 上記の「1.1 抵抗分割 NFB アンプ試作」試験では「取りあえずの動作課題」が先行して MOSFET の入力容量課題は後回しでしたが、カソードフォロワ・トライブ回路併用では、正面から「どのような電圧増幅三極管ドライバーにてドライブできるか」を確認しようと考えました。
(2) ドレーン〜カソード NFB の適用
追試験での再現性を確保するため、真空管回路では所謂 P-K NFB と称される、二段アンプにて終段ドレーンから初段カソードへの局所 NFB である D-K NFB を適用しました。 この回路ならば、出力トランスはインピーダンス変換が主体、追試験の際に出力トランスの選択自由度を高く保ち得る点は、(準) 超三結アンプおよび P-K NFB アンプと同様です。
この試作にてドライバーに適する電圧増幅三極管を概ね特定しました。 試作の結果、前記の抵抗分割 NFB アンプよりはマトモな音を得ましたが、満足はせず分解・転用しました。
2.1 MOSFET に固有の課題
取りあえず行き当たった課題は、多極管終段による超三結の回路構成を「どのように MOSFET に適用すれば良いか」という点でした。 そこから基本回路を設定するに「何かヒントはないかな、経てきた段階を順に見たら見つかるかな」と発想して、過去の試作例を再度レビューしました。 直結部分がよく見えません。
バイポーラ Tr (BJT) 終段による超三結アンプ (2004/05 - 2006/03) の例では、終段素子である BJT のベース電極が電流駆動であるため、ダーリントン構成にした電圧増幅三極管が「全力投球」のカソードフォロワ・ドライブを行う「タマリントン回路」とし、初段は純粋の電圧増幅動作とした準超三結回路 (Semi-STC=SS) としたものでした。 タマリントン回路では超三結の帰還管の機能であるコレクタ〜ベース間の NFB、C-B NFB を包含しており、敢えて直結の超三結回路とする必然性はなく、安全な C/R 結合にて済むために助かっていました。 それらは、別項に示す試験回路 *2SC3486 SS および *2SC4029 SS に示すとおりです。
2.2 三極五極管の選択
本アンプでは、前段は容易にドライブ振幅がとれて所要部品数が少ない三極五極管一本で済ませました。 問題はドライバーに相当する三極管部の特性です。 D-K NFB アンプにて特定したような強力なドライバーは、大抵の三極五極管の三極管部では得難いのですが・・・試作用のシャーシに余裕スペースがなく、ドライブ不足を覚悟の上にて取りあえずは超三結アンプを構成し動作させよう・・・と意識しながら管種を決めました。
6U8/6U8-A に代表される、口金接続が 9AE の三極五極管はいずれも性能が高くて優れているのですが、超三結回路に使用すると G1p/Pt・・・五極管部の第一グリッドおよび三極管部のプレート・・・のピンが隣り合っており、飛びつき発振を起こしやすいのです。 終段出力管が高性能な場合にはより敏感となり、G1p のインピーダンス低下対策等が必要でした。 そして改造・更新の際には三極管・五極管を独立させたり、G1p/Pt のピンが離れた管種を採用して対策としました。
MOSFET の場合も同様に発振の危険があり対策が必要でした。 本アンプでは口金接続が 9DX にて G1p/Pt が離れていて、2E24 超三結アンプにて前例のある 6AW8-A を採用しました。 これと類似の 6JV8、または他の G1p/Pt のピンが離れている類似品種であれば同様に使えそうです。 できれば 6AN8 を使ってみたい所です。
2.3 直結部分の課題(1)・・・立ち上げ時
MOSFET 終段では、ゲートが真空管終段の G1と同様に電圧駆動であり、さらにゲートが動作電流を吸い込まないので、そのまま直結が可能です。
傍熱管の真空管終段ならスロースタートにて問題はありませんでしたが・・・MOSFET 終段は電源 on にて瞬時に動作に入るので前段の動作開始とのタイミング調整を考慮しないとバランスが取れずに、短時間の不適切なゲート電圧が掛かりラッシュ・カレントが流れる可能性があり、防護処置を施さないと素子を壊しかねません。
そしてヒントは、筆者が試作した直熱多極管終段の 1619, 2E24 による超三結アンプ例にありました。 それらでは、パワー・オンした直後の立ち上がりの際に、終段が前段より先に動作に入るため「先行して」終段 G1 に適切な抑制バイアスを掛けていました。 すなわち前段からの直結回路には高抵抗によるグリッド・リークを設けて、予め B マイナス電位に設定しておき、前段のヒーターがエミッションを開始して徐々に終段グリッド電位が上がるに任せ、問題なく逃げていました。
そこで MOSFET の直結回路では高抵抗ゲート・リーク?をソースに接続すれば、立ち上がり時には Vgs の制限範囲から大きくは外れまい・・・と判断し S-G 間に高抵抗一本を接続するのみにて GO としました。
そして実際にパワー・オンすると 6AW8-A の五極管部が三極管部より遅れて立ち上がるため軽いハムが一瞬出ました。 信号入力したままの立ち上げでは、超三結本来の D-G NFB が掛からずに裸ゲインの音が一瞬出るものの 15秒程度で安定しました。 そして後述の過剰ソース電流の検出・表示 LED は灯りません。 従ってラッシュ・カレントは許容範囲と判定し、立ち上げ時の遅延リレーによるスピーカ回路の短絡措置は省略しましたが、次回の試作では・・・。
2.4 直結部分の課題(2)・・・動作の安定化
超三結回路アンプでは、初段を五極管とした場合には直結動作を安定化するために終段のカソード電圧を嵩上げして初段 G2 に供給でき代替手段も兼ねています。 同様に MOSFET 終段の場合もソース電圧を初段 G2 へ供給して構成できます。
終段の嵩上げソース電圧は電力が無駄ですが、直結部分を安定化させます。 また電源電圧の変動があれば、それに沿って音質の変化も少なく動作点を自動調整して吸収します。
実は、(1) この安定化制御と動作電圧の自由度、および (2) オーバーオール NFB を併用しない出力トランスの選択自由度、この二項目が、超三結回路の高い追試験再現性の鍵となっています。
さらに本アンプの場合は高過ぎの B 電源電圧を利用しながら、使用部品を制限するため直結超三結回路を採用せざるを得ない必然性がありました。
なお、大半のマイナス・バイアスによる多極管終段による超三結回路では、G1電位はカソード電位よりマイナス側に設定されますが、 N チャン MOSFET 終段のゲートではプラス・バイアスにてプラス側です。 初段のバイアス電圧調整によって電圧配分を調整し、終段動作点を所定値に調整する点では同一です。
2.5 過大ソース電流の検知および表示、回路図
本アンプの場合はソース電流が 60mA 程度になるとゲート回路に追加した zener diode による過電圧検出回路の LED が点灯します。 何らかのトラブル発生時の表示以外に、動作点設定時に過大ソース電流に至った場合の警報表示にもなります。
回路図を下記に示します。