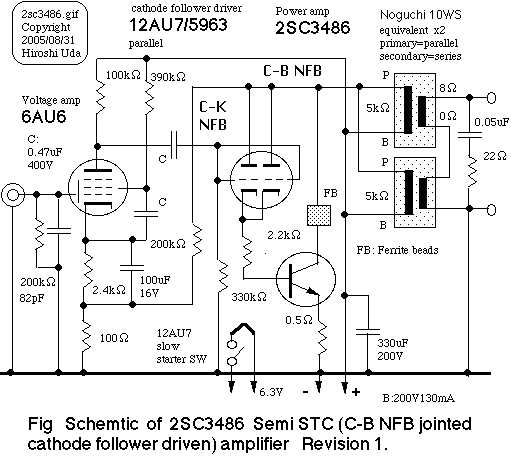2SC3486 準超三結アンプ
2005/06-2006/03 宇多 弘

1 経過
別項に示すパワー Tr 2SC4029 終段の準超三結アンプが一応完成したので、さらに高電圧動作の水平偏向出力用パワー Tr の 2SC3486 による準超三結アンプに挑戦してみました。 オーディオ出力管によるアンプ試作経験を経て、水平偏向出力管のアンプに取り掛かるケースと類似です。
2 回路構成と課題
基本的な回路は 2SC4029 準超三結アンプに準じました。 2SC3486 はより高いコレクタ電圧を掛けることができ、コレクタ電流が少ない動作点にて内部インピーダンスが高くとれ、真空管用出力トランスの流用が楽になります。 一方 Hfe=8 と電流増幅率が小であり、カソードフォロワ・ドライバが若干大変かな、と感じました。
3 初段・ドライバ段管、出力トランス、電源と電圧
● 初段・ドライバ段
以前に試験した G2 ドリブン・アンプなどの経験に照らし合わせて、Hfe=8
のパワー Tr をカソードフォロワ・ドライブするには、プレート電流の多いローμからメディアムμ管の起用が適当と見当をつけました。 該当管種はたとえば 5687, 7044, 6EW7 などです。 またゲイン確保のため別途に電圧増幅管による初段が必要です。
さらに初段およびドライバ段を一本の複合管にて構成するとなると、ポピュラーな管種ではハイμ電圧増幅部をもつ 6EM7 または 6BM8 の三極管接続あたりとなります。 取りあえず 6BM8 でカバーしたら、トータル・ゲインが若干不足でした。(2005/06)
ゲイン不足の解消のため初段管を 6AU6 に変更し、別建てのドライバ段管は 12AU7 (または同等管) のパラレルに変更して問題ありませんでした。 初期に見当つけた管種はややオーバー・スペックでした。(2005/08)
●出力トランス
コレクタ電流の上限は、出力トランスの許容最大 DC 電流から逆算して、先に決めます。 使用する出力トランスは一次側 5kΩ/3.5kΩ max 80mA のものを二個並列としました。
●電源と電圧
適正な動作電圧が直ちに判らないので、汎用外部電源にて120V〜200V 程度の範囲にて動作試験することにしました。 出力トランスの制限を考慮するとコレクタ電流は無信号時に2ユニット分として最小 300mA 、これにドライバ段向けに 10% 程度を上積みして、さらに任意の余裕係数があればヨシとしました。
4 ドライバ段管とそのバイアス設定方法
6BM8 の三極管接続の Eb-Ib 特性図を参考にして、 Hfe=8 の 2SC3486 を120mA 程度の動作点に設定するには、全カソード電流をベースに流し込むとして、カソード電流は15mA くらいの見当にて自己バイアス発生用の抵抗値は 2.5kΩ程度です。 安全を期して 3.3kΩに設定してほぼ正解でした。(2005/06)
12AU7 および同等管のパラレルに変更、自己バイアス発生用の抵抗値を調整し、初期構成のコレクタ電流に合わせました。(2005/08)
5 終段 Tr のコレクタ電流監視
代わりにエミッタ電流を監視しました。 エミッタ回路に挿入した抑制抵抗 0.5Ωの両端電圧 mV の読みを二倍して mA と読み替えました。
6 出力トランスの構成とインピーダンス
5kΩ/8Ωの中型出力トランスを二個使用して、一次側を並列にして許容電流を稼ぎ、二次側は直列にてほぼ整合するものと考えました。 動作試験の結果ほぼ正解、二次側の接続変更による調整は不要でした。
7 ヒートシンクと冷却ファン
A級動作の終段パワーTr はかなり発熱します。 100x200mm 程度のヒートシンクを使って自然空冷した先行例の 2SC4029 では 12W 程度の動作にて、すでにあまり余裕がありませんでした。
手持ちの同サイズのヒートシンクをコレクタ損失 30W 程度にて使う場合はファン併用が不可欠と考え、ヒートシンク直下のシャーシに大穴を開けて、シャーシ内部には120x120mm とやや大きめの 12V0.5A DC にて駆動するマッフィン・ファンを取り付けて下から強制空冷しました。
12V そのままではファンの風切り音が大きく音楽を聴くには邪魔なので、直列抵抗を挿入して 6V 程度にまで抑えて静かにしてもかなりの冷却効果があり、室温+15度程度に収まって安心しました。
8 立ち上げ時の課題
別項に示した、電源内蔵の 2SC4029/5200 準超三結アンプでは、パワー ON 立ち上げ時には特段の問題は起きませんでした。 本アンプでは実験用の外部電源を利用し、予め AC 電源 ON すなわち前段管とドライバ段管のヒーターを予熱してのち、B 電源 ON して動作開始しました。 その過程にて終段パワーTr のエミッタ電流を監視すると、B 電源 ON の際に定常状態の倍程度のラッシュ・カレントが見られました。
その原因は初段とドライバ段管との間の C/R 結合にあり、B 電源 ON の瞬間に C を介してドライバ段のグリッドに+が掛かり、ドライバ段のカソード電流が一瞬過大に流れるけど、グリッドリークを通じ放電して定常状態に戻るものです。 但し、終段エミッタに挿入した抑制抵抗がある程度効き、また終段パワーTr の最大コレクタ損失の 50% 程度で、かなり余裕は残っています。 また外部電源のフューズが切れるほどの影響はありませんでした。 この課題は外部電源を AC/B 電源同時 ON 操作とするか、または電源内蔵・専用外部電源による AC/B 電源の同時 ON で解決できます。
しかし本アンプでは AC 電源を OFF せずにドライバ段管の挿し換え試験ができないか・・・との横着な考えから、解決方法の模索にかかりました。
● 終段パワーTr のベースの接地スイッチを ON、B 電源 ON 後に頃合を見て OFF すればラッシュ・カレントは避けられるも、コレクタ電流が流れてスピーカから「ポッコン」音。 それを防ぐスピーカ切放スイッチも可能だけど、更に操作が面倒になるだけ。 二段にタイムディレー・リレーを使っても同じ・・・これは却下です。
● 抵抗を介してベースを接地しても「ポッコン」音は大差はなく、抵抗値を大きくすればラッシュ・カレントが増えて抑制効果が減り・・・これも却下です。
結局、ドライバ段管の挿し換え試験時に限り、B 電源およびドライバ段管のヒーター回路を予め OFF にして、挿し換え後に同時 ON とする、ドライバ段管限定の ヒーター/B 電源同時立ち上げ方式に至りました。(2005/08)
9 最後に
本アンプの音質は超三結各アンプに類似し、出力トランスに余裕があるためシッカリした低音が得られました。 本アンプにて自室でのリスニングには問題ありませんが、心配したとおり若干トータル・ゲインが不足です。 取りあえずフラット・アンプ併用にて +10db 程度の余裕をもたせました。(2005/06)
ゲイン調整等のための前記の構成変更・改造にて「改」となりました。
(2005/08)
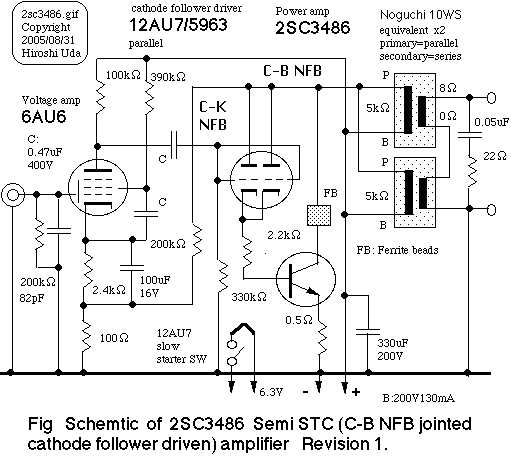
以上
改訂記録
2005/06:初版記述
2005/08:改訂第一版、構成変更等にて「改」へ改造
2006/03:分解・転用
End of text