
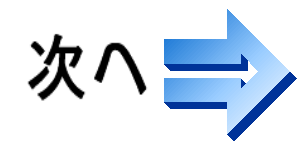
浩二が次に僕を連れていったのは、ジーンズ専門店だった。
そこに着くまで、僕はただ呆然として流れる音楽もろくに耳に入らなかった。ちょっとしたカルチャー・ショックに陥っていたのだ。日本人以外の人間と言葉を交わしたのは初めてだったし、ジョンという大きな黒人が薄暗いライブ・ハウスでギターを弾いている姿はどうしても現実感を伴わない『風景』として僕の目に焼き付いた。
「敏、オレが何で音楽関係のサークルに入らないのか、ちょっとは分かっただろう?アメリカにはジョン見たいのがそこいらじゅうにゴロゴロいるんだよ。いくら日本でロックだ、ブルースだっていったところで本物にはかなわないよ。オレがあそこでバイトやっているのも彼らの音楽に触れられるからなんだ」
浩二は放心状態の僕に向かって独り言のように呟いた。
6月の陽射しは強かったが、車の窓から入ってくる風は気持ちよく、僕の顔を撫でていった。
「さあ、次の目的地に着いたぞ。敏、あれ見て見ろよ」
浩二がそう言って指さしたほうにボケッとしていた僕が目を向けると、早撃ちをしているガンマンのイラストが建物の壁一面に描かれているのが目に入ってきた。
「凄いな、このイラスト。この建物は一体なんだい?」
「ジーパンの専門店さ。安い『おつとめ品』があるから、気に入ったのがあれば買っていけば?」
「ジーパンの専門店?こんなに大きいジーパンの専門店があるのか。本当にこの街には驚かされるな……」
僕は溜め息混じりに言いながらビートルから降りた。
「まあ、そう言うなよ。おまえ、かなりカルチャー・ショック起こしたみたいだけどいい刺激にはなってるだろう?」
浩二はそう言うと店の外に出ている赤札の『おつとめ品』のコーナーでジーンズをあれこれ探しはじめた。
その店で僕は前から欲しかったジーンズのベストを、浩二は色が褪せてボロボロになったストレートのジーンズを買った。
「どうだ。安いだろう?サイズは少し大きめだけどな」
「うん、安いし量も沢山あるな。東京にはこういう店ないの?」
「この店のチェーン店が福生と立川にあるはずだけど……。この店、オレが中学くらいの時には『アメリカ衣料』って看板が出てたんだ。つまり、基地から要らなくなったものを安く仕入れて売ってたらしいんだ。その頃の日本はちょうどアーミー・ルックとかジーパンがブームになりかけの時だったんだけど、素材が悪くてゴワゴワのものが多かったんだ。でも、ここで売っていたものはサイズも大きくてボロボロのものばかりだったんだけど、はき心地が良くて安かったんだ。だからそのブームに乗って大きくなったんだ。福生と立川にあるのは基地があるからだよ」
浩二はハンドルから右手を窓の外に出してドア・ミラーを直しながら説明してくれた。
「へー、そうか。基地のある街っていうのはやっぱりどこか違うんだな」
「今の話で変なこと思い出しちゃったな。やっぱり中学くらいの頃の話なんだけどさ。物凄く給料のいいバイトがあったんだ。その頃で一日1万円以上になったんだけど、どんなバイトだと思う?」
僕は首を傾げるしかなかった。全然予想がつかなかったからだ。今だって一日1万円になるバイトなどザラにはないはずだ。
「死体洗いだよ」
浩二がポツリと言った。
「えっ、死体洗い?」
僕は背筋がゾクッとした。そして思った。いったいこの街はどうなっているんだと……。
「そう、死体洗いだよ。このはなしは嘘か本当か分からないんだけど……。相模原にアーミー病院があって、そこでベトナム帰りの兵士の死体を洗うバイトがあったんだ。戦争で死んだ人間の死体は普通じゃない。そこいらじゅう傷だらけで、頭が割れていたり、手や足がなかったり、内臓が飛び出していたりそれはひどいものらしい。それを繕いながら遺族に渡すために死体を洗うんだ。本当は一体につき1万円らしいんだけど……。でも、これをやるとホルマリンの臭いが一週間くらい取れないし、暫くは飯喉を通らないって言う話だ。まあ、それはオレが本当にやった奴にあったわけじゃないから噂話に過ぎないんだけどな……。それともう一つの話がこのジーパン屋にあったんだ。『アメリカ衣料』の看板で店を出していたとき、ジーパンやジャケットに赤い染みがよく付いていたって言うんだ。敏、その赤い染みなんだと思う?」
「血か?」
「そうなんだ。だから『あそこの店ではベトナムで死んだ人間や負傷した人間の着ていたものを売っている』って噂になったんだ。時代が時代だけにそういう噂が出たんだけど。これも本当のところは分からない。単に赤いインクが染み付いたのかも知れないし……。その頃は逆に米軍の兵士が着ていた証だっていうんでそういう染みの付いたもののほうがうれたらしけど。でもそれが本当だったら怖いよな。ベトナムで必死に戦って死んだ人間の着ていたものがファッションになっちまうんだからな。それで死体洗いの話を思い出したんだ……」
浩二はなんとなく寂しい顔でその話をやめた。
陽はもうかなり傾いて、早撃ち姿のガンマンを赤く染めていた。浩二は黙って車のエンジンをかけてそのジーンズ専門店を後にした。
僕は浩二が何故、反戦とか安保とかいう言葉におかしな反応を示すのか分かったような気がした。僕にとってのアメリカと浩二にとってのアメリカ、言い換えれば、僕にとっての60年代、浩二にとっての60年代があまりにも離れすぎていた。この街に住んでいるすべての若者が浩二のように考えているわけではないだろう。しかし、少なくとも『早川浩二』という人間にとっては、かなり大きな問題として心に残っているに違いない。
浩二は暫く車を黙って運転していたが、FENから『ロング・トレイン・ランニン』が流れ出すとまた陽気な声でハミングし始めた。
「さっきは悪かったな。変なこと聞かしちゃって……」
「いや、浩二はとんでもないこと知ってるんだなって驚いただけだよ。おまえが反戦とか安保に変な反応するのはアメリカやベトナム戦争に対する接し方がみんなと違うからなんだな」
「そうじゃないよ。オレはただ、ひねくれているだけさ……。もともとこういう性格なんだよ」
浩二は自分の心をごまかすようにタバコに火をつけた。
浩二は友達にビートルを返しに行ってから、その足で僕を最後にディスコに連れていった。
『J』というそのディスコに着いたときは、まだ夜も早い時間だったが客はけっこう入っていた。激しいソウル・ミュージックの流れる中、一人の黒人が見事なステップを踏んでいた。その黒人を中心に他の客達も思い思いにステップを踏んでいた。
その黒人は僕たちに気が付くと茶目っ気たっぷりにウインクを投げてきた。
「ハーイ、コウジ。待ってたよ。こっちに来て一緒に踊ろう」
「ヘーイ、ジョン。相変わらず凄いステップだな」
僕はまたまた唖然としてしまった。ジョンはその逞しい体をうまくリズムに乗せて、汗だくになりながら踊っていた。その姿は見るものにある種の畏怖感を伴った感動を与えるように美しかった。これが『アメリカ』なのかと思った瞬間、僕はめまいを起こした。
「敏、大丈夫か?」
浩二が心配そうに僕の腕を支えた。
「ああ、ちょっとめまいがしただけだよ。でも、ジョンて凄い人だな。オレ、圧倒されちゃったよ。これがアメリカなんだな」
僕の異常に気が付いたジョンが一人のハーフと思える女の子を連れてやってきた。
「ヘーイ、ボウイ。大丈夫ですか?ユーに会わせるためにリエちゃん連れてきたのに」
「初めまして、利恵です。気分悪そうだけど大丈夫……。浩二君、調子に乗っていろんなところ引きずり回したんでしょ」
利恵は僕に挨拶すると浩二に皮肉を言った。
浩二はバツが悪そうに、
「うん、ちょっと刺激が強かったかもな……。敏、オレの家に戻って休んだ方がいいよ」
僕はこんな自分が情けなかった。
「いや、もう少しここにいるよ。曽根です。よろしく」
僕は利恵に握手を求めた。
彼女はにっこり笑って、僕の手を握り返した。
「君の噂は浩二君からよく聞かされていたの。会えて良かったわ。映画を作るために東京に出てきたんだって?浩二君感心してるのよ。君のこと。あいつならきっと何かやってくれるって……」
「利恵、もういいよ。オレ、照れちゃうだろう。敏、本当に無理しないで帰ろう。またいつでも来れるよ。ジョンと友達になれたし、利恵は明日付き合ってくれるし……」
「そうね。明日もあるし今日は帰った方がいいわ」
「ソレガイイデス」
ジョンと利恵ちゃんは僕に気を使ってそう言ってくれた。
僕はみんなを見回しながら頷いた。
「じゃ、そう言うことだから。ジョン、利恵、また……」
浩二は二人にそう言うと、僕の腕を抱えて店を出た。
* * *
その夜、僕は精神的な疲れでなかなか眠れなかった。今日見たこと、聞いたことが頭の中でグルグル回っていた。
気が付くと、僕は夢の中を彷徨っていた。僕は目を覚ますまで、その夢にうなされていた。それはリアルで恐ろしい夢だった。
夢の中で僕は機関銃を持っていて、『J』で踊っているジョンをうっとり見ていた。そして突然そのジョンめがけて、機関銃を発射した。ジョンは血塗れになって僕のほうを向いて倒れた。場面は変わって、病院の死体置き場で浩二が泣きながら穴だらけで腕がちぎれかかっているジョンの死体を繕いながら洗っていた。僕はその様子を血だらけで穴のあいたジョンの着ていたものを身につけて、冷たい目で見つめていた。
「敏、飯ができてるぞ。もう起きろよ。9時過ぎてるぞ。飛行機、見に行かないのか」
浩二の起こす声で、ようやく僕は夢から解放された。
「ああ、もう9時過ぎか。昨日はやっぱり疲れてたんだな。久しぶりによく寝たよ」
「そうか。それは良かった。でも、何かにうなされてたみたいだけど変な夢でも見たか?」
「いや、大丈夫だよ。ただ少し疲れていただけさ。もうたっぷり寝たから本当に大丈夫」
僕は夢のことは黙っているつもりだった。
僕たちは浩二の母親の手料理を食べた後、迎えに来た利恵ちゃんと一緒に基地の南側にある草むらの空き地に飛行機を見に出かけた。そこには僕たちと同じような若者が沢山いて、カメラや双眼鏡を手にして飛行機が飛び立つのを熱心に見ていた。
「奴らはみんな飛行機マニアさ。仲間同士で情報を交換しあって、いつどんな飛行機が飛ぶのか知ってるんだ。それで今日はこんなにいっぱいいるんだ。たぶん、今日はP3CオライオンとかF4ファントムが飛ぶはずだ。今、ゴーゴー音がしてるだろう?あれはファントムのエンジン音だ」
「へー、音だけで良く分かるな」
「ああ、前に騒音調査のバイトやったときに一緒だった奴がマニアでいろいろ教えてくれたんだ」
僕たちが話している間にエンジン音が高まり、3機の戦闘機が僕たちの真上を飛び立った。
その銀色に光る翼を持つ鳥は轟音を残し、アッと言う間に南の空へ消えていった。
「凄いな。ファントムってあんなに速いのか……」
僕は呆気にとられて呟いた。
「ああ、とんでもない速さだ。でも、ここに来ている連中にはあれが本当に人を殺すための道具だっていう意識がほとんどないんだよな……」
「そうね。あの綺麗な鳥は人が作り出した殺人兵器なのよね……」
浩二と利恵も僕に合わせるように呟いた。
それから僕たち3人は午前中いっぱい、草むらに寝ころんで飛行機が飛び立つのをボケッとしながら見て過ごした。
僕はボケッとしながらも、昨晩の夢のことを考えていた。何であんな夢を見たのだろう?僕の頭に浮かんだのは『コンプレックス』という言葉だった。昨日ほどアメリカを意識させられたことはなかった。それはジョンという黒人に対するコンプレックスそのものだった。ライブ・ハウスで聞いたあのベトナムで死んだ友達のために作ったというブルースが今も耳から離れず頭の中で何回もリフレインされていた。そしてそれは同時に浩二に対するコンプレックスでもあった。環境の違いとはいえ、同じ世代の浩二が60年代のアメリカを象徴するベトナム戦争に関わっていたことが羨ましかった。だから、あんな夢を見てしまったんだと思う。
その日の午後、僕はコンプレックスの塊となって浩二の住む街から出ていった。
* * *
浩二の住む街に行って以来、僕の頭の中は益々混乱していった。それは浩二の見せてくれたものが、僕の想い描く60年代とはまったく別のものだったからだ。僕はまた東京にあるいろいろな街を模索しながら歩いた。しかし映画のヒントになるものは何も見つからなかった。僕はやり場のない苛立ちを覚えた。
そんなある日、僕は下北沢で『朗読喫茶』という耳慣れない言葉に出会った。そして気がついたときにはもう店の中に入っていた。
その日の出し物は永山則夫の『絶叫未練』という詩集だった。永山則夫と言えば、連続射殺事件の犯人死刑を求刑されている人間だ。僕は咄嗟にあの日の夢のことを思い出した。そして、朗読を聞いているうちにだんだん胸が熱くなってきた。
“聞こえてくる 街の声
越えてゆく 囚人の声
この20センチの厚さに
ひとり、ひとりの来る日、行く日の
歴史が生まれていく……”
僕は心の中で『これだ!』と叫んでいた。そして頭の中にぼんやりと映画の構想が見えてきた。
永山則夫が事件を起こしたのは1968年、僕たちと同じ19才の時だった。時代は70年安保闘争の真っ直中、しかし、彼はそんなこととは関係なく貧乏と闘っていた。そして、彼は自分が貧乏であることに対するコンプレックスから事件を起こした。それは僕があの日見た夢に通じるところがあるように思った。そして今、彼は刑務所の中にいてもがき苦しんでいる。それは浩二の言った『刑務所』という僕たちの学生生活、いや、今の僕のやり場のない精神状態と似ている。
僕の頭の中で映画のカットが浮かんでは消えた。
僕はアパートに戻ると早速原稿用紙と睨めっこを始めた。