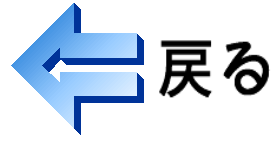
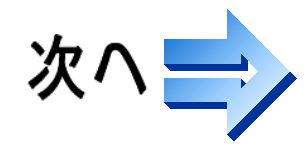
僕の学生生活も5月にはいるとようやく落ち着いて、受ける講義、受けない講義を選り分けるようになった。僕は東伏見の駅前のスナックでアルバイトを始め、時間の許すかぎり『ぴあ』を片手に自主制作の映画を見て歩いた。学内の映画関係のサークルに入会しようと思ったが、気に入ったサークルはなかった。と言うより、浩二のように個性の強い人間に出会うことが出来なかったというのが本当のところだった。
その浩二だが、あれだけのギターの腕を持っていながら音楽関係のサークルにはまったく興味を示さず、僕の映画鑑賞によく付き合ってくれた。
「なあ、浩二。おまえ何でサークル入んないんだ。あれだけギター弾けたら、オレだったらどこかのサークルに入るけどな。もったいないよ……」
僕は浩二に会う度にその話を持ち出した。
「いいじゃないか。おまえだってサークル入ってないじゃないか。オレはおまえがどんな映画作るのか見てみたいんだ。それにしても、自主映画ってメチャクチャなのが多いな。学生の作るものってあんなもんか?ストーリーはいい加減だし、基地の場面さえあれば反戦のイメージが出来上がるとでも思っているのか?あいつらが一体何考えてんだかさっぱり分からないよ。たぶん、ああいうのをつくるやつらはセクト崩れなんだろうけど……」
浩二はその日見た3本の映画をボロクソにけなした。僕は耳が痛かった。もし今、僕が映画を作ったとしたら今日見た映画と大差ないものが出来ただろう。それは作った者の自己満足に過ぎず、見たものの共感を呼べるものではないということだ。
「そう言うなよ。オレ、耳が痛いよ。オレが今映画を撮ったら、今日の3本とあんまり変わらないものを作っちゃうよ。自己陶酔の極みの映画をさ……」
「だから、おまえが映画を作るときにはオレみたいな素人の意見を聞いた方がいいんじゃないか?そのためにオレがおまえのそばにいるんだよ。オレは決まり切ったバンドのコピーをやる気はない。だから音楽関係のサークルに入会するつもりはないんだ。それより、おまえの映画作りの方がずっと魅力があるんだ。オレに何が出来るのかわからないけど、映画を作るときはオレも仲間に入れてくれよ。映画に使う音楽くらいは作るぜ」
浩二の心がそんなところにあるとは思いもよらなかった。僕は彼の気持ちが嬉しかった。僕は浩二に見せても恥ずかしくない映画を撮りたいと本気で思った。しかし今の僕には、浩二の気持ちに答えるだけの用意が何もなかった。どんなストーリーにするのか、どんな映像にしたらいいのか、音楽は何を使うのか、すべては闇の中にあって何も見えなかった。
「時間はまだいっぱいあるよ。おまえが『これだ!』と思うものが見つかるまでじっくりアンテナを張って待ってるんだな」
僕の気分が落ち込んでいるのを察してか浩二は冗談めかしてそう言った。
* * *
僕はそのことがあってから、自主制作の映画を見に行くのをやめた。その代わりにいろいろな街を歩き回った。いろいろな情報を自分の中に吸収するために……。新宿を始め、渋谷、青山、六本木、自由が丘といった若者が集まる街を中心に浩二の言ったアンテナを張り巡らせた。しかし、僕のアンテナには『これだ!』と思うようなものは何一つ引っかからなかった。僕にはどの街も同じように見えた。
それぞれの街に特徴がないわけではなかった。田舎から出てきた僕にとって、どの街も刺激的で表面を眺めているだけだったらそれなりに楽しかった。しかし、僕の心を揺さぶるようなものは何もなかったし、求める60年代の欠片もなかった。それどころか、僕にはそこに集まる若者達が腐りかけのケーキに群がる蟻のように思えた。そして僕自身もその蟻の一匹になったような気がして気分が悪くなった。
浩二にそのことを話すと、
「ふーん。随分いろんなところ回ったんだな。でもな、おまえの見た街は大きすぎて何かを見ようとすればするほど、何も見えなくなるような所ばかりだと思うけどな。でも、おまえが自分のことを腐りかけのケーキに群れる蟻だって思ったことが大事なんじゃないか?地方から出てきた人間はみんな同じ気持ちだ。自分は何か新しいものを見つけるために街をさまよい歩く。だけど、気が付いてみたら街というケーキに群がる蟻だった……。それだけでも映画のヒントになると思うけどな……。それでもおまえが60年代に拘りたいなら、それなりの街があるだろう?例えば、下北とか吉祥寺とか……。あの辺ならおまえが考えているようなものがあるんじゃないかな……」
「そうか、蟻でも映画になるか……。そうかも知れないな。でも、オレはやっぱり60年代を追いかけてみるよ。近いうちに下北沢や吉祥寺に行ってみるよ。オレの目は大きい街、遠い街に向いていたんだな。その方がいろんなものが見えると思って……」
実を言えば、僕の回った街のほとんどは『ピア』を手本にして決めた街だった。その中に下北沢や吉祥寺も載っていたのだが、大学に近いということもあって後回しにしていた。
「でも、いろんな街を見て回るっていうのはいいことなんじゃないか。何回も足を運ぶうちに何か新しいものが見えてくるかも知れないし……。おまえのやっていることは間違えじゃないと思うけどな」
浩二は僕が泥沼の中で喘いでいるのを分かってくれて、そうアドバイスしてくれた。彼も今はアルバイトで忙しく、僕に付き合っている暇はあまりなかった。どちらにしろ僕自身が何かを掴まないかぎり、映画を作る話は前には進まないのだ。
「敏、今度の休みの日、オレの家に来ないか?気分転換になると思うぜ。それに約束してたしな」
僕はその言葉で一瞬何かが閃いたような気がした。『そうだ。浩二の住む街があった!』。僕は自主映画を見に行くようになってから、知らず知らずのうちに東京ばかりを意識するようになっていた。それは結局、僕が地方出の田舎者だということの証に違いない。考えてみれば、浩二が言ったとおり東京で若者の集まる場所というのは僕のような田舎者が集まる場所とイコールになるのだ。そんな街へ出ていっても東京にドップリと浸かった地方の人間しか映らない。その光景は僕にとっては苦痛以外の何ものでもなかった。浩二にはたぶんそれが分かっていたのだろう。
「うん、そうするよ。おまえの住んでいる街だからな。オレの心を揺さぶるようなものがきっとあるよな」
僕は自問するように呟いた。
「おまえ、考えすぎだよ。俺は気分転換のために誘うんだぜ。まあ、ボケッとしながら飛行機が飛び立つところでも見に行こうぜ……」
浩二は僕を茶化すように笑顔を見せた。
* * *
次の休みの日、僕は浩二の家に遊びに出かけた。
浩二の家は小田急線で新宿から1時間くらいのところにあった。駅に降りてまず驚いたのは、ものすごいジェット機の爆音だった。
「今日はエンジン・テストやってるんだ。だからいつもよりうるさいんだ。まあ、驚くのも無理ないけどな……」
僕は耳を塞ぎながら、
「おい、ジェット機の騒音てこんなにすごいのか?ビートルズの『バック・イン・ザ・USSR』どころの騒ぎじゃないな」
「ああ、このエンジン・テストっていうやつをやられると、部屋でレコード聞いてても何も聞こえなくなっちゃうんだ。オレの家はここよりもっと基地に近いから、それは見事なもんだぜ」
浩二は僕の無様な格好をいたずらっ子のような顔で見た。
僕と浩二は駅から爆音のする方へ歩き始めた。
暫く行くと穏やかな坂がありその坂を下りきったところを細い川が流れていた。
「随分汚い川だな。これじゃ、神田川と変わらないよ」
「そりゃそうさ。この辺りで綺麗な川なんてどこにもないさ。ほんの数年前までは、この道の両側は田んぼだったんだけど、今じゃ見ての通り住宅街だ。生活排水とか工業用水でみんな川が汚れちまったんだ……。おまえの田舎の川はもっと綺麗なんだろう?」
「うん、どんな小さな川でも透き通ってて魚が泳いでいるよ」
「ふーん、いいな。そんなにいい環境にいながらわざわざ東京へ出てきたんだ。おまえの求める60年代を見つけるために……」
浩二は不思議そうな表情を浮かべて僕を見た。それは暗に僕が東京へ出てきたことに対する批判ともとれた。
「それは映画を作りたいからそうなったんだ。田舎に引っ込んでいたら、何も見つからないと思ったから……」
僕はそこまで言って、ハッとした。そうなのだ。東京に出てきてもまだ何も見つかってはいないのだ。
浩二はにやりとして、
「まあ、今日と明日はそういうことは考えないでのんびりしようぜ。でも、この爆音じゃイライラするだけかな。この坂を登り切るともう基地は目の前だ」
僕たちはまたゆっくりとした足取りで歩き始めた。
坂を上りきると目の前に広大な風景が広がった。それは僕の想像を遙かに超えていた。
「これが厚木基地か……。すごいな。こんなに広いとは思わなかった。でも、飛行機はあんまりいないな」
「ここから見えるのは、基地のほんの一部だよ。ジェット機はエンジン・テストやってるから滑走路の方にはいないんだ。明日あたりはP3Cオライオンとかファントムが飛ぶんじゃないかな。オレの家、そこを曲がってちょっと行ったところなんだ」
浩二はその曲がり角を指さした。
浩二の家の前まで来ると、そこに黄色のワーゲン・ビートルが止まっていた。浩二は車のボンネットに寄りかかりながら、
「敏、荷物オレの部屋に置いてちょっとドライブに行こうぜ。この車、オレの友達が米軍の知人から安く売ってもらったのを借りてきたんだけどさ。気晴らしになるぜ。昼間からオレの部屋にいるよりは……」
浩二はいつものクールな浩二ではなく、無邪気な子供のようだった。
僕は取り敢えず荷物を浩二の部屋に置いて、ドライブに行くことにした。荷物を置きに浩二の部屋に入ったとき、僕は不思議な気分になった。浩二の部屋には本と呼べるものはほとんどなく、ベッドにステレオ、テーブルの上に転がったコーラの空き缶、そして無造作に置かれた生ギターがあるだけだった。しかし、そこからは何故か60年代の香りがほんのりしたような気がした。その風景は僕に一種の既視感を起こさせた。
僕がビートルの助手席に座ると、
「じゃあ、行くか。おまえの拘り続ける60年代の車でオレの知っているこの街を見せてやるよ」
浩二は嬉しそうにクラッチをつないで車を発進させた。
「おまえ、いつ免許取ったんだ。オレ、全然知らなかった」
「敏の田舎の方じゃどうか知らないけど、この辺じゃ生まれの早いやつはみんな高3の夏休みに免許とるんだ。オレも5月生まれだから去年の夏休みにとったんだ。車はないけどね」
浩二はさっき渡った川を横に見ながら答えた。
浩二の運転するビートルは街の繁華街の一角にある雑居ビルの前で止まった。そこに着くまで、浩二はFENのラジオ放送をずっと流していた。そして自分の気に入った曲がかかると、一緒になって口ずさんでいた。
僕には東京にいるときの浩二と今の浩二はまるで別人のように思えた。それをたとえて言うなら“静”から“動”、“陰”から“陽”へと心のスイッチが切り替わったような状態だった。
浩二は車を止めると、
「さあ、着いたぜ。このビルの中に最近できたライブ・ハウスがあるんだ。まだ時間が早いから客はいないと思うけどちょっと覗いてみよう」
浩二はそう言うとスタスタと中に入ってしまった。僕も浩二の後について中に恐る恐る入ってみた。中はほんのり薄暗く、誰かが生ギターで見事なブルースを弾いていた。
僕たちが中に入ってくるとギターの音が止み、「ハーイ、コウジ。元気かい」という声が響いた。
「オーケー、ジョン。元気だよ。今日はマイ・フレンド連れてきた」
浩二はギターを抱えた黒人に答えると僕を指さした。
ジョンと呼ばれた黒人はギターを置いて僕の方へやってきて握手を求めてきた。
「えーと、マイ・ネーム・イズ・サトシ。こちらこそよろしく」
僕がこの大きな黒人に違和感を抱いていることは隠しようがなかった。このライブ・ハウスに一歩踏み入れた途端に、僕は別の世界へ連れ込まれたような気がした。それはこのライブ・ハウスがいつか見た映画に出てきたアメリカのライブ・ハウスに雰囲気がよく似ていたかも知れない。この小さな街にはアメリカそのものがある。僕はそう思った。
浩二はにやにやとして、
「実はオレ、ここでバイトしてるんだ。ジョンはここの常連さ。と言ってもこういう暇なときにしか来ないけどな。ジョン、利恵は?」
「オー、リエちゃん、買い物ね。3時まで帰らない。ボク、留守番頼まれた」
「そうか。残念……。敏に紹介しようと思ってたのに。まあ、ジョンに会えただけでもラッキーだったな。ジョン、彼に今の曲もう一回聞かせてやってくれないか?」
「オーケー、このブルース、ベトナムで死んだフレンドのためにボク作りました。どうぞ聞いて下さい」
ジョンは僕に向かって丁寧に挨拶すると静かにギターを弾き始めた。
僕はこの薄暗いライブ・ハウスに響く魂の叫びを聞いた。ここにもう一つの僕の知らない60年代を見たような気がした。それが切なくて悲しいベトナム戦争の傷なんだとジョンの歌声が教えてくれた。
「グレイト!やっぱり凄いな。ジョンのブルースは……」
ジョンの演奏が終わると浩二はやんやの喝采を送った。僕も知らないうちに拍手をしていた。
「サンキュー、ありがとう」
ジョンは僕に丁寧に頭を下げた。
浩二は僕の方に向き直ると、
「どうだ、敏。本物のブルースを生で聞いた気分は?」
「物凄く感動した。だけど、まるで現実感がないんだ……。ここが夢の世界みたいなところだからかな?」
「何バカなこと言ってるんだよ。ここは夢の世界じゃないし、ジョンは幻でもない。ただのオレの友達だ」
確かに浩二の言うとおり、ここは夢の世界でもなくジョンの聞かせてくれたブルースは幻でもなかった。しかし、僕の心の中にある違和感は拭えなかった。
僕は浩二の入れてくれたコーヒーを飲みながら、浩二とジョンの話を黙って聞いていた。浩二とジョンは音楽で結ばれた本当の友達だった。そこには国籍や人種、世代の違いなど何もなかった。僕はそんな二人が羨ましかった。
ひとしきり話が終わると浩二は僕を促した。
「敏、そろそろ行こうか。利恵にも会わせたかったんだけど時間なくなっちゃうからな……。じゃあ、ジョン。また後で……」
「オーケー、コウジ。後でリエちゃん連れて『J』に行ってるよ」
ジョンはにっこり笑って、僕にウインクをした。