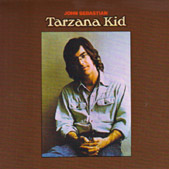*2004年春*
|
| 5月 |
| John Sebastian / Tarzana Kid ■ラヴィン・スプーンフルのメンバーだったジョン・セバスチャンが1970年代にソロになって発表したアルバムが、一斉にCD化・日本で発売になりました。 中でもお勧めが、1974年発表、4作目の『Tarzana Kid』。 ジョン・セバスチャンの持ち味である、土臭さ、人懐こさ、オールド・タイム・フィーリングが前面に出て、アルバムの統一感も一番です。 アルバムのハイライトは5曲目「Face of Appalachia」。じわじわと盛り上がる激渋曲で、サビのファルセットに入るメロディーが美しく、ローウェル・ジョージが弾く重めのスライド・ギターが印象的です。 ブルージーなトラディショナル曲「Wild About My Lovin'」は、ライ・クーダーのフラット・マンンドリンのトレモロ・プレイを大きくフィーチャーして、まんまあの頃のライ・クーダーの雰囲気。グッド・タイムな雰囲気がなんともいい感じ。 ジミー・クリフの「Sitting in Limbo」、本家よりぐっと締まって泥臭いリトル・フィート作「Dixie Chicken」のカバーも秀逸です。 |
◇◇◇ Bonnie Pink / Even So ■ボニー・ピンクの新作は、久し振りにトーレ・ヨハンソン全面プロデュース。 装飾を削ぎ落とした潔い音作りは相変わらずで、やっぱりこの人には生音が似合う。 一見地味渋・通好みに見えて、その実いろんな音楽スタイルが同居。 3曲目「New Dawn」は彼女には珍しい、ファンキーで跳ねたリズムが新鮮なナンバー。 続く4曲目「5 more minutes」は、歪んだギターのカッティング・リフが印象に残ります。 どことなく原田知世を思わせる8曲目「1・2・3」はアルバムの中でもっともキャッチーでポップな曲です。 9曲目「Last Kiss」はドリーミーなメロディーが印象的。 全編ボニー・ピンクらしいボニー・ピンクがここにいる、そんな気がします。 |
| 3月 |
| 木住野佳子/ プラハ(特薦!) ■音で情景を描く。きっと音楽家なら誰でも目指すに違いないそのことが、1曲目を聴いた瞬間に頭に浮かんだ。 1曲目のタイトルは「フォレスト・レイン」。雨の雫が流れ落ちるかのようなピアノの音。少しもの悲しく湿度を帯びた控えめなストリングス。ボトムをどっしりと支えるジョージ・ムラーツのウッド・ベース。 ■木住野さんの新譜は、全曲プラハで録音。そのためか全編に流れるのは、ヨーロッパ・ジャズにも通じる純真で美しい音の佇まい。 プロデュース、ストリングス・アレンジも彼女自身で、空気が流れるように情景を描き出す深みのあるストリングスも素晴らしい。 収録曲11曲中、冒頭7曲までが彼女自身のオリジナル。マイルス・デイビス、バーンスタイン、ショパン、ドヴォルザークの曲が各1曲という構成。 感動的なバラード曲集『テンダネス』、ジャズ・ボサノバが小気味良い『シエスタ』も素敵なアルバムだったけれども、また彼女は違った地点に素晴らしい音を見つけ作り上げたようです。いいです。 ■本人による曲のライナー・ノート付き。SACDハイブリッド盤。 |
 |