*1999年秋* 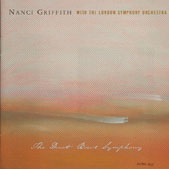  11月 aiko 「カブトムシ」(12cm Maxi-Single) もうさっきから10回近く聴いている。印象的な歌が耳から離れない。 落ち着いたミディアム・ナンバーの「カブトムシ」。キャロル・キングの純粋さにジョン・レノンの憂いを加えたようなメロディーラインを、リンゴ・スターのような落ち着いたドラミングが先導する。ピアノのタッチもジョン・レノンみたいだ。そこに椎名林檎を少し柔らかくしたような凛としたたたずまいの声が乗るころには、すっかり彼女の魅力にはまってしまった。 「桃色」はポップな曲で、滑るような声使いが歌詞と相俟って色っぽい。 「恋人」はピアノとストリングスによる3拍子のバラード。全曲自作。素敵な曲を書く。 ビョークを思わせるファニー・フェイスは10代のようにも見えるが、彼女は'75年生まれである。 インナーの煙草をくわえた写真に少しどきっとする。 楽しみな人である。 aiko 「小さな丸い好日」(推薦!) 「カブトムシ」の感動冷めやらぬうち、彼女の1stアルバムをGetしてきました。1999年4月リリース。 なんといっても彼女の歌の素晴らしさは、ソウル・ミュージック、SSW、ポップスといったものからの影響を感じさせながら、どこを切っても彼女でしかあり得ないオリジナリティーと才能が溢れるソング・ライティングと凛々しい歌声だと思います。 1曲目「オレンジな満月」はソウル感覚溢れる軽快なポップスですが、独特な節回し、言葉の区切り方が印象的。1曲目から気分爽快なaiko Worldが展開します。 3曲目「私生活」はミディアム・テンポの落ち着いた曲で、ここでもふんわりとしたソウルがいい味を出しています。少しだけ鈴木祥子さんに通じるものを感じました。 そして、4曲目「歌姫」が素晴らしい。ピアノで始まる感動的なバラード。ぼくの心はすっかりCarol King with John Simon and The Band!(←私見です。念のため)もう、涙ちょちょぎれました、ぼくは。 9曲目「ボブ」はaiko自らが弾くWuritzer Pianoだけをバックに歌う曲。シンプルな分、彼女の歌の素晴らしさが際立つ。彼女のソングライティングの懐の深さにも注目されましょう。 10曲目「ナキ・ムシ」はシングル・カットされている、ミディアム・テンポのレイド・バックしたバラード。ああ、いい曲だー。いままで、彼女の存在を知らなかったのが惜しい。すっかりファンになってしまったのでした。 Dance Hall Crashers 「Purr」 今にも錆びた釘を踏んづけんとするふざけたジャケットの前作「破傷風」(笑)を見たときから、何か面白そうだなと気にはなっていたんですが、スカ・コアパンク・バンドという謳い文句に躊躇してしまいました。この歳でパンクはないだろう(笑)。 しかーしである、聴いてみたらなかなかいいんである。演奏は確かに元気痛快なギター・ロックだが、パンクと呼ぶにはとってもポップ。演奏もとてもしっかり練られている。中華ファン的に言えば、莫文蔚の「消滅」のような曲が満載。 そして、なんといってもこのバンドのいいところはリード・ボーカルが女性2人であること。2人の声質は良く似ていてどの曲も見事にハモる。しかもメロディー・ラインはきれいでキャッチー。 なかなか侮れないバンドという気がしました。なお、アルバム・タイトルの「パー」とは、猫がごろごろいう、という意味です。 10月 鈴木祥子 「この愛を」(12cm Single)(特薦!) 年末には待望の新譜を発表予定の鈴木祥子さん、一足先のシングルです。 1曲目「この愛を」のピアノによるイントロ8小節聴いただけで狂喜乱舞する方が恐らく10人はいらっしゃることでしょう(笑)。「思いっきり、キャロル・キングだ〜。」 歌が始まってさらにびっくり。ここ数作はラフでタフなバンド・サウンドを志向していた彼女でしたが、久々に初期(名作「水の冠」から「Long Long Way Home」あたり)のアコースティックでスムースな70年代のアメリカン・ロック/ポップスの感触が蘇っているのです。クレジットを見て納得。佐橋佳幸さんのプロデュース・アレンジが復活しているではありませんか!間奏でのキレのいいBruce Hornsbyばりのピアノもかっこいいです。 一時、自分の音楽を模索していたように思えましたが、原点に戻り吹っ切れたようなすがすがしさに満ちています。 2曲目「25歳の女は」はボトムの重いご機嫌なロックンロール。聴いて驚け、Drums/Russ Kunkel, Bass/Leland Sklar, Piano/Bill Payne, Percussions/Lenny Castro, Chorus/Valerie Carter, Arnold McCullerだぞぅ。 来る新譜への期待が膨らむ名シングルです。 Nanci Griffith with The London Symphony Orchestra 「The Dust Bowl Symphony」(特薦!) ..This album is dedicated with love and devotion to memory of my grandmother Susan Griffith, who took flight from this dust bowl in January 1999... ナッシュビルの歌姫、Nanci Griffithの久々のニュー・アルバムは、いつものバンド・メンバーに加え、The London Symphony Orchestraを迎えて制作されたセルフ・カバー集で、ロンドンのAbbey Road Studiosでレコーディングされました。 オーケストラの演奏は、決してシンプルな歌を邪魔することなく、むしろ控えめながら独特の拡がりと表情を歌に与え、彼女の美しく透明な歌世界をよりいっそう魅力的に引き立てています。また、何曲かではケルティックな編曲も聴けます。 デビュー当時に較べると少し低くハスキーな声になったものの、ファニーでキュートな歌声は昔のままです。 英語が堪能でないのが悔しいですが、彼女の描く詞の世界もツアーやライブ、様々な経験から生まれたのであろう味わい深いものです。 それにしてもなんと美しい歌たちなのでしょう。もうただただ聞き惚れていたい気分です。 9月 Crusaders 「Street Life」 Crusaders、1979年発表の名盤。 ジャズ・ファンク/ジャズ・ロック路線から次第にメロウ・ファンクに移行していった彼らが、はじめて当時新人シンガーだったRandy Crawfordを迎え録音した、会心の作。このアルバムはかなり売れたと記憶しています。 当時は、都会的でメロウな側面ばかりが取り上げられた気がしましたが、今聴くと結構ファンキーさもあって、両者のバランス感覚が絶妙。突然の世界的なR&Bブーム(かな?)が起こっている今聴いても、この音楽はとても自然で、すんなり体になじみます。案外この辺にルーツがあるのかもしれませんね。 白眉はやはりRandy Crawfordがボーカルを取る表題曲。11分と長い曲ですが、ピアノ・ソロやサックス・ソロを挟み聴き応え充分。冗長な感じはありません。 個人的には、単なるAORに終わらせない、Stix Hooperのすぱすぱキレのいいドラミングが好き。 ヴォーカル曲は1曲だけですが、ソウルファンにもお勧めです。 原田知世 「a day of my life」(推薦!) ときどき素敵なアルバムに出会うと、あ〜、この人のファンやってて良かった、なんて誰に言うでもなくにんまりしてしまう時がありますが、原田知世さんの新譜はまさにそんなアルバムです。 本作は原田知世セルフ・プロデュースで、全曲作詞に加え7曲も初作曲しております。かなり気合を入れて取り組んだアルバムに違いないと想像しますが、できてきた音は、スウェーデン・レコーディングで培った才能を遺憾なく発揮した、それでいて暖かく、力んだところがひとつも感じられない名盤となりました。 前作「Blue Orange」も前々作「I Could Be Free」も、1曲目は軽快で掴みのいい曲でしたが、今回は珍しく、とても柔らかく穏やかな自作曲「シンプルラブ」で意表を突きます。 続く「君の住む星まで」はざっくりとした肌触りが気持ちよいノリのかっこいい曲。この冒頭2曲のコントラストは最高! めずらしくファンキーで渋い味わいの「秘密のキス」、70年代後半のダンス・ミュージック(Abbaとか)のような雰囲気が微笑ましい「You can jump into the fire」、快活な「Take me to a place in the sun」など佳曲揃い。 それにしてもどうしてこんないいメロディーを書けるのでしょう。芸能界の真中を歩きつづけながらここまで歌謡曲から遠い独自の音楽ができることが不思議ですらあります。世界観を作りすぎだといいたげな評を書いている人もいましたが、それはおかしいと思うな。好き、ならそれでいい。 The Corrs 「Live At The Royal Albert Hall」 (DVD)(推薦!) いやあ、こんなに実直で素晴らしいバンドだとは知りませんでした。MTVではとりわけポップな曲がカットされるのかどうか知りませんが、AOR色の濃いバンドぐらいの印象しか無かったからです。 ステージでは全員黒の衣装に身を包み、ギミックなしの音楽を真摯に送る姿に好感度大! 全編でシャロンのバイオリンとアンドレアのティン・ホイッスル(トラディショナルでは一般的な縦笛)がフィーチャーされ、曲によってはドラムのキャロラインがバウロン(これもトラディショナルでは一般的な片皮の太鼓)を叩きます。これらの楽器が自由自在に泳ぎ回るインスト曲では、じっと座っていられないほどの躍動感で、アイルランドのバンドならではの素晴らしさです。 歌物でもツボを押さえたいいメロディーの曲が続きます。 オーラスの「Toss The Feathers」ではMick Fleetwoodが加わりツイン・ドラムで迫るインスト曲で、感動の嵐。いつまでもコンサートの余韻が残ります。 アイルランドの今の音楽を牽引していくのはもしかしたら彼らなのかもしれません。 The Beatles 「Yellow Submarine Songtrack」 Yellow Submarine30周年だそうである。全編リミックスが施され音質アップ、さらにオリジナル盤に入っていたインストのオーケストラの部分を削って、劇中に使われたThe Beatlesの曲を全部網羅している。 リミックスについては「レコード・コレクターズ」10月号に詳しく載っているが、かなり手の込んだ作業であったようだ。 聴いた印象は確かに音質はアップしているが、あくまで原曲の雰囲気を大切にしているので、驚くほど質感は変わっていない。なんていったって、もとが「Yellow Submarine」や「All Together Now」である。変わりようがないっていう話もある。 全部で15曲であるが4曲もGeorge Harrisonの曲が入っているのが嬉しい。彼のこの頃の曲はどれも少し変わっていて面白い。 詞の世界では、救いようのない絶望的な歌詞が映像ととてもマッチしていた「Ereanor Rigby」、ぼくが64歳になっても食べさせてくれるかい、と歌われる(ポールのお父さんが64歳になったときに書き上げたそうである)「When I'm Sixty Four」が素晴らしくて、胸を打つ。 実験精神溢れた、それでいてポップな名演である。 |
