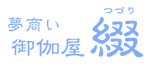
綴達が去って間もなく、七星も空になった茶器を下げに席を立った。
独り取り残されたラズは、周囲を観察して無聊を慰める事にする。
部屋の隅に置かれた香炉で焚かれている抹香は、おそらくは部屋の名に因んで桂の葉から採られたものだろう。
渡廊と板の間を隔てる蔀戸の上の欄間にも、特徴的な形の桂の葉を象った連続模様の透かし彫りが見られる。
この店らしい異国情緒を堪能していると、縮緬の風呂敷に包まれた小函を手に七星が戻って来た。
「綴からの言伝デス。今宵は、桔梗の間でお休みください」
「解った」
エルマの夢解きが終わるまで待機しているつもりだったラズは、その申し出を有り難く受ける。
蜻蛉の許を頻繁に訪れているラズにとって桔梗の間への道筋は勝手知ったる何とやらなのだが、どうやら綴から案内を申し付かって来たらしい七星は、包みを抱えたまま先に立って渡廊を歩き出した。
さやさやとそよぐ風の音に耳を傾けて進む事暫し、ラズの口からふとこんな言葉が零れ落ちる。
「神様を創るなんて、有り得るのかな?」
返答を期待しての問いではなく、何となく間が持たなくて頭に浮かんだ疑問を口にしたに過ぎなかったのだが、意外にも先を行く七星から反応が返った。
「それは、神の定義の依るのだと思いマス」
歩を緩める事も、振り返る事すらもしないまま、七星はラズの問いへの答えとなる言葉を紡いでいく。
「例えば創造者と呼ばれるような超常的な存在には人はなれない。でも、ささやかな奇跡の物語なら世界中に溢れてイマス。稀ではあっても、人の身に降りた神や、神の子供を宿した巫女の伝説も語り継がれてきマシタ」
「だから、それを真に受ける輩がいても不思議はないってコト?」
七星は、ラズの疑問を肯定するでも否定するでもないまま、こう切り出した。
「桃花源教に連れ去られた子供達の中には、実際に信者達から現し神として祀られるようになった者が在りマシタ」
儀式に適合した子供は7人。
彼等が得たのは、福を授ける力だった。
英知、健康、技芸、恋愛、財力、武運、そして、安らぎ。
信者達は、自らの願望を叶えようと挙って彼等の力に縋った。
「でも、教祖達が捕まった時には、子供達はもういなかったって…」
綴の話を思い出して首を捻るラズに、七星は先程は触れられなかった事後の顛末を語って聞かせる。
「教団の解散直前、子供達はそれぞれ里親の許に引き取られマシタ」
だが、そこに幸福な家庭生活を見出す事は終ぞなかった。
神憑りの子供を過剰に畏れ敬い、或いは気味悪がって、大抵の者は「家族」としての距離を測り損ねたのだ。
周囲に持て余されるばかりか迫害まで受けるような事も多く、子供達は転々と居を移す暮らしを余儀なくされた。
そして、子供達を手放した家は、一様に凋落していった。
「どうして?」
まさかそれが彼等の復讐という訳でもあるまいに、とラズは訝しむ。
丁度桔梗の間に辿り着いた七星は、扉の手前で足を止めると、真っ直ぐラズへと向き直った。
「子供達が得たのは幸運を齎す力。身を守る術を持たない彼等は、与えられた庇護への返礼として自らの力を揮いマシタ。けれど、分不相応の運を得れば、反動も大きくなりマス。授けられた幸運に見合うだけの対価が支払われていなければ、いつか揺り返しが来るのデス」
舌足らずな声は幼くとも、その語り口は厳然たる摂理を説く者のそれに相違ない。
だから、ラズは自分の理解の及ばぬ理を、ただそういうものとして受け入れた。
その上で、ひとつ、気になった事を質す。
「7人の子供って言ってたけど」
七星の双つ名は「夢を贈る者」。
彼女の紡ぐ夢は時に優しく時に切なく、人の想いを伝え、癒しと安寧を齎す。
「もしかして、七星もその1人だったりする?」
半ば予想していたものの、七星がその問いに応える事はなかった。
ふいと目を逸らして桔梗の間に足を踏み入れた七星は、衝立障子の奥、置畳の上に敷かれた寝具の枕元にすとんと腰を下ろすと、紅葉の葉のように小さな手で器用に包みを解いていく。
取り出されたのは、一見何の飾り気もない桐箱だった。
「何が入ってるの?」
隣に座り込んで興味深げに身を乗り出してくるラズに、七星はにこりと笑みを浮かべる。
「これは、夢を灯す明かり」
良い夢を。
祈るようにそう呟いて、七星は戸惑うラズを残してひっそりと桔梗の間を後にした。
|