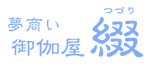
結局、その夜はラズの都合がつかず、解呪と夢解きは日を改めて執り行われる運びとなった。
蜻蛉が抱えている仕事も考慮して、日取りを3日後の新月の日と決める。
約束の日、夕刻を待って「綴」を訪れたラズは、綴に先導されて再び蜻蛉の待つ桔梗の間に通された。
先日面談した板張りの部屋に蜻蛉の姿はなく、代わりに間仕切りに使われている衝立障子が僅かばかり開かれている。
おそらく、その先は蜻蛉の私室なのだろう。
文机や箪笥、小間物を飾った違い棚等の調度品が並ぶ室内に足を踏み入れたラズは、そこで待ち受けていた光景にぴしりと硬直した。
「えーっと、これって…?」
困惑する彼の視線の先には、床に敷かれた一組の寝具がある。
その傍らには、白い狩衣に身を包んだ蜻蛉がこじんまりと座していた。
「ラズ様には、今宵は蜻蛉と共にこちらでお休みいただきます」
「いや、それは解ってるんだけど」
単刀直入な綴の言葉にそう応えつつ、ラズは予想外の成り行きに戸惑いを覚える。
解呪といえば、もっと儀式めいた状況で行われるものとばかり思っていた。
それが、こんな風にごく普通の、ご丁寧に甘やかな香まで焚かれた寝室で眠れと言われても…とラズは弱りきってしまう。
甘い薫香の漂う室内で、年頃の男女――というには些か蜻蛉が幼い気もするが――ともかく男と女が2人きりで夜を過ごすとなると、健全な男子としてはあらぬ想像を掻き立てられてしまうのだ。
口許を手で覆ってあらぬ方を見るラズの態度を不審感とでも取ったのか、綴が見当違いの弁明を口にする。
「この香は眠りを誘う物。危なげな品ではござりませぬのでご安心を」
それでも尚ラズが躊躇っていると、腰の辺りから消え入りそうな声が聞こえてきた。
「ごめんなさい」
見下ろせば、冷たい床に座ったままの蜻蛉が真っ直ぐラズを見上げている。
「夢詣では私の得意とするところではないの。胡蝶《コチョウ》なら離れていても夢を訪なう事が可能だけど、私はこうして夢を見る人の傍に侍って、その身に触れていなければならなくて…貴方には不快かもしれないけれど…」
長い睫毛に縁取られた瞳を哀しげに伏せて口篭ってしまった蜻蛉の姿に、ラズは己の態度を恥じた。
「…別に、不快とかじゃないけどさ」
どちらかというと、疚しい想いを抱いている自分の方こそ嫌われて当然だとラズは反省する。
ラズは、蜻蛉の前に膝をつくと、俯き加減の彼女の顔を覗き込むようにしてこう告げる。
「解った。蜻蛉に任せるよ」
蜻蛉は、氷のような顔(かんばせ)を花のように綻ばせてこくりと頷いた。
※※※
綴が部屋を辞して間もなく、ラズは思いの外あっさりと眠りに堕ちた。
眠らなければと意識している時ほど得てして寝つけなかったりするものだが、部屋の中で焚かれている催眠香が効いているらしい。
こんな事を考える余裕があるのも、これが常ならぬ眠りであればこそなのだろう。
そう思い巡らせつつ、ラズは辺りを見回す。
いつもの夢と同じように荒野に立つ彼の隣に、いつの間にか蜻蛉の姿があった。
眠る前に見たのと同じ狩衣姿の彼女の手には、身の丈程も長さのある弓が握られている。
ラズが見慣れたものとは違い握りの上部が下部より長い風変わりなその弓を、蜻蛉は矢は番えずに構えた。
彼女が見つめる先の空が、黒い風に染まり始める。
その遥か彼方に、風に翻弄される灯火が見えた。
「この風が惑わしの呪いなのか?」
何度も目にしてきた景色の中で炎を揺らめかせる風に不吉なものを感じていたラズは、夢を読み解く力を持つ少女にそう問いかける。
だが、蜻蛉は黙って首を横に振ると、吹き荒ぶ風の中へと足を踏み出した。
慌てて追おうとして、ふと沸き起こった思念にラズの足が止まる。
――これ以上先に進んではいけない。
それは、強迫観念といって良いほどの禁忌の念だった。
――あの灯火に近づいてはいけない。
物理的な重圧感さえ伴う意識に耐え切れずに、ラズは膝を屈する。
だが、いつものように、彼の意識がそこで途切れる事はなかった。
目を閉じたラズの耳に、りぃぃぃんという澄んだ音が触れる。
その音色が齎す波動は、彼を取り巻く大気を震わせ、見えない呪縛の糸を断ち切った。
「…え…?」
顔を上げると、目の前に凛然と風に向かって立つ蜻蛉の姿が在る。
長い髪を風に舞わせた彼女は、嫋やかな指で弓弦をかき鳴らしていた。
彼女の指が動く度に生じる音の波が風を鎮め、ラズの身を縛る力を打ち祓っていく。
「…凄いな」
しかし、安堵したのも束の間、今度は何処からともなく湧き出した闇の触手が蜻蛉に襲いかかった。
普段の夢の中でラズの意識を奪ってきたそれは、彼を護る邪魔者を排除しようと不気味に蠢きながら蜻蛉に迫る。
蜻蛉は、ラズを背後に庇ったままその場を動こうとはしなかった。
我が身に迫る危険を顧みる事無く、弦を弾き続ける。
「危ないっ!!」
遂に彼女の身を闇が絡め取るかに見えたその時、ラズは弾かれたように大地を蹴って触手の前へと飛び出していた。
闇に背を向けるようにして立ちはだかった彼は、そのまま蜻蛉の身体を腕の中に抱き抱える。
蹲ったラズに、弓弦を鳴らす蜻蛉に、闇の触手は容赦なく絡みついた。
2人の身体が、意識が、昏い闇に飲み込まれていく。
ラズは、最後の力を振り絞って、腕の中の蜻蛉に囁きかけた。
「ごめんな、蜻蛉」
音さえも闇に飲み込まれたかのように、完璧な静寂が訪れる。
次の瞬間、爆発的な白光が辺りを包んだ。
|