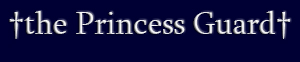|
「…何だか、やたらと物々しい雰囲気だなぁ」 悪路にがたがたと揺れるワゴンの車窓から町の様子を眺めていたルディが、思わしげな表情で眉を顰める。 斜め後ろの席に座るティアラも、怯えた声で小さな呟きを漏らした。 「うん、空気が凄くトゲトゲしてるみたい」 感じたままを素直に口にした2人に、助手席のアナから応えが返る。 「この辺りは、昔からいろいろと難しい土地柄なのよ」 彼等が車を走らせているのは、東欧と中東の狭間に位置するとある国の小さな町だ。 東西世界の境界に位置し、内海に面した地勢から古くから交易の要として栄えてきたこの国は、支配者が変わる度にいろいろな意味で柔軟な変化を遂げてきた。 何事にも寛容なその有り様は多彩な文化を育んだが、同時に多くの根深い問題をも齎している。 民族や宗教の相違から生じる軋轢に軍事的、商業的な利害関係も加わって、周辺国との紛争や内戦の要因となっているのだ。 ここ数年は大きな戦闘は行われていないが、依然として緊張状態が続いている事に変わりはない。 「一応、この町は戦闘禁止区域って事になってるけど、それだって治安維持なんて名目で駐留してる監視部隊のおかげで辛うじて保たれてるようなものだもの」 そう言って、アナは溜め息を吐く。 彼女の言葉を裏づけるかのように町の入り口には厳重な検問が置かれていたし、こうして町中を移動していても武装した警官だか兵士だかが通りの其処此処に立つ姿が目につく。 ルディの鬱屈やティアラの怯えも、そうした緊迫した空気に端を発しているのだろう。 「その割りには、こっちの警備は随分心許ないよな」 こちらは比較的落ち着いた様子のステラが、皮肉っぽい調子で口を挿む。 アナに随行しているのはバックバンドのメンバーやスタッフに通訳といった一般人が殆どで、戦闘要員と言えそうなのはステラ達を除けばボディーガードの2人組くらいだ。 この町の現状を鑑みれば、何者かに狙われているという自覚がある人間の警護に当たる身としては聊か無用心に思えるのも無理はない。 その事は充分理解した上で、運転席に座るアナのマネージャーは、より現実的な問題点を口にした。 「仕方ありません。下手に武器等を持ち込んで警戒心を刺激した挙句、疑惑を持たれたりすると厄介ですから」 それに、と言葉を切った彼は、真っ直ぐ前を見据えたまま、僅かに声を潜める。 「おそらく、真の危険は人ならぬ身によって齎されるものと思われます。その場合、こちらが幾ら武装したところでたいした援けにはならないでしょう」 淡々とした口調ながら、アナを心から案じている事が窺える物言いに、ステラは秘かに目を細めた。 ニコル、という名前以外、アナの本業を知る数少ない「協力者」だというこの青年の素性をステラ達は知らされていない。 エキゾチックな容貌のアナとは対照的に膚も髪も色素の薄いその姿から北方の出自であろう事は窺い知れるが、どういった経緯で今の関係に至ったのか、そもそもマネージャーと「協力者」どちらの立場が先立つのかすら定かではないのだ。 ただ、彼の言動の端々から、年の離れたアナへの心酔と敬慕が感じられるのは確かだった。 「そっち方面は、抜かりはないけどさ」 ステラは、自らの好奇心を封じるべく、敢えて素っ気無い態度で肩を竦めて見せる。 今回のアナの「任務」は、この町に在る孤児院の慰問だ。 表向きのメイン事業である食料や医薬品等の物資の搬送を済ませた後、夕刻からライブを行う予定になっている。 今は、閉鎖されて久しい小学校の校庭で仮設ステージの設営が急ピッチで進められているところだった。 プリンセス・ガードとしては、ルディが到着次第、防御の結界を張り巡らせる事になる。 イベント中は会場内の様子をランが常に監視する予定だし、アナの傍にはステラとティアラが控えている手筈になっていた。 以後の対応は敵の狙いがアナの活動の妨害なのか、彼女自身の拉致や排除なのかによって変わってくるが、今の段階で打てる手は全て打ってある。 「一応、会場やキャンプの周辺は地元の警官隊が重点的に警備しているそうですが、彼等の力も人外のものには及びません。くれぐれも警戒を怠らないでください」 「大丈夫よね」 硬い表情のニコルとは裏腹に、アナは気楽な調子でそう言ってのける。 標的である自覚がないわけでもあるまいに、彼女の声の響きからは、どこか事態を愉しむような余裕が感じられる。 「年少部隊期待の新人が専属で警護してくれるんだもの。頼りにしてるわよ」 彼女の楽天的な態度には、ルディやティアラの漠然とした不安を払拭する力強さがあった。 |