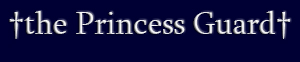|
古の城塞都市や学園都市の風格を漂わせる魔導騎士団LUX CRUX年少部隊の建造物群の中でも、正門を入ってすぐの場所に建つレセプションセンターのエントランスホールは、一際荘厳で神秘的な空間だ。 入り口正面の壁に穿たれた壁龕には騎士団の創設者とされる7人の魔導士を象った雪花石膏製の彫像が飾られており、訪れる者を温かくも透徹した眼差しで出迎える。 白と黒の大理石で市松模様が描かれた床は地上における相対する理念の調和を説き、夜空に星を鏤めたような青金石の丸天井は聖なるものへの憧憬をかき立てる。 見る者の胸に敬虔の念を呼び起こすような神聖な美しさは、魔導に携わる者を迎え入れるのに相応しいと言えよう。 だが、そういった近寄り難い雰囲気を敬遠する向きもあって、騎士団の隊員をこの場所で見かける事はあまりない。 そもそも、隊舎を始めとする各施設には外壁の各所に設けられた門から直接アクセス出来るよう通路が整備されているのだ。 わざわざ好んで役員の執務室や幕僚本部といったお堅い部署が置かれている建物に立ち寄る事もあるまい。 しかし、その日、司令部への道すがらプリンセスガードの面々がホールに足を踏み入れると、玄関の外にちょっとした人だかりが出来ていた。 ちらちらとホールの中を覗き見ては何事かひそひそと言い交わしているのは大半がローティーンの隊員達で、何故か皆一様に浮き足立っているように見える。 加えて、扉の前には黒尽くめのスーツにサングラス着用という非常に解り易い身形の男が2人、狛犬だか衛兵だかよろしく仁王立ちで辺りを睥睨していた。 あからさまに訝しげな顔をするステラ達を他所に、キーラムは涼しい顔で一行を先導する。 隊長の執務室に辿り着く頃には、ステラ達の好奇心と不審感はかなりの大きさに膨れ上がっていた。 ノックもそこそこに名乗りを告げる彼等を、常と変わらぬ硬質な少女の声音が迎え入れる。 「来たな」 彼等を待っていたのは、隊長であるシェルアともう1人、彼女よりやや年嵩の少女だった。 金粉を塗したかのような艶やかなココアブラウンの肌に輝く琥珀色の双眸、細かく縮れた髪は意外に色素が薄いのか、砂色の煌めきを宿している。 見た目だけなら清楚で儚げな深窓の令嬢といった風情のシェルアとは対照的に、華やかでエネルギッシュで、鮮烈な印象を与える容貌の主だ。 その圧倒的な存在感に記憶を刺激されて戸惑うステラに、シェルアの一言は更なる衝撃を齎した。 「彼女はアナスタシア=ルーア。今回の特別任務の依頼人だ」 「アナ…って、あのアナ!?」 「アナ・ジ・オーラム?」 ステラが素っ頓狂な声を上げ、日頃はおっとりと構えているルディまでもが意外そうな面持ちで目を瞠る。 それもその筈、「オーラム【黄金の】」の二つ名を持つその人物は、現在人気急上昇中のポップシンガーだった。 ゲリラ的なライブ活動とネット上での音楽配信がメインで既存メディアへの露出こそ少ないものの、口コミでの評価は高く、ティーンを中心に多くの支持を集めている。 何でそんな有名人が?というステラ達の困惑を他所に、アナは如何にも親しげにランへと話しかけてきた。 「久しぶりー、ラン」 「その節はお世話になりました」 こちらも平然と挨拶を返すランに、ステラ達は尚一層目を丸くする。 「知り合いなのか?」 「以前、任務で一緒になった事があるのよ。あのちっちゃなユエルの聖童がウチの後輩になるなんて、あの時は思ってもみなかったけど」 「任務?後輩?」 アナの返答を受けて頭上に盛大に疑問符を浮かべているステラ達を、シェルアは実に愉しそうに眺めている。 意地の悪い上官に弄ばれている後輩を哀れんだのか、苦笑を口許に刷いたキーラムが事情を説明する為に口を開いた。 「アナは、LUX CRUX年少部隊の一員だよ。と言っても、ほとんど部隊に戻る事はないし、学業の方はほぼ休業状態だから、知らない者が多いだろうけど」 「えーっ!?」と揃って声を上げるラン以外の3人に、当の本人はひらひらと手を振ってこんな事を言う。 「騎士団なんて言われても、戦うのとかって性に合わないのよね。だから、別の方向からアプローチしようかと思って」 その発言を受けて、シェルアも漸く悪戯っぽい笑みを収めた。 「アナの表の顔を知ってるなら、彼女が慈善活動に力を入れてるのも聞き知っているだろう?」 断定的な問いかけに首を捻りつつ、ステラがメンバーを代表してこう答える。 「えっと、確か、難民キャンプとか帰還兵を収容してる病院とか避難所とかを廻ってるんだっけ?」 「あれは、LUX CRUXの任務の一環だ」 隊長としての表情に戻ったシェルアがそう断言し、アナもまた真摯な面差しでそれを肯定した。 「災害や戦場の記憶は、心に傷を残すわ。たとえ自ら志願した職業軍人でも、PTSDに悩まされるケースも珍しくない。まして、望まずして災渦に巻き込まれたのなら尚の事。そして、そういう痛みは、様々な誘惑につけ込まれる隙を生む…そうさせない為の「予防」と「治療」が、私の仕事なの」 痛みを孕む声で、けれど毅然とそう言いきったアナは、そこで一転して軽い調子で溜め息をつく。 「ただ、そういう仕事をしてると、やっぱり目障りに思う輩も多いのよね」 「そこで、お前達に警護の依頼というわけだ」 こちらもまた気安い口調で本題を切り出したシェルアに、ステラは一応常識的と思われる質問を投げかけてみた。 「玄関のトコに立ってる強面のオジサマ達の立場は?」 それには、頬に手を添えて首を傾げたアナが、わざとらしく困った顔で応じる。 「あの人達は、対人間専用のボディーガードだもの。人外の相手はちょーっと無理よねぇ」 「…つまり、何か厄介な相手に狙われてる自覚はあるわけですね」 「そ。今回は、行き先が行き先だからあんまり大事にはしたくないし、1度噂のプリンセス・ガードの仕事ぶりを見てみたいと思ってたから、丁度良いかなって」 気遣いと諦観の相半ばした様子でランが呈した疑問をあっさりと認めた上、あまつさえにっこりと微笑んでみせるアナに、要するに自分達は先輩運が悪いに違いないとステラは肩を落とした。 |