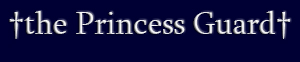|
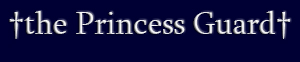
資料庫を後にしたステラは、図書室で待っていたティアラと落ち合って研究棟へと向かった。
次の試験は【木星】、錬金術の実技だ。
天井には曼荼羅、床にはセフィロト、壁には錬金術の鍵と呼ばれる連続絵と古式ゆかしき魔法使いの館といったおどろおどろしい雰囲気を漂わせつつ、電子顕微鏡や分光偏光計といった大手製薬会社のラボ並みの最新設備と高等学校の理科室の使い勝手の良さを兼ね備えた実験室に通された2人は、思いがけず此処にいない筈の友人の姿を見出して目を瞬かせる。
「ルディに、ランも?」
「何でお前等が此処にいるんだ?2人とも【木星】は試験免除だろ?」
「彼等には、オブザーバーとして協力してもらってるの」
そう答えたのは、ミルクティのような亜麻色の髪をおさげにした小柄な少女だった。
返答の内容から察するにこの場の責任者かそれに近い立場にいる筈なのだが、あどけなさの残る童顔にハニーイエローの瞳の甘やかさも手伝って近寄り難さはまったく感じられない。
少女は、春の日向のようなほっこりとした印象そのままの笑顔で受験生達に向き直るとこう名乗る。
「私はニナ=ランスベルク。【木星】の司です」
彼女の後ろには、何れも【木星】の徽章を身につけた数名の隊員が控えていた。
「今日は、痛み止めの麻酔薬を調合してもらいます。出来上がった薬は、【木星】の有志が被験者になって出来具合を確認するわね」
途端に背後から上がる「鬼〜」「悪魔〜」といった呪詛の声をあっさりと黙殺して、ニナは人好きのするおっとりとした口調で説明を続ける。
「レシピは前の黒板に書いてあるけど、自己流にアレンジしても構わないわ。材料もこの部屋のものを好きに使って良いけど、鍵のかかってる棚に入ってるのは劇薬だから扱いに気をつけてね」
にこっと可愛らしく笑いながらさらりと怖い事を言っておいて、ニナは朗らかに宣言した。
「では、試験開始!」
隊員達は、何とはなしに言い知れぬ不安を抱えながらも課題に取り掛かる。
試験内容自体は至って単純な為、然程混乱する事もなく作業は淡々と進んでいく。
だが、さすがに魔導騎士団で用いる魔法薬だけに、指示通りの材料を工程に沿って加工すれば完成、という訳にはいかない。
それらしい効能の薬を調合できたのは半数程度で、あとは効き目が弱過ぎたり、全く別の薬が出来上がったりして不成功に終わる。
ステラの被験者に指名されたシゲルは、薬を塗布して数秒で痙攣を始めた左腕を指し示して苦情を申し立てた。
「ス〜テ〜ラ〜?腕が痺れて動かないんだけど〜?」
「あれ?おっかしいなぁ」
そう言って首を捻るステラに、解毒薬を調合中のルディが失敗の原因を説明する。
「南天の実を混ぜたでしょ。あれ、神経麻痺の効果があるんだよ」
「課題は痺れ薬じゃなくて麻酔薬!痛みを止めるだけで良いのに、完全に麻痺させてどーするんだよ」
呆れるシゲルに、ステラは悪びれるでもなくへらっと笑ってこんな言い訳を口にした。
「感覚が麻痺するのは一緒かなぁと」
一方、その隣のティアラに宛がわれたスペースからは、緊急事態を告げる【木星】の隊員の声が上がる。
「先輩!大変です!被験者が1名昏倒しました!」
恐慌状態に陥る後輩達を他所に、ニナは小首を傾げつつ緊張感のない足取りで現場に歩み寄った。
「おかしいわねぇ。使った薬も調合の手順も間違ってなかったから、そんなに強い薬効が出る筈ないんだけど」
その台詞から察するに、トラブルメイカーとして名の通っているプリンセス・ガードの2人の動向には、一応気を配ってはいたらしい。
傍に控えていたランが、意識を失った隊員の様子を手早く確認しながら問題点を冷静に指摘する。
「調合者の魔力の高さが考慮されてなかったのでは?」
「そっか、なるほどね〜」
ぽん、と手を打つ彼女の背中を遠巻きに見守っていた【木星】の隊員達は、一様に頬を引き攣らせた。
+ + +
ティアラの犠牲者の治療にあたっているランを残して、ステラ達3人は研究棟の隣に並び立つ医療棟へと移動した。
そこで待っていたのは、野戦病院さながらの惨状だった。
重症者の横たわるベッドの隙間を縫ってをバタバタと小走りで行き来する救護要員の間で飛び交う質問と指示の声、軽症者は床に広げられたシートに直に座らされ、治療待ちの列は廊下にまで続いている。
一行を出迎えた華奢な体つきの少年は、苦鳴と泣き言をBGMに開口一番こう命令を発した。
「【太陽】の司、レックス=マクリーンだ。早速だがこれから1時間、此処で働いてもらおう」
あまりに唐突な命令に、試験を受けに来た隊員達は互いに顔を見合わせる。
治癒や浄化の魔法には適性が求められるし、素養があったとしても訓練を受けていなければすぐに使い物になるものではない。
【太陽】に所属していないからこそ査定を受ける新人隊員達にいきなり実践を求めるのは少々無理があった。
困惑する一同を代表して、ステラがおずおずと疑問を呈する。
「働くって言ったって、俺達みたいな素人に治療任せちゃまずいんじゃ?」
それに対する返答は、苛立ち混じりの叱責だった。
「やかましい!誰の所為でこんな状況になってると思ってる!」
考課査定の各試験の過程で生じたトラブルによって怪我人や病人が続出しており、治癒・回復魔法を専門とする【太陽】の魔法使いは現在深刻な人手不足に陥っているのだ。
黄金の巻き毛に高貴な紫の双眸の美少年という宗教画に描かれた天使のような風貌に似合わぬ尊大な口調で、レックスと名乗った【太陽】の司は困惑する隊員達を一喝する。
「オレ様だって元々は神聖魔法系の人間じゃないんだ。それを、たまたまこっちにも才能があった所為で司なんて面倒事を押しつけられてるんだぞ。だいたい、戦場じゃ回復魔法を使えるかどうかが文字通り生死を分ける場合もあるんだ。身につけておいて損はないだろうが!四の五の言わずに出来る事から手をつけろ!」
びしっと医務室を指差すレックスの勢いに半ば押される形で、隊員達は自分に出来る仕事を求めて散って行った。
多少なりとも回復や治癒の魔導に通じている者はもちろん、神聖魔法を使えない面々も見よう見真似で傷の消毒を手伝ったり包帯を巻いたり何とか役に立とうと努める。
そうこうするうちに、多忙を極めている筈の【太陽】の魔導士達の的確な指示もあって、徐々にではあるが治癒魔法を使えるようになる者も出て来た。
元々多少なら治癒魔法を使えるルディは、負傷者を治療する傍ら魔法薬について助言を与えている。
一方、ステラは傷の治療を終えた負傷者の生命力の回復にあたっていた。
自身も重傷の患者を優先的に治療しながらその様子を見ていたレックスは、やや意外そうな顔で感心する。
「ほぉ。ルディが怪我の手当てに慣れてるってのは聞いてたが、お前が回復魔法に長けてるとは知らなかったな」
その率直とは言い難い褒め言葉に、ステラはさして面白くもなさそうに素っ気無く肩を竦めてみせた。
「俺のもルディと同じ、必要に迫られてってヤツだよ。約一名体力に難有りなのがいるんでね」
幼等部に在籍していた頃からやんちゃで年中擦り傷や切り傷を拵えていたステラに振り回されていたルディがいつの間にか傷の治療方法を覚えたように、魔力の高さに見合う生命力を欠いていながら自分の身を顧みずに無理をしがちなランを助けているうちに、ステラも自然と生命力を回復する魔法だけは使えるようになっていたのだ。
何故だが不機嫌な表情のステラを興味深げに一瞥したレックスは、次いで視線をやや離れた場所に向けて溜め息を落とす。
「で、あれはどうしたもんかな」
彼の視線の先、中毒症状を起こした患者が隔離されたスペースでは、ティアラが幻獣カーバンクルを召喚したところだった。
カーバンクルの額に埋め込まれた赤い石が光を放つと、患者を侵していた毒素が瞬く間に浄化される。
つられるままにその様子を眺めていたステラは、脱力気味の苦笑を浮かべて口を開いた。
「あー。あれはしょうがないんじゃねぇ?本人が呼ばなくても幻獣の方が勝手に出て来ちゃうんだし」
「しかし、【太陽】としては査定のしようがないぞ」
端整な顔を顰めて思案するレックスを取り成すように、治療を一段落させたルディも口を挿む。
「でも、役には立ってますよね?」
「…まぁ、極端な話、実戦で使えりゃ何でも良いんだろうけどな」
聞き様によっては投げ遣りとも取れるそんな言葉を、レックスは苦笑混じり呟いた。
BACK <<< ◆ >>> NEXT
|