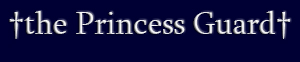|
普段は古文書や呪陣の読解に用いられている研究室らしく、部屋の中央には様々な計測機器に囲まれる形で透明な障壁で区切られた結界が敷かれている。 壁に設えられた黒檀の棚に整然と並ぶ文献や資料は、何れも計り知れない価値を持つ稀覯品ばかりだ。 外界の喧騒から切り離された室内は冷ややかな静寂に満たされており、年代物の家具や調度と最先端の分析機器という取り合わせの妙と相俟って、何やら浮世離れした雰囲気を醸し出していた。 そんな何となく息を潜めてしまうような厳かなその場の空気にひっそりと溶け込むように、1人の少女が佇んでいる。 透けるような蒼白い肌に銀色のショートヘア、切れ長の双眸も霞みのようなブルーグレイととにかく色素が薄いその少女は、しかし、それでいてけして儚い印象は与えない…むしろ、静謐な毅さを秘めた存在感を感じさせる。 「【水星】の司、サラ=クリエです。此処では言霊魔法の適性を審査します」 熱を感じさせない容姿そのままの氷のように硬質な声でそう名乗った少女は、緊張からかやや気後れしている様子の隊員達に向けて簡単な講義を始めた。 「言霊は、ある意味あらゆる魔導の基本といえるものです。多くの魔法使いが術の発動に呪文や呪符を用い、言霊の力によって幻獣を従え、誓約を結びます。秘伝とされる業の多くは、文書や口伝の違いはあれ、言葉によって伝承されてきました。そもそも、我々は多くの場合言語によって思考しているのです」 彼女自身年少部隊の隊員である以上、年齢的にはステラ達と数歳しか違わない筈なのだが、淡々とした語り口は非常に理知的で大人びている。 さすがに、各分野を統べる司の位に就いているだけの事はある、といったところか。 「一方で、偉大な先駆者達は濫りに魔導が用いられる事を懼れ、様々な秘密の言語を生み出し、或いは既存の文字に深遠な意味を与えて知識を暗号化しました。それ故、私達が先人の偉業を学ぶ為には、それらの言語を解き明かす能力を身につける必要があります」 そこで1度言葉を切って、サラは神妙な面持ちで耳を傾けている隊員達の顔を見渡すとこう切り出した。 「今回の試験では、魔法文字の1つであるルーン文字の理解度をチェックします」 困惑する者、焦りを覚える者、安堵する者…俄かにざわつく受験生達を咎めるでもなく、サラは部屋の中央に展開された結界を指し示して試験の内容を告げる。 「この結界の中では、何らかの困難な状況が待ち受けています。受験者は、これから渡す文字盤から正しいルーン文字を選び出し、対面する事象に対処しなければなりません」 その上で、手許の名簿にさっと目を通したサラは、ついと視線を上げると真っ直ぐにルディを見つめてその名を読み上げた。 「ルディ=ソラリス」 「はい」 突然の指名に動じる風もなく、ルディは朗らかに返事をして前に進み出る。 「貴方はルーン文字に慣れ親しんでいますね。彼等に模範を示してもらえますか」 ルディは、命令ではなく協力を依頼する口調で指示するサラに頷くと、進んでルーン文字の刻まれた文字盤を受け取った。 その様子を意外そうに見つめながら、ティアラが隣に立つステラに肩を寄せてひそひそと問いかける。 「ルディってルーン文字詳しいの?」 ステラは、ティアラの方に僅かに身体を傾けると、低く潜めた声で彼女の問いに答えた。 「あぁ、お家柄ってヤツ?あいつの実家は北欧系の術士の裔だから」 背後から聞こえてくる2人の会話にちらりと口許を綻ばせて、ルディは特に気負う様子もなく結界へと手を伸ばす。 彼が呪陣の中に足を踏み入れた途端、結界の効力が発動して外部の視線を遮断した。 代わりに、障壁の一部がスクリーン状に変化して、中の様子を映し出す。 其処は、一面の暗闇だった。 右を見ても左を見ても、前を向いても後ろを振り返っても、結界の外の様子はおろか、其処に在る筈の障壁さえ目にする事は出来ない。 足元さえ覚束ないような暗がりの中にあって、サラから手渡された文字盤だけが仄かな燐光を放っている。 ルディは、其処に刻まれた文字の中の1つを迷いなく選んで押下した。 かちりという音がして、選ばれた文字――くの字状に屈折した直線――が中空に浮かび上がる。 同時に、サラの声がその文字の音価と意味を読み上げた。 「ケン。意味は炬火」 その答えが正しかった事を示すかのように、ルディを包む闇は即座に晴れる。 そのまま結界を出たルディから文字盤を受け取ったサラは、息を呑んで見守っていた隊員達に改めて試験の開始を宣告した。 「方法は以上です。では、試験を開始します」 それからは、受験生が1人ずつ結界の中で試験を受ける事になった。 橋のない川を渡る為に「石」のルーン「スタン」を、重い荷を運ぶ為に「馬」のルーン「エオ」を、亡者の群れを退ける為に「太陽」のルーン「シギル」を、といった風に、問題を解決する為に相応しい文字を選択すれば、結界から出る事が出来る。 なかなか正答を見出せずに途中棄権する者も出たものの、真に身に危険が迫っていると判断されれば結界が解除される為、試験は大きな混乱もなく順調に進んでいった。 そういった中で、最も危うかったのがステラの試験だ。 結界の中で彼を待ち受けていたのは、溶岩に囲まれた灼熱地獄だった。 「えーっと、氷、氷…」 周囲からじわじわと迫り来る岩漿に熱気の所為ばかりでない汗をかきながら、ステラは懸命に文字盤を目で辿る。 「これか?」 彼が選んだのは、直線の上部が右下に折れた半分だけの矢印のようなルーンだった。 「ラグ。意味は流れ」 不正解。 抑揚のないサラの声を受けて、無情にもマグマの流れが加速する。 「って、待て待て待てっ!!」 ステラは、必死の形相で文字盤を睨みつけると、別の文字――真っ直ぐな縦の直線のルーンを選び出した。 「イス。意味は氷」 今度は無事に正しい文字を選んだステラは、間一髪で溶岩の海を氷原へと変える事に成功する。 解かれた結界の真ん中にへたり込むステラに、サラは落ち着いた声音でこう忠告した。 「教本通りに丸暗記しただけの知識は思わぬ時に脆さを露呈するもの。きちんと言葉の意味を識る訓練をなさい」 そしてもう1人、別の意味で危険だったのがティアラである。 燃え盛る炎に囲まれた彼女が選んだのは、「雹」のルーン「ハガル」だった。 降り注ぐ氷塊は猛烈な勢いで大地を穿ち、火を消し止めるどころか辺り一面を凍りつかせる。 おかげで炎の包囲網は脱したが、本来は「水」のルーン「エアル」を選択すべき場面だった。 結界を出たティアラに、サラは「ハガル」のルーンを選んだ理由を訊ねる。 それに対するティアラの返答はこうだ。 「何となく、冷たい気配がしたから?」 確かに文字に込められた魔法を感じ取るという意味では間違いではない。 間違いではないが、正しいとも言い難い。 もしもこれが実際の戦いの場面だったなら、氷の礫は凶器となって周りの味方まで傷つけただろう。 「貴方のその感覚の鋭さや魔力の高さは驚嘆に値するけれど」 ティアラが抱える問題の本質を、サラは端的に指摘する。 「その力を的確に制する術を身につける必要があるようね」 |