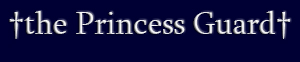|
まだ軽くふらついているランを気遣ってそちらに向かおうとしていたルディが、はっと森の奥へと視線を投げる。 次の瞬間、がんっという音と共に大地に振動が走った。 「地震…?」 ティアラの腕に抱かれたまま怯えた表情で辺りを見回すルカの様子を見る限り、意識して力を揮っているわけではないらしい。 だが、地下深くで蠢く熱は、間違いなくルカの波長に共鳴している。 おそらくは、ルカの激情に引き摺られて暴走した力の反動が出ているのだ。 一時的に揺れは収まったものの、すぐにもっと大きな波がやって来るだろう。 「まずいな」 同じ懸念を抱いているのであろう、厳しい表情で呟くランに頷いて、ルディは鋭く1つの名を呼ぶ。 「ライカ!」 彼の声に応えて現れたのは、銀灰色の毛並みをした大きな魔法狼だった。 「此処から1番近い地脈の要を探して」 主の依頼に疑問を挟む事もなく、銀狼は巨躯を翻して森の中へと駆け去る。 その後姿を見送ったルディは、意識を研ぎ澄ますかのように天を仰いで目を閉じた。 ステラは、精霊銀を編んだ鞭を握った掌を足元の地面に押しつけて大地を司る精霊に語りかける。 「土精【ノーム】、今しばし大地の怒りを抑えててくれ」 そうする間にも、大地は微かな鳴動を繰り返していた。 緊迫した空気の中、不安に満ちた数分が過ぎる。 やがて、ルディの唇から零れた小さな呟きが張り詰めた沈黙を破った。 「見つけた」 瞑っていた目を開いて、ルディは腕の中に身の丈を超える長さのウイングドスピアを召喚する。 自身の周りを囲むように素早く穂先で呪陣を描いたルディは、くるりと槍を回転させると大地に石突を突き立てた。 そのまま、胸の前で真っ直ぐに伸ばした腕で槍を支えると、荒れ狂う地脈を宥める呪文を唱え始める。 呪文といっても、柔らかな声で紡がれるそれは人の耳で聞き取れる言葉で紡がれたものではない。 普通の人間が耳にするそれは、譬えるなら独特の節回しで謳い上げられる聞きなれない異国語の詩か、意味のある詞を持たないハミングのようなものだ。 だが、そこに込められた力は、確実に地中を巡るエネルギーに働きかける。 言葉とも旋律ともつかない音が連なっていく毎に、大地の揺れは徐々に静まっていった。 虚空に据えられた眼差しで目の前にはない景色を見つめて、ルディはひたすら自然の気を慰撫する呪文を詠唱し続ける。 その姿を茫然と眺めるラウルの傍まで近づいたランは、傷ついた彼の額に腕を伸ばしながら静かに口を開いた。 「ルディの力はルカのそれと近い。森羅万象に宿る自然の力を借りて歪みを正し、恵みと安定を齎す力だ」 視線はラウルに向けたまま、ランは彼と、彼の隣で悄然と項垂れているルカへと語りかける。 「きちんと使い方を覚えれば、周りを傷つけるのではなく、護り癒す力になる」 まるでその言葉を証明するかのように、ランが翳した掌の下で、ラウルの傷は見る間に癒えていった。 ステラは、ルカの目の前に膝をついて揺れ動く双眸を覗き込むとこう問いかける。 「なぁ、ルカ。自分の力を使いこなせるようになりたいか?」 ルカは、僅かに迷ったものの、すぐにはっきりと頷いた。 「…うん。僕、お兄ちゃんを困らせるんじゃなくて、ちゃんと皆の役に立てるようになりたい」 「そっか」 真っ直ぐ返された眼差しに幼いルカなりの覚悟を見て取って、ステラは笑顔でそう応えた。 それから、表情を隠すように顔を伏せる。 再び視線を上げた時、その顔つきは魔導騎士であるプリンセス・ガードのリーダーのものに変わっていた。 「俺達は魔導騎士団LUX CRUX年少部隊の隊員だ。LUX CRUXには、ルカや俺達みたいな子供がいっぱいいて、魔法の勉強をしたり、その力を仕事に役立てたりしてる。此処に来たのも、ルカの立場を救いたいっていう司祭殿の依頼があったからだ」 あくまで任務に徹する為に、ステラは敢えて極力感情を排した声で事実を告げていく。 「司祭殿は出来ればこの町で今まで通りの生活が出来るようにって言ってたけど、町の人の反応を見る限り難しいだろう。今回みたいな騒ぎがあったら尚更だ。俺達としては、此処での暮らしを続けるのは無理があると判断せざるを得ない」 すると、状況についていけずに黙り込んでいたラウルがぼそりと口を挿んできた。 「…ルカを連れてくのか?」 俯いたまま発した震える声が、彼自身の感情の堰を切って落としたのだろう。 顔を上げ、縋るような眼差しをステラに向けて、ラウルは素直な真情を吐露する。 「父さんと母さんが死んでから、俺達はずっとふたりで生きてきたんだ。それなのに、俺からルカを奪うのか?」 懸命に言い募る彼の面持ちはそれまでの警戒心から来る険しさが嘘のように頼りないもので、打ち捨てられた仔犬か仔猫のように見る者の良心に訴えかけるものだった。 ステラは、深々と1つ溜息を落とすと、困惑の極みにあるであろうラウルに救いの手を差し伸べる。 「LUX CRUXにいるのは魔法使いだけじゃない。これまでルカの傍にいて何でもなかったって事は、あんたにも魔法に対する耐性があるんだろ。あんたさえその気なら働き口の1つや2つ見つけてやれない事もないさ」 それでもなお躊躇するラウルの後ろで、ティアラは抱き締めたままのルカににっこりと微笑んで問いかけた。 「あたし達と一緒に来る?」 ルカは、今度は迷う事なくしっかりと頷く。 その様子を視界の端で捉えたステラは、不意に誰もいない背後を振り返ると声高にこう宣言した。 「そんなわけで、ルカとラウルはLUX CRUXで保護させてもらう」 彼の言葉を待っていたかのように、屋敷の影から黒い法衣に身を包んだ老司祭が姿を現す。 「司祭様!」 驚くラウルを尻目に、ステラは動揺する風も見せずに彼の決断に対する了承を求めた。 「構わないな?」 「えぇ、それが良いでしょう」 こちらも落ち着いた態度でそう応じてから、老司祭はラウルとルカの兄弟に歩み寄る。 司祭は、戸惑うラウルの手を両手で包み込むと、その手に額を押しつけて謝罪の言葉を口にした。 「すまない、ラウル、ルカ。私が不甲斐ないばかりに、君達を守る事が出来なかった。神の司祭を名乗りながら、私はこの町の人々の心を正しい道に導く事さえ出来なかったのだ」 「司祭様…」 早くに両親を喪ったラウル達兄弟の事を、司祭はいつも気にかけてくれていた。 ルカの不可思議な力の事を知っても、彼を案じこそすれ咎め立てするような事は一切しなかった。 神に仕える身とはいえ…否、だからこそ、特異な能力を看過するのは難しかった筈だ。 それなのに、彼はここまでラウル達兄弟の為に心を砕いてくれていた。 司祭の誠実な人と為りを知るラウルは、感謝と恐縮の念から言葉を詰まらせる。 そんなラウルの気持ちは解らないでもないステラだったが、無粋を承知で2人の間に割って入った。 何しろ、まだ対処すべき問題が幾つか残っているのだ。 「町の人達には、遠い親戚に引き取られる事になったとか何とか無難な話をしておいた方が良いと思う」 「それと、あの連中も何とかしないと」と視線を流した先には、ティアラの召喚魔法で未だに眠り続ける襲撃者達の姿が在った。 「そうですね」 ステラの提案を溜息混じりに受け入れて、老司祭は遣る瀬無くも淡い笑みを疲れた顔に湛えて目を伏せる。 「せめて彼等が望む時にこの町に戻って来られるように、私は人々の疑心暗鬼を払い、2人の名誉を守る事に力を尽くしましょう」 そうして、改めてステラ達へと向き直った司祭は、彼等に向かって深々と頭を下げた。 「どうか、2人を宜しくお願いします」 「解ってる」 短く応えるステラの苦い感傷を和らげるように、地脈を鎮め終えてライカとの同調を解いたルディが穏やかにこう言い添える。 「大丈夫。LUX CRUXは悪い所じゃないよ」 それは何の根拠もない言葉だったけれど、その場にいる誰にとっても救いを齎すものだった。 |