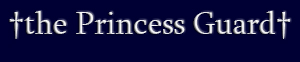|
ベッドに横たわるランの蒼白な寝顔に向かって、ステラが苦々しげに舌を打つ。 任務を終え、LUX CRUXの宿舎に戻ってすぐに、ランは意識を喪った。 医師の見立てでは、魔力の過負荷による一時的な貧血と過労が原因らしい。 医務室という場所柄から声は低く抑えているものの、ステラは不機嫌に毒づく。 「体調が悪いくせに、暴走した魔法の相殺なんて無茶するからぶっ倒れる羽目になるんだ」 彼の苛立ちは、ランを案じる気持ちの裏返しだ。 それが解っているから、ルディは敢えてステラを宥めようとはしなかった。 代わりに、常々感じていた疑問を思いつくままに口にする。 「ランって、あんまり丈夫じゃなさそうだよね。戦闘実技のクラスでも優秀な成績を取ってるから身体が弱いってワケじゃないみたいだし、あれだけ大きな魔法をいろいろ使いこなせるって事はそれに見合うだけの魔力も体力もある筈なんだけど…」 魔法というのは、知識を得ただけでは使える事にはならない。 実際に発動し、自分の意思で操る事が出来て初めて会得したと言えるのだ。 賢者と呼ばれる【月】の魔法使いを目指しているランは数多くの術を習得しており、それはつまりそれらの魔法を実践可能な実力が彼にある事を示していた。 「鍛え方が足りないんだろ」 未だ怒りの収まらないステラは、ルディの疑問を素気無く両断する。 そこに、俯き加減で心配そうにランを見つめていたティアラのか細い声が割って入った。 「ランを責めないで」 いつもは麗らかな春の陽だまりのようにほわほわとした印象を与える顔に思いつめた表情を浮かべて、ティアラはそっと唇を噛む。 「ランの生命力が落ちてるのは、あたしの所為なの」 そう言って、ティアラは首に掛かった銀の鎖を引き出した。 鎖の先には、交差する2本の細いリングでカボションカットのルビーを挿むようにしたデザインの指輪がペンダントトップの代わりに提げられている。 ピジョンブラッドと呼ばれる最上級のその石には、見事なスター効果が現れていた。 LUX CRUXでは、入団時に魔導武器の他に護符・魔導防具の類を1点のみ持ち込む事を認めている。 大抵の場合、それらは使い手の力を高め、その身を護る役割を担う物だった。 ステラは精霊との交渉力を高める五芒星が刻まれたイヤーカフスを、ルディは魔性を祓うケルト十字を象ったペンダントをそれぞれ身につけている。 ティアラの指輪にも守護の霊気が秘められていたが、それとは別の波動も感じ取れた。 ティアラは、ベッドの上に力なく投げ出されたランの左手をそっと持ち上げる。 ティアラのものと同じ意匠で石だけが違う指輪が、ほっそりとした中指に嵌められていた。 ランのそれは鮮やかなコーンフラワーブルーのスターサファイアだ。 「…それ…」 躊躇いがちに訊ねるルディにこくりと小さく頷いて、ティアラは2つの指輪にかけられた術の名を告げる。 「これは、【絆魂の鎖】。あたしとランの魂を繋ぐ誓約の魔法」 その途端、ステラの顔にさっと嫌悪の色が走った。 「掌魂術か!」 掌魂術――文字通り対象者の魂を掌握し、それによって相手の運命を絡め取り、時には意のままに操る事すら可能とする術である。 使い方次第では力ずくで他人を支配する事にも繋がるこの術は、自由を愛するステラからすれば唾棄すべき邪法だった。 「ふざけんなよ!何でそんなもん!」 今にもランに掴みかかりかねない勢いで声を荒げるステラに、ティアラは必死の面持ちで首を横に振る。 「違うの!そうじゃなくって――」 だが、弁明を試みるティアラの言葉は、何の前触れもなく寸断された。 糸が切れた操り人形のようにくったりと崩れ落ちるティアラの身体を、ベッドの上から伸ばされたランの腕が抱き止める。 「ラン!」 「少し眠ってもらっただけだ」 非難の声を上げるステラを小さく手を上げる仕草で遮って、ランは億劫そうに半身を起こした。 その気怠げな動きと疲れを感じさせる声に、ステラは辛うじて冷静さを取り戻す。 「…ティアラには聞かせたくない話か」 それでもまだ刺々しさの残る口調で問いかけたステラに頷いて、ランは静かに口を開いた。 「…2年前、南太平洋で海底火山の噴火があったのを覚えているか?」 「ポリネシアの各地に地震や津波を引き起こしたあれか」 「あれはティアラが惹き起こした厄災だ」 唐突に切り出された話題の意味を図りかねて怪訝そうな顔をしていたステラが、ランのその一言に絶句する。 「正確には、ティアラの存在が、と言うべきかな」 自分の言葉が与える影響を予期した上で爆弾発言をしてのけたランは、幾分口調を和らげた上で詳細を語り始めた。 「現場付近の海域では、通常噴火に先立って観測される予兆は全く探知されていなかった。大掛かりな魔法が行われた可能性も踏まえ、月瑠家は周囲への影響を最小限に食い止めるべく現場に術者を派遣した」 「そう言えば、噴火の規模の割りに被害は少なかったって聞いてる」 当時の記憶を辿っていたルディが、得心したという様子で口を挿む。 自然の力を無理に枉げれば、必ず別の場所で反動が生じる。 その為、自然崇拝系の魔導士は天災で生じたエネルギーを完全に封じ込めるのではなく、力の流れに干渉する事で極力被害を抑える術を模索する傾向にあった。 この時の月瑠家が採ったのもそういった策だったのだろう。 ランは、ルディの発言には応えずに淡々と話を続ける。 「噴火の中心地には、海底が隆起して出来た小さな島が在った。噴火の沈静化と共に海に沈んでしまったその島で、俺は1人の少女と出逢った」 未だ炎熱の朱を覗かせる大地に裸足で立ち、立ち上る蒸気の中で火傷ひとつ負わずに茫洋とした夢現の表情で佇んでいたその少女がティアラだった。 「ティアラの処遇を巡っては月瑠の家だけでなく多くの組織が参加して議論が繰り返された。岩漿の海から生まれたかのような不自然な出自に加えて、高熱の大気に晒されても傷つかない肉体、更に噴火そのものも彼女が招いた可能性が高い。魔導に携わる者にとって、彼女は驚異であると同時に脅威でもあった」 膝の上に広がるティアラの柔らかな髪にそっと手を滑らせて、ランは冷ややかに事実を告げる。 「この世に生まれてきた以上、ティアラにも生きる権利はあるし、それを奪う権限は我々にはない。だが、彼女の存在はあまりに危険過ぎる――結局、彼等は彼女を生かすなら厳重に封印された空間に閉じ込めておくしかないという結論に至った」 それは、未だ少年の域を出ないステラ達にとって、あまりに非人道的な裁決に思えた。 「保護観察を名目とした体の良い幽閉、だね」 「そんなの、生きてるなんて言えねぇだろ」 普段は温厚なルディがさすがに眉を顰め、ステラは忌々しげにそう吐き捨てる。 彼等の憤りは、かつてランも抱いたものだった。 「そう。だから、俺は彼等にひとつの案を提示した」 憤慨する2人に同意を示したランは、指輪を嵌めた左手を顔の前に翳すと、けして波立つ事のない声で彼自身の選んだ道を口にする。 「俺自身が彼女の力を封じる鳥籠になる」 魔力によって互いの魂を結びつける【絆魂の鎖】。 それは、見方を変えれば自らの命を賭けて相手の命に責任を負う事を意味する。 諸刃の剣ともいうべきこの術を、ランはティアラを護る鍵として用いたのだ。 「月瑠の長を務めていた俺の魔力を持ってすれば、辛うじてティアラの力にも対抗できる。更に、万が一彼女が暴走した時は、俺の命と引き換えに術を発動させれば良い。そう言って渋る長老達を納得させた」 「それで、月瑠の長を退いたんだ…」 代々魔法使いの家系で生まれ育ったルディは、ランが月瑠の長を下りた時の噂を聞き及んでいた。 月瑠家始まって以来の能力を持つと言われていた年若い長の突然の引退を、当時は誰もが訝しんだ。 だが、ティアラの力を封じる為に魔力と生命力を割いたのだとしたら納得できる。 己の力を律し、月瑠の長の座に留まる事で自らに枷を掛けていたラン。 自身も籠の鳥同然の立場に在ったからこそ、彼はティアラの境遇が見過ごせなかったのだろう。 今回の依頼を受けてからずっと様子がおかしかったのも、ルカに同情的だったのも説明がつく。 「LUX CRUXに入ったのもティアラの為なんだね」 しみじみと嘆息するルディに、ランはそっと目を伏せてこう呟く。 「ティアラには、出来るだけ普通の生活をさせたかった。此処でなら多少変わってはいてもそれが叶うし、俺の力を高める事も出来る」 静かに凪いだ声音からは、ランの揺るがない覚悟がひしひしと伝わって来た。 「なぁ、1つ訊いて良いか?」 暫しの沈黙の後、ステラがおずおずと口を開く。 「その術、本当に完全にティアラの力を抑え込めるものなのか?」 火山の噴火と共にこの世界に現れたと思しきティアラ。 天性の幻獣使いと称される彼女は、おそらく純粋な人間ではない。 そんなティアラの力を、幾ら強大な魔力を有するとはいえ果たして一介の人間が制御できるものだろうか? ランは、その問いに答える代わりにうっすらと微笑む。 それは、虚を突かれたステラが思わず見蕩れてしまったほどに綺麗で危険な微笑だった。 「…とにかく、事情は解った」 額に手を遣り、がっくりと項垂れながら、ステラは深々と溜息を吐く。 それから、勢い良く顔を上げると、ランの鼻先にびしりと人差し指を突きつけて力強くこう宣言した。 「解った以上、俺達も共犯だ。良いよな?」 「もちろん」 強引なステラの言い分を、ルディは当たり前のように受け入れる。 その上で、ルディは困惑するランに向かってにこやかに釘を刺した。 「だから、ラン独りで無理はしない事」 その言葉に瞠目したランは、ややあってふわりと口許を綻ばせる。 有無を言わせぬステラ達の態度に呆れて苦笑しているかのようなその表情は、けれどどこか泣き出しそうな切なさを孕んでいた。 ランの腕の下で眠り続けるティアラを愛しげに見下ろして、ステラはぎゅっと握った拳に決意を込める。 「俺達でティアラを護る」 それは、本当の意味で「プリンセス・ガード」が結成された瞬間だった。 |