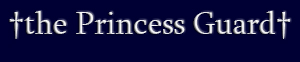|
おっとりとしたティアラと人当たりの良いルディの組み合わせは、初対面の相手にも警戒心を抱かせる事が少ない。 その為、見知らぬ土地でもするりと人の輪に溶け込む事が出来るのだ。 問題を解く鍵は、得てしてありきたりな日常の中に隠れているものだ。 他愛のない会話の中に垣間見える本音を拾い集める術に長けている2人は、この手の情報収集にはうってつけの人材だった。 月瑠家の長としての経験と知識を持つランと魔法界の常識に囚われない視点で物事を見据えるステラが、意図的に秘められた真実を過たず見抜くのとは好対照と言えるだろう。 今も、何処となく所在無げにも見えるティアラの様子に目を留めた小さな女の子が、物怖じする様子もなくにこにこと声を掛けてくる。 「お姉ちゃん達も、ルカに逢いに来たの?」 「ルカ?」 ぱちくりと目を瞬かせるティアラに、女の子は大切な秘密を打ち明けるようにほんのちょっぴり声を潜めて、けれど嬉しそうにこう答えた。 「そうよ。ルカは天使様なの。ママが病気になった時、ルカと一緒にお祈りしたら良くなったのよ」 彼女につられたのか、他の子供達も次々と声を上げる。 「日照りが続いて困ってた時に、雨を呼んでくれたよ」 「枯れかけてた広場の木も元気になったよね」 「隣町のいじめっ子だってやっつけてくれたんだ!」 ティアラを取り囲んだ子供達が口々に自慢の友人について語る姿は微笑ましいものだったが、最後の男の子の一言はルディに微かな不安を抱かせた。 魔法使いや超能力者といった超常者は、常に微妙な立場に置かれている。 人々の願いを叶え、役に立っているうちは多少の奇異にも目を瞑ってもらえるが、他人に危害を加えたとなれば話は別だ。 それまで口を揃えて誉めそやしていた人々が掌を返したように冷たい仕打ちに出たり、迫害者に変わる事も珍しくない。 更に、大人達の間でひそひそと交わされる噂話がルディの危惧を強める。 「聞きました?また北の森で野犬の屍骸が見つかったそうですのよ」 「先月だけでもう4匹目でしょう?」 「この間は、鶏舎で何羽も鶏が死んでたとか」 「先だっては、季節外れの長雨の所為で、山で土砂崩れがありましたしねぇ」 「気味の悪い。きっとそれもこれも、あの子供の所為ですわ」 輪になって頷き合う女性達の目には、既に半ば狂信的な光がちらついている。 このまま放っておけば、確実に厄介な事態に陥るだろう。 顔には穏和な笑みを浮かべたままルディが不穏な未来に思いを馳せていたところに、教会から出て来たステラ達が合流する。 「どうだった?」 早速依頼主について尋ねたルディに、ステラは僅かに言い澱む様子を見せた。 「あー、何て言うか、人の善い司祭サマだったぜ。元エクソシストって言ってたけど、積極的に異端狩りするタイプじゃなさそうだし。依頼の内容も、やっぱり悪魔祓いってのは口実で、異端視されそうな教区の子供を護りたいってのが本心なんだろーなーって感じ」 基本的に、ステラは情に篤い。 口は悪いし態度も大きくて滅多に他人を甘やかす素振りは見せないけれど、実際には優しい心根の持ち主なのだ。 だからこそ、今回の依頼人である老司祭のように悪意のない相手からの頼まれ事には、ビジネスライクに割り切れない分苦手意識を持っているのだろう。 「で?そっちはどうだった?」 ステラが話題を変えたがっているのを察したルディは、それ以上追求はせずに自分達の仕入れた情報を簡潔に伝える。 子供達の並べ立てた「天使様の奇蹟」の内容を一通り聞いたステラは、軽く肩を竦めて見せた。 「病気の治療に雨乞い、植物の蘇生に攻撃魔法までこなすのか。何でも有りだな」 呆れ半分に感心するステラに、ティアラが不思議そうな顔をする。 「でも、もともと魔法って何か1つしかできないっていうものじゃないでしょ?」 「まぁな。神聖魔法とか精霊魔法とかってのは人間が便宜上勝手に分類してるだけだし、得意不得意はあってもいろんなコトできるヤツの方が多いよな」 ステラの言葉通り、LUX CRUXに所属する魔道士のほとんどが複数の系統に跨って魔法を使いこなしている。 特に、訓練を受けていない幼い子供ほど制約なしで様々な方面の魔法を発動する傾向にあった。 大人になると魔力を喪うというのは、「魔法なんて有り得ない」という思い込みが力を封じる枷となっているという説もある。 特定の集団に属し、そこで教育を受ける事で能力がある方面に特化する、というのが実情なのだろう。 そういった事情を踏まえた上で、ルディは自身の見解を口にする。 「うん、でも、たぶんルカって子の能力は僕と同じ風水系なんじゃないかな」 広義での風水術とは、竜脈や地脈、精気、マナ等の名前で呼ばれる自然エネルギーを力の源とする魔法全般を指す。 この術を用いれば、大地に宿る生命力を動植物に分け与える事も、天候を操る事も理論上は可能だった。 もちろん死者を甦らせるような明らかに自然の摂理に反する業は使えないし、濫用すれば周辺の土地を痩せ衰えさせて不毛の地に変えてしまう場合もある。 「話を聞いた限りじゃ、その子の近辺で小規模とはいえ天変地異の類も起きてるみたいだし、周りの生態系にも影響が出始めてるんだと思う。ちゃんと力を制御できてない反動が出てるんじゃないかな」 「となると、早いとこ手を打たないとまずいな」 ルディの危惧するところを正確に酌んで、ステラは眉を顰める。 早急に行動に移るべくルカの自宅の場所を確認しようとしたステラは、その時になって漸くランの異変に気づいた。 「ラン?」 普段ならステラ達の先手を打って冷静かつ的確に指示を出す筈のランが、今日に限って司祭館を出て以来ずっと黙りこくったまま全く会話に参加していなかった。 それどころか、きつく握った左手で胸元を押さえて思案に暮れている姿は、どこか苦しそうにも見える。 「どうした?具合悪いのか?」 だが、気遣わしげなステラの声に我に返ったランは、すぐにいつもの調子を取り戻して淡々と応えた。 「いや、何でもない」 「ほんとに大丈夫?」 まだどこか心配そうなティアラを宥めるように微笑みかけるランの様子を、ステラはじっと凝視する。 常に卒なく振舞っているランのらしくもない態度が、ステラには気がかりだった。 しかし、今は目の前の任務が優先だ。 「ルカって子の家は町外れの森の近くって話だったよな。とりあえず、家族なり本人なりに会って話をつけよう」 「そうだね。これ以上大きな問題になる前にその子を止めた方が良い」 ステラの妥当な提案に、ルディも深刻な面持ちで頷く。 明るい陽射しに包まれた広場を抜けて、ステラ達は町の北側を覆う森へと向かう小道へと急いだ。 |