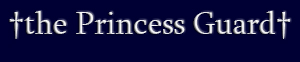|
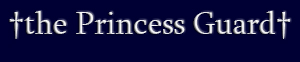
すっきりと晴れた翌日の日曜日、ステラ達はとある町の外れにある小さな教会を訪れていた。
昨日の午後、昼食もそこそこに呼び出しを受けた彼等は、年少部隊長のシェルアから直々に悪魔祓いの任務を申し渡された。
「悪魔祓い〜?」
盛大に顔を顰めるという上官に対するには論外な態度で、ステラは与えられた指令を鸚鵡返しにする。
「そんなもん、ヴァチカンのエクソシストにでもやらせとけよ」
魔法とは縁のないキリスト教圏の一般家庭で生まれ育ったステラは、同じ年頃の普通の子供達並には信仰心を持ち合わせている。
だが、魔法使い全般に対する彼の宗教の行って来た行為を思えば、屈託がないと言えば嘘になる。
シェルアは、不快感も露に苦々しく言い捨てるステラを諫める代わりに、素気無く彼の憤りを往なしてのけた。
「依頼してきたのはその町の司祭殿だ」
「…つまり、悪魔祓いというのは口実に過ぎないと?」
「おそらくな」
慎重に訊き返すランに頷くシェルアの表情からは、楚々とした風貌に相応しからぬ老獪さが窺える。
「万が一本当に悪魔憑きだったとしても、お前達なら祓えない事はないだろう」
それに、とランとティアラに意味深な視線を送って、シェルアは何時になく厳しい顔つきでこう続けた。
「対象は7歳の子供だそうだ。場合によっては、我々で保護する事になるかもしれん」
丁度朝の日曜学校が終わったところなのだろう、礼拝堂から出て来た子供達が焼き菓子の入った袋を手に迎えに来た家族の許へと駆けて行く。
最後の子供が元気良く挨拶して走り去るのを見送った司祭が、遠巻きに人々を見守るステラ達に気付いて動きを止めた。
ステラ達は、司祭と視線を合わせたまま目礼する。
司祭は、彼等に会釈を返すと、何事もなかったかのように礼拝堂の中へと戻って行った。
後には、誘うように僅かに開かれたままの扉が残される。
「神の家の扉は常に開かれているってか」
ほんの少し皮肉な口調でそう呟いて、ステラはルディとティアラをその場に残し、ランと連れ立って教会の扉へと向かった。
+ + +
「LUX CRUXの騎士殿ですな」
礼拝堂に足を踏み入れたステラとランを迎え入れたのは、穏和な雰囲気を纏った老司祭だった。
「お待ちしておりました。どうぞこちらへ」
とりあえず、落ち着いた物腰や気負いのない笑顔を見る限り、偏見に凝り固まって異端狩りに血道を上げるタイプではなさそうだ。
そう内心で値踏みするステラ達を、司祭は礼拝堂の奥にある司祭館に招き入れる。
通されたのは、年季の入った家具やオーブンの並ぶ厨房に小振りなテーブルセットを並べただけの、簡素な造りの食堂だった。
飾り気のない室内からは、この教会の倹しい暮らしぶりが見て取れる。
手ずから淹れた紅茶をテーブルに並べた老司祭は、2人がカップに口を付けるのを待って用件を切り出した。
「貴方方をお呼びしたのは、ある少年と会っていただきたかったからなのです」
そう言いながら、法服の胸ポケットから1枚の写真を取り出してステラ達の前に差し出す。
「名前はルカ。町の裏手にある森のそばの一軒家に、兄のラウルと2人で暮らしています」
写真の中央でにこやかに笑っている黒髪の子供がルカという少年らしい。
くるくるとした巻き毛をくしゃりとかき混ぜるようにして頭を撫でてやっているのが兄のラウルなのだろう。
甘えるように兄に笑いかけるあどけない横顔は、悪魔だとか悪霊だとかの類に憑かれているとは到底思えない無邪気なものだった。
ステラ達の思いを見透かしたかのように、老司祭は温かな眼差しを写真の中の兄弟に注いで口を開く。
「古くからの町の住人や子供達は、あの子を天の御使いと呼んでおります。彼等曰く、ルカは傷や病を癒し、願いを叶えてくれるのだとか」
「例えば、貴方のその左腕のように」
静かにカップをソーサーに戻しつつ断定的にそう指摘したランに、老司祭は軽く目を瞠って息を呑んだ。
教会に限らず、各宗教の寺院や神殿には特殊な場が築かれ易い。
信徒の捧げる祈りや信仰心が――往時の力を失いつつあるとはいえ――ある種の結界を形成するのだ。
そうした状況下で、何か月も前に発動したささやかな魔法の痕跡を見抜いたランの慧眼に、老司祭は彼等を頼った己の判断が正しかった事を悟る。
「えぇ、そうです。しかし、一方では、彼の周りで不可解な凶事が続いている節も見られます。その為、最近この辺りに越して来た若い世代の者の間ではあまり良くない噂が囁かれているのです」
思わし気に顔を曇らせてそう語った老司祭は、そこで1度言葉を切ると唐突とも思える話題を口にした。
「私はかつて、ヴァチカンで悪魔祓い師の職に就いておりました」
その時の縁で今回の件で魔導騎士団LUX CRUXに頼ろうと思い至ったのだと言って、司祭は続ける。
「悪魔憑きと一言に言っても様々なケースがありますが、その大半は心の問題として処理されます。思春期に特有の幻覚や妄想、強迫観念からくる集団ヒステリー…そういった精神的な要因に拠るケースがほとんどなのです。それでも、時に常識や科学では説明のつかない事例に遭遇する事もあります。私自身は然程力の強い祓い師ではありませんでしたが、人ならぬものの存在を見極める目にだけは恵まれておりました。あの子には、確かに人智を超えた力が与えられています」
「それで?」
これまでの遣り取りで、ステラはこの司祭が信頼に値する人物だと判断していた。
それでも、念の為に彼の本心を確かめておかなくてはならない。
「あんたとしては、そのルカって子を奇蹟の主として教区に報告して名を上げようってところか?」
「とんでもない」
不躾な口調で尋ねるステラの無礼を咎めるでもなく、老司祭は哀しげに首を横に振る。
「聖人に列せられれば、本人の意志に係わらず生涯を教会に捧げる事になります。おそらくは、聖なる力を守るという名目の下に聖都に閉じ込められて一生を終える事になるでしょう。ましてその力が魔のものと判じられればどのような仕打ちが待ち受けている事か…」
司祭の言動を注意深く見守っていたステラだったが、その時隣で黙って話を聴いているランの指先に一瞬不自然な力が込められたのを見逃さなかった。
だが、今はその意味を詮索する時ではない。
「いずれにせよ、あのような幼い子供にそのような過酷な運命を齎すのは神の思し召しではありますまい。出来る事なら、これまで通り兄弟揃ってこの町で静かに暮らせればと願っております。ですが、心無い中傷が町の人々の間に広がりつつあるのも事実なのです。私には、この町の人々の穏やかな日々を守る務めがあります」
言葉の端々に滲む司祭の苦悩には同情しつつも、ステラは容赦のない指摘を投げかける。
「汝の隣人を愛せよって有り難いお言葉はどこに行ったんだよ」
「残念ながら、人間は心弱いものなのですよ」
だからこそ、灯りを掲げて迷える子羊達を導く羊飼いが必要なのだとどこか寂しげに呟いて、老司祭は眩いほどに明るい窓の外に視線を流した。
熱を伴わない冬の陽射しは家々の屋根に降り積もった雪をきらきらと輝かせ、子供達の笑い声が教会前の広場に響く。
それは、何処にでもあるような、のどかで平穏な田舎町の光景だった。
しかし、光在るところには必ず影も生じるものだ。
再びステラ達に向き直った司祭は、孫ほども年の離れた彼等に真摯な面持ちで懇願する。
「このままでは、あの子の噂は早晩教区を統括する司教の耳にも届くでしょう。その前に貴方方にその力の真偽を見定めていただきたいのです」
それで彼等がルカの力を魔性と断じたらどうするつもりだと訊く事は、ステラには出来なかった。
BACK <<< ◆ >>> NEXT
|