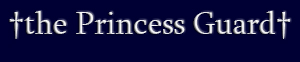|
如何にも高級そうなマホガニー製の扉を叩きつけるように閉めながら、ステラが怒り心頭といった態で喚き散らす。 仕事の拠点として提供された居間の中央に据えられた身体が沈み込むような豪奢なソファで早くも寛ぐ姿勢をみせていたルディは、興奮気味のステラを宥めようとやんわりと言葉を返した。 「お客様、かな。一応」 「そーゆーコト言ってんじゃねぇ!」 「そうよね。依頼主はあの子のお父様だもの、あの子はお客様じゃないよね」 「…いや、そういう話でもなくってな」 ルディに続きティアラにまで的外れにも程があるフォローをされてしまったステラは、がっくりと脱力して項垂れる。 彼等は、たった今警護対象の少女、エヴァ=テレサとの面談を終えたところだった。 クライアントである彼女の父親は上流階級特有の尊大さが少々鼻につくものの上品で温厚な紳士だったし、年若い――と言うかむしろ幼いと言っても良いステラ達を相応の礼を持って遇する理性の人でもあった。 問題は、肝心のエヴァの方だ。 「こんな子供が護衛ですって?」 彼女は、ステラ達を一目見た途端、蔑むようにそう口走ったのだ。 彼等の実力を知らない一般人から見れば、確かに十代前半の少年少女だけのチームが頼りなく思われるのは仕方ないとは思う。 だが、自分達より更に年下のお子様にまで言われたくない、というのがステラの正直な心情だ。 しかも、エヴァの高慢さは実の父親にも向けられる。 「ばっかみたい。お父様ったらいつもそう。世間体ばかり気にして、本当は私の事なんてどうでも良いんだわ。だからこんな形ばかりの警護なんてしてみせるのよ」 これには、さすがに温厚なルディも眉を顰めた。 当然の事ながら、魔導騎士団としてのLUX CRUXは誰にでも知られた存在という訳ではない。 魔導の実在を信じない人々にとってその称号は何の意味も持たないし、それどころか胡散臭いカルト集団として攻撃される危険性さえ伴う為、巧妙に秘匿されているのだ。 そんな彼等にコンタクトを取り、仕事を依頼する程事態を深刻に捉えている親の想いをまったく意に介さない彼女の言い草は、ステラ達の目には甘やかされて育った子供の我儘と映る。 思わず立場を忘れて反論しかけたステラだったが、彼に先んじてランが口を開いた。 「聖女に名を連ねようかという歌姫が魔物の歯牙に掛かろうとしているなど醜聞の極みだ。家の体面を考えるなら、LUX CRUXに警護の依頼などせず秘密裏に処理するだろう。お父上は真に君を思えばこそ、我々を呼んだんだ」 冷静な彼の言葉は、エヴァの口を噤ませる。 プリンセス・ガードへの依頼内容は、「エヴァを魔性の者の手から保護する事」だった。 聞く者の心を静め、苦悩を癒すと言われる奇跡の歌声…その力を狙う魔物が彼女にマーキングした痕跡が見つかったというのだ。 数日後に迫った列聖の式典までエヴァの心身を純潔のまま保って欲しいという依頼は、裏を返せば彼女が魔性に堕ちる懸念を抱かれている証に他ならない。 やれ聖女よ奇跡の歌姫よと祭り上げられる事に慣れたエヴァにとって、ランの指摘は屈辱的だった。 「何よ、雇われ魔導士のくせに偉そうな事言わないで!」 エヴァは、どこまでも相手を見下す事で自尊心を満たそうとする。 「そもそもプリンセス・ガードなんてふざけた名前からして気に入らないのよ。私は何も出来ずに庇われるだけのお姫様なんて真っ平だわ」 だが、そんな彼女の虚勢をステラは鼻で笑い飛ばした。 「安心しろよ。俺達が護るお姫様はあんたじゃない。あんたはただの警備対象、ショーウィンドウに並んだ商品みたいなもんだ」 エヴァの頬にかっと朱が上る。 「とにかく!警護なんて不要よ!出てって!」 癇癪を起こしたエヴァの剣幕に押される形で、ステラ達は彼女の私室から追い出された、という訳だ。 「とはいえ、任務を投げ出すわけにもいかないよなぁ」 うーとかあーとか意味不明の唸り声を上げて癖の強い赤毛をくしゃくしゃとかき混ぜていたステラだったが、半ば自棄気味とはいえ気持ちを切り替えて意を決する。 「とりあえず、ティアラには彼女と同じ部屋で寝泊りしてもらうとして、俺等で屋敷の内外の守りを固めるか」 「彼女が納得してくれれば良いけどね」 至ってにこやかなルディの相槌は、ステラの意気込みを挫くのに充分な破壊力を秘めていた。 + + +
|