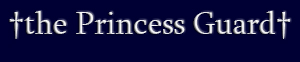|
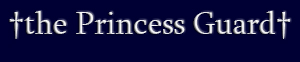
小春日和の、のどかな昼下がり。
午後一限目の授業が行われている魔導騎士団LUX
CRUX年少部隊魔法史学の教室は、まったりとした空気に包まれていた。
昼食を終えたばかりのこの時間帯は、ただでさえ眠気を催しやすいものだ。
その上陽射しはぽかぽかと暖かく、実験や計算で頭を使う理数系と違って講義に耳を傾けるだけの授業は退屈になりがちだ。
子供達の気が殺がれるのも無理はない。
欠伸を噛み殺す生徒も多い中で、熱心に窓の外を眺める少女が1人――。
「…アラ、ティアラ!ティアイエル=フュー!」
数度に渡って名を呼ばれて漸く我に返ったティアラは、ことりとあどけない仕草で小首を傾げた。
「はい、先生?」
全く悪びれる様子のないティアラに、厳格な女性教師は溜息を落とす。
「今は授業中ですよ、ミズ・フュー。窓の外ではなく教科書に集中なさい」
しかし、ティアラは何か気がかりでもあるのか、再び窓の方に視線を転じて口を開いた。
「でも…」
頑なな彼女の態度につられるように、窓際の席に座っていた何人かが外の景色に目を向ける。
「おっ、ステラとランの一騎打ちだ」
その中の1人がそう呟くと、たちまち他の子供達も窓辺に集まって来た。
「え、ほんと?見たい見たい!」
「あーあ、相っ変わらず派手だねぇ」
「ルディも大変だ」
好奇心と興奮に満ち溢れた歓声は、だが、すぐに悲鳴に変わる。
「うっわ!」
「嘘、危ないっ!」
+ + +
その時、グラウンドでは、戦闘技術の科目を択っている生徒達によるサッカーの試合が行われていた。
もちろん、魔導騎士団の隊員がプレーするだけあって、唯のサッカーとはワケが違う。
追加ルールは至ってシンプルだ。
ラフプレーは無し、魔法は有り。禁止事項はプレイヤーを直接魔法で攻撃する事。
とはいえ、地面が突然隆起したり不自然に芝が伸びたりする状況だけに気を抜けば容易く足を取られて転倒するし、魔法のかかったボールは立派な凶器になる。
相手が繰り出してくる技にどう対抗するのか、どんな魔法を使えば相手の守りを崩せるのか、咄嗟の判断力と魔導センス、そしてそれらを実行に移すだけの能力も求められるこのゲームは、魔導と戦闘能力の双方を鍛える訓練の一環だった。
もっとも、実際の試合そのものは大掛かりな奇術かサーカスかといった様相を呈している。
「行っけー!火の玉シューット!」
追い縋る相手ディフェンダーを自慢の俊足で躱わしたステラが、気合と共に文字通り火炎呪文で火の玉と化した弾丸シュートを放つ。
触れれば火傷は確実、キーパーも迂闊に手が出せない必殺技だ。
だが、ゴールへと突き進むボールの軌道上には、臆する様子もなく立ちはだかるランの姿があった。
彼の前には、揺らめく流水の壁が一定の間隔を保って立ち並んでいる。
炎を纏ったボールが水の壁に触れた瞬間、じゅっという音と共に盛大な水煙が上がった。
「危ないなぁ。もうちょっと加減してくれないと」
視界を奪う高温の蒸気から周りの子供達を守る障壁を作り出したルディが、過激な攻防を繰り広げる友人ににこやかな表情でおっとりと苦言を呈する。
当然、審判役の教師は己の身はしっかり守ったものの、その額には脂汗が滲んでいた。
その間にも、水の壁を突き抜けるごとに炎共々勢いをなくしたボールはランの足許にぽとりと落ちる。
「くそっ、やるな!」
ちっと舌打ちひとつ、ステラは攻勢に転じるランを止めようと駆け出した。
が、急激に凍りついた大地に足を滑らせて勢いバランスを崩す。
危うく転倒しかけた彼を嘲笑うかのように、ランの蹴ったボールがふわりとステラの頭の上を越えていった。
ボールは、そのままステラの横を駆け抜けたランの足許にぴたりと吸いつく。
「逃げるな、ラン!俺と勝負しろ!」
「君みたいな体力バカをまともに相手にする気はない」
「なーにぃー」
挑発をあっさりとかわされたステラは、体勢を立て直すや否や猛然とランを追いかけた。
ステラをサポートすべくチームメイトが繰り出す魔法は、残念ながらランと彼の操るボールには一切効果を及ぼさない。
ランの守護魔法の方が、彼等の魔法より強力に働いているのだ。
魔導で敵わぬのならせめて肉弾戦で…とばかりに突っ込んでくるディフェンス陣を軽やかな身ごなしで振り払ったランが、雷を帯びたシュートを打つ。
「させるか!」
背後から走り込んで来たステラは、ボールをゴールから弾き出そうと力一杯風の魔法を叩き込んだ。
ランとステラ、衝突する2人の力に耐え切れずにボールが破裂する。
衝撃はそれだけに留まらなかった。
フィールド上の生徒はもちろん、グラウンドを囲む櫟の並木まで薙ぎ倒す勢いで爆風が同心円状に広がっていく。
居合わせた教師とルディ、そしてラン自身の結界によってどうにか事なきを得たものの、その余波は学舎の窓ガラスをびりびりと震わせた。
「ステラ=ミラ!ラン=ユエル!」
一瞬の安堵の後に、担当教師が当事者2人を怒鳴りつける。
ばつが悪そうに首を竦めるステラの隣で、ランは溜息混じりに天を仰いだ。
+ + +
「またお前達か…」
年少部隊の司令部に呼びつけられたステラとラン、ルディ、ティアラの4人は、隊長であるシェルアのうんざりとした声に出迎えられた。
「まったく、次から次へとよくもまぁ騒ぎを起こすものだ」
呆れるシェルアの隣で、副隊長のキーラムが零れ落ちそうな微苦笑を懸命に堪えている。
入隊から早数ヶ月、ステラ率いるプリンセス・ガードはすっかりLUX CRUX年少部隊の名物パーティーになっていた。
完遂した任務の数やその難易度もさる事ながら、彼等――と言っても、主にステラとティアラの2人が発端となるのだが――が起こした騒動は騎士団の内外を問わず枚挙に暇がない。
今日のように危うく学舎を吹き飛ばしそうになった事も、1度や2度ではないのだ。
糅てて加えて、彼等1人ひとりの人気の高さがその注目度に拍車を掛けている。
ステラのやんちゃぶりは同性の悪童達の共感を集めているし、ランはその優秀さと品のある立ち居振る舞いから憧憬の的になっている。
穏やかで愛想のいいルディは年上のお姉さま方のアイドルで、おっとりとしていて掴みどころのないティアラは妹キャラとして周囲から可愛がられていた。
首脳陣としては、他の団員に及ぼす影響を考えると非常に頭の痛いところである。
シェルアは、紅茶を一口啜る事で幾分気を取り直すと、困った可愛い後輩に向かってこう切り出した。
「丁度良い。プリンセス・ガードを名指しで要人警護の依頼が来ている。その有り余る力を任務で発散して来い」
「要人警護、ですか?」
告げられた内容を、ランが怪訝そうに鸚鵡返しにする。
通常、人身警護の仕事は年少部隊にはほとんど回って来ない。
それは、純粋な能力の問題だけではなく、心理的な配慮に基づく判断だった。
護られる側としては、派遣されたのが子供ではどうしても心許無く感じてしまう。
ただでさえ不安に駆られている筈の依頼人に少しでも安心してもらう事も仕事の内だった。
それに、未成年では立ち入りを禁じられる場所があったり周囲からも見くびられて協力を拒まれたりと何かと不便な事も多い。
尤も、逆に子供だからこそ入り込める場所や、活躍できる状況というものも有る。
「特殊事情ってヤツか?」
立場の違いなど何処吹く風といった調子で訊き返すステラに、シェルアは我が意を得たりと微笑み返す。
「そうだ。どうやら、依頼人はお前達のコードネームが甚くお気に召したらしい」
目にも艶やかな笑顔からは、しかし、何やら意味深長な様子が伺えた。
案の定、続く彼女の言葉には、プリンセス・ガードの面々をからかう響きが含まれる。
「警護対象は希代の歌姫エヴァ=テレサ。若干10歳にしてグレゴリオ聖歌を解する神童だ」
BACK <<< ◆ >>> NEXT
|