あなたはご存じだろうか、”エルドラン”という島を。
遠い海の遙か彼方に、その島はあるという・・・・
「よしっ! 待ってろよ、サヤカ、エディン!」
斜面の下の藪に消えた二人を助けるべく、勢いよくナユタは飛び出した。浅黒くて凛々しいその顔立ちは、どこか野性的なたくましさを感じさせる。さすがは、”森の住人”狩人に変身しているだけあった。
夕焼けを背景に、コンドルのように両手を広げるナユタのシルエット。本当に鳥になって飛んでいきそうだ。そんな、神話のような雰囲気さえ感じさせるほどである。
サヤカ達を見つけだすという使命を刻み込んだナユタの瞳は、真っ赤な夕日よりも燃え上がっていた。
・・・・という美しい描写は、
「うひゃあ~!」
という情けない声と共に、ガラスのように崩れ去っていくのであった・・・・。
その先に急な斜面があることも忘れ、猛然と飛び出すお間抜けな男に待っている運命は、言わずもがなである。あのライオンのように凛々しい顔つきはどこへやら。涙を流しておののく猫のキャラクターのような顔をして、ナユタは落下していく。
そんなナユタを、手を振って見送ってやろうではないか。彼の体を張った芸に、敬意を表して・・・・
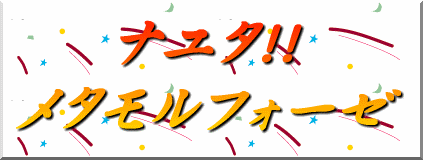
第二笑・楽しいピクニックに・・・・なるわけないよね(^^;②
6
ドドドドドドドドドドドドドドドドド・・・・ズシャシャシャシャシャッ!!
派手な土埃をあげて、ナユタが急斜面を転げ落ちてくる。ナユタはそのまま背の高い藪の中に突っ込み、枯れ草を巻き上げた。騒々しく擦れる草の音が、小石を投げた池の波紋のように広がっていく。
突然の珍事に驚いたのか、藪の中から茶色いリスが二匹、「キュキュッ」という鳴き声をあげて飛び出してきた。やがて藪の中は、それまでの静けさを取り戻していく。
藪の中に目を向けると、後ろまわりに失敗したような格好で、ナユタはひっくり返っていた。
「げほっ、げほっ! ぺぺっ」
その体勢のまま、ナユタは二、三度むせ返る。そして、舌に張り付いていた葉っぱをツバと共に飛ばした。
「いててててて・・・・」
顔をしかめ、背中をさすりながらナユタは上体を起こした。服やら顔やらには、雪を被ったように枯れ草がへばりついている。
辺りを見回すと、うっそうと生い茂る藪がナユタの視界をさえぎった。”恐怖の回転地獄!! 急斜面で一人大車輪”の次に待っていたのは、気の遠くなるほどの”藪地獄”である。
唯一視界が開けているのは、紅に染まる空の覗く頭上だけであった。それ以外は、自分の落ちてきた斜面の方向すら分からない。前も、後ろも、右も、左も、藪また藪である。
狩人らしく、ナユタは羽根つき帽子と身軽な服装、そして背中には弓矢を背負っていた。しかし、茶色というよりむしろ黄色に近いその服は、狩人にしてはかなり珍しい。エルドランはもとより、世界中を見渡しても二人といないだろう。
そんな疑いたくなるようなセンスを持つ妖怪が、ナユタの頭上に飛んできた。
鷲に変身したナインテールである。ナユタが転がり落ちるのを楽しそうに斜面の上から見物し、自分は鳥に変身してゆったりとやってきたのだ。
「とことんドジだなぁ、お前は。表彰したいぐらいだ」
呆れながらもどこか楽しげに、ナインテールはナユタの声をかけた。
「しないでよ、そんなことで」
ふてくされるように頬を膨らませながら、ナユタは立ち上がる。それからポンポンと身体を叩いて、張り付いた枯れ草を払おうとした。
が、細かい枯れ草はなかなか払い落とせない。ムキになって強く叩いたら身体が痛くなってきたので、「ふんっ」と鼻息をついて諦めてしまった。
「ところでナユタ、どうやってサヤカ達を探すんだ?」
「ふふふ~、そこは任せてよ」
立ち直りの早いナユタは、目を閉じて口の前で人差し指を左右に振り、「チッチッチ」と舌を鳴らした。なかなかカッコイイ仕草ではあるが、至る所に張り付いた枯れ草がすべてを台無しにしている。
「下を見てごらん」
そう言って、ナユタは自分の立っている地面を指さした。
「お前が無様な格好でひっくり返っていた所だろ。それがどうかしたのか?」
「・・・・いつも思うんだけど、なんか一言いつも余計なんじゃない?」
「んん、そうか? オレ様は思った通りのことを言っているだけだが」
「・・・・まあいいよ」
まじめな顔をしてナインテールが答えるので、ナユタはあえてそれ以上突っ込むのをやめた。
「僕が立っている場所をよく見てみると、藪がかなり荒れているだろ?」
「だからそれは、お前が無様にひっくり返ったからだろうが」
「・・・・ぼ、僕一人だけが転がり落ちてきたんじゃ、こんな広範囲に藪は荒れないんだよ」
目尻をピクピクさせ、奥歯を噛みしめながらナユタは答えた。いまにも湯気が立ち上りそうほど真っ赤な表情を、どうにか冷静に保とうとする。
「つまり、ここで僕以外の誰かが倒れてたってことさ」
ナユタが示すとおり、彼のまわりの藪はずいぶんと荒れていた。何かの力が加わったかのように、根元の方から折れ曲がった藪が目立つ。
「いったい誰かと問えば?」
「もちろんサヤカとエディンに決まっている。二人はここに転がってきたんだよ。斜面に残っていた跡も、ここに通じていたからね」
「なるほどな。でもサヤカ達の姿は見えないじゃないか」
頭上のナインテールが、あたりをキョロキョロと見渡しながら言った。
背の高い藪が目立つので姿は見えないが、もしサヤカ達が近くにいれば、その辺りの藪がざわついているはずである。しかしナインテールの見たところ、広い藪はいたって静かであった。風になびく藪がサワサワと揺れている。
「ここから移動したんだよ。藪をかき分けたような跡が続いているだろ」
「ああ、そう言われてみれば・・・・」
藪を上から見ると、ナユタの指し示す方向に不自然な筋が走っていた。その筋はそのまま、藪の先にある森の方に伸びている。
「この先に必ずサヤカ達がいるはずだよ。僕には分かるんだ。サヤカ達の残していったこの跡が、感動の再会へと続く希望の道だってね」
不自然にかき分けられた藪を指さすナユタの眼が、すべてを悟ったかのようにキラリと輝いた。爆笑のオチへと続くいつもの前フリでないことを祈るが・・・・。
まぁ、それはとにかく。ナユタは誘(いざな)われるようにして、藪の踏み分けられた跡へと足を踏み入れたのであった。
それから、さらに夕日が傾いた・・・・。
まるで果てしなく続くカーテンのような藪を、ナユタは両手を使って左右に切り開いていった。
いつまでも、
さらにいつまでも、
まだまだいつまでも、
本当にいつまでも、
果てしなくいつまでも、
まだあるのかって程いつまでも。
もういいだろって程いつまでも。、
いい加減に飽きたよって程いつまでも、
そこまでやる必要はないだろって程いつまでも、
どこまで続ける気だよって程いつまでも、
ムキになっているだろって程いつまでも、
読者も疲れてきそうな程いつまでも、
作者も嫌になる程いつまでも・・・・。
醜い悪魔をさらに踏みつぶしたようなナユタの表情からは、疲労の色がありありとうかがえた。額に光る汗が目尻の横を通り抜け、頬を使ってあごの先から足下に落ちていく。それほど藪の中を抜けるのは重労働なのだ。
ヘトヘトになりながら一歩踏み出した瞬間・・・・
パシッ!
足下からせり上がってきた藪に顔面を叩(はた)かれた。さらに藪を押さえていた両手を放したもんだから、左右から同時にバシッと叩かれる。
「・・・・・・」
たちまちナユタの顔面には、メロンのような筋が現れた。ナユタはワナワナと震える手で、腰の短剣を掴む。
「だ~、くそ~! 藪まで僕を馬鹿にするか~! このひょろっとした草野郎~! 結局お前なんかそうやって集まらなきゃ何にもできないんじゃないか! お前一人で何ができる、ええっ!? どうなんだ、答えて見ろ! 答えられないだろう! なぜかって? それはお前には口がないからだ、はっはっは~! どうだ、悔しかったら喋ってみろ! ベロベロバ~、だ!」
いわれのない罵声を浴びせられながら、細切(こまぎ)れにされた哀れな藪は、埃のように舞い上がった。藪相手に、ムキになって対抗意識を燃やすナユタもナユタである。
結局ナユタの大噴火は、ナイフの刃がボロボロになって藪が切れなくなるまで続いた。
さらに藪を進むことしばし・・・・。
「ねぇ、ナインテール。まだ藪を抜けられないのぉ?」
足枷をはめられた囚人のように身体を引きずり、けだるそうな表情でナユタはナインテールを見上げた。
そのナインテールは、空を気持ち良さそうに羽ばたいていた。ゆったりとした動きで、ナユタの頭上を優雅に旋回している。夕日に燃える空を背景になかなか美しい姿なのだが、ナユタにとっては忌々しいこと極まりなかった。
「う~ん、もうちょっとかなぁ~」
「さっきからそればかりじゃないか・・・・」
「じゃあ、あとほんのちょっとだ」
「”じゃあ”ってねぇ・・・・」
ナユタは深いため息をつく。肉体的な疲労に加え、精神的な疲労がどっと湧いてきた。
「何だ? オレ様の言葉にケチを付けようってのか?」
「ケチって言うか、どう考えても一人で楽をしてるような気がするんだけど・・・・」
「ああ、楽してるさ」
なぜかナインテールは親指を立てる(あくまで様な)仕草をして即答した。
「どうして誇らしげなんだよ~」
「なぜかって? 当たり前だろう、オレ様は大妖怪なんだから」
ナユタに見せつけるように、ナインテールは空中で次々と別の鳥に変身していった。
始めは勇ましいコンドルに。そして華やかな孔雀、優美な白鳥、かわいらしい文鳥、不気味な大烏(おおがらす)、さらには幻のドードー鳥、ファンタジー世界ではお馴染みの大怪鳥ロック鳥。しかし最後は空を飛べないキューイに変身してしまったため、きりもみ回転をしながら墜落していく・・・・。
「ど、どうだナユタ。エルドラン最高、いや、エルドランなどオレ様には小さすぎる。世界だ。オレ様は世界最高の妖怪だ。わ~はっはっはっはっ!」
多少慌てつつも、鷲に戻ったナインテールは会心の笑みを浮かべていた。そしてナインテールは高らかに宣言するかのように、
「ナユタのようなドジな男が主人公のアホな物語なんか今回で終わり。今度こそオレ様が主役だ。その名も”大妖怪ナインテール様の、妖怪退治など小指一本で十分だ!”のスタートォ~~!」
などと大それた戯言まで口に出した。完全に自分の世界に入ってしまったナインテールを、もう止めることはできない・・・・。
「正義の妖怪ナインテール様の活躍を描く、まさに妖怪退治モノの最高傑作だ。うなる鋭いツメ、炸裂する鬼火、華麗なる変身術。やがて新たなる仲間との出会い、敵か味方か謎の妖怪の出現、そして闇に蠢(うごめ)く巨大な悪。ライバル達との死闘と、そして仲間の死を乗り越えて、オレ様はたった一人で妖怪の大王をうち倒した。しか~し!」
そこでナインテールは拳を握り、さらに口調を強めた。いつの間にやら、オーバーなアクションまで加えている。
「傷つくオレ様の前に、大王を陰で操っていた妖怪の神が現れる。圧倒的な力を持つ神に、オレ様は為す術もなく倒れた。しかしとどめを刺される直前、オレ様はもう一人の妖怪の神に助けられる。つまり、邪悪な神と正義の神とがいたわけだ。正義の神はオレ様を救うために命を落とすが、生き残ったオレ様は奥義を会得するために地獄の修行を積む。そしてスーパー九尾となったオレ様は、邪悪な妖怪の神に最後の戦いを挑むのだ。
はたして生き残るのはどちらか? 手に汗握る、ノンストップアクションSF伝奇ホラー学園ラブコメディーミステリーファンタジー超大作。乱れ飛ぶ銃弾、宇宙に飛び交う閃光、封印を解かれた悪の妖怪、迫り来るゾンビ、華麗に舞うセーラー服少女、爆笑のギャグ、完全な密室殺人、大地を揺るがす大魔法。オレ様の強さと、知性と、格好良さだけが目立つ完全無欠の物語だ!」
「途中から激しくむちゃくちゃになってないか? 妖怪退治モノの最高傑作だか何かはどこにいったんだよ・・・・」
地上で一人呟くナユタは、自分に酔いしれるナインテールを思いっきり冷めた目つきで見つめていた。
しかし逆にいえばチャンスである。ここでナインテールをのせてしまえば、ホイホイと自分も鳥に変身させてもらえるかも知れない。そうすれば自分の同じように楽ができるのだ。
「いよっ、世紀の大妖怪! 強くて、頭が切れて、カッコイイ。まさに三拍子揃ったスーパースター! 世界中の女性の視線は独り占めだ。にくいねぇ~、この!」
「はっはっは~、ようやくお前もオレ様のすごさが分かってきたか。何ならお前を付き人ぐらいにさせてやってもいいぞ」
裸の王様のようなナインテールは、途方もなく勘違いな自己満足に浸っていた。しまいには、世界は自分のために回っているとでも言い出しそうなほどである。
「そんなナインテール様のお力で、僕も鳥に変身させてくれない?」
「・・・・・・。ヤダね」
ナユタの企みはあっさりと崩壊した。
「考える素振りもなしかい~!」
「お前は何も分かっちゃいないんだな・・・・」
ナインテールは「はぁ~」と深いため息をつく。そして出来の悪い生徒に教える教師のように、目を閉じて腕(コンドルの場合は羽根であるが)を組むような格好で言葉を続けた。
「変身、変身と干しブドウのような脳ミソを持つお前は気軽に言うけどな、変身させるのも結構力を使うんだぞ。例えこのオレ様であっても、ポンポンと使えるような能力ではないんだ」
「さっきはポンポンと使っていたくせに・・・・」
ナユタは地面に吐き捨てるように、ボソリと呟いた。
「あ゛あ゛? なんか言ったか?」
「い、いやっ、なにも。へっへっへ・・・・」
結局これがいつものパターンなのである。ヘビなど遙かに通り越し、暗殺者(アサッシン)のナイフのようなナインテールの鋭い視線に、苦笑いを浮かべてナユタは降参した。
7
さて、気を取り直して、ナユタは再び藪の中を進み始めた。そして、一歩、二歩、三歩・・・・
藪を抜けたのだった・・・・。
「ナインテール・・・・」
声のトーンが、井戸に落とした石のように落ちていく。すべてを集約したつぶやきと共に、ナユタの全身から力が抜けていった。肉体的に疲れ、精神的に疲れ、しまいには魂まで疲れてくるような感じがしてきた。
うなだれるナユタの耳には、風になびく木々のざわめきが、まるで笑い声のように聞こえてくる。
そして頭上では、けたたましい歓声が上がった。
「ほっ、ほら見てみろナユタ。すぐに藪を抜けたじゃないか!」
「自分で驚いてどうするんだよ~!」
羽根つき帽子を地面にたたきつけて、ナユタが叫ぶ。
「はっはっは~! 直感だけで未来を当ててしまうとは、やはりオレ様は大妖怪だったんだ。これが世に言う”予知”だな。おおっ、そういえばオレ様は”テレパシー”も使えるではないか! 残るは”念力”だな。すぐにマスターして、念力でナユタにツッコミを入れてやる。名付けて”念力ツッコミ”だ。ボケた瞬間、見えない力に吹き飛ばされるナユタ。まったく新しいツッコミだ、ふっふっふ・・・・」
「”念力ツッコミ”って、なんか嫌だなぁ・・・・」
もはや”直感”という言葉には少しの疑問も抱かない、理解ある男である。
そのナユタは、気持ちを切り替えるように短いため息をつくと、その場にしゃがみ込んだ。そして何かを探すように、土の地面の上を手でなぞっていく。
「んん?」
その仕草に興味を持ったのか、ナインテールは地上まで降りてきて変身を解いた。
九尾の姿に戻ったナインテールは、地面の上を這うナユタの手と真剣な眼差しを、代わる代わる見つめる。そしておもむろに、こう訊ねた。
「金貨でも落としたのか?」
「・・・・・・はぁ?」
「いや、マジな顔して何か探してたみたいだから」
「あのねぇ、そんなわけないだろ」
「じゃあ家の鍵だな! どうしてくれる、帰っても家の中に入れないじゃないか! 家には入れないってことは・・・・。うおおおおおお、飯が食えないぃぃぃぃぃぃ!」
「勝手に断定するんじゃな~い!」
この世の終わりを宣告されたように頭を抱えるナインテールの言葉を、ナユタは猛然と否定した。
「足跡だよ。あ・し・あ・と」
「ほぉ~、サヤカ達の足取りを追おうっていうんだな?」
「その通りさ」
ナユタは腕組みをしながら、コクリと頷いた。
「サヤカ達がこっちの方に来たのは間違いない。しかもこんな森の奥まで人間が入ってくるとは思えないから、この辺に足跡が残っているとしたら、それは絶対サヤカ達のものだよ」
「おお、冴えてるじゃないか」
「へへっ、伊達に狩人に変身しるわけじゃないさ」
ナユタはちょっと得意げな表情をして、鼻の下を指でこすった。
「以外とこんな所にあったりしてね」
冗談半分で指さしたまさにその位置に、
「ホントにあった~!」
足跡があったのである。見つけた本人が一番驚いていた。
「ちょ、ちょっと確かめてみよう」
興奮醒めやらぬ様子のまま、ナユタは足跡を調べてみることにした。
黒い地面の上に、くっきりと靴の跡が残っている。靴を履く動物なんているわけないだろうから、まず人間のものと思って良いだろうと、納得するようにナユタは一つ頷いた。
次にナユタは、自分の履いていた靴をその足跡の隣りに並べてみる。地面に残っている足跡は、自分のものよりもいくらか小さい。しかし子供にしては大きいから、サヤカのものであろう。
靴のつま先の方向は、ナユタの正面の方に向かって続いている。視線を真っ直ぐ地面の上に沿って進めると、その先にも同じような靴の跡があった。
(よしっ!)
ナユタの心の中で、期待が一気に膨らんでいった。目をいっぱいに開いて、靴の跡を追っていく、まるでクリスマスの日までを、カレンダーで数える子供のような表情だ。
やがて足跡は、草むらへと続いていた。人間の腰の高さほどあるその草むらは、いかにも何か出てきそう雰囲気を醸し出している。その草むらが、不意に「ガサリ」と音を立てた。
「サヤカ!」
弾けるようにナユタは立ち上がり、草むらの上に視線を向けた。そしてそこにいたのは・・・・、
「・・・・あれ?」
サヤカではなくワーウルフだった。
ワーウルフとは、いわゆる狼男のことだと思ってもらうといい。つまり人間と同じような手足を持った、直立歩行する狼のことである。人間に変身する能力も持っており、滅多に見ることのできない幻獣である。
ナユタの前に現れたワーウルフは、ボロボロのシャツを身につけていた。下半身は草むらに隠れて見えないが、シャツと同じようにボロボロのズボンを革のベルトで留めているのが分かる。
「サ、サヤカ・・・・。どうしてそんな鋭い目をしているの?」
完全に錯乱しているナユタは、震える口調でわけの分からない言葉を口に出した。
「それはなぁ、獲物を睨み付けるためさ」
ワーウルフから帰ってきた言葉は、紛れもなく人間のものだった。低く、まるで裏通りのチンピラのような殺気すら感じさせる。
「どうして、そんな大きな口をしているの?」
「そいつはなぁ・・・・」
ワーウルフが、その双眸を上弦の三日月のようにニタリとゆがめた。
「お前を食うためだ!」
雄叫びと共に、ワーウルフは草むらから躍り出た。その足には、しっかりと靴が履かれている。
ナユタは完全に失念しているが、ここはファンタジー世界。なにも靴を履くのは、人間だけとは限らないのだ。幻獣達の中にも、靴ぐらい履くやつがいたっておかしくない。
「こちとら三日三晩森をさまよって獲物を探しているんだ。さっきはいきなり鉛の球が飛んできて人間のガキ二人を見失なっちまったが、やっと食い物にありつけそうだぜ。ひっひっひ・・・・」
よく見ると、ワーウルフの額は小さく腫れ上がっている。そんなワーウルフの口の中からはダラダラと唾液が溢れ、地面を濡らしていた。大雨警報まっただ中の大きな口は、血の雨注意報が発令されてもおかしくない。
イカれたジャンキーのようなワーウルフの姿を見ながら、ナインテールはこう呟いた。
「つまりこういうことか。あのワーウルフはサヤカ達を追いかけ、そのワーウルフの後をナユタが追いかけていたと・・・・」
推理をする探偵のごとく、ナインテールは細い眼をさらに細めてシリアスな顔をする。
「挙げ句の果てに、サヤカ達を見失ったワーウルフの前にノコノコと現れるとは・・・・。相変わらず、何のために変身したのか分からんやっちゃなぁ・・・・」
シラけた眼で言うナインテールの呟きもナユタには聞こえていなのか、身動き一つしないまま表情を引き締めている。
「くっくっく、ビビッて固まっちまったか? まぁ安心しろ、ひと思いに喉をかき切ってやる。痛みは一瞬だ」
鋭い犬歯をむき出しながら、ワーウルフは一歩二歩とナユタに近づいていった。油断のないその動きは、やはり獣の血が混ざっていることを思い起こさせる。
しかし、いまのナユタはいつものナユタではない! 身動きができなかったのではなく、ただカッコつけたかっただけなのだ。
「待てっ! それ以上近づくとお前の腹に風穴が開くぞ!」
ナユタは素早く弓矢を構えると、鉄の矢じりをワーウルフの腹に向けた。ナユタの思わぬ行動に、ワーウルフの足がピクッと止まる。
「へへっ、脅しのつもりか? そいつはオモチャじゃないんだぜ。危なっかしいモンをむけるんじゃねえよ」
ナユタの行動を、ただのハッタリだと思ったのであろう。子供をおちょくる悪党のようなせせら笑いを浮かべ、構わずワーウルフはナユタに近寄っていった。
その時「ヒュン」という音が、夕日の溶け込んだ空を切り裂いた。その刹那、ワーウルフの額の毛皮がヒラヒラと舞い、「ダン!」という重い音を立てて弓矢が背後の木に突き刺さる。
ワーウルフは大きく見開いた両目をヒクヒクとさせながら、剥製のように硬直していた。
「脅しなんかじゃないさ。今のはわざと外してやったけど、次はその身体を射抜くぞ。命が惜しかったらここから去るんだ」
ナユタは次の矢を構え、視線の先にある矢じりをワーウルフの眉間に重ねた。黒光りする鉄の矢じりの向こうでは、ワーウルフがこちらを睨み付けながら、黄ばんだ歯をギリギリと擦り合わせている。
時が止まってしまったかのように、二人はにらみ合いを続けた。水を打ったように静まり返った森の中には、次第に大きくなっていくワーウルフの歯ぎしりだけが響いている。そして、
「なめんなぁー! 人間の狩人ごときにやられてたまるか! こっちだって命賭けてんだ!」
意を決し、ワーウルフは大地を蹴ってナユタに襲いかかってきた。両者の距離が一瞬にして縮まる。
ナユタも素早く反応し、矢を射るべく渾身の力を込めて弓矢を振り絞った。そして次の瞬間!
ブチッ!
何と弓矢の弦が切れたのであった。
「どわあああああ!」
目玉が飛び出さんばかりの勢いで、ナユタは弓の弦を凝視した。希望を根こそぎ奪い去るように、切れた弦がフラフラと力無く垂れ下がっている。
唾液にまみれたワーウルフの牙は、もう目の前まで迫っていた。ナユタは一瞬の判断で、いまの自分の状況を頭の中に並べる。
左手には弦の切れた弓。右手には射ることのできな矢。そして腰には刃がボロボロになったナイフ。
(まともな武器が一つもない・・・・)
余計惨めになるだけだった・・・・。
(こうなったら最後の武器を使うしかない)
ナユタの最大にして唯一の武器、それは・・・・
「逃げろ~!」
逃げ足の早さである。
役に立たなくなった弓矢を投げ捨て、まるで砲台から打ち出されたかのように、回れ右をしたナユタはものすごいスピードで逃げ出した。勢い余ってずり落ちた羽根つき帽子が、ポトリと地面に落ちる。
「待ちやがれ~!」
ワーウルフも足の速さには自信があった。自らのプライドと、そして明日への命を懸けて、ワーウルフはナユタを追いかけたのである。
ナユタは半泣きの状態で眼から涙を、ワーウルフは大きな口を開けて唾液を、それぞれ風になびく蜘蛛の糸のように流していた。
しかし、二人の距離は一向に縮まりそうになかった。空腹であるとはいえ、足の速さで有名なワーウルフに、ナユタは脚力でまったく引けを取っていないのである。そんな人類の神秘を感じさせるような檄走で、ナユタは逃げているのだ。凄いんだか情けないんだか、よく分からない。
ただ、一つだけ確かなことがある。それは、ナユタが走っているちょうどその真下に、サヤカ達の足跡があったことだ。ナユタはご丁寧にも、一つ一つその足跡を消すようなコースで走っていた・・・・。
8
さて、ワーウルフと遊んでいるナユタは放っておいて、ここでサヤカ達の様子を追いかけていこう。
草むらの陰でチラリと何かが動くのを見たエディンは、それを妖精だと思って草むらの中に入っていった。
しかし草むらの陰から現れるのは、なにも妖精や愛くるしい小動物とは限らない。滅多に姿を見せることはないが、獰猛な熊や狼が襲ってくることもあるのだ。
それでも、子供の好奇心が上まったのであろう。それに、サヤカが妖精を見るのを楽しみにしていたことに影響されたのかも知れない。エディンの頭の中には、その先に妖精がいるということしかなかった。
しかしそこに待っていたのは、大人でもすくみ上がってしまいそうな急斜面。どんなすべり台よりも急角度な斜面を、エディンは顔から滑り落ちていったのである。
エディンの上げた悲鳴は、すぐにサヤカとナユタの耳に届いた。そしてその悲鳴が消えるよりも早く、サヤカはエディンの名を叫ぶと同時に駆けだしていた。心臓がドクドクと跳ね上がり、嫌な胸騒ぎがこみ上げてくるのを感じながら。
草むらに飛び込んだサヤカの前には、待ちかまえるようにエディンの滑り落ちた急斜面が存在していた。踏みしめる地面を失ったサヤカは、草むらに飛び込んだ勢いそのままに斜面を転がり落ちるしかなかったのであった。
だが幸運だったのは、その先の藪の中でエディンとぶつかったことである。しかし二人に待っていたのは、広い藪であった・・・・。
「いった~い・・・・」
エディンとぶつかったときに肩を打ったのか、サヤカは右手で左肩を押さえている。
「エディン、大丈夫? エディンったら?」
仰向けに倒れているエディンは、苦しそうに眉間にしわを寄せながら目を閉じていた。そして赤く腫れた鼻からは、鼻血が口元の方に流れている。
サヤカはその肩は揺らすが、エディンはまったく反応を示さなかった。おそらくぶつかったショックで気を失っているのだろう。
サヤカは片目をつむって肩の痛みを堪えながら、辺りを見渡した。まわりには、まるで自分たちを囲い込む壁のように枯れた藪が迫っている。何か言いしれぬ圧迫感を感じ、サヤカは両手で自分の身体を抱きかかえた。
その時はじめて、自分の視界が少し歪んでいることにサヤカは気付いた。何でだろうとサヤカが眼鏡に手をかけた瞬間、彼女の表情がハッとなる。
サヤカはむしり取るように眼鏡を外し、目を凝らしてその眼鏡を見つめた。
「ああっ!」
パッと両目を開いたサヤカの視線が一点で止まった。右のフレーム部分が、わずかに歪んでいたのである。
「ナユタにもらった眼鏡なのに・・・・」
言葉を失ったまま、サヤカはじっと銀縁の眼鏡を見つめ続けた。歪んだフレームの部分には、目立たないように金色の文字で何かが書かれている。サヤカにとって大切な思い出が、無惨にも潰れていた。信じられないという表情を浮かべながら、眼鏡を持つ手が自然と震えてくる。
やがてその眼鏡に注がれる瞳の中に、キラキラと輝くものが浮かんできた。そして一筋の光りが、彼女の頬を伝う。
ふとその時、気を失っていたエディンが、「痛てててて」と鼻を押さえながらムクリと起き上がった。エディンの髪に絡まった枯れ草の一部が、ハラハラと落ちてゆく。
サヤカはビクリと慌てて瞳を拭うと、眼鏡をかけ直してエディンに声をかけた。
「大丈夫、エディン?」
「ううん・・・・、何とかね」
鼻血がたまっているのか、鼻をフガフガとさせながらエディンは答える。そのエディンの視線が、フレームの歪んだサヤカの眼鏡を捕らえた。
「あれ? サヤカ姉ちゃん、その眼鏡・・・・」
「あっ、ああ、何でもないの。それよりどこか怪我してない? ちょっと見せて」
サヤカはエディンの視界から逃げるように、手や足を調べ始めた。エディンはキョトンとしながらサヤカの様子を眺めていたが、サヤカの頬にかすかに残っていた滴を見た瞬間、わずかにその表情が曇る。
(サヤカ姉ちゃん・・・・)
傷を見つけるというより悲しさを紛らわそうとしているサヤカの姿に、エディンの視線と心も吸い寄せられていく。
エディンも知っていたからだ。サヤカがどれほどその眼鏡を大切にしていたのかを。
「あらっ、大変。膝を擦りむいているじゃない」
「えっ?」
サヤカの声が聞こえてきて、ふと一点に集中していた意識が途切れた。エディンは自分の膝に視線を落としす。そこには、金貨ほどの大きさのすり傷があった。
「痛ててっ!」
途端に傷口がズキズキと疼き出した。エディンは地面に尻餅をついて倒れ、もう一度恐る恐る傷口をのぞき込む。傷口には真っ赤な血がにじんでいた。
「ちょっと待っててね。いま消毒してあげるから」
サヤカは慌ててエディンの前にしゃがみ込む。そして肩から掛けていたポーチを開き、消毒薬とガーゼ、さらに包帯を取り出した。こんなものをいつも持ち歩く少女も珍しいものだが、むろん自分が使うためではない。
「沁みるわよ」
合図するように声をかけてから、傷口に消毒液を染み込ませたガーゼをあてた。たまらずエディンは悲鳴を上げ、歯を食いしばって痛みを堪える。
「もうちょっとだから、我慢してね」
まるで自分も痛そに顔をしかめながら、サヤカはガーゼを傷口に当てていく。
消毒が終わると新しいガーゼを傷口に被せ、新たにポーチの中からテープとハサミ取りだした。十分すぎるぐらいの重装備である。
サヤカはテープを二つ切り、それを十字にしてガーゼをとめた。そのまわりを包帯で巻いていく。ちゃんと膝も動かせるように、まずは膝のまわりから。そして最後に膝小僧の上を四回ほど巻いて、包帯を縛った。下手な看護婦よりよほど手際がよい。
「どう、きつくない?」
エディンは立ち上がって膝を何度か曲げてみたが、ほとんど違和感を感じることはなかった。少しもきつくないし、曲げにくいこともない。
「うん、ちっとも。それに、なんだか痛いのもどっかに飛んでいっちゃったみたいだよ。サヤカ姉ちゃんってもしかしたら魔女なのかもね」
大丈夫だよと言いたげに笑顔を見せるエディンであったが、わずかにその口元を引きつらせていた。
「魔女?」
「あっ、でも魔女ってみんなおばあさんなんだよね。この前で本で見たよ。でっかい芋虫みたいな鼻をしててさ、オバケみたいにギロギロした眼をしてるんだ。気持ち悪ぅ~って感じなんだよね」
絵本の中の黒いボロボロのローブを身にまとった魔女を思いだして、エディンは露骨に嫌そうな顔をした。大きな瓶で緑色をした液体を煮立てながら、薄笑いを浮かべてこちらを振り向く魔女の姿を、いまだに忘れることができない。
「ゴメン、ゴメン。ははははっ」
「まぁ、ヒドイわね」
エディンの笑い声につられるように、サヤカも乾いた笑みを浮かべた。しかしまだ、どことなく寂しげな笑顔である。
「さっ、そろそろ行こうよ。いつまでもこんな所にいてもしょうがないし」
「でも、どっちに行ったらいいのかしら・・・・」
まわりに見えるのは藪だけ。まるで藪の檻に入れられたようで、自分たちがどこから転がってきたのかも分からない。
「悩んでたってしょうがないよ。それに早く帰らないと、ナユタ兄ちゃんが心配して探しに来るかもしれないし」
エディンの最後の一言に、サヤカは「あっ!」と声を上げて立ち上がった。
「ナユタ兄ちゃんって、そういうところがあるからね」
「あり得るわね。でもナユタのことだわ、きっと森で迷うに違いない。いえ、迷うだけならまだ良いわ。もし狼なんかに追いかけられて、そして・・・・」
自分のことはそっちのけでナユタのことを心配するサヤカ。彼女はまだ知らないが、このあと本当にナユタは狼(正確にはワーウルフ)に追いかけられることになる。
「行きましょう、エディン。なんだか悪い予感がするの」
「オッケイ。狼なんかが出てきても僕がサヤカ姉ちゃんを守ってあげるよ」
エディンは得意げな表情をすると、リュックサックに留めていたパチンコを手にした。そしてポケットの中から鉛の球を取り出し、ゴムの部分にセットして球を飛ばした。鉛は勢いよく飛び出し、藪をバシバシと弾いて消えていく。
「ありがとう、エディン。本当に・・・・」
サヤカに少し元気が戻ってきたことに、エディンも「へへへっ」と照れ笑いを浮かべていた。そんな二人には聞こえなかったであろう。藪の向こうから、「ぎゃん!」という狼にも似た悲鳴が聞こえてきたことに。
こうして、サヤカとエディンは一寸先も分からぬまま藪の中を進んでいくことになった。そのサヤカ達の残した跡を、鉛玉を食らった空腹のワーウルフと狩人に変身したナユタが追いかけていくのは、それからほんの少し後のことである。
9
地平線の彼方へと消えようとしてる夕日に焼かれた木々が、長い影法師を地面に描いていた。その中の一つが、時の経過と共に一人の少年の身体にスルスルと延びていく。
「サヤカ姉ちゃ~ん、もう疲れたよぉ~」
地面に腰を下ろして後ろ手に身体を支えるエディンが、眉毛をハの字にしながら呟いた。
「疲れた疲れた疲れた疲れた~、もうっ!」
エディンはだだっ子のように両手を振り回し、地面から雑草を引き抜いては真上に投げ飛ばしていった。すぐにその草は、エディンの頭の上にパラパラを落ちてくる。
「私だって疲れているのよ。がまんしなさい」
元気なく答えるサヤカも腰を下ろし、木の幹に寄りかかっていた。サヤカの答えを聞いたエディンは、「ちぇ~」と言って拗ねたように口を尖らせる。
疲労のためか、サヤカの透き通った白い顔はやや赤みがかり、額には玉のような汗が浮かんでいた。汗を拭くのも忘れ、おでこには前髪が張り付いている。そしてむくんだ足をほぐすように、両足を軽くもんだり叩いたりしていた。
(あ~あ、せっかくのお洋服が台無し・・・・)
お気に入りのブルーのワンピースを眺めながら、サヤカは心の中で深いため息をついた。所々に細かい切れ目が走り、その下から彼女の白い肌が覗いている。上手に裁縫すれば目立たなくすることもできそうだが、あいにくと裁縫の方は料理ほどの腕前を持っていなかった。
それもこれも、あの藪のせいだった。
藪をかき分けながら進む作業は、少女のサヤカにとっては重労働であった。それに自分だけならまだしも、後ろには小さいエディンもいる。弟の背丈も考え、彼女は低い部分の藪もかき分けなくてはならなかった。
中には先の尖った藪があり、それが服にひっかかるのである。気にしていると余計疲れるし時間もかかるので、途中からはとにかく進むことに集中した。その結果が、今の有様である。ナユタの服がほとんど無事だったのも、最初に彼女がかき分けていたからだ。
ようやく藪を抜けた頃には、だいぶ疲れ切っていた。それからはほとんど足の赴くままに森の中を彷徨っていたが、それも限界に来ていた。
疲れ切った二人の間には、しばらくの間沈黙が訪れる。やがて思い出したように、サヤカが口を開いた。
「ナユタ、今頃どうしてるんだろう?」
「さあねぇ・・・・」
エディンは草の上に大の字になって、素っ気ない返事を返す。もはやエディンの方は、ナユタを気にするどころではないのだろう。
「助けを呼びに行っているのかなぁ・・・・」
ふと空を見上げると、紅に染まっていた空はいくぶん蒼さが増していた。もうしばらくすれば、白銀の月が姿を見せるかも知れない。街道沿いならまだしも、こんな森の奥を夜に捜索してもらえるかどうかは疑問だった。
「はぁ・・・・」
深いため息と共にサヤカは視線を下ろした刹那・・・・
うわあああああ~!
彼女の前を、黒い影が二つ横切った。それこそ、つむじ風が通り抜けるような早さである。叫び声の余韻を残しながら、何事もなかったかのように二つの影は彼方へと消えていった。
パッと見ただけでよく分からなかったが、叫び声を上げながら前を走っていたのは確かに人間のようだった。そして後ろを走っていた、というより、前の人間を追いかけていたのは、たしかワーウルフである。サヤカは昔学校の教科書で見たワーウルフと、たったいま見た直立の狼とを重ね合わせる。
「サヤカ姉ちゃん、いまのなんだろう?」
エディンも見ていたのであろう。突然の出来事にポカンとした表情でサヤカに訊ねた。
「う~ん、前を走っていた人は狩人さんのようにも見えたけど・・・・」
眉と眉の間にしわを作って、サヤカはわずかの間見えた人間の姿を思い出した。
着ていた服は、いかにも狩人が着そうな身軽なものであった。問題はその色である。茶色に黄色を混ぜたようなあの何とも言えない色の服を着た人間が、はたして狩人なのか。おまけに狩人の象徴とも言える弓矢を持っていなかった。サヤカの頭の中にある狩人の姿とは、あまりにもかけ離れていたのである。
サヤカが気付くわけもないだろう。あの服の色はとある妖怪の趣味であり、弓矢は自らのドジのせいで使い物にならなくなってしまったことを。
「もしかして、ナユタ兄ちゃんが助けを呼んでくれたのかなぁ!」
先程までの疲れを吹き飛ばし、エディンはサヤカに声をかけた。ランランと輝くその瞳は、「絶対そうだよね」と訴えかけているようである。
「そうかもしれないわね・・・・」
エディンの勢いに押され、サヤカもそんな風に答えてしまった。まるで確証はなかったのであるが。
「でもドジな狩人さんだよね。ぼくたちを捜しに来てくれたのに、自分が幻獣に追いかけられるなんて」
「はははっ」と笑い声を上げるエディンは、最後に「ナユタ兄ちゃんみたいだね」と付け加えた。
サヤカも「そうね」と微笑みながら、なんとなしに向こう側にある一本の木の方を見やる。幹の所に動物の巣らしき穴が開いており、青々とした葉に枝が覆われている以外は何の変哲もない木だ。幹の太さだって、サヤカの肩幅とそれほど変わりそうにない。
しかし、不思議とサヤカにはその木に引き寄せられるものを感じた。瞬きも忘れたまま、サヤカは魅入られたようにぼんやりとその木を眺める。やがて、まるで微睡みの中のような視界の中で、何かが生い茂る葉の中から降りてきた。背中の透明な羽根をパタパタとはためかせ、ふわりと地面に降り立つ。
「あっ・・・・」
サヤカがわずかに腰を浮かせた時、背中に羽根を持つ少女はニッコリと彼女の方に微笑みかけた。
「サヤカ姉ちゃん、あっ、あれ・・・・」
それから後は言葉が出てこないのか、エディンは口をパクパクさせてその少女を指さした。
「本当に見られたんだ。妖精を・・・・」
サヤカも驚きのあまり、声を震わせている。
サヤカ達の前に現れた妖精は、姿こそ人間にしてみれば10歳ほどの少女であったが、背は30センチほどしかなかった。クルリとした瞳は、クルミのように丸い。緑色の服を身にまとい、背中からは透明な羽根が生えている。まるで人形のようであったが、スラリと伸びる手足はふっくらとした張りを感じさせた。
愛らしい微笑みを浮かべたまま、妖精はサヤカ達の方に飛んでくる。妖精が羽根をはためかせるたびに、まるで星屑のような光りがキラキラとこぼれた。
妖精はちょうど腰を下ろしたサヤカの頭の高さで止まると、鈴の音のような声で訊ねてくる。
「どうしたの? 道に迷っちゃったの? こんな森の奥まで人間が入ってくるなんて」
「え、ええ、そうよ。崖から落ちて、道に迷ったの。どうやって帰ったらいいのか分からなくて・・・・」
「ふぅ~ん、そうなんだ?」
妖精は下唇に指を当て、物珍しそうにサヤカを見つめる。その仕草は、初めて両親以外の人と接する赤子に似ていた。
「お願い、妖精は願いを叶えてくれると聞いたことがあるわ。早くナユタに会いたいの」
女神にすがりつくように、サヤカは懇願した。妖精は黙ったまま、サヤカの心をのぞき込むように透き通った眼をじっと向けている。サヤカは胸の前で小さく手を組んだまま、妖精の答えを待った。
「・・・・・・。良いわ、あなたの願いを叶えてあげる」
「本当に!?」
疲れ切ったサヤカの瞳が、一気に輝きを増す。
「うん。だからちょっと目を閉じてて。その間に私がおまじないをかけて上げるから。そして目を開けたら、あなたの願いは叶えられているはずよ」
「分かったわ」
サヤカは胸を弾ませながらキュッとまぶたを閉じた。エディンも慌てながら一応まぶたを閉じておく。二人が目を閉じたのを見た妖精は、ポケットから金色の粉を取りだし、おまじないを唱えながら二人に粉をかけていった。
「人の願いは心の光り。夢と希望は、幸福へと導かん・・・・」
妖精の声を遙か彼方のように聞きながら、サヤカは何か頭の中をかき混ぜられるような感覚を覚えた。そして、ナユタに会いたいという気持ちと、もう一つ別の気持ちが心の中で膨らんでいく。
「もういいわよ」
妖精の声が聞こえてきた。サヤカはゆっくりとまぶたを開ける。そこにナユタの笑顔があると信じながら。
「ナユタ?」
しかし、そこは先程までの森の中だった。あたりを見渡すが、ナユタの姿も見えない。目を閉じる前の風景と何一つ変わることなく、妖精が微笑みを浮かべながら目の前を飛んでいるだけだった。
「私の願いを叶えてくれたんじゃなかったの?」
唖然としたままサヤカは訊ねた。
「人間は、私たち妖精は願いを叶える力を持っていると信じている。でも、それは違うの」
「えっ・・・・?」
「願いは、それを叶えようとすることに価値があるもの。私たちはそのために手助けをするだけ。本当に願いを叶えたいという強い心があれば、その願いはきっと叶えられるはずよ。見てごらん、あなたの壊れた眼鏡」
「眼鏡?」
妖精に言われ、サヤカは眼鏡を外してみた。壊れてしまった眼鏡を、本当はあまり見たくなかったのであるが。
「あれ?」
サヤカは我が目を疑った。壊れてしまったはずの眼鏡は、新品のようにきれいに直っていたのである。歪んでいたフレームの部分には、”Happy Birthday”という文字がしっかりと刻まれている。
さらに所々切れ目の入っていたワンピースも、元に戻っていた。
「どうして・・・・?」
「あなたの願いが叶えられた証拠よ。あなたに強い思いがあったから、その眼鏡と服は元に戻ったの。もしあなたの心の中にもっと強い願いがあれば、それもきっと叶うはず」
「ナユタに会えるのね!」
はしゃいで喜ぶサヤカに、妖精はだまって微笑みを返すだけだった。妖精という名に相応しい、心を癒すような笑顔である。
「よかったね、サヤカ姉ちゃん。眼鏡が直って」
「うん」
エディンの言葉にサヤカは大きく頷く。
「だから言っただろ、ナユタ兄ちゃんもやるときはやるって。ちょっと見掛けは頼りないけどね。はははっ」
「そうね。ふふふっ」
エディンの言葉に、サヤカはいつもの屈託のない笑みをこぼす。藪に落ちてからというもの沈みがちだったサヤカの表情に、夕日に負けないぐらいの輝きが戻ってきた。
「ありがとう、妖精さん」
「あなた達の願い、きっと叶うと思うわ。強い心がある限り、私たちはいつでもあなた達の側にいる・・・・」
そう言い残して、笑顔を浮かべた妖精は陽炎のようにフウッと消えてしまった。
「あれっ、消えちゃったよ?」
狸に化かされたような顔で、エディンは虚空を見つめる。一瞬前までそこに妖精がいたとは思えないほど、そこには何もなかった。
「願いを叶えてくれた私たちには、もう見えないのよ」
「ええっ、どうして?」
「そういう存在なのよ、夢を叶える妖精さんは」
「・・・・??」
「エディンはまだ分からないか・・・・」
曖昧な答えに困惑しているエディンの頭を、サヤカは優しく撫でる。
「あのお月様にもお願いしておきましょうか。ナユタのところに戻れますようにって」
サヤカはおぼろげに顔を出した月を指さし、祈りをささげるように跪いて手を合わせる。まるで神殿のレリーフに描かれた聖女のような彼女の遙か上空を、流星が一つ煌めいた。
10
ここで場面は、再びナユタへと戻っていく。
「はぁ、はぁ、はぁ・・・・」
ナユタはまだ命を懸けた檄走を続けていた。後ろからは、血に飢えたワーウルフが牙をむいて追いかけてきている。そんな恐怖を背中にひしひしと感じ、もはや無意識的に足を前に送っていた。
しかし、いかに驚異的な脚力を持つナユタといえども、所詮は人間である。いつかは疲れる。汗が目に入り、足は鉛のように重く、心臓は警笛をならすかのようにバクバクと激しく鼓動していた。
(ワーウルフなんかに食べられてたまるか。サヤカを探すんだ)
奥歯を噛みしめながら走るナユタは、最後に残った力を振り絞るように目を閉じた。目尻と眉間には、いくつものシワができる。
確かに疲労も限界に近づき始めていた。疲労メーターは、”MAX”の一歩手前で揺れている。しかし同時に、ワーウフルも疲れているはずである。例え幻獣であろうと、空腹ならば長時間走り続けることはできないはずだ。
(ワーウルフはどうなっているんだろう?)
いままでそんなことを考える余裕すらなかったが、ふと疑問がわき上がってきた。いまはそれどころではないと心の底に押し込めそうとするが、意識すればするほど、一度生まれた疑問は広がっていく。
そういえば、さっきまで「待ちやがれ」だの「食い殺してやる」だの騒いでいたワーウルフの声が、いつの間にか聞こえなくなっていた。
(もしかして振り切ったのか?)
それで緊張の糸が途切れてしまったのか、ナユタは人形のようにガクガクと雑草の生い茂る地面に倒れ込んだ。途端に疲労が全身に広がっていき、もはや立ち上がる気力は湧いてこない。
「あ゛あ゛~疲れた。死ぬかと思った・・・・」
目を閉じたまま、ナユタは頭の中に浮かんだ言葉をそのまま吐き出した。頭がガンガンし、喉の奥が火傷したようにヒリヒリする。冷たい水をたらふく飲みたい気持ちだった。顔を洗ったらさぞ気持ちいいだろう。
頭の中に、モヤモヤと小川の風景が浮かんでくる。その川は、底まで見えそうなほど澄んだ水と共に涼しげな音を運んでいた。まるですぐ側にあるように、はっきりと耳に聞こえてくる。
「そんな都合よく・・・・あった!」
ヘロヘロな顔を上げた先には、本当に小川があった。しかも少し動けば届きそうなほどの距離でサラサラと流れている。夢か幻でも見たようなナユタの表情は、まさに砂漠でオアシスをみつけた旅人に近かった。
ひんやりと冷たそうな水に突き動かされ、ナユタは疲れているのも忘れて地面をがむしゃらに這っていった。その眼には、完全に流れる水しか映っていない。
「み、水ぅ~!」
最後は川縁までバッタのように勢いよく跳ねる。だが、完全に思考回路は真っ白になっていたのだろう。あまりにも勢いよく飛んだもんだから・・・・
ばしゃ~ん!
となるのがいつものナユタだが、今回は違った。驚異的な瞬発力と腕力(あくまでも狩人に変身して得たものだが)で、エビ反りのような格好をしながらギリギリ踏みとどまったのである。どれだけギリギリだったかというと、鼻の頭が水面に触れるか触れないかというほどだ。
「ふぅ~、よかった・・・・」
ホッと一安心するナユタの前に、川の中から一匹のカエルが顔を出した。カエルもまさか、そこに人間がいようとは思ってもいない。その結果・・・・
チュッ(はあと)
「・・・・・・」
「・・・・・・」
・・・・・・。
「おえぇぇぇぇぇぇぇ」
カエルと熱い抱擁を交わしたナユタは、舌を出してうめいた。しかし、気を抜いたのが命取りである。
ばしゃ~ん!
今度こそ本当にナユタは水しぶき上げて落ちた。不運な男だ。最初から潔く水に落ちていれば、カエルと口づけを交わすなどという苦い経験をしないで済んだであろうに。
「げほっ、げほっ・・・・。いててて」
水の中から顔を出したナユタは、赤く腫れた鼻の頭を押さえていた。底まで見える澄んだ水を思われたのは、ただ底が浅かっただけなのだ。どこまでも不運な男である。
ナユタは川から上がると喉の渇きを思いだし、あらためて川の水をすくった。喉越しのよい森の水を、喉を鳴らせて一気に飲み干していく。その度に、冷たい水が体の中を下っていくのが感じられた。ようやくナユタにも至福の時が訪れたようである。
「ナインテール、もうワーウルフは追ってこないかい?」
さわやかな笑顔を見せながら、息を吹き返したナユタは側にいるはずのナインテールに声をかけた。
「って、おい・・・・」
そのナユタの視線の先では、一羽の鷲が野イチゴを美味しそうについばんでいたのだった・・・・。ナユタの最高の笑顔は、見る見るうちに干し柿のようにシワシワになっていく。
「おう、ナユタ。お前も食わないか? 鳥に変身してお前達を追いかけている途中で見つけたんだ。なかなかイケてるぞ」
「そんな暇があったら僕を助けてくれよ・・・・」
「助けるも何も、ワーウルフはとうの昔にぶっ倒れたぞ」
「へっ?」
丸まったダンゴムシのような眼をしてアホ面を下げるナユタの頭の上に、”?”マークが3つ浮かぶ。
「今頃その辺でくたばってるんじゃないのか。で、やれやれと一安心しているところに、このイチゴを見つけたわけさ。一つ食ってみると、これが旨いのなんのって。激しい稽古をした後で、幼なじみの女の子が「お疲れさま」ってタオルをくれたときの甘酸っぱさって言うかなぁ・・・・。心が満たされていくのを感じたよ」
「そんな青春に浸っている暇があったら教えてくれよ・・・・」
せっかく回復しかけた疲労メーターはあっさり振り切れ、ナユタは塩をかけられたナメクジのようにドロドロと溶けていく。
「そういやぁ、さっき気になることがあったんだが・・・・」
そんなナユタを無視するように、九尾の姿に戻ったナインテールは前足に残ったイチゴの汁を舐めながら呟いた。だが元に戻ったナインテールの顔を見たナユタは、思わずひょっとこのような顔をして吹き出すのを押さえる。
「ぷぷっ、何だよその顔?」
「あん? オレ様の顔になんかついてんのか?」
「ぶふっ、ぷぷぷぷぷ・・・・」
ナユタは目に涙をためて笑いを堪えるのが精一杯だった。ナインテールの顔をチラリと見ては、顔を真っ赤にして口を押さえる。
「な、何なんだ・・・・?」
訝しげに思ったナインテールは、ナユタに奇異の眼を向けつつ小川で自分の顔を覗いてみた。いつもと変わらない、カッコイイ自分の顔がそこにはあるはずだった。が・・・・
「うげっ!」
ナインテールの口のまわりは、赤紫色をしたのである。もちろんそれは野イチゴの汁がついたからなのだが、見ようによっては口紅を引いたように見えなくもない。
「何かの間違いだろ?」
水面に映る口紅を引いた狐を否定しようと、ナインテールはゴシゴシと目を擦る。目を開けたときには、今度こそいつものカッコイイ自分が映っているはずだった。しかし・・・・
「な、なんじゃこりゃ~!」
今度はまぶたまで赤紫に染まっていた。説明するまでもないが、野イチゴの汁がついた前足でまぶたを擦ったからだ。
さて想像してみよう。みかけは九尾の狐。しかし唇とまぶたは、化粧でもしたように赤紫をしている。唇には口紅を引き、まぶたにはアイシャドウを塗ったかのごとくにだ。
こんなケバくて色気を誘う化粧をする男(オス?)は、ニューハーフぐらいなものである。妖怪のニューハーフなど前代未聞、古今東西見たことも聞いたこともない。
その顔をナユタが横からのぞき込む。途端にナユタはナインテールを指さしながら、切ったスイカのような口をして笑い転げた。
「はっはっはっ! サイコ~だよ、ナインテール。まさかそんな趣味があったとはねぇ」
「あるかっ、ヘボナスが!」
ナインテールは大慌てで川の水で顔を洗った。屈辱的な化粧と共に、悪夢も洗い流すかのように。
しばらくして赤紫の汁も流れ落ち、ナインテールはブルブルと頭を振るわせて身体についた水を飛ばした。それでも湿り気の残ったナインテールの顔は、ぬいぐるみのように毛皮が膨らんでいる。
「ふぅ、とんだ災難だったな・・・・。ところで脱線していた話を元に戻すが、さっき人影みたいなものを見なかったか?」
「ああ、僕も見たような気がするよ。ワーウルフに追いかけられてた時だから、チラッとしか見えなかったけどね」
「もしかして、あれがサヤカ達だったんじゃないのか?」
「まっさかぁ」
雪女が夏のビーチで日焼けをしていたと聞いた時のような勢いで、ナユタはあからさまに否定する。
「いっつもドジやってる僕だよ。逃げた先にサヤカ達がいるなんて幸運なこと、あるわけないじゃないか。いくら僕だって、自分の身の程を知らないドジじゃないよ」
確かに身の程を知ることは大切だが、自分の見た人影がサヤカではないと考えることこそドジなことに、自称ドジではないドジ男は気付いていない。
「狩人になった僕の脳ミソは、もうあの影の正体をはじき出しているよ。ズバリ、あの影はサルさ」
「ほぉ~」
愚かなナユタは、一人で勝ち誇ったように納得してしまった。威勢だけは立派だが何の根拠もないナユタの推測に、ナインテールは適当に答えておく。
確かに、ヒトとサルは種族としてかなり近いし、人間なんているはずもない森の奥では、さすがは狩人だと拍手を送りたいほどである。が、あれだけナユタのことを心配し、そして信じていたサヤカ達のことを、サルと間違えるのはヒドイ話だ。いまさら指摘するまでもないが、間抜けである。
「ところで、これからどうするんだ?」
「う~ん、いろいろと問題があるんだよね」
ナユタは後頭部をポリポリと掻いてから、その問題とやらを指折り挙げていく。
「一つは、せっかく見つけたサヤカ達の足跡を完全に見失ってしまったこと。あの場所に帰ろうにも、どこをどう走ってきたのはもう分からない。二つめは、ここが妖精の森であること。妖精の森の中には、一度入ったら二度と出てこれない不思議な空間があったり、動物を襲う植物が生息していたるするんだ。それから三つ目は、夜が近づいていること。ワーウルフよりももっと凶暴な獣が現れるかも知れないから、サヤカ達だけではなく僕たちも危ない。」
「それから一番の問題は、探すのがお前だということもあるな」
「そうそう、それを忘れてた・・・・って、あのねぇ~」
何のためらいもなく下ろしてしまった四つ目の指を、ナユタは慌てて上に上げる。いつもからかわれてある意味不運なナユタだが、からかわれる方もからかわれる方である。
「とりあえずサヤカ達を早く探さないといけないけど、僕たちにだって危険はあるわけなんだ。そこでだ、こうなったら最後の手段だよ」
「最後の手段?」
「うん。妖精の力を借りるのさ」
一つ頷き、ナユタはまじめな顔をして続ける。
「妖精は夢や希望を叶えるというけれど、それは噂や伝説ではないんだ。そしてその妖精は本来一人一人の心の中に住んでいて、願いを叶える手助けをしているものなんだよ。ナインテールのような妖怪と同じように、目には見えないけどね。この森は、そんな心の中にいる妖精の力を高めてくれる不思議な森なんだ。だからその姿を見ることができるし、本当に叶えたいという強い願いがあれば、それを叶えてくれる。もちろんそう簡単に会えるわけでもないけどね」
森と共に暮らす狩人達は、そのことを知っていた。この森は強い願いがあれば妖精と出会えるが、逆に悪い心を持っていると、不思議な空間に引きずり込んだり凶暴な植物を現実化させる。人の心を映し出す鏡のような森とも言えるだろう。
「つまり、妖精を探してサヤカ達を見つけたいという願いを叶えてもらうわけか?」
「いや、そうじゃないんだ。言っただろ、例え願いがあったとしても、妖精に出会えるのは難しいって」
ナインテールの言葉を、ナユタは首を振って否定する。
「そこでナインテール、一生のお願いなんだ・・・・」
ナユタはシリアスな顔のまま、ナインテールの前足を握った。ナユタの突然の奇行に、ナインテールは困惑した表情をしたまま「何だ?」と訊ねる。
「妖精に変身してくれないか?
「・・・・・・」
ナユタの言葉をよく飲み込めなかったナインテールは、たっぷり10秒は沈黙した後にこう叫んだ。
「なんじゃそりゃ~!」