丂偁側偨偼偛懚偠偩傠偆偐丄乭僄儖僪儔儞乭偲偄偆搰傪丅
丂墦偄奀偺辍偐斵曽偵丄偦偺搰偼偁傞偲偄偆乧乧丅
丂怷偱偼偖傟偨僒儎僇払傪扵偡偨傔丄晛抜偺棅傝側偄巔偲偼帡偰傕帡偮偐側偄傎偳檢乆偟偄庪恖偵曄恎偟偨僫儐僞丅偦偺僫儐僞偼丄恄柇側柺傕偪偱峫偊崬傫偩偁偲丄偙偆尵偭偨丅
乽僫僀儞僥乕儖丄偲偭偰傕尵偄擄偄偙偲側傫偩偗偳丄堦惗偺偍婅偄側傫偩乧乧乿
丂怷偺拞偱嬻暊偺儚乕僂儖僼偵捛偄偐偗傜傟丄棧傟偽側傟偵側偭偰偟傑偭偨僒儎僇偲僄僨傿儞傪扵偡庤偑偐傝傪姰慡偵幐偭偰偟傑偭偨僫儐僞丅巆偝傟偨婓朷偼堦偮偟偐側偄偲偽偐傝偵丄惞曣憸偵偡偑傝偮偔傛偆側惃偄偱僫僀儞僥乕儖偺慜懌傪埇偭偨丅
丂帨斶傪岊偆傛偆側偦偺摰偼丄椞庡偺埑惂偵嬯偟傔傜傟傞擾柉偵傕晧偗偢楎傜偢偱偁傞丅偩偑僫僀儞僥乕儖偵偲偭偰傒傟偽丄抝偵乽尵偄偵偔偄偙偲乿偲尵傢傟傞偺偼丄偁傞堄枴暋嶨偩偭偨丅
乽側丄壗偩傛乧乧乿
丂僫儐僞偺撍慠偺婏峴偵僑僋儕偲懥傪堸傒崬傒丄僫僀儞僥乕儖偼崲榝偵枮偪偨昞忣傪僫儐僞偵岦偗偰恥偹偨丅
乽壜垽偄梔惛偵曄恎偟偰偔傟側偄偐丠乿
乽乧乧乧乿
丂壜垽偄梔惛偵曄恎偟偰偳偆偟傠偲尵偆偺偐丅僫儐僞偺尵梩傪傛偔堸傒崬傔側偐偭偨乮偲尵偆傛傝怺偔峫偊偨偔側偐偭偨乯僫僀儞僥乕儖偺摢偺拞傪丄乫栂憐乫偲偄偆柤偺朶憱攏幵偑嬱偗弰傞丅峫偊傟偽峫偊傞傎偳丄僀働僫僀曽岦偵朶憱攏幵偼撍偒恑傫偱偄偭偨丅
丂偙偺暔岅偼僀儎乣儞側曽柺偺榖偟偱偼側偄偺偱丄僫僀儞僥乕儖偼僽儖僽儖偲婄傪寖偟偔嵍塃偵怳傞偲丄
乽側傫偩偦傝傖乣両丂傾儂偐両丂偙偺僿儃僫僗両丂儃働両丂僗僇両丂曋強拵両丂僈儔僈儔僿價偺僈儔偲僗乕僾両乿
丂偲堦婥偵傑偔偟棫偰傞丅
乽乧乧慜夞偺儔僗僩偱偦偙傑偱尵偭偰偐丠乿
丂僫儐僞偼寉偔偨傔懅傪偮偄偰偐傜丄乽偮傑傝偩偹偉乣乿偲恖嵎偟巜傪棫偰偰尵梩傪懕偗偨丅
乽僫僀儞僥乕儖偵梔惛偵側偭偰傕傜偆偺偼丄杔偺婅偄傪姁偊偰梸偟偄偐傜側傫偩丅杔偺婅偄偼丄傕偪傠傫僒儎僇払傪尒偮偗傞偙偲偝丅偦傟傪梔惛偵側偭偨僫僀儞僥乕儖偵姁偊偰梸偟偄傫偩傛乿
乽傆乣傫丅偱丄壗偱偦傟偑堦惗偺婅偄側傫偩傛丠乿
丂僫僀儞僥乕儖偼偡傑偟偨婄偱丄僫儐僞偺尵梩偵偼傎偲傫偳姶怱側偝偘偵敀偄旹傪偄偠偔傞丅
乽偄傗丄偩偐傜乧乧丅慺捈偵梔惛偵偼側偭偰偔傟側偄偩傠偆偲巚偭偰乧乧乿
乽摉偭偨傝慜偩乣両丂壌偵塇偺惗偊偨彈偺巕偵側偭偰乽僉儍僺僢侓乿偭偰偟傠偲偱傕尵偆偺偐両丂壗傪岲偒偙偺傫偱梔惛側傫偐偵曄恎偟側偄偲偄偗側偄傫偩両乿
丂偨偪傑偪僫僀儞僥乕儖偼丄偙傔偐傒偺曈傝偵惵嬝傪棫偰偰寖搟偡傞丅惃偄偁傑偭偰旹傪堷偒敳偄偰偟傑偭偰偄傞偑丄摢偵寣偑忋偭偨杮恖偼婥晅偄偰偄側偄丅
乽暿偵乽僉儍僺侓乿偭偲偟傠偲傑偱偼尵偭偰側偄傛乧乧丅偄偄偐偄丄僫僀儞僥乕儖偑杔偺婅偄傪姁偊偰偔傟偨傜丄偦偙偵懸偭偰偄傞偺偼側傫偩偲巚偆丠丂偦傟偙偦姶摦偺懳柺偲僴僢僺乕僄儞僪偠傖側偄偐丅僫僀儞僥乕儖偼偦偺慺惏傜偟偄僄儞僨傿儞僌偺墘弌偑偱偒傞傫偩傛丅僇僢僐僀僀偲巚傢側偄偐丠乿
乽傆傫偭丄偍偩偰傝傖撠偼偍傠偐徾偩偭偰栘偵搊傞偐傕抦傟側偄偑側丄僆儗條偼偦傟傎偳扨弮偱偼側偄偧丅偳偆偣偄偮傕傒偨偄偵僆儗條傪忔偣傛偆偭偰嵃抇偩傠丠丂偳偆峫偊偨偭偰丄堦斣僆僀僔僀偺偼偍慜偠傖側偄偐乿
乽偆偆偭乿
丂僫僀儞僥乕儖偺塻偄巜揈偵丄僫儐僞偼旣栄偺抂傪僺僋儕偲摦偐偣偰尵梩傪媗傑傜偣偨丅
乽偦丄偦傟偼堘偆傛丅傛偔峫偊偰偛棗丅屆崱搶惣丄恖婥偑弌傞偺偼壗傕庡栶傗僸儘僀儞偩偗偠傖側偄丅姶摦偺柤僔乕儞傪堿偱墘弌偟偨丄僋乕儖側擇枃栚偺偩偭偰恖婥偑弌傞傫偩傛丅偩偭偰偦偆偩傠丠丂寛偟偰帺暘偺庤暱傪昞偵弌偝偢丄堿偱擇恖傪廽暉偡傞丅傑偝偵乭悎乭偠傖側偄偐丅偦偆偄偆巔偙偦丄杮摉偺奿岲椙偝偲偼巚傢側偄偐偄丠乿
乽僋乕儖側擇枃栚乧乧丄恖婥偑弌傞乧乧丄悎乧乧丄奿岲椙偝乧乧乿
丂丂僫儐僞偺尵梩偼丄僫僀儞僥乕儖偺怱傪寖偟偔梙偝傇偭偨丅僫儐僞偼偙偙偱堦婥偵忯傒偐偗傞丅
乽偦偆偝丄僫僀儞僥乕儖偼僋乕儖側擇枃栚偩丅恖婥NO丏侾娫堘偄側偟両乿
乽傆偼偼偼偼乣丄僆儗條偲偟偨偙偲偑丄壗偱偦傫側偙偲偵婥偑晅偐側偐偭偨傫偩両丂僆儗條偙偦僋乕儖側擇枃栚偩両丂恖婥NO丏侾偩両丂傛乣偟丄梔惛偵曄恎偟偰偍慜偺婅偄傪姁偊偰傗傞偧乿
丂壥偰偟側偔扨弮側僫僀儞僥乕儖偼丄柍堄枴偵椉栚傪儊儔儊儔偲擱傗偟偰曄恎傪巒傔偨丅堦弖僫僀儞僥乕儖偺恎懱偑敀偄墝偵曪傑傟丄偦偺拞偐傜堦恖偺梔惛偑巔傪尰偡丅
丂恎挿俁侽僙儞僠傎偳偺彮彈偺攚拞偵偼丄僩儞儃偺傛偆側摟柧偺塇崻偑晅偄偰偄傞丅垽偔傞偟偄旝徫傒傪晜偐傋偰旘傇偦偺巔偼丄傑偝偵梔惛偲屇傇偵憡墳偟偐偭偨丅
丂偑丄恎偵晅偗偰偄傞暈偼椺偺彫敒怓傪偝傜偵墿怓偵嬤偯偗偨傛偆側怓偩偭偨丅僫僀儞僥乕儖濰偔乭僫僀儞僥乕儖丒僽儔僂儞乭偲偄偆傜偟偄偑丄棳峴傞婥攝偼僟僯偺梒拵傎偳傕柍偄丅
乽偝偁峴偔偧丅乧乧偠傖側偄丄峴偔傢傛侓乿
丂偁傟傎偳寵偑偭偰偄偨僫僀儞僥乕儖偩偭偨偑丄偡偭偐傝偦偺婥偵側偭偰偄傞丅
乽偆偘偭丄婥帩偪埆偅乧乧乿
丂偨傑傜偢僫儐僞偼丄椻傗娋傪偐偒側偑傜僽儖僢偲恎傪恔傢偣偨丅奜尒偼壜垽傜偟偄梔惛側偺偩偑丄拞恎偑僫僀儞僥乕儖偩偲巚偆偲丄崱偺尵梩偼攚拞偵僑僉僽儕偑憱傝夞傞傛偆側姶妎偩偭偨丅
乽偝偁丄栚傪暵偠偰丅帺暘偑姁偊偨偄偲巚偆婅偄傪嫮偔怱偵巚偄昤偔偺傛乿
乮壗偲偐側傜側偄偺偐丄偦偺岥挷丅嫮偔怱偵巚偊偭偰曽偑柍棟偩傛乧乧乯
丂偦偆怱偺拞偱欔偒側偑傜傕丄僫儐僞偼栚傪暵偠偨丅偦偟偰丄僒儎僇偵夛偄偨偄偲偄偆婅偄傪嫮偔怱偺拞偱巚偆丅
丂梔惛偲側偭偨僫僀儞僥乕儖偼丄崢偐傜壓偘偰偄偨妚戃偐傜岝傝婸偔暡傪僫儐僞偵怳傝偐偗側偑傜丄庺暥傪彞偊巒傔偨丅
乽恖偺婅偄偼怱偺岝傝乧乧乿
丂庺暥偵屇墳偡傞傛偆偵丄僫儐僞偺怳傝偐偐傞暡偼偝傜偵婸偒傪憹偟偰偄偭偨丅偦偺岝宨偼丄墿嬥偵婸偔愥傪梺傃偰偄傞偐偺傛偆偱偁傞丅
乽僫儐僞偺柌偲婓朷偼丄寢嬊晄岾傊偲摫偐傟傞乧乧乿
乽偍偭丄偍偄僫僀儞僥乕儖両丂側傫偩偦傟両乿
乽傆傆偭丄寉偄僕儑乕僋偩傢傛丅師偼偪傖傫偲傗傞偐傜乿
乽傕偺偡偛偄晄媑側僕儑乕僋偩傛乿
丂溼慠偲偟側偑傜丄僫儐僞偼傕偆堦搙婅偄傪巚偄昤偒巒傔偨丅
乽柌偲婓朷偼丄岾暉傊偲摫偐傫乧乧乿
丂庺暥偑廔傢傞偺偲摨帪偵丄僫儐僞偺恎懱偑寖偟偄岝傝傪敪偟偨丅敄埫偔側傝巒傔偨怷偺拞偵丄傑傞偱惎偑鄪傔偄偨偲巚偆偲丄岝傝偼堦婥偵廂懇偟偰丄揤偵岦偐偭偰曻偨傟傞丅
乽傆傆偭丄婅偄偼姁偭偨傛偆偹乿
丂僫儐僞偺徚偊偨嬻傪尒偮傔側偑傜丄梔惛偼枮懌偘側徫傒傪晜偐傋偨丅偒偭偲僒儎僇偺嫋偵岦偐偭偨偲怣偠偰丅
乽偲偙傠偱乧乧乿
丂偙偙偱僫僀儞僥乕儖偼傆偲婥晅偄偨丅
乽傢偨偟偼偳偆傗偭偰僫儐僞傗僒儎僇偺強偵峴偗偽偄偄偺乧乧丠乿
丂梔惛帺恎偱偼丄婅偄傪姁偊傞偙偲偼偱偒側偄丅僫僀儞僥乕儖偼丄偨偭偨堦恖庢傝巆偝傟傞偙偲偲側偭偨乧乧丅
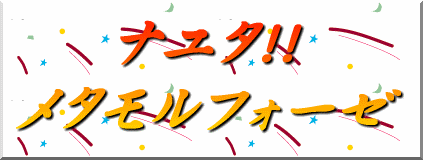
戞俁徫丒妝偟偄僺僋僯僢僋偵丒丒丒丒側傞傢偗側偄傛偹乮丱丱丟嘊
侾侾
乽傑偭偨偔乧乧丄嵟嬤僣僉偑偹偊偤乿
丂偍傏傠偘偵婄傪弌偟偨寧偑尒壓傠偡怷偺拞傪丄堦旵偺儚乕僂僼儖偑恎懱傪堷偒偢傞傛偆偵曕偄偰偄偨丅偦偺杍偼怺偔棊偪偔傏傒丄庤懌偼屚傟栘偺傛偆偵嵶偄丅堦尒偟偰嬻暊偵枮偨偝傟偰偄傞偺偑暘偐傞丅
丂偙偺儚乕僂儖僼偼丄傕偆悢擔娫傕壗傕岥偵偟偰偄側偐偭偨丅偲偼偄偊儚乕僂僼儖偼庪傝偺柤庤丅慡椡偱憱傟偽偳傫側摦暔傛傝傕懍偄偟丄戝偒側帹偼彫偝側暔壒偱傕暦偔偙偲偑偱偒丄塻偄捾偼堦寕偱妉暔偺岮傪愗傝楐偄偨丅乫怷偺僴儞僞乕乫偲偄傢傟傞強埲偱偁傞丅
丂偩偐傜丄妉暔傪庢傝摝偑偟偰偄偨傢偗偱偼側偐偭偨丅扨偵妉暔偑偄側偐偭偨偺偱偁傞丅梔惛偺怷偵偼彫摦暔偑朙晉偵偄傞偼偢側偺偱丄妉暔傪尒偮偗傜傟側偐偭偨偺偼晄塣偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅
丂偟偐偟偮偄偵崱擔丄懸朷偺妉暔傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒偨丅偦傟傕丄恖娫偺巕嫙偑擇恖丅嬻暊傪枮偨偡偵偼廫暘夁偓傞傎偳偩偭偨丅
丂斵帺恎偼恖娫傪尒偨偺偼弶傔偰偱偁偭偨偑丄恖娫傪怘傋偨偙偲偺偁傞拠娫偺榖偱偼丄偦偺擏偼偡偙傇傞巪偄傜偟偄丅偟偐傕恖娫偼偦偺曈偵偄傞摦暔偲堘偭偰丄嫲晐偵愴乮偍偺偺乯偄偨傝媰偒嫨傇昞忣偑偼偭偒傝暘偐傞偲偄偆丅偦偺榖傪暦偄偨偲偒丄斵偺拞偵偁傞廱乮偗傕偺乯偲偟偰偺怱偑醬偒丄偦傟偩偗偱儓僟儗偑枮偪偰偒偨傎偳偩丅
丂偩偑偦偺巕嫙払偵嬤偯偙偆偲怲廳偵愙嬤偟偰偄偨偲偒丄偄偒側傝墧偺僞儅偑旘傫偱偒偰斵偺旣娫偵柦拞偟偨丅偦偺偍偐偘偱擇恖偺巕嫙偐傜抶傟傪偲傞偙偲偵側傝丄屻傪捛偄偐偗傛偆偵傕攚偺崅偄錗傪偐偒暘偗偰恑傓偺偼丄嬻暊偺斵偵偲偭偰崪偺愜傟傞嶌嬈偱偁偭偨丅
丂寢嬊錗傪敳偗傞崰偵偼丄姰慡偵擇恖傪尒幐偆偙偲偵側偭偨丅
乽偔偦偭丄偄偮傕偺壌偩偭偨傜丄偁傫側僈僉擇恖乧乧乿
丂媣偟傇傝偺妉暔偱偁偭偨偟丄側偵傛傝傕傑偩怘傋偨偙偲偺側偄恖娫傪摝偑偟偨偺偼丄夨傗傫偱傕夨傗傒偒傟側偐偭偨丅
丂偦傫側偲偒偩偭偨丅抝偺庪恖偑丄偟偐傕帺暘偺曽偐傜僲僐僲僐偲偙偪傜偺曽偵傗偭偰偒偨偺偱偁傞丅
丂崱搙偙偦妉暔偵偁傝偮偗傞偙偲傪妋怣偟偨丅崱搙偺恖娫偼巕嫙偱傕側偔丄傑偨晲婍傑偱帩偭偰偄傞丅偩偑彮側偔偲傕斵偵偼丄帺暘偺巔傪尒偰摦梙偟偰偄傞傛偆偵尒偊偨丅
丂偟偐偟丄憡庤偼憡摉庤楙傟偺庪恖偩偭偨傛偆偩丅抝偺曻偭偨栴偼斵偺摢傪偐偡傝丄攚屻偺栘偵撍偒巋偝偭偨丅偦傟偼庤尦偑嫸偭偨偺偱傕側偔丄傢偞偲奜偟偨偺偩丅偦偺婥偵側傟偽丄抝偼偄偮偱傕帺暘傪巇棷傔傞偙偲偑偱偒偨偲尵偄曻偭偨丅
丂抝偼丄乽柦偑惿偟偗傟偽嫀傟乿偲尵偭偨丅偦偺尵梩偑丄栴傪岦偗傞偦偺巔偑丄彮偟傕嫰偊偰偄側偄偦偺摰偑丄偡傋偰偑釠偵忈偭偨丅
丂偩偐傜偙偦丄婥晅偄偨偲偒偵偼抝偵廝偄偐偐偭偰偄偨丅抝偑媩傪堷偄偨偺傕尒偊偰偄偨偑丄偦傫側偙偲偼傕偼傗娭學側偄丅壗搙傕妉暔傪摝偑偟偰惗偒偰偄偗傞傎偳丄栰惗偺悽奅偼娒偔側偄偺偩丅偙偙偱抝傪怘偆偐丄偦傟偲傕帺暘偑巰偸偐偩偭偨丅
丂偟偐偟丄岾塣偑朘傟偨偺偼斵偺曽偩偭偨丅憡庤偺抝偑晄塣偩偭偨偺偐丄偦傟偲傕傛傎偳偺娫敳偗偩偭偨偺偐傕抦傟側偄丅抝偑栴傪傂偄偨弖娫丄媩偺尫乮偮傞乯偑愗傟偰偟傑偭偨偺偩偭偨丅偦偺搑抂丄抝偼栰僂僒僊偺傛偆偵摝偘弌偟偨丅
丂妉暔偑帺暘偵攚傪岦偗偰摝偘偰偄偔丅偦傟偼丄偄傑傑偱壗搙傕尒偰偒偨庪傝偺岝宨偩偭偨丅偦偟偰偦偺搙偵丄妉暔傪曔傜偊偰偒偨偺偩丅斵偼抝傪捛偄偐偗側偑傜丄崱搙偦偙暊堦攖偺擏偵偁傝偮偗傞偙偲傪妋怣偟偨丅
丂偩偑偦傟傕懇偺娫丄斵偼抝偺摝偘懌偵嫼埿傪姶偠偨丅偄偔傜捛偊偳傕嵎偑弅傑傜側偄偺偱偁傞丅崱傑偱庪傝傪偟偰偒偰丄偙傫側偙偲偼偙偲偼弶傔偰偱偁偭偨丅帺暘偑嬻暊偩偭偨偣偄傕偁傞偩傠偆偑丄拠娫偐傜傕恖娫偑懌偺懍偄摦暔偩偲暦偄偨偙偲偼側偄丅偦偺曈傝偵偄傞栰僱僘儈偺曽偑傛傎偳偡偽偟偭偙偄偲偄偆榖偟偩丅
丂嵟屻偼帺暘偺旀楯偑尷奅偵払偟丄抝傪摝偑偟偰偟傑偭偨丅妉暔傪擇搙傕摝偑偟偨偺傕弶傔偰偱偁偭偨偑丄側偵傛傝傕偁偺抝偵懌偺懍偝偱晧偗偨偺偼丄斵偺僾儔僀僪偼戝偒偔彎偮偗偨丅
乽抺惗偭丄偳偄偮傕偙偄偮傕壌傪偍偪傚偔傝傗偑偭偰両乿
丂儚乕僂儖僼偼懁偵偁偭偨憪傓傜偵岦偐偭偰丄傗偨傜傔偭偨傜偲僣儊傪怳傞偭偨丅姶忣傪敋敪偝偣偨偦偺嫨傃偼丄傕偼傗尵梩偵偼側偭偰偄側偄丅嵶愗傟偵側偭偨梩偑恎懱偵崀傝偐偐傞偺傕堄偵夘偝偢丄斵偼偦傟傑偱婔懡偺妉暔傪曔傜偊偰偒偨僣儊怳傞偄懕偗偨丅
乽傊傊偭丄愗傝崗傫偱傗傞乿
丂偄偮偟偐栚偺慜偺憪傓傜偼丄悢擔慜偵嵟屻偵曔傜偊偨栰幁偵曄傢偭偰偄偨丅暊偵捾傪撍偒棫偰偨偲偒偵幁偑晜偐傋偨嬯栥偺昞忣偑丄偼偭偒傝偲晜偐傃忋偑偭偰偔傞丅
丂嫸婥偲夣妝偵揗傟偰偄傞偲偟偐巚偊側偄傎偳榗傫偩娽嵎偟傪岦偗偨傑傑丄斵偼暥帤捠傝愗傝崗傫偱偄偭偨丅壗搙傕壗搙傕丅
乽偼偀乧乧丄偼偀乧乧丄偼偀乧乧乿
丂傗偑偰懅傪愗傜偟偨儚乕僂儖僼偼丄慜孅傒偵側偭偰峳偄懅傪晅偄偨丅栚偺慜偵偼丄儃儘儃儘偵側偭偨憪傓傜偑丄柍尵偺傑傑儚乕僂儖僼偵偦偺巔傪偝傜偟偰偄傞丅
乽壗傪傗偭偰偄傞傫偩丄壌偼乧乧乿
丂偦偺岝宨傪栚偺曈傝偵偟偰丄寣憱偭偨儚乕僂儖僼偺摰偐傜丄媫寖偵椡偑幐傢傟偰偄偭偨丅
乽乧乧偄傛偄傛懯栚偐乿
丂偡偱偵慡恎偺姶妎傕敄傟巒傔丄摢傕傏傗偗巒傔偰偄偨丅崱嵺偺嵺乮偄傑傢偺偒傢乯偲偼偙傫側傕偺側偺偩傠偆偐偲丄敄傟備偔堄幆偺拞偱愨朷姶偩偗偑朿傜傫偱偄偔丅偦偙偵偼乫怷偺僴儞僞乕乫偲嫲傟傜傟傞埿埑姶偼側偔丄傑傞偱楬抧棤傪偆傠偮偔晜楺幰偺傛偆偱偁偭偨丅
丂偦傟偐傜偳傟偩偗曕偄偨偐暘偐傜側偄偑丄晄堄偵丄傏傗偗偨帇奅偺拞偵尒偨偙偲偺偁傞塭偑旘傃崬傫偱偒偨丅
乽偁傟偼妋偐乧乧乿
丂敿娽偩偭偨豳偑彊乆偵奐偄偰偄偔偵廬偭偰丄栚偵擖偭偰偔傞塮憸偑偼偭偒傝偟偰偄偔丅斵偺帇慄偺愭偵偄偨偺偼丄暣傟傕側偔巒傔偵庢傝摝偑偟偨擇恖偺巕嫙偩偭偨丅側偵傗傜寧偵婩傝偱傕曺偘傞傛偆側奿岲傪偟偰偄傞丅
乽傊傊偭丄傊傊傊傊傊乧乧乿
丂怣偠傜傟側偄偲偄偭偨昞忣偺儚乕僂儖僼偐傜丄偐偡傟偨徫偄惡偑楻傟傞丅擇恖偑壗傪寧偵婩偭偰偄傞偐偼抦傜側偄偑丄帺暘傕寧偺彈恄偵姶幱偡傞偙偲偵偟偨丅婏愓偼婲偙傞傕偺偩偲丅
乽傕偆丄偟偔偠傜偹偉乿
丂巰偵偐偗偰偄偨摰偵丄嵞傃巆擡側岝傝偑廻傞丅傕偼傗姰慡偵擇恖偵廤拞偟偰偄偨偑丄斵偼杮暔偺廱偺傛偆偵慡偔柍懯偺側偄摦嶌偱丄堦曕擇曕偲擇恖偵嬤偯偄偰偄偭偨丅僴儞僞乕偲偟偰偺寣偲嬌尷傪挻墇偟偨惛恄忬懺偑丄柍堄幆偵偦偆偝偣偰偄傞偺偩傠偆丅
丂掅偔恎傪孅傔偨儚乕僂僼儖偑丄懌壒堦偮棫偰偢偵怷偺埮偺拞傊偲徚偊偰偄偭偨乧乧丅
侾俀
乽偝偰丄偍婩傝傕偡傫偩偙偲偩偟乧乧乿
丂暵偠偰偄偨豳傪僗僢偲奐偒丄僒儎僇偼嫻偺慜偱慻傫偱偄偨椉榬傪壓傠偟偨丅偦偺惏傟傗偐側昞忣偵偼丄戝愗側娽嬀偑捈偭偨偲偄偆婌傃偲丄傕偆堦偮丄僫儐僞偲嵞夛偱偒傞偲偄偆婅偄傊偺婓朷偑偼偭偒傝偲尰傟偰偄傞丅
乽偦傠偦傠峴偒傑偟傚偆偐丄僄僨傿儞乿
丂僒儎僇偼丄椬偱摨偠傛偆偵庤傪崌傢偣偰偨僄僨傿儞偵惡傪偐偗偰棫偪忋偑傝丄儚儞僺乕僗偺僗僇乕僩偵挘傝晅偄偨憪傪暐偄棊偲偡丅
乽偁偁偭丄懸偭偰傛乿
丂栚傪暵偠偰庤傪崌傢偣偰偄偨傜柊偦偆偵側偭偰偄偨僄僨傿儞偼丄僗僞僗僞偲曕偒巒傔偨僒儎僇偺偁偲傪峇偰偰捛偄偐偗偨丅
丂柊偦偆偵側傞偺傕柍棟偼側偄丅僫儐僞傗僒儎僇偑拫怮傪偟偨娫傕乮僫儐僞偼婥愨偟偰偄偨偺偩偑乧乧乯丄斵偼堦恖偱梀傃夞偭偰偄偨偺偩丅偟偐傕崱擔偼挬偐傜曕偒偯傔丅愭掱偼儚乕僂僼儖偵捛偄偐偗傜傟偰偄傞傊傫偰偙側庪恖傪尒偰丄僫儐僞偑彆偗傪屇傫偱偒偰偔傟偨偲婓朷偼桸偄偰偒偨偑丄彫偝偄恎懱偵棴傑偭偨旀楯偼偳偆偟傛偆傕側偐偭偨丅
丂旀傟偰偄傞偺偼僒儎僇傕摨條偱偁偭偨偑丄崱偼旀楯傛傝傕婓朷偺曽偑彑偭偰偄偨丅怷偱柪偄丄偝傜偵戝愗側娽嬀傪夡偟偰偐傜偲偄偆傕偺捑傫偱偄偨斵彈偺昞忣偵傕丄梔惛偲弌夛偭偰婅偄傪姁偊偰栣偭偨偙偲偱丄傛偆傗偔偄偮傕偺柧傞偝偑栠偭偰偄偨丅
乽峴偔偭偨偭偰偳偙偵峴偔偺偝丠乿
乽偳偙偭偰丄怷偺奜偵寛傑偭偰偄傞偠傖側偄乿
丂僒儎僇偼庱偩偗怳傝岦偄偰丄曕偒側偑傜摎偊偨丅
乽曄偵曕偒夞傞偲丄傕偭偲柪偭偪傖偆傫偠傖側偄偺丠乿
乽偩偐傜偭偰丄偠偭偲偟偰偄傞傢偗偵傕偄偐側偄偱偟傚丅傕偆偡偖栭偵側傞偟丄偲偵偐偔偙偺怷偐傜憗偔弌側偄偲乿
乽偱傕偝偀乧乧乿
丂僄僨傿儞偼晄埨偘側昞忣傪偟偰棫偪巭傑傝丄岥偺拞傪壗傗傜儌僑儌僑偝偣偰偄傞丅壗偐尵偄偨偄傜偟偄偑丄偼偭偒傝偲偼尵偊側偄傜偟偄丅
乽偁傜乣丄偳偆偟偪傖偭偨偺偐側丄僄僨傿儞孨丠丂傕偟偐偟偰嫲偄偺偐側丠乿
丂僒儎僇傕棫偪巭傑偭偰怳傝曉傞偲丄傑傞偱梒抰墍偺愭惗偺傛偆側岥挷偱僄僨傿儞傪偐傜偐偭偰傒偨丅
乽偪丄堘偆傛偭両乿
丂僄僨傿儞偼岥偺抂偵朅傪偨傔側偑傜丄栆楏側惃偄偱斲掕偟偨丅
乽偝偭偒傒偨偄夦暔偑僂儓僂儓偟偰傞偐傕抦傟側偄傫偩傛丠丂傕偟偐偟偨傜丄僒儎僇巓偪傖傫偺屻傠偵乧乧乿
乽偊偭丄偆偦両丠乿
丂抁偄斶柭偲嫟偵丄僒儎僇偼庱傪堷偭崬傔側偑傜丄娽嬀偺墱偺摰傪堦攖偵奐偄偰屻傠傪怳傝曉傞丅傑傞偱丄尐偺岦偙偆偱柍悢偺抴鍋偑帺暘偺巺偱僶儞僕乕僕儍儞僾傪偟偰偄傞丄偲暦偐偝傟偨帪偺傛偆側嬃偒傛偆偱偁傞丅
丂偩偑僒儎僇偑怳傝岦偄偨愭偵偼丄夦暔偳偙傠偐儕僗偺巕堦旵偄側偐偭偨丅傓傠傫丄僶儞僕乕僕儍儞僾傪偡傞抴鍋傕偄傞偼偢偼側偄丅
乽偁傟乧乧丠乿
丂數偑摛揝朇傪怘傜偭偨傛偆偵偒傚偲傫偲偟側偑傜丄僒儎僇偼曈傝傪尒搉偡丅偦偺攚拞偺岦偙偆偐傜丄僄僨傿儞偺僎儔僎儔偲偄偆徫偄惡偑暦偙偊偰偒偨丅
乽偼偼偼偭丄僒儎僇巓偪傖傫偩偭偰嫲偄傫偠傖側偄偐丅巕嫙偺杔傛傝偢偭偲擭忋偺偔偣偵乿
乽乧乧乧乿
丂偩丒傑丒偝丒傟丒偨丅偙偺屲暥帤偑丄儊儕乕僑乕儔儞僪偺傛偆偵僌儖僌儖偲僒儎僇偺摢偺拞傪夞偭偰偄偨丅傗偑偰僒儎僇偺対偑彫崗傒偵恔偊巒傔丄偍偱偙偵偼惵嬝偑堦偮擇偮傪憹偊偰偄偔丅
乽僐乧乧丄僐乧乧乧乿
丂乽僐儔乣丄僄僨傿儞乿偲怳傝岦偙偆偲偟偨僒儎僇偺攚拞偵丄僄僨傿儞偑旘傃偮偄偨丅偪傚偆偳僒儎僇偺尐偺忋偐傜榬傪夞偡傛偆側奿岲偵側傞偲丄僒儎僇偺庱嬝傪寉偔掲傔晅偗傞丅
乽僈僆乣丅偍慜傪嶦偟偰偦偺擏傪怘偭偰傗傞乣丅偼偼偼偭乿
乽僐丄僐儔僢両丂傆偞偗傞偺偼傗傔側偝偄丄僄僨傿儞乿
丂夦暔傛傝傕巒枛偺埆偄掜傪僒儎僇偼側傫偲偐怳傝暐偍偆偲偡傞偑丄僄僨傿儞偼墡偺傛偆偵傂傚偄傂傚偄偲僒儎僇偺庤傪偐傢偟偰丄偄偮傑偱傕棧傟傛偆偲偟側偄丅
乽幱傞傑偱棧偝側偄偧乿
乽傕乣丄偟傚偆偑側偄傢偹偉乿
丂巇曽側偔僒儎僇偑幱傠偆偲偟偨偦偺檵撨乧乧
丂僷僠僢
乽傫傫丠乿
乽偁傟丠乿
丂擇恖偺帹偵丄傗偗偵偼偭偒傝偲偦傫側姡偄偨壒偑暦偙偊偰偒偨丅偪傚偆偳彫巬傪摜傫偱丄愜偭偰偟傑偭偨傛偆側壒偩丅
丂擇恖偺摦偒偑堦弖偺偆偪偵巭傑傝丄嬃偒偺昞忣傪晜偐傋偨傑傑曈傝偺條巕傪偆偐偑偭偨丅憶偄偱偄偨擇恖偲偼懳徠揑偵丄曈傝偼晄婥枴側傎偳惷傑傝曉偭偰偄傞丅
乽側乧乧壗傛崱偺壒丠乿
乽僂丄僂僒僊偐壗偐偑巬傪傆傫偩傫偩傛丅偒偭偲偹乧乧乿
丂僄僨傿儞偺乽偒偭偲乿偲偄偆尵梩偵偼丄傎偲傫偳椡偑偙傕偭偰偼偄側偐偭偨丅僂僒僊偺傛偆側彫偝側摦暔偑棫偰偨傛偆側壒偱偼側偐偭偨偐傜偩丅傕偭偲戝偒側丄偦偆丄偪傚偆偳愭掱尒偐偗偨傛偆側儚乕僂儖僼偑棫偰偨傛偆側丄偦傫側壒偩偭偨丅
乽偦丄偦偆傛偹丅儚乕僂儖僼側傫偰偙偲偼丄側偄傢傛偹丅傆傆偭乧乧乿
丂僒儎僇偑堷偒偮偭偨徫傒傪晜偐傋傞丅
乽傗偭傁傝峴偙偆偐丅憗偔壠偵婣傜側偄偲乿
丂偓偙偪側偄摦偒偱僒儎僇偺攚拞偐傜崀傝傞偲丄僄僨傿儞偼僋僀僋僀偲僒儎僇偺暈偺懗傪堷偭挘傞丅
乽偦丄偦偆偟傑偟傚偆偐乿
丂僫儐僞偵夛偊傞偲偄偆婓朷偑尒偊偨偲偰丄傗偼傝嫲偄傕偺偼嫲偄丅媫偵怷偺埮偺岦偙偆偑丄嫲晐偵姶偠傜傟偨丅愡偔傟棫偭偨栘偺昞柺偑丄側傫偲側偔恖偺婄偵尒偊偰偔傞丅梔惛偺怷偵偼丄儚乕僂僼儖偺傛偆側梔杺偩偗偱側偔丄恖娫傪廝偆恖柺庽偑偄傞偲偄偆塡傪僒儎僇傕暦偄偨偙偲偑偁偭偨丅
丂擇恖偼曈傝傪僉儑儘僉儑儘偲偆偐偑偄側偑傜丄婑傝揧偆傛偆偵曕偒巒傔偨丅
丂僈僒儕僢
丂偳偙偐偱憪偑嶤傟傞壒偑偟偨丅
乽傂偂偭乿
乽偹丄巓偪傖傫乧乧乿
丂帺慠偲擇恖偼憗曕偒偵側傞丅
丂壗偐偺帇慄傪姶偠偨丅懅偑媗傑傝偦偆側傎偳丄姦婥傪妎偊傞傛偆側帇慄偱偁傞丅偪傚偆偳丄偦偽傪捠傝敳偗偨戝栘偺曽偐傜偩偭偨乧乧
乽偆傢偀丄巓偪傖傫両乿
丂僄僨傿儞偑斶柭傪忋偘偨丅拑怓偄壗偐偑丄栘偺墱傜偐傜怢傃偰偔傞丅僒儎僇偑怳傝岦偄偨帇慄偺愭偵偁偭偨偺偼乧乧
乽偒傖偁丄幹両乿
丂栘偺墱偐傜尰傟偨偺偼丄妼怓偺抧偵愒妼怓偺栦傪帩偮僯僔僉僿價偱偁偭偨丅偟偐偟摲偺戝偒偝偼僒儎僇偺榬傛傝傕懢偔丄挿偝偵帄偭偰偼梩偺堿偵塀傟偰憐憸傕偱偒側偄丅
丂幹偑寵偄側僒儎僇偼摢傪書偊傞傛偆偵偟偰旘傃偺偄偨偑丄偦偺攺巕偵僶儔儞僗傪曵偟偰抧柺偵怟栞傪偮偄偰偟傑偭偨丅偦偺僒儎僇偺栚偺慜偵丄戝幹偑偸偅偭偲嬤偯偔丅
乽偁乧乧丄偁偁乧乧乿
丂栚偺慜偱愒偄愩傪僠儘僠儘偲偝偣側偑傜丄戝幹偼偠偭偲僒儎僇傪尒偮傔偰偄傞丅傑傞偱憡庤傪尒掕傔偰偄傞偐偺傛偆偩丅旼傪僈僋僈僋偲怳傞傢偣偨傑傑丄僒儎僇偺昞忣偼搥傝晅偄偰偄偨丅
丂偩偑傗偑偰戝幹偼摢傪擇搙嶰搙傪傂偹傞偲丄偦偺傑傑僗儖僗儖偲栘偺忋偵栠偭偰偟傑偭偨丅偳偆傗傜怘傋傛偆偲偟偰偄偨傢偗偱偼側偐偭偨傜偟偄丅憶偄偱偄偨偺偱丄條巕傪尒偵棃偨偺偱偁傠偆偐丅
乽偼偀乧乧乿
丂慡恎偺椡偑敳偗偰偄偔偺傪姶偠側偑傜丄僒儎僇偼怺偄偨傔懅傪晅偄偨丅埨揼偺昞忣傪晜偐傋傞僒儎僇偺攚屻偱丄壒傕側偔塭偑摦偔丅
丂檵撨丄屲杮偺慚岝偑憱偭偨丅丂
乽偁傇側偄偭両乿
丂慚岝偲嫨傃惡偑岎嵎偡傞側偐丄壗偐偑僒儎僇偺恎懱偵傇偮偐傝丄斵彈偼抧柺偺忋傪墶偵揮偑偭偨丅偦偺僒儎僇偺栚偺慜傪丄塻偄捾偑嬻傪愗傝楐偔傛偆偵夁偓偰備偔丅
乽僄僨傿儞丠乿
丂抧柺偵搢傟傞僒儎僇偺忋偵忔偭偰偄偨偺偼丄僄僨傿儞偱偁偭偨丅斵偑僒儎僇傪墴偟搢偟偰偄側偗傟偽丄偁偺捾偼僒儎僇偺恎懱偵崗傑傟偰偄偨偩傠偆丅
乽僠僢乿
丂愩懪偪偲嫟偵丄偺偦傝偲恖塭偑憪傓傜偺墱偐傜尰傟傞丅斲丄偦偺榬偼擹偄拑怓偺懱栄偵暍傢傟偰偍傝丄偦偺摢偼恖娫偺傕偺偱偼側偔丄楾偱偁偭偨丅
乽儚乕僂儖僼両乿
丂欜歭偵僄僨傿儞偼攚晧偭偰偄偨儕儏僢僋僒僢僋傪慜偵書偊丄拞偵擖傟偰偍偄偨僷僠儞僐傪峔偊偨丅慱偄傪儚乕僂儖僼偺妟偵掕傔傞丅
乽偄偪偄偪乧乧乿
丂儚乕僂儖僼偼丄僄僨傿儞偲偦偺僷僠儞僐傪憺乆偟偔嵘傒偮傔偨丅弶傔偰擇恖傪尒偮偗偨偲偒傕偦偺僷僠儞僐偺偣偄偱擇恖傪尒幐偄丄崱搙傕傑偨僄僨傿儞偑僒儎僇傪彆偗偨丅
乽幾杺偡傫偠傖偹偉両乿
丂儚乕僂儖僼偼僄僨傿儞偺婄柺偵対傪怘傜傢偣偨丅撦偄壒偲嫟偵僄僨傿儞偼悂偒旘偽偝傟丄擇搙嶰搙偲抧柺傪揮偑傝丄戝幹偺弌偰偒偨戝栘偺姴偺懁偵偆偮暁偣偵側傞丅墸傜傟偨攺巕偵婥傪幐偭偨偺偐丄僄僨傿儞偼偦偺傑傑偖偭偨傝偲摦偐側偔側偭偰偟傑偭偨丅
丂搢傟偨僄僨傿儞偺懁偵偼丄儕儏僋僒僢僋偺拞偵擖偭偰偄偨斵偺娺嬶傗丄曎摉偺饽傗傜悈摏傗傜偑嶶棎偟偰偄偨丅
乽僄僨傿儞両乿
乽偍偭偲乿
丂僄僨傿儞偺條巕傪尒偵峴偙偆偲怳傝曉傞僒儎僇偺懌傪丄儚乕僂儖僼偑屻傠偐傜偼傜偭偨丅偦偺攺巕偵丄僒儎僇偼嵞傃抧柺偺忋偵搢傟傞丅
乽傊傊偭丄懠恖偺怱攝傛傝帺暘偺怱攝傪偟偨曽偑偄偄偤乿
丂儚乕僂儖僼偼夊傪傓偒弌偡傛偆偵偟偰偣偣傜徫偭偨丅嬃湵偵恔偊傞僒儎僇偺栚偺慜偱丄儚乕僂儖僼偼備偭偔傝偲榬傪怳傝忋偘傞丅揤偺寧偲廳側傝崌偭偨屲杮偺捾偑丄晄婥枴偵撦偄岝傪曻偭偨丅
丂偦偺帪丄擇恖偺娫偵惵敀偄慚岝偑鄪傔偄偨丅
侾俁丂
丂惵敀偄悽奅偑丄備偭偔傝偲怓偁偣偰備偔丅
乮偄傛偄傛偐乧乧乯
丂僫儐僞偼丄備偭偔傝偲姎傒偟傔傞傛偆偵欔偄偨丅
丂巚偊偽挿偄摴偺傝偱偁偭偨丅梉擔偼抧暯慄偺斵曽偵徚偊備偒丄寧偑怷傪徠傜偦偆偲偟偰偄傞丅
乮偲偙傠偱丄側傫偰尵偭偰僒儎僇偵惡傪偐偗偨傜椙偄傫偩傠偆乯
丂僫儐僞偼傆偲嵞奐偺応柺傪峫偊偰傒偨丅
乮偄偒側傝書偒偮偔偭偰偺傕偁傞偗偳側偀乣丅庪恖偵曄恎偟偨傑傑偩偐傜媡偵僒儎僇傪嬃偐偣傞偩傠偆偟丅偳偆偣僒儎僇偵夛偊傞傫側傜丄僫僀儞僥乕儖偵曄恎傪夝偄偰栣偊偽傛偐偭偨丅偦偆偟偨傜丄怷偱偼偖傟偨梒側偠傒摨巑偺姶摦偺嵞奐丄書偒崌偆擇恖傪枮寧偑廽暉丄撉幰偼姶摦偺椳偭偰偄偆揥奐偵側偭偨偺偵乧乧丅偆乣傫丄傗偭傁傝偙偙偼惓媊偺枴曽傒偨偄偵丄偝傢傗偐偵尰傟傛偆丅妏搙揑偵偼塃係俆搙偺傾儞僌儖偑椙偄偐側丅乽孨傪彆偗偵棃偨傛丄僒儎僇偪傖傫乿偲偐尵偄側偑傜丄僯僢僐儕偲徫偄偐偗偰墱帟傪岝傜偣傞傫偩丅僒儎僇偼姶寖偺偁傑傝椳傪棳偟側偑傜丄傗偭傁傝杔偵書偒偮偔丅偦偺僒儎僇傪丄杔偑桪偟偔庴偗巭傔傞傫偩丅傆傆偭丄僫僀儞僥乕儖偲偄偆幾杺幰偼偄側偄丅偦偺傑傑椳偲姶摦偺僴僢僺乕僄儞僪偩丅慜偼僔儍僪僂傪曔傑偊偨姶幱忬傪數偵庢傜傟偰廔傢傞偭偰偄偆僆僠偩偭偨偗偳丄崱搙偼嵟屻偱僉儊偰傗傞傫偧乯
丂乽傛偟偭乿偲婥崌偄傪擖傟偰丄僫儐僞偼偓傘偭偲対傪埇傝偟傔偨丅
丂傗偑偰丄栚偺慜偵恖塭偑尒偊偰偒偨丅偄傛偄傛懳柺偺弖娫偱偁傞丅僫儐僞偼塃係俆搙偵峔偊偰丄姶摦偺僄儞僨傿儞僌偵旛偊傞丅
丂偦偟偰乧乧丄
乽孨傪彆偗偵棃偨傛丄僒儎僇乧乧偪傖傫丠乿
丂嵟崅偺徫婄偱僶僢僠儕寛傔偨丄偼偢偩偭偨丅偟偐偟栚偺慜偵尰傟偨偺偼丄僒儎僇偲偼帡偰傕帡偮偐側偄楾偺巔傪偟偨梔杺丅
丂偦偺巔偼朰傟傞偼偢傕側偄丅儚乕僂儖僼偩偭偨丅
丂偩偑儚乕僂儖僼偺曽傕丄撍慠僫儐僞偑栚偺慜偵尰傟偨傕偺偩偐傜丄捾傪怳傝偐傇偭偨傑傑椉栚傪僉儍價傾偺傛偆偵彫偝偔偟偰屌傑偭偰偄傞丅
乽僒丄僒儎僇丠乿
丂僫儐僞偼塻偄夊偺暲傇岥傪丄戝偒側帹傪丄挿偔怢傃偨捾傪丄堦偮堦偮妋偐傔傞傛偆偵怗偭偰偄偭偨丅
乽偦丄偦傫側攏幁側乧乧乿
丂傗偑偰僫儐僞偼儚僫儚僫偲恎懱傪怳傞傢傞偲丄曵傟棊偪傞傛偆偵偟偰抧柺偵椉庤偲椉旼傪偮偄偨丅偦偟偰丄偳偙偐傜偲傕側偔僗億僢僩儔僀僩偑僫儐僞傪摂偡丅傑傞偱幚尡偵幐攕偟偨偳偙偐偺妛幰偺傛偆偩丅
乽偁丄偁偺乣丅僒儎僇偼乧乧乿
丂屻傠偐傜彮彈偺惡偑偟偰尐傪扏偐傟偨偑丄撧棊偺掙偵撍偒棊偲偝傟偨僫儐僞偵偼撏偔偼偢傕側偐偭偨丅
乽偳偙偺扤偩偐偼抦傜側偄偑丄偟偽傜偔杔傪堦恖偵偟偰偔傟側偄偐丅偙傟偐傜丄扵偟媮傔偰偄偨彮彈傪幐偭偨庡恖岞偑丄怱偺嫨傃傪揻業偡傞斶偟偄応柺側偺偩偐傜乿
乽偼丄偼偄乧乧乿
丂彮彈偼偍偢偍偢偲庤傪壓偘傞丅
乽偁偁丄寧偺彈恄傛丅壗偲塣柦偼旂擏側傕偺偱偁傠偆偐乿
丂寧傪尒忋偘傞僫儐僞偺摰偐傜丄椳偺揌偑偼偠偗偨丅偦偺庤偵偼偟偭偐傝偲栚栻偑埇傜傟偰偄傞乧乧丅
乽怷偱柪偭偨垼傟側孼掜傪彆偗傞偨傔丄怺偄錗傪敳偗丄儚乕僂儖僼偵捛偄偐偗傜傟丄壥偰偼僇僄儖偲岥偯偗傪岎傢偡偲偄偆嬯偄宱尡傑偱偟偰丄偲偆偲偆夛偊傞弖娫偑傗偭偰偒偨偲巚偭偨偺偵丅悢乆偺崲擄偺偔偖傝敳偗偰夛偊偨彮彈偼丄偙傫側廥偄巔偵乿
丂乽偙傫側乿偲尵偄側偑傜丄僫儐僞偼儚乕僂儖僼傪巜偝偡丅
乽杔偼堦弖偨傝偲偰擇恖偺偙偲傪朰傟偨偙偲偼側偄丅擇恖偺巕嫙偑埫偄怷偺拞偱柪偄丄晄埨偵嬱傜傟丄嫲晐偵懪偪傂偟偑傟丄庘偟偝偵嫰偊傞巔傪巚偆偩偗偱丄杔偺怱偼丄僔儍儃儞嬍偺傛偆偵抏偗偰徚偊偰偟傑偄偦偆偩偭偨乿
丂僫儐僞偼椳傪怈偭偰棫偪忋偑傝丄揤偺寧偵岦偐偭偰椉榬傪偐偞偟偰峏偵尵梩傪懕偗傞丅
乽彈恄傛丄傑偩帋楙偑懕偔偲偄偆偺側傜丄偙偺杔偵椡傪戄偟偰偔傟丅偦偺桪偟偄旝徫傒偼丄杔偺怱傪桙偟偰偔傟傞偩傠偆丅偦偺婸偒偼丄偙偺埫偔壥偰偟側偄堬偺摴偵岝傝傪摂偡摴昗偲側偭偰偔傟傞偩傠偆丅栭偺挔乮偲偽傝乯傪摫偒丄偁側偨偼偦偺偨傔偵巔傪尒偣偨偺偩偐傜丅傗偑偰尰傟傞偩傠偆揤偺愳偼丄偁側偨偐傜偺偭両丠乿
乽偔偩傜偹偉嶰暥幣嫃偼偦偙傑偱偩乿
丂晄堄偵僫儐僞偼嫻尦傪曔傑傟丄儚乕僂儖僼偵堷偒婑偣傜傟偨丅栚偺慜偱偼丄搟傝偺偁傑傝偵寣憱偭偨儚乕僂儖僼偺帇慄偑丄恀偭捈偖僫儐僞傪嵘傒晅偗偰偄傞丅
乽媣偟傇傝偩側偀丅偺偙偺偙偲傑偨尰傟傞偲偼丄恖娫偵摝偘傜傟偨儚乕僂儖僼傪偍偪傚偔傝偵棃偨偺偐丠丂偦傟偲傕乧乧乿
丂儚乕僂儖僼偼峏偵僫儐僞傪堷偒婑偣丄僪僗偺棙偄偨惡偱偙偆懕偗偨丅
乽偦傫側偵壌偵怘傢傟偨偄偺偐丠乿丂
乽乧乧傕丄傕偟偐偟偰丄偝偭偒杔傪捛偄偐偗偰偄偨儚乕僂儖僼偐丠乿
丂栚傪娵偔偟偰嬃偔僫儐僞偺栤偄偐偗偵丄儚乕僂儖僼偼柍尵偺傑傑桴偒丄傑偨塻偄帇慄傪僫儐僞偵岦偗偨丅
乽偲偄偆偙偲偼丄偝偭偒偺彈偺巕偺惡偑乧乧乿
丂傑偝偐偲巚偄側偑傜傕丄備偭偔傝偲怳傝曉偭偨偦偺愭偵偼丄怽偟栿側偝偦偆側婄傪偟偨僒儎僇偺巔偑偁偭偨丅
乽偁偺丄側傫偩偐惡傪偐偗偢傜偐偭偨傕偺偱偡偐傜乧乧乿
丂戝棻偺娋偲嬯徫偄傪晜偐傋偨傑傑丄僫儐僞偼儊僨儏乕僒偵嵘傑傟偨偐偺偛偲偔彊乆偵愇壔偟偰偄偔丅
丂堦昩乧乧丄
丂擇昩乧乧丄
丂嶰昩乧乧丄
丂巐昩乧乧丄
丂屲昩乧乧偲丄偁偨傝偼捑栙偵曪傑傟偨丅
乽偼偼丄偼偼偼偼偼乧乧乿
丂偦偺捑栙傪攋傞傛偆偵丄僫儐僞偺姡偄偨徫偄惡偑偁偨傝偵偙偩傑偟偨丅
乽偩乣偼偭偼偭両丂偦偆偐丄偦偆偩偭偨偺偐両丂偁乣偭偼偭偼偭偼偭偼偭偼偭両乿
丂僫儐僞偼儚乕僂儖僼偺尐傪億儞億儞偲扏偒丄乽傢偼偼偼偼乿偲攏幁徫偄傪忋偘側偑傜僗僞僗僞偲偦偺応偐傜棧傟傛偆偲偟偨丅偩偑儚乕僂儖僼偼嫀傝備偔僫儐僞偺嬢傪屻傠偐傜捦傓偲丄嫮堷偵栚偺慜偵堷偒栠偟偨丅
乽懸偰僐儔偀丅徫偭偰嵪傑偦偆偲偡傫偠傖偹偉乿
乽烼摡偟偄搝偩側偀丅偍慜偺廘偄懅傪偙傟埲忋歬偓偨偔側偐偭偨偩偗偩乿
乽憡曄傢傜偢岥偺尭傜偹偉搝偩側丅崱搙偼帺枬偺媩栴傕帩偭偰偹偉傫偩偧乿
乽妋偐偵丄媩栴偼傕偆側偄乧乧乿
丂僫儐僞偑帩偭偰偄偨媩栴偼丄慜夞儚乕僂儖僼偵廝傢傟偨偲偒偵丄嬸偐偵傕帺暘偱夡偟偰偟傑偭偨偺偩丅
乽偮傑傝丄崱偺偍慜偼娵崢偭偰偙偲偩側乿
乽偦偺捠傝偩丅偦偙偱丄偙傟偱寛拝傪偮偗側偄偐乿
丂偦偆尵偆偲丄僫儐僞偼対傪埇傝偟傔偰儚乕僂儖僼偺栚偺慜偵宖偘偨丅
乽傕偟偍慜偑晧偗偨傜丄擇搙偲杔傜偺慜偵偼巔傪尰偝側偄偲栺懇偡傞傫偩丅偦偟偰傕偟杔偑晧偗偨傜丄幭傞側傝從偔側傝岲偒偵偟偰峔傢側偄丅偨偩偟丄僒儎僇偪傖傫傗僄僨傿儞孨偼尒摝偟偰傗偭偰偔傟丅杔堦恖傪怘傋傟偽廫暘偩傠偆乿
乽側傞傎偳側丅抝偲抝偺丄恀寱彑晧偭偰傗偮偐乿
乽偦偆乧乧丅抝偲抝偺墛偺恀寱彑晧丄僕儍儞働儞偩偭両乿
乽乧乧乧乿
乽傾儂僅乣丄傾儂僅乣乿丂
丂帪崗奜傟偺僇儔僗偑旘傫偱偄偔丅悽奅堚嶻媺偺偍攏幁偩丅
乽傆偞偗傫偺傕偄偄壛尭偵偟傠乣両乿
丂儚乕僂儖僼偼偮偄偵僽僠愗傟偰乮摉慠偱偁傠偆乯丄塃庤傪怳傝偐傇偭偨丅
乽偔偭丄懸偰丅偄偒側傝巒傔傞側傫偰斱嫰偩偧乿
丂偙傟偐傜堦夞彑晧偵偟傛偆偐偵嶰夞彑晧偵偟傛偆偐寛傔傛偆偲巚偭偰偄偨僫儐僞偼丄峇偰偰僕儍儞働儞偺儌乕僔儑儞偵擖傞丅
乽僕儍儞丄働儞丄億儞偭両丂杔偼僠儑僉丄偍慜偼僷乕丅杔偺彑偪偩偭両乿
丂惓恀惓柫偺僷乕偼僫儐僞偺曽偱偁傞丅儚乕僂僼儖偺僷乕乮傕偪傠傫捾傪棫偰偰廝偄偐偐偭偰偒偨傕偺乯偼丄偦偺傑傑僫儐僞偺婄柺偵岦偐偭偰怳傝壓傠偝傟偰偒偨丅
乽偆偍偭乿
丂僫儐僞偼儚乕僂儖僼偺捾傪娫堦敮偱傛偗丄僒儎僇傪書偒偐偐偊偨傑傑戝偘偝偵抧柺傪壗搙偑揮偑傞丅偪傚偆偳戝幹偑尰傟偨戝栘偺姴偺懁傑偱揮偑傝偱丄朤傜偱偼僄僨傿儞偑搢傟偰偄傞丅
乽戝忎晇偐偄丄僒儎僇偪傖傫丠乿
乽偊偭丠丂偁偁丄偼偄乧乧乿
丂廝傢傟偦偆偵側偭偨偺偼僫儐僞偺曽側偺偵丄壗屘帺暘偑彆偗傜傟偨偺偐偼傛偔暘偐傜側偐偭偨偑丄偲傝偁偊偢僒儎僇偼曉帠傪偟偰偍偄偨丅
乽墭偄搝偩丅僕儍儞働儞傪偡傞偲尒偣偐偗偰杔傪桘抐偝偣丄幚偼偡偖屻傠偵偄偨僒儎僇偪傖傫傪慱偆側傫偰乿
乽慱偭偨偺偼傆偞偗偨偰傔偊偺曽偩両丂姩堘偄偡傞偺傕掱乆偵偟傠両乿
乽姩堘偄丠丂姩堘偄偟偰偄傞偺偼偍慜偺曽偩丅偍慜偐傜棧傟偨偺偼丄傕偪傠傫嫍棧傪庢傞偨傔偱偼偁傞丅偩偑丄傕偆堦偮偺慱偄偼乧乧乿
丂僫儐僞偼堄枴偁傝偘側徫傒傪儚乕僂儖僼偵岦偗偨傑傑丄攚屻偺戝栘偵庤傪怢偽偟偨丅偦偟偰偦偺戝栘偵棈傑偭偰偄偨枲乮偮傞乯傪埇傞偲丄椡傪崬傔偰偦偺枲傪堷偒婑偣傞丅
丂僈僒僈僒偲壒傪棫偰偰堷偭挘傜傟偰偒偨枲傪丄僫儐僞偼抧柺偵扏偒晅偗偨丅僶僔僢偲偄偆塻偄壒傪棫偰偰丄枲偼抧柺偺憪傪壗杮偐姫偒忋偘傞丅傑傞偱曏偺傛偆偩丅
乽庪恖偼怷偺愱栧壠丅椺偊娵崢偩偭偨偲偟偰傕丄帺暘偺恎傪庣傞弍偼偄偔傜偱傕偁傞偝乿
乽傆傫偭丄偦傫側懄惾偺曏偱壗偑偱偒傞丠乿
乽壗偑偱偒傞偐偭偰丠丂側傫側傜帋偟偰傒傛偆偐丠乿
丂旲偱徫偆儚乕僂儖僼偵丄僫儐僞偼枲偺曏傪埇傝捈偟偨丅偦偟偰丄棐偺傛偆側曏嵸偒偑巒傑傞丅
僸儏儞乧乧丄僶僔僢丄僶僔僢丄僶僔僢丄僶僔僢丄僶僔僢丄僶僔僢丄僶僔僢丄僶僔僢丅
丂栚偵傕棷傑傜偸憗偝偩偭偨丅儚乕僂儖僼偺懌壓偱丄椢怓偺憪偑寖偟偔姫偒忋偑傞丅椺偊傞側傜偽丄壗昐偲偄偆彫嫑偑悈柺偱挼偹偰偄傞傛偆丄偲尵偊傞偩傠偆偐丅悢偊愗傟側偄傎偳偺憪偑旘傃挼偹偰偄偨丅
乽乧乧偲丄偙傫側嬶崌偝乿
丂僫儐僞偑枲偺愭抂傪僉儍僢僠偟偨弖娫丄棐偼惷傑偭偨丅儚乕僂儖僼偼堦曕傕摦偄偰偄側偄丅偄傗丄摦偗側偐偭偨偺偩丅
丂偟偐傕丄僫儐僞偼偨偩傗傒偔傕偵枲偺曏傪怳傞偭偰偄偨傢偗偱偼側偄丅儚乕僂儖僼偺懌壓偺憪偼丄傑傞偱揤偵婸偔枮寧偺傛偆偵悺暘偺嫸偄傕側偔墌宍偵姞傜傟偰丄抧柺偑業傢偵側偭偰偄偨偺偱偁傞丅偳傟掱弉楙偟偨僒乕僇僗偺挷嫵巘偱傕丄崏栤棛偱傕丄偙傟傎偳尒帠側曏嵸偒傪尒偣傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆丅
丂儚乕僂儖僼偼丄偁傫偖傝偲岥傪奐偗偨傑傑峝捈偟偰偄偨丅傗偑偰偦偺岥偐傜怢傃傞俀杮偺將帟偺堦偮偵僸價偑擖傝丄僷僉僢偲偄偆彫偝側壒偲嫟偵搑拞偐傜愜傟偰偟傑偭偨丅
乽崱偺偼寈崘戙傢傝偩丅帺枬偺夊傪擇杮傕幐偄偨偔側偄偩傠丅柦偑惿偟偐偭偨傜偙偙偐傜嫀傟乿
丂嫼偟偱偼側偐偭偨丅堦曕偱傕嬤偯偄偨傜梕幫側偔曏傪怳傞偆偧偲偄偆堄巙偑丄僫儐僞偺摰偐傜嫮楏偵曻偨傟偰偄傞丅
乽偙偙偐傜乧乧嫀傟偩偲乿丂
丂僫儐僞偺尵梩偵丄儚乕僂儖僼偺帇慄偑彊乆偵塻偔側偭偰偄偔丅恔偊傞傎偳嫮偔埇傝偟傔偨対偐傜偼丄偄偮偟偐愒偄寣偑愼傒偩偟丄億僩儕億僩儕偲揌傝棊偪偰偄偨丅
乽偰傔偊偺偦偺尵梩偑儉僇僣僋傫偩両丂偦偺懺搙偑丄偦偺娽偑丄偦偺摝偘懌偺憗偝偑丄偡傋偰偑儉僇僣僋傫偩傛両丂怷偺愱栧壠偩偀丠丂僫儊傫側両丂偙偺壌偼儚乕僂儖僼偩両丂怷偺僴儞僞乕偩両丂妉暔傪栚偺慜偵偟偰摝偘傜傟傞偐偭偰儞偩両乿
丂儚乕僂儖僼偼戝抧傪廟偭偨丅懱惃傪掅偔偟丄偐傑偄偨偪偺偛偲偔堦捈慄偵僫儐僞偵撍偭崬傫偱偄偔丅
乽嬸偐側乿
丂抁偔欔偔偲丄僫儐僞偼曏傪戝偒偔怳傝偐傇偭偨丅僸儏儞偲偄偆壒傪棫偰偰丄曏偼傑傞偱惗柦傪摼偨偐偺偛偲偔僫儐僞偺摢忋偵怢傃偰偄偔丅偦偟偰丄慱偄傪儚乕僂儖僼偵掕傔偨丅
乽壗搙傗偭偰傕摨偠偙偲偩両乿
丂偦偆丄壗搙傗偭偰傕摨偠偱偁傞丅偦傟偑廻柦側偺偩丅
丂傑偝偵曏傪曻偲偆偲偟偨弖娫丄價僋儕偲曏偑摦偐側偔側偭偰偟傑偭偨偺偩丅
乽傫傫偭丄偳偆偟偨傫偩両乿
丂曏偺愭傪尒忋偘傞僫儐僞偺帇慄偺愭偵偼乧乧丅
乽偒丄栘偵曏偑棈傑偭偰傞両乿
丂傑偭偨偔丄偳偪傜偑嬸偐側偺偩傠偆偐丅慡偔摨偠岝宨偱丄慜夞偼媩栴傪夡偟偰偟傑偄丄崱夞偼曏傪栘偵棈傑偣偰偄傞丅壗傪傗偭偰傕忋庤偔峴偐側偄丄僫儐僞偺斶偟偄廻柦乧乧丅
丂偡偱偵儚乕僂儖僼偲偺嫍棧偼敿暘埲忋弅傑偭偰偄偨丅僫儐僞偼堦弖偺鐣弰偺屻丄曏傪埇傝偟傔偨傑傑儚乕僂儖僼偐傜棧傟傞傛偆偵戝栘偺姴偵岦偐偭偰僕儍儞僾偟偨丅儚儔價乕傗僇儞僈儖乕偵傕晧偗偢楎傜偢偺丄慺惏傜偟偄挼桇椡偱偁傞丅
丂壈偟偨偐丄僫儐僞丠丂
丂偦偆巚傢傟偨偦偺帪丄僫儐僞偼僕儍儞僾偟偨栘偺姴傪廟偭偰斀摦傪偮偗丄怳傝巕嬍偺傛偆偵敿墌偺婳愓傪昤偒側偑傜丄儚乕僂儖僼傔偑偗偰塃懌傪撍偒弌偟偨丅
乽偒偂偊乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣偭両乿
丂偝偡偑丄揮傫偱傕偨偩偱偼婲偒側偄偺偑曄恎偟偨僫儐僞偺惁偝偱偁傞丅栘偵棈傑偭偨曏傪棙梡偟偰丄嶰妏廟傝傕偳偒偺僂儖僩儔俠媺偺棧傟嬈傪孞傝弌偟偨丅
丂墿嬥偺塃懌傪曻偮僫儐僞偲丄嫢埆側捾傪怳傝偐傇傞儚乕僂儖僼丅椉梇偑崱傑偝偵帗梇傪寛偟傛偆偲偟偨偦偺帪丄
儃僉僢両
丂偁偁乧乧丄傗偼傝廻柦偲偼旂擏側傕偺偱偁傞丅
丂晄塣偵傕丄僫儐僞偑曏傪棈傑偣偨巬偼晠偭偰偄偨偺偩丅恖娫偺懱廳偲丄側偵傛傝傕僫儐僞偺嶰妏廟傝傕偳偒偺惃偄偵懴偊傜傟側偐偭偨偺偱偁傠偆丅巬偺晅偗崻偁偨傝偐傜崑夣偵儃僢僉儕偲愜傟偰偟傑偭偨丅
丂巬偑愜傟傟偽丄摉慠僫儐僞偵巆偝傟偨摴偼丄棊偪傞偟偐側偄丅
丂偪傚偆偳僗僺乕僪傕堦斣忔偭偰偒偨惃偄偺傑傑丄偟偐傕廟傝偺儌乕僔儑儞偦偺傑傑偵丄僫儐僞偼抧柺偲寖偟偔徴撍偟偨丅嫮惂揑側屢楐偗偱偁傞丅乽偖偓偂偭乿偲偄偆壒偑暦偙偊偰偒偦偆偩丅壛偊偰屢娫傕嫮懪偟偨丅
乽偭両両乿
丂嫨傃惡傕忋偘傜傟偢丄僫儐僞偼栥愨偟偨丅擇嵨帣偺傜偔偑偒偺傛偆偵曄宍偟偨僫儐僞偺婄柺偐傜嶡偡傞偵丄偒偭偲偙偆嫨傃偨偄偺偩傠偆丅
傕偪傖偪傘傄傟偆偵傚偵乣傫仸仩仛亰仌仹丠侓乮丱丱丟(TT)乮亅仮亅乯乮亜亙乯丷(佫佨丷)(僲佨佫乯僲
丂嶌幰傕傛偔暘偐傜側偄偑丄偲偵偐偔乽傕偪傖偪傘傄傟乿側忬嫷側偺偼妋偐側傛偆偩丅
乽偁偺丄戝忎晇偱偡偐丠乿
丂僒儎僇偑怱攝偦偆側婄傪偟偰惡傪偐偗偨丅
乽偄丄偄傗丄孨偵偼暘偐傜側偄捝傒偩傠偆偐傜乧乧乿
丂抝偲偟偰偙傟傎偳抪偢偐偟偄奿岲偼側偄丅偱偒傟偽偦偭偲偟偰偍偄偰梸偟偐偭偨丅
乽傊偭丄偮偔偯偔娫敳偗側栰榊偩側偀丅栺懇捠傝丄偍慜偺擏傪怘傢偣偰傕傜偆偤乿
丂屢傪墴偝偊側偑傜鏛傞僫儐僞偺朤傜偵丄敄徫偄傪晜偐傋偨儚乕僂儖僼偺塭偑嬤偯偄偨丅
乽壌偺帺枬偺夊傪曅曽愜偭偨曬偄偩丅巆偭偨夊偱偍慜偺庱傪僇僢愗偭偰傗傞乿
丂僫儐僞丄愨懱愨柦偺戝僺儞僠両
丂儚乕僂儖僼偑夊傪攳偒弌偟偰僫儐僞偵廝偄偐偐傠偆偲偟偨傑偝偵偦偺帪丄儚乕僂儖僼偺栚偺慜偱愒偄偺墛偑朿傟忋偑偭偨丅
乽偖傢偭丄壗偩両丠乿
丂儚乕僂儖僼偼峇偰偰婄傪攚偗偨丅偟偐偟偦傟偱傕丄旹偑壗杮偑徟偘偰偟傑偭偰寵側廘偄傪敪偟偰偄傞丅傕偆彮偟摜傒崬傫偱偄偨傜丄姰慡偵婄柺偼娵從偗偵側偭偰偄偨偩傠偆丅
乽偼乣偼偭偼偭偼偭偼偭偼偭両乿
丂敄埫偄怷偺拞偵丄崅徫偄偩偗偑偙偩傑偡傞丅惡偺庡偺巔偼偳偙偵傕側偄丅
乽偦丄偦偺惡偼傑偝偐乿
丂暦偒妎偊偺偁傞偦偺惡偵丄僫儐僞偼僴僢偲婲偒忋偑偭偨丅
乽庣岇楈偲偟偰惗傑傟曄傢偭偰憗侾侽侽擭丅偙偺僆儗條偑偄傞尷傝丄僫儐僞偺堦懓偵晄岾偼朘傟側偄丅楈奅偺婱岞巕丄戝梔夦僫僀儞僥乕儖條嶲忋両乿
乽僫僀儞僥乕儖両乿丂
丂夛怱偺徫傒傪晜偐傋偨僫僀儞僥乕儖偑丄堄枴晄柧偵愒偄儅儞僩傪側傃偐偣丄僫儐僞偑曏傪棈傑偣偨戝栘偺巬偺忋偵忔偭偰偄偨偺偱偁傞丅
侾係
乽僫僀儞僥乕儖丄彆偗偰偔傟偰偁傝偑偲偆両丂傛偔偙偙偑暘偐偭偨偠傖側偄偐乿
丂僫儐僞偵偲偭偰丄僫僀儞僥乕儖偺巔偑偙傟傎偳傑偱偵棅傕偟偔丄偦偟偰怱偺掙偐傜奿岲椙偔巚偊偨偙偲偼偐偮偰側偐偭偨丅婌傃偵栚傪婸偐偣側偑傜丄僫儐僞偼椡堦攖僫僀儞僥乕儖偺柤傪嫨傫偩丅
乽傆傫丄僆儗條傪尒偔傃傞側丅僪僕偱丄娫敳偗偱丄偳乣乣乣乣乣乣偟傛乣傕側偄偍慜偺庣岇楈傪傗偭偰傗偭偰傞傫偩偧丅偍慜偺婋婡偲傕側傟偽偡偖偵嬱偗偮偗傞偖傜偄丄儕儞僑傪俆昩偱怘偆傛傝傕梕堈偄偙偲偩丅僆儗條偼偙傟偵曄恎偟偨偺偝乿
丂偦偆尵偭偰僫僀儞僥乕儖偑曄恎偟偨偺偼丄慡恎偑恀偭崟偺將偩偭偨丅偟偐偟晛捠偺將偱偼側偄丅嶰偮偺摢傪帩偪丄偦偺摰偼儖價乕偺傛偆偵峠偔岝傝丄岥偐傜偼僠儔僠儔偲墛傪擿偐偣偰偄傞丅嶰摢偺嫸將丄働儖儀儘僗偱偁傞丅
丂梔杺偱偁傞働儖儀儘僗偼丄偦偙傜偵偄傞將傛傝傕擻椡揑偵辍偐偵桪傟偰偄傞丅椺偊偽將偼恖娫傛傝傕嬃偔傎偳歬妎偑敪払偟偰偄傞偑丄働儖儀儘僗偺歬妎偼偦偺將傛傝傕峏偵桪傟偰偄傞偟丄媟椡傕怷偱嵟懍傪屩傞儚乕僂儖僼偵旵揋偡傞傕偺傪帩偭偰偄傞丅
乽働儖儀儘僗偺歬妎傪巊偊偽丄偙傫側恖婥偺側偄怷偺拞丄恖娫側傫偰偡偖偵尒偮偗傞偙偲偑弌棃傞偺偩丅傆傆偭丄傗偼傝僆儗條偭偰摢偑愗傟傞側偀乿
乽傫傫丠丂偡偖偵尒偮偗傞偙偲偑弌棃傞丠乿
丂彑庤偵帺暘偺擼枴慩傪帺夋帺巀偡傞僫僀儞僥乕儖偺尵梩傪暦偒側偑傜丄僫儐僞偺摢偵偼堦偮偺媈栤偑晜偐傫偱偄偨丅
乽懸偭偰傛丅偠傖偁巒傔偐傜働儖儀儘僗偵側偭偰偄傟偽丄偡偖偵僒儎僇払傪尒偮偗傜傟偰偄偨偭偰偙偲丠乿
乽傑偁丄偦偆側傞偐傕抦傟傫側乿
丂帺屓枮懌偺梋塁偵怹傝側偑傜丄嬨旜偺巔偵栠偭偨僫僀儞僥乕儖偑摎偊傞丅
乽偩偭偨傜崱傑偱偺嬯楯偼壗偩偭偨傫偩傛乣両乿
乽抦傞偐儃働両丂庪恖偵偟偰偔傟偲尵偭偰偒偨偺偼偦偭偪偺曽偩傠偆偑丅僆儗條偼偦傟傪暦偄偰傗偭偨偩偗偩丅偍慜偼働儖儀儘僗偺乽働乿偺帤傕尵偭偨偐丠丂傑偁偦傟偵婥晅偄偨僆儗條偲丄婥晅偐側偐偭偨偍慜偺嵎偼丄傗偼傝偙偙偺堘偄偩傠偆側偀乿
丂偲尵偭偰丄僫僀儞僥乕儖偼帺暘偺摢傪巜偝偟偨丅
乽偟偭偐偟偍慜傕憡曄傢傜偢僪僕偩側偀丅偦傫側儚乕僂儖僼偲僒儎僇傪尒娫堘偊傞側傫偰丅偦偺忋曏偼栘偺巬偵堷偭妡偗傞偼傢丄柍條偵屢楐偗傪傗傞偼傢乧乧丅変側偑傜丄壗偱偙傫側搝偺庣岇楈傪傗偭偰偄傞偺偐偲帺屓晄怣偵娮傝偦偆偩乿
乽偪傚偭偲懸偰乣両丂偳偆偟偰偦傫側偙偲傑偱抦偭偰傞傫偩傛丠乿
乽壗屘偐偭偰丠丂堿偐傜尒偰偨偐傜偵寛傑偭偰傞偩傠丅堄奜偲偡偖懁偵偍慜払偑偄偨偐傜側丅働儖儀儘僗偺慺憗偝傪帩偭偰偡傟偽丄偡偖偵拝偗傞偝乿
乽偩偭偨傜傕偭偲憗偔彆偗偰偔傟傛乣両丂偙偭偪偼婋偆偔怘傋傜傟偦偆偵側偭偨傫偩偧両乿
乽傆傫偭丅偍慜偼尵偭偨偱偼側偄偐丅僆儗條偼僋乕儖側擇枃栚偲丅庡恖岞偺婋婡傪媬偆僋乕儖側擇枃栚偼側丄僊儕僊儕偺僞僀儈儞僌偱彆偗傞偲憡応偑寛傑偭偰偄傞傕偺偩乿
乽偄傜傫偙偲傑偱庣傞側乣両乿
乽嬸偐側搝傔丅僊儕僊儕偺僞僀儈儞僌傪寁傞偺偑偳傟掱戝曄側偺偐暘偐偭偰偄傞偺偐丠丂抶偗傟偽庡恖岞傪嶦偟偰偟傑偆偙偲偵側傞偟丄憗偡偓偨傜偪偭偲傕奿岲椙偔側偄丅愨柇偺僞僀儈儞僌偱彆偗傪擖傟傞偺偑丄擇枃栚偺擇枃栚偨傞巊柦偩乿
乽偁偁乧乧丄堦弖偱傕僫僀儞僥乕儖偺偙偲偑棅傕偟偄偲巚偭偨帺暘偑攏幁偩乿
丂僫儐僞偼怱偺掙偐傜屻夨偟側偑傜丄摢傪書偊偨丅
丂偦傫側偙偲偼偍峔偄側偟偵丄僫僀儞僥乕儖偼巬偺忋偐傜僕儍儞僾偡傞偲丄僫儐僞偲儚乕僂儖僼偺娫偵拝抧偟偨丅偦偟偰儚乕僂儖僼傪價僔僢偭偲巜偝偟丄偙偆尵偄曻偮丅
乽傛偔暦偗擇棳梔杺丅偙傫側嶰棳庡恖岞傪憡庤偵壗傪儉僉偵側偭偰偄傞丅偦傟傛傝傕丄堦棳梔夦偺偙偺僆儗條偲嵟屻偺寛拝傪偮偗傛偆偱偼側偄偐丅偍慜偑晧偗偨傜丄偦偆偩側乧乧丄僆儗條偺偨傔偵摿忋偺擏偱傕梡堄偟傠丅偦偟偰傕偟僆儗條偑晧偗偨傜丄偦傟偼偁傝摼側偄偑丄偦偺帪偙偦偙偺娫敳偗傪怘偭偰傕椙偄丅傑偁怘偭偰傕偁傑傝巪偄偲偼巚偊傫偑側乿
乽偍偭丄偍偄丅彑庤偵寛傔側偄偱傛乿
丂偳偆峫偊偰傕僫僀儞僥乕儖偺尵梩偼棟晄恠偱偁傞偑丄僫儐僞偺尵梩偼僫僀儞僥乕儖偺塃帹偐傜嵍帹偵捠傝敳偗傞偩偗偩偭偨丅
乽偳偆偩丠丂崱搙偙偦恀寱彑晧偩丅僋儔僀儅僢僋僗偵憡墳偟偄嵟崅偺晳戜傪偙偺僆儗條偲乧乿
乽偝偭偒偐傜栿偺暘偐傜偹偉偙偲傪僊儍傾僊儍傾偸偐偟傗偑偭偰丅偄偒側傝墛偑弌偰偒偨棟桼偼傛偔暘偐傜偹偉偑丄崱搙偙偦偍慜傪怘偭偰傗傞両乿
丂僫僀儞僥乕儖偺僙儕僼偺搑拞偱偁偭偨偑丄儚乕僂儖僼偼僫僀儞僥乕儖偺墶傪傑傞偱娽拞偵側偄傛偆偵憱傝敳偗丄嵞傃僫儐僞偵廝偄偐偐偭偰偄偨丅
丂偦傟傕摉慠偱偁傞丅側偤側傜丄儚乕僂儖僼偵偼僫僀儞僥乕儖偺巔傕尒偊偢丄惡傕暦偙偊側偄偐傜偩丅偩偐傜撍慠僫儐僞偑栘偺忋偵岦偐偭偰挐傝偩偟偨偺傕丄嫲晐偱婥偑嫸偭偨偺偩偲儚乕僂儖僼偼巚偭偨偱偁傠偆丅
丂偩偑僫僀儞僥乕儖偼丄偦傫側偙偲偵偼彮偟傕婥晅偄偰偄側偄丅
乽偍丄偍偺傟擇棳梔杺傔丅傛偔傕丄傛偔傕僆儗條偺偙偲傪乧乧乿
丂搟傝偵擱偊傞僫僀儞僥乕儖偺摢偺忋偵丄恀偭愒側嫄戝側墛偑晜偐傃忋偑偭偰偄偭偨丅
丂堦曽僫儐僞偲儚乕僂儖僼偵栚傪岦偗傟偽丄崱傑偝偵儚乕僂儖僼偑僫儐僞偵廝偄偐偐傜傫偽偐傝偱偁偭偨丅偟偐傕僫儐僞偼丄傑偩愭掱偺屢楐偗偺捝傒偑廂傑偭偰偄側偄丅
乽偔偆偭乿
丂僫儐僞偼崱搙偙偦婄傪偟偐傔偨丅晲婍偵側傝偦偆側暔偼丄崱傗崢偵嵎偟偰偄傞僫僀僼偺傒丅偟偐偟偦偺僫僀僼傕丄錗傪敳偗傞嵺偵梩傪愗傝奐偒側偑傜恑傫偩偨傔丄恘偑儃儘儃儘偵側偭偰偄傞丅
丂崱偼柪偭偰偄傞壣偼側偄偲巚偄丄僫儐僞偼摢傪弖帪偵愗傝懼偊偨丅暿偵巊偄暔偵側傜側偔偰傕椙偄偺偩丅撍慠栚偺慜偵恘暔傪岦偗傜傟傟偽丄椺偊儃儘儃儘偵側偭偰偄偰傕埿奷偵偼側傞偼偢偱偁傞丅偨偩丄儚乕僂儖僼傪嫼偐偡偙偲偑弌棃偝偊偡傟偽傛偄丅
乽偩偁偭両乿
丂僫儐僞偼慺憗偔崢偐傜僫僀僼傪敳偒丄戝惡傪忋偘側偑傜儚乕僂儖僼偺栚偺慜偵偐偞偟偨丅
乽偆偍偭両乿
丂岠壥偼廫暘偩偭偨傛偆偩丅僫僀僼偵嬃偄偨儚乕僂儖僼偼僶儔儞僗傪曵偟丄惃偄梋偭偰慜偵偮傫偺傔傞傛偆側奿岲偵側偭偨丅
丂乽傗偭偨偧両乿偲怱偺拞偱娊婌偺惡傪偁偘丄僫儐僞偼廃埻偵栚傪岦偗偨丅恘偺寚偗偨僫僀僼偼丄強慒嫼偟掱搙偵偟偐岠壥偼側偄丅怴偨偵晲婍偵側傝偦偆側暔傪扵偝側偔偰偼側傜側偐偭偨丅
丂偩偑偦偺捈屻偩偭偨丅
乽傛偔傕乧乧丄傛偔傕僆儗條偺偙偲傪柍帇偟偨側乣両乿
丂僫僀儞僥乕儖偑丄搟傝偺尵梩偲嫟偵婼壩傪曻偭偨偺偩丅
丂偟偐偟婼壩傪曻偨傟偨憡庤丄偮傑傝儚乕僂儖僼偼懱惃傪曵偟偰偄傞丅婼壩偼嬐偐偵儚乕僂儖僼偺摢傪偐偡傔偨偩偗偱丄斵偺慜偵棫偭偰偨晄岾側抝偵岦偐偭偰偄偨丅
乽偆傢偁両乿
丂僫儐僞偼悽奅怴婰榐媺偵栚嬍傪旘傃弌偝偣丄壗屘偐帺暘偺曽偵岦偐偭偰偒偨婼壩偵嬄揤偟偨丅丂
乮偳丄偳偆偵偐偟側偔偪傖乯丂
丂峫偊傞僫儐僞偼丄婏愓揑偵懌壓偵揮偑偭偰偄偨悈摏傪尒偮偗偨丅僄僨傿儞偑儚乕僂儖僼偵墸傜傟偨偲偒偵丄帩偭偰偄偨儕儏僢僋僒僢僋偺拞偐傜曎摉饽側偳偲堦弿偵傑偒嶶傜偣偨暔偩丅拞偵偼僒儎僇偑娫堘偊偰庰傪擖傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞偑丄拫怘傪怘傋偰偄傞偲偒偵僫僀儞僥乕儖偑偦傟傪堸傫偱偟傑偄丄僫儐僞偼僸僪僀栚偵憳傢偝傟偨丅
丂偙傟傪巊偊偽婼壩偑杔傪傛偗傞偐傕抦傟側偄丅僫儐僞偼偦偆峫偊丄慺憗偔悈摏傪廍偄忋偘偰婼壩偵岦偗偰拞恎傪傇偪傑偗偨丅
丂悈傪巊偭偰壩傪徚偡側傜傑偩偟傕丄惗偒暔偱傕側偄婼壩偑丄悈偵晐偑傞偩傠偆偲偄偆敪憐偼偁傑傝偵傕妸宮偱偁傞丅
丂偑丄僫儐僞偺峴摦偼偁側偑偪娫堘偭偰傕偄側偐偭偨丅側偤側傜丄杮摉偵婼壩偼惗偒偰偄偨偺偱偁傞丅
乽偍偍偭偲両乿
丂婼壩偼悈乮偙偺応崌偼庰偩偑乯傪偐傢偡傛偆偵偟偰戝偒偔捑傒崬傒丄嵞傃晜偒忋偑偭偰僫儐僞偵岦偐偭偰偄偨丅憂傝弌偟偨梔夦偵帡偰偐丄惈奿傕傂偹偔傟偰偄傞丅
乽偰傗傫偱偉丅婋偹偉偠傖偹偊偐丄偙偺僗僢僩僐僪僢僐僀両乿
乽側傫偩傛偙偺婼壩偼乣乿
丂偳偆峫偊偰傕柍拑嬯拑側婼壩傪憡庤偵丄傕偼傗傛偗傞偟偐側偄丅僫儐僞偼崢傪孅傔偰摢傪婽偺傛偆偵堷偭崬傔丄惗偗傞婼壩偼偦偺忋傪捠夁偟偰偄偭偨丅
丂偩偑偦偙傊丄崱搙偼僶儔儞僗傪曵偟偨儚乕僂儖僼偑撍偭崬傫偱棃偨丅壗傪傗偭偰傕忬嫷偑岲揮偟側偄丄嵭擄側抝偱偁傞丅
丂挌搙擇恖偱摢撍偒傪傗傝崌偆奿岲偲側傝丄偝傜偵儚乕僂儖僼偺惃偄傕壛傢偭偰丄僑僣僢偲偄偆撦偄壒偑嬁偄偨丅
丂嬻暊偱摢偑濶濷偲偟巒傔偰偄傞偲偒偵丄嫮楏側摢撍偒偼僣儔僀丅偝偟傕偺儚乕僂儖僼傕僶僞僢偲抧柺偵搢傟丄摦偐側偔側偭偰偟傑偭偨丅
乽偄偰偰偰偰乧乧乿
丂偟偐偟丄偄偮傕懱傪挘偭偰偄傞僫儐僞偼懪偨傟嫮偄丅栚怟偵椳傪晜偐偽偣側偑傜傕丄婼壩偺峴曽傪扵傞丅
丂婄傪偟偐傔偰尒偮傔傞愭偱丄婼壩偼峏偵僫儐僞偺攚屻偵偁偭偨戝栘偺墶傪捠傝敳偗丄偦偺屻傠偵偁偭偨庽楊壗昐擭偲巚偊傞嫄栘偵撍偭崬傫偱偄偨丅丂
乽傂傖乣偼偭偼偭偼丄婼壩條偺偍捠傝偱偄両丂擱偊傠擱偊傠乣両乿
丂婼壩偑撍偭崬傫偱偄偭偨弖娫丄崒壒偲嫟偵嫄栘偼峠楡偺壩拰偵曪傑傟偨丅偝傜偵傕偺偡偛偄敋晽偑峀偑傝丄曈傝偺栘乆偑栘偺梩傪晳傢偣側偑傜僓儚僓儚偲梙傟傞丅
丂墛偵曪傑傟偨嫄栘偼丄傑偝偟偔乽壩拰偺庽乿偱偁傞丅怺偄棔怓乮偁偄偄傠乯傪懷傃偰偒偨嬻傪攚宨偵丄尒忋偘傞傎偳攚偺崅偄庽偑墛偵曪傑傟偰偄傞丅偁傞堄枴丄寍弍揑偲傕尵偊傞岝宨偩丅
丂偦偟偰堦弖偟偰嫄栘傪扽偵曄偊偰丄墛偼偐偒徚偡傛偆偵徚偊偰偟傑偭偨丅
乽乧乧乧乿
丂僫儐僞偼岥傪戝偒偔奐偗側偑傜丄洎慠偲偦傟傪尒偮傔偰偄偨丅惓捈丄僔儍儗偵側傜側偄攋夡椡偱偁傞丅
乽側丄側丄側丄側傫偰偙偲偡傞傫偩乣両丂杔偵摉偨偭偰偄偨傜丄妋幚偵崪偡傜巆偭偰側偐偭偨偧両乿
丂僫儐僞偼僫僀儞僥乕儖偵岦偗偰巚偄偭偒傝搟傝傪傇偪傑偗偨丅
乽僆儗條偺偙偲傪柍帇偡傞偺偑埆偄傫偩傠偆偑両乿
乽柍帇偟偨偺偼杔偠傖側偄丄儚乕僂儖僼偺曽偩傠両乿
乽抦傞偐両丂偣偭偐偔偺尒偣応傪傇偪夡偟傗偑偭偰両丂偁傟偐傜僆儗條偺奿岲偄偄僙儕僼偑懕偔偲偙傠偩偭偨傫偩偧両乿
乽偦傟偺偳偙偑亀楈奅偺婱岞巕亁側偺偝両丂偦傫側僟僒僀栄旂側傫偐偟偪傖偭偰偝両丂偦傟偵壗偑亀偙偺僆儗條偑偄傞尷傝晄岾偼朘傟側偄亁偩傛両丂偐偊偭偰嬯楯偑憹偊傞偽偐傝偠傖側偄偐両丂乿
丂僫儐僞偼偄傑偩偵丄僫僀儞僥乕儖偑尵偆偲偙傠偺僫僀儞僥乕儖丒僽儔僂儞乮偮傑傝僫僀儞僥乕儖偺栄旂偺怓乯偑棳峴偡傞偲偼丄儈僕儞僐偺椳傎偳傕巚偭偰偼偄側偐偭偨丅
丂偦偟偰丄妋偐偵僫僀儞僥乕儖偑偄偰偔傟偰椙偐偭偨偲偼巚偭偰偄傞丅偦偺曄恎擻椡偑側偗傟偽僔儍僪僂傕曔傑偊傜傟側偐偭偨偩傠偆偟丄崱傕偙偆偟偰僒儎僇傪尒偮偗傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偱偁傠偆丅偩偑丄偦傟埲忋偵婥嬯楯偑憹偊偨偺傕傑偨帠幚側偺偩丅
乽側偵偂丠乿
丂暦偒幪偰側傜側偄尵梩偩偭偨偺偐丄僫僀儞僥乕儖偼帹傪僺僋儕偲摦偐偟偰惡傪掅偔偟偨丅偦偟偰僫僀儞僥乕儖偼傕偺偡偛偄惃偄偱僫儐僞偺榚傪憱傝偡偓傞偲丄攚屻偺戝栘傪搊傝巒傔偰懢偄巬偺忋偵忔偭偐傞丅
乽暦偗偂丄偙偺巐棳庡恖岞両乿
丂妋偐偵僫僀儞僥乕儖偼攚偑掅偄暘丄壓偐傜偩偲偄傑偄偪埿埑姶偵寚偗偰偟傑偆丅偦傟偱栘偺忋偵搊偭偨偺偱偁傠偆丅偐偮偰柍偄傎偳偺搟傝偺宍憡偱丄僫僀儞僥乕儖偼懕偗傞丅
乽僆儗條偵偼寵偄側尵梩偑偄偔偮偐偁傞両丂偦偺堦偮偑丄乫僟僒僀乫偩両丂偄偮傕僪僕偱娫敳偗側屲棳庡恖岞偺偍慜偵丄乫僟僒僀乫側偳偲尵傢傟傞妎偊偼側偄両丂偦偟偰榋棳庡恖岞偵丄帺枬偺栄旂傪偲傗偐偔尵傢傟傞嬝崌偄傕側偄両丂僼傽僢僔儑儞姶妎側偳傑傞偱側偄幍棳庡恖岞偵丄偄偭偨偄壗偑暘偐傞傫偩両丂偦傕偦傕僫僀儞僥乕儖丒僽儔僂儞偑棳峴傜側偄偺偼丄偍慜偑奿岲椙偔妶桇偟側偄偐傜偱側偄偐丄偙偺敧棳庡恖岞傔両乿
丂偳偆傗傜乫僟僒僀乫偲尵傢傟偨偙偲偑憡摉摢偵棃偰偄傞傛偆偱偁傞丅偙偺挷巕偩偲丄屻敿偺嬯楯偑憹偊偨偲偄偆尵梩偼帹偵傕擖偭偰偄側偄偺偱偁傠偆丅
丂僫儐僞偼乽偼偀乣乿偲廳嬯偟偄偨傔懅傪偮偄偨丅傗偼傝偙偺梔夦偲晅偒崌偭偰偄傞偲丄婥嬯楯偑愨偊側偄丅
乽偩偄偨偄嬨棳庡恖岞偺偍慜偵偼乧乿
丂偲丄僫儐僞偺奿偑嬨棳偵傑偱棊偪偨偲偙傠偱丄僫僀儞僥乕儖偺尵梩偑搑愨偊偨丅壗偐偵婥晅偄偨偺偐丄帇慄偺愭傪塃庤偺曽偵偁偭偨栘偺姴偺曽偵岦偗傞丅
丂偡傞偲丄僫僀儞僥乕儖偺恓偺傛偆偵嵶偄栚偑彊乆偵尒奐偄偰偄偒丄妟偵偼堦偮擇偮偲帀娋偑晜偐傫偱偄偭偨丅
丂姴偵偼丄嫄戝側僯僔僉僿價偑棈傒偮偄偰偄偨偺偱偁傞丅愭掱僒儎僇偺栚偺慜偵尰傟偨丄妼怓偺抧偵愒妼怓偺栦傪帩偮僯僔僉僿價偱偁傞丅
乽傊丄傊丄傊丄幹乧乧乿
丂僫僀儞僥乕儖偼巐杮偺媟傪僈僋僈僋偲怳傞傢偣側偑傜丄栚傪僐僀儞偺傛偆偵傑傫娵偵偟偰丄戝幹傪尒偮傔偨丅偝傜偵偦偺戝幹偑丄懢偄巬傪揱偭偰僰儖僰儖偲僫僀儞僥乕儖偺曽偵嬤偯偄偰偄偔丅
乽傛丄傛丄婑傞側棃傞側嬤偯偔側怗傞側偔偭偮偔側偁偭偪峴偗僐僲儎儘乕両乿丂
丂僫僀儞僥乕儖偺昁巰偺尵梩傕嫊偟偔丄戝幹偼偳傫偳傫偲僫僀儞僥乕儖偵嬤偯偄偰偄偔丅
乽偼偼偼偭丄壗傪嬃偄偰傞傫偩傛丅幹偵梔夦偺僫僀儞僥乕儖偼尒偊傞傢偗側偄偠傖側偄偐乿
丂僫僀儞僥乕儖偺偁傑傝偺嫰偊傇傝偵丄僫儐僞偼暊傪書偊偰徫偭偨丅
乽傎傜丄偦偄偮偺摢偺屻傠偵敀偄斄揰偑嶰偮暲傫偱偄傞偩傠丅偩偐傜暿柤僆儕僆儞偭偰屇偽傟偰偄傞傫偩傛丅偪傚偆偳僆儕僆儞嵗偺俁僣惎傒偨偄偩偐傜偹乿
乽僆丄僆儕僆儞偩偐僆僯僆儞僌儔僞儞僗乕僾偩偐抦偭偨偙偲偐丄儃働両乿
丂價僋價僋偲恔偊偰偄傞巔偱偼丄偨偩偺嫊惃傪挘偭偰偄傞偵偟偐尒偊側偄丅
丂戝幹偼峏偵僫僀儞僥乕儖偵嬤偯偔偲丄偵傘偆偭偲摢傪婲偙偟丄懥塼偺巺傪堷偐偣側偑傜備偭偔傝偲岥傪奐偄偨丅偦偟偰儐儔儐儔偲摢傪摦偐偟偰慱偄傪掕傔傞丅
丂偦偟偰師偺檵撨丄僼僢偲戝幹偺塭偑徚偊偨丅
丂僫僀儞僥乕儖偑斶柭傪忋偘傞壣傕側偔丄戝幹偼僫僀儞僥乕儖偺摢偺忋偡傟偡傟傪捠傝敳偗偰偄偒丄僈僒僢偲屻傠偱壒傪棫偰偨丅偦偺傑傑戝幹偼備偭偔傝偲摢傪栠偟偰偄偒丄僶儕僶儕偲岥偺拞傪摦偐偡丅崺拵偱傕曔傑偊偨偺偱偁傠偆丅
丂偦偺壓偱丄僫僀儞僥乕儖偼敀栚傪攳偄偨傑傑攳惢偺傛偆偵屌傑偭偰偄偨丅嫲傜偔偦偺栚偺慜偵岲暔偺儕儞僑偑弌偝傟偰傕丄挻崅媺怘嵽傪巊偭偨崑壺椏棟傪暲傋傜傟偰傕丄摦偔偙偲偼側偄偩傠偆丅
丂戝幹偼岥偺拞偺崺拵傪堦婥偵堸傒崬傓丅嵟屻偵僠儘儕偲愒偄愩傪弌偟丄偦偺傑傑壗傕側偐偭偨偐偺傛偆偵僘儖僘儖偲恎懱傪姴偺曽偵攪傢偣偰偄偭偨丅
丂峝捈偟偨僫僀儞僥乕儖偺慜傪丄戝幹偺挿偄恎懱偑栠偭偰偄偔丅傗偑偰嵟屻偺怟旜偑僫僀儞僥乕儖偺恎懱傪抏偒丄僫僀儞僥乕儖偼巬偺忋偐傜棊壓偟偰偄偭偨丅
乽傆偅乣乿
丂惷偗偝偺栠偭偨怷偺拞偵丄僫儐僞偺抁偄偨傔懅偑楻傟傞丅
丂僫僀儞僥乕儖偑婥傪幐偭偰埨揼偡傞偺傕偍偐偟側榖偟偱偁傞偑丄僫儐僞偵偼偦傫側旀楯姶偑偁偭偨丅
丂偲傕偁傟丄僒儎僇払傪尒偮偗傞偙偲傕偱偒偨偟丄傗偭偐偄側儚乕僂儖僼傕崱偼婥傪幐偭偰偄傞丅屻偼僒儎僇払傪怷偺奜傑偱憲傝撏偗傞偩偗偩丅
乽孨偑僒儎僇偪傖傫偩偹丠乿
丂僫儐僞偼僒儎僇偺曽偵怳傝曉傝惡傪偐偗偨丅僒儎僇偼乽偼丄偼偄乿偲岥偛傕傝側偑傜僐僋儕偲桴偔丅
乽怷偺拞偱僫儐僞偲偄偆彮擭偵夛偭偰偹丄斵偵棅傑傟偰孨偲僄僨傿儞孨傪憑偟偵棃偨傫偩乿
乽僫儐僞偵両丠乿
丂僫儐僞偲偄偆尵梩傪暦偄偨弖娫丄偦傟傑偱嫊傠偘偩偭偨僒儎僇偺昞忣偑僷僢偲柧傞偔側偭偨丅
丂柍棟傕側偄偩傠丅偦傟傑偱偵丄栚偺慜偵偄偒側傝戝幹偑尰傟丄偝傜偵儚乕僂儖僼偵廝傢傟偦偆偵側偭偨偲巚偭偨傜丄崱搙偼撍慠尒抦傜偸抝偑弌偰偒偨偺偩偐傜丅
丂偦偺屻偼嫲傜偔斵彈偺棟夝傪挻偊偰偄偨偩傠偆丅壗傕偄側偄嫊嬻偵岦偐偭偰抝偑挐傝巒傔傞傢丄撍慠戝栘偑墛傪悂偒忋偘偨偺偩偐傜丅偦偺偡傋偰偵崅旘幵側屜偺梔夦偑娭傢偭偰偄傞側偳丄僒儎僇偼抦傞桼傕側偄丅
丂僫儐僞偼偦傫側斵彈偵桪偟偔旝徫傒偐偗丄埨怱偝偣傞傛偆偵尐偵庤傪抲偙偆偲偟偨丅偦偙偵偼塃係俆搙偺妏搙偑偳偆偺偙偆偺偲偐偄偆傾儂傜偟偄偙偩傢傝偼丄傕偼傗柍偄丅
乽偄偒側傝偱嬃偐偣偰偟傑偭偨偐傕抦傟側偄偗偳丄傕偆戝忎晇偩傛丅怷偺奜偱僫儐僞孨偑懸偭偰偄傞丅杔偑昁偢孨偲僄僨傿儞孨傪斵偺偲偙傠偵楢傟偰偄偭偰偁偘傞傛乿
乽偼偭丄偦偆偄偊偽僄僨傿儞両乿
丂僄僨傿儞偺柤慜傪暦偄偰丄僒儎僇偼峇偰偰戝栘偺姴偺嬤偔偵搢傟偰偄傞僄僨傿儞偵嬱偗婑偭偨丅偪傚偆偳儚乕僂儖僼偵墸傜傟偨僄僨傿儞偺條巕傪尒偵峴偙偆偲偟偨偲偒偵丄儚乕僂儖僼偵懌傪偐偗傜傟偰揮傫偱偟傑偄丄偦偺帪偵僫儐僞偑尰傟偨偺偩丅
乽乧乧乧乿
丂僫儐僞偼柍尵偺傑傑丄峴偒応傪幐偭偨塃庤傪拡偵昚傢偣傞丅
乽僄僨傿儞丠乿
丂僒儎僇偼偆偮暁偣偵搢傟偰偄傞僄僨傿儞偵惡傪偐偗丄嬄岦偗偵婲偙偟偰傒偨丅僄僨傿儞偺婄偼丄墸傜傟偨塃偺杍偑愒偔庮傟忋偑偭偰偍傝丄怬傕敄偔愗偭偰偄傞丅
乽僄僨傿儞孨偼戝忎晇偐偄丠乿
丂僒儎僇偺攚拞偐傜僫儐僞偑惡傪偐偗偨丅
乽偊偊丄婥傪幐偭偰偄傞偩偗傒偨偄偱偡乿
丂栚尦傪柧傞偔抏傑偣側偑傜丄僒儎僇偼怳傝曉偭偨丅彮偟條巕尒傪尒偨偩偗偱暘偐偭偰偟傑偆偲偙傠偑丄僒儎僇偺偡偛偝偩丅傛偔婥愨偡傞晄塣側抝偑懁偵偄傞偩偗偁偭偰丄僒儎僇偼宱尡朙晉偱偁傞丅丂
丂僒儎僇偼億働僢僩偐傜僴儞僇僠傪庢傝偩偟偰僄僨傿儞偺怬偵燌傫偩寣傪怈偄丄懁偵嶶傜偽偭偰偄傞僄僨傿儞偺娺嬶傪斵偺儕儏僢僋僒僢僋偵媗傔巒傔偨丅
丂巄偔偟偰偦偺庤偑丄傆偲巭傑傞丅
乽僄僨傿儞孨傕柍帠偩偭偨偙偲偩偟丄偡傋偰廔傢偭偨側乧乧乿
丂庤傪崢偵摉偰側偑傜丄僫儐僞偼嬻偵岦偐偭偰欔偄偨丅惣偺嬻偵婸偔彧偺柧惎傪尒偮傔側偑傜丄崱傑偱偺嬯楯偑慼偭偰偔傞丅
乽偄偊丄傑偩廔傢偭偰傑偣傫傛乿
丂偲丄嬯楯傪姎傒偟傔傞僫儐僞偺帹偵僒儎僇偺惡偑擖偭偰偒偨丅
乽偊偭丄偳偆偄偆偙偲偩偄丠乿
乽儚乕僂儖僼傪彆偗偰偁偘側偄偲乿
丂僫儐僞偵攚傪岦偗偨傑傑丄僒儎僇偼僗僋僢偲棫偪忋偑傞丅
乽儚乕僂儖僼傪彆偗傞偩偭偰両丠乿
丂僫儐僞偑変偑帹傪媈偄側傜嫨傫偩丅
乽孨偨偪偼偁偄偮偵怘傋傟偦偆偵側偭偨傫偩偧乿
乽偦傟偼偍暊偑尭偭偰偒偨偐傜偱偡丅偁偺恖丄偁偺傑傑偩偭偨傜杮摉偵巰傫偱偟傑偄偦偆偠傖側偄偱偡偐乿
乽偦傟偼巇曽側偄傫偩傛丅怷偺拞偠傖丄妉暔偵偁傝偮偗側偄幰偼巰傫偱偄偔丅偦傟偑栰惗偺潀偝丅怘偆偐丄怘傢傟傞偐側傫偩乿
乽乧乧偡偄傑偣傫丄曻偭偰偍偗側偄傫偱偡傛丅偍恖岲偟偡偓傞偺偐傕抦傟側偄偱偡偗偳偹丄傆傆偭乿
丂嬯徫偄傪晜偐傋偨偺偐丄僒儎僇偺億僯乕僥乕儖偑彫偝偔梙傟偨丅
乽偦傟偵丄偪傖傫偲峫偊傕偁傝傑偡偐傜乿
丂怳傝曉偭偨僒儎僇偼丄堦偮偺饽傪書偊偰偄偨丅
侾俆
丂恀偭敀偄悽奅傪昚偭偰偄偨丅丂忋傕丄壓傕丄塃傕嵍傕側偄丅
丂姶偠傜傟傞偺偼丄暊偺掙偐傜暒偄偰偔傞嬻暊姶偲丄傂偳偄摢捝偩偗偩偭偨丅
乮壌偼偙偺傑傑巰偸偺偐丠乯
丂帺暘偺惡偑偁偨傝偵嬁偒丄傑偨婣偭偰偔傞丅
乮偙偺傑傑暊傪嬻偐偟偰巰偸傫偩側丄壌偼乧乧乯
丂怷偺僴儞僞乕偲屇偽傟偨帺暘偑丄側傫偲柍條側巰偵曽偱偁傠偆偐丅偦傟傕丄偝偭偒傑偱栚偺慜偵偼妉暔偑偄偨偲偄偆偺偵丅
丂嬻暊偱峴偒搢傟偨偲偄偆摨懓偺榖傪暦偄偨偲偒丄斵偼偦傫側拠娫偺偙偲傪徫偄旘偽偟偨偑丄崱偼偦傫側帺暘偑傂偳偔嬸偐偵巚偊偨丅
乮壗偑怷偺僴儞僞乕偩丄傑偭偨偔傛偋乧乧乯
丂斵偼帺殅婥枴偵徫偭偨丅強慒偼恖娫偑彑庤偵晅偗偨柤偩丅偦傫側柤慜傪屩傝偵巚偭偰偄偨崱傑偱偺帺暘偵丄暊偑棫偮丅僴儞僞乕偲偄偊偳傕丄偦偺擔偺妉暔偵柦傪寽偗偰偄傞丅妉暔傪曔傜偊傜傟側偗傟偽丄崱偺帺暘偺傛偆偵巰傫偱偄偔偩偗偩丅
乮擏偑怘偄偰偉乧乧乯
丂岥偺拞偑幖偭偰偄偔偺偑姶偠傜傟偨丅巰偵備偔嵟屻偺婅偄偑怘傋暔偺偙偲偩偲巚偆偲変側偑傜忣偗側偔側傞偑丄偒偭偲偦傫側傕偺側偺偱偁傠偆丅崱嵺偺嵺偵崅彯側婅偄傪弌棃傞幰側偳丄偄傞偼偢偼側偄丅
丂偦傫側偙偲傪峫偊偰偄傞偲丄岥偺拞偵擏偺枴偑峀偑偭偰偄偭偨丅
丂尪妎傪姶偠巒傔偨偺偩偐傜丄偄傛偄傛側偺偩傠偆丅斵偼妎屽傪寛傔偨偑丄岥偺拞偵偼妋偐側帟偛偨偊偑姶偠傜傟傞丅偙傫側偼偭偒傝偲偟偨尪妎偑偁傞偺偩傠偆偐丅
丂斵偼傕偆堦搙偟偭偐傝偲丄岥偺拞偺暔傪姎傒偟傔偰傒偨丅偦偺弖娫丄僷僢偲岥偺拞偵擏偺枴偑峀偑偭偰偄偔丅
乽偭両両乿
丂斵偼嵞傃尰幚偺悽奅偵栠偭偰偄偭偨丅
丂傏傗偗偨帇奅偺岦偙偆偐傜丄堦恖偺彮彈偺巔偑晜偐傃忋偑偭偰偔傞丅偦傟偼丄斵偑捛偄偐偗偰偄偨娽嬀傪偐偗偨億僯乕僥乕儖偺彮彈偩偭偨丅丂
乽偁偺丄偍岥偵崌偄傑偟偨丠乿
丂晄埨偘偵僒儎僇偑恥偹偰偒偨丅偦傫側僒儎僇傪丄儚乕僂儖僼偼垹慠偲偟側偑傜尒偮傔偰偄傞丅
乽偍拫偺偍曎摉偑彮偟梋偭偰偄偨傫偱偡丅偙傟偩偗偠傖偁懌傝側偄偱偟傚偆偗偳丄傕偟椙偐偭偨傜怘傋偰壓偝偄乿
丂僒儎僇偼曎摉饽傪峀偘偰偄傞丅偦偺拞偵偼丄僠僉儞偺搨梘偘偄偔偮偐巆偭偰偄偨丅
丂儚乕僂儖僼偺堦弖巚峫偑巭傑偭偨丅壗偑側傫偩偐暘偐傜側偄丅僒儎僇偲曎摉饽偺拞偺搨梘偘傪岎屳偵尒偮傔側偑傜丄儚乕僂儖僼偼屗榝偭偰偄偨丅
乽搨梘偘側傫偰怘傋側偄偱偡偐偹丠丂巹偨偪偼惗偺偍擏側傫偰怘傋側偄偺偱丅偱傕搨梘偘傕旤枴偟偄偱偡傛乿
丂偦偆偄偭偰僒儎僇偼丄僠僉儞偺搨梘偘傪儚乕僂儖僼偺旲愭偵嬤偯偗偨丅偄偐偵傕怘梸傪偦偦傝偦偆側崄傝偑丄儚乕僂儖僼偺旲傪巋寖偟丄偙偙悢擔暊偺拞偵憙偔偭偰偄偨嬻暊偺拵傪堦婥偵憶偑偣偨丅
乽偔丄偔傟両乿丂
丂儚乕僂儖僼偼扗偄庢傞傛偆側惃偄偱曎摉饽傪庤偵偡傞偲丄僠僉儞偺搨梘偘傪榟捦傒偵偟偰丄岥偺拞偵杍挘偭偨丅偦偺弖娫丄庒寋偺擏廯偲丄崄恏椏偺崄傝偑岥偺拞偵峀偑傞丅
丂崱傑偱怘傋偨偳偺擏傛傝傕旤枴偟偐偭偨丅椻傔偰傕旤枴偟偝傪懝側傢側偄偺偑丄僒儎僇偺曎摉偺恄悜偱偁傞丅
丂変傪朰傟偰搨梘偘傪偑偭偮偔儚乕僂儖僼傪丄僒儎僇偼枮懌偘偵旝徫傫偱尒偮傔傞丅
乽傆偅乣乿
丂嬐偐偵巆偭偨搨梘偘傪傾僢偲尵偆娫偵暯傜偘丄儚乕僂儖僼偼怺偄偨傔懅傪偮偄偨丅偦偟偰儚乕僂儖僼偼丄偦偺傑傑偛傠傝偲抧柺偵戝偺帤偵側傝丄椉栚偺忋偵塃榬傪忔偣傞丅
乽抺惗乧乧乿丂
丂儚乕僂儖僼偺惡偼嬐偐偵恔偊偰偄偨丅塀偟偨椉栚偺榚偐傜丄岝傞暔偑揌偭偰偄偔丅
乽壗偱乧乧丄壗偱偙傫側偵巪偄傫偩傛乿
丂寛偟偰嬻暊偑枮偨偝傟偨傢偗偱偼側偐偭偨偑丄傕傗偼斵摍傪廝偭偰怘傋傛偆側偳偲偄偆婥偼姰慡偵幐偣偰偄偨丅偦傟傎偳傑偱偵丄僒儎僇偺曎摉偼儚乕僂儖僼偺怱偵嬁偄偨偺偱偁傞丅
丂僒儎僇偼曎摉饽偺奧傪暵傔偰鉟楉偵曪傒捈偡偲丄儚乕僂儖僼偵攚傪岦偗偰棧傟偰偄偭偨丅偦偟偰偦偺僒儎僇傪丄僫儐僞偑寎偊傞丅
乽椙偐偭偨側乿
乽偊偊丄旤枴偟偄偲尵偭偰栣偊偰乿丂
丂帺暘偺椏棟傪怘傋偰婌傫偱偔傟傞側傜丄偦傟偑堦斣婐偟偄丅僫儐僞偼偦傫側尵梩傪僒儎僇偐傜暦偄偨偙偲偑偁偭偨丅
乽杮摉偵椙偐偭偨偱偡丄壗傕偐傕乧乧乿
丂偦偺帪丄僒儎僇偑恎懱傪僼儔儕偲僶儔儞僗傪曵偟偨丅僫儐僞偑峇偰偰嬱偗婑偭偰丄僒儎僇偺恎懱傪惓柺偐傜庴偗巭傔傞丅
乽偡偄傑偣傫丅側傫偩偐巹傕丄旀傟偪傖偭偨乧乧傒偨偄偱偡乿
丂僫儐僞偺嫻偺拞偱丄僒儎僇偼忋栚尛偄偵旀楯姶傪堦攖偵棴傔偨婄傪僫儐僞偵岦偗偨丅
乽杮摉偵丄巹偨偪偺偙偲傪憑偟偵棃偰偔傟偰偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅偱傕偪傚偭偲偍偭偪傚偙偪傖偄側庪恖偝傫傪尒偰偄傞偲丄側傫偩偐僫儐僞傪尒偰偄傞傛偆偱乧乧乿
乽偊偭丠乿
乽僫儐僞傕丄偄偮傕僪僕偱偍偭偪傚偙偪傚偄側傫偱偡丅偩偐傜曻偭偰偍偗側偔偰丄懁偵偄偰偁偘偨偄偺偱偡偗偳丅偱傕丄幐攕偡傞偙偲傪婥偵偡傞偙偲側偔丄偄偮傕慜岦偒偱丅傕偟偐偟偨傜丄僫儐僞偑彆偗偵棃偰偔傟傞偐傕抦傟側偄偭偰巚偭偰偄偨傫偱偡丅搑拞偱怷偱柪偭偨傝丄夦暔偵捛偄偐偗傜傟傞偐傕抦傟側偄偱偡偗偳偹丅僫儐僞偭偰偦傫側抝偺巕側偺偱乿
丂僒儎僇偑嬐偐偵旝徫傓丅
乽僫儐僞偵夛偭偨傜幱偭偰偍偄偰壓偝偄丅怱攝偐偗偰偛傔傫偹偭偰丅偦偟偰丄愭偵媥傫偱偛傔傫乧乧偭偰乿
丂偦偺傑傑僒儎僇偼丄備偭偔傝偲栚傪暵偠偰怮懅傪棫偰巒傔偨丅
乽乧乧僒儎僇丄傕偆備偭偔傝媥傫偱暯婥偩傛丅屻偼杔偑偪傖傫偲壠傑偱憲偭偰偁偘傞偐傜偹乿
丂壐傗偐側僒儎僇偺怮婄傪尒偮傔側偑傜丄惷偐側偲偒偼夁偓偰偄偭偨乧乧丅
乽偁乣傗傟傗傟丅僸僪僀栚偵偁偭偨側丄傑偭偨偔乿
丂庺敍偐傜夝曻偝傟偨僫僀儞僥乕儖偑偺偦偺偦偲弌偰偒偨丄摢偺忋偺戝偒側僞儞僐僽偑捝乆偟偄丅
乽偍偭丄僫僀儞僥乕儖丅傛偆傗偔偍栚妎傔偐偄丠丂偝偭偒偼悽婭偺尒暔偩偭偨側乣丅偄偮傕偼埿挘傝嶶傜偟偰偄傞僫僀儞僥乕儖偑丄幹傪尒偰幐恄偡傞側傫偰偝乿
乽偍丄偍慜乣両乿
乽偼偼偭丅忕択偩傛丄偠傚乣偩傫丅偦傫側偵偡偖偵栚偔偠傜傪棫偰傞側傛丅扤偵傕尵傢側偐傜偝乿
乽傆傫偭丄塕偮偄偨傜撆恓傪堦愮枩杮堸傑偣傞偐傜側乿
丂僫儐僞偵偟偐僫僀儞僥乕儖偼尒偊側偄偲偄偆偺偵丄偄偭偨偄扤偵僶儔偡偲偄偆偺偩傠偆偐丅憡曄傢傜偢偺偍偲傏偗僐儞價偱偁傞丅
乽偝偰丄憗偔壠偵婣傜側偄偲僒儎僇偺偍偽偝傫傕怱攝偡傞傛偹丅杺朄巊偄偵偱傕曄恎偟偰堦婥偵婣傠偆偐丄僫僀儞僥乕儖丠丂偪傚偆偳僒儎僇傕僄僨傿儞傕怮偪傖偭偰傞偟乿
乽傆偭丄僆儗條偵椙偄峫偊偑偁傞乿丂
丂尵偆偑憗偔丄僫僀儞僥乕儖偼曄恎傪巒傔偰偄偨丅僫僀儞僥乕儖偺恎懱偑丄敀偄墝偵曪傑傟傞丅丂
丂偦偺墝偺墱偐傜尰傟偨偺偼丄傑傞偱愥偺傛偆偵敀偄栄墣傪帩偭偨丄堦摢偺儁僈僒僗偱偁偭偨丅偦偺攚拞偵偼丄摨偠傛偆偵弮敀側梼傪帩偭偰偄傞丅
乽杺朄偠傖偁枴婥側偄偩傠丅僆儗條偑憲偭偰傗傞傛丅備偭偔傝儖僓僀傾偺栭宨傪尒偣偰傗傞丅僆儗條偐傜偺朖旤偩乿
乽偱傕丄嶰恖傕僫僀儞僥乕儖偺攚拞偵偼忔傟側偄偩傠丠乿
乽傆偅乣丅撦偄傗偮偩側偀乣丄杮摉偵乧乧乿
丂僫僀儞僥乕儖偼偨傔懅傪偮偔偲丄偙偆尵偭偨丅
乽偍慜偑僒儎僇傪書偄偰偄偭偰傗傟傛乿
乽傏丄杔偑両丠乿
乽尵偭偨偩傠丄僆儗條偼僋乕儖側擇枃栚偩偭偰丅帺暘偺庤暱偼昞偵弌偝偢丄塭偱姶摦偺儔僗僩僔乕儞傪墘弌偡傞丅偦傟偑崱偺僆儗條偺栶栚偩丅僸儘僀儞傪桪偟偔書偒偟傔傞丄奿岲偄偄庡栶傪墘偠偰偔傟傛乿
乽僫僀儞僥乕儖乧乧乿
丂僫僀儞僥乕儖偺尵梩偵嬐偐側徠傟徫偄傪晜偐傋側偑傜丄僫儐僞偼僄僨傿儞傪僫僀儞僥乕儖偺攚拞偵忔偣丄帺暘偼僒儎僇傪書偒偐偐偊偨傑傑偦偺屻傠偵崢傪壓傠偟偨丅
乽偝偁丄峴偔偧両乿
丂惷偐側怷傪愗傝楐偔傛偆側殀乮偄側側乯偒偲嫟偵丄僫僀儞僥乕儖偼栭傪寎偊傛偆偲偟偰偄傞嬻偵岦偐偭偰嬱偗偩偟偨丅
丂栭嬻偺忋傪丄儁僈僒僗偑梼傪偼偨傔偐偣側偑傜嬱偗偰偄偔丅
丂偦偺攚拞偵偼堦恖偺彮擭偲丄億僯乕僥乕儖偺彮彈傪書偒偐偐偊偨庪恖偺庒幰偑忔偭偰偄偨丅偦偺檢乆偟偔偰庒乆偟偄婄偼丄懢梲恄偱偁傝丄傑偨媩偺柤庤偲偟偰傕抦傜傟傞傾億儘儞偺條偱傕偁偭偨丅
丂偦偺孼掜偲偟偰傕抦傜傟傞寧偺彈恄偼丄婸偗傞敀嬧偺枮寧偑偲側傝丄擇恖傪廽暉偡傞傛偆偵偦偺岝傪搳偘偐偗偰偄傞丅
丂恄榖偺堦応柺傪巚傢偣傞忣宨偺拞偱丄庒幰偺拑怓偺敮偲彮彈偺億僯乕僥乕儖偑晽偵阹乮側傃乯偄偰偄偨丅偙偺岝宨傪夋壠偑尒偰偄偨側傜偽丄嫲傜偔壗傪曻傝弌偟偰偱傕丄僉儍儞僶僗偵岦偐偭偰偄傞偙偲偩傠偆丅偦傟傎偳偵恄旈揑偱偁偭偨丅
丂傗偑偰攏忋偺庒幰偑丄儁僈僒僗偵堦惡偐偗傞丅儁僈僒僗偼偦偺尵梩偵墳偊傞傛偆偵丄庱傪忋偘偰殀偄偨丅
丂儁僈僒僗偼峏偵戝偒偔梼傪偼偨傔偐偣丄旘傇傛偆側惃偄偱嬱偗巒傔偨丅傑傞偱渁惎偺傛偆偱偁傞丅儁僈僒僗偑梼傪偼偨傔偐偣傞偨傃丄偦偟偰栭嬻傪嬱偗傞偨傃丄惎孄偑崀偭偰偄偭偨丅
丂偟偐偟儁僈僒僗偺忋偱偼丄媫寖側僗僺乕僪傾僢僾偱庒幰偑僶儔儞僗傪曵偟偰棊偪偦偆偵側偭偰偄偨傢偗偱偁傝乧乧丅