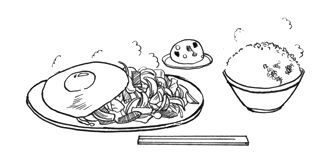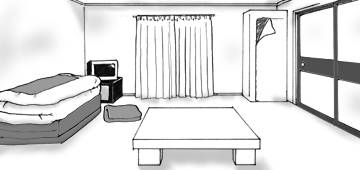
「ここに……住んでいらっしゃるのですか……?」
それがセイリオスの部屋を見たシルフィスの第一声だった。
セイリオスが築後30年にはなろうかという古いアパートを指さして、
「あそこの2階なんだ」と言われたときは、冗談としか思えなかった。
実際に、鍵を開けて、部屋の中に案内されると、ただただ驚くしかなかった。
旧式のキッチンが付いている分、シルフィスの部屋よりは広いが、
6畳一間のその部屋は、清潔ではあるが快適とは言い難い。
学校ではピカイチのお嬢様として有名なあのディアーナの兄が、
こんな部屋に住んでいるとは、誰が想像しただろう。
シルフィスはそれ以上口も利けずに、部屋を見回した。
「高校のときに家を出て以来、自活しているんだ。
今はそれなりの収入もあるが、引っ越すのが面倒でね。
この部屋にいる時間も短いし」
セイリオスの言葉に、シルフィスは自分がとんでもなく
失礼な態度を取っていることに気づいた。
「すみません。ただ、あまりに意外だったもので……」
「だろうね」
セイリオスは気を悪くした様子はなく、
むしろ、彼女の反応を楽しんでいるようだった。
「前に、傘を返そうと思って、家を探したことがあるんです。
駅から歩いて1分とおっしゃっていたので……」
「この部屋を見て、どおりで見つからなかったはずだ、とでも思ったかい」
シルフィスは正直にうなずいた。
「高そうな傘でしたので、その……」
「高級マンションが並ぶ表通りで探したのだろう?」
「はい」
くすっ。
こらえられない、と言わんばかりに、セイリオスは笑いはじめた。
普段のクールさはどこにいったのだ、と問いつめたくなるような大爆笑である。
「笑いすぎです」
「いや、すまない。予想した以上にきみの反応が面白くてね」
「笑い事じゃないんですよ。見つけられなくて、ものすごく残念だったんですから」
「本当に?」
セイリオスはもう笑っていなかった。
むしろ、あまりにも真面目な顔つきに、シルフィスは動揺した。
「あ、あの……」
「なんだい」
「おなかがすいたので、ご飯の支度にかかりますね」
シルフィスは台所に逃げた。
【小牧】
1DKの安アパートです。
こういう展開は苦情の元になるので、一応、アンケートを取ることにしました。
ご協力をお願いします。