ドボッキー語を分かりやすく解説することにします。ここに掲載するドボッキー語は、普通の言葉だけれども、ドボッキーの世界では違った意味となるものや、聞いたことがあるけれど何の意味か分からないようなものを集めたつもりです。
新たに3つの言葉を追加しました。今回はおとーとさんから貴重な情報を頂きました。ありがとうございます。他に情報があれば教えて頂き、随時追加していきたいと思います。また、わかり難いなどの意見も頂ければ幸いです。
 あ行
あ行
- ・あーるしー(RC)
- 鉄筋コンクリート(Rainforced Concrete)のことを言います。これが成功したものが、RCサクセションてなことはありません。
- ・あかり(明り)
- トンネル工事現場から出た言葉。トンネル内と比べて、外は明るいことから"明かり"と呼ぶようになった。明かり工事などと使われる。
- ・あさがお(朝顔)
- コンクリートを打つ時に使われる小型の枡のようなもの(ホッパー)。一方の口が他方の口より大きい角錐状の筒形をしています。
他に、水を取り入れる構造物(取水口)の種類として、朝顔の形に似ていることから、"朝顔型"と呼ばれているものがあります。
- ・いぬばしり(犬走り)
- 堤防の裏側(川と反対の面)ののり尻付近の、地盤よりちょっと高い位置に設けられた狭い平場を言います。堤防ののり尻を保護するために設けられるものです。
- ・いらう
- 中国地方では触る、触れるという意味の言葉です。これが転じて、掘削する、浚渫するなどに意味に使われているようです。
- ・うききそ(浮き基礎)
- 構造物が堅い支持層に設けられていないものを言います。正式な基礎形式の一つなので、きとんと設計していれば特に問題はありませ。なお、以前世間を騒がせたいかだの家は典型的な浮き基礎の構造物でしょうか。
- ・うちっぱなし(打放し)
- コンクリートそのものが仕上げとなるものを言います。このため、コンクリートの色(灰色)が見える状態となります。ゴルフの練習とは関係ありません。
- ・えん
- メートルのこと。センチメートルのことをせん(銭)と言ったことから、その上の単位であるため、えん(円)と呼んだとも言われています。
- ・おがむ(拝む)
- 直立しているもの、または直立に近いものが、前かがみになることを言います。
また、道路で両側に勾配が付いている場合を"拝み勾配"と言います。
 か行
か行
- ・かいがらかいがん(貝殻海岸)
- 文字通りに、貝殻で出来た海岸のことを言います。自然の営造物ですが、情緒がありますね。
- ・かいさき(開先)
- 溶接する場合の接合部の溝のことを言うようです。確か先の尖ったスコップをかいさきと呼んだような気がします。
- ・かすみてい(霞堤)
- 河川の堤防の種類の一つで、連続していない(途中で切れている)堤防のことを言います。これは、堤防が壊れて欲しくないところを守るため、川の氾濫する個所を特定するために設けられるものです。洒落たネーミングだと思います。
- ・かたおし(片押し)
- コンクリートを打つ時、打つ区画の一方からコンクリートを流し込むこと。
また、道路工事やトンネル工事で、片方からのみ工事を行うとき、片押しで工事を行うなどといいます。
- ・がっしょう(合掌)
- 手を合わせることではありません。木材などを山形に組むことを言います。
- ・かぶり
- 鉄筋コンクリートで、鉄筋の表面とコンクリートの表面との長さのことを言います。
- ・かんしょうりん(緩衝林)
- 比較的新しい用語です。木を観賞して楽しむというこではありません。土石流や土砂流の力を弱める目的で設けられる林のことを言います。木にとっては迷惑な話ですね。
- ・きりもり(切り盛り)
- 家計をきりもりすることではありません。道路や鉄道工事など土を扱う工事のことを言います。"切り盛りする"と使われます。
- ・クリープ
- コーヒーに入れるものではありません。もの(土や鋼材)に長時間重さを与えると、次第に変形することを言います。
- ・けあげ(蹴上)
- 階段の一段の高さのことを言います。走って駆け上がるイメージでしょうか。当時、この専門用語を決めた人はせっかちだったのでしょう。
- ・こうがん(硬岩)
- 非常に硬い岩のことを言います。硬岩を掘るときには、爆破により壊すのが一般的です。誰ですか、スケベなことを想像しているのは。
- ・こぐちどめ(小口止め)
- 川に護岸を作る際、その上下流の端に、洪水によって洗掘することを防ぐために設けられるコンクリート構造物のことを言います。対比語として大口止めという用語はありません。
- ・ゴヘ(情報提供:サムスングさん)
- 海上の工事で台船を進めるときに使う言葉です。"Go ahead(ゴウアヘッド:前へ行け)"がなまって出来た言葉のようです。
 さ行
さ行
- ・さかまき(逆巻)
- コンクリートを打つ時に、上から順々に打つ方法のことを言います。また、下から順々に打つことは順巻きといいます。主に地面より下にものを作るときに使われる方法です。
- ・さぎ
- 細木がなまったもの。木っ端のこと。学生の頃アルバイトしていた時、職長さんが使っていました。
- ・ししょう(支承)
- 橋などを支える構造物のことを言います。師匠も弟子を支えているのでしょうか。
- ・しじそう(支持層)
- 橋などの構造物を支える地盤のことを言います。大きい構造物の場合には、通常岩盤などの堅い地盤が支持層となります。政党などを支持する人たちを呼ぶのと全く同じ字ですネ。
- ・しめきり(締切り)
- "寒いので部屋を閉切る"のではありません。水の中で工事をしなければならないとき、水を遮る目的で作られる構造物のことを言います。
- ・ジャンカ
- ジャンジャカジャーンと浮かれているようですが、違います。コンクリートの欠陥の一つです。
- ・シュート
- コンクリートを打つときに使う樋のことです。ドボッキーの世界では、シュートを決めたとは言いません。トホホ。
- ・すいしん(推進)
- 地中の中に管を押し込みながらトンネルを作る方法のことを言います。下水の工事によく使われます。
- ・すいせい(水制)
- 川の堤防を守るなどの目的で、水の強さや流れの方向を制御するための構造物を言います。川の中に張り出したように設けられたものなどで、何だろうと思われるものは水制かもしれません。
- ・すてこん(捨てコン)
- コンクリート構造物を造るときに、工事をし易くするなどの目的で、その底に敷くコンクリートのことを言います。余ったコンクリートを捨てることではありません。
- ・スランプ
- 型枠に流し込む前の(まだ固まる前の)コンクリートの状態を示す指標です。この値が大きいと軟らかいことを示します。
 た行
た行
- ・ダイク
- 海外で活躍する日本の技術者が時々使っています。大工さんのことではありません。英語で堤防のことをダイクと言うのです。
- ・たこ(蛸)
- 短い杭や、土の突固めに使う道具のこと。時代劇で見たことはありますが、今はあまり使われていないと思います。
- ・たたき(三和土)
- 軟弱な土に石灰とにがりを混ぜて強固にしたものをいいます。昔はたたいて混ぜたのでしょうか。また、土に石灰のみを混ぜたものを二和土といいます。
- ・だとう(妥当)
- 妥当投資額の略語。「妥当が出る」などと使われると、その事業の効果が期待できるという意味です。
- ・たまがけ(玉掛け)
- すけべな言葉ではありません。クレーンなどにものを吊り下げるとき、この吊り方のことを玉掛けといいます。
- ・だんどりまけ(段取負け)
- 目的とする主体の工事より、その準備により多くの労力を要してしまうことを言います。やる前に負けてしまう・・・。通常の生活でもよくあることでしょうか。
- ・チーズ(情報提供:サムスングさん)
- 水道用のパイプなどで、T字になっているものを言います。ですから、食べ物ではありません。東北出身者がT字(ティージ)をチーズと発音したのが語源のようです。類似語:ワイズ
- ・ちゅうせいか(中性化)
- コンクリートが劣化する化学的現象の一つです。人間の世界でもコンクリートの世界でもやはり中性に収束するのでしょうか。
- ・つま
- 端っこのこと。端の型枠のことをつま型枠などと言います。なぜ、つまというかは分かりません。多分・・・
- ・つぼほり(坪掘)
- 地面の浅いところに、人力や小型の機械を使って小規模な穴を掘ることを言います。一坪位掘るということから言われたのでしょうか。ちょっと洒落た言葉と思います。
- ・でいすい(泥水)
(情報提供:おとーとさん)
- 孔を掘る時にその孔が壊れないようにするなどの目的で、比重の高い液体をその孔に満たします。この液のことを言います。通常は水にベントナイト(粘土鉱物)などを混ぜて作ります。これを飲んでも泥酔はしませんが、身体には悪そうです。
- ・テンドン
- 決して天丼のことではありません。専門的には引張を受ける材料のことです。鋼線や鋼棒のことを指します。
- ・とうじょう(凍上)
- かっこいい人やアイドルが登場するのではありません。土が凍って地面が持ち上がる現象を言います。
- ・とけい(情報提供:おとーとさん)
- 都市計画の略語です。市街地に道路、公園、上下水道など整備する時にはこれを策定する必要があります。正式な名称は忘れましたが、誰か教えてくれるでしょう。
- ・どじょう(土壌)
- ドボッキーの世界以外にも使われていますが、単に土のことを言います。これを食べても精はつきません。
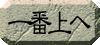
 な行
な行
- ・ないすい(内水)
- 川を流れる水のことを外水(がいすい)といいますが、その反対に堤防に囲まれた土地の水のことを内水といいます。堤防を境に考えると理解し易いと思います・
- ・なまげすい(生下水)
- 処理をしていない、汚いままの下水のことを言います。ストレート過ぎて強烈な表現ですね。
- ・ぬいじ(縫地)
- トンネル工事において、地質が悪いときにトンネル前方の天端に矢板などを打込むことです。別に針と糸を使うわけではありません。
- ・ぬのきそ(布基礎)
- 建物などの荷重を支えるために、一連の柱や荷重が伝えられている壁を帯のような細長い盤で支えるものです。別に建物の下に布を敷いている訳ではありません。
- ・ねこ
- 土などの小運搬に使用する手押車のこと。一輪車と二輪車とがあり、一輪車のことは猫車とも言われています。
- ・ねぼり(根掘り)
- 構造物を作るために、地面を掘ること。色々と嫌なことを聞かれることではありません。
- ・のり
- 土を切ったときや、盛ったときに出来る斜面のことを言います。別にべたべたしている訳ではありません。
 は行
は行
- ・はいごう(配合)
- ドボッキーの世界で配合というと、コンクリートを作るために使う材料の割合のことを言います。競馬の世界で使うインブリードとかニックスなどの知識は全く必要ありません。
- ・はだおち(肌落)
- トンネルにおいて、掘った面から大小の岩が落ちてくること。別に年をとると肌落ちが激しくなる訳ではありません。岩の状態が悪いときに起こります。
- ・はっぱ(発破)
- 爆薬で岩石を破壊することを言います。トンネルを掘るときや、採石場で岩を採取するときなどに行われます。そよ風に揺らぐ葉っぱとは正反対の趣でしょうか。
- ・バラスト
- 線路の枕木の下に敷く砂利や砕石のことをいいます。バラバラなストーンの略ではありません。ちゃんとした専門用語(英語)です。
- ・ふみづら(踏面)
- 階段の平たい部分のことを言います。足で踏まれることをイメージしているようですが、つら(面)とは乱暴な言い方のような気がします。
- ・ピーシー(PC)
- パソコンのことではありません。プレストレスコンクリートの略語です。簡単に説明するのは難しいですが、要するに普通のコンクリート構造物より、より大きな外力に対抗できるようにしたものです。
- ・ビン
- 材料を貯蔵するための器のこと。ダムの工事現場などでは、コンクリートの材料(石)を貯蔵する施設を見ることが出来ます。
- ・ふとんかご(布団籠)
- 鉄線で作られた網の中に石ころを入れたもの。川や水路などに使われています。布団の形をしていることから、こう呼ばれているのでしょうか。他に、横に長いものは蛇籠(じゃかご)と言います。
- ・ベンチ
- 土を掘るときに、段差を設けて掘ることがあります。この段差の平たいところをベンチと言います。ここで、彼女と語り合ってもムードは盛り上がらないと思います。
- ・ボーリング
- 地下の状況を調査するなどのために、孔を掘ることを言います。仲間とワイワイ楽しく遊ぶのではなく、れっきとした仕事です。
 ま行
ま行
- ・まきこみ(巻込み)
- 川に設けられている護岸工事にあたり、端部を地盤に食い込ませること。最近では、別に小口止め工(コンクリート構造物)というもので、端部をとめていることが多いです。
- ・マグネチュード
- 地震の大きさを表すものです。これを英訳すると、単に"大きさ"を示すようです。日本では地震に特定して用いられています。
- ・みずしめ(水締め)
- 土砂に水を加えて放置すると、締固まった状態となります。このことを言います。水を使って、懲らしめることではありません。
- ・みみしば(耳芝)
- 堤防の天端(一番高いところ)の端に沿って張られている芝のことを言います。端の崩れを防ぐために設けられます。
- ・ミルク
- ドボッキーの世界では、セメントペースト(セメント、水、砂などで出来たもの)のことをこう呼びます。確かに、ちょっと白っぽくてミルクみたですが、飲みたいとは思いません。
- ・めがね(眼鏡)(情報提供:おとーとさん)
- めがねトンネルやめがね橋とかに使われています。円あるいはアーチ形状が二つ並んでいると眼鏡に似ていることから、そう呼ばれるようになったのでしょう。
- ・メッシュ
- ふるいの網の目の数として使われています。また、金網の意味で使われることもあります。
- ・めちがい(目違い)
- コンクリートの仕上り面に段がつくことや、構造物の境目が段違いになることを言います。
- ・めんとり(面取り)
- 面食いとは違います。コンクリートや石でできた構造物の角に丸みを付けることを言います。
- ・もぐり
- ダイバー(潜水夫)のこと。別に悪い人ではありません。立派な職業です。
- ・もぐりぜき(潜り堰)
- 堰の上の水深が大きく、水没しているような状態の堰を言います。水理学的にはもうちょっと説明しなければならないのですが、この辺にしておきましょう。別名、溺堤(できてい)ともいいますが、私はこちらの言い方の方が好きです。
- ・モンケン(情報提供:サムスングさん)
- ボーリングの標準貫入試験(地質調査の方法の一つ)で使用するオモリのことを言います。このオモリは英語ではMonkey(モンキー)なのですが、作業員がモンケーと発音したのが語源のようです。
 や行
や行
- ・やくちゅう(情報提供:おとーとさん)
- 薬液注入の略語です。地盤を固めたり、地盤中の水の流れを止めたりするために、セメントミルクなどを地盤の中に入れることです。これをやったからといって、癖になったり、警察につかまることはありません。
- ・やぐら
- 杭を打ったり、ものを吊り上げたりするために使うもの。お祭りでは使いません。仕事道具です。
- ・やまはね
- 山羽根さんとか、"山はネ"とかのことではありません。トンネルを掘っているとき、突然爆発的に壊れてしまう現象のことです。とっても怖いことなのですが、その原因はよく分かっていません。
- ・やまつなみ(山津波)
- 土石流(どせきりゅう)とほぼ同じ意味です。現在、専門用語としては使われませんが、こちらの言い回しの方が凄み(恐ろしさ)があると思います。
- ・ヤングけいすう(ヤング係数)
- 部材の変形のし易さを表す数値のことです。若さをアピールするものではありません。
- ・ようじょう(養生)
- コンクリートを丈夫なものにするため、打設後に一定期間、適当な温度や湿度に保つことをいいます。コンクリートも人間と同様にゆっくり休める期間が必要なのです。
- ・よっこ
- ものを横に動かすこと。普通の言葉のような気がしますが、土木用語のようです。土木からでて一般的になったのか、その逆なのかは分かりません。
- ・よまき(余巻き)
- 夜着る寝巻きのことではありません。トンネルを掘る時は、その施工方法により、設計上必要な範囲より大きく掘ることになります。このため、コンクリート(覆工)を打つ時に、余分なコンクリートを打たざるを得ません。これを余巻きと言います。
 ら行
ら行
- ・ラーメン
- 食べるラーメンのことではありません。線と線とが、がっちり繋がった構造のことです。ドボッキーの世界では、骨が繋がったような感じであることから、骨組み(ほねぐみ)などとも呼びます。
- ・ラス
- コンクリートやモルタルを打つときに、下地として用いられる金網状のものを言います。
- ・レミコン
- レミィーさんにコンプレックスを抱いている訳ではありません。レディーミクストコンクリート(まだ固まらないコンクリート)の略語です。ドボッキーも子ギャル語に負けず、昔から変てこな略し方をしていたようです。
- ・ろかた(路肩)
- 道路において車道の左右の端に設けられるものを言います。道路本体を保護する目的や、非常駐車の目的などのために設けられます。見た目には、車道とどう違うのか良く分からないと思います。
- ・ロサンゼルススモッグ
- いわゆる光化学スモッグのことです。外国の地名が付くと何となくカッコよく聞こえますね。
- ・ロック
- フィルダム(土や礫で作られたダム)を作るときの材料の一つで、大きな石(礫)材のことをいいます。
- ・ロックボルト
- 岩盤が緩んだり、崩れたりしないようにするため、岩盤に孔をあけて挿入する鋼棒のことを言います。石で作ったボルトではありません。スチィールボルトの方がイメージに合うのですが。
 わ行
わ行
- ・ワイズ(情報提供:サムスングさん)
- 水道用のパイプなどで、Y字になっているものを言います。東北出身者がY字(ワイジ)をワイズと発音したのが語源のようです。類似語:チーズ
- ・わりいし(割石)
- 川の護岸などで見られる石積み用の石材のことです。ギャルが使う"悪いシー"とは違うのは明らかです。