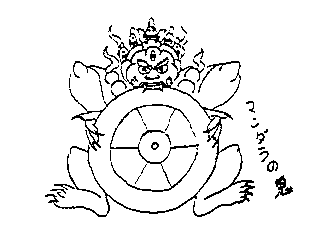淡く光る街
晩飯はネパールの伝統的な家庭料理を楽しもう、ということで、これまたS(ネ)一族のある一家の家を訪ねることになる。この一家、カトマンズではごく平均的な家屋でごく平均的な家庭を形成しているという。ネパールの現代市民生活というのに興味がないでもなかったのだが、俺は実はこの手の家族的な話や雰囲気が苦手だ。少々気が重いが、まあなんとかなるだろう。
汚れきったルンギとパンジャビを脱ぎ捨て、昨日買ったティベタンの衣裳をフルセットで着込んだ。こんなかっこ、観光客も地元の人も、だれもしてない。でもお気にいり。
薄暮につつまれた街区にそぞろ歩く人の群れは絶えず、俺たちはのんびりとした足どりでラトナ公園をまわりこみ、ポテトチップの屋台が出ていた広場のわきに出た。あれだけあふれかえっていた屋台は忽然と消え失せ、異様なほど広大な広場が森閑と横たわる。車の光がつぎつぎによぎり、肌に心地よい風がタメルの熱にうかされた身体からやさしく熱を奪う。
大通りをしばらく進んで右に曲がると、中国風のでかい門がそびえ立っていた。ここから先がニューロードだ、とM(日)さんがいう。
道のとっぱなまで歩いて右に曲がると、でかくて妙な寺院がいくつも立ちならぶ一角が出現する。なかなか荘厳な景観だ。そこを通りぬけてごちゃごちゃと入り組んだ路地の中へ。案内なしでは、生きて出られぬのではないかと不安になってしまうほどぐにゃぐにゃとあちこちを曲がった。傾いた家や路地の上にさしわたされたつっかい棒を指さし、M(日)さんは「地震の名残です」といった。恐ろしい街だ。丈の高い建物がひしめきあってるから、倒れたらさぞ景気のいいスペクタクルが展開することだろう。
「ああ、ここ。ここです」とM(日)さんは塀に穿たれた低い門をくぐった。後につづくと、ティベタンの衣裳を購入した時と同じような中庭に出る。基本的な構造や全体のコンパクトさなども同じだ。
「カトマンズはどんどん人が集まってきて居住する空間がたりないので、こういうつくりになるんです」とM(日)さんはいった。なるほど、この狭さ、ある意味では東京より過密かもしれない。時間の経ちかたがのんびりとしているから気づかなかったが、人間もまた街にあふれかえっている。
さらに二つの扉をくぐり屋内に入ると、どことなく旧い日本の家屋と似た雰囲気がある。渋い色あいの柱が張りわたされ、木枠を基本にして屋内が形成されている。なかなか丈夫そうなつくりだ。
と思っていたらM(日)さんが、
「見てください、この柱」
と一本の柱をぽんぽんと叩いた。「ほら、これ、はさみこまれてるだけ」
ぎょっとしてよく見ると、たしかに単なる支え棒だ。思いきり蹴とばせば簡単にすっとんでいくだろう。Kも目を丸くしている。地震が多くてしょっちゅう被害が出ているというのに、この大ざっぱさはなんなんだ、いったい。
S(ネ)さんの呼びかけに答えて、さらに上のほうから階段をたんたんと鳴らしてひとりの女性が降りてきた。大きくてやさしい目の女性だ。どうやらこの家の女主人らしい。年令は二十代後半くらいか。「ナマステー」彼女は大きな瞳を驚きにか、さらに大きく見開いてわれわれを見つめながら、笑顔で両手をあわせた。俺たちも両手を顔の前であわせ、「ナマステー」と答える。
なにやらカーテンでしきられた一室を指さし、入れという。「靴をぬいでくださいね。日本といっしょです」とS(ネ)さんが言って部屋に先導する。つづいて俺たちも、入口に靴をぬいで歩を踏みこんだ。
天井は低いが、さすがに居住空間だけあるせいか立って歩けぬほどではない。六、七畳ほどの空間の半分ほどを、巨大なベッドがでんと占領している。ベージュ地に赤と黒が基調の星型と円を組み合わせたような巨大な模様が掛け布団に描きこまれていた。この模様、シンプルだがなかなかいい。ベッドのむこうはカーテンで仕切られている。もの置きかなにかか。ベッドの横手にはガラス窓のついた棚があり、その中には、こどものものなのだろう、おもちゃのラッパやのりものといった玩具がいっぱいに詰めこまれている。「こういう感覚って、日本の主婦とおんなじだねえ」とはKの弁。その隣にカーテンのかかった小さな出窓様の風入れが開き、そのむこうに冷蔵庫がひとつ、でんと控えていた。冷蔵庫にはなぜか鍵がかけられている。この国ではなんにでも鍵をかける習慣があるらしい。そういえば、街にも鍵売りがたくさんいた。
「どうぞすわってください」M(日)さんがきっぱりと言い、自分は冷蔵庫の隣のひとりがけ椅子にさっさと腰をおろす。このM(日)さんという人、口調は丁寧だがいつもきっぱりとしたしゃべり方をする。ものごしもいちいちきっぱりしていて、一種気持ちいい。俺たちもベッドの縁にならんで腰をおろした。
現われた部屋の主人はジャヤさんという人だった。顔の輪郭と口上の部分をきれいに髭で覆っている。目もとがやさしく、終始にこにこと微笑んでいる。後にKが「ジョン・ローンに似てる」と評したが、たしかにラスト・エンペラーの柔らかさと似た雰囲気がある。「ナマステー」とあいさつを交わす。
ジャヤさんはぺらぺらの英語とカタコトの日本語で一所懸命話をする人だ。コミュニケーションが心底好きらしい。奥のもの置きからいくつかのアルバムを取り出してきて開陳し、いちばん端に腰かけたKを相手にいろいろと説明を加えはじめる。Yはジャヤさんの愛娘のジュンコちゃん(日本語とネパール語を組み合わせてつけた名前らしい)がしきりに照れているのをなんとかなつかせようと懸命だ。ジャヤさんの長男(中学生くらいか)は部屋の端で所在なげに、にこにことしている。
で、俺はM(日)さんの結婚写真、新婚旅行の写真を膝の上に乗せながら、世界を股にかけて放浪し、ネパール人の女性を射止めて妻とした日本人の体験談や人生訓に耳を傾ける。実はこれが少しうざったかった。身ひとつで山野をかけめぐり、その一方でネパールで得た家族の援助をも抜け目なく利用する根っからの放浪者の話はたしかに興味深い部分もあるが、おおかたは個人的な決意や文明論の類だ。同意はできても、とりたてて改めて拝聴するほどのことでもない。適当に相槌をうちながら俺はアルバムを繰っていた。お互い暇つぶし程度の会話だったのだが、帰途、S(ネ)さんがKとYに「あそこまでいうことないのにねえ……」などともらしていたらしい。どうもS(ネ)さんはM(日)さんよりよほど日本人らしい感覚をしている。
やがてスダさん(ジャヤさんの奥さん、私は最初「須田」さんだと思っていたらさっきの女性の名前なのだと知らされた)の手料理が小さなテーブルの上にどさりとならんだ。メニューは、なぜか味噌汁(もとの味噌にはMISOと書かれたラベルがはられている)にインディカ米のご飯、カレーベースの野菜の炒めものとほううれんそう、カレーに、ネパール人の食卓の基本だという妙なスープ。味つけはともかくとして、本当に普通のお惣菜といったラインナップだ。今日訪問することがうまく伝わっていなかったというので、たぶんこれはほんとうにネパールの一般家庭の食卓にならぶメニューに近いものなのだろう(K注:でもジャヤさんちの味付とか清潔観は日本人の出入りが多いこともあって、一般のネパーリよりマイルドみたいです。M(日)さんがいってた)。貪り食った。味噌汁は、だしに使ったものが根本的にちがっていたのだろう、なんだか妙な味がしたがこの国独特の料理だと思えばこれもうまい。腹が減っていたこともあり、白っぽい透明の妙なスープをのぞいてはどれも極上のうまさだった。
ちなみにネパールの一般的な家族形態は大家族方式だが、飯を食うときは小家族単位だという。俺たちも飯を食っているときは五人だけだった。ジャヤ一家はどこか別の部屋で食っていたのだろうか。よくわからない。
そんなこんなでわれわれは、ジャヤ家でのんびりとした一時を過ごして後、帰路につく。俺にとっては多少窮屈な時間ではあったが、腹もふくれたしなかなか悪くない一時でもあった。
夜に踏み出すと、街はすっかり人群れも絶え、森閑とまどろみに入っていた。ときどきすれ違うバイク、リクシャ、車、そして人びと。昼間にぎにぎしく露店が開かれていた場所にもぽっかりとした空間があるだけで、二階から突き出した棒にも今はラクのセーターや見なれぬ民族衣裳がかけられてはいない。
寺の屋根の下に無数の人びとが夜露をしのいで身をよせあいながら眠っていた。国境からインド人が流れこんで街の下層を形成しているという。いつまでの朝を、彼らはこうして過ごすのだろう。
祭りの果てた夜は静かに眠り、街区を淡く照らし出す街灯に周囲はまるで映画のフレームのなかの光景のように、遠く、かすかに、静謐のなかに浮かびあがっていた。路傍に佇む奇妙な神々。細かな模様の刻まれた、人びとの眠る集合建築。かすかな熱気と、かすかな冷気。影絵のなかのオレンジの街。
宿に帰ると明日の行動計画をかねて酒盛りである。ネパール語がくねくねとラベルに書かれた酒ビンをとりキャップをひねると、なんだか異様な臭気が鼻をついた。酒の臭いじゃない。これはどうも……臭い……というよりは……刺激……という感じだな……。なんだか目がちくちくして涙が出てくる。
やめたほうがいいよと制止をかける二人を尻目に、俺は一口飲んでみた。
……。
……なるほど。
……なるほど。これはたしかに「SO BAD」だ。
これは飲めない。即座に判断し、蓋を固く閉じようとする。と、なぜかたった一回ひねって開いただけなのに溝がつぶれてしまっていて、スカスカとまるで閉まらない。うーん、こいつは極めて「SO BAD」だ。
しかたがないのでウォッカをちびちびやりながらYとKの熱烈な青春論に耳を傾ける。こいつら、若いなあ。俺が歳とったのかなあ。まあいいや。おもしろいし。人が歳をとると理想は言葉を失い、内に沈みこむ。そして理想にとってかわった愚痴を気怠くたれ流すか、あるいは、己の夢や理想にむかって黙々と行動する。ただそれだけだ。
夢なかばで潰えたとしても、後悔だけはしたくない。