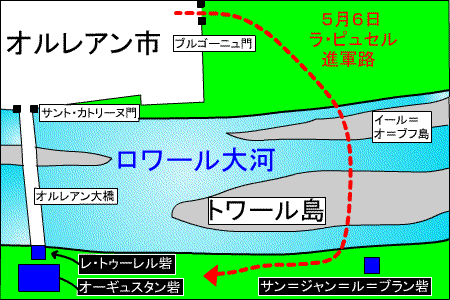
嗚呼! この身は目に見えぬ矢に射抜かれて
我が心臓は大いなる痛手を被りぬ。
今際の際にいたりてもはや抗う術なく
我は果てなんとす……
DARC
-ダァク-
全てを凌駕するもの
MEDIEVAL VII
「さよなら、レイ」
RETURN TO THE:36 『コイゴコロ?』
RETURN TO THE:37 『さ迷える心』
RETURN TO THE:38 『死の決意』
RETURN TO THE:39 『ページをめくると……』
RETURN TO THE:40 『さよなら、レイ』
RETURN TO THE:36
『コイゴコロ?』
サン=ルー砦奪還に成功した日の翌日――
5月5日木曜日は、キリスト昇天の祝日であった。
この時代、神が定めた休日である日曜日、それにキリストに関する祝日に関しては如何なる戦闘行為も行わないという決まりがあった。
従来の騎士道や慣例を虚構とし、合理性を追求する構えをとる連合も、この取り決めだけは結構真面目に守っていた。
彼らの思想の根底にも、やはりキリスト教の流れがあるからだ。
敬虔なキリスト教徒であるラ・ピュセルも、勿論この日は連合に仕掛けない。
休める兵は、今日1日を使って休養を取るようにと、全軍に通達した。
そして彼女自らは、なんと大胆にも、アランソン侯の私室を訪れていた。
先の戦闘により、オルレアン篭城軍の傭兵や騎士たちから信頼と忠誠を勝ち取ったラ・ピュセルではあるが、悩み事や相談事など、真に心を許せる人物はアランソン侯以外には1人もいない。
軍首脳も、ラ・ピュセルが軍全体に与える影響力こそ認めたものの、やはりそれはマスコットとしての存在意義であり、戦や政に関する分野においてはまだ部外者扱いしていた。
やはり、彼女が孤立しているという事実はそうそう変わらない。
……アランソン侯と昨夜再会するまで、彼女はずっとひとりぼっちだったのだ。
「――えっ? 読み書きを教えてほしい?」
ラ・ピュセルの突然の訪問を受けたアランソン侯は、彼女を部屋に迎え入れると、その要件を聞いた。
「……」
侯をじっと見詰めたまま、こくりと小さく頷くピュセル。
「あ、そうか。
ラ・ピュセルって貴族出身じゃなかったんだよね。
振る舞いが洗練されてるから、すっかり忘れてたけど」
彼女の気品にしばしば忘れがちになるが、彼女はもとは一介の村娘だったのだ。
貴族か聖職者でもない限り、農民が読み書きを習うようなことはない。
まして、女子供なら尚更だ。
「そうだね。
軍司令になったなら、勧告状や嘆願書なんかを送ったり読んだり出来なくちゃ不便だし……」
「……ええ」
これまで、何度か勧告状や要請書など出していたピュセルだが、それはすべて口述した内容を代筆官に書かせていたのだ。
せめてサインくらい書けなくては、後々困るだろう。
そう判断したラ・ピュセルは、アランソン侯に教えを請うことにしたのだ。
「いいよ。読み書きだけじゃなくて、ラテン語や、戦略・戦術、政治や帝王学……良ければチェロも。
僕の知っている限りのことなら、何でも教えてあげるよ」
にこやかにアランソン侯は言った。
「……いいの?」
読み書きでさえ、断られても仕方ないと思っていたラ・ピュセルは、以外な申し出に少し驚いて訊き返した。
「勿論だよ。ピュセルといると、楽しいし」
その一言に、体をビクッとさせるピュセル。
知らぬ内に敵に接近されていたのを発見したかのように、バッと身を引き離すと、その神秘的な紅い目を見開いてアランソン侯を凝視している。
「あ……の、ピュセル……?」
いきなり脅えにも似た反応を見せたラ・ピュセルに、逆に驚かされた侯は、遠慮がちに呼びかける。
「僕、なにか変なこと言ったかな……?」
ラ・ピュセルは、ドキドキと高鳴る胸に当惑していた。
顔も火照りだすのを感じ、尚混乱する。
――何、この感じ
自分といるのが楽しい。
そんなことを言われたのは、生まれて初めてだった。
また、如何に初めて受けたとはいえ、たたったひとつの言葉で動悸が激しくなり、顔が火照り出すなど……
明らかに異常である。
やはり、アランソン侯だけは、違う。
アランソン侯の全てが、自分をおかしくする。
ラ・ピュセルは、彼によって変えられていく自分に、焦りと恐怖にも似た感覚を感じていた。
だが、恐怖しているというのに、心の深層の何処かでは、彼に変えられていくことを喜んでいる自分がいる。
喜びと恐怖。
相反する感情が同時に彼女の胸を支配する。
ただでさえ感情の起伏に慣れていないラ・ピュセルが、それに大いに戸惑うのも無理はないことだった。
「……ラ・ピュセル。本当に大丈夫なの?」
劇的な反応を見せた後、今度は硬直したまま動かなくなってしまったラ・ピュセルに、アランソン侯が心配そうな表
情で訊いた。
「――ええ。問題ないわ」
問題ないことはないのだが、彼女には、この問題が何なのか分からない。
「そ……そう?
……じゃあ、とりあえず文字の勉強からはじめようか」
何だか納得のいかない様子ではあるが、ラ・ピュセルが『問題ない』と言ってしまえば、それ以上は何を訊いても無駄ということを学習していた彼は、とりあえず最初のレッスンを開始することにした。
アランソン侯は、文を書くのに使う1人用のデスクの椅子を引くと、ラ・ピュセルにすすめた。
彼女が言われた通りに、大人しく椅子に腰掛けるのを見届けると、自分は部屋の隅に置いてある客人用の椅子を引っ張り出してきて、ラ・ピュセルの隣に設置すると、腰を落とした。
つまり、ひとつの小さな机に2人仲良く並んで座ることになったわけだ。
「……じゃあ、アルファベェ(アルファベット)からはじめようね」
アランソン侯は机に置いてある文箱を開けると、紙とペンを取り出しながら言った。
「知ってるかもしれないけど、僕たちの母国語は全部で26個の『アルファベェ』という文字から構成されているんだ。
だから、字を読み書きしようと思ったら、まずこのアルファペェを覚えなくちゃならない」
アランソン侯の説明に、小さくこくりと頷いて了解を示すラ・ピュセル。
「……じゃあ、ちょっと書いてみるね」
そう言うと、アランソン侯は紙に『A』と、『A』、ふたつの文字を書いた。
「この文字の発音は、『ア』だよ。
2つある内、左が大文字、右が小文字。
文は、この大文字と小文字によって構成されるんだよ」
ラ・ピュセルは、また、こくりと頷いて了解を示す。
実に大人しい生徒である。
だが、やる気がないわけでも、集中してないわけでもない。
それは彼女の真剣な紅い瞳が、真っ直ぐにアランソン侯の書出す文字に向けられていることからも窺える。
「……えっと、次の『H』、『H』は『アッシュ』と言って、アルファベェの中でも特殊なんだ。
文字として単語の中に含まれはするけど、決して発音されることはないんだ。
だから、読む時はこの『H』を考えずに発音してね」
こくり。
頷くラ・ピュセル。
これで4分の一ほど消化したわけであるが、本当に分かってるんだろうか?
……ちょっと不安になるアランソン侯だったが、こんなことでめげていては、彼女の相手は務まらない。
気にせず続けることにした。
――殊勝な心がけである。
以後、延々とアランソン侯が説明し、ピュセルが小さく頷いて了解を示す……という光景が続いた。
「……これで、アルファベェは全部だよ。まずは、これを全部覚えてね」
「――覚えたわ」
ぼそりと呟くようなラ・ピュセルの声に、アランソン侯は一瞬耳を疑った。
「えっ?」
「……」
「あの、ピュセル……。今、覚えたって言ったの?」
「――ええ」
即答するピュセル。
「じゃあ、僕が書いたのを見ないでアルファベェを全部書出せる?」
半信半疑だが、アランソン侯は一応訊いてみた。
ラ・ピュセルは応えず、おもむろにペンを取ると1枚紙をとって自分の手元に置いた。
だが、なかなか書きださない。
どうやら、ペンの持ち方に苦戦しているようだ。
「……あっ、ペンはね、こう持つんだよ」
思わずピュセルの手をとったアランソン侯に、驚くほどしなやかな肌の感触が伝わる。
彼は、今更ながらにラ・ピュセルが女性であることを認識した。
普段は男装をして、生まれながらの騎士のように甲冑をまとい、勇敢に戦場に向かう彼女であるが……
17歳の少女であることに変わりはないのだ。
一瞬、ぼおっとそんなことを考えていたアランソン侯であったが、ピュセルの目が握られている手に向けられているのに気付くと、慌てて離した。
「あ……ご……ごめん!」
おろおろと謝るアランソン侯だが、当のピュセルはそんなことには構わずに、さっきまで侯に触れられていた自分の白い手を、まだじっと見詰めている。
――アランソン侯の手、温かかった
彼女は他人に身体を触られるのは嫌いだった。
異性ならば尚更のことである。
だが、何と言うか……
アランソン侯に触れられた時、彼の生命の息吹とでも言おうか、力強い何かをその手を通じて感じた。
生理的嫌悪感は感じない。
いやむしろ、心地良さすら感じる温もり。
何故だろうか、もっと長く彼に触れていたい――
ピュセルは己の抱いた欲求を認識し、また戸惑った。
「ピュセル……怒ってるの」
思わず触ってしまったラ・ピュセルの白く細い手。
その手をじっと見詰めたまま、また動かなくなった彼女に、アランソン侯は恐々と声をかけた。
アランソン侯のその声にラ・ピュセルは紅い瞳で一瞥くれると、ペンを握り多少ぎこちなくではあるが、アルファベェを正確に書出しはじめた。
――よかった。……とりあえず、怒ってはいないみたいだ
ちらりと向けられたラ・ピュセルの瞳に、責めるような色が無かったことから、アランソン侯はホッと胸を撫で下ろした。
彼は、これまでの何度かのコミュニケーションにより、何らかの形でラ・ピュセルの機嫌を損ねてしまった場合、彼女は見るものを恐怖させるほどの冷たい視線をよこすという事実を発見していた。
| ア ベェ セェ デェ |
| 「【A】、【BE】、【SE】、【DE】……」 |
囁くような小さな声で発音しながら、ラ・ピュセルは次々とアルファベェを紙に書出していく。
――凄い……、全部あってる。本当に一通り聞いただけで覚えたんだ……
言葉通り、本当にアルファベェをマスターしてしまっているラ・ピュセルに、アランソン侯は驚いた。
大した記憶力である。
もともと、日常生活の端々からラ・ピュセルの賢さ、器用さなどは窺い知ることができていたが、どうやらこれは本物らしい。
彼女が、馬術・剣術・宮廷作法など、訓練を受けたこともないのに難なくこなしてしまえるのは、この彼女の頭の良さにあるのだろう。
あるものを一見しただけで、原理やコツなどを一瞬で見切り、それを自分のものにできる。
それだけではない。
それらのある技術や命題を検証し、問題点や改良点を提起して、それらを統合して弁証法的発展を成す。
柔軟性と応用力がずば抜けて高い。
アランソン侯は知らないが、彼女が独学ながらATフィールドを、短期間でかなりのレヴェルまで使いこなせるようになったのも、この彼女の才能と努力があったからだ。
自らの能力やもとから備わった素質を的確に把握し、努力や鍛練によって効果的に高め、生かすことが出来る。
――彼女は、所謂『天才』と呼ばれる種の人間だった。
RETURN TO THE:37
『さ迷える心』
「……なるほど」
静かな室内に、クレスの低い声が響いた。
彼は、自分の肩口にちょこんと頭をのっけているリリアの髪を、優しく撫でながら続けた。
「それで、その『自由天使タブリス』……リッシュモン元帥は信用できるのか?」
「――恐らく」
クレスとリリアのふたりの姿は、彼ら夫婦に割り当てられたオルレアン城内の私室の大きな寝台の上にあった。
いつも彼らは、ひとつの寝台で身体を触れ合わせて眠る。
長い黒髪に、同じく黒の鋭い瞳。
どこか冷酷な感じすら与えるクレスではあるが、その顔に似合わず彼は甘えたがりである。
こうしてリリアの存在を感じていなければ、安心して眠れないと駄々をこねる彼に、リリアが付き合っているのだ。
勿論、リリアも別に嫌々というわけではない。むしろ、それを微笑んで受け入れているようだ。
まあ、ふたり夫婦の誓いを交わした仲なのであるから、さほどおかしな風景でもないが。
「……リリアは、これからどうするつもりだ?」
自由天使タブリスとは和解できたから良いようなものの、これから彼らの命を狙って差し向けてこられるであろう使徒達が、皆彼のように理解があるわけではない。
完全に人類監視機構の裏切り者となったリリアと、それに同調するクレス。
前途は多難である。
「監視機構の動きを静観――と言いたいところですが、現状でそんな悠長なことは言っていられませんね。
戦力は明らかにこちらが劣っているわけですから……」
「……悪かったな。オレが足手まといで」
これが、並みの傭兵団や騎士小隊が相手というのなら、クレスの実力でも充分戦力にはなる。
が、相手は使徒。
しかもそのバックには人類監視機構などという得体の知れない組織があるのだ。
例えクレスが後100人いたとしても、使えるかどうか分からない。
何しろ、リリアひとりが手練の傭兵80をひとりで殲滅したというデータがあるのだ。
使徒という存在は、それほどに強い。
「クレス……本気でそう思っていますか?」
「え……」
リリアの唐突な問いかけに、クレスは言葉に詰まった。
「そう思うのなら、強くなって下さい」
「……強く……」
「そうです。あなたには、私と契って以来、少しずつ”使徒”の力が備わってきているはずです。
真面目に鍛練をつめば、ATフィールドくらいなら使いこなせるようになるでしょう。
……私があなたをこんなことに巻き込んでしまったことは、本当に悪かったと思っています。
ですが、私を受け容れ――それでも私を想ってくれる。
あの夜言ってくれた言葉が真実であるのなら、今こそ行動をもってそれを示して欲しいのです」
いつに無くリリアは饒舌であった。
そうならざるを得ないほど、事は深刻であるということだ。
クレスは、今更ながらに監視機構の脅威を思い知っていた。
「……強く……なる……これから来る使徒達と戦えるほどの実力が、オレにも着くのか?」
「――可能性はあるでしょう。
現に私と”意志”で会話できるほど能力が高まってきています。
これは、あなたの身体が、徐々に使徒のそれに変化していっている何よりの証ですから」
――そう。
クレスは、徐々に『使徒』になりつつあった。
はじめてその事実を、リリアの口から知った時には、飛び上がって喜んだ。
普通の人間にはない、特別な力。
それを持つことが許されたという、優越感を感じたからだ。
だが、しばらくして冷静に判断ができるようになった時に襲ってきた感情は、恐怖だった。
自分が、人間でなくなることへの恐れである。
今もそれが克服できずにいるが、これから生き延びるためには必要な力である。
とりあえずでも、受け容れて磨きをかけなければ死ぬだけだ。
「……分かった。それで、オレはどうすればいいんだ?」
「私が責任を持って鍛え上げます。あなたは私の指示に従ってくれさえすれば結構です」
「よ……ろしく」
普段物静かな女性であるだけに、いざと云う時なにをされるか想像が付かない。
ちょっと心配なクレスであった。
「……だが、オレの強化を図るのは良いとして、それで『人類監視機構』とやらと渡り合えるのか?」
「いえ。無理です」
きっぱり断言するリリア。
「お……おいおい! 勝てないのか?」
「正直に言って、監視機構が何なのか、何人の使徒が存在するのか、その使徒たちの実力はどのくらいなのか。
……分からないことの方が多いんです」
「……それで?」
聞きたくないが、あえてクレスは先を促した。
「監視機構支配下にある使徒達が束になってかかってきた場合、仮にリッシュモン元帥がこちら側に付いてくれたとしても、勝てる自信はありませんね」
「――」
クレスは絶句するしかない。
リリアがこうまで言い切るのだ。実際勝ち目はないのだろう。
「……じゃあ、どうするんだ……よ?」
ぎゅっとリリアの身体を抱き寄せて、クレスは言った。
どう足掻いても勝ち目のない、強大な組織を敵に回したという事実。
――怖い。
クレスは、怖かった。
「タブリス――リッシュモン元帥は、ラ・ピュセルをこちら側に引き込めと言っていました」
リリアは縋りついてきたクレスを抱擁しながら、変わらぬ声で言った。
何時も、どんな時でも変わらない、自信に満ちたリリアの澄んだ声。
「ラ・ピュセルを?」
母親に抱かれる子供のようにクレスは瞳を閉じ、その温もりに感じ入りながら言った。
「そうです。彼女は、今、何の情報も持っていません。
恐らく自分が”使徒”であるという事実も、神だと信じきっている存在が <人類監視機構> であることも知らないのでしょう。
そして、彼女の側にいつもある『アランソン侯』の影響で、彼女に心が生まれようとしています。
丁度、私があなたによって心という『知恵の実』を手にした時のように……」
「心……知恵の実? 分からないな。どういう意味だ?」
「神という存在を忌み嫌うアランソン侯に触れることで、彼女の心は今揺れています。
はっきり言うならば、ラ・ピュセルはアランソン侯に対して、淡い恋心を抱きはじめているのです。
また、アランソン侯の主張が正しいのか、それとも今まで無条件に受け容れてきた神たる『人類監視機構』が正しいのか。
どの陣営に属するか、何を信じるべきか……彼女は今、悩んでいます」
「……あのラ・ピュセルが、アランソン侯をねぇ」
クレスが意外そうな声を上げる。
「もっとも、ラ・ピュセル自身は、自分がアランソン侯に抱きつつある感情がなんであるのか、気付いてはいないようですが」
「しかし……何でそんな詳しいことまでリリアが知ってるんだ?」
クレスの疑問ももっともである。
リリアの言い方には、まるで、常にラ・ピュセルの動向に目を向けてきたかのようなニュアンスが含まれている。
「リジュ伯カージェスを知っていますよね?」
「ああ。オレはアランソン侯とも結構仲が良いからな。
リジュ伯カージェスも当然知ってる。まぁ、ちょっとした戦友だな」
「……彼は私の協力者です。
現在、彼はラ・ピュセルの観察と、その身辺、監視機構の内部調査を行っています」
「リジュ伯カージェスが?」
アランソン侯の腹心にして、王国最強の剣士。
剣匠の誉高き伯爵位を持つ貴族、それがリジュ伯カージェスである。
間諜として暗躍するには、ちょっと身分が高すぎる。
リジュ卿くらいの地位にあるのなら、部下を使って諜報活動をさせるのが普通だ。
「私は時々、あなたと別行動をとっていた時がありましたよね?
そのほとんどは彼とコンタクトをとるためだったんです」
「……」
次々と明かされていく裏事情に、クレスは開いた口が塞がらない。
「彼は”使徒”という訳ではありませんが、早い時機から『監視機構』の存在に気付き、私と利害が一致することから、協力関係をとるようになったんです」
クレスは、愕然としていた。
「オレは……
オレ、今まで何にも知らなかったんだな。
リリアが裏で何かしていたのは知っていたけど……本当に、オレには何も知らされてなかったんだな……」
何時もリリアといたのは自分だ。
一番彼女を理解しているのは自分だ。
無邪気にそう信じきっていたこれまでの自分が、何故だか急に空しく感じられた。
疎外感――とでも言うのか。
ふたりでいたはずなのに、実はひとりだったわけだ。
「……バカみたいだな……オレ……」
クレスはそっと呟いた。
一番大切な部分を知らされてなかった。
一番必要とされる力になれなかった。
その部分を知り、必要とされる力を提供していたのは、自分ではない別の男。
自分よりも強く、頼りとされていた、リジュ伯カージェスという男。
クレス・シグルドリーヴァではなかったのだ。
弱かったオレが悪い。
話してくれなかったリリアが憎い。
リジュ卿を選んだリリアが憎い。
選ばれたリジュ卿が憎い。
支えにすらなれなかった自分を殴り倒したい。
これは、嫉妬だろうか?
それとも、悲しみ?
後悔?
分からないが、何かが許せない。
クレスは、ベッドから身を起こすと部屋着から外出用の服に着替えはじめた。
「……クレス」
そんな彼の気持ちを、リリアは察していた。
巻き込みたくない、迷惑をかけたくない。
そう思って彼には話さなかった。打ち明けなかった。
その結果が、これだ。
クレスを傷つけてしまった。
だが、あの時はそれが最善の選択だと思ったのも確かだ。
「……今、ちょっと感情的になってる。
リリアに八つ当たりしちまいそうだ。……嫉妬……かな、そいつを持て余してる」
テキパキと要領よく服を着ながら、クレスはリリアに顔を向けずに淡々と言った。
「なんか、気に入らねえよ。
……こんな感情を抱くことも、それを制御できない自分も、気に入らない」
リリアに言葉はない。
彼女にはどうすることも出来なかった。
「外に行って、頭を冷やしてくる。
――こんなこと言いたくないけど、今はリリアといたくないんだ」
寝室の出口に向かいながらクレスは言った。
「今夜はもう戻らないと思う。……朝食の時、会おう」
短くそう言い残すと、クレスは静かにドアを閉じ、部屋から去っていった。
結局、一度もリリアを振り向かずに。
リリアは、その胸の中で何度もクレスに謝罪した。
口に出すと、逆に彼の感情を昂ぶらせる結果になるだろうと思ったからだ。
リリアには、ただ祈ることしか出来ない。
どうか、2人の間に溝を作るような結果にはならないように……と。
だが、彼女には祈るべき神が無かった。
RETURN TO THE:38
『死の決意』
――昇天祭の翌朝、5月6日。
ラ・ピュセルは立腹していた。
また、軍の幕僚会議からつまはじきを食らったのだ。
アランソン侯や、ラ・ピュセルの理解者となったル・バタール、ラ・イールなどが説得に回ってくれたが、結局彼女の参加が認められることは無かった。
しかも、その席で決定された軍の意向もまた気に入らない。
――サン=ルー砦の奪還は当面の成果としては充分であり、しばらくは軍事活動は行わない。
彼女からすれば、なんともふざけた話である。
久方ぶりの勝利に、現場の兵士達の士気は上がっている。
ここで一気に勝負を決するべきなのだ。
だが、ここ数年というもの、連戦連敗を喫していた貴族たちは、すっかり怖じ気づいて腰を重くしてしまっていた。
……何とも情けのない話ではないか。これでは勝てる戦も勝てなくなるというものだ。
第一、この名前と地位だけで軍首脳を語っている無能な連中の怠惰や消極性が、現在の王国側の劣勢を生み出してきたのではないか。
憤りで、徹夜の眠気や疲れも吹き飛んでいた。
昨夜は、アランソン侯の部屋で夜を徹して勉学に勤しんだ。
結果アランソン侯をもつきあわせることになってしまったが、優秀な生徒である彼女は、一夜にしてほとんど完全に読み書きをマスターしてしまった。
勧告書など、独特の言い回しや専門用語が用いられる文(ふみ)は無理だが、一般レヴェルの手紙程度ならラ・ピュセルはもう楽に読み書きできる。
彼女は副官たちを各首脳たちの元に走らせ、今度はオルレアン橋を渡った対岸、南の要所である『オーギュスタン砦』を叩くべきだと焚き付けた。
多くの騎士、傭兵、町民たちはラ・ピュセルのこの意見を支持したが、結局軍首脳を動かすことは出来なかった。
ならばと、特に士気の高い兵達を集め、ラ・ピュセルはブルゴーニュ門から出撃した。
すっかりラ・ピュセル信奉者となったラ・イール、それにクレスとリリアも其々の傭兵隊を連れて参加した。
問題は、アランソン侯である。
実を言えば、彼も出撃することを強く望んでいたのだが、国王筋の貴公子である彼は微妙な位置にある。
軍首脳のトップのひとりとしての地位もあるが、このオルレアンでは所詮余所者。
発言による影響力は大きいが、肝腎の発言権がない。
軍首脳の決定を無視して、アランソン侯自身の恣意で行動するには、彼を縛り付ける貴族という立場は重過ぎた。
それなら、一時でも良い。貴族という身分ではなく、一兵士として戦に出る。
つまり、ロンギヌス隊の指揮者としてでなく、ラ・ピュセルの部下として出撃するわけだ。
ふたつの顔を使い分ける。
アランソン侯が考え出した、苦肉の策であった。
そうしてまで、彼はラ・ピュセルから目を離したくなかったのだ。
何故か、と問われれば彼は答えに窮するだろう。
ただラ・ピュセルの身を案じるというならば、些か度が過ぎる。
ならば、ラ・ピュセルの行動を見届けるためか?
これも、どうもしっくりこない。
――結局のところ、無性に彼女が気になるのだ。
理由は分からないが、最近気が付けばラ・ピュセルの姿を探し、ラ・ピュセルの顔を思い浮かべ、ラ・ピュセルの心配ばかりしている。
これまでには無かったことだ。
最初は、ラ・ピュセルの反応にいちいちビクビクして、会話を楽しむ余裕など無かった。
だが、特別長く同じ時間を共有するうち、ラ・ピュセル一流の無反応というか、無愛想な対応や接し方にも大分慣れてきた。
その不器用さに、何だか可愛らしさすら感じるようになってきたくらいだ。
とにかく、できるだけラ・ピュセルの側にいたい。
アランソン侯は今、強くそう願っている自分を認めないわけにはいかなかった。
それ故、無茶な言訳まで付けて彼女の出撃に付き合うのだ。
| ■オルレアン市南側 5月6日~7日 オーギュスタン&レ・トゥーレル砦攻防戦周辺図 |
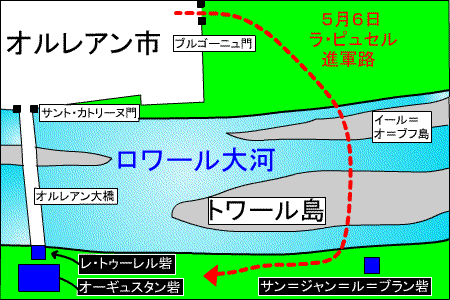
「ラ・ピュセル、調子はどう? 昨夜徹夜だったけど……」
小船に揺られながら、アランソン侯は訊いた。
「……問題ないわ」
ラ・ピュセル率いる隊は、オルレアン市の東門である『ブルゴーニュ門』から出ると、補給物資輸送用の小船に馬ごと乗り込んで、街の南を流れるロワールの大河を渡っていた。
このまま、イール=オ=ブフやトワール島といった中州を経由して、対岸に上陸しオーギュスタン砦に奇襲をかけるのだ。
「そんなことより、アランソン侯。おたくは良かったのか?」
遊撃隊を引き連れたクレスが近寄ってきて言った。
アランソン侯としてではなく、ラ・ピュセルの守護兵のひとりとして戦に出るという、大胆とも言えるアランソン侯の決意は、クレスにとってもいささか意外だったらしい。
「……いいんですよ。今回の軍の決定はどう考えても妥当じゃない」
「それは言えてるな」
侯爵という最高の爵位をもつアランソン侯と、一介の傭兵隊長でしかないクレス。
その身分の差は歴然としている。
クレスがこんな横柄な口調で話し掛けられるのは、ひとえにアランソン侯の人柄のおかげである。
アランソン侯は自分の身分にはあまりこだわっていない。
高すぎる身分に気兼ねして遠巻きにされたり、妙に気を使われるよりも、ピュセルや、ラ・イール、そしてこのクレスのように気さくに話し掛けてくれる方が嬉しい。
彼はそんな男だった。
そして、だからこそロンギヌス隊や、リジュ卿といった最高の男達が彼に忠誠を誓うのだ。
さて――
今回ピュセルの狙いである『オーギュスタン砦』であるが、この砦を陥落させるためには、幾つかの障害がある。
ロワールの大河を挟んで、オルレアン市の対岸には連合の占拠する大きく3つの砦がある。
まず、オルレアン大橋のたもとに位置する『レ・トゥーレル砦』。
そして、そのすぐ南にある『オーギュスタン砦』。
3つ目はそのオーギュスタンから700M程東にある『サン=ジャン=ル=ブラン砦』である。
障害のひとつは、オーギュスタン砦に仕掛ける際、この『サン=ジャン=ル=ブラン砦』に駐留する連合兵に挟撃される可能性である。
もうひとつは、『レ・トゥーレル砦』があまりにも近すぎること。
『オーギュスタン砦』を攻撃しているラ・ピュセル軍に『レ・トゥーレル砦』から大砲を撃ったとしても、十分効果を上げられるだろう。
下手をすれば大砲の援護射撃だけなく、援軍を差し向けてくるかもしれない。
「……で、どうなさいますんでしょう? ラ・ピュセル様」
まだ妙な病気が治ってないラ・イールが、しなを作りながらピュセルに訊いた。
ちなみに、彼の今日の装備は聖職者用の純白のローブの上から、ごつい鋼鉄製の板金鎧。
そして、クレイモアという外国製の超大剣である。
例によって、彼の白いローブは丈と袖が短く、見たくもない彼の肌を露出している。
「どうって……なんのこと、ラ・イール?」
なるべく目を合わさないようにアランソン侯が訊ねた。
「決まってんじゃねェではありませんか。
このまま挟撃の危険性を無視して、オーギュスタンに直接向かうか――
或いはサン=ジャン=ル=ブラン砦を先にぶっ潰して差し上げて、後方の脅威を絶つかです。
もっとも、サン=ジャン=ル=ブラン砦に攻撃を仕掛ければ、オーギュスタン側も騒ぎを聞きつけて警戒しだすでしょうから、奇襲は台無しになりますけど。
ウォ~ッホッホッホッ……!」
右手の甲で口元を隠しながら、高らかに笑うラ・イール。
――やっぱ、この人を連れてきたのは失敗だったかな……
アランソン侯は顔を蒼くしながら、真剣に悩んだ。
……だが、ラ・イールの提起した問題は一考に価する。
「アランソン侯、相変わらずラ・イールはおかしいが、言ってることはマトモだぜ。
このままオーギュスタンに向かうか、サン=ジャン=ル=ブランを先に陥とすか。
――どっちをとるんだ?」
クレスは、アランソン侯に訊いた。
普段なら、傍らにいるリリアに訊く類の話を……だ。
彼らの間には、本当に溝が出来てしまったのか?
出撃して、この船に乗り込んで以来、まだふたりは一言も言葉を交わしていない。
どこかよそよそしい雰囲気すらする。
「そうだなぁ……。一応この戦では僕は一兵士だし。
先にサン=ジャン=ル=ブランを陥落させて、後方を確保した方がいいとは思うけど……。
ピュセル、君はどう思う?」
「――貴方がそういうなら」
アランソン侯の問いに対し、ラ・ピュセルは短くそう答えた。
分かり難いが、サン=ジャン=ル=ブラン砦を先に攻撃するというアランソン侯に賛同するということだろう。
事実上、この隊の中で最高の権力を持つのはラ・ピュセルであるから、彼女の意向が採用された。
だが、結局この決定は無意味なものに終わる。
日差しを浴びて銀色に輝く、鏡のようなロワールの大河を渡り終え、サン=ジャン=ル=ブラン砦に辿り着いたラ・ピュセルの兵団が見たものは、ただの瓦礫の山だった。
連合は逸早くこの襲撃を察知したか、あるいはこのラ・ピュセルの進軍を予め予測していたのか、ともかく、サン=ジャン=ル=ブラン砦を取り壊したのだ。
では、ここにいた連合の兵はどうしたかといえば、九分九厘、オーギュスタン砦に行ったのだろう。
サン=ジャン=ル=ブランは放棄して、規模の大きなオーギュスタン砦の守りをより強固なものにするつもりなのだ。
荒々しく緑の草原を削るようにして作られた道には、西の方角……
即ちオーギュスタン砦の方角に向けて馬車や蹄の跡が残っている。
「この蹄の痕……
やはり、 <サン=ジャン=ル=ブラン> の兵は <オーギュスタン> に移ったんだ」
屈み込んで刻み込まれたような馬車の痕跡を手で触れて確認しながら、アランソン侯は言った。
「引き上げだな」
クレスが呟くように言った。
もともと、士気の高い一部の兵と、ラ・イール、クレス、リリアそれぞれが預かる傭兵隊という万全とは言い難い体勢で臨む戦だ。
奇襲を成功させなければ勝率はグンと下がる。
連合がサン=ジャン=ル=ブラン砦を捨て、オーギュスタンに賭けたということは、敵は既に警戒態勢を敷いているわけである。
どう考えても奇襲どころの話ではない。
ここは一旦退却して、体勢を整えて出直すしかないのだ。
「仕方ない……かな」
そうは言うが、アランソン侯はどこかホッとした表情をしている。
ロンギヌス隊に内緒で出てきたことに、負い目を感じているのだ。
「ラ・ピュセル、残念だけどここは一旦退こう?」
再び渡河の用意をしはじめた兵達がたてる音を耳に、アランソン侯はラ・ピュセルに声をかけた。
だが、ラ・ピュセルはその声には応えなかった。
真っ直ぐにオーギュスタンへと続く、馬車の車輪の残した痕をじっと見詰めている。
「ピュセル……」
睨み付けるように、ひたすら西に紅い目を向ける彼女に、再びアランソン侯が呼びかけようとした時、不意にピュセルが口を開いた。
「――来る」
その声が切っ掛けであったかのように、弓矢が風を切る音が一斉にアランソン侯の鼓膜を刺激した。
火矢である。
木造の小船に突き刺さった矢は、そのまま抱いてきた炎を船に渡してゆく。
突発的な戦術ではない。
明らかに計画されていたやり方である。
「しまった! これが、連合の狙いか」
クレスが、瞬く間に火だるまになっていく船を見やりながら言った。
撤去された砦を見て、敵が退却しようと背を向けたところを、オーギュスタン砦から逆に仕掛けて殲滅する。
それが連合の作戦だったのだ。
残った船を死守するオルレアン兵たちに、今度は容赦なく長弓から放たれた高い貫通力をもつ矢が雨のように降り注ぐ。
ひるんだところへ、とどめとばかりに騎馬隊、歩兵隊が突撃を仕掛けてきた。
ラ・ピュセルの兵団は、いきなり絶体絶命の状況に陥っていた。
「ラ・イール! クレスさん、リリアさん!
ここは僕らだけで防ぎましょう!
ラ・ピュセルは後方で船を死守。一刻も早く渡河の用意をさせて!」
イグドラシルの馬上、スラリと帯剣を抜刀しながらアランソン侯が叫ぶ。
「……ダメ。あなた達だけでは防ぎきれない」
ラ・ピュセルが珍しくアランソン侯に真っ向から反論する。
彼女の愛馬スレイプニールも、何かを訴えかけるように高く嘶いた。
「分かってるよ! でも、何とかしてみせる!
君は逃げて! ラ・ピュセルと言う名の救世主は、この国にまだまだ必要なんだ」
明らかに、死を覚悟してラ・ピュセルをはじめとする兵を、1人でも多く逃がそうというアランソン侯の言葉に、ラ・ピュセルは絶句した。
そんなラ・ピュセルに、優しく微笑んでアランソン侯は言った。
「……君は死なないよ。僕が守るから」
これが死に逝く者の顔だろうか?
あまりの穏やかな笑みを、ラ・ピュセルはただ見送ることしか出来なかった。
ラ・ピュセルを守るため死を覚悟したアランソン侯に対し、クレスは迷っていた。
既に突撃してくる連合の騎馬隊の第一波が目前まで迫っている。
――くっ……どうする……?
リリアの使徒としての力――
ATフィールドとデス・クレセントの力を借りればこの場を凌ぐことも出来るだろう。
だが、もうリリアに頼るのは御免だった。
彼女に頼るのならば、これまでと変わらない。
強くなると誓った矢先に、泣き付くような真似は出来ない……だが、このままでは確実に死ぬ。
数倍の数で攻めてきた連合の兵団を、ラ・イールとアランソン侯、リリアの4人と、その指揮下の僅かな手勢で防ぎきれる訳がない。
嫉妬か……
昨夜、胸を掻きむしりたくなるほどに強く湧き上がった、黒い衝動をクレスはそう表現する。
頭を冷やす、と一旦リリアから離れてはみたものの、その感情は収まることは無かった。
リジュ伯カージェスが、自分の知らないリリアを知っていたことへの嫉妬。
リリアが、自分ではなく他の男を頼ったことへの怒り。
全部、自分の無力が……オレの弱さが引き起こしたことだ。
戦場で、弱いものが死ぬ。
今まで自らに戒めてきた、自然の摂理だ。
オレは激動する時代に対して、弱すぎた。だから、全てを失いここで死ぬ。
――上等じゃねえか!
キッと顔を上げると、クレスは覚悟を決めた。
嫉妬を持て余すような弱い男に、リリアの愛を受ける資格はない。
これは、自分の弱さという罪に対する罰なのだ。
ならば、それを受け容れようじゃないか。
「うおぉぉぉぉぉっ!」
馬を鞭打つと、クレスは自ら連合の突撃兵に突っ込んだ。
RETURN TO THE:39
『ページをめくると、いつも……』
――何故?
リリアは、まるで死にに行くかのように、連合の騎兵隊に突撃していくクレスの後ろ姿を、絶望的な思いで見詰めていた。
リリア・シグルドリーヴァは、力を司る最強の使徒である。
その使徒の力――
つまり、ATフィールドやデス・クレセント等を利用すればこの絶望的状況も打破することができるだろう。
確かに、使徒は恣意による歴史への介入を許されていない。
仮に、この場で死の三日月……デス・クレセントを使い、連合を退けたとしよう。
この場を乗り切れたとしても、相手を皆殺しにしない限りデスクレセントを『見た』人間が生き残ってしまう。
また、リリアが使徒であることを知らない、いや使徒の存在すら知らないオルレアン側の兵にも、使徒の力の存在を明かしてしまうことになる。
『使徒』の超然たる力が公になった時、民はそれをどのように受け止めるだろうか?
自分が魔女だか異端者として、処刑されるだけで済むならまだいい。
だがそれだけではなく、人間を超えた存在が実在したという記録が、歴史に残ってしまうことはまず間違いないだろう。
また、ここでオルレアン側が負けるというごく自然な歴史の流れを、変えてしまうことにもなる。
これらが未来に与える影響と、それによって生じる歪みは計り知れない。
人類そのものの在り方を変えてしまうほどの、壊滅的打撃を与えてしまうことにもなりかねないのだ。
歴史とは、言わば進化の過程にある生物のようなものだ。
ある時期の気候がたった1℃違っただけで、生まれた惑星の重力が微妙に違っただけで、その生物の進化の過程は大きく変動し、結果全く別の生物を生み出すことになってしまう。
……歴史も同じだ。
ある時点では大した現象ではないように思われても、後の世に大きな歪みとなって現われる可能性があるのだ。
歴史を改変、改竄するという行為は、それだけの危険性を持つ。
だからこそ人類監視機構は自分達を裏切り、歴史を改変させたリリアの抹殺をリッシュモン元帥に命じたのである。
過去、クレスの故郷の村である、スウェーデンのシグルズ領に襲い掛かった壊滅の危機をリリアは使徒の力を使って救ったことがあった。
その際は、デス・クレセントとATフィールドを見た敵兵は皆殺しにしたし、クレス以外の味方もその場にはいなかった。
――使徒の力を見た者は、生かして返せない。
その最低限のルールは守れたわけだ。
だが、本来壊滅するはずだったシグルズの歴史を恣意で変えてしまったことは事実。
実のところ、このシグルズの街を壊滅の危機に追いやった武装集団ラクライム。
彼らはDEATH REBIRTH=リリアの介入が無ければ、当然の如くシグルズを陥落させ、そこを根城として勢力を拡充していく……それが自然な歴史の流れだった。
そして、人類監視機構のシナリオも、それに準じたものであった。
力を司る使徒=リリアをこのラクライムの内部に送り込み、ラクライムの成長に加速を付けさせる。
そして現在スウェーデンを震撼させる王国と国民との内乱に、第三勢力として参戦し、三つ巴の大戦まで持ち込んだ結果、全ての勢力を疲弊させ共倒れさせる。
このシナリオ通りに事が運べば、スウェーデンの国力は大きく低下、長期に渡って文化の成長を抑制できたはずだ。
が、リリアは個人的な感情で、このラクライムを壊滅させてしまった。
監視機構の思惑からは大きく逸脱する出来事である。
現に、ラクライムという第三勢力になりうる芽は潰され、依然スウェーデンでは王国と国民の内戦が続いているものの、文化を破壊するまでの戦火は広がっていない。
――歴史を変えてしまったのだ。
これが後の世にどのような影響をもたらすかは、今のところは不明である。
だが、かなりの大きな歪みが生じるであろう事は容易に想像が付く。
人類監視機構はこの事態を収拾するため、今頃、計画補正及び修正に躍起になっているはずだ。
このような理由からリリアは、今までクレスと共に幾多の戦場を傭兵として駆け抜けてきたものの、余程のことがない限り”使徒”の力を使うことは無かった。
例え監視機構から抜けたとは言え、そうそう使徒の力を行使するわけにはいかないのだ。
使徒という、強大な力を持つ者故に、自らに制約を設けなければならない。
それが力を手にすることへの代償。守らなくてはならない義務であるとリリアは考えていた。
だが、今回の場合……
もし使徒の力を使わなければ、クレスは死ぬだろう。
これは間違いない。
歴史を変えてまで守りたかったクレスを、失ってしまう。
しかし、今度ばかりは簡単に使徒の力を使う訳にもいかないのだ。
光り輝く死神の鎌、『デス・クレセント』の目撃者が、大勢生き残ってしまうからだ。
――どうすれば……?
リリアは決心が付かずにいた。
――候
ラ・ピュセルはロワールの河縁、渡河の用意を指揮しながらも気持ちは前線に向いていた。
相手の数は、こちらの数倍……恐らく4~500はいるだろう。
しかも、こちらの兵の大半は渡河の用意を進めていて、戦闘に参加していない。
アランソン侯、クレス、ラ・イール、リリアを筆頭とする指揮者と、それにしたがう50ばかりの兵でなんとか後方の退路を守っているが、それにも限界というものがある。
怒号を上げてぶつかり合う両陣営の兵たちが巻き上げる砂塵で戦況は窺えないし、ましてアランソン侯が何処にいるか、まだ無事であるかを確認することなどできない。
まだ無事であるか……?
では、無事でなかったら――
アランソン侯は、どうなったというのか。
死んだということか?
『死』。
アランソン侯の死。
――ラ・ピュセルは考える。
もし……
もしも、死んでしまったら……
もう彼には逢えない。
アランソン侯はもう微笑まない。
ホッと落ち着くような、あの笑みがもう見られない。
碇シンジの、はにかむような笑顔は永遠に失われるのだ。
――それだけじゃない
あの月夜の晩のように、感情を露わに神の存在を討論したり、
月明かりの下、ゆったりと馬の背に揺られながら、一緒に散策したり、
静かな夜に草原でふたり、語り合ったりすることも……できなくなる。
「……お初にお目にかかります。私はアランソン侯爵、ジャン・ダランソンです」
「あ……貴女が……あの、ラ・ピュセルなのですか……?」
「君と……話がしたかったんだ。……ラ・ピュセル」
「神秘的って言うのかな……凄く奇麗だよね?」
「勿論だよ。ピュセルといると、楽しいし」
はじめて、シノン城の庭園で出会った時のこと。
優しく穏やかな夜風を浴びて、ふたり言葉を交わした時こと。
はじめて人に奇麗だと言われた時のこと。
自分の存在を、喜んで受け容れると、そう言われた時のこと。
今でも鮮明に思い浮かべられる。
悪魔の子としてでもなく、神の遣いとしてでもなく、純粋に人間として自分と接してくれた。
自分の異形をごく当たり前のように受け容れ、包み隠さず自分から心を開いてくれた、はじめての人だった。
――だから、彼と過ごしたひとときは楽しかった。
出会ってから2ヶ月しか経っていないというのに……
彼とのひとつひとつの思い出が、何時の間にか彼女の大事な宝物になっていた。
まだ数少ない、思い出を綴ったラ・ピュセルの心のアルバム。
ページをめくると、いつも、そこに、――彼がいた。
凄く、あたたかい感じがした。
……そう、いつしか”天の声”よりも、彼の声を聞く方が嬉しいと感じるようになっていた。
彼が死ねば、それは失われてしまう。永遠に。
――それは、嫌。
もう、あったかくしてもらえなくなるのは……
――嫌。
今、あの人の温もりを失うのは……
――絶対に
「……嫌」
ラ・ピュセルはポツリと呟いた。
「……ラ・ピュセル!」
競り合いの続く前線から、白馬に乗ったリリアが真っ直ぐこちらに向かってくる。
彼女はラ・ピュセルの前でピタリと馬を止めると、その碧と金色の瞳を真っ直ぐ、蒼銀の髪の少女に向けた。
「行って下さい!
でなければ……クレスが……あなたのアランソン侯も死んでしまいます。
今彼らを救えるのは……唯一公然と使徒の力を行使できる、貴方しかいないのです」
「……」
『使徒の力』――
初めて聞く言葉だが、漠然と神の声から教わった、『ATフィールド』のことを指しているのだとラ・ピュセルは悟った。
確かにあの力を使えば、この場を切り抜けることが出来るかもしれない。
……いや、切り抜けるのだ。
そのためのATフィールド。
そのためのラ・ピュセルなのだ。
確かに、この女傭兵隊長の言う通り、今、アランソン侯を救えるのは自分ひとりしかいない。
彼女の紅い瞳に、光が宿った。
ラ・ピュセルは、既に渡河のため船に乗せられてしまったスレイプニールのところまで歩み寄り、一気にその背に飛び乗ると、彼女のたてがみを撫でながら言った。
「……スレイプニール、私をあの人のところへ連れて行って。
貴方とずっと一緒だった、あの人のところへ」
人の言葉が解せるのか、スレイプニールは一際高く嘶くと、ラ・ピュセルを乗せたまま船から飛び降り、凄まじい勢いでサン=ジャン=ル=ブラン砦跡へ駆け出した。
リリアもそれに続く。
デス・クレセントはどうしても空気中の塵と化学反応を起こして発光してしまうが、原理の異なるATフィールドなら力をセーブする限り、不可視の存在として、普通の人間には見ることが出来ない。
混戦の中なら、十分誤魔化しきれるだろう。
「ラ・ピュセル!
いいですか、あなたの持っている能力……ATフィールドはただの防御用の壁ではありません。
イメージ次第で、如何様にも姿を変えられるはずです。
強く剣をイメージすれば剣に。
槍をイメージすれば槍にその姿を変えるはずです!」
無論、リリアにも容易に出来ることだが、彼女はこの使徒の力をあまり派手に使う事は出来ない。
せめて、一瞬だけ防御用にATフィールドを展開するのが限界だ。
それ以上だと、周りの兵士に不審に思われる。
だが、神の使いだと周囲に認識されているラ・ピュセルなら、使徒の力を堂々と行使したとしても神の奇跡として受け取られるだろう。
ラ・ピュセルは、何故この傭兵隊長がATフィールドの存在と、自分がその力を使いこなせることを知っているのか疑問に思ったが、今は問い質すような余裕はない。
リリアに言われた通り、ラ・ピュセルは目を閉じて精神を集中すると、弓矢をイメージしてATフィールドの形状を固定していく。
その間にも、スレイプニールの俊足は前線への距離をグングンと縮めていった。
打ち合わされる剣の音が、随分とクリアに聞こえてくるほどの位置に達した時、ラ・ピュセルは閉じていた目を開いた。
同時に十数本、ラ・ピュセルの周りに展開されたATフィールド製の不可視の矢が、連合の兵に向けて放たれた。
その貫通力は連合自慢の長弓など、比較にもならない。
鋼鉄製の薄い板を何枚も重ねあわせた、プレートメイルを易々と貫かれ、連合の兵士達が次々に倒れていく。
見えない矢に倒れ行く仲間を目の当たりにした連合の兵士達は、ちょっとした恐慌状態に陥った。
それを尻目に、ラ・ピュセルは戦場を真っ直ぐに駆け抜ける。
――待っていて
ラ・ピュセルは、唇でそう呟いた。
振り下ろされる剣を受け流すと、甲冑を押し出すように蹴り、馬上から叩き落とす。
横から突き出される槍を躱すと、腕を叩き切る。
アランソン侯の剣技は、一対一の試合でこそ真価を発揮する。
いくら技術が卓越していようと、それだけでは乱戦の中生き残ることは難しい。
現に彼はその体中に小さな傷を受けていた。
致命傷がないのは、ひとえに技巧を凝らした特注の鎧を身に纏っていたからだ。
「くっ……!」
連合の歩兵が切り払ったショートソードが左肩、丁度鎧と鎧の継ぎ目を掠めた。
鮮血が吹き出すが、手で庇う間も無く次の敵が襲いかかってくる。
なんとか切り捨てるが、気付けば周りを囲まれていた。
既にイグドラシルは捨てていた。
乱戦になった時、馬上にいたのでは小回りが利かないからだ。
だが、アランソン侯にも限界がある。
技術で相手を圧倒し、さっぱりとした勝利を得てきた彼である。
やはり他の大柄な兵達に比べれば、力も体力も劣る。
疲れからステップが鈍り、剣の描く軌道も芸術的な美しさと正確さを失い、乱れが目立ちはじめた。
時々連合兵の槍や剣の切っ先が鎧を掠り、嫌な金属音が聞こえてくる。
「アランソン侯、無事か?」
横から連合の兵を切り倒し、クレスとラ・イールが近付いてきた。
流石に戦場の中で育ってきただけあって、ふたりともこういった乱戦には慣れている。
この状況下では、彼らの方がアランソン侯よりも生き残れる可能性は高いだろう。
アランソン侯は、はぁはぁと荒い息を吐くのが精一杯で、言葉で返す余裕はない。
「とりあえず、『サン=ジャン=ル=ブラン砦』跡まで後退しよう。
あそこならまだ壊され損ねた柱や壁といった障害物がある。
……場所が狭いから一気に襲い掛かられる心配がない分、まだマシなはずだ!」
クレスが敵歩兵に睨みを利かせながら怒鳴った。
「行きましょう。早くしないと完璧にぶっ殺されてしまいましてよ!」
ひらひらと短い裾を不気味に閃かせながらラ・イールが叫んだ。
矢のように駆けていくスレイプニールとラ・ピュセルに、リリアの愛馬では追いつくことは出来ない。
リリアは後を追うのは諦め、アランソン侯達の救出を彼女に任せることにすると、その場に残り、連合の兵と剣を合わせはじめた。
つい先程までは、自分もラ・ピュセルと共にクレスの救出に向かうつもりだった。
だが、ラ・ピュセルのATフィールドによる攻撃を見て気が変わった。
ただの壁ではない。
攻撃にも使える。
ただそれだけのアドバイスをしただけなのに、ラ・ピュセルは初の試みとなるATフィールドのイメージ・フィードバックを、複数の弓矢のようなものを展開し、それを以って一斉攻撃するという高等技術をもってやり遂げてみせたのである。
リリアは内心舌を巻いていた。
無形のATフィールドを、ただ意志とイメージの力だけで擬似的に形状固定し、それを自在に操るというのは口で言うほど易しい事ではない。
超人的な精神力、集中力が要求されるからだ。
そうおいそれと出来る事ではない。
それをラ・ピュセルは事も無げにやってみせたのだ。――しかもエキスパート・レヴェルの発想で。
彼女が1度に形状を固定できたATフィールド製矢は、全部で12本。
はじめての人間が、いきなり矢だけを作り出したというその発想の柔軟性もさる事ながら、12本という数も物凄い。
普通ならとりあえず1本作れるかどうか試行してみるのが関の山だろう。
彼女の応用力と集中力は、よく人からバケモノ扱いを受けるリリアの超絶レヴェルから見ても普通じゃない。
しかも、ラ・ピュセルの才が窺えるのはそれだけではないのだ。
彼女が作り出した12本の見えない矢は、全て連合の兵を貫いた。
まるでホーミング(自動追尾)するかのように、自ら軌道を修正しながら12本それぞれが独自の動きを見せて、見事敵を射抜いたのである。
種を明かせば、ラ・ピュセルが連合の兵に向けてそれぞれを誘導したせいだが……
12本の矢を、全部同時に誘導してみせたのである。
どう考えても、並みの神経をしているとは思えない。
ラ・ピュセルはとんでもない可能性を秘めた、未完の超大器――
それが、最強の使徒リリア・シグルドリーヴァのラ・ピュセルに対する評価であった。
砦跡の瓦礫を背景とする戦場に、剣がかち合う金属音が響き渡る。
アランソン侯、ラ・イール、クレス共に未だ健在でっあたが、3者とも疲労の極地にあった。
ガクガクと震える膝が、ともすれば地に付いてしまいそうになる。
よろけるアランソン侯の身体が、クレスの肩に接触した。
「大丈夫か……しかっかりしろ、侯」
叱咤するクレスの声も力ない。
アランソン侯は乱れた呼吸で肩を揺らしながら、蒼白な顔を頷かせる。
疲れもあるだろうが、肩からの出血が酷い。
傷口から体力、気力が抜けていくような脱力感。
気を抜けばすぐにでも意識を失ってしまうような感覚に、アランソン侯は必死に抵抗していた。
アランソン侯、クレス・シグルドリーヴァ、ラ・イールは、互いの背を合わせてそれぞれ正面の敵を片っ端から蹴散らしていたが、3者とも動きがかなり鈍くなってきている。
「ちくしょう、まだなんでしょうか、退却準備はっ?もう完璧にヤバイんですのにッ」
ラ・イールが怪しい言葉遣いで怒鳴る。
だが、その顔つきは冗談を言っている顔ではない。
返り血を浴びて、角張った彼の顔は赤鬼のように真っ赤だった。
身体が大きいと、体力が尽きるのが速い。
大男はその巨体を支えるだけでも体力を使うため、スタミナの消費が激しいのだ。
しかも、ラ・イールはクレイモアという普通の剣の2倍以上ある重量を誇る大剣を振り回しているのだ。
一見元気そうなラ・イールにも、確実に限界が近付いていた。
彼らの役目は、退却のため味方の渡河を擁護することだ。
一兵たりともラ・ピュセルたちのもとへ近付かせるわけにはいかない。
アランソン侯たちと同じく、退却擁護のために前線で戦っていたオルレアン側の兵は、もうほとんど残っていない。
だが、まわりにはまだ100を優に超える敵兵がいるのだ。
クレスは敵の戦斧を受けとめた衝撃で手が痺れ、手持ちのロング・ソードを取り落としてしまった。
隙を突いて、ここぞとばかりに振り下ろされる連合歩兵の剣を、素早く抜刀したショート・ソードで受け流し切り捨てる。
が、勢いを殺しきれずそのまま片膝を付いた。
「く……っ……、リリ……ア……」
絶望的な呟きと共に、クレスは気を失った。
壁の1枚が崩れ落ちたことで、連合に勢いが付いた。
アランソン侯とラ・イールには、同時に7人の敵兵が襲い掛かってきた。
それを凌ぎきれるほど、2人には余力は残されていない。
――防ぎきれない
もうピクリとも動いてくれない利き腕。
自分に振り下ろされる銀色の刀身を、無感動に見詰めながら、アランソン侯は覚悟を決めた。
これで……終わり……か……
ゴメンね、ラ・ピュセル……最後まで君を見届けたかったけど……
……もう、ダメみたいだ……
母上……悲しまれるだろうな……最後の家族まで戦でなくすなんて……
……ゴメンね……みんな……
……ゴメンね……ラ・ピュ……ううん……綾波……
願わくば……、君が神と信仰の束縛から……開放され……自由になれますように……
……さよ……なら……
最後に浮かんだのは、いつも無表情な赤い瞳の少女の相貌だった。
……さよなら……レイ……
……一度でいい……君の微笑んだ顔が見てみたかった……よ……
| こんじき | |
| ――意識が闇に捕われる寸前、 | 金色に光る幾多の流星を見たような気がした。 |
to be continued……