|
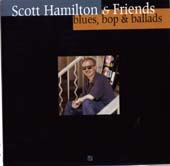
|
|
Scott Hamilton & Friends "Blues,Bop & Ballads" |
|
コンコード・レーベルを代表するテナー奏者スコット・ハミルトンの新作が到着しました。
前作のバッキー・ピザレリ(g)とのデュオ作「ザ・レッド・ドア」から約1年ぶりとなるこの新作は、彼のカルテットに(ハミルトン:saxノーマン・シモンズ:pデニス・アーウィン:bチャック・リッグス:ds)CrissCrossからリーダー作もあるトランペットのグレッグ・ギスバートが加わったクインテットをベースに、曲によってトロンボーンのジョエル・ヘレニー、ギターのデューク・ロビラードが加わる編成です。選曲は、タイトル通りビ・バップやブルース、バラードをテーマにしたもので、コールマン・ホーキンスの「アイ・ミーン・ユー」やマーサー=カーマイケル作の「スカイラーク」など全10曲となっており、1曲ハミルトンのオリジナルも収録されています。
今回は、歌モノのスタンダードよりも、コールマン・ホーキンスやアイク・ケベック、ナット・アダレイ、タッド・ダメロンといったジャズ・メン・オリジナルのナンバーが中心で、特にホーキンスのナンバーが2曲もセレクトされているのが気になります。ホーキンスといえば、ハミルトンが大きな影響を受けたサックス奏者のひとりで、ホーキンスへのオマージュを感じさせる歌心満点でスケールの大きなテナーを聴かせてくれます。
バックメンバーもハミルトンのレギュラー・グループが中心で、心地よくスウィングしています。
やれコルトレーンだ、グロスマンだのマレイだの言っているTがなぜスコット・ハミルトンか?と疑問をお持ちの方も多いと思います。テナーサックスの魅力は、スタイルはどうであれ、スケールの大きい豪快なサウンドだと思います。フュージョン旋風の吹き荒れる70年代後半に鮮烈のデビューを果たして以来、ジジ臭いだの、保守的だのいろいろ言われたハミルトンですが、自分の信じるスタイルを貫きスウィング一筋に生きる姿はブレッカーやグロスマンに勝るとも劣らない迫力を持っていると思います。
西海岸のコンコード市で、中古車屋を営んでいたカール・E・ジェファーソンというオヤジが、趣味でジャズのレコードの制作を始め、通信販売でそれを売ったのが、コンコード・レコードのルーツなんですが、そのオヤジも他界し、経営も変わってしまったコンコードですが、このハミルトンの新作は家内制手工業的でインティメイトな魅力に溢れていた初期のコンコードの匂いを感じさせる作品です。
天国のカール・E・ジェファーソンも微笑むスウィンギーな1枚。
8.14 Update |
|
★★★★ |
|
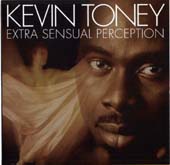
|
|
Kevin Tony "Extra Sensual Pweception" |
|
若手キーボード・プレイヤー、ケヴィン・トニーの新作が、Shanachieレーベルから到着しました。
スムース・ジャズ・シーンでは、若手ながらかなり人気のあるピアニストのようで、ゲストにも、カーク・ウェイラム、ジェラルド・アルブライト、レイ・パーカーJr.らが参加しているということで、期待して聴いたのですが…。
ソウル系スムースジャズといった感じのリズム・トラックにアコースティック・ピアノのメロディがのるというような構成の作品となっています。
ピアノの雰囲気は、ラムゼイ・ルイス+ディヴィッド・ヴェノワ。リズムもケヴィン自身の打ちこみ中心で、2~3年前のサウンドと言われても、そうかなと思うほどの中途半端さとチープさ。収録曲もほぼ彼のオリジナルなのですが、これがまた中途半端。黒人らしくグルーヴィーなR&B路線で行くのかと思うと、ディヴィット・ベノワ風のナンバーも登場するというありさま。
正直、久々の出た超駄盤です。このレビューでは何度も書いているのですが、スムース・ジャズのツボは、作曲とアレンジのパッケージングなんです。ピアニストとしては、そこそこの才能があるのかも知れませんが、作曲やアレンジ、プロデュースのツボはまったく心得ていないようです。
ピアノは平凡、印象的な良い曲は無い、リズム・トラックもダサい。これでは到底他人には薦められません。久しぶりの「金返せ~」盤です。
8.19 Update |
|
★ |
|

|
|
Ron Carter Sextet "Orfeu" |
|
6月16日の発売の作品なんですが、最近入手したのでここで「遅刻レビュー」。
何も言うことは無い超ベテラン・ベース奏者ロン・カーターの新作で、今回はボサノーヴァがテーマのようです。ボサノーヴァといえば、ギターが大切なのですが、その重責を担うポジションには何とビル・フリゼールを起用。これは、意外にもクールで、本物のボサの感覚とはもちろん違うのですが、このフリゼールのギターが醸し出す雰囲気がこの作品のイメージを決定付けているようです。
またサックスのヒューストン・パーソンもいつものコテコテ・プレイから一歩離れ、スィートなメロウなサックスを聴かせてくれます。
当のリーダーのカーターなんですが、ラストの「オルフェのサンバ」で全編コントラバスで、メロディー&アドリブに大活躍してる以外は、はとんどバッキングに徹しているのです。自己の作品では、ピッコロ・ベースでメロディーをとったりと結構自己顕示欲の強いジャズ・メンにしては珍しいことです。
Tは今までのカーターのリーダーセッションで、いいと思った作品は、正直1枚もありませんでした。ピッコロ・ベースのメロディーや、クラシックのプレイヤーが聴けば卒倒するようなピッチのおかしさでやるクラシック作など…。カーターの自己満足以外の何者でも無い作品ばかり。ベーシストとしての才能は誰もが疑うべきところはありませんが、サウンド・メイクやプロデュースにおいては二流以下でしょう。
今回のボサ・ノーヴァ作ですが、推測ながら、このプロジェクトにはカーター自身はあんまり関わっていないように思うのです。もちろん、クレジット上はカーターのプロデュースなんですが、コンサヴァなカーターが、アグレッシヴなフリゼールを全編ギターでフィーチャーさせるなどの考えが思い浮かぶとは思えません。「ブラジル音楽がテーマです。パッケージはこんな感じです。お膳立ては完璧です。ではカーター先生宜しくお願いします。」そんな感じで作った作品のような気がします。だからこそ、本職であるリズム・マスターとしてのカーターの魅力がクローズ・アップされ、アルバムラストのカーター出ずっぱりの「オルフェのサンバ」も活きてくる感じがします。
夏らしいいい意味でのイージーリスニング・ジャズ的な作品ですから、今までTのようにカーターのソロ作を避けてきた人にもお勧めできる、肩の力の抜けた佳作です。ただSJ誌でゴールド・ディスクにするほどのインパクトがあるかと言われれば疑問ですが…。
8.19 Update |
|
★★★★ |
|
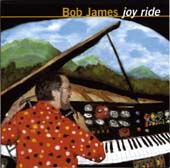
|
|
Bob James "Joy Ride" |
|
前作「プレイン・フッキー」から約2年ぶりとなる”フュージョン・マイスター”ボブ・ジェイムスの新作が到着しました。
まず今作の裏話から…。
今年の暮れにリリース予定のフォープレイの新作やその他の仕事を抱えてかなり忙しかったボブが、どうしてもソロ作を作らないといけないということで、たくさんのプロデューサーにバックトラックを依頼し、後でボブのピアノをオーバーダビングして完成、というスタイルで制作されたのがこの作品なんです。
プロデューサーには、チャック・ローブ、ポール・ブラウン、マイケル・コリーナ、ハービー・メイソンJr.、ディヴィッド・マクマレイ、マーセル・イーストが参加し、どのプロデューサーも、現在のスムース・ジャズ・チャートを強く意識したトラックを制作しています。その中で○だったのが、ボブとの共演歴も長いマイケル・コリーナです。コリーナ制作で、ザビヌル・シンジケート出身で今一番注目を集めているベーシスト、リチャード・ボナやリー・リトナーらが参加したタイトル曲が、ピョコタン、ピョコタンした昔のボブ・ジェームスを彷彿とさせる軽快なナンバーで、やっぱりボブ・ジェイムスのフュージョンはエエなと思わせるものでした。
その他のナンバーは、それぞれのプロデューサーのソロ作に、ボブ・ジェームスがピアノでゲスト参加したような感じのナンバーばかりです。また、ボブ自身の書き下ろした曲がチャック・ローブとの共作曲を含めてもたった2曲だけというのも納得出来ません。
チャック・ローブ制作のトラックには、ウィル・リー(b)チャック・ローブ(g)キム・ウォーターズ(sax)が、ポール・ブラウンのトラックには、ボニー・ジェイムス(sax)やトニー・メイデン、ノーマン・ブラウン(g)が、ハービー・メイソンJr.やマーセル・イーストのトラックにはネイザン・イースト(b)が参加など、これだけの面子を揃えると悪いサウンドとなる訳はありませんが、すべてが平均点。
正直、時間が無いのならやめておいてもよかったんじゃないという感じの内容です。
ただピアノやフェンダーローズのソロになると途端にボブ・ジェイムスの世界になるというのは、やっぱり凄いです。本物のボブ・ジェームスのソロ作は、年末のフォープレイまで御預けといった感じです。
8.23 Update |
|
★★★ |
|

|
|
Victor Bailey "Low Blow" |
|
ジャコの後を受け、ウェザー・リポートに参加し一躍注目を集めるようになったベーシスト、ヴィクター・ベイリーの10年ぶりとなるセカンド・リーダー作が日本盤先行でリリースされました。
もう10年も前のことなので、印象に残ってる人も少ないでしょうが、前作「ボトムズ・アップ」では、マイケル・ブレッカー、ウェイン・ショーター、ブランフォード・マーサリスからマーカス・ミラー、リチャード・ティーまでNYのジャス/フュージョン・シーンの大物が勢揃いしたオールスター作でしたが、この新作では、リズムセクションを、ヴィクター=オマー・ハキム、ヴィクター=デニス・チェンバースという2種類に絞り、ソリッドなバンド形式で、コンテンポラリーでR&Bテイストなエレクトリック・ジャズ(フュージョンにあらず)を聴かせてくれます。他の参加メンバーは、ジム・ベアード(key)ウェイン・クランツ(g)ビル・エヴァンス、ケニー・ギャレット(sax)などです。
この作品の聴き所はなんと言っても参加している2人のドラマーです。ヴィクター自身が、今作を制作するにあたって、単純でダルなリズムをやる気はなかったと語っているように、2人のドラマーとヴィクターは、ジャズやR&Bをベースにしながらも、凡庸なフュージョンとは一線を画すハイパーなビートを聴かせてくれます。
フレッティッド・ベースをフレットレスのようにウネウネと聴かせるヴィック(ベイリーの愛称)のベースは、はまると印象的ですが、さらっと聴くと結構地味な感じですが、誰が聴いてもスゲーと思うのが、デニスとオマーのタイコです。譜面にすると相当複雑なリズムを、R&B~ファンク仕込みのパワーとジャズで培われた最高のテクニックで、超ゴキゲンにプレイしています。手数が多くなり小技が利くようになったデニスと、少しレイド・バックした感じで力でおしまくるオマーという2人の最高のドラマーによる最高のプレイを聴けるだけでも買いの作品です。
ヴィックと2人のドラマーによるリズムがあまりにも印象的な為、他のミュージシャンのプレイがほとんど頭に残っていないのは、作品全体で考えるとちょっとマイナスかなという気もします。ベーシストやドラマー、それにそれらの楽器が好きなジャズ/フュージョン・ファンは必聴ですが、それ以外の人には、モノトーンで地味な作品と感じるかもしれません。
ヒューマンなグルーブを堪能する1枚。T的には買いです。
8.25 Update |
|
★★★★ |
|

|
|
Tower Of Power "Soul Vaccination~Tower Of Power Live" |
|
タワー・オブ・パワーですよっ!。新作ですよっ!。それもライブっ!!。わぁー、どないしよ~。
のっけから取り乱してしまうほどTが好きなバンドなんです。タワー・オブ・パワーは。
60年代後半からサンフランシスコで活動しているR&Bテイストなブラス・ロック・バンドであるタワー・オブ・パワーは、70年代初期に、地元のロックの殿堂であるフィルモア・オーディトリアムに出演し、一躍人気を集めました。その後は何度もメンバーの脱退等で解散の危機を迎えましたが、グループ結成当時からのリーダー、ミミの愛称で親しまれるエミリオ・カスティリオのグループへのこだわりにより、乗り越えてきました。70年代後半~80年代のグループ沈滞期を経て91年にアルバム「モンスター・オン・ア・リーシュ」をリリースして以降は、リズムの要とも言えるベーシスト、ロッコ・プレスティアもグループ復帰を果たし、コンスタントな活動を行うようになりました。
この新作となるライブ盤は1998年のワールドツアーでのカリフォルニアのステージをシューティングしたもので、何曲かは彼らの思い出の地フィルモアでのライブも含まれています。選曲も彼らの30年近くにも及ぶ輝かしい音楽キャリアを集大成したようなもので、「ホワット・イズ・ヒップ?」「ダウン・トゥ・ザ・ナイト・クラブ」「ユー・アー・スティル・ア・ヤング・マン」といった70年代初期の大ヒット曲から「ソウル・ウィズ・ア・キャピタル‘S’」「ソウルド・アウト」といった90年代以降のヒットナンバーまで幅広くセレクトされています。
メンバーは、リーダーのエミリオ、バリトンサックスのドク・クプカ、ベースのロッコ・プレスティア、ドラムのディヴィッド・ガリヴァルディ(祝!グループ復帰)以外は、オリジナル・メンバーではありませんが、グループの看板ともいえるファンキーなホーン隊とガリバルディ=ロッコのグループ全盛期のリユニオン・リズムセクションも、70年代中期の全盛期を思わせるファンキーさです。そのファンキーさの理由の一つが、95年の「ソウルド・アウト」から参加している黒人シンガー、ブレント・カーターです。リード・ヴォーカルに、曲間のMCにと大活躍の彼は、70年代中期のグループのヴォーカリスト、レニー・ウィリアムスを彷彿とさせるファンクネスとソウルをグループに注ぎこんでくれています。
サンプリングやプログラミングなどコンピューターによる擬似R&Bが幅を利かす中、こんなタワー・オブ・パワーのような汗や体臭のにおいがプンプンした人間の手による本物のR&Bを聴くと、まだまだR&Bもすてたものじゃないなと思わせてくれます。
最後に余談ですが、今作からグループ復帰を果たしたディヴィッド・ガリバルディ(ds)なんですが、あのディヴ・ウェックルがもっとも影響を受けたドラマーなんです。ここでのガリバルディのタイコを聴くと、ウェックルの「裏打ち」ビートのルーツがここにあることが実感できるはずです。
サンフランシスコのベイブリッジから吹く超ホットなR&Bストーム!。あんたの趣味やろ~!というつっこみは甘んじて受けますので、5つ星を付けさせて頂きます。ハイ。
8.25 Update |
|
★★★★★ |
|

|
|
Jeff "Tain" Watts "Citizen Tain" |
|
80年代中期にウィントン・マーサリスのバンドで頭角を現し、その後ブランフォード・マーサリスや故ケニー・カークランド、それに最近ではマイケル・ブレッカーのバンドでも活躍していた売れっ子ドラマー、ジェフ・ワッツの初リーダーアルバムが、米ソニーから登場しました。(サニーサイド・レーベルからリリースされていた、ケニー・カークランド:p チャールス・ファンブロー:b ジェフ・ワッツ:dsのメンバーからなる"J.F.K"というユニットの作品があり、実質的なリーダーはワッツだったそうですが、ワッツ名義のリーダー作としてはこれが初めてです。)
アルバムの初っ端、1曲目(The Impaler~コルトレーンとオハイオ・プレイアーズにインスパイアされた曲らしい?。)からアップテンポのスウィング・ナンバーが登場!。これはカッコ良いぞ!。いきなりのトランペット・ソロ何とウィントン・マーサリスで、それに絶妙なタイミングでバトンタッチして登場するテナーソロは、ブランフォードです。そして続いては今は亡きケニー・カークランドのピアノ・ソロ登場。ワッツも、それぞれのソロのバックで煽る、煽る。それに答えてウィントン、ブランフォード、カークランドが自分のソロ作でも見せないほどの大熱演。
続く2曲目はワッツ=カークランド=レジナルド・ヴィール(b)のトリオで、モンクのナンバーを彷彿とさせるような…、とまぁ全曲紹介してゆきたいほどの中身の濃い作品なんです。基本的には、ワッツ=レジナルド・ヴィール=カークランドのトリオに、ウィントンやブランフォード、ケニー・ギャレットらが参加するというもので、1曲ポール・モチアンの曲がある以外は全曲ワッツのペンによるナンバーが収録されています。
プロデュースはデルフィーヨ・マーサリスということで、全体の雰囲気は、「ブラック・コーズ」や「Jムード」の頃のウィントンと「ランダム・アブストラクト」以降のブランフォードの作風をミックスしたような感じで、結構暗めの曲が多いのですが、イントロでよく登場するワッツの豪快なソロや、絶妙なリズム・チェンジなどワッツの緩急をつけたタイコにより、ダルな印象や重すぎる印象はありません。やはり「ジャズはタイコだ」ということを改めて実感させられます。
それとやはり感じるのが、故ケニー・カークランドのピアノの素晴らしさです。バド・パウエル~ビル・エヴァンス~ハービー・ハンコックのラインの次ぎに繋がる類稀なジャズ・ピアノのスタイリストだっただけに彼の早過ぎる死は、ここでのプレイを聴くにつけ、残念を通りこして悔しくてたまりません。
80年代初期にウィントンが頭角を現し、それに兄ブランフォードが続いたという、その流れが80年代以降のアコーステック・ジャズのメインストリームを形成していった訳ですが、世紀末の今日に登場した、この作品はまさに、その流れを集大成したような感じとなっています。
またこの作品から21世紀に繋がるものがあるとすると、ウィントンとブランフォードの双頭コンボの結成です。これをきっかけに、2人のスケジュール調整が始まったという噂もあります。
とにもかくにも99年を代表するジャズ・アルバムになること間違いなしの、ワッツの初リーダー作。ジャズ・ファンなら絶対、聴かねばなりません。
8.25 Update |
|
★★★★★ |
|

|
|
Larry Goldings Trio "Moonbird" |
|
近作はメジャーのワーナーよりリリースしていたオルガン/ピアノ奏者ラリー・ゴールディングスですが、残念ながらメジャーとの契約が切れたようで、最新作は"Palmetto Jazz"という無名のマイナー・レーベルからのリリースとなってしまったようです。
前作はピアノ奏者としてのゴールディングスにスポットを当てたもので、耽美的なジャズ・ピアノの世界を追求しようとしたものでしたが、彼の豪快でグルーヴィーなオルガンでのプレイを期待した多くのリスナーを結果的に裏切るものとなってしまいました。
この新作では、ラリー・ゴールディングス(Org)ピーター・バーンスタイン(g)ビル・スチュワート(ds)というお馴染みのオルガン・トリオとなっており、まぁ一安心といった所です。
ラリーは、ジェイムス・ブラウンとの共演で知られるメイシオ・パーカー(as)のバンド出身なので、もちろんファンキーなのですが、それだけではない、良い意味でのクールさを持っているオルガン・プレーヤーです。そのあたりが、同じ若手白人オルガン奏者でも、ジミー・スミス直伝のコテコテ路線を猛進するジョーイ・デフランチェスコあたりと違う所です。
この新作でもオルガン・トリオ=コテコテのソウル・ジャズというイメージを覆す、クールな雰囲気の作品に仕上がっています。純粋な4ビートものは少なく8ビート系で、ちょっぴりダークでクールな雰囲気は70年代初期を思わせるものがあります。収録曲の中に、ジョニ・ミッチェルやランディ・ニューマンの曲があることからも、いつもとは違ったポイントにフォーカスが当っていることがうかがえます。
盟友ピーター・バーンスタインもソウルフルなグラント・グリーン・ライクないつもとは、ちょっと違って、ジョニ・ミッチェルの曲でのプレイなどはガボール・ザボを思わせるプレイです。
正直、あまりとらえ所の無いあいまいな雰囲気の作品ですが、この作品のどこか一部から新しいオルガンジャズの未来が生まれてきそうな気がします。
おまけトラック入り。
8.25 Update
|
|
★★★ |