U.Gallery
アメノチハレノチ… | ||
雨が降っている。ザーザーと唸りを上げて。
雨が降っている。雨音がリズムを奏でて、弾け、踊る。
俺は雨が嫌いだ。ブルマがふざけて俺に言う。俺が雨男だと─。
俺は雨が嫌いだ。雨はいつまでも──止まない。
今日も雨。
昨日も、一昨日も、確かその前も。
雨が降っている。窓ガラスに水滴の模様を描きながら。
「なぁ、ベジータ」
不意に俺の名前が呼ばれる。
「…………」
雨が──。
「ベジータ……何か嫌なことでもあったのか?」
雨が、止んだ。どうして、急に──。
「おっ?ここんとこずっと雨だったのに」
カカロットは、窓の外に視線を向けながら俺に話しかけてくる。俺も、外を見ていた。雲がさっと逃げ出して隠されていた太陽が顔を見せる。久しぶりの日差しが、部屋を照らした。
太陽の日差しに照らされたカカロットの服は輝くようなオレンジ色。差し込んできた光に溶け込んで、その幻想的な雄姿は言葉に窮するほどだ。俺はとり憑かれたように、ヤツの姿に魅せられてしまった。
「……ん? オラの顔になんか付いてるか?」
ヤツは少し戸惑いながら俺に問う。俺としたことが、思わず見つめ続けてしまったようだ。
「いや、そういうわけじゃない……」
「そっか」
ヤツは微笑んだ。
「オラ、晴れ男なんだってさ」
カカロットは笑ってそう言っていた。
「もしかしたら今晴れたのもオラのお陰かもな」
──晴れ男。それは自分と正反対の人間。俺の雨を今日一日で止めた、晴れ男。
俺は無愛想な、曇天が似合う雨男。
ヤツは明るく、まるで太陽みたいな晴れ男。
何もかもが自分と正反対だった。
だから俺は怖かった。ヤツが怖かった。
自分という存在が消されてしまいそうな、得体の知れない恐怖感。
「ベジータ」
名前が、呼ばれる。
「ベジータ?」
「……」
俺は声のする方へ目線をやる。ヤツと目が合った。カカロットと。
「なぁ、ベジータ。オラが……怖いのか?」
「……っ!」
単刀直入に問われ、俺は目を見開く。言葉を失うというのはこういうことなのだと初めて実感する。
カカロットはじっと俺を見ていた。俺も、カカロットを見ていた。
人は光を、温かさを望むものだ。そしてついにそれらを満たす存在が蘇った。今まで日陰で生きてきた自分は、もはや厄介な邪魔者──諸悪の根源でしかない。
──だから。
「もうここへは来るのは止めてくれ。」
外は──雨。
ザーザーと降り続く雨は、部屋の窓ガラスを延々と叩いている。
「……ベジータ!」
名前が、呼ばれた。その瞬間、得体の知れない恐怖が俺を怯えさせる。俺の顔がひきつって色を失くした事に狼狽える。
「来るなとあれほどっ!」
「逃げるなよ」
「……っ!」
腕をがっしりと掴まれる。俺はびくともしないその腕へ目線をやった。
目が、合った──カカロットと。
「この雨に濡れてたら──おめぇに会いたくてたまんなくなった」
「……」
見ればカカロットの服も髪もびっしょりと濡れていた。
「おめぇがいないと、だめなんだ」
カカロットは俺の腕を掴んだまま、小さく小さく呟いた。
「晴れ続けると花も草木も全部枯れて、やがて何もかも朽ちちまう」
腕を引かれて、ヤツの胸に俺の体が包まれた。どれだけの時間雨に打たれていたんだろうか。肌が、とても冷たい。
「雨はめんどくさくて鬱陶しいかも知れねぇけど。でもオラは、オラだけはお前が必要なんだ」
「……!」
ぎゅっと俺を抱きしめるカカロットの力が強まって、カカロットの表情が寂しくなって。
「カカロッ……ト」
ああ、もしかしたらカカロットも罪悪感に苛まれていたのかもしれない。俺と同じように。
明るすぎても暗すぎても、花を枯らせ草木を朽ちらせる。晴れ続けるのも、雨が降り続けるのも──結局は同じなのだ。
「ベジータ、ずっとオラの側にいてくれよ」
対の存在でありながら、自分と一番近い男。
ああ、必要とされることが、こんなに心地良いなんて。
──カカロット。
俺は力を抜いて、そっとヤツに体を預けた。
冷えた身体を案じて着替えを促す。しかしヤツは衣服を脱ぎ捨てると、そのまま俺をベッドへ押し倒した。
初めは抵抗していたが、ヤツに慣らされた身体はあっさりとそれを放棄する。
「あ、ぅ……」
「最高……」
「ん、あ、あぁぁっ……!」
その衝撃と痛みと──認めたくない既知の快楽が俺を襲う。
信じられるか?この俺がお前がいないと、だめだなんて。
ヤツは幸せそうな顔でにっこり笑う。身体の奥にヤツを感じる。
待ち望んだ、突き抜けるような快感。抑えきれない歓喜の声。
下腹部に与えられる陶酔感が一点に集中して、大きな波を生む。
「あっ、っ……あぁ、……くっ……!!」
痛快なほどの衝撃。身体の芯をゆするような、信じられない気持ち良さが俺を襲った。それと同時にぴくぴくと小気味よく悶える俺の肢体。とろけるような悦楽にうっとりと放心する。
「あ……」
──雨が。
「お、晴れた」
カカロットも俺の視線の先を追って、笑った。
「今晴れたのはやっぱオラのお陰かもな」
「そうだな……」
俺も笑った。雨上がりの空は、オレンジ色。壁にかかるヤツの服の色。
──雨が、止んだ。
「もう少し……こうしていたい」
「あぁ……」
部屋に差しこむ夕日がヤツを照らした。その彩られたまぶしさを素直に美しいと思った。
Fin
 back
back
.
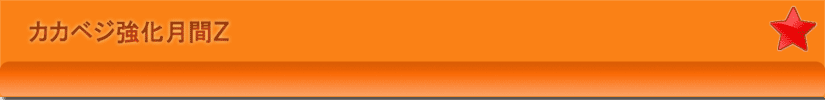
 U.illust/Novel / イラスト小説
U.illust/Novel / イラスト小説 BBS / 掲示板
BBS / 掲示板