![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@���C���{���͓����`�_�˂̂��Ƃ��w���Ă��邪�A���܂�ɂ��������������߂ɂ������ɕ����邱�Ƃ��o����B
�܂���Ђŕ�����ƁA�����`�M�C��JR�����{�A�M�C�`�Č���JR���C�A�Č��`�_�˂�JR�����{�ł���B
�X��JR���C���́A�M�C�`�L���̐É����ƖL���`�Č��̖��É����ɕ����邱�Ƃ��ł���B
���̃y�[�W�ł́A�����Ȃǂ̗D����Ԃ��p�ɂɉ^�]����閼�É����ɂ��Č��Ă݂�B
�@���É����̓����Ƃ��ẮA���ʉ����A�V�����A�����A��ԉ����ɑ�\�����D����Ԃ��p�ɂɉ^�]����Ă��邱�Ƃł���B
�I��15�`20���Ԋu�ɑ����Ă���A��s�s���̎��S�Ɠ������炢�̊Ԋu�ő����Ă��ė��p���₷���B
���̓_�A�������̓��C���{���́A�����u�A�N�e�B�[�v��Ó�V�h���C�����ʂ̓��ʉ����������Ă��邪�A1���Ԃ�1�{���ł���B
�܂�����1�̑傫�ȓ����Ƃ��āA���É������łȂ������̒��K�͓s�s�ւ̒ʋE�ʊw�������Ƃ������Ƃ���������B
�������ł́A�����b�V�����͏��A�[���b�V�����͉���ւ̗��ꂪ�傫���A����I�ȕЗA���ƂȂ��Ă��邪�A
���É����́A�V������ԉw�̋��S�͂������āA
�L���`��_�͖��É��𒆐S�Ƃ����i�q���C�ݗ����̃h������ԁB
���É��ւ̋��S�͂��������A��s���̂悤�Ɉ���I�ȕЗA���ł͂Ȃ��A
�V�����̒�ԉw�ɂȂ��Ă���悤�Ȓ��K�͓s�s�ւ̋��S�͂����Ȃ肠��B
�������A��s���⋞��_�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�A���ʂ͏��Ȃ��A�Q�`�W���̗�Ԃ��P���ԂɂW�{���x�B
�D����Ԃ�����������A�ɋ}�ڑ����s���Ă��邱�Ƃ���e��͂��قǂ̍��G�ł͂Ȃ����A�D����Ԃ͓����ł������Ƃ������Ƃ������B
�ݗ����̐V�^�ԗ������������ƁA��������Ԃɉ���Ă���i�R�P�R�n�͑����x�ꂽ���ǁj�B
�܂��A�قƂ�ǂ̋�ԂŖ��S�ƕ������Ă��邱�Ƃ���A�X�s�[�h�A�b�v���^����ɂ���A�V����������̕\�葬�x�͂P�O�O�L�����z�����Ԃ�����B
���̈���ŁA��_�`�Č��͓��C���{���̒��ōł��A���ʂ̏��Ȃ���ԁB
�ɐ��R�Ɨ{�V�R���̊Ԃ��邽�߂ɐl�����ȑ��A�}���z�������A��a��z���A����R�z���ƕ���œ��C���{���̓�Ƃ���Ă���B
����A�փ����͂��������̏�~�q�͂��邪�A�������͊ՎU����ƂȂ�B
���܂ł͓����P���ԂɕČ��n�������P�{�A�փ����n�������P�{���������A�悤�₭�����P�P�N�P�Q���̉����ŁA�Č��܂łP���ԂQ�{����悤�ɂȂ����B
����͓��C���{���̖��É����ɂ��Ď��グ�Ă݂�B
��ɖL���`��_�̕����P�P�N�P�Q���̉����O����r���Ă��������B���̍ہA���̃_�C���������u�����v�Ɗ��ʕt���ŕ\�L����B
�@
�@
�w�f�[�^
�L���͓��C���{�����S�`�W�Ԑ��̂R�ʂT���ŁA�ѓc�����P�E�Q�Ԑ��̂P�ʂQ���A���É��S�����É��{�����R�Ԑ��̂P�ʂP���Őڑ����Ă���B
���̑��ɓ��C���V�����A�L���S���������i�V�L���j�A�L���S�����c�{���i�w�O�j�ƘA�����Ă���B
�ѓc���Ɩ��S�͖L���n�������܂Ő��H�����L���āA�����Ƃ��ė��p���Ă���B
�܂��ѓc���Ɩ��S�̃z�[���͂Ȃ����Ă��邪�A���C���{���̂S�Ԑ��Ƃ��Ȃ����Ă���A���̂�����ѓc�������S�ł��������Ƃ�������B
�k���ɂ͑傫�ȉw�r���������A�L���S���O�������w�߂��܂ʼn��L����芷���₷���Ȃ����B
�����̏Z���́A���É��܂œ��C���{���Ɩ��S�̑I����Ԃ��o���邪�A
���ԓI�ɂ͂قړ����A�����I�ɂ͖��S������A��Ԗ{���I�ɂ�
���C���{�����V�����Q�A�����Q�A���ʂQ�A���S�����}�S�A�}�s�Q�ł��܂�ς��Ȃ�
�i���S�̋}�s�͒�ԉw�������i�q�̕��ʂɑ������A���}�����B�^�C�v�ƕW���^�C�v������j�B
���É��܂ł́A�����ɂP�P�V�n����Ɏg�p����Ă������́A�X�s�[�h�̈Ⴂ����R�P�P�n�V�������T���x�������B
���̂��߁A�����ƐV�����͂P�T���Ԋu�ł͂Ȃ��P�O�E�Q�O���Ԋu�ƕ��Ă���A���v���Ԃ������邱�Ƃ�������͌h�����ꂪ���ł������B
�������u�����v�œ����̉������P�Q�O�L���ɃX�s�[�h�A�b�v����A�V�����Ƃ͓������x�ɂȂ������߁A�P�R�E�P�V���Ԋu�ɏk�܂��Ă���B
��������͂Q�ʂS���̉w�B���̗��O���ɂ͍X�ɑ���������B
���Ă͊O���̐��H�͎g���Ă��Ȃ��������A�u�����v�Œǂ��z�����s����悤�ɂȂ������߂Ɏg����悤�ɂȂ����B
�����Ƃ��Ă��邪�����䣂͔ѓc���ɑ��݂��A������͖����R�P�N�R���P�R�����炷�łɂ������B
���Ă͓����P���ԂɂR�{�̊e�₪�����Ă������A�u�����v�łR�O�����ɂȂ��Ă��܂��s�ւɂȂ����B
���m����͂i�q�^�z���B�������Жʃz�[���{�{���A������������z�[���ɂȂ��Ă���B
�ǂݕ��͢�������݂���ł���B�����͌���ƌĂ�Ă������A�����̏h�꒬�Ƃ͂S�L������Ă����̂Œ�������邱�ƂɂȂ����B
���̍ہA�����̢��ã�ł͢���ˣ�ƍ������Ă��܂��̂Ţ���m����t����ꂽ�B
���������ʂȂ碎O�ͣ��������͂��ł���B����T��{��⢒������R��ƕ���œ�ȉw���ł���B
���̉w���u�����v�ɂ���ē����P���ԂɂR�{����R�O�����Ɍ����Ă��܂����B
�O�͑���͑��Ύ��z�[���B���炩�ɑ��̉w�ƌ`�����Ⴂ�A���ɂł����w���Ƃ������Ƃ�������B
���H�͒z���ɂ��邪�w�ɂ͒z��̉��ɂ���B���̂��߂ɉw�ɂƃz�[���͒n�����łȂ����Ă���B
���Ƃ��Ƃ͉���ԏ�Ƃ��ĊJ�Ƃ��ꂽ�w�ł��������A���a�R�T�N�R���P���ɂ߂ł����w�ւƏ��i�����B
���̉w���������A���m��ÂƓ��l�ɗ�Ԗ{���������Ă��܂����B
�O�͎O�J�����Ύ��z�[�������A�㉺�{���̊Ԃɒ������P�{����B
�����͂����炭�ݕ���Ԃ̑Ҕ����舵�����ɍ��ꂽ���̂Ǝv���邪�A���݁A�L�����͏㉺�{���ɂȂ����Ă��Ȃ��B
���Ύ��z�[���Ȃ̂ŁA���̉w�����炩�ɊJ�ʓ����̉w�łȂ����Ƃ�������B
�u�����v�O�͓����P���ԁi�Q�O�����ł͂Ȃ��A�����Ԃ�Ă����j�Ɋe��R�{�Ɖ����Q�{����܂��Ă����B
�u�����v��͊e�₪�R�O�����A�������P���ԂɂP�{�i�Q�{�ɂP�{�̊����Œ�܂�j�ƌ����Ă��܂����B
�����̂����P�{�̕��́A�O�͎O�J�ł͂Ȃ��K�c�ɒ�܂�B
��Ԗ{���͍K�c�Ɠ��������A�u�����v�O�̍K�c�͂P���ԂɊe�₪�R�{��܂��Ă��������������B
���̂��ߍK�c�͉�������܂镪�֗��ɂȂ������A�O�͎O�J�͕s�ւɂȂ��Ă��܂����B
���S�͖��S���S���ƘA�����Ă���B
�����z�[���Q�ʂS���Ŋɋ}�ڑ����ł���悤�ɂȂ��Ă��āA�S�Ă̗D����Ԃ���Ԃ���B
�u�����v�O�͊ɋ}�ڑ����s���Ă������A���݂͒����b�V�����ȊO�s���Ȃ��Ȃ����B
���S���S���͓쑤�ɓ����̍��˃z�[��������A�i�q�ƌא��������L���Ă��̂܂܂Ȃ����Ă���B
���R�̂��ƂȂ��犗�S�s�̒��S�n�ŁA�L���`����̓r���w�ł͈��|�I�ȏ�~�l�����ւ��Ă���B
�܂��ʋΒʊw�ȊO�ɂ��A�O�͘p��������̒��S�n�Ƃ��Ċό��q�������B
�O�͉����͖��S���S���i���S������O�j�ƘA�����Ă���A���S�ɍs���ꍇ�͑I����Ԃ��邱�Ƃ��ł���B
�i�q�͑��Ύ��z�[�������A�쑤�ɖ��S���S���̕Жʃz�[��������A��������w�ɂ���z�[���ɍ~��邱�ƂɂȂ�B
���a�S�R�N�P�O���P���ɂ��łɖ��S�̉w�͂ł��Ă������A���a�U�R�N�P�P���P�U���ɂi�q�̉w���ォ��J�Ƃ����B
�J�ʓ����͊��S�`�K�c�V�D�X�L���̊Ԃɉw�͂Ȃ��A�ߔN�ɂȂ��Ă���Q���w�����ꂽ���ƂɂȂ�B
��~�l���͐����Ə��Ȃ����A����͖��S�ƃp�C�������Ă��邱�Ƃ�����̂��낤�B
�܂���~�l�������Ȃ��̂ŁA�������Ƃ��̉w�����́u���[�����C�g�Ȃ���v�����Ԃ͒�܂�Ȃ��B
�������������`�O�͑�˓��l�ɓ����P���ԂɊe�₪�R�{�ł��������A�u�����v�Ȍ�͊e�₪�R�O�����ɒ�܂邾���ɂȂ��Ă��܂����B
�O���������Ύ��z�[���̉w�ŁA�J�Ɠ������狴��w�ɂɂȂ��Ă���B
���̍����瑊�Ύ��z�[���ŋ���w�ɂƂ����p�^�[���������Ă����悤�ł���B
�������O�͉��Ó��l�A�����͊e��R�O�����ɂȂ��Ă��܂��s�ւɂȂ����B
�K�c�͐��m�ɂ����Ƃi�q�^�z���ł��邪�A���ݎg���Ă���̂͌א�����n���������z�[�������ł���B
�u�����v�ȑO�͓����P���ԂɊe��R�{���������A�u�����v�Ȍ�͊e�₪�R�O�����ɂȂ�������ɁA
�����̂Q�{�ɂP�{�i�O�͎O�J�ɒ�Ԃ��Ȃ����j����Ԃ���悤�ɂȂ�A�{���I�ɂ͕ς���Ă��Ȃ��B
�����ɏ��X���[�Ŗ��É��ɍs�����Ƃ��ł��邱�Ƃ���A���̕��֗��ɂȂ����Ƃ�������B
�܂��A���̉���������Ŏn���̊e��ɐڑ����邱�Ƃ���A���肩�琼�̊e�w�ɍs�����Ƃ��ł��邪�A
�Q�O�E�P�O�E�R�O���Ԋu�ƕ��ω�����Ă��Ȃ��̂Łi�d���̂Ȃ����Ƃ����j�A���̓_�͏��X�s�ւ��B
�����͈��m��S���Ɛڑ����Ă���B
�i�q�͓����Q�ʂS���ŁA���̖k�Ɉ��m��S���̕Жʃz�[���i�O�Ԑ��j������B
���m��S���͉w�̐��ň�x���C���{���ƍ������A������x�㉺���̊Ԃɕ��āA���C���{�������̉����������č������Ɍ������B
���̂��̂悤�ȕ��ʌ����ɂȂ������ƌ����A���m��S���͂��Ƃ��ƍ��S�������i����`�������j�Ƃ��Č��݂��ꂽ����ł���B
�������͉���`�L�c�`���ˁ`�������`����`�������̋{�`���E���f���Ƃ����O���[�g�̈ꕔ�ŁA�ݕ��^�A���s���Ƃ������̂ł������B
�������A�ݕ���Ԃ̐��ނƍ��S�̍����Ԏ��ŖL�c�s�܂ŊJ�ʂ������_�œ�������A
���̌�R�Z�N�̈��m��S���������p���A���������獂�����Ƀ��[�g�ύX���S�ʂ������̂ł���B
�����̓��C���{���͒�������Ԏ�̂Ŗ{�������Ȃ��A����ȏ�ɉ������̖{�������Ȃ������̂Ŗ��͂Ȃ������̂����A
���݂͓��C���{���͓����P���ԂɂW�{�A���m��S���͂Q�O�E�S�O�����̂Q�{�܂ő����āA���ʌ����ł͌��E�ɋ߂Â��Ă���B
���C���{���͂P�T���T�C�N���i���m�ɂ����ƂR�O���T�C�N���j�A���m��S���͂Q�O���T�C�N���i���͂Q�O�E�S�O���Ԋu�����j�Ńp�^�[�������킸�A
���̂��߂Ɉ��m��S�������S�ɂQ�O���Ԋu���ł��Ȃ����̂Ǝv����B
���C���{���͂����܂ŁA�R�O���T�C�N���ɐV�����A�����A�e�₪�e�P�{���������A��������܂Ŋe�₪�����P�{������B
�L������̊e��͂����ŐV�����Ɛڑ����A���w�n���̊e��͉����ɐڑ����ďo������悤�ɐݒ肳��Ă���B
��������̐V�����Ɖ����͋��a�ɒ�܂邩��܂�Ȃ��������Ȃ̂ŁA�����悻�P�T���T�C�N���ƌ������Ƃ��ł���B
��~�l���͂��Ȃ葽���������A���m��S�����ڑ����Ă��銄�ɏ��Ȃ��B
����͎s�X�n���痣��Ă��邽�߂ŁA�s�X�n�ɂ���͖̂��S���É��{���̓�����ł���B
���̂��߁A���Ă͖��S����s�X����������Ɖ���̊Ԃ�����ł������Ƃ�����B
�������͑��Ύ��z�[���ŋ���w�ɂƂ����A�����ɂ��ߔN�ł����悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B�B
���ۂɎO�͈���A���ȂƂƂ��ɏ��a�U�R�N�R���P�R���ɂł����V�����w�ł���B
����`����͂V�D�W�L���̂قڒ��ԓ_�ɍ���A�i�q�ɂȂ��ċߋ����A���ɖڂ������n�߂����̂�����ł���B
�����͂R�ʂS���Ƃ����ϑ��z�[���B
�����z�[���𑊑Ύ��z�[���ŋ��\���ƂȂ��Ă��āA�w�ɂ͓쑤�̉w�r�����ɂ���B
�����̓����z�[�����㉺�{�������A�R�ʂS���̂��߂Ƀz�[�����芷���ɂ��ɋ}�ڑ��͂ł��Ȃ��B
���̂��߂��A�����b�V�����������Ċɋ}�ڑ��͍s���Ă��Ȃ��B
�����������b�V�����ł����Ă��A���̉w�Ŋɋ}�ڑ�����̂͊��S���Ȃ��B
�ǂ����ē����z�[���Q�ʂS���ɂ��Ȃ������̂����s�v�c�ł���B
�����炭�����͂i�q�^�z�[���ɂȂ��Ă��āA��Ԗk���ɕЖʃz�[�������ՂɈ����t�������炾�낤�B
�i�q�^�z�[�����瓇���Q�ʂS���ɂ��邽�߂ɂ́A�w�ɂ̎��A�w�Ɏ��ӂ̗p�n�����Ǝ����������邩�炩������Ȃ��B
�܂��A�����̈�͏o�Ȃ����c�N�����̍\���ɂȂ����o�܂�m���Ă���l���������炲�����B
���̉w�͎s�X�n��W���ɉw���ł����̂ł͂Ȃ��A�c���n�тɉw������A���̌�ɏW�����ł����悤�ł���B
���ۂɈ���s�́u���{�̃f���}�[�N�v�Ə̂����قǂ̔_�Ɛ�i�n�тŁA���̒��S�w�Ƃ��Ė�����S���Ă���B
�O�͈����͓��C���V�����ƘA�����Ă���B
�ݗ����ƐV�����̉����Ȃ������_�ɓ����ɐV�w��݂����H�L�ȗ�ł���i���ɂ͌������炢�����Ȃ��j�B
�ݗ����͑��Ύ��z�[���A�V�����͂�����V�����^�z�[�������Ă��āA
�ݗ����̏�ɋ���w�ɂ�����A��������V�����z�[���ւ̘A���ʘH������B
�V�����ƘA��������̂́A�V�����́u�����܁v������܂炸��~�q�����Ȃ���ɁA
�ݗ����̏�~�l��������Ȃɑ����Ȃ����Ƃ���A�V��������������܂炸�ɂP�T�����̊e�₾������Ԃ���B
�V�������p�^�[���_�C���ɂ��A���߂ĉ��������ł���߂ė��ւ�}��ׂ��ŁA�����łȂ��Ȃ�w��ݒu�����Ӗ������܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�����J�͑��Ύ��z�[���ŋ���w�ɂƂ����ߔN�̂ł����w�̃^�C�v�ł���B
�Ƃ͂������̂ł����̂͏��a�S�P�N�ł���قǍŋ߂ł��Ȃ��B
�����z�[���E����w�ɂƂ����`�̉w���o�n�߂����̉w�Ƃ�����B
���J�͖��S�O�͐��ƘA�����Ă���B
�����z�[���Q�ʂS���̋���w�ɂɂȂ��Ă��āA��ɂ��铇���z�[���̎O�͐��ւ̘A���ʘH���o�Ă���B
�����͂����ŕK���ɋ}�ڑ����s����B
�����̎��͖��É��Ŋɋ}�ڑ�����̂ŁA���J�`���R�E���É��͂ǂ̗�Ԃɏ���Ă���ԑ��������A���ɗ����̂����w�ł���B
�u�����v�O�̉�����́A�H���Ńz�[���̐����������Ă���s����A���É��Ŋɋ}�ڑ������Ɋōs���Ă����B
���̂��߁A������{��֍s���ꍇ�ł��e��ɏ�邱�Ƃ͂ł������A�̎�O�܂ŗ���Ɗe��ɒǂ����Ă��܂��悭�x�����Ă����B
�u�����v�ɂ�������{�E�֍s���̂Ɋe��ł͓r���Ŕ�������邱�ƂɂȂ������A�����̂Ȃ��_�C���ɂȂ����B
���J�͔Z������̒��ł��A�L�c�s�ƕ��ѓ��ɋ@�B�H�Ƃ����B���Ă���B
���̂��߂���~�l���́A���C���{���i�L���`��_�j�̒��ł��g�b�v���x���ł���B
�����͑��Ύ��z�[���B
�w�̓��͌@����ɂȂ��Ă��āA�w�ɂ͂��̌@���̏�ɐݒu����Ă���A�z�[���ւ͍~��邾���ōςނƂ����\���ɂȂ��Ă���B
�ߔN�A���R�ʘH�̖�����������������w�ɂ����s���Ă��邪�A���̃^�C�v�̉w�͕K������~�肪�K�v�ɂȂ�Ƃ������_������B
���̓_�A���Ȃ̂悤�Ɍ@����̉w�́A�w�O�Ɖw�ɂ͏���~��Ȃ��ňړ��ł���Ƃ������z�I�ȍ\���Ƃ������Ƃ��ł���B
���̉w���V�������A���J�܂łP�D�X�L���A��{�܂łR�D�O�L���Ə������Ăł����B
��{�͕��L���Ɛڑ����Ă���B
�R�ʂS���̕ϑ��z�[���ŁA���Ύ��z�[���̐^�ɓ����z�[�������`�ɂȂ��Ă���B���̂��߁A�����ł̓z�[�����芷�����ł��Ȃ��B
�O���̑��Ύ��z�[���͓��C���{���㉺�����A�����̓����z�[���͕��L���܂�Ԃ���ԂƓ����̖��É��X���[��Ԃ��g�p����B
���̕��L���́A���C���{�������Ɨ��̌������Ă��āA���݂��ɋ������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B
�z�[�����芷�����ł��Ȃ����Ƃ������āA�����Ŋɋ}�ڑ��͂���Ȃ��B
�����������b�V�����́A���L������̋�ԉ������R�Ԑ��ɁA�L������̓��ʉ������S�Ԑ��ɓ����i���A
���ʉ����͂��̂܂܍����Œʉ߂��A��ԉ����͓��ʉ����̏o���P����ɏo���A
����ɓ��ʉ����Ɗ��J�Ŋɋ}�ڑ������e�₪�A��ԉ����̂Q����ɂS�Ԑ��ɓ�������Ƃ����_�Ƃ݂����Ȃ��Ƃ��s����B
�u�����v�O�͕��L���̋C���ԁi�L�n�Q�W�E�T�W�E�S�V�j���x�����Ƃ������ĂقƂ�ǖ��É��ɏ�����Ȃ��������A
�L�n�V�T�ɑS�Ēu������蓌�C���{���̉����ȂǂƑ��F�Ȃ�����ɂȂ������߂ɁA���ʗ�Ԃ͑啝�ɑ����A
���L�����ƂƂ��ɓ��C���{���̑�{�`���É����{���������ĕ֗��ɂȂ����B
�w�̓쑤�ɂ͑������L�����Ă���A�w���œ��C���{�������Ɨ��̌����łȂ����Ă��āA���L���Ƃ��Ȃ����Ă���B
�Ȃ����̌����ɂȂ��Ă��邩�܂ł͒肩�łȂ����A��{�`���É��̉ݕ��ʐ��ɂ�镡�X�������v�悳��Ă������Ƃ��炻�̊W�Ǝv����B
���������̉ݕ����͌��NJJ�ʂ��Ȃ��܂ܕ�������Ă��܂��A���݂ł����ˋ�����H���c���Ă���B
���̉w�͂��Ƃ��ƕ��L�`���璆�R�������̌��ݎ��ނ�A��������H��ɐ݂���ꂽ�B
�����͓����`�������ԘH���͒��R���o�R�Ōv�悳��Ă����̂ł���B
���̂��ߖ��É����ŏ��߂ĊJ�ʂ����͕̂��L�`���É��ŁA���̌�A�ؑ]��A���[�i���F�j�Ɩk�サ�Ă������̂ł���B
�����������v�悪���R�����瓌�C���Ɉڂ����ɂ������āA���̉w�œ����猚�݂���Ă����H���Ɛڑ����A���L�`��{�͕��L���ƂȂ����B
�܂�A���Ă̕��L���͓��C���{���̈ꕔ�Ƃ��Č��݂���Ă����̂ł���B
���ꂪ�؋��ɁA�ʏ퉺���ԂƂ����Γ��C���{�����番�Ă������������ԁA���C���{���Ƃ̐ڑ��w�Ɍ�������Ԃ����������A
���L���̏ꍇ�A��{�Ɍ��������������ԁA���L�Ɍ�������������ԂƂȂ��Ă���̂ł���B
���a�͖��É��ߕӂł͒������i�q�^�z�������Ă��邪�A�w�ɂ͋���ƂȂ��Ă���B
������������z�[���ƂȂ��Ă���A�z�[�����芷�����ł���悤�ɂȂ��Ă��邪�A���݂��̉w�Ŋɋ}�ڑ��A�ǂ��z���͍s���Ă��Ȃ��B
�u�����v�̍X�Ɉ�O�̑�����܂ł́A���̉w�Œǂ��z�����s���Ă����i�m���ɋ}�ڑ��͂��Ă��Ȃ������Ǝv�����c�j�B
��x���a�P�T�N�P�P���P���ɋx�~�w�ƂȂ������A�푈�����̏��a�Q�O�N�V���P�P���ɕ������Ă���B
����͔p�~�A�x�~�̑��������푈���ł͈ٗ�̂��ƂŁA�����炭�H��̊W�ŕ����������̂Ǝv����i��{�ɂ͍q��@�̍H�ꂪ�������j�B
�卂�͓����z�[���ŁA���X���v��̂Ƃ��Ɉꏏ�ɍ��ˉ�����Ă���B
���ۂɖ{���쑤�ɂ͂����P����������A�k���ɂ͕ʂ̍��˂ŐV�������������Ă���B�������쑤�ɂ��镡���͌��ݎg���Ă��Ȃ��B
����͓���ݕ����ƂȂ��āA�}�����甪�c�ݕ����[�h���������̂ł��������A�ݕ��̐��ނɂ��H���r���Œ��f����Ă��܂����B
���݂ł����̕����̑��ɁA�}�������ɍ��ˋ����c���Ă�����A�V�����������˂Ōׂ��ł�����Ƃ��낢��Ȉ�\�����邱�Ƃ��ł���B
�ƌ��������A�������ɂł����H��~�݂��ĉc�Ƃł������ȏ�ԂŎc���Ă���B
�������疼�É��s�ɓ���A�e��݂̂̒�ԉw�ł���~�l�����O���Ƒ����Ȃ�B
���̂��߂������b�V�����̂R�{�̋�ԉ����͂��̉w�ɂ���܂�悤�ɐݒ肳��Ă���B
����́u�����v�O�̒����b�V�����͊e���̂ŁA���������s�_�C���ɂ��Ė{���𑽂����点�Ă������A
�u�����v��͗D����Ԏ�̂̃_�C���Ƃ��āA�e�₪���b�V�����ł��P�T���Ԋu�ɂ�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������߂̑[�u�ł��낤�B
�}����������{�Ɠ����悤�ɂR�ʂS���̕ϑ��z�[���B
�������u�����v��͂����Œǂ��z�����s���Ȃ��Ȃ������߂ɁA�O���̑��Ύ��z�[���������g���Ă���B
����w�ɂƂȂ��Ă���A��Ɍ������ĉݕ��^�[�~�i�����ׂ������א������˂����Ă��āA�A���[�i�Ȃǂɒ������Ă���B
�쑤�ɉݕ��^�[�~�i�����L�����Ă���A�k���ɂ͐V�������n���܂ō~��đ����Ă���B
���̐V�����͊}���̐�ő傫�����J�[�u�i�����ʂɌ��������j���ē��C���{�����ׂ��ł���B
����ɉ����悤�ɐ����̉ݕ����������\�肾�����B
�܂�}�������C���{�����q���Ɖݕ����̕���w�ł������̂ł���B
���̉w�͊J�ʓ����͐ݒu����Ă��Ȃ��������A�펞���ɍH��ւ̒ʋΎ҂�Ώۂɍ��ꂽ�Ƃ����O���������Ă���B
���݂ł����ӂɍH�ꂪ�����ʋΎ҂��������A���ɂ��}���ω���A���[�i�ւ̗��q�������B
�M�c�͓����Q�ʂS���̃z�[�������A�O���̕��{�����g���邱�Ƃ͂Ȃ��A���݂͑��z�[���̂悤�Ɏg���Ă���B
�w�̍\���ɂ͉��{���̑���������A�w�̖k���ɂ͓��{���p�̍H��������A�����̎ԗ������܂��Ă���B
�L���ȔM�c�_�{�͉w�̓쑤�ɂ���A�����ւ̎Q�q��������ł��̉w�����ꂽ���̂Ǝv����B
�������̌�y�ƌ����Ύ��Ђւ̎Q�q����ȖړI����������ł���i�����Ȃǂ͂��̍ł����j�B
���݂̏�~�l���͎��͂̉w�ɔ�ׂđ����͂Ȃ��A�D����Ԃ͂���������܂�Ȃ����A
���Ă͋}�s����܂��Ă������A���R���ł���O�܂ł͉�������܂��Ă������Ƃ�����B
���R�͒����{���A���S���É��{���A���튊���A���É��s�𖼏���A���S�����ƘA�����Ă��閼�É���Q�̃^�[�~�i���ł���B
�k�����璆���{�������̂P�E�Q�ԃz�[���A���S���É��{�������Q�ʂS���̂P�`�S�ԃz�[���A���C���{�������̂R�E�S�ԃz�[���ƂȂ��Ă��āA
���S���Ԃɋ��ς�����z���ɂȂ��Ă���B���R�A���C���{���ƒ����{���̐��H�͂Ȃ����Ă��Ȃ��B
�Ȃ����̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂����̂��́A�������C���{���ɉw���Ȃ��������Ƃɂ��B
���C���{���̋��R�w���J�Ƃ����͕̂������N�V���X���ƂȂ��Ă��邪�A���a�R�V�N�P���Q�T���ɂ͒����{���̋��R�w�����݂̐ݒu����Ă����B
���̎��A���S�̉w�͋��R���Ƃ������O�Ō��݂̈ʒu����L�����ւS�O�O���[�g���قǂ���Ă������B
���a�S�Q�N�R���R�O���ɂ͖��É��s�𖼏�����J�ʁA�o���o���ɂ������w�����݂̈ʒu�ɓ�������v�悪���サ���B
�����ĕ������N�ɋ��R�����w���J�Ƃ���Ɠ����ɁA���C���{���̋��R�w���ݒu�A
�����Ƀ_�C�������ŐV�������ݒ肳����R�ɂ���܂�悤�ɂȂ����B
�w�͌@����ɂȂ��Ă��āA���̏�����R�ʘH���ђʂ��Ă���B
�i�q�Ɩ��S�̉��D�͂��̒ʘH������ł��āA�i�q���ʘH���ʖ��É����A���S���ʘH���ʖL�����ɂ���B
�n���S�͒ʘH�k�[����n���ɍ~��Ă����G�X�J���[�^�[������B
�i�q�E���S�ƒn���S�̏�芷���ɂ͈��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�n���S�̃A�N�Z�X���ǂ����Ƃ��炻��ȂɋC�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���݂ł͖��É��Ɏ�����~�l���ƂȂ��Ă��邪�A���̑����͂��̂܂ܒn���S�ʼnh���ʂɌ������B
���̉w�̐ݒu�ɂ���āA���É��E���R���o�R�ʼnh���ʂɍs���Ă������̂�������o�R�ɂȂ��āA���R���̍��G�ɘa�ɂ��𗧂����B
�܂��h���ʂłȂ����É��A�h�Ɏ����^�[�~�i���Ƃ��ē��w���Ԃ������Ȃ��Ă���͂��ł���B
�����P�P�N�ɂׂ͗�Ɂu���É��{�X�g�����p�فv���ł��āA�V���ȏ�~�q�����N���Ă���B
�������͕����V�N�R���P�U���ɂł����V�����w�ŁA�ߔN�ł����w�炵�������z�[���P�ʂ̃V���v���ȍ\���ł���B
�����{���E���S�ƂƂ��ɒz���ɂ���A���D�̓z�[�����ɂ���B
�i�q���C�ł͒��������R����P�L��������Ă��Ȃ��悤�ȋ����ɂ��邽�߁A��~�l���͂���Ȃɑ����Ȃ��B
���̂��߂��O�͉��ÂƂƂ��Ɂu���[�����C�g�Ȃ���v�����Ԃ͒�܂�Ȃ��B
���������̉w�́A�i�q�`�̂v�h�m�r�i��O�n������j��p�w�Ƃ����Ă悭�A�y�j���j�͔��ɍ��ށB
���É��͒����{���A���{���Ɛڑ����A���C���V�����ƘA���A
�X�ɖ��S���É��{���A�ߓS���É����A���É��s�𓌎R���A�����ʐ��ƘA������B
���C���{�����P�`�U�ԃz�[���̂R�ʂU���ƁA���}�u�Ђ��v���P�P�ԃz�[�����g�p���A
�����{�����V�A�W�A�P�O�A�P�P�ԃz�[���i�X�ԃz�[���͂Ȃ��j�̂Q�ʂS���A
���{�����P�P�`�P�R�ԃz�[���̂Q�ʂR�����g�p����B
���̂������C���{���́A�P�A�Q�ԃz�[�������̃X���[��ԃz�[���Ŋɋ}�ڑ������A
�T�A�U�ԃz�[��������̃X���[��ԃz�[���Ŋɋ}�ڑ�����B
�^�̂R�A�S�ԃz�[���͎�ɁA���w�܂�Ԃ��̗�ԁA���L�����ʗ�Ԃ���}���g�p����B
���ăZ���g�����^���[�Y���H�����������ۂɂ́A�P�A�Q�ԃz�[������A
���R�A�S�ԃz�[��������ԂɎg�p���A����͊ɋ}�ڑ��������ɂT�ԃz�[������}�p�Ƃ��Ă����B
���É��͌��킸�ƒm�ꂽ�������A���C���A�����n���Ȃǂ̒��S�n�B�l���͂��悻�Q�T�O���l�B
�������A�����̓����̈�Ƃ��ēS���̃V�F�A���Q�Q�������Ȃ��A���É��ł̉���~�q���́A
�ݗ����Q�R���l�]��A�V�����P�O���l�]��i�ݗ����ւ̏�芷���q�����Ɋ܂ށj�ƂR�O�����x�������Ȃ��B
����́A��s���V�h�̂P�S�O���l�A����_�����̂W�O���l�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ菭�Ȃ��B
�������A�i�q�ɂȂ��Ă���̓X�s�[�h�A�b�v��^���̋t�]���ۂȂǂ�����A
���S�A�ߓS�̌Œ�q��D������A�ŋ߂̃f�[�^�͕s���ɂ�������炸���������Ȃ��Ă��锤�ł���
�i�����Ƃ��S���̃V�F�A���̂͑����Ă��Ȃ��͂������c�Ƃ������Ƃ́A�������͂قڑS�Ď��S����V�t�g�����l�j�B
���f���ł͓��C��ʎ��Ə�k���ƘA���B
���C���{���A��k�����ɓ����z�[���ƂȂ��Ă��邪�A
��k���̃z�[���́A���C���{���ɕ��s���đ���ݕ����ɍ���Ă���B
�w�ɂ͋��L�ŐV�����̍��ˉ��ɂ���A���X�ڗ����Ȃ��ʒu�ɂ���B
�w�ɂ����L���ꂽ��ݕ�����Ƀz�[��������̂́A��k�������Ƃ��ƍ��S���ォ��v�悳��Ă����ݕ����ŁA
���c����AJR���C���P�O�O���o�����ē��C��ʎ��Ƃ������A���݂��ꂽ����ł���B
�i�q���C�̘H���łȂ��̂́A�̎Z���ꂷ�邱�Ƃ��m���ŁA�^�������߂ɐݒ肷�邽�ߕʉ�Ђɂ����̂ł���B
���S�̐{�������߂����߂��A���̉w�Ƃ̊Ԃɓ���^�����ݒ肳��Ă���Ƃ��������B
���F�͓����z�[���̊ȑf�ȉw�B
���傤�ǐV���������֕�����Ă����Ƃ���ɂ���B
�o������͓��݂̂ɕt���Ă��āA�����ɍs�����߂ɂ͉w�k���̓��H��n��K�v������B
���ɐl�Ƃ͂��܂薳�����A�����Ђ����邽�߁A���ΎЈ��̗��p��������̂ł͂Ȃ����낤���H
���Ȃ݂ɖ��S�V���F�Ƃ͂����Ԃ�Ă���i�ނ���嗢�̂ق����߂��j�̂ŁA�Z�ݕ����͂Ȃ���Ă���B
����������z�[���B
�����ɂ͂��āA�L��Ȉ�ԏꂪ�L�����Ă������A���݂͈ꕔ���i�q�ݕ��̊�n�ɂȂ��Ă��邪�A�唼�͍r�n�ƂȂ��Ă���B
���݁A�悤�₭��n���p�̌v�悪���サ�Ă����悤���B
���Ɍ��킹��A���m�����͎��R���Ă���ȕ�翂Ȓn�ōs�����A�����ōs���ق�������ۂǗǂ��Ǝv���B
���Ă̓z�[���̈�ԓ������ɖ{���ւ̌א���������A�w�ɂ͐����ɂ������B
���̌�A�z�[���𓌋����ɒ������ăz�[���^�Ɍא���������悤�ɉ������ꂽ�B
�X�ɑ��ԏ�̏���ׂ����H�����݂���āA������ɉw�{�����ڂ������ł��֗��ɂȂ����B
�����P�P�N�̉����O�́A�����̉������P���ԂɂP�{��Ԃ��Ă������A�u�����v�ł��ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
������{�ł͖��S���É��{���A���������i�V��{�j�ƘA�����Ă���B
�z�[���͂Q�ʂS���̍��˂ŁA�����ɍX�ɂP�{���H������B
���̐��H�́A���ˉ��r���̒i�K�ʼn��z�[��������Ďg�p����Ă����B
���݂͉�b��A���ȂǂőҔ��Ɏg���Ă���B
�l���Q�T���l�̈�{�s�̒��S�ŁA�i�q���C�̒��ԉw�̒��ł����Ȃ��~�l���������B
����͋ߔN�A�V�����Ȃǂ̃X�s�[�h�A�b�v�Ɩ��S�̒l�グ�ŁA���S����V�t�g���Ă������Ƃ��傫���B
���݂̏�~�q���͂قړ������A�i�q���L���ȏɌX������B
���S���É��{�������Ɣ�ׂ�A�i�q�̗L���͊m���ƌ�����B
������V�����́A�P�V�D�P�L���i���É�����j���P�O���A�\�葬�x�łP�O�Q�D�U�L���ŋ삯������̂ł���B
�ؑ]���͓����z�[���B
�w�̂������w�\���Ő��ɃJ�[�u���Ă���A����ȂɃJ�[�u�͂����Ȃ����A
�V����������͌��������ɐi�����邽�߁A�傫���h���n�_�ł���B
�����������ɍL�����Ă���A����Ƃ̌��ˍ����ŃJ���g�̌�����܂܂Ȃ�Ȃ����߂��H
���̑����͂��܂ɑҔ��ȂǂɎg���Ă���B
���S�ɐV�ؑ]��Ƃ����}�s��ԉw�����邪�A�ނ���e��̂ݒ�Ԃ̍��c�̕����߂��B
���ł͍��R�{���ƘA���A���S�s�����i�w�O�j�ƘA�����Ă��邪�A
�w�k���ɂ��閼�S���É��{���Ɗe���������̐V�Ƃ��߂��i�����ĂT�`�P�O�����x�j�B
�����V�̕������S���ɋ߂��A��{�ƈႢ������͖��S���D���ł���B
�Ƃ͂����A���É��܂ł�JR�V�����A�������P�V���A�S�T�O�~�A�P�T�����A
���S���}���Q�R���A�T�S�O�~�A�P�T�����Ƃi�q���L���ŁA�������A���S�̏�~�l���͊e���������Ƃ̍��Z�ł���B
���̕ӂ͖ړI�n�̈Ⴂ�ƁA����邩�̖��i�i�q�V�����E�����ł͂܂�����Ȃ��j�ɂȂ��Ă��邾�낤�B
�R�ʂU���̍��˃z�[���ŁA�쑤����P�`�U�Ԑ��ƂȂ��Ă���B
�P�A�Q�Ԑ��͓��C���{�������A�T�A�U�Ԑ������C���{��������A���̊Ԃ̂R�A�S�Ԑ��͍��R�{���ƂȂ��Ă��邪�A
�e��̑唼�������ɂȂ������߁A���̗�Ԃ��Q�Ԑ��A�T�Ԑ��Ɩ@���Ȃ����Ԃ�����A
���܂ɂR�E�S�Ԑ������̗�Ԃ����݂���悤�ɂȂ�A���̂�����ꂷ��K�v��������B
�w�̐����ɂ͉��{���̑Ҕ��������A���C���{���̐܂�Ԃ��e��⍂�R�{���̋C���Ԃ��~�܂��Ă���B
���̌������ݒn�ŁA�s�̐l���͂S�O���l���B�������A����ɂ��Ă͏�~�l�������X���Ȃ��B
����͊��̓S���ɑ���l���������₩�Ȃ��߂ŁA�s���̌�ʂ͂����ς玩���Ԃ��o�X�ł���B
�������A���Ȃ��p�C�𖼓S�Ƃŕ��������Ă��邩��A�܂��܂���~�l���͏��Ȃ��B
����ł��A�w�암�����JR�̕����֗��ŁA������[�^���[����������A���S����̃V�t�g�����邱�Ƃ���A
���X�ɂł͂��邪��~�l������������悤�Ɏv����B
�w�k���Ɋւ��Ă͑傫�ȃ��[�^���[�͂��邪�A�����C�O���i�ɉ�����C���̑@�ۊX�����邾���ŁA�������ݒn�ɂ��Ă͑e���ł���B
���Ă̓f�p�[�g�������Ȃ��������A�����P�Q�N�V���Ɂu�A�N�e�B�u�f�v�Ȃ���X�X�����ˉ��ɂł��A���D�ƒ������Ă���B
�����͓����z�[���B
���S�����ɍ��ꂽ��r�I�V�����w�ŁA�����ɐ����Ɋݕ��^�[�~�i�����ڐ݂��ꂽ�B
�����Ȃǂ͂�������ԋ߂����A�������y����ɏ�����������قlj����B
�o�X�̖{���������Ȃ��A���S�Ɏ��͂̏Z����p�̉w�ƂȂ��Ă��邪�A
�����P�P�N�̃_�C�������ŐV�����E��������܂邱�ƂɂȂ�֗��ɂȂ����B
����������z�[���B
���̊O���ɂ͏㉺���Ƃ��P�{�������������Ă���B
�܂��A�����Ō������钷�ǐ�̋߂��܂ŁA�o���X�g��ςݍ��މݕ��������тĂ���B
�ߔN�͖��É��A�Ȃǂ̃x�b�h�^�E���ƂȂ�A���̐l���Ƌ��ɏ�~�l���������X���ɂ���B
���Ă͉�������܂��Ă������A���x����V��������܂邱�ƂɂȂ�A���É��܂ōX�ɕ֗��ɂȂ����B
��_�͒M���S���A�ߓS�{�V���Ɛڑ����A
���C���{�����Z�ԍ�x���A�V����I���������i���m�ɂ͂R�L����̓�r���M�����Łj�B
�茇���z�[�������邽�߁A�R�ʂV���Ƃ��Ȃ�ϑ��I�ȃz�[���ƂȂ��Ă���B
��ԓ�̃z�[���͉w�r��APIO�Ɛڂ��Ă��邽�ߕЖʃz�[���ƂȂ��Ă���P�Ԑ��B
�����ē����z�[���̂Q�A�S�Ԑ��B
�R�Ԑ��́A�S�Ԑ��̐�����茇���z�[���ɂ����Z�ԍ�x���p�Ƃ��Ă���B
�����ē����z�[���̂T�A�U�Ԑ��B
�V�Ԑ��́A�U�Ԑ��̓�����茇���z�[���ɂ��M���S���p�Ƃ��Ă���B
�Q�Ԑ�������{���A�S�Ԑ������{���ƂȂ��Ă���A
�P�A�T�Ԑ��͎�ɐ܂�Ԃ����╪�����鎞�Ɏg�p����Ă���B
��芷���鎞�A�قƂ�ǂ̏ꍇ�͊K�i���g��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A���Ȃ�s�ւȉw�ł���B
�U�A�V�Ԑ��͒M�����p�����A���̋q�ԗ�Ԃ݂̂U�Ԑ����g�p���A
���[���o�X�̏ꍇ�͒Z���V�Ԑ����g�����Ƃ��قƂ�ǂȂ̂ŁA
�����͓��C���{�����U�Ԑ����g�p���A�z�[�����芷���o����悤�ɂ��ׂ��ł���B
�Ȃ��A�ߓS�̓����z�[���ւ͂P�Ԑ�����s�����Ƃ��o�������A���݂͒��ԉ��D������A�A���ؕ��������Ă���l�������p�ł��Ȃ��B
���Ắu��_��s�v�̏I�_�ł���A���݂́u���[�����C�g�Ȃ���v�ɕς�������A���ł��I�_�ł��邱�Ƃɕς��͖����B
����͐����ɑ�_�d�ԋ悪���邽�߂ł���B
����������_�ɓd�ԋ悪����̂́A���C�@�֎Ԏ���̖��c�ł���B
��_���o��Ɗփ����z���łQ�O����z������₪�A�����邽�߁A�����ŋ@�֎Ԃ̑����⋋���A�⋋�Ȃǂ��s�����̂ł���B
���̂��߁A���������Ŕ����ƂȂ��Ԃ������A��ʂ̗v�Ղł��邱�Ƃɕς��͖����B
�▼�É��ւ̒ʋΌ��ł��邽�߁A�x�b�h�^�E���Ƃ��Ă̋@�\���傫�����A
��_�s���̂����Z�n���P�s�T�S�i��_�s�A�s�j�S�A�K��S�A�����S�A�C�ÌS�A�{�V�S�j�̒��S�Ƃ��āA�����փ�������̋��S�͂�����B
�i���Ȃ�ڂ����������Ă��܂����c�c�n�����ŃX�C�}�Z���j
��r���M�����͏㉺�{���Ɛ���x���Ɣ��Z�ԍ�x��������n�_�A��_���N�_�ɂ��ĂR�D�P�L���ɐ݂����Ă���B
�����Œ��ӂ������̂��A����{���͐����ʂ��Ă�����̂ł͂Ȃ��A���V����o�R�̉I�[�g�̕��ł���B
�����ĒM���ʂ��Ă���̂́A����x���Ƃ����x���Ȃ̂ł���B���{���ƕ��s���đ����Ă��Ă��x���Ȃ̂ł���B
�܂��������̓n���������A�����ď���������Z�ԍ�Ɍ��������H�����Ă��āA��_������Z�ԍ�Ɍ��������ɓn������g����B
���Z�ԍ���͖{�����番����Ă����̏��ɍr���w������B
�����Ė{�����͐��y�ō����Ȃ�A���̉�����������番���ꂽ����{���I�[�g���������Ă����B
������͋��V������ʂ̉I�[�g�����Ă̖{���ŁA��Ő���x����~�������Ƃ���A
����{���I�[�g�������A����x�����|�C���g�ŕ�����Ă���`�ɂȂ��Ă���B
���̂��߂ɉ���̕��ʗ�Ԃ͑傫�Ȍ������邱�ƂɂȂ�B
���}�͉�����}�͉I�[�g���g�����ƂɂȂ�̂ŁA���������ɂ��̂܂ܑ��苎���Ă����B
�Ȃ����̂悤�ȉI�[�g������̂��H�����ĂȂ��x����������Ă���̂��H
�I�[�g�͏��C�@�֎���̖��c�ł���B
��_�w�̍��ł����������悤�ɁA�փ����z���͂Q�O�p�[�~���̍₪�A������B
���̂��߁A�����ł��}���z���ɘa���邽�߂ɍ��ꂽ�B���ۂɌ��z�͂P�O�p�[�~���ɗ}�����Ă���B
����ł��⏕�̋@�֎Ԃ̗͂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂł������B
���̋@�֎Ԃ͊փ����w���߂��ĉ����ɓ��钼�O�A���s���ɐ藣����đ�_�w�ɖ߂��čs�����炵���B
���Z�ԍ�x���͐ΊD�̉ݕ��A���̂��߂ł���B
��_�s�̖k���ɂ͋����R�i���傤����B�ʖ��F�ԍ�R�j�Ƃ����R������A��������ΊD������̂ł���B
���̉ݕ��A���̂��߂ɔ��Z�ԍ�܂ō���A���̐�͐��Z�S���Ƃ����ݕ����̘H�����^�c���Ă���B
�����͕ό`�̂i�q�^�z���ƂȂ��Ă���B
�����i�P�Ԑ��j���Жʃz�[���Œ����i�Q�Ԑ��j�Ɖ�����i�R�Ԑ��j�������z�[�������A
��_���ʂ��璆���ɍs�����Ƃ͂ł����A����ɂR�Ԑ������_���ʂɍs�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B
������������_���ʂɍs�����Ƃ��ł���B�Č����́A�ʏ�̒�������㉺���ɍs�����Ƃ��ł���\���ł���B
���S����ɂ́A�����Ԃ͐V����o�R�̉I�[�g���g���Ă��āA����Ԃ�����܂�Ȃ������Ƃ����ς�����w�ł������B
���̂��߂ɑ�_���ʂ֍s���Ƃ��͂��̂܂܍s�������A��_���ʂ���A���Ă��鎞�͐V����o�R�Ŋփ����܂ōs���A
�����������ԂŐ���ɋA���Ă��邩�A����ƐV���������ł����o�X���g��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B
���������a�U�O�N�P�O���R�P���������ĐV����͔p�~�A�㉺��ԂƂ��ɐ���o�R�ƂȂ����B
���������ł�������}�͉I�[�g���g���Ă���B
�i�q�^�z���ƂȂ��Ă��邽�߂ɁA�ݕ���ԂȂǂ̈ꕔ�͕��{���ɒ�Ԃ��ė��q��Ԃ����߂������肵�Ă���B
�܂��u�����v�O�͕��ʗ�Ԃ����}�����߂������肷����̂��������B
���䒬�͊▼�É��̃x�b�g�^�E���Ƃ��Ĕ��W���Ă��āA�s�j���Z�i�ƌ����Ă����Ȃ�������j�����邱�Ƃ����_�`�Č��̒��ł���~�q�������B
���̂��߂��u�����v�O�́A�����b�V�����ɐ���n���̗�Ԃ��ݒ肳��Ă������炢�ł���B
�փ����͓����Q�ʂS���z�[���B�w�ɂ͓�ɂ���쑤����P�`�S�Ԑ��ƂȂ��Ă��邪�A��ʓI�ȂQ�ʂS���z�[���̎g�����͂��Ă��Ȃ��B
�܂���r���M���ꂩ�番���ꂽ�V����o�R�̉I�[�g�͂��̉w�ō�������B
�I�[�g�͂R�Ԑ��ɓ����Ă��āA���̂܂ܒ����ŕČ����ʂɌ������B
����o�R�̉���{���͂P�Ԑ��ɒ�Ԃ��A�R�Ԑ��ɍ�������悤�ɂȂ��Ă��邽�߂ɁA���x�ɐ������邱�ƂɂȂ�B
�����͂S�Ԑ������̂܂܃X���[�B���͓��}������o�R�ő���B
�Q�Ԑ��͑�_���ʂ���̋�ԗ�Ԃ����̉w�Ő܂�Ԃ��Ă����B
�u�����v�O�A��_�`�փ����͉����i�ƌ����Ă���ψȐ��e��j���R�O�����ɑ����Ă������A
�Q�{�ɂP�{�͊փ����܂�Ԃ��ŁA�Č��܂ōs���̂͂P���ԂɂP�{�ł������B
���[�͊փ����`�Č����R�O�������m�ۂ���Ă������A�����Ɂu�t�P�W�ؕ��v�Œʂ낤�Ƃ���ɂ͂��Ȃ茵������Ԃł������B
�u�����v��͓����ł��R�O�������m�ۂ���֗��ɂȂ����B
����������͔����A�ߍ]�����A������A�Č��̏�~�q�ɂƂ��Ăł���B����A�փ����͖{���I�ɂ͕ς��Ȃ��B
������肩�u�����v�O�͉�������_�Ȑ��������Ă������A�u�����v��͓����̂قƂ�ǂ̗�Ԃ���_�����̋�ԗ�ԂɂȂ��Ă��܂����B
��Ԃ͂R�P�R�n�R�O�O�ԑ�̂Q���Ґ����g����̂ŁA�P�P�V�n�ɔ�ׂĊi�i�ɂ悭�Ȃ����B
�L���`��_�̉����A�V�����̂قƂ�ǂ͂R�P�R�n���g����悤�ɂȂ����B
�������R�P�R�n�O�ԑ�i�L�����j�{�R�P�R�n�R�O�O�ԑ�i��_���j�̂U���Ґ��ɑ�������Ă�����̂����Ȃ肠��B
�������_�ŕČ����̂R�O�O�ԑ�Q�����E�藣�����āA��_�Ȑ��ɂ����ʂ�����ׂ��ł���B
��~�l���͂���܂葽���͂Ȃ��B
�փ����̐킢�̕���ɂ��Ȃ����Ƃ��낾���A��ՂȂǂ�����킯�ł��Ȃ��ό��q�͂قƂ�ǂȂ��A�ʋΒʊw�q���唼���߂Ă���B
�����������Q�ʂS���z�[���B���������q��Ԃ����{���őҔ�����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
���̉w�́u�������v�ƓǂށB���{�������w�́u�������v�A���m�R�������́u������v�ł���B
�փ����z���͗L�������A�փ������T�~�b�g�ł͂Ȃ��B��_����̏����z�͂��̉w�܂ő����Ă���B
�փ����̍��ł��q�ׂ����A�u�����v�ɂ���ē����P���Ԃ̖{�����P���Q�{�ɂȂ�g���₷���Ȃ����B��������~�l���͑����Ȃ��B
�ߍ]�����������Q�ʂS���z�[���B
���̉w�͍ŋ߂܂ŐΊD�̉ݕ����������������߂ɁA�\���ɂ͑���������������B
���̂����̂P�{���ɐ��R�̕��Ɍ������ĉ��тĂ��āA�Z�F�Z�����g�܂ő����Ă���B
���������݂ł͂����ݕ��A���͍s���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�L���\���͎��ė]���C���ł���B
��������͋}�J�[�u�������Ă��đ傫���I�Ă��邪�A����͋}���z������邽�߂ł���B
�������͂i�q�^�z���B
��ɉw�ɂ�����삩��P�`�R�Ԑ������A�w�ɂɖʂ����P�Ԑ��͎g��ꂸ�A�㉺���͓����z�[���Q�E�R�Ԑ����g���Ă���B
�w���́A�ŋC�������{���������̋߂��̐�ɂ���Đ��C�ɖ߂������Ƃ��痈�Ă���炵���B
�߂��ɂ͖����P�P�N�ɍ��ꂽ�{���ꂪ����A���݂ł��܂����Ă���B
�Č��ł͖k���{���Ɛڑ��A���C���V�����A�ߍ]�S���ƘA�������ʂ̗v�Ղł���B
�����������̂̋K�͂������đ傫���킯�ł͂Ȃ��B��~�l���͎v�����قǑ����Ȃ��Ƃ����l�����邩�Ǝv���B
���Ă͂T�ʂX���Ƃ����傫�ȉw�ŁA�R�ʂT���{�w�{���̉���z�[���ƂQ�ʂS���̏��z�[���̊ԂɃ��[�h������㉺���͐����Ɨ���Ă����B
�������ݕ���Ԃ̐��ނƂƂ��Ƀ��[�h�Ɖ���z�[����P���A���z�[���̓�ɂP�z�[��������ĂR�ʂU���ɂȂ��Ă���B
�P�Ԑ��͑�_���ʂ��瓞�������ԁA�Q�Ԑ��͋��s���ʂ֔��Ԃ����ԁA�R�E�S�Ԑ��͖k���{���̓��}��ԁA
�T�Ԑ��͒��l���ʂ֔��Ԃ����ԁA�U�Ԑ��͑�_���ʂ֔��Ԃ����Ԃ̃z�[���ƂȂ��Ă���B
���݂ł͓����P���Ԃɐ����{�̐V�������Q�{�A�������Q�{�A���C�̑�_�`�Č��𑖂��Ԃ��Q�{�ł����Ă��\���ł���B
�����{�̉����͂T�Ԑ��ɓ���������A�w�����̐܂�Ԃ������g���ĂQ�Ԑ����甭�ԁA
���C�̗�Ԃ͂P�Ԑ��ɓ���������A�w�����̐܂�Ԃ������g���ĂU�Ԑ����甭�Ԃ��Ă��邽�߂ł���B
�V�����͒��l�`�P�H�Ƃ����悤�ɕČ����X���[����̂œ��ɖ��͂Ȃ��B�B
���̂��߁A��_���ʂ���̗�ԂƕP�H�s���V�������A�P�H���ʂ���̐V�����Ƒ�_�s�����z�[����ŏ�芷���邱�Ƃ��ł��ĕ֗��ł���B
�܂��u������ɂ���ĕČ��ł̐ڑ��͗ǂ��Ȃ����̂ŁA�u�t�P�W�����Ձv���p�҂ɂƂ��Ă͕֗��ɂȂ����B
�r���͕Жʃz�[���B��r���M���ꂩ�炽�����R�O�O���[�g���̂Ƃ���ɂ���B
���C���{���ł����ɏ�~�l�������Ȃ��B������l�w�ł���B
���Z�ԍ�x���͖{�������Ȃ��A�o�X���R�O���Ԋu�ɑ����Ă���Ƃ������Ƃ������ď�~�q�͏��Ȃ��B�B
�������u�����v�ɂ���Ė{���͑����}�V�ɂȂ�A�ԗ����R�P�R�n�Ɨǂ��Ȃ����B
���Z�ԍ����Жʃz�[�������A�ݕ��̗��u������������B
����͋����R����ΊD���^�яo�����߂̉ݕ��ŁA���Z�S���Ƃ����ݕ���p�̎��S���^�c���Ă���B
�ݕ���Ԃ����ނ������݂ł����Ȃ�̗�Ԃ��^�s����A�M���S���̑�Q�̏o���҂ł���B
���Z�ԍ�x���͐ΊD���^�Ԃ��߂ɂɌ��݂��ꂽ�ƌ����Ă��悭�A���݂ł����q��Ԃ̖{���͑����Ȃ��B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���Q�P�E�X�E�P |
�S�T�X�S�O |
|
���m���L���s�ԓc�� |
|
|
|
���Q�R�E�W�E�P |
�Q�X�P�U |
|
���m����ьS����䒬�ɓ� |
|
|
|
���Q�P�E�X�E�P |
�S�O�P�O |
|
���m����ьS��Ò����� |
|
|
|
���Q�W�E�V�E�W |
�Q�X�S�S |
|
���m�����S�s��˒� |
|
|
|
���S�E�V�E�R |
�T�T�S�O |
|
���m�����S�s�O�J�� |
|
|
|
���Q�P�E�X�E�P |
�P�R�R�T�U |
|
���m�����S�s���� |
|
|
|
���U�R�E�P�P�E�P�U |
�R�T�P�W |
|
���m�����S�s�|�J�� |
|
|
|
���S�Q�E�R�E�Q�O |
�Q�W�U�U |
|
���m���z�c�S�K�c���[�a |
|
|
|
���S�P�E�X�E�P�P |
�W�O�O�U |
|
���m���z�c�S�K�c�����J |
|
|
|
���Q�P�E�X�E�P |
�Q�R�V�X�W |
|
���m������s�H���� |
|
|
|
���U�R�E�R�E�P�R |
�R�R�S�S |
|
���m������s���a�� |
|
|
|
���Q�S�E�U�E�P�U |
�P�X�S�Q�O |
|
���m������s��K�{�� |
|
|
|
���U�R�E�R�E�P�R |
�W�T�T�S |
|
���m������s��{�ؒ� |
|
|
|
���S�P�E�P�Q�E�Q�S |
�P�O�O�R�O |
|
���m�����J�s�����J���P���� |
|
|
|
���Q�P�E�X�E�P |
�R�X�W�W�O |
|
���m�����J�s�����P���� |
|
|
|
���U�R�E�R�E�P�R |
�R�X�V�W |
|
���m�����J�s�F�쒬�Q���� |
|
|
|
���Q�O�E�X�E�P�O |
�Q�R�O�U�O |
|
���m����{�s�������R���� |
|
|
|
���W�E�P�Q�E�V |
�P�T�O�Q�Q |
|
���m����{�s���h���X���� |
|
|
|
���P�X�E�R�E�P |
�P�P�O�S�S |
|
���m�����É��s��卂�� |
|
|
|
���P�W�E�U�E�P |
�P�R�S�W�Q |
|
���m�����É��s��旧�e���Q���� |
|
|
|
���P�X�E�R�E�P |
�U�O�Q�W |
|
���m�����É��s�M�c��X�㒬�Q���� |
|
|
|
���P�E�V�E�X*�@ |
�W�X�W�R�U |
|
���m�������s������R�P���� |
|
|
|
���V�E�R�E�P�U |
�U�O�U�O |
|
���m�������s�����������R���� |
|
|
|
���P�X�E�T�E�P |
�Q�R�S�T�R�U |
|
���m�����É��s�����於�w�P���� |
|
|
|
���R�X�E�S�E�P�U |
�U�S�R�Q |
|
���m�����t����S�����f�������� |
|
|
|
���X�E�Q�E�Q�S |
�V�T�W�O |
|
���m�����s�k�s�꒬ |
|
|
|
���R�X�E�W�E�T |
�P�Q�W�W�W |
|
���m�����s�w�O�P���� |
|
|
|
���P�X�E�T�E�P |
�S�V�V�U�S |
|
���m����{�s�h�R���� |
|
|
|
���P�X�E�U�E�P |
�U�X�W�S |
|
���m���t�I�S�ؑ]�쒬���c |
|
|
|
���Q�O�E�P�E�Q�P |
�T�T�Q�T�U |
|
���s���{���P���� |
|
|
|
���U�P�E�P�P�E�P |
�U�U�Q�Q |
|
���s�s���R���� |
|
|
|
���R�X�E�W�E�P |
�P�V�W�Q�O |
|
���{���S��ϒ��ʕ{ |
|
|
|
���P�V�E�T�E�Q�T |
�R�T�O�O�U |
|
����_�s�������P���� |
|
|
|
���P�V�E�T�E�Q�T |
�U�P�V�U |
|
���s�j�S���䒬���� |
|
|
|
���P�U�E�T�E�P |
�Q�T�S�S |
|
���s�j�S�փ������փ��� |
|
|
|
���R�R�E�Q�E�Q�P |
�W�V�O |
|
���ꌧ��c�S�R�������� |
|
|
|
���Q�Q�E�V�E�P |
�P�X�R�O |
|
���ꌧ��c�S�R�������� |
|
|
|
���R�R�E�Q�E�Q�P |
�W�U�O |
|
���ꌧ��c�S�Č������� |
|
|
|
���Q�Q�E�V�E�P |
�W�W�R�W |
|
���ꌧ��c�S�Č����Č� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
���T�E�P�Q�E�P |
�W�T�S |
|
����_�s�r���� |
|
|
|
��W�E�W�E�P |
�W�P�S |
|
����_�s�ԍ⒬ |
�@
�@
�ԗ�
���ʗ�ԗp�Ƃ��āA313�n�A311�n�A213�n�A211�n�A117�n���g���Ă��āA
���}��ԗp�Ƃ��āA�u���炳���v�p683�n�A�u���[�����C�g�Ȃ���v�p373�n�A�u���Ȃ́v�p383�n�A�u�Ђ��v�p�L�n85�n���g���Ă���B
313�n�͍��S�`�ԗ�113�n�𓑑����邽�߂ɕ���11�N���瓱������Ă���ԗ��ł���B
���C���{���ł͎�ɐV�����E�����Ƃ��Ďg���Ă���A���������z����130�L���^�]���ł���悤�ɂ��Ă���B
���������VVVF�ƂȂ��Ă��邪�A�����{���ł͒��[�𒆐S�ɁA�E���Y���㎥�����211�n�Ƃ̕������Ȃ���Ă���B
�Ґ��͓�������ɍ��킹��2�E3�E4���Ґ�������A0�E300�E1000�E1500�E3000�E8000�ԑオ�U�蕪�����Ă��ď��X���G�Ȍ`���ɂȂ��Ă���B
���܂ŐV�����ɂ�311�n���g�p���Ă������A4���Œ�Ґ��ƂȂ��Ă���A4���ł͗A���͂��s�����A8���ł͗A���͉ߏ�ł������B
���̂��߁A4�{2���Ґ���6���Ґ��Ƃ��ĉ^�]�ł���悤�ɂ��āA���_��ȕҐ���g�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
���Ȃ�3000�ԑ�ȊO�͓]���N���X�V�[�g��̂����A�ʋΎ��̍��G���l���A311�n�ɔ�ׂĔ��Ԃ�1�Ȃ����Ă���i6��5�j�͎̂c�O�ł���B
�܂��A1000�E1500�ԑ�̍ȕ��̓����O�V�[�g�ɂȂ��Ă��āA��͂�ʋΗ�Ԃɋ߂��Ȃ������͔ۂ߂Ȃ��B
�܂�Tc�Ԃɂ��ẮA�ȕ��Ƀg�C�����݂����Ă���B
311�n�ɂ̓g�C�����ɃJ�[�h��p�d�b���t���Ă������A�g�ѓd�b�����y�������߂�����͕t�����Ă��Ȃ�
�i���̊��ɂ͎ԓ��ł̌g�т͂�߂�悤�ɌĂт����Ă���̂����������Ǝv�����j�B
���̃g�C���ł��邪�A311�n�ɔ�ׂđ傫���Ԉ֎q�Ή��ɂ��A�܂肽���݂̃x�r�[�x�b�h���t����ꂽ�B
�g�C�����Α��̍��Ȃ͌Œ�N���X�V�[�g�ƂȂ��Ă��邪�A2�~1�ɂ��āA1�Ȃ��Ȃ����ꏊ�͎Ԉ֎q�p�ɂȂ����B
���̑��A311�n�͍ȕ���LED�̎ԓ���u���t�����Ă������A313�n�͔���ɕt�����Ă��āA�h�b�g���������Ȃ��Č��₷���Ȃ����B
4���Ґ���0�ԑ��1000�ԑ�ł���B���҂Ƃ��AMcTMTc��2M2T�ƂȂ��Ă��蓯���悤�Ɍ����邪�A
0�ԑ�̓I�[���]���N���X�V�[�g�i�����������ƍȕ��͌Œ�N���X�V�[�g�j�ƂȂ��Ă���̂ɑ��A
1000�ԑ�͔��Ԃ͓]���N���X�V�[�g�i�����͌Œ�N���X�V�[�g�j�A�ȕ��������O�V�[�g�ƂȂ��Ă���A��~�̂��₷���悤�ɂȂ��Ă���B
�Ȃ�1000�ԑ��Tc�Ԃ�����0�ԑ�ƂȂ��Ă���A�N�n312�|1�`3�ƂȂ��Ă���B
�����Tc�Ԃ̃g�C�����Α��̍��Ȃ��Œ�N���X�V�[�g�ɂȂ��Ă��邽�߂ŁA1000�ԑ�̍ȕ������O�V�[�g�Ƃ�����`�ɓ��Ă͂܂�Ȃ�����ł���B
����ɂ��O�ԑ�̂s���Ԃ́A���̂R�����g�b�v�i���o�[�ł����Ă��A�P�O�O�O�ԑ�E�P�T�O�O�ԑオ��s���ĂU�Ґ��������������߁A�V�`�ɂȂ��Ă���B
�O�ԑ�́A�P�T�Ґ�����_�d�ԋ�ɔz������Ă��āA���C���{���̗D����ԂɎg���Ă���B
�P�O�O�O�ԑ�́A�R�Ґ����_�̓d�ԋ�ɔz������Ă��āA�����{���Ɏg���邽�߂ɓ��C���{���ł̉^�p�͂Ȃ��B
�R���Ґ��͂P�T�O�O�ԑ�ƂW�O�O�O�ԑ�ł���B���҂Ƃ��A�l���l�s���̂Q�l�P�s�ƂȂ��Ă��邪�A
�l�s����P�F�P�ɂ��邽�߂ɁA�l�Ԃ̕Е��̑�ԁi�l���Ԋ��j�ɂ������[�^�[�����Ă��Ȃ��̂ŁA���m�Ɍ����ƂP�D�T�F�P�D�T�ł���B
�P�T�O�O�ԑ�͂P�O�O�O�ԑ�̂R���Ґ��o�[�W�����ŁA�s���ԂɊւ��Ă͂P�O�O�O�ԑ�Ɠ����悤�ɂO�ԑ�i�S�`�U�j���A������Ă���B
�W�T�O�O�ԑ�͒����{���Z���g�������C�i�[�p�̎ԗ��ŁA�O�ς̓V���o�[���^���b�N��n�ɃI�����W�тƂȂ��Ă���B
�܂��A���̓]���N���X�V�[�g�ԂƈႢ���Ԃ͑S�ē]���N���X�V�[�g�ƂȂ��Ă���i�ȕ��͌Œ�N���X�V�[�g�j�A�w��������T�O�~���g�傷��ȂǁA
���ʎd�l�Ԃɂӂ��킵�����̂ƂȂ��Ă���B�@��ނɊւ��ẮA�P�O�O�O�E�P�T�O�O�ԑ�Ɠ����ł���B
�܂��A�l���ԂƂl�Ԃ͂W�T�O�O�ԑ�A�s���Ԃ͂W�O�O�O�ԑ�ƂȂ��Ă���B
�P�T�O�O�ԑ�͂R�Ґ��A�W�O�O�O�ԑ�͂S�Ґ��A�S�Ă��_�̓d�ԋ�ɔz�u���Ă���A���C���{���Ŏg���邱�Ƃ͂Ȃ��B
�Q���Ґ��͂R�O�O�ԑ�ƂR�O�O�O�ԑ�ł���B�g���͂l���s���̂P�l�P�s�ƂȂ��Ă���B
�R�O�O�ԑ�͂O�ԑ�̂Q���Ґ��o�[�W�����ŁA�I�[���]���N���X�V�[�g�łs���Ԃɂ̓g�C�������Ă���B
�O�ԑ�̑����p�Ƃ��������������A�����͑�_�`�Č�����Z�ԍ�x���̗�ԂɎg�p���ꂽ��A
�Q�`�R�Ґ����ē��C���{���̗D����ԂƂ��đ��邱�Ƃ�����B
�R�O�O�O�ԑゾ���̓Z�~�N���X�V�[�g�ƂȂ��Ă��āA��i�i��������Ƃ��������͂���B
�g�p����̏ɍ��킹�Ĕ��d�u���[�L�����Ă���_�����̔ԑ�Ƒ傫���Ⴄ�Ƃ���ł���B
�R�O�O�ԑ�͂P�U�Ґ�����_�d�ԋ�ɔz������Ă���A��L�̂悤�Ɏg�p����Ă���B
�R�O�O�O�ԑ�͂R�O�O�P�`�R�O�P�Q�̂P�Q�Ґ����É��d�ԋ�ɔz������A�g�������a����Ɏg�p����Ă���B
�R�O�P�R�`�R�O�Q�W�̂P�U�Ґ����_�̓d�ԋ�ɔz���A���{���Ɏg�p����鑼�A���Ð�`���K�ȂǂɎg�p����Ă��邽�߃����}���Ή��Ԃł���B
�������킸���ł͂��邪�A�R�O�O�O�ԑ�����C���{���𑖂��Ă���B
�O�ԑ�
|
|
|
|
|
|
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T �P�U �P�V �P�W �P�X �Q�O �Q�P |
|
|
|
|
�R�O�Q �R�O�R �R�O�S �R�O�T �R�O�U �R�O�V �R�O�W �R�O�X �R�P�O �R�P�P �R�P�Q �R�P�R �R�P�S �R�P�T �R�P�U |
�R�O�Q �R�O�R �R�O�S �R�O�T �R�O�U �R�O�V �R�O�W �R�O�X �R�P�O �R�P�P �R�P�Q �R�P�R �R�P�S �R�P�T �R�P�U |
|
|
|
|
�R�O�P�S �R�O�P�T �R�O�P�U �R�O�P�V �R�O�P�W �R�O�P�X �R�O�Q�O �R�O�Q�P �R�O�Q�Q �R�O�Q�R �R�O�Q�S �R�O�Q�T �R�O�Q�U �R�O�Q�V �R�O�Q�W |
�R�O�P�S �R�O�P�T �R�O�P�U �R�O�P�V �R�O�P�W �R�O�P�X �R�O�Q�O �R�O�Q�P �R�O�Q�Q �R�O�Q�R �R�O�Q�S �R�O�Q�T �R�O�Q�U �R�O�Q�V �R�O�Q�W |
�R�P�P�n�͐V�����̉^�]�ɔ����A�������N�V���̃_�C���������瓊�����ꂽ�B
��{�\���͂Q�P�P�n�T�O�O�O�ԑ�Ɠ����ŁA�R���ԁA�E���Y���㎥����ƂȂ��Ă��邪�A
�ō����x�͂i�q�ݗ����ł͏��߂ĂP�Q�O�L���Ɉ����グ���A���Ȃ��]���N���X�V�[�g�ɉ��߂�ꂽ�B
�Q���̂P�P�V�n���]���N���X�V�[�g���������A���Ȕz�u�̉��P��^�]���̏k���ɂ��R���ɂ��Ă��������Ȑ����m�ۂ����B
�����͂P�Q�O�L���^�]���ł���ԗ��͂��ꂵ���Ȃ��������߂ɁA�V�����͕K���R�P�P�n���g�p����Ă���
�i�������N�_�C���������͂P�P�V�n�Ȃǂ��V�����Ɏg���Ă����j�A�ԍ����g�p�ʼn�����e��ɂ��Ȃ����B
���݂͂��̔C���R�P�R�n�ɏ����Ă���A�e��Ƃ��Ďg�p����邱�Ƃ������Ȃ������A
�V�����͂R�O�����A�e��͂P�T�����Ȃ̂ŁA�S�Ă̊e�₪�R�P�P�n�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�l���l�s�s���i�Q�l�Q�s�j�̂S���Ґ���g��ł���A��_���̂s���Ԃɂ̓g�C���ƃJ�[�h��p�̌��O�d�b���݂���ꂽ�B
�܂��A�e�ԑO��̍ȕ��ɂ͂k�d�c�ɂ��ԓ���u���݂����Ă���B
�S���Ґ��P�T�{�ő����U�O�����邪�A�S�đ�_�d�ԋ�z�u�ƂȂ��Ă���B
|
|
|
|
|
|
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�Q �R �S �T �U �V �W �X �P�O �P�P �P�Q �P�R �P�S �P�T |
�Q�P�R�n�͓����A���ˑ勴�𑖂�}�������C�i�[�p�ɍ��ꂽ�ԗ��ł���B
�}�������C�i�[�p�O�ԑ���x�[�X�ɁA�i�q���C�d�l�Ƃ����̂��Q�P�R�n�T�O�O�O�ԑ�ł���B
�Q�P�R�n�͂Q�P�P�n�̃V�X�e�����P�l�����ɂ��āA�Q�P�P�n�Ƃ̕������\�ɂ��Ă���B
�Q�P�P�n�ƈႤ�̂͂Q���Ԃœ]���N���X�V�[�g�ƂȂ��Ă���_�ł���B
�������A�O�ԑ�͍ȕ��̍��Ȃ��]���N���X�V�[�g�����A�T�O�O�O�ԑ�̓����O�V�[�g�ɂȂ��Ă��āA�����ɂ͎��[���⏕�֎q���݂���ꂽ�B
�܂��A�O�ԑ�͂R���Ґ������A�T�O�O�O�ԑ�͂l���s���i�P�l�P�s�j�̂Q���Ґ��ƂȂ��Ă���B
�������N�ɂP���ԂP�O�Ґ����_�̓d�ԋ�ցA�����Q�N�ɂQ���ԂR�Ґ��A
�����R�N�ɂR���ԂP�Ґ�����_�d�ԋ�ɔz�����ꂽ���A�P���Ԃ������Q�N�ɑ�_�d�ԋ�ɓ]�z���ꂽ�B
�Ȃ��A�Q�E�R���Ԃ͖y�g�Ȃǂ̂e�q�o���A�ԊO�X�s�[�J�[�̎��t���ʒu�̕ύX�A��Ԕԍ��\���̔p�~�A
�ђʈ��ˑ��̊g��Ȃǂ̃}�C�i�[�`�F���W���Ȃ���Ă���B
��_�d�ԋ揊���ɂȂ��Ă������A�Q���Q���Ґ��ł͏�~���Ԃ��������Ċe��ł��g���ɂ����A��Ɋ��{���d����ԂɎg�p����Ă��Ă����B
�����������P�P�N�P�Q���̃_�C�������ɂ����āA���{���ł��R�P�R�n����ʓ������ꂽ���Ƃ���A���[���b�V�����ȊO�ɂ͎g���Ȃ��Ȃ����B
�܂������ɁA��_�d�ԋ悩��_�̓d�ԋ�ɓ]�z���ꂽ�B
���{���ł�������ȏ���A���C���{���Ŏg����̂͂قƂ�ǂȂ��B
�����ł���Ȃ�É��n���ѓc���i�g���l���f�ʂ̊W�œV�����Ȗk�H�j�ɂ܂킷���Ƃ͂ł��Ȃ����낤���H
|
|
|
|
�T�O�O�Q �T�O�O�R �T�O�O�S �T�O�O�T �T�O�O�U �T�O�O�V �T�O�O�W �T�O�O�X �T�O�P�O �T�O�P�P �T�O�P�Q �T�O�P�R �T�O�P�S |
�T�O�O�Q �T�O�O�R �T�O�O�S �T�O�O�T �T�O�O�U �T�O�O�V �T�O�O�W �T�O�O�X �T�O�P�O �T�O�P�P �T�O�P�Q �T�O�P�R �T�O�P�S |
�Q�P�P�n�͖��c����A��ʂɓ������ꂽ�ԗ��ł���B
����܂ł͂P�P�R�n�ɑ�\�����悤�ȍ��̎ԗ����嗬���������A�Q�P�P�n�̓X�e�����X�ԗ����̗p�A
������@���A��R����̉��nj^�Ȃ���u���[�L���g����E���Y���㎥���䂪�̗p���ꂽ�B
�ԓ��̓����O�V�[�g�A�Z�~�N���X�V�[�g�̗��������邪�A�i�q�����{�̎ԗ��͍��G�ɘa�̂��߁A�قƂ�ǃ����O�V�[�g�ɉ�������Ă��܂��Ă���B
�i�q���C�ɓ������ꂽ���̂͂O�ԑ�A�T�O�O�O�ԑ�A�U�O�O�O�ԑ���̂��Ă���B
�O�ԑ�͂l���l�s�s���i�Q�l�Q�s�j�̂Q�Ґ��݂̂���_�d�ԋ�ɑ��݂��Ă��āA���Ȃ̓Z�~�N���X�V�[�g�ƂȂ��Ă���B
�����P�P�N�P�Q���̃_�C�������ɂ����āA�P�Q�O�L���^�]��R�P�P�E�R�P�R�n�Ƃ̕������ł���悤�ɉ������ꂽ�B
�T�O�O�O�ԑ�͂i�q���C�ŕ��y���Ă���^�C�v�ŁA�R���Ґ��ƂS���Ґ�������B
�R���Ґ��͂l���l�s���̂Q�l�P�s�A�S���Ґ��͂l���l�s�s���̂Q�l�Q�s�ƂȂ��Ă���A�R���Ґ��̕����l�s�䂪�����̂ʼn����������B
�����P�P�N�P�Q���̃_�C�������ȑO�͑�_�E�_�̓d�ԋ旼���ɂR�E�S���Ґ����������݂��A�^�p�����݂��Ďg���Ă����B
�������_�C�������Ȍ�A���C���{���͂P�Q�O�L���Ή��Ԃ��������Ԃ̉^�]�Ɍ��肵���̂ŁA�S���Ґ��̕��͑S�Đ_�̓d�ԋ�ɓ]�z���ꂽ
�i���̂��߁A�O�ԑ�͂P�Q�O�L���Ή��ɉ������ꂽ�j�B
���݂͑�_�d�ԋ�ɂR���Ґ��~�Q�O�A�_�̓d�ԋ�ɂR���Ґ��~�P�V�A�S���Ґ��~�Q�O�A�É��^�]���ɂR���Ґ��~�P�P���ݐЂ��Ă���B
���̂������C���{���ł́A��_�d�ԋ�̂��̂͋e��`�Č��Ɏg�p����Ă��āA���̂قƂ�ǂ͊e��Ƃ��Ďg�p�����B
�É��^�]���̎ԗ��͖L���ȓ��̎g�p�ŁA�_�̓d�ԋ�̂��͓̂��C���{���ł͉^�]����Ȃ��B
�U�O�O�O�ԑ�͂l���s���̂P�l�P�s�ŁA�É��^�]���ɂX�Ґ��ݐЂ��Ă���B
�l���Ԃ͂U�O�O�P�`�U�O�O�X�����A�s���Ԃ̕��͂T�O�O�O�ԑ�ł���B�É��^�]�������Ȃ̂ʼn^�]��Ԃ͖L���ȓ��ƂȂ��Ă���B
�O�ԑ�
|
|
|
|
|
|
�Q |
�P�S |
�P�S |
�W |

�T�O�O�O�ԑ�
|
|
|
|
|
�T�O�P�Q �T�O�P�R �T�O�P�S �T�O�P�T �T�O�P�V �T�O�Q�S �T�O�Q�U �T�O�Q�V �T�O�Q�X �T�O�R�O �T�O�R�R �T�O�R�T �T�O�R�U �T�O�R�W �T�O�R�X �T�O�S�P �T�O�S�Q �T�O�S�S �T�O�S�T |
�T�O�P�Q �T�O�P�R �T�O�P�S �T�O�P�T �T�O�P�V �T�O�Q�S �T�O�Q�U �T�O�Q�V �T�O�Q�X �T�O�R�O �T�O�R�R �T�O�R�T �T�O�R�U �T�O�R�W �T�O�R�X �T�O�S�P �T�O�S�Q �T�O�S�S �T�O�S�T |
�T�O�P�Q �T�O�P�R �T�O�P�S �T�O�P�T �T�O�P�V �T�O�Q�S �T�O�Q�U �T�O�Q�V �T�O�Q�X �T�O�R�O �T�O�R�R �T�O�R�T �T�O�R�U �T�O�R�W �T�O�R�X �T�O�S�P �T�O�S�Q �T�O�S�S �T�O�S�T |
�P�P�V�n�͓����A����_�n��Ŏ��S�ɑR���邽�߂ɍ��ꂽ��Ԃł���B
��R����ł͂��������A�Q���I�[���]���N���X�V�[�g�Ƃ������S�Ƃ��Ă͎v�������ԗ��ł���A��������a�T�V�N���璆���n��ɂ����������B
���������͂U���Ґ��ł��������A���c���O��̒Z�Ґ����̒��ŁA�N�n�P�P�V�|�P�O�O�ԑ�ƃN�n�P�P�U�\�Q�O�O�ԑ�Ƃ����擪�Ԃ�V�����āA
�s���l�l�s���i�Q�l�Q�s�j�Ƃ����S���Ґ��ɉ��g�����B
���̐V���擪�Ԃ͉��~���P�����ɕς���ꂽ���߂ɁA�Ґ��̒��ŕ��������݂ƂȂ��Ă���B
�܂��A�U���Ґ����̐擪�Ԃɂ̓g�C�����t���Ă��邱�Ƃ���A�g�C���ݔ��͕t���ĂȂ��B
�����𒆐S�ɉ^�p��C����A�������N�ɐV�������V�݂��ꂽ�Ƃ����R�P�P�n�̖{�������肸�ɐV�����Ƃ��Ďg��ꂽ�B
���̌�A�V�������S�ĂR�P�P�n�ɂȂ��Ă���͉����𒆐S�ɉ^�p����Ă����B
�������A�����P�P�N�P�Q���̃_�C�������ŐV�����A�����Ƃ��ɂR�P�R�E�R�P�P�n������A
�Q���ŏ�~�Ɏ��Ԃ�������A�ō����x���P�P�O�L���ł��邱�Ƃ���A�����̉^�p����͊O��Ă��܂����B
���[���b�V�����͋��R�`�Č��𒆐S�ɉ^�]����Ă��邪�A�[������ɂP�{�����V�����Ƃ��ĉ^�p����Ă���B
|
|
|
|
|
|
�Q�R �Q�X �Q�T �Q�S �Q�U �Q�Q �Q�V �Q�W |
�S�T �T�V �S�X �S�V �T�P �S�R �T�R �T�T |
�S�T �T�V �S�X �S�V �T�P �S�R �T�R �T�T |
�Q�O�R �Q�O�P �Q�O�U �Q�O�T �Q�O�S �Q�O�Q �Q�O�V �Q�O�W |
|
|
|
|
|
|
�P�P�Q �P�O�T �P�O�V �P�O�U �P�P�P �P�O�X �P�P�O �P�O�S |
�U�O �S�S �T�Q �S�U �T�U �T�O �T�W �T�S |
�U�O �S�S �T�Q �S�U �T�U �T�O �T�W �T�S |
�R�O �Q�Q �Q�U �Q�R �Q�W �Q�T �Q�X �Q�V |
�@
�@
�_�C��
��Ԏ�ʂ͋�ԉ����A�����A�V�����A���ʉ����A���}�A�z�[�����C�i�[������B
��ԉ����͖L���`����̊e�w�A����A���J�A��{�A���a�A���R�A���É��A������{�A�`�Č��̊e�w�A
�����͖L���A���S�A����A����A���J�A��{�A���a�A���R�A���É��A������{�A�`�Č��̊e�w�A
�V�����͖L���A���S�A����A����A���J�A��{�A���R�A���É��A������{�A�`�Č��̊e�w�A
���ʉ����͖L���A���S�A����A����A���J�A���a�A���R�A���É��A������{�A�`�Č��̊e�w����{�ƂȂ��Ă���B
�������A���ԑтɂ���Ă͂�������ԉw�������邱�Ƃ�����B
��ԉ����͒����b�V��������ő卂�A�}�����A
�����͓����𒆐S�ɎO�͎O�J���K�c���A�����b�V�����Ɨ[���b�V��������ň�A
�V�����͗[���b�V�����𒆐S�ɎO�͎O�J���K�c����ԉw�ɂȂ邱�Ƃ�����B
�܂��A�`�Č��ł͗D����Ԃ��e�w�ɒ�Ԃ���̂ŁA�e��͊Ȑ��ɂ͑����E�[��̎ԌɉȊO����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
����n���́A
��_�T�F�R�Q���Č��s���A���É��T�F�T�O�����Z�ԍ�s���A�L���S�F�T�T����_�s������[�����C�g�Ȃ��磁i�O�͉��ÁA�������ʉ߁j�ł���B
���n���́A
����T�F�T�V���L���s���A���É��T�F�R�P������s���i���ȁA�����J�A�O�͈���A������ʉ߁A�y�j�E�x���^�x�j�A��_�T�F�P�P���l���s���A
�փ����T�F�T�T���L���s���A�Č��U�F�P�S���L���s���V�����ł���B
����͑�_�n�����o����ɁA��_�U�F�O�Q���Ԋ��s���i�y�j�E�x���͂U�F�O�O���P�H�s���j�A�U�F�R�Q���Ԋ��s���i�y�j�E�x���͕P�H�s���j�A
�V�F�O�Q���Ԋ��s���ƁA�R�{�̂i�q�����{���ʗ�Ԃ��o�čs���B�g�p�ԗ��͂�������i�q�����{�̎ԗ��ŁA�Č�����͉����ƂȂ�B
�V�F�O�Q���́u���[�����C�g�Ȃ���v�A�Վ��̢��_��s��ɐڑ����邱�ƂɂȂ�A�V���Ґ��ł��A���͂��������̂����ł���B
�����ࢃ��[�����C�g�Ȃ��磢��_��s��ƖԊ��s���̓z�[�����Ⴂ�A���Ȋm�ۂ̂��߂ɉ��ɋ����K�i�ɎE��������i��������B
��̎��������Ă�������悤�ɁA��_�`�Č��͎n������I���R�O�����̉^�]�ƂȂ��Ă���B
���É�����n���͔��Z�ԍⒼ�ʂƂȂ��Ă���A�������Ȍ�A���Z�ԍ�x�����ʂ͂P���ł���P�{�����ł���i���͒��ʗ�Ԃ��Ȃ��j�B
�D����Ԃ͖L���U�F�O�T�����É��s����ԉ����i�y�j�E�x���͂U�F�O�U����_�s���j�ƂȂ��Ă���A���̗�Ԃ͖��É��ŁA
�������n���s���̉����Ƀz�[�����芷�����邱�Ƃ��ł���B
�������O�͒����{�����ʂ����{���ݒ肳��Ă������A�������ɂ���Ă���P�{�ɂȂ��Ă��܂����B
�����b�V�����͖��É������ɂ��ăp�^�[�����قȂ�B
�L�������É��͖L���U�F�S�T���i�l���n���j���ʉ�������P�T���T�C�N����g��ł���B
�P�T�����ɓ��ʉ���������A�L���U�F�S�T���͕l���n���A
�V�F�O�O���͐V��n���A�V�F�P�T���͖L��n���A�V�F�R�O���͖{���n���i���j�͖L��n���j�A�V�F�S�T���͐V��n���ƂȂ��Ă���B
�ѓc�����璼�ʂ��Ă���S�{�͂R�P�R�n�Q���Ґ��ŁA�L���ő������đ��点�邱�ƂɂȂ�B
�W�F�O�O���A�W�F�P�T���͖L���n���A�W�F�R�O���͖L���n���̐V�����ŁA�W�F�S�V�����ʉ����������ĕ��������b�V�����̓��ʉ����͏I���B
�x���͂��̌�����炭�A�����̐V�����̃X�W����ʉ���������B�����đ���ɁA�����̉����̃X�W��V����������B
�U�F�S�T�A�V�F�O�O�A�V�F�P�T�̓����̂T����ɂ͋�ԉ���������B
�n���w�͕l�����L�������A�I�_�͂���������É��ł���B
���̋���͊��S�łP�{���Ƃ̓����ɐڑ��A���肩������ƂȂ�B
�Ƃ肠��������ł́A����n���̊e��ɐڑ����Ă���`�Ԃ͎���Ă��邪�A�����P�{���Ƃ̓����̌�ɔ��Ԃ��邽�߂ɁA�P�P�����҂��ƂɂȂ�B
�܂�P�{�O�̊e��ɂ킸���S�����Œǂ����Ȃ��_�C����g��ł���̂ł���B
�����͊e�w�Ŋɋ}�ڑ����s���Ă���B
�L�����O�O���A�R�O���ɉ������o������B
�O�O���͎O�͎O�J��ԁA�R�O���͍K�c��ԂƂ����Ⴂ��������B
��ԉw���Ⴄ���߂ɁA�L���`������Y��ȂR�O���Ԋu�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A��ԉw���͓����Ȃ̂ŁA����Ȑ��͂R�O���Ԋu�ɂȂ�B
�܂������͋��a�ɒ�Ԃ���̂ŁA���É��܂ł͐V���������Q�w������Ԃ���B���̂��ߏ��v���Ԃ��R���]�v�ɂ�����B
���É��܂ł̏��v���Ԃ͂��傤�ǂT�O���A�\�葬�x�͂W�U�D�X�L���ł���B
���É������͐V�����ƒ�ԉw�������Ȃ̂ŁA�V�����ƍ��킹�ĂP�T�����ɉ^�]���邽�߁A���É��łS����Ԃ���i�V�����͂T���j�B
���É��`�̏��v���Ԃ͂P�V���A�\�葬�x�͂P�O�V�D�O�L���Ƃ������ق̑����ł���B
���É��`��_�̏��v���Ԃ͂Q�X���A�\�葬�x�͂X�P�D�O�L���ŁA�`��_�͊e��ɂȂ�Ƃ͌��������B
����ł͉���n���̊e��ɂV���Őڑ��A���J�A���É��ł͊ɋ}�ڑ����A�ŊI���̊e��̂Q����ɓ�������B
�������L�����o���Q����Ɋe�₪���Ԃ���B����͉���Ō㔭�̐V�����Ɗɋ}�ڑ�����B
�������`�K�c�̗��p�҂͂P���ԂɂQ�{�̊e�₾���ɂȂ��Ă��܂������A����ŐV�����ɂS���Őڑ����邱�Ƃ���A
���J�ȉ��̊e�w�ɍs�����́A�V�����ɏ����̂܂܊e��ɏ���Ă��������P�T���ȏ㑬���Ȃ�B
����ł͑O�q�̂悤�ɐV�����Ɛڑ����邪�A�V�������o����������ɂ͏o�������A�V����ɏo������B
����͊��J�ł��ɋ}�ڑ������A������̕������É��ɋ߂��A�Ȃ�ׂ���Ԏ��Ԃ�Z������������Ȃ̂ł��낤�B
�������҂����킹�Ƃ͌����A�P�O���߂���Ԃ���̂͂Ђǂ��B���������ł̊e���ԉw���m�̈ړ��ɂ͎��Ԃ��������Ă��܂��B
����͉����E�V�����̃X�s�[�h�A�b�v�ő҂����Ԃ͏������Ȃ�̂ł����Ǝv���邪�A����܂ł͊��S�Ҕ��ɂ��ׂ��������̂ł͂Ȃ����낤���H
�����Ċ��J�ʼn����Ɗɋ}�ڑ��B������̑҂����Ԃ͂���Ȃɒ����Ȃ��A�������o���R����ɂ͏o������B
����Ԃ������Ŋɋ}�ڑ����邪�A���Ɏ����Ă͉����E�V�����̏o���P����i���ۂɂ͂P���S�T�b�ゾ�Ǝv����j�ɂ͏o������B
�����Ė��É��܂Ŋɋ}�ڑ��͂Ȃ��B�܂芠�J����͊e��ɏ���Ă����É��܂Ő�s���čs�����Ƃ��ł���B
���J����͖��S���o�Ă��邪�A��x�m���܂ŏo�āA�����Ŗ{���ɏ��p���i���ʗ�Ԃ�����j�̂Ŏ��Ԃ�������B
�i�q�́A������{�Ƌ��Ɋ��J���P���ԂɂW�{�S�Ă̗�Ԃɏ���悤�ɂ��čU���������Ă��Ă���B
���É��ł͑O�̊e�₪�o���Q����Ɏ��̊e�₪��������B�܂薼�É��ł͂P�R������Ԃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B
��������q�̂قƂ�ǂ͖��É����ړI�n�ŁA���É����X���[���闘�p�҂͂���Ȃɂ��Ȃ��B�e��Ȃ�Ȃ�����ł���B
������P�R����Ԃł��\��Ȃ��Ƃ����l�����ł��낤�B
���É��ł͐V�����Ɗɋ}�ڑ������邪�A�����ɖ��É��n���̓��}��҂����킹�Ă���o������B
�e��̓����z�[���͂T�Ԑ��A�����E�V�����͂U�Ԑ��Ńz�[�����芷���ł��邪�A
���}�́A�P�R���i�ꕔ�P�P���j�̓��}�u���炳���v���S�Ԑ��A�S�R���̓��}�u�Ђ��v���P�P�Ԑ��ŕʂ̃z�[���ł���B
���Ɂu�Ђ��v�͂R��̃z�[���Ȃ̂ŏ�芷������ςł���B
�V�������o���U����A���}���o���Q����ɖ��É����o������B�����Ă��̂܂܊܂Ő�s���đ���B
�����̊e��͑S�Ċ~�܂�ł���B���̊ɂ͂T�Ԑ��ɓ����A�Q����ɉ������U�Ԑ��ɓ������Đڑ�����B
�T�Ԑ��ɓ���������A�قƂ�ǂ̗�Ԃ̓z�[�����ɂ��闯�u���Ő܂�Ԃ����A�T�Ԑ�����܂�Ԃ��Ă����B
��q���邪�A����Ȃ��Ƃ͊��ł͍s��Ȃ��B�ɋ}�ڑ��̓z�[����ōs����̂�����������ł���B
��q�̗������l����̂ł���A��͂�Q�Ԑ�����o������̂��Ó��ȂƂ��낾�낤�B
�e�₪�L�����o���P�T����ɐV�������o������B
�����ƍ��킹�ĂP�R�E�P�V�����̉^�]�Ƃ���Ă��܂����A��ԉw���Ⴄ���Ƃ���v�����Ȃ����Ƃł��낤�B
�u�����v�O�͒�ԉw�̈Ⴂ�̑��ɃX�s�[�h�̈Ⴂ�����������Ƃ���A�P�O�E�Q�O�����ƂȂ��Ă����B
������͂����ƕ��ω����ꂽ�_�C���ɂȂ��Ă������肵���B
����A���J�Ŋɋ}�ڑ������Ė��É��ɓ�������B���É������̎��_�ł́A�����ƂP�U�E�P�S�����ƂȂ��Ă���B
���v���Ԃ͂S�V���A�\�葬�x�͂X�Q�D�S�L���ƂȂ��Ă���B�\�����̂Ȃ��X�s�[�h�ł���B
����⊠�J�Ŋɋ}�ڑ����邱�Ƃ�������p���͔��ɂ悭�āA�����Ȃ͖��܂��Ă���B
���É��ł͂T����Ԃ���B�����͂S����ԂȂ̂łP���������A����͖��É��`��_�̃T�C�N�������S�ȂP�T�����ɂ��邽�߂ł���B
����ɂ��Ă͂T����Ԃ͒�������B�u�����v�O�͂R���P�T�b�������B
����_�̐V�����͑��łP��������Ԏ��Ԃ��Ȃ��A�x�����ł��Ȃ����Ƃ��������A�����ł͑��قǗ��p�҂������Ȃ��A
�x�����Ă��Q�����x�̒�Ԃʼnł���Ǝv����B
���É����X���[�����q�͑����Ȃ��Ƃ͌����A���R�`������{�E�Ȑ��̊e�w�̗��p�҂͂��Ȃ肠��B
���̗��p�҂ɂƂ��ĂT���̒�Ԏ��Ԃ͒ɂ��B�������Q���A�V�������R���ɂ��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
���É�����͐V�����Ɖ����Ŋ��S�ȂP�T���T�C�N����g��ő��邽�߂ɕ�����₷���B
�����Ɠ����悤�ɁA�ł͊I���̊e��ɐڑ����A����͊e�w�ɒ�Ԃ��đ�_�ɓ�������B
���̐V�����͑�_�ŁA��_�`�Č��̋�ԗ�ԂɂV���Őڑ�����B
�V�����̓����z�[���͂P�Ԑ��Ƃ������Ƃ������A��ԗ�Ԃ͂R�ԃz�[���Ȃ̂Ōא������g��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Q�E�S�Ԑ��Ȃ�z�[�����芷�����ł��邪�A�Q�Ԑ��͉���{���A�S�Ԑ��͏��{���ŁA�ݕ���Ԃ̒ʉ߂Ȃǂ�����̂ōǂ����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�z�[�����芷�����ł��Ȃ�����Ȃ̂��A�V���Ƃ����ڑ����Ԃ�����Ă���̂��낤�B
�܂��A���̂V���̑҂����Ԃ̊Ԃɓ��}�u���炳���v���������Ă����i��_�͒�ԁj�B
�y���_�C���ł͐V�����i���ɂ͓������j�����ʉ^�]���Ă��邱�Ƃ����邪�A�����̓����͊F���ł���B
���̒��ʗ�Ԃ��R�O���T�C�N���ɂ��邽�߂ɑ�_�łV����Ԃ��ďo������[�u������Ă���B
����Ȃ��Ƃ��邭�炢�Ȃ�S�Ă̗�Ԃʂ����āA��_�ł̒�Ԏ��Ԃ��}����ׂ��ł������B
�A���ʂ��傫������Ă��邪�A�����������s��������N���A�ł���B
���}�̑҂����킹���Ԃ��Ȃ��Ȃ邪�A����͐V�����̒���ɑ��点��̂ł͂Ȃ��A�����̒���ɑ��点��N���A�ł���B
��ԗ�Ԃ͉���͂R�R���A���͂R�O���ő���B��͂�փ����ł̌��z�̉e�����o�Ă���B
����̕\�葬�x�͂U�T�D�R�L���A���͂V�P�D�W�L���Ɗe��ɂ��Ă͗��h�����A����ł��X�T�L�����炢�ɗ}���đ����Ă���B
����̓J�[�u�̉e�������邪�A���H�̋K�i�����������Ƃ������Ƃ�����B
�Č��ł́A�W���ŐV�����i���s���ʁj�ɐڑ����Ă���B
���É����畁�ʗ�Ԃ��������p���ŋ��s�E���ɍs���ꍇ�A���s�͂Q���ԂV���i�\�葬�x�U�X�D�W�L���j�A
���͂Q���ԂR�T���i�\�葬�x�V�R�D�V�L���j�ƂȂ�A�u�t�P�W�����Ձv���D�҂ɂ͍D�]�Ă���炵���B
�V������������o���V����ɁA����n���̊e�₪�o��B����͖L���n���̊e��Ɗ��S�ȂP�T�����ƂȂ��Ċ܂ő���B
���J�ŐV�����A���É��ʼn����Ɗɋ}�ڑ�����B
���É��ł̂P�R���҂��͕ς��Ȃ����A������͓��}���o�Ă��Ȃ��B
���������ĉ������o����A���Ӗ��ɂU���҂��ƂɂȂ邪�A���É��`��_���P�T���T�C�N���ɂ��邽�߂ɂ͒v�����Ȃ����Ƃł��낤�B
�ɓ���������A�Q����ɑ�_�s���̐V�����Ɛڑ�����B
���}�͖��É��P�R�������u���炳���v�A�S�R�������u�Ђ��v�ɂȂ��Ă���B
�u���炳���v�͓��C���{���㉺�z�[���̊Ԃɂ���S�Ԑ�����̔��ԁA�u�Ђ��v�͒����{���z�[���̂P�P�Ԑ����甭�Ԃ���B
�u�Ђ��v�͂W�`�P�T���܂ł͖����Ԕ��Ԃ��邪�A�u���炳���v�͂X����̌�A�P�O�`�Q�O���܂ł͂Q���Ԃ����ɑ���B
�܂��A�P�O�E�P�U�E�P�W�E�Q�O����͂P�P���ɔ��Ԃ���ȂǕs�m��ł���B
�P�O����͂܂������̃T�C�N���ɂȂ��Ă��Ȃ����炾���A�[������̂R�{�͂Q���������ĊŐV�����Ƒ҂����킹�����Ă���B
�u�Ђ��v�ɂ��Ă�������{�ɒ�Ԃ��Ȃ����̂�����i�ނ��낻����̗�Ԃ̕��������Ȃ����j�A����͊ɂO�������ƂȂ��Ă���B
���É���V�����̂S����ɏo�����Ă��邪�A�����̎��_�łU���ɍL�����Ă���B
����́A�u�Ђ��v�͂P�P�Ԑ�����o�����ă|�C���g��������n�邩��������i�ނ��߂ŁA���s���\�͐V�����Ƒ��F�Ȃ��B
�����Ĕ�����{�ɒ�Ԃ��Ȃ��u�Ђ��v�͐V�����Ɠ������v���Ԃő����Ă���B
�ɂ͍��R�{���z�[���̂R�E�S�Ԑ��ɓ������A�Q�`�S���قǒ�Ԃ��ăX�C�b�`�o�b�N�ŏo�����Ă����B
�u���炳���v�͍��S����̂S�W�T�n���g���Ă��邩��ŁA������͒P�ɃX�s�[�h���o���Ȃ����߂ł���B
�`��_�͐V�������e��ɂȂ邽�߂ɁA��_�������_�łR�����܂ŋl�߂邱�ƂɂȂ�B
��_�`�Č��̋�ԗ�ԂƂ́A��_���S����s���ďo�����邪�A�Č������̎��_�łP�O���ɂ����L�����Ă��Ȃ��B
����́A���}���V����o�R�̉���{���I�[�g���g���Ă��邩��ŁA���C�@�֎Ԏ���͂�����̕��������ł������������A
�d�Ԃł͂قƂ�Ǎ����t���Ȃ��Ȃ������߂ł���B�܂��A���H�̋K�i����`�������̂ō����ő���Ȃ��Ƃ������Ƃ�����B
�Č��ł͖k���{���z�[���ɓ������āA�X�C�b�`�o�b�N���ċ�����ʂɌ������Ă����B
����Ԃɂ��ẮA��_�`�L���̐V�����E�����Ɗe��̃p�^�[���͉���Ɠ����ł���B
�҂����Ԃ⏊�v���ԂȂǂׂ̍����Ƃ���͈���Ă��邪�A�ɋ}�ڑ�����w��^�]�Ԋu�������ł���B
�Č��`��_�̋�ԗ�Ԃ͉���ƈႢ�A��_�ʼn����ɂT���Őڑ����Ă���B
�����Ċł́A�V�����E�������o�����Ă���U����ɏo�����Ă���B
����͊e�₪���蕛�{���̂T�Ԑ����甭�Ԃ��邽�߂ŁA�K�i���g���Ă̏�芷���ɂȂ邽�߂ł��낤�B
�X�ɓ��}�ɂ��Ă͉����̒���ɑ���B�ł͏�L�̂U���̑҂����Ԃ̊Ԃɓ��}���o������B
���}�̖��É����͂��������V���O��ƂR�V���O��ŁA�P�`�Q������Ă����肷�邱�Ƃ������B
�܂��A����̂悤�Ɂu�Ђ��v�͂S�R���A�u���炳���v�͂P�R���Ɩ��m�ȋ敪�͂Ȃ��A
�u���炳���v�͂V�������A�u�Ђ��v�͂R�V���𒆐S�ɂV���i�O��j�ɓ���������̂�����i���R�u���炳���v�̑���Ȃ����ԁj�B
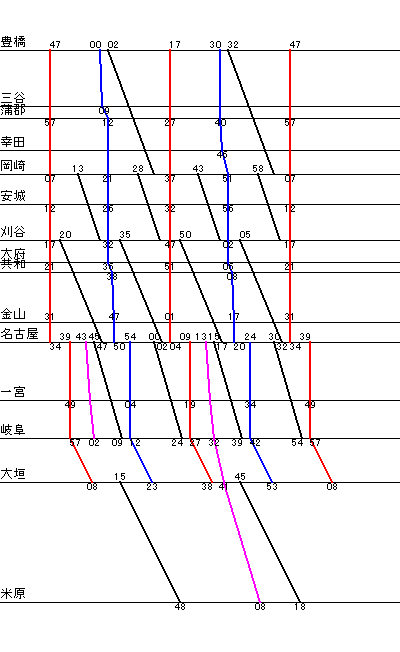
���F�͓��}�A�ԐF�͐V�����A�F�͉����A���F�͊e��
�����͖����̔������܂��͒�����
��Ԃɂ���Ă͂P�����x�x���Ȃ���̂�����
���}�u���C�h�r���[�Ђ��v�Ŕ�����{�ɒ�Ԃ��Ȃ����̂͊����O����
�[���b�V�����ɂ��Ă������̃_�C���p�^�[���P���Ă���B���������̓_�ň���Ă���B
�܂��w�ł̒�Ԏ��Ԃ����������Ȃ��Ă���̂Łi�ƌ����Ă��P�T�b�`�R�O�b���x�j�A�����̔��Ԏ��Ԃƍ����ł���B
�܂������̉^�]���Ȃ��Ȃ�A�����̃X�W�ɐV�������A�V�����̃X�W�ɓ��ʉ���������B
���̂��߁A���������Q�����x���v���Ԃ������Ȃ��Ă��A�قړ����_�C���p�^�[�����ێ��ł���̂ł���B
�Ȃ������̃X�W�ɐV���������邪�A�O�͎O�J�A�K�c�ɂ���Ԃ���B�܂苤�a�ɒ�܂�Ȃ��Ȃ��������ł���B
�����ē��ʉ����́A�œ��}�ɔ����������̂�����B
�����͐V���������}�ɂS����s���Ė��É����o�����Ă����̂ŁA��_�܂ł����Ɛ�s���邱�Ƃ��ł������A
�[���͓��ʉ����̖��É������Q���x���Ȃ��Ă���̂ŁA���}�Ƃ̍����Q�������Ȃ����߂ł���B
���ʉ����͊���e�w�ɒ�Ԃ���̂ŁA��_�̎�O�œ��}�ɒǂ�����Ă��܂��̂ł���B
����ɑ�_�`�Č��̋�ԗ�Ԃ͂Ȃ��Ȃ�A�V�����E���ʉ��������̂܂������i�[�������O�A��_�P�T�F�S�T���̂��̂���j�B
��_�ł͎��Ԓ����̂��߂ɁA�����̐ڑ����ԂƓ������Ԃ�����Ԃ���B
�������������肩�Ǝv�����A�œ��}�ɔ����������̂͂قƂ�Ǒ҂����ԂȂ��ŏo�����邱�ƂɂȂ�B
�܂����{���̗�Ԃ͑�_�Ő藣�����s�����߂ɁA�����P�T�E�S�T�����Ƃ����̂�������̂���B
��{�`���É��ł͕��L������̋�ԉ��������ʂ��Ă���B
����͒����b�V�����Ɠ����悤�ɁA��������{��ʉ߂�������ɏo��������̂ł���B
�ȏ�̂悤�ȑ���͂��邪�A��{�I�ɂ͓����ƕς��Ȃ��B
�[���b�V�����ɂ��Ă������̃_�C���p�^�[���P���Ă���B���������̓_�ň���Ă���B
�܂��w�ł̒�Ԏ��Ԃ����������Ȃ��Ă���̂Łi�ƌ����Ă��P�T�b�`�R�O�b���x�j�A�����̔��Ԏ��Ԃƍ����ł���B
�܂������̉^�]���Ȃ��Ȃ�A�����̃X�W�ɐV�������A�V�����̃X�W�ɓ��ʉ���������B
���̂��߁A���������Q�����x���v���Ԃ������Ȃ��Ă��A�قړ����_�C���p�^�[�����ێ��ł���̂ł���B
�Ȃ������̃X�W�ɐV���������邪�A�O�͎O�J�A�K�c�ɂ���Ԃ���B�܂苤�a�ɒ�܂�Ȃ��Ȃ��������ł���B
�����ē��ʉ����́A�œ��}�ɔ����������̂�����B
�����͐V���������}�ɂS����s���Ė��É����o�����Ă����̂ŁA��_�܂ł����Ɛ�s���邱�Ƃ��ł������A
�[���͓��ʉ����̖��É������Q���x���Ȃ��Ă���̂ŁA���}�Ƃ̍����Q�������Ȃ����߂ł���B
���ʉ����͊���e�w�ɒ�Ԃ���̂ŁA��_�̎�O�œ��}�ɒǂ�����Ă��܂��̂ł���B
����ɑ�_�`�Č��̋�ԗ�Ԃ͂Ȃ��Ȃ�A�V�����E���ʉ��������̂܂������i�[�������O�A��_�P�T�F�S�T���̂��̂���j�B
��_�ł͎��Ԓ����̂��߂ɁA�����̐ڑ����ԂƓ������Ԃ�����Ԃ���B
�������������肩�Ǝv�����A�œ��}�ɔ����������̂͂قƂ�Ǒ҂����ԂȂ��ŏo�����邱�ƂɂȂ�B
�܂����{���̗�Ԃ͑�_�Ő藣�����s�����߂ɁA�����P�T�E�S�T�����Ƃ����̂�������̂���B
��{�`���É��ł͕��L������̋�ԉ��������ʂ��Ă���B
����͒����b�V�����Ɠ����悤�ɁA��������{��ʉ߂�������ɏo��������̂ł���B
�ȏ�̂悤�ȑ���͂��邪�A��{�I�ɂ͓����ƕς��Ȃ��B
�[���b�V�����ɂ��Ă������̃_�C���p�^�[���P���Ă���B���������̓_�ň���Ă���B
�܂��w�ł̒�Ԏ��Ԃ����������Ȃ��Ă���̂Łi�ƌ����Ă��P�T�b�`�R�O�b���x�j�A�����̔��Ԏ��Ԃƍ����ł���B
�܂������̉^�]���Ȃ��Ȃ�A�����̃X�W�ɐV�������A�V�����̃X�W�ɓ��ʉ���������B
���̂��߁A���������Q�����x���v���Ԃ������Ȃ��Ă��A�قړ����_�C���p�^�[�����ێ��ł���̂ł���B
�Ȃ������̃X�W�ɐV���������邪�A�O�͎O�J�A�K�c�ɂ���Ԃ���B�܂苤�a�ɒ�܂�Ȃ��Ȃ��������ł���B
�����ē��ʉ����́A�œ��}�ɔ����������̂�����B
�����͐V���������}�ɂS����s���Ė��É����o�����Ă����̂ŁA��_�܂ł����Ɛ�s���邱�Ƃ��ł������A
�[���͓��ʉ����̖��É������Q���x���Ȃ��Ă���̂ŁA���}�Ƃ̍����Q�������Ȃ����߂ł���B
���ʉ����͊���e�w�ɒ�Ԃ���̂ŁA��_�̎�O�œ��}�ɒǂ�����Ă��܂��̂ł���B
����ɑ�_�`�Č��̋�ԗ�Ԃ͂Ȃ��Ȃ�A�V�����E���ʉ��������̂܂������i�[�������O�A��_�P�T�F�S�T���̂��̂���j�B
��_�ł͎��Ԓ����̂��߂ɁA�����̐ڑ����ԂƓ������Ԃ�����Ԃ���B
�������������肩�Ǝv�����A�œ��}�ɔ����������̂͂قƂ�Ǒ҂����ԂȂ��ŏo�����邱�ƂɂȂ�B
�܂����{���̗�Ԃ͑�_�Ő藣�����s�����߂ɁA�����P�T�E�S�T�����Ƃ����̂�������̂���B
��{�`���É��ł͕��L������̋�ԉ��������ʂ��Ă���B
����͒����b�V�����Ɠ����悤�ɁA��������{��ʉ߂�������ɏo��������̂ł���B
�ȏ�̂悤�ȑ���͂��邪�A��{�I�ɂ͓����ƕς��Ȃ��B
����ŏI�́A
��_�Q�R�F�Q�Q���Č��s���i��_�ŋ��R�Q�Q�F�S�O�n���A���É��Q�Q�F�S�W�������ƂR���Őڑ��j�A
�L���Q�P�F�T�Q���փ����s���i���É��Q�R�F�P�W���A��_�Q�R�F�T�U���j�A
�L���Q�Q�F�S�Q���i�����O�F�O�R���j��_�s���A
�l���Q�R�F�O�V���i�L���Q�R�F�O�V���j����s���A
���ŏI�́A
��_�Q�Q�F�R�T���i���É��Q�R�F�P�T���j�L���s����ԉ����A
�Q�Q�F�T�P���i���É��Q�R�F�Q�Q���j���S�s���i�őO�q�̑�_�n���ƂS���Őڑ��j
��_�Q�R�F�O�T���i���É��Q�R�F�S�V���j�L���s���i�Łu���[�����C�g�Ȃ���v�ɔ��������j�A
��_�Q�R�F�O�X���i���É��Q�R�F�S�P���j�����s���u���[�����C�g�Ȃ���v�i��ԉw�͐V�����̒�ԉw�{��ρj�A
���Q�R�F�O�Q���i�P�H�P�X�F�Q�Q�n�������j��_�s���A
��_�Q�R�F�R�V�����É��s���i��_�őO�q�̕P�H�n���ƂQ���Őڑ��j�A
���É��O�F�P�V����{�s���i�O�q�̑�_�n���ƂP���Őڑ��j�ƂȂ��Ă���B
�@
�@
����
�ԗ��ʂɂ����ẮA313�n�̓����ɂ���Ė��É�������113�n���������ꂽ�B
�܂����[��117�n���g����ԂȂǂ��c���Ă��邪�A���R�����Ȃǂ̋�ԗ�Ԃ̉^�p���قƂ�ǂł���B
313�n���g�p���Ă���V����������́A130�L���^�]���s����\�肾�������A���S�����D�ʂɗ����Ă��邽�߂����������ƂȂ��Ă��܂����B
130�L���^�]�ɂ�薼�É��`��16�����x�ɒZ�k����A�L���`���É��ɂ��Ă�2���ȏ�̎��ԒZ�k���ł����̂ł��낤���A
���̌��m�@��ATS�Ȃǂ̐M�����u��130�L���Ή��Ɍ������Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�����ւ̓������n���ɂȂ�Ȃ��̂ł���B
�܂�JR���C�́A���C���V�����̉^�A�������S�^�A������85�����߂Ă���ƌ����A
��ɐV�����̐ݔ��������s���Ă���̂ŁA�ݗ����ɗ͂�����Ȃ��Ƃ����̂��{���ł͂Ȃ����낤���B
�܂����݁A�������ݕ��w���疼�É��ݕ��^�[�~�i�����o�R���Đ����É��`�܂ő����Ă��鐼���É��`��������B
����͉ݕ���p�H���ł��邪�A���q�������肵�Č��݂��̍H�����ł���B
�H���͐����É��`����A����u���܂ʼn����\��ł���B
�X�ɂ͏튊���Ɍ��݂���钆�����ۋ�`�܂ŐL���v�悪����炵�����A���R�̂��ƂȂ��疼�S�͂���������Ă��炸�ǂ��Ȃ邩������Ȃ��B
�����É��`���͖��É��w�œ��C���{���̗��q���Ƃ͂Ȃ����Ă��炸�A���ݕ����ɃX���[���Ă���B
���̂��߁A�������ۋ�`�܂ŊJ�ʂ����Ƃ��͈����̗��q���������������̂Ǝv����B
���̎��͕Č��E��_�E���琼���É��`���o�R�ŋ�`�ɍs����Ԃ���������邾�낤�B
���c��`���ɂ͓��}�������Ă��邪�A����ł͒Z�����ŁA�����l�͂����ɃV�r�A�Ȗʂ����邽�߂ɉ�����̂ƂȂ邾�낤�B
�ԂƂ̋��������邱�Ƃ��痿���͗}�������Ƃ���ł���B
�����炭�A�����̉����E�V�����̊Ԃ��ʂ��āA�P�T�����ɉ������^�]�����̂��낤�B
�܂����ݕ����͔��f���œ��C��ʎ��ƂƂȂ����Ă��邱�Ƃ���A����ɏ�����ď��삩��X�ɒ����{���ɏ�����邱�Ƃ��ł���B
�����͕��L������튊���܂ʼn��L����\�肾�������A���S�Ƃ̕��s�H���������͂�����̕����y���ɗ��ւ��ǂ������ł���B
�@
�@
���P�_
�e�w�Ŋɋ}�ڑ����s���Ă��āA��Ԃ̍ō����x���P�Q�O�L���ƕ���͂Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ������ȃ_�C����g��ł��邪�A����ł��܂����P�_�͑����B
�܂��A����Ɗł̊ɋ}�ڑ��ł���B
����ł͊e��̂Q�{�ɂP�{���A�ł͑S�Ă��܂�Ԃ��^�]���s���Ă���B
�������A�܂�Ԃ����ɐ܂�Ԃ������g�킸�ɓ��������z�[������܂�Ԃ��o�����Ă���B
�����ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ̓T�[�r�X�_�E���Ƃ��Ă܂��s���Ȃ��B
�ǂ��������Ƃ��ƌ����ƁA�w����̗�Ƃ��ċ����Ă݂�Ƃ悭������B
�w�ł͂P�Ԑ������{���A�U�Ԑ�������{���ƂȂ��Ă��āA�n���̊e��͂Q�E�S�E�T�Ԑ��Ń����_���Ő܂�Ԃ��Ă���B
�Q�Ԑ��͐��m�Ɍ����Ɛ܂�Ԃ��ł͂Ȃ��A�ݕ��^�[�~�i���̒�����܂�Ԃ����Ǝg���Ă�����A��_�d�ԋ悩��o�ɂ��Ă������̂ł���B
���͂T�Ԑ��Ő܂�Ԃ����ł���B
���É����ʂ��痈���e�₩������E�V�����ɏ�芷����ɂ́A�z�[�����芷���ƂȂ邩��֗��ł���B
�������A�����E�V�����ɏ���đ�_���ʂ������Ă����l���A�ȓ��̊e���ԉw�ɍs�����Ƃ��鎞�͑�ςł���B
�P�Ԑ�����T�Ԑ��Ɉړ����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A���Ȃ�ʓ|�ł���B
�S�Ԑ��܂�Ԃ��Ɏ����ẮA���E���藼���Ƃ��K�i���g���Ă̈ړ��ƂȂ�B
�܂��A�w������l���ǂ̃z�[�����甭�Ԃ���̂�������ɂ����B
���̂悤�Ȗʓ|���Ȃ������߂ɂ��A�����͂T�Ԑ��A�o���͂Q�Ԑ��ɌŒ肷��ׂ��ł���B
�z�[���̐����ɂ͐܂�Ԃ������Q�{����B���R�{���𗯒u���邽�߂ɍ��ꂽ���̂����A�ː��������Ă��肷���ɂł��g����B
���܂蒷���͂Ȃ����A�����̊e��͂R�`�S���Ґ��Ȃ̂Ŗ��͂Ȃ��͂��ł���B
�������R�{���������Ƃ��ǂ��悤�Ȃ��Ƃ�����Ȃ�A���܂ʼn^�]��L���Đ܂�Ԃ��Ƃ����������B
���݁A���͉����E�V�������������Ă���e�₪���Ԃ���܂łU���̊Ԋu�A
����͊e�₪�������Ă�������E�V��������������܂łQ���̊Ԋu�ł���B
����������̊e��́A���É��ʼn����E�V�������o�Ă���U����ɏo�����Ă���̂ŁA������Q����ɏo��������A
�ŁA�e�₪�����Ă�������E�V��������������Ԋu�͂U���ɂȂ�B��������ΐ��܂ōs���Ă��]�T���ł���B
���̏�~�l���͂���Ȃɑ����͂Ȃ����A�����╶���{�݂�����̂ŁA���É�����P���ԂɂW�{�S�Ă̗�Ԃ���s���Đ��ɍs���A
���ɕ֗��ɂȂ��ď�~�l���͑�����Ǝv����B
��Ԗ{���𑝂₵�������~�l�����������̂��A��~�l���������������Ԗ{���𑝂₷�̂��A
����͌{�Ɨ��̖��łǂ��炪�����Ƃ������Ȃ����A��͂�{�������Ă���������ʋ@�ւƂ�����B
����ɂ��Ă��������Ƃ������A�܂�Ԃ�����݂��āA�����͂P�Ԑ��A���Ԃ͂R�E�S�Ԑ��Ƃ��ׂ��ł���B
�������ɂ���đ�_�`�Č��͑S���R�O�����̉^�]�ɂȂ����B
����������A�փ��������́A�����ɂȂ��Ă��Ȃ��Ɣ������������B
�ȑO�͉��������ڑ�_�Ȑ��������Ă������A�������ɂ���ē����̒��ʗ�Ԃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�A�ȑO�̂T���̂P�ɂȂ��Ă��܂�������ł���B
��������_�ł͉����E�V�������P�Ԑ��ɒ�܂�A�Č�����̗�Ԃ͂R�Ԑ��ɓ������邱�Ƃ������A���̏ꍇ�͌א������g���K�v������B
��͂�א������g���Ă̏�芷���͖�肪����B
�א������g��Ȃ��悤�z�[�����芷���ɂ���ɂ́A��_�w����������K�v������B
�������A�����ƊȒP�ȕ��@������B
���݁A�����E�V�����͂R�P�R�n�𒆐S�Ƃ����S���A�܂��͂Q�{�S�̂U���Ґ��ʼn^�s����Ă��āA��_�`�Č��͂R�P�R�n�Q���Ґ��ʼn^�s����Ă���B
�����E�V�����͂܂��S���Ґ��������Ă��邪�A����ł͗A���͕s���ł���B�S�ĂU���Ґ��ɂ��ׂ��ł���B
�S�ĂQ�{�S�̂U���Ґ��Ƃ��āA��_�Ő藣���A�Q���Ґ���Č��܂ő��点��ׂ��ł���B
��_�ł̒�Ԏ��Ԃ͂Q�`�R���K�v�ɂȂ�A�������ȑO�̒��ʂ��������Ȃ��Ă��܂����A���̎��̒��ʎԗ��͂P�P�V�n�ŁA
�ō����x���P�P�O�L���ō����x���A�Q���Ȃ̂ł悭�x�����Ă����B�����瑍���I�Ɍ���ΈȑO��葁���Ȃ�͂��ł���B
�A���͂ɉ����ĕ����E�������s����悤�A�Q���Ґ���o�ꂳ�����̂�����A��͂肱�ꂪ�{���̎d�����낤�B
�]�k�����A����A�փ��������̔������������ƌ��������A���͑�_�͂����Ƒ傫�Ȕ������������B
����͢������ȑO�͂P���ԂɂW�{�̉^�]�ŁA�V�����ɂ�閼�É��܂ł̏��v���Ԃ��Q�W���������̂ɑ��A
�e����Ő܂�Ԃ��A�Ȑ��͉����E�V�������e�w�ɒ�߂�悤�ɂ������߁A�P���ԂɂS�{�Ɍ��ցA���v���Ԃ��R�O���ɉ��т�����ł���B
�܂ōs���̂ɂ͊m���ɕs�ւɂȂ����B���������É�����A�鎞�͂��������ɕs�ւɂȂ��Ă��Ȃ��B
�ȑO�̉����Ԃ́A�e��͊ʼn����E�V�����ɔ�������Ă������߁A�����A��_�܂Ő�s������̂͂P���ԂɂS�{�������̂ł���B
����Ԃ͖��É��܂Ő�s���Ă������߂Ɋe��ɏ���Ă��悩�������A
��_��V�����̂Q����ɔ��ԁA���É��ɂP�{��̉����̂Q���O�ɓ�������_�C����g��ł����B
������A�V�����ɃM���M�����x�ꂽ�l�������p���Ȃ��e�₾�����Ƃ�������B
�������e�₪�����ł��x������ƁA���É���O�Ō��̉������m���m���^�]�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��������B
�i�q���C�͗A���͂ɍ��킹�Ăƌ����Ă��邪�A����͐������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�������S���Ґ��ł͑�_�łقڐȂ����܂��Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA�S�Ă��U���Ґ��ɂ���K�v�͂���Ǝv���B
���āA��L�̂悤�ɂQ�{�S�̂U���Ґ��ő��点��ƁA�L�����ł��傫�ȃ����b�g������Ǝv����B
��͂�t���̂Q����L���Ŕѓc���ɒ��ʂ�����̂ł���B���݂ł����[�ɍs���Ă��邪�A�ǂ����Ȃ�S���s���Ăق������̂ł���B
���S���L���ׂ���V���É��ւ̒��ʗ�Ԃ����邪�A�R�O�����ɋ}�s�������Ă��邾���ł���B
�i�q�͖L���o�R�ʼn����Ȃ邪�A���S�̓��}�ƃ^�C�ő��邱�Ƃ��ł���B
���S�̋}�s�͒�ԉw����������A�L���o�R�ł��\���ɏ����Ƃ��ł���A�A�A���ԓI�ɂ́B
�������^���ʂł́A�ѓc�����n����ʐ��Ƃ������Ƃ������ď��ĂȂ��B
�L��`���R�E���É��ɓ���^����ݒ肷��K�v������B
���͖L���`���R�E���É��ɂ��Ă�����^���͐ݒ肳��Ă��Ȃ��̂ł���B
�ѓc���̔����w�͐V�邪�Ó��ȂƂ���ł���B
�L��ł͒Z�����Č��ʂ��o�Ȃ����A�{���ɂ���Ɖ������đ�ʂ̑������K�v�ɂȂ�i�����Ƃ��P�P�X�n�����낻�늷���������j�B
�Ƃ肠�����͉������V�����̂ǂ��炩��������āA�R�O�����ɏ������̂��Ó����낤�B�K�v�ɂȂ�P�T������������B
�X�ɂ͖L�����瓌�A�l���܂ŏ������ׂ��ł���B
�L�������ɓ����Q�O���T�C�N���A�����R�O���T�C�N���i�P�T���ƍl���Ă�����Ă������j�ɂȂ��Ă��āA���܂����ݍ����Ă��Ȃ��B
�����ŕl���`�L�����P�T���T�C�N���ɕύX���āA�������V�����̂ǂ��炩�������ꂳ����B
�ѓc��������̂��߂ɐ藣���āA�]�����S���Ґ��ʂ�����̂�������������Ȃ��B
�L������V����l�������������R�O�����ōs���āA�L���ɖ߂��Ă������ɓ����Ґ����m�ŕ������ł���B
��������ƂR�O���ɂP�{�����É����璼�ʂɂȂ�B�É���������R�O���ɂP�{�����ꂳ���āA�P�T�����̉^�]�ɂ���ׂ��ł���B
�É��n��͂P�O�����ɑ����Ă���A�������{�������c�܂�Ԃ��ƂȂ��Ă���B�l���ɂ͂U�{�̂����̂S�{���炢������B
�����痝�_��͂P�O�E�Q�O�����ɉ^�]����Ȃǂ��ĂR�O���ɂP�{��L�����ʂɂ��邱�Ƃ͂ł���B
�����Ƃ��É��n��ł����낻��A�P�T���T�C�N���ɂ������^�]���K�v�Ȏ����ɗ��Ă���Ǝv�����B
����͒������ۋ�`�����݂���A���S�튊�����������ď�����邪�A�i�q���������\��͍��̂Ƃ���Ȃ��B
�������O�q�����悤�ɁA�����É��`�������q�������ɂ������āA���ꂪ���ۋ�`�܂ŏ������\�����傫���B
���̎��̃_�C�����ǂ��Ȃ邩�ł���B
�܂�����u���܂Ō��݂������_�ŁA���[�V�D�T�����A�����P�T�����̉^�]�ɂȂ�Ƃ���Ă���B
�Ս`�n�т𑖂邽�߂ɂ��̒��x�ł��Ó��Ȑ��ł��낤�B
���C���{�������É��`��_�łP�T���T�C�N����g��ł���̂Ń_�C���͑g�݂₷���B
�܂����É��`������{�암�ł͈��ݕ����������Ă���̂ŁA������ɑ��点��Ί����̗�Ԃ�W�Q����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����A
���ڐ����É��`���̃z�[���ɃX���[���邱�Ƃ��ł���B