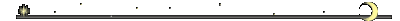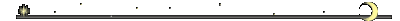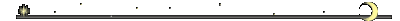
Call 7
BACK
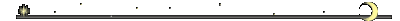
| <SIDE 拓也> 「あれ、聖夜じゃない?」 最初、ひそめられていた声は、そこに立つ人物が『聖夜』本人だとわかると、きゃーという黄色い声に変わった。 「聖夜よ、撮影かしら?」 「綺麗ねぇ……」 ホテルのロビー中央に置かれた、見事なクリスマスツリーのところで、金髪の美女がカメラマンに向かってニッコリ笑っている。 ざわざわと、その風景を取り囲むように人垣ができていく。人垣の中には、手の空いたホテル従業員の姿もあった。 それを見届けて、拓也と勝也はフロントへと向かった。 「聖夜のマネージャーです、部屋をお願いしていたはずですが」 フロントにいた女性は柔らかく微笑んで、一本のルームキーをカウンターの上に静かに置いた。 「ありがとう。支配人は……?」 「少々お待ち下さいませ」 女性は内線電話で、支配人を呼び出した。 支配人が到着するまでのわずかな時間さえも、拓也は焼けるような焦燥感に襲われる。 ―――ここに京がいる。どこかに、今も捉えられている……――― そう思うと、居ても立ってもいられない。今すぐ全室を開けて、探し回りたかった。 だが、それは即、京の身を危険に曝してしまうだろう。焦る気持ちをぐっとこらえる。今は……、自分に出来ることをするんだ。それが京を救い出す事に繋がるんだ。 必死で言い聞かせる。 「タクちゃん、大丈夫?」 勝也が気遣うように、小さな声で尋ねてくる。よほど、顔色が悪いのだろうと思う。 昨日は一睡も出来なかった。正也や勝也は仮眠を取ったようだが、自分はずっと、洋也と一緒に、これからのことを話し合ってきた。 つまり、京を救い出した後の事を……。 救い出しただけでは、京はまた、同じような連中に狙われるだろう。それを防止する為に、できるだけの手は打たなくてはならない。 洋也たちが作り上げた「R」という人物を、これからもダミーとして存在させ続けるのか、「Kv」自体を公表してしまうか、ロバートとの約束通り、これからも「I」社とあらたに契約を結び、製作者の秘密を確約してもらうか……。 けれどどの案を採ってみても、決め手に欠けた。京が帰ってこなければ、決められないのだと気付いて……。 「大丈夫だよ」 「お待たせしました」 拓也が答えるのと、支配人がやってくるのとは同時だった。 「お部屋の事でちょっとお願いがあるのですが……」 拓也は打ち合わせ通り、ストーカーが心配なので、各階に異常がないか、調べたいのだと言った。 聖夜のファンだという支配人は、撮影風景が気になっているのか、拓也との話は上の空で、いいですよといった。 「ありがとうございます。聖夜もきっと喜びます」 その一言はかなり効果があったようだ。彼はフロアマネージャーを呼び寄せ、便宜を図るようにといった。自分はこれから聖夜の撮影を見るつもりらしい。 拓也と勝也はフロアマネージャーに連れられ、とりあえず、聖夜にと用意された部屋に落ちついた。 聖夜がストーカーに付きまとわれて困っている事を切々と訴え、拓也はこのホテルに、ずっと部屋にこもったきりの人はいないかと聞いた。 聖夜のスケジュールを知り、前もって隠れているのかもしれないと、不安そうな顔をする。 フロアマネージャーは、ふと眉を寄せ、迷う素振りを見せた。 「聖夜が、もしこのホテルでもしもの事があったら、マスコミが……」 何気なく言ったつもりの一言が、効を奏す。 「実は……」 マネージャーは、くれぐれもご内密にと言いながら、……ある部屋を教えてくれた。 「ヒロちゃん、わかった」 携帯を取り出して、洋也に電話をかける。もちろん、向こうもプリペイド式の携帯だ。 『間違いないか?』 「うん、フロアマネージャーに聞いてあたりをつけた。その階の清掃担当の人に聞いて確かめたら、外国人が3人。内一人は日系人みたい。京のことはわからないけれど、部屋には清掃も入れないでこもりっきり。教えられた通り、パソコン繋いでアクセスかけてみたんだけど、その部屋、確かに通信、繋いでる」 『上の部屋は押さえたか?』 「うん、勝也に行かせて、上の部屋を取った。チェックアウトしたばかりで渋られちゃったけど、なんとかね。今、勝也がそこにいる」 本当は、今すぐにでも乗りこみたかった。 ドアを叩いて、飛びこみ、京を救い出したい。 心はそれを望んでいた。けれど、ギリギリの理性が、そんな自分を諌めている。 相手は少なくとも三人いる。どんな武器を持っているのかもわからない。一人で飛びこんで、犯人の一人を相手にしている間に、残りの誰かが京を傷つけたりしたら……。 そう考えるとぞっとした。 『わかった。じゃあ、今からプログラム引渡しに関する、メールを送るから』 洋也の言葉に、拓也はゴクリと息を飲む。 「わかった」 喉が痛むほど、からからに乾いていた。緊張しているのだろう。当たり前だ。 失敗は、決して許されない。 「うん、お願い」 今は信じるしかない。これが最良の方法なのだと。 ―――京……、もうすぐだから。どうか、無事で……――― 今はまだ祈るしか出来なかった……。 ********** |
|
| <SIDE 京> 手や指先を一切使わず、白い刃の先だけで京のシャツが開かれてゆく。 京は身じろぎさえままならない緊張の中、その動きから目が離せないでいた。 時折刃先が皮膚を掠め、薄い切り傷から淡い血が浮かぶ。 小さな傷が増える度、反射的に緊張する京の身体が楽しいのか、爬虫類男はわざと動きを狂わせている節があった。 じっくり楽しむようにナイフを操る陰湿な男に、叶わないと解っていても止めて欲しいと願う視線を必死で送る京。 そしてその様子を大男が面白気に見つめるという悪趣味な構図。 『やっぱり東洋人の肌っていいわよね...キメが細かくて。体臭も薄いし』 『お前だって日系だろうが。しかし東洋人の裸をこうやってじっくり見るのは初めてだな』 『肉食の歴史が長い白人のとはまた違って良いものよ。特にこのコ。なかなか上物だわ...』 『確かに奇麗だな。しかし細いな...本当に男か?コレ。』 『胸は無いみたいだけど』 クスクスと笑いながら、爬虫類男が肌蹴たシャツの布地にナイフを引っかけ、一気に引き降ろした。 布地の裂ける音。 京は思わず目をつぶる。 次に何をされるかなど、どれを考えてみても最悪ととれるもの以外思い浮かばない。 自分の耳にも響いてくるほど心臓の音が高い。 酸素を求める口は塞がれ、息苦しさが一層増してゆく。 いっそ気を失えたらどれだけ楽だろう。 京は霞む思考の中、ギリギリの所で意識を保ってしまう自分を呪わずにはいられなかった。 『こういう子の泣き姿ってそそるわね。縛られてるのも倒錯的だし、好みダワ...フフ』 『妙な色気があるしな。このボウヤ』 大男の無骨な手が京の脇腹を撫であげる。 「〜〜〜〜〜〜!!」 その感触に京の身体が怖気上がり涙が滲む。 必死で首を振りながら逃れようとするが、身を捩るのが精一杯の身体はあっけなく捕らえられてしまう。 『デニムもゆるゆるだ...ちゃんと食ってねーのかな?』 そう言って大男の手がウエストにかかる。 直接触れるざらついた硬い皮膚の感触に全身鳥肌が立った。 『その辺の女より全然いいな』 肌の感触を更に楽しもうとするかのように、男の手がウエストの隙間をくぐり、下着の中へと潜り込んでくる。 (い..いやだ!.............拓也さん!!!) 痛いのはまだいい。どんなものでも耐えようとそう決めていた。 だが、そういう意図で身体を触られるのだけは絶対に厭だった。 自分の身体は既に自分だけのものではないのだ。 しかし、もし、そうなったとしたら、自分はどうすればいいのだろう。 一切の抵抗も出来ない事は目に見えている。 まさかこの状況で自分の身体がそういう意味を持つなど考えもしていなかった。 無造作な手がベルトにかかる。 (.....!拓也さん...!!) 『なにやってんの?私が遊んでんのよ!ジャマしないで!』 突然金切り声が上がった。 『ちょっとくれぇいいじゃねぇか。ケチくせぇ...』 『図々しいのよ』 『はいはい』 『まぁ、いいわ。ちょっとあんた。その子後ろから押さえてて』 『なにするんだよ?』 そう言いつつも、大男は京の身体を抱き起こし、床に胡座をかくように座った自分の上に乗せる。 『やっぱ軽いなぁ。ちゃんと食ってるか?ボウヤ』 『そうそう。それでいいわ』 満足そうな声。 『"そっち"で良い反応見せられたのは面白くないけど...今の「嫌がる顔」はカナリ良かったからね。さぁもう一度。今度はナイフで見せてもらわなきゃ』 ぞっとするような笑みを浮かべると、爬虫類男は慣れた仕草で京の左胸部に、ほぼ刃渡りの先1/3ほどの範囲を押し当てた。 「...!」 プツ...という厭な感触のすぐ後に訪れる激痛。 浅く広い範囲で埋め込まれてゆく刃。 押すでなく引くでなく。 ただ押し付けてゆく力。 文字どおり身裂けてゆく激しい痛みに、身体が本能的に逃げを打つ。 『暴れるなよ』 見透かされたように、体が更に強い力で拘束される。 「...ぐっ...!」 『大丈夫。ここは皮膚は薄いけど、深くなければそんなに沢山の血は出ないわ』 しかし、刃が埋め込まれていく部分から生暖かい濡れたものが腹部を伝い流れ落ちているのが解る。 (....ぁっ!!あ.....!父さん!母さん!....拓也さんっ!拓也さん!!) 痛みを逃そうと喘ぐが、相変わらず塞がれたままの口ではそれもままならず、苦し紛れに京は天を仰いだ。 その無防備に晒された首筋を、後ろから抱きかかえるようにしていた大男の舌がぞろりと舐める。 あまりの感触に京の塞がれた口からくぐもった絶叫が放たれた。 大男の手は京の身体を這い回り手触りを楽しんでいる。気付けば男の股間は服の下に押し込められているにもかかわらず、恐ろしいほど大きさまで膨れ上がり、京の後ろに当たっていた。 (た..たすけて!拓也さん!!) 限界だった。 今まで何処か冷めていた部分も一瞬で蒸発したかのように消え去り、辛うじてその部分で継ぎとめていた精神がバラバラに千切れてゆく。 「っ!!」 (.........は..........吐.....く...) ********** |