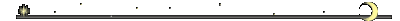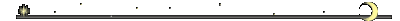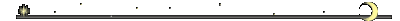
Call 10
BACK
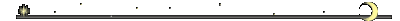
| 「拓也さんになら...なにされてもいい......痛くしていいよ」 思うより先に言葉になった。 |
|
| その言葉を聞いて、拓也はこみ上げてくるものを隠しきれず、また一粒涙を落とした。こんなにも京は傷ついているというのに、自分は何をしようとしているのか。 「拓也さん……、嫌だ」 京は拓也の涙を見ると、しがみついてきた。 「ごめん、京。傷が治ったら、これを受けとって」 拓也が箱の蓋を閉めようとするのに、京は激しく首を振る。 「今でないと嫌だ。拓也さんの手で、つけて」 見上げてくる目の澄んだ色に、拓也はいたたまれなくなる。やめてやらなければ、そう思うのに、どうしても、京を縛り付けたいという欲望を押さえることは出来なかった。 氷で念を入れて冷やし、赤くなって、感覚が遠のいたのを確かめて消毒をしてから、拓也はその器具を右の耳朶に押し当てる。 「いい?」 「うん」 京の返事を聞いてから、拓也は指に力をこめた。 「ッ!」 バチッという音の後、器具の手応えがなくなる。そっと離すと、京の耳にはそれが付けられていた。 「ついた?」 「見てご覧」 部屋のドレッサーの前に京を連れていく。 白い耳朶に、青味を帯びたその石が、輝いていた。 「これ、サファイヤ?」 「違うよ。ルビー」 ルビーというのは紅い色ではなかったか? 鏡の中の京が、不思議そうに拓也を見た。 「珍しい物を見つけて、京の知っている海とは違うかもしれないけど、似合いそうな気がして。ルースで買おうかと思ったんだけど、いつも京を僕の物にしたかったんだよ」 拓也が告白すると、京はありがとうと唇だけを動かした。 「痛むだろ?」 拓也が心配そうに聞くと、京は小さく笑って、痛み止め飲んでいるから大丈夫と囁いた。 「しばらくシャワーも無理だって言われてるから、身体を拭いてあげるよ」 「い、いい。自分で出来る」 今にも京をバスルームに連れていきそうな拓也を、京は慌てて引き止める。 「僕がしてあげたいんだよ? ね?」 いつもの優しい笑顔で諭すように言われ、頬にキスまでされて、京は黙りこむ。逃げ出したいと思いながらも、心は拓也の傍を選んでいる。 「わ、わー、拓也さん!」 横抱きに抱き上げられ、京は慌てた声をあげる。 「何?」 「は、はずかしいよ」 「どうして? こうしてあのホテルから病院の救急治療室まで運んだんだよ?」 京の頬が朱に染まる。 「やっぱり気がついてなかったんだなあ。途中、車で一度、目が覚めたみたいで、抱きついてきたのに」 「え? 誰が運転してたの?」 拓也に抱きついたということは、運転していたのは、拓也ではないのだろう」 「秋良さん」 「俺、みんなにお礼言ってない……」 「元気になった笑顔を見せてあげてくれれば、みんな喜ぶから。それでいいんだよ」 きっと、自分はみんなに守られている。それが嬉しかった。喜びだけが、胸の中を浸していく。 あの闇の中で感じた不安を、今の京は忘れている。脳が喜びだけを選ぼうとしている。生きる為の本能として……。 |
|
| 部屋の中にベッドがないと思っていたら、奥にもう一つ部屋があった。そこはベッドルームになっているらしい。ダブルの天蓋付きのベッドが設えてあった。 その寝室の脇のドアを開けると、そこがパウダールームになっていた。 「ここ、高いんじゃ……」 スウィートルームの中でも、きっとグレードの高いその部屋に、京は目を丸くする。 「さあ、誕生日プレゼントらしいから、わからないな。請求書は、兄さんに行くから。でも、こっそりこの部屋を取って、何をするつもりだったんだろうねー」 自分たちの『家』を持ちながら、このシーズンに部屋を取るとは、かなり前から用意していたのだろうと思われる。 京がその意味を理解したのか、頬を染める。 「じ、自分で脱ぐから」 拓也が京のボタンに手をかけると、京は慌ててシャツの前を握り締めた。 「お願い、電気、消して」 京の懇願する目に、拓也は黙って部屋のライトを、スモールにした。 京がほっと息を吐いて、衣服を剥いでいく。 拓也はそれを見て、自分も服を脱ぎ捨てた。 薄闇に浮かび上がる、京の裸体。胸には白い包帯が、幾重にも巻かれている。 「背中だけでも、シャワーをかけてあげるよ。あとでまたちゃんと巻いてあげるから」 包帯を解いていく。 ……かなり痩せている……。 それは昨日今日のことではないだろう。医者がかなり深刻に、栄養失調気味だと教えてくれた。弱っている身体には、今回のことはかなりの負担を強いただろうと思う。けれど、こんなにも痩せるには、それなりの日数が必要だったはずだ。 ずっと傍にいたのに……。 気づいてやれなかった。身体を重ねながら、幸せだという京の言葉ばかりを信用していた。 何も話してくれなのだろうか。 自分といると幸せだと言う京の言葉を信じたい。だが、それと同時に抱え込んでいるらしい、不安は、京の中では消えてはくれない。まるで、表裏一体のように……。 「拓也さん?」 振り返った京が、少し不安そうに拓也を見上げていた。拓也は安心させるように、京に微笑みをみせる。 「何もないよ。胸をタオルで押さえて。背中にシャワーをかけてあげる」 浴室内に連れて行き、シャワーの温度を確かめて、背中にかけてやる。 京の安堵の溜め息が聞こえてきた。 |
|
| 背中にぬるい温度のシャワーを静かに当ててもらいながら、京はまた一つため息を吐く。 やはり、自分が安心して息を吐けるのは拓也の前だけなのだと。 だが、逆に京は自分の中に生じた不安をどうしても拭い切れないでもいた。 先程着替えた時に見た自分の身体はあまりにも酷すぎた。無数の切り傷と青黒い痣。指先で痣に触れると、焼けるような痛みがあり、無性に自分が穢れているようで、込み上がってくる鳴咽を堪えるのがやっとだった。 拓也の傍に居たいという気持ちに嘘はないのに、彼を目の前にするのが怖い事に気付く。 そして今、まさか、プレゼントを引き取りに来た後、ホテルに連れてこられるとは思ってもみなかったので、正直な所、京は戸惑っていた。 シャワーを。と言われ、服を脱ぐのにどれだけの勇気が必要だっただろう。 包帯を外されて新たに現れた傷と、それを見た拓也の表情に息が詰まりそうになる。 どう言えばいいのだろう。 どうしたら許してもらえるだろう。 好きな人にこんな顔をさせてしまう自分の愚かさを心の底から呪った。 「痛くない?」 何処までも優しいその声に涙が零れる。 「ごめんなさい...拓也さん」 「なぜ?どうして謝るの?」 自分の無口をこれほど怨んだことはない。心を紡げる雄弁な口がが欲しい。どうしたらこの気持ちを伝えられるのか。 京はただただ首を振ることしか出来なかった。 シャワーから上がると、拓也は京をバスタオルで包みそっと抱き上げベットへと横たえた。 暖かく絞った小さなタオルを幾つか使い、どうしても洗いきれなかった場所を丁寧に拭いてゆく。 「い..よ。自分で..でき.る」 「おねがい...させて。京。」 京の哀願も優しく拒否される。 「傷が開くから。大人しくしててね」 そういいうと拓也の手が信じられない所まで延び、その部分まで丹念に拭かれ、京は恥ずかしさのあまり気を失いそうになる。 上がった心拍数のせいだろう。身体のあちこちが悲鳴を上げ心臓のように脈を打つ。 胸からじんわりと濡れた感触が広がってゆくので、少し傷が開いたのかもしれない。 痛みのせいなのか、それとも羞恥なのか。枕に押し付けた顔は熱く、京はただ溢れる涙が白い布に吸い込まれて行くのを感じていた。 どのくらいそうしていただろう。いつのまにかきつくシーツを握り締めていた手をそっと外され、抱き起こされる。 「おわったよ」 拓也が京の耳元に囁くと、右耳のピアスに唇が触れた。 京の背筋に甘い疼きが走る。 そのままキスされるとのかと期待していたのかもしれない。しかし、拓也の動きは京にバスローブを着せ始めている。 「拓也さん...?」 「...安静にしないと」 拓也の言葉に京は厭だと首を振る。 「言うこと聞いて?」 「.....嫌になった?」 「え?」 拓也の動きが止まる。 「も.....俺の事................嫌になった?」 「京。そんなことある訳ないだろう?」 嘘だと言うように京の涙が訴える。 「京」 「拓也さん...お願い」 「先生にも言われただろう?しばらく安静だって」 拓也の優しく抱きしめる腕も、心からの心配も、不安に駆られる京には別の意味で伝わる。 今どうしても抱いてもらわなければ死んでしまいそうな、そんな強迫観念にも似た欲望。 「京...頼むから...我侭言わないで」 瞬間、京の記憶が蘇る。 あの偏執的な男にナイフで刻まれた恐怖と痛み。生臭い息を自分に吹きかけながら身体中を執拗に撫で回す大きな無骨な男の手、首筋に残る生暖かく濡れた舌の感触。 そんな事をこの身に受けてしまった自分がどれだけ汚れているのか。こんな身体で拓也に抱かれたいなどと思うこと自体、罪深い事に気付く。 (拓也さん...) 欲望と自制ギリギリの狭間で、その言葉は思わず口を衝いて出た。 「俺......汚い?」 |