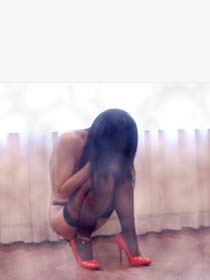 昼間のあたたかさを裏切るようにして、夜の闇ととも冷気が忍びこんでくる。 そんな初秋の風に、薄手のコートの襟を立て。マンションの脇にある、外付けの階段に回りこむ。 エレベーターは、いつしかまったく使わないようになっていた。 人と会ったり挨拶したりするのは、煩わしかったし。何よりも、ここに自分が存在することを、誰にも知られたくなかった。 マンションですれ違う人などが、それほど自分に興味を持つはずもないのに。 それでも、誰にも知られずに存在していたい。 そう思うのは、稼業のせいか、それとも単なる自意識過剰なのか・・・などと考え、苦笑しながら、怪盗YUKIはマンションの脇の階段に差しかかった。 そのとき。 階段に、白い野良猫が、膝を抱えてうずくまっている、ように見えた。 裸の白い肌。 薄手の下着だけの、ヒップラインを隠すようにして。 野良猫は、うつむきかげんに夜の寒さに震えている。 「な、なにやってんの? こんな所で!」 YUKIはそう言いながらも、寒そうな野良猫の背中に薄手のコートを、思わず差しかける。 うずくまっているその姿に、自分の心の状態が重なりあうような気がして。そうせずにはいられなかったのだ。 YUKIの姿を見つけると、野良猫はじっと、その目を見つめる。 瞬時に、敵か味方かを判断するような目。 そうして、野良猫は、判断を下す。 「放置されちゃったの・・・お願い・・・部屋に入れて」 野良猫は、生きるためのすべてを自分で判断する。 そのときYUKIは、判断を下されるだけの存在でしかなくなる。 どんな意思もそこには存在しない。 つまり、断るなどという余地は、そこにはないのだ。 YUKIは、その言葉に吸い込まれるようにして。 野良猫を自分の部屋に導いた。 * * * YUKIは、野良猫を部屋のソファに座らせて、あたたかいココアを差し出した。 なにか、着るものを・・と、思ったが。 これで十分、と言って、薄手のコートを羽織ったままだ。 「クルミって言うの、よろしくね」 そう言って、野良猫が笑う。 彼女が心を開くと、赦されたような気持ちになった。だが逆に、素直にそんな気持ちになれる自分が不安になったりもした。 いくつかの仕事を一緒にこなしたSARAは、今、ここにはいない。新しい男ができて、サイパンに旅行中だ。 帰国すればまた、おみやげなどを手にこの部屋に寄ったりもするだろうが。今の彼女は、ここよりか男の部屋にいる時間の方が長い。 幸せを妬むほど狭量ではない。だが、心を許しあった分だけ、孤独の分量は以前よりも増えたような気がしていた。 「ひどい男ね。こんな目に遭わせて」 YUKIが、そう言うと、そんなもんかな、という目でクルミが見つめる。 「わたしが自分を放っておいたから、って彼は言うのよ。そんなつもりなんてなかったのにね」 こまめにメールを送る男なのだと言う。 だから、ちゃんと、あとで返事しようって、そのときは思うの。でも、他のことで頭がいっぱいだったりすると、夜にゆっくり書こう、なんて思って。でも夜にメール書いてても、そのまま眠ってしまったりして。そんなことが何度か続いて。 それで、ひさしぶりに会ったら。 放って置かれる方の気持ちになってみろ、なんて言われて、車から放り出されちゃった。 「それにしても、ひどい・・・こんな格好で・・」 「うーん、そうかなあ。これはこれで、いいのよ。あの人、普段はそんなことするような人じゃないんだけど。そうしてみたかったんじゃないのかな? わたしの、さみしそうな顔とか、困った表情がいいって。それで、そんなふうにしたかったのよ、きっと」 ぐるぐるぐるぐる。 YUKIの思考回路は、高速に回転したが、それでも理解することができない。 「じゃ、彼は、どっかで隠れて、あんたのことを見てたわけ?」 「ううん。それはないと思う。それじゃ単なるまぬけだし、おもしろくないじゃない? そのまま家に帰って、想像して楽しむのね。裸のわたしがどんな目に遭ってるか、とか・・・それが楽しいんじゃない?」 「危ない目に遭ってるかもしれないじゃない」 「それも想像するのかなあ・・・でも、わたし、野良猫だから。やっぱり、どっかで生き延びるって思うのかもしれない」 クルミは、自分がひどいことされたなんて思っていないようにも見える。 むしろ、放り出されるという行為を楽しんでいるみたいだ。 放り出され、どっかを歩き回るというのが、まるで自分が自分自身に戻ってゆく行為であるかのようにも見える。 それは、ある種のプレイというやつなのか? 趣味の世界は広くて、YUKIには理解できないものばかりだ。 クルミは、吸い込まれるようなくるんとした目と、とてつもなくやせっぽっちの身体を除けば、どこにでもいる普通の女の子だ。 あるいは、誰だって、そんな趣味嗜好のひとつやふたつはあるのかもしれない。 SARAがボンテージの衣装を好むように・・ キャッツ探偵事務所のスギが、かつてSMの女王をやっていたように・・・ いずれにしても、わたしには関係のないことだ。 日頃は、これと言った男関係もなく、ここで息を潜めるようにして暮らしているが。こういう暮らしを続けるために、男関係を一切断ってきたわけではない。 そういう機会に恵まれなかっただけだ。 クルミはすぐに帰るだろう、と思っていたが。 このような一日に疲労したのか、膝を抱えたままで、ソファで寝息をたてはじめていた。 それで取り急ぎシャワーを浴び、YUKIもまた、別のソファに横たわる。 信用していないわけではない。だが、この部屋の中は見られてはいけないものばかりだ。出来心で何かを持って帰られては、大変なことになる。 そんなことを考えながら、YUKIは浅い眠りのあいだを、行き来していたが。 明け方、目覚めると、クルミの姿はすでにそこになかった。 コートはあとで返します、というメモだけが残っている。 慌てて部屋の中を見回したが、何かを物色した形跡もない。 まるで、野良猫。 ふらりとここに入ってきたのと同じようにして。 何事もなかったように、ここから、出てゆく。 * * * YUKIは、以前はきらびやかな怪盗ぶりに自分でも酔いしれていたが、リスクの大きさもあり、最近は堅実な仕事が多くなってきた。 キャッツ探偵事務所の方も、最近は小さな仕事に追われていると風の噂に聞く。 主に金銭がらみの失踪者探しだ。それでも景気の悪い世の中で生き残れた分だけ、キャッツは幸せなのかもしれない。 だけど、お互い、面白味がなくなってきた。 それでも、キャッツを嘲笑しようという気にはなれない。所詮自分も同じ穴のムジナだ。 つい最近の仕事と言えば、宝石商の外回りの営業車から、宝石入りのカバンをひとつ失敬したくらいだ。 人が良くて気が弱そうな営業部員に目をつけていたところ、カバンを車に置いたまま昼食に出かけたのだ。 郊外レストランの駐車場で、車のカギを開けるなんて、とても簡単。まるで、自分の車からバッグを取り出すみたいに平気な顔してやれた。 宝石にはだいたい保険がかけられている。だから、派手でない分だけリスクも少なかった。 その宝石は、馴染みの闇業者がすぐに換金してくれた。 質屋などに流通すればすぐに足がつくはずなのに、どう、売りさばくつもりなのか、と、不思議に思って尋ねると、ロレックスの時計が不似合いな太った男は、笑いながらそれに答えた。 「YUKIさんも、こんな仕事してるわりには経済には弱いんだなあ。世の中には、裏金ってものがあるんだよ。銀行にも預けられない、家を建てても怪しまれる、そんなふうに、表に出られないお金が、あるところにはあるんだよ。帳簿に載せられない、税務署も把握できない金がさ。そんな使い道のない金は、どうしたらいいと思う? 闇で使うのが一番安全なのさ。そんな金があるかぎり、俺たちの商売は困らないんだよ。今時、派手な窃盗は流行らない。警察の動きもその分大きくなるからね。これからもこんな感じでやってくれよ。これくらいなら、すぐに捌けるからさ」 まあ、あんたも、それで生きてるわけだから、わかってるとは思うけど、と男は、いまどきめずらしい金歯を見せて笑った。 たしかにその金で、YUKIは、ある程度お金に困らない生活を続けられていられた。毎日自宅のマシンで身体を鍛え、図書館やパソコンで地図を読んだりして過ごしてゆける。地図を見ていると、いくつもの大きな窃盗を想像できた。それだけで、時間を忘れられるくらいに、幸せだった。 だけど、誰にも知られずにそうして生きてゆくことが、ときおり虚しくなったりもする。 工場で部品を組み立てるみたいに、簡単な窃盗を繰り返していると。 いつか、何かがすり減ってゆくのかもしれない。 そんな不安を感じはじめていた。 * * * 夜も遅くに、YUKIのマンションのチャイムが鳴る。 こんな時間に・・と、いぶかしげに覗いてみると、所在なさげにクルミが立っている。 「この前のコート、返しに来たの」 と言うクルミ。中に招こうとすると、彼も連れてきたけど一緒にいいか、と尋ねる。 ここにいろんな人が出入りするのをYUKIはあまり好まない。だが、断る術もなく、招き入れてしまった。 誰かを連れてくるのは、野良猫が、餌場を同じ野良猫にこっそりと教えるような。そんな感じにも思えたし。 何よりも、どんな男か、見てみたかったからだ。 クルミと同い年くらいだろうか、品のいいダークスーツの男性が、大好物のピエトロのケーキを持って玄関に立っている。 「突然ですが、お邪魔ではなかったですか?」と、丁寧な言葉遣い。 「彼。秀一」と、クルミ。 「先日は、ご迷惑をかけてすみませんでした。これ、お詫びに。僕のお気に入りの店のものなんですけど」 丹精な顔立ち、。背が高くて、育ちの良さそうな雰囲気。 とてもあのような趣味の男とは思えない。 女の子をひどい目に遭わせて、となじってやりたい気持ちも、ピエトロのケーキを前にして、しゅるしゅると消え失せてしまった。 「普段はしないようなことを、してしまいました。僕は、クルミにいやらしい格好をさせて写真を撮ったりするのが好きなんです。彼女は、それを人に見られるのが好きで。おもに、そういうのはそう言った類のお店の中でやるんですが。あのときは、仕事で失敗して落ち込んでて。それで、自分たちの領域でない部分に踏み込んでしまった」 「でも、自分の領域でないことって・・・やっぱり、楽しい?」 「そうですね。ワクワクした。家に帰っても、今頃、どんな目に遭ってるだろうかと、いろいろ考えて・・・でも、もう、やらないと思う。なんていうか。そういうのって、みんな領域があると思うんです。野外が好きなカップルもいれば、室内で危険のない場所を好む人間も多い。ぼくたちは、やはり、安全な室内で遊ぶタイプなんです・・・」 「野外でって、そんなのが好きな人もいるの?」 「ぼくたちが行くスナックのマスターですが、奥さんが野外で犯されるのが好きっていう人もいます。地下鉄のホームや夜の公園で、彼は奥さんの裸体を撮影します。奥さんが身もだえしてるのを見ると、自分の女が女優になったような錯覚に陥るんだそうです、あれは、生粋の変態だ。その写真をCDに焼いて、お客に配ったりもする。まあ、そういう意味では尊敬してますけど」 「そういうお店があるの?」 「興味があるんなら、ご案内しますよ、クルミなんか、盛り上がるとすぐに脱いじゃう」 「わたしは遠慮しとくわ」 ほんとは行ってみたかった。 だけど、人前で裸体を晒す人間がいれば、自分もまたそれを要求されるのかもしれない。 たとえば、SARAやスギならば喜ぶのだろう。だけど、YUKIにはその勇気はなかった。 「なるほど、いい部屋だ、クルミがここで写真を撮って欲しいってのも無理はない。よかったら、ここで写真を撮らせて貰えませんか?」 銀ラメのシンプルなTシャツのクルミの裸を想像してみた。 胃袋がほんとうに入っているのかと思うほど、ウエストが細い。そして、そこからヒップラインが桃の実のようにゆるやかに広がっている。 ジーンズごしからも想像できるそのラインの美しさを、この目で確かめたい衝動に駆られた。 「ごめんなさい、クルミの姿は見てみたい、これはほんとう。でも、この部屋の写真を撮られるのが好きじゃないの。でも、いつか、見てみたい」 「それじゃ、いつか、お見せます。クルミが言うとおり、僕もYUKIさんのことが好きになった。彼女は誰にでも心を許せる子じゃないんで。これからも、よろしくお願いします」 そう言って、ふたりはこの部屋をあとにした。 写真を撮られたくない理由はふたつあった。 ひとつは、この部屋には、見せてはいけないものがたくさんあるの で、証拠を残したくなかったから。 そして、もうひとつは。 レストランの駐車場で宝石を盗んだのは、間違えるはずもない。 この秀一の運転していた営業車だったからだ。  * * * クルミは、それから、ひとりでふらりと遊びに来るようになった。 おもに仕事が終わったあとに、泊めて、と言っては、夜遅くにやってくる。 彼とどこかに行ったりもしてるようだ。 「じゃ、あんた、ほとんど家に帰ってないんじゃない?」 と言うと、着替えとかもあるし、ときには帰るよ、と言う。 「家に帰るのがイヤなの?」 「そういうのもあるかもしれない。ひとりで部屋にいるのが嫌いなの。自分の部屋よりか、知らないところで、いつも寝ていたいんだけど。ホテルを渡り歩いたり、野宿したりするわけにもいかないしね」 仕事もいくつかかけもちしているらしく、朝から深夜まで働いていることも少なくなかった。 ねぐらを定めたくない、というのは、若者特有の格好良さを気取っているわけでもないらしい。 ここでいいよ、と、いつもソファに寝転がるクルミは、それくらい中途半端な場所で眠る仕草が、うまく身についていた。 仕事が休みだとクルミは、YUKI を散歩に誘う。 そこは、大きな複合ビルのロビーから続く長い螺旋階段だったり、市庁舎のガラス張りの玄関だったり、ひと気の少ない画廊だったりした。 「ひんやりした床が好きなの」と、クルミは言う。 「そんなところに寝そべって、上から写真撮られたりしたいなんて、思うの。大理石の床、美術館のロビー。そこにぽつんといるのって、なんだかかっこいいって思わない?」 野草の上よりも、クルミはそういうところを渡り歩く野良猫なのだろう。 でも、なかなかうまくいかない。そんなとこで変な格好してたら、おまわりさん来そうだし・・・ などとクルミは続けるが。いっしょに歩いていて、そういうクルミを想像するだけで、YUKIは心騒いだ。 クルミのイメージする世界を見てみたいと思わせるチカラ。 そんなチカラを彼女は持っていた。 歩き疲れて、お互いの身体が夕闇に紛れる頃。 クルミは、「服が見たい」と言って、雑踏の中をすたすたと歩き、店内の暗い小さな店に入った。 もちろんそこはジーンズショップなどではない。大きくスリットの入ったチャイナドレスや、ボンテージばかりが並び、その横には怪しげなカタチをした卑猥なおもちゃも並んでいるといった類の店だった。 一度シャノワールを襲撃したことはあるが、客としてこんな店に入るのははじめてだ。拘束用の椅子が正面に飾られたその店で、なんだかYUKIは恥ずかしいように顔を伏せてしまった。 「いらっしゃいませ」 女性の店員の声が、背中に追いついてくる。 「ああっ、あんた、YUKIじゃない。いったいこんなところで何してんのよ!」 意外なところでその名を呼ばれ、驚いて振り返る。 そこに立っていたのは、キャッツ探偵事務所の社員であり、元SMの女王であるスギだった。 「スギ! あ、あんたこそ、こんなところで・・・」 「まさか、ここを襲撃しようなんて思ってんじゃないでしょうね、こんなちっぽけな店、得にもなんにもならないわよ」 スギは、革製のミニスカートに、同じ素材のハーフトップの上着を着ている。腰のあたりには、金属の鎖をいくつも束ね、ヒールの細いブーツは蛇皮。まさに女王の風格だ。 「スギ、キャッツ、辞めたの? こんなとこで働いて・・・」 「まさか、辞めはしないわよ。ここは副業でバイトしてんの」 「キャッツって、仕事ないんだ」 「失礼ね、仕事は山ほどあるわ、後味の悪い、債務者探しばっかりがね。それで何だかおもしろくなくてね。気分転換にバイトさせてもらってんのよ。ところで、その子、誰?」 そう言ってスギは、値踏みするように、クルミを上から下まで舐めるように見つめた。 「YUKIさんの知り合いです、今日は服を探しに来たの」 クルミがそう言って、スギを見つめ返す。小さな火花がカチャリと飛び散った。 「ああ、あなた、スレンダーでいいわね、セパレートタイプにしたらいい。上は、切れ込みの深いVカットがいいわ。新しいのが入っているの」 そう言ってスギは、黒いボンテージを合わせてみせる。 あ、ほんと素敵と、クルミが言う。 「下はね・・・腰のラインがきれいだから、スカートなんて履いちゃダメ。これがいいわ・・・」 そう言ってスギが差し出したのは、赤いティーバックのパンティだった。前の部分が少し隠れるだけ、後ろは、まさにひも一本のヤツだ。 穴あきタイプなのよ、きつくて食い込むかもしれない。と、スギが付け加えた。 試着していいかしら・・・と、鏡の前で合わせてみるクルミを見ていたら、上はまさにぴったり。しかし、パンティは素肌につけるわけもいかず、感覚がよくわからない。 「クルミ。そのパンティ、履いてるところが見てみたい。わたしが買ってあげるから、つけてみて・・」と、思わずYUKIは口にした。 どうして? と自問したが、興味の方が勝っていたとしか言い様がない。 やっぱりちょっときつい・・・ と、クルミがその上下を着て、試着室から現れた。 すらりとした長い脚。エナメルの赤いヒールとパンティが絶妙だ。 細すぎるカラダの痛々しさが、妖しさへと変わってゆく。 「それくらい、食い込んだ方が、あんたには似合うわ。どう? 誰かに見て欲しくなったでしょ」 ここの椅子に座りなさい! と、スギが、レジ脇の椅子を指差した。それはまさに、女王様の口調だ。 言われるままにクルミがそこに座ると、スギは、手を後ろで固定し、あっという間に、クルミの両脚を椅子に手錠で繋いだ。 クルミは恥ずかしそうに顔をそむけていたが、その頬は紅潮してるようにも見える。 「その格好で留守番しててね。わたしは、YUKIとお茶でも飲んでくるから」 そう言ってスギはレジに鍵をかける。 「いいこと。ちゃんと客が来たら、お相手するんだよ」 そのままスギは、YUKIを連れて、お店の外へと消えていった。 * * * 「Mとして調教されてるわけじゃない。でも、ありゃ、マゾだね」 「どうして、そんなことわかるの?」 「匂いよ。あんたも感じない? あの子見てたら、そういうふうにしてみたくなるって。もっとも、自分で認識してるMだけがMじゃない。あんなふうに、自分を分類しきれてない人間の方が、とまどいも大きくて、やってて楽しいのよ。調教する喜びってやつね」 秀一のことを思った。彼自身サディスティックな部分はないのかもしれない、それでも、置き去りにしてみたくなる、たしかにクルミにはそういう匂いがあった。 スギは近くのスターバックスに入り、椅子に座ってラテをごちそうしてくれた。 「借りは作りたくない」とYUKIが言うと。でも、聞きたいことがあるから、と彼女は言った。 「どこから拾ってきたの、あの子」 「拾ったわけじゃない、野良猫みたいに迷いこんだだけよ」 「親がね、キャッツに捜索依頼出してんのよ」 たしかにクルミはあまり家には帰っていないはずだ。でも、捜索依頼なんて、思いもしなかった。 「でも、警察じゃなくて、なんで、キャッツなんかに・・・」 「なんか、で、悪かったわね。家にも行ったことあるけど、すごい豪邸だったよ。でも、まともな仕事じゃないね、これはあくまで勘でしかないけど。どっちかって言うと父親はダーティな仕事って雰囲気。母親は品が良くて優しそうだったけど、高そうな宝石つけてた」 「理由なんてわからない。あの子、なんにも言わないから」 「縁談から逃げてるんだって。相手は名家みたいよ。成金と名家。よくある組み合わせよね」 「つきだすつもり?」 「うーん、迷ってる。あの素材で、ふつうの奥様に収まるのかしら。それにね、すぐに見つけるよりか、情報を小出しにして長引かせた方が、こっちもお得だし」 「しばらく待ってて、お願い」 情が移ったのだろうか。今はまだ、クルミを手放したくはなかった。 秀一のことも頭によぎった。 いいよ、わたしも、そのつもりだから。 とスギが言い。 それから二人で、クルミの待つ店へと戻った。 * * * 店に戻ると、ふたりの男性客がいた。 衣装を扱うショップに男性のふたり連れというのも変だが。ここは、フロアを半分に間仕切りして、ビデオコーナーと衣装関係のコーナーに分けられている。 ただ、入り口がひとつしかないので、おそらく入店した際に、入り口付近のレジに縛られていたクルミに気づいたのだろう。 ふたりは腰をかがめて、椅子に固定されたクルミの脚を押し広げていた。 ひとりの男性が開脚させた状態で、もうひとりが、指を出し入れしているのがわかる。 激しく指を動かすたびに、クルミの中からぴちゃぴちゃという音が漏れていた。 すごい、音たててるよ、どう? 感じてるんだろう? 何も答えないクルミ。だけど、その息づかいの荒さが、ここまで伝わってくる。 それから、男がクルミのクリトリスらしき場所を、指の先で軽く刺激すると、ほんの僅かな刺激に屈するようにして、クルミはイッてしまった。 息の荒さが、止まらない。 クルミは、そのままの格好で、膝を小刻みに震わせていた。 うーん、いい感じね、とスギがつぶやく。 ふたりの客に、いらっしゃいませ、楽しんでいただけましたか? と、スギが言うと、ふたりは、ニヤニヤ笑いながら、ビデオコーナーに入ってゆく。 「さ、解放してあげるわ」 と、スギが、手錠と荒縄を外す。 クルミはそのままYUKIに駆け寄り、声を震わせて泣いた。 「いい経験したでしょ、クルミ。あんた、才能あるわ」 とスギが言う。 「また、ここにいらっしゃい、いろんなことを教えてあげるから」 クルミは涙を溜めた目のままで、スギの言葉にこっくりとうなづいた。 さ、帰ろうか、とYUKIが言うと、 「待って。YUKIさん。買って欲しいものがあるの」 と、クルミが言う。 クルミは、赤い革製の首輪をひとつ指差した。なんの変哲もない、細いシンプルな皮。特別高価なものでもない。 YUKIは、その分の金を払って、クルミと共に、店の外に出た。 「嬉しい。これ、買ってほしかったの」 クルミが嬉しそうに紙袋を胸に抱く。まるで、さっきのことなど、忘れてしまったかのようにはしゃいでいる。 あれだけの目に遭ったのに・・・そういうものなのか・・・ と思うと、余計にクルミのことがわからなくなってきた。 「誰かに、この首輪、見せたい。ねえ、この前、秀一が話してたスナックがこの近くにあるの、これから行ってみない?」 はしゃいでいるクルミに、断るすべもなく。 ふたりは、そのスナックへと、向かっていった。 * * * そのスナックは雑居ビルの一角にあった。 「会員制なんだけど、わたしと一緒だから大丈夫」 そう言って、クルミがドアをノックすると、中からヒゲのマスターがドアを開ける。 奥さんが犯されるのを見るのが好きな変態、というイメージとはほど遠い、物腰の柔らかな男性だった。 「おや、クルミちゃん、お友だちといっしょ?」 と声をかける。 見た目はまったく、何の変哲もないただのスナックだ。奥で飲んでいた3人の男性はクルミの知り合いらしく、気軽に声をかけてくる。 それでもYUKIの身体は緊張してこわばったままだ。 それを察してか、マスターが笑いながら声をかけてくれた。 「心配しないで、ここにはちゃんとルールがあるんですよ。女の子がやりたいと言えば何でもやれるけど。無理強いはしてはいけない。ストップ、と言えばそれまでなんです。もちろん、こうして座ってお酒を飲んでるだけでもいいんです。なんたって、ここは普通のスナックなんだから」 そう言われて安堵し、YUKIはそのままカウンターで水割りをちびちびと舐めていた。 クルミは、ねえ、首輪、つけてみていい? と、紙袋をびりびりと破りはじめる。 「マスター、YUKIさんに買ってもらったんだ、どう?」 「あ、いいねえ、クルミちゃん、さっそく写真撮ってあげるよ」 YUKIさん、つけて・・・というクルミの首に赤い首輪をまわしてみる。きつめに締め上げてみる。すると、首筋の細さが際立ったような気がした。 あ、そう、さっきのパンティも、と言って、クルミはジーンズを脱ぐ。 薄手のシャツも脱ぎ、ビスチェのようなデザインの黒いブラがあらわになる。 奥の男たちも歓声を上げながら、クルミにあれこれ注文をつけはじめた。 脚を椅子の上に置いて、とか、お尻を突き出してとか。 そうこうしているウチに、クルミはそのうちのひとりの背中に、ピンヒールの靴のまま足をあげる。 「おお、クルミちゃん、その格好、いいよ」 と、マスターが写真を撮る。 「そう? 今度は、馬乗りになってみるわ」 と言って、クルミは男の背中に跨る。 まるで女王のようにふるまうクルミを、YUKIは呆然と見ていた。 加虐にうち震えていたさっきまでのクルミと、女王のような今のク ルミ。 SとMというのは、同じ人格の表裏なのかもしれない。 だけど、どっちが本来のクルミなのかは、一目瞭然だった。 あのとき・・・ 椅子に縛られてうち震えるクルミほど、クルミにいとおしさを感じたことは、これまで一度もなかったからだ。  * * * その日、やってきたクルミは、いつになくドレスアップしていた。 胸の大きく開いた黒のワンピースに、同じく黒のフェイクファーのコート。相変わらずのピンヒールは銀色のパンプスだ。 そうしてクルミは、大きめのダイヤがついたペンダントを短めにつけている。 「どう? 今日の格好? 例のスナックでパーティやるの。露出が好きな人ばっかり。あっちで秀一と待ち合わせてるんだけど、YUKIさんも来ない?」 YUKIは、そのクルミのペンダントを見て、危うく絶叫しそうになる。 細長いアーモンド型にカットされた大きなダイヤ。鎖に施された柔らかくカーブするような模様。 間違いない。 秀一のカバンから盗んだ宝石の中に入っていたヤツだ。 とても気に入っていて、自分のモノにしようかと悩んだものの、こんなところで足がついてはおしまいだからと、あきらめてて売り渡したものだった。 だけど、なぜ・・クルミがそんなものを? 「これ? ママから前に貰ったヤツ。ちょっと派手すぎるから、ずっとつけてなかったんだけど、この服だといいでしょ?」 秀一がこれを見たら・・・ 秀一とて、自分の商品だとすぐに気づくはずだ。 そうすると。クルミの母親も・・・わたしも・・・ 「クルミ。あんたには、それ、似合わない。派手すぎるわ。預かっておくから、ここに置いてゆきなさい」 「えー、そんなことないわよ、きれいでしょ?」 「置いてゆくのよ! 飾り物なんて似合わない、あんたには!」 「イヤ! YUKIさん、なんでそんなこと言うの!」 「外しなさい、命令よ!」そう言って、YUKIは、そのペンダントを引っぱる。抵抗しながらも、その勢いに押され、クルミの首からペンダントが外された。 「わかったわ・・・置いてゆく・・でも、その代わりに・・・わたしにキスして・・・」 それに抗するすべもなかった。 女の子を愛したことなんてなかったし、これからも、そんなことなんてないだろう。だが、なぜだかYUKIは、クルミを抱きしめて、その薄い唇に、自分を合わせてみる。 柔らかい。なんて、柔らかいんだろう。 わたしも誰かに愛されていたとき、誰かにそんなふうに思われていたのだろうか? 「どうして、あのときYUKIさんに、首輪を買って欲しかったか、わかる?」 クルミはYUKIの目を見つめてそう言う。 「ずっと野良猫でいたいのに、ときどき誰かのものになってみたくなるのよ。わたしを縛りつける強い力に憧れるのかもしれない」 「秀一がいるじゃない」 「みんな、みんな、わたしのこと、わかってくれない。誰かひとりの人だけを頼りにして、みんな生きていけるの? 人を好きだって思うのは、もっとシンプルなものだと思う。なのにみんな、それを一括りにして、その中だけで生きていけるなんて思っている。わたしは、小さくて綺麗な石を、いくつも持っていたいだけなのに」 折れそうなクルミの細い背骨を抱きながら。 いつしかYUKIの頬には涙が流れていた。 「もう、時間だから」 と、クルミが部屋を出てゆく。 ダーティな仕事に違いない、と、スギは、クルミの家庭を評した。 そう、クルミの家が、あの換金屋の客だったのだ。 怪盗という仕事の業の深さは、身に染みているはずだった。 なのに・・・ その盗品を、巡り巡って、こんなところで見つけるなんて・・・ 巡り巡る。そうして、YUKIの業は、YUKI自身を痛めつける。 YUKIは、パーティに行くこともなく、そのまま部屋で放心していた。 * * * 数日して、クルミが来たときにはもう、彼女の顔を見る気にさえならなかった。 YUKIは自己嫌悪を繰り返し、何の言い訳も考えていなかったが。 それでも、ペンダントを返さないわけにもいかなかった。 結局、クルミを招き入れる他ないのだと、あきらめて中に入れる。 「もう、何を聞いても驚かない」 クルミは、そう切り出した。 「パパやママのことは、わたしが一番よくわかってるつもりよ。どんな仕事をしてるかも。どんなお金がウチにあるのかも。でも、ひとり娘で、誰にも負けないくらいに可愛がってもらった。それは、お金とか宝石とかじゃなくて、本当に可愛がってくれてたの。そろそろ野良猫を辞めて、結婚話も受けるつもり。潮時だなって、思ってたから」 「秀一は? 秀一のことはどうするの?」 「気づかなかった? 彼は結婚してるの。わたしたちは、プレイ上のパートナーだったけど。でも、ときどきそれ以上のものを求めあってしまってた。でも、それはどうにもならないことなのよ。彼にはもう話してあるの。でも、別れるってわけじゃない。結婚生活が落ち着いたら、今度は同等の立場で遊ぶことだってできる」 「ほんとに、それでいいの?」 「仕方ないじゃない、わたしは、パパもママも裏切れないのよ!」 そう言ったクルミの声がかすれて聞こえた。 「そんなことより、YUKIさんも、嘘はつかないで。仕事らしい仕事してないのに、こんな生活、不自然だとは思ってた。YUKIさんもアッチの世界の人なのね。別に軽蔑して言ってるわけじゃないの。わたしは、YUKIさんが大好きだったから。何をしていようと、全然構わない」 仕事をしているわたしじゃない、そんなわたしを大好きと言ってくれる人なんて。今まで、いたのだろうか? クルミには嘘はつけない、そんな気がして、洗いざらいすべてを話した。 仕事のことも、秀一のことも、そうして宝石のことも。 それから、クルミに、アーモンド型をしたダイヤのペンダントを返した。それをクルミは、もう一度首にまわした。 「不思議ね、こんなきれいな石なのに、ここには、たくさんの邪悪な物語が詰まってる。案外みんな、そうなのかもしれない。ウチだって、傍目には幸せそうな家庭で。YUKIさんだって、何の曇りもないいい人に見えるのに。みんなみんな、人に言えない汚いものを抱えてる。でも、わたしは、それがイヤなんじゃない。汚いものばっかりだから。せめて、小さな綺麗を持っていたかったの」 クルミは、そこで、ちょっと窓の外に目をやる。 「ねえ。お願いがあるの」 そう言って、クルミがじっと見つめる。 その目は、あなたには断ることはできないはずよ、と言っていた。 クルミが淡々と話をはじめる。 そこへ、バンっとドアが開き、SARAが入ってきた。 彼氏とサイパン旅行に出かけていた、以前ここに居候していたSARAだった。 ひさびさのSARAは、こんがりと日焼けしている。手には、おみやげの束をぶらさげ、相変わらず、胸の大きく開いたTシャツにミニスカートと、冬とは思えないくらいに露出の多い服装だ。 「ねーさん、ただいまぁー。おみやげにパレオ買ってきたわよー」 そう言いながら、SARAはクルミに目をやる。 「おやまあ、きれいなお嬢さんね。それに、わたしとおんなじ匂いがする」 そう言って、SARAは、クルミの腰に手を回す。うーん、いい腰つきね、あんたも露出、好きなんでしょ? とたたみかけた。 なんで、初対面同士で、そんなことがわかるのか? SARAにしろスギにしろ、そのあたりの嗅覚はすごい。やはり蛇の道は蛇なのか? 「SARA、サイパンはどうだった?」 「うーん、もう、まったりしてた。やっぱり、彼とはまったりが一番ね」 「そんなことより、仕事よ。仕事、ていうか、お遊びみたいなもんだけど、やる?」 「やるやる、最近、おっきな仕事がなくって不満だったのよ。ひさびさね、何でもやるわよー」 そう、最近、派手な仕事なんて何ひとつしてなかった。 元々、派手な立ち回りで目立つことが大好きだったのに。なんで、こんなに保身に走ってしまってたのだろう。 クルミの言うとおりだ。この世界には邪悪なものが当たり前のように存在している。だけど、それを噛み潰すように生きてなんていられない。 わたしたちは、わたしたちのように行くだけなのだ。 SARAがいて、クルミがいて、それからわたしたちが始まる。 ひさびさにYUKIは、自分の胸の鼓動が聞こえたような気がした。  * * * 集合場所はYUKIの自宅兼オフィス。 メンバーは、SARAにクルミに、そして秀一だ。 こんなに大勢の人間がここにいるのなんて、初めてのことではないか。 これじゃ秘密のアジトでも何でもないんじゃないか、と、YUKIは苦笑した。 SARAは、シャノワールから強奪してきて未だダンボールに眠っているいろんなコスチュームをひっくり返しては、クルミに着せている。 「あんた、痩せ過ぎ! みんな胸の谷間が泳いでるわ。うーん、パットでも詰めようかしら」 「SARAさん、それはイヤ。わたし、そんなの嫌い」 「じゃさ、その衣装のまま、片足を椅子に載せてみて」 ミニのコスチュームのまま片足を上げると、剃毛してつるんとしたクルミの陰部が、その隙間から、少しだけ見えた。そこにクルミは、ふたつのピアスをつけているのだが、そこまでは残念ながら見えない。 「うーん、ピアスも見せたいのに、もったいないなあ・・・」 もっと、足、広げてみなさい。と、クルミは言われるままに広げてみせるが、どうも、SARAにはお気に召さないらしい。 「SARAさん、ぼくはクルミは、パンティ一枚がいちばん綺麗だと思うんです」 そう言いながら、秀一が、未開封の下着をビリビリと破り、ストレッチの効いた一枚を見つける。 「クルミ、これは、どう?」 クルミ、それを着用してみる。 なかなかいいとYUKIは思う。やはりクルミの事を一番よく知っているのは、秀一かもしれない。 「これ、好き」 「うーん、よく似合うよ・・・」そう言いながら、秀一は、パンティ越しにクルミに口づけをする。長い、長い口づけ・・・だんだんと、その舌が、クルミの一番感じるところに到達し、クルミの口から吐息が漏れる。 YUKIは、その様を呆然と見ていたが、「ほーら、そんなヒマないのよ」とSARAがそれを遮った。 「時間が限られているのよ。秀一、早く機材を積みなさい。それから三脚はあきらめてね。荷物はできるだけ少なくするのよ」 今回の現場の指揮は、すべてSARAに任せた。 彼女は、現場を見ただけで、防犯カメラの死角をすべてチェックした。それで、たぶん、十分なはずだ。 YUKIはあくまで監視役。だが、それでも緊張感は押さえられない。 現場を踏むときの高揚感。 この感触があるから、いつまでも、この仕事を続けていたのだ。それを、今、ようやく思い出せたような気がした。 レンタルしてきた白いワゴンに、機材を積む。 SARAは、ワゴンの中に、ノートパソコンをセットした。 「軽いハンドバッグとか、持ってる方がいいかもしれない。手ぶらだと変だから」 YUKIの言葉に、おのおのが自分の荷物をまとめ、それから4人で、ワゴンに乗り込んだ。 平日の夜、午後10時を過ぎて、夜の人混みもまばらになってくる時刻に。 ワゴン車は、複合ビルの裏にあるだだっ広い公園の脇に横付けにされた。 ここの北側が、大きな複合ビルだ。コンサートや講演会ができる大ホール、そして、小さなギャラリー。道路に面した場所は趣味のいい文具店になっている。 一階の回転ドアを抜けるとロビーは広く、とても豪華な作りだ。 そして3階より上は、オフィスビルになっている。 「3階より上の電気は真っ暗ね、もともと、お役所の出先機関が多いから、遅くまで仕事はしないの。コンサートホールも今日は使われてないし」 「ほんとに、こんなに無防備なの?」 YUKIは、少し不安になる。 「地下鉄から、このビルを通って地上に出る人が多いから、開けっ放し状態なのよ。ただ、終電が出た後は、シャッターが閉まる。そのときには、警備員が一巡するわ。でも、それは浮浪者対策。ここで寝泊まりされちゃたまらないからね」 「巡回の時間は?」 「12時50分。ふたり一組。でも、電気は全部はつけない。彼等は、懐中電灯と、無線機を持っている」 そんなやりとりを聞いて緊張したのか、コートを羽織ったクルミの脚が震えてきた。 「大丈夫よ、SARAの場所を読む目に間違いはないわ。あんたと秀一は、ちゃんと自分の仕事をすればいいのよ」 YUKIはそう言って、クルミの肩をぽんと叩いた。 痩せた野良猫の肩胛骨が、指先に刺さったような気がした。 4人は、いったん地下鉄に降りて、そこから複合ビルに上った。 なるほど、大勢とまではいかないが、会社帰りらしいサラリーマンの幾人かがビルを通り道に使っているようだ。 ただし、それは一階までだ。 通行人が使用するのは、ロビーの手前側の通路だけで、コンサートホールや広大なロビーはすでに照明が消えて真っ暗だ。一応、簡単な仕切のロープが張られているが。それは、たやすく乗り越えられるものだ。 人が途切れるのを見計らってから、4人はロープを越してロビーの奥まで行き、公園に面した大きなガラス窓へと伸びる階段を上った。 広い広い。ひんやりした床。 いつか、クルミとふたりで歩いた階段。こんな、ひんやりした所が好きなのだと彼女が言った場所だった。 音の出ないようにゴム底のブーツを選んだが、その音さえもがこだまする静けさだ。 中二階まで階段をのぼり詰めると、そこは窓に面した広い踊り場。 そこから先は階段は折れ曲がっている。 「この踊り場なら大丈夫よ。バックには、公園ごしに繁華街のネオンがキラキラしてるし。どう?」 「SARAさん、最高です」 秀一がそう言う。 「じゃ、チャッチャッとやってちょうだい。これからは、秀一とクルミの仕事よ」 クルミがするりとコートを脱いだ。 パンティ一枚で、その踊り場の窓に横たわる。 夜景が、うっすらと彼女を照らしていた。 その様子を、秀一が、階段の下から、見上げるように撮影した。 YUKIとSARAは一階のロビーに戻り、人の出入りを見張っていた。 「こういうのも、一種のプレイって言うのかなあ・・」 SARAが手持ちぶさたにつぶやく。 「わたしにはわからない。でも、わたしも、クルミが綺麗に写真に収められるところを見てみたいと思う」 「YUKIねーさんって。そういう趣味が、あったんだー」 そう言われて、かっと頬が赤くなった。女性が好き、などと考えたこともなかったが。クルミのあのクチビルの感触を思い出した。 たぶん、それは恋愛ではなかった。だけども、それに近い、なんらかの感情を、クルミには感じていたのは確かだ。 遠方の窓でポーズを取っているクルミ。 彼女の、カラダの美しさを想像しながら。 その写真を、見てみたい衝動が、湧き水のように溢れてきた。 そのとき。 後ろから、ぽんと、肩を叩かれた。 「YUKI」 見覚えのある声が、小さく低く、背後にこだまする。 緊張のきわみを突き破るような声に、YUKIは身を固くして振り返る。 そこにはキャッツ探偵事務所のスギの姿があった。 「もう、クライアントを待たせるのも限界よ。クルミの結納の日が迫ってるんだって。悪いけど、お遊びはこれまで。今日は彼女を連れてゆくわ」 スギがそう言った。 結納・・・ もう、そんなとこまで進んでいるのか・・・ クルミは何も言ってなかったけれど、彼女の言い方から察するに、おそらくその通りなのだろう。 「わかった。でも・・・もうちょっと待ってて。ふたりの撮影が終わるまで。あれが終われば、クルミはそれで帰るつもりよ。だから。それまで待って」 「最初っから、そのつもりよ」 スギは、そう言いながら、踊り場を見上げた。 「クルミ、きれいだね。服を着てるときよりも。ショップで羞恥プレイしたときよりも、今の方がずっときれいだね」 「うん・・・秀一に撮られてるクルミはきれい。いつものクルミの何倍も。クルミは、彼の前ではとてもきれいになれる」 たとえば、このままふたりが別々になったとしても。それは、憎しみとか、引き裂かれるような痛みとか、何一つないような気がした。 もっとも、別れには、それに伴う痛みは必ずあるのだが。 こんなに信頼しあっているふたりが。この世に変わらぬまま存在していることには変わりはない。 どんな流れの中にいようとも。 ふたりは、そのことを支えに生きていられる。 ふたりの中には、きっとそんなものが存在しているような気がした。 撮影が終わったらしい。 コートを羽織ったクルミが、踊り場から手を振った。 満足気な顔をした秀一が、その隣りでオーケーサインを出している。 「撤収よ!」 SARAが低い声でそう言って、4人とスギは、もう一度地下に降りて、早足で静かにワゴンに乗り込んだ。 * * * ワゴンの中で、自販機で買ったコーヒーをみんなで飲んだ。 甘い甘い缶コーヒーだった。 「あまーい。こんな甘いコーヒーなんて、ひさしぶり。でも、あったかくっておいしい」 クルミは、まだ興奮が収まらないのか、いつもよりか饒舌に見える。 「クルミ、わかってる? わたしはあなたをこれから家まで連れて帰らなきゃいけないのよ」 「スギさん、ごめいわくをかけました。でも、わたしもそのつもり。ほんとに、みんなに迷惑かけて、ごめんなさい」 秀一は、やはり別れがつらいのか、何の言葉も持たない。 そんな秀一からデジタルカメラを取り上げ、SARAは写真を確認している。うん、いい出来ね、なんていいながら、SARAはノートパソコンを広げて、写真を取り込みはじめた。 「わたしね・・・」 クルミが、コーヒーを飲みながら、ポツポツと話をはじめた。 「愛してるとか、恋人だとか、そんな言葉が大嫌いなの」 誰に対してそう言ってるのか、YUKIは真意を測りかねた。 「だって、大きな言葉で一括りにしてしまうと、いつも、少しだけ嘘が混じってしまうでしょ。それがとってもイヤなの。大きな言葉で括られると、誰かの所有物になってしまえる。でも、そこでしか生きられない。わたしが持ってるのは、もっと小さな感情。小さくて綺麗な石ころ。それがいくつか心の中に散らばっていれば、それだけでいいの。それしかないけれど。そんな小さなものには、嘘なんてひとつも混じらないもの」 秀一、と、クルミが彼の名を呼んだ。 「秀一に写真を撮られるのが好き。自分が一番自分らしく見えるし。ときには自分じゃないみたいに見えるから。秀一にキスされたりセックスしたりするのもすごく好き、そのとき愛されてるのがわかったから。わたしは秀一と一緒にいるのが好きだった。 それからYUKIさんの部屋で眠るのも好き。YUKIさんのソファって、なんだかわたしの本当のねぐらみたいだった。それから、YUKIさんといろんなところを散歩するのも楽しかったよ。 SARAさんも好き。SARAさんは会った瞬間から、はじめから友だちみたいに接してくれてたし。わたしの匂いを感じてくれるSARAさんの感覚が好きだった。 そして、スギさんも好き。わたしを探してたのがスギさんだったから、わたしは帰る気になれたの。わたしはマゾだなんて思ってなかったけど、それをすぐに見抜いてくれた。実は、今度結婚するお医者さんってサディストなのね。何度か会ってるうちにそれがわかって躊躇したけれど。今は、新しい世界を楽しめるみたいな気がしてる。 きっと、何もかもむつかしく考えすぎて、それで混乱してたのね。 もう、でも、いい。みんなの好きなところを、わたしはみんな知ったから。この小さな好きを、宝物にして、これからは生きていける」 野良猫は。こんな純粋な子だったから、野良猫になるしかなかったのかもしれない。 当たり前の世界を当たり前に受け入れることができなかったクルミ。 でも、一度、何かを知れば、彼女は、それをまっすぐに受け止めてゆけるはず。 さ、そろそろ行こうか、とスギが声をかける。 「待って。もう一度、現場に戻って!」 と、そのときSARAが叫んだ。 SARAの手には、プリントアウトしたクルミの写真が一枚。 まるで絵画のように、美しいクルミの姿がそこにはあった。 「どお? 今、加工したの。額縁も用意したわ。これを、コンサートホールのロビーに掛けていくってのはどう? 何も盗まず、跡形も残さずなんて、怪盗YUKIの名がすたるわ」 「いいねえ。いい写真よ、さっそく行こう」 と、スギが言う。 あと14分で地下鉄のシャッターが閉まる。そうSARAに施され、5人は、もう一度、複合ビルに戻った。 真っ暗なロビーに、手早くSARAがその写真をかける。 まるで、最初からその場所にあったみたいに、その写真はホールの壁にしっくりと馴染んだ。 「いいねえ、とってもいいよ」 「でも。盗むんじゃなくて、置いてゆくなんて。これじゃ、怪盗でもなんでもないわね」 とYUKIが笑う。 「ううん、盗むのよ。これを見る人の心と、立ち止まる時間を。わたしたちは奪うの。クルミの写真にはそれだけの価値がある」 SARAが満足げにそう言うと。 「ありがとう、SARAさん」 と、秀一がSARAの手を取って言った。 ここに飾られた写真が、秀一の中のふっきれてないものを、ふっきれさせてくれたのかもしれない。 どこに行ったって。写真の中のクルミは、クルミのままでここにいる。 クルミはそのままスギが連れていった。 大きく腕を振りながら、笑うようにして、クルミは去ってゆく。 ワゴンには、秀一とSARAとYUKIだけが残される。 もう、誰も何も喋らなかった。 別れに伴う痛みがあった。 だけど、それ以上に。 クルミという女の子とさっきまで一緒にいたことを、誰もが、宝物の小石のように共有していた。 * * * あれから3ヶ月もたったにもかかわらず。 その「写真」は、今も複合ビルのコンサートホールのロビーに飾られている。 ここの管理者が怠慢なのか。 それとも酔狂で、このまま飾り続けているのかは、わからない。 とりあえずクルミの写真は取り外されることもなく、最初からコンサートホールの装飾物であったかのようにして、今も飾られている。 YUKIはときおり地下鉄を利用することがあると、ふらりとコンサートホールの中を覗いては、その写真を確かめる。 野良猫のようにふらふらと動きまわるクルミでもなく。子供のような丸い声でポツポツと喋るクルミでもない。ただ、おとなしく、物憂げに横たわっているクルミだったけれど。その身体はいつも、いろんなことを語りかけてくれるような気がした。 「こんなとこにいたのね」 後ろから、声をかけられ振り返る。そこにはスギの姿があった。 「クルミの両親は、とても喜んでいたよ、クルミが帰ってきて。あの子も子供みたいにしおらしくしてた。突拍子もないくせに、なんだか変な子だったね」 「ほんとに結婚するの?」 「ああ。今頃もう、新婚旅行だってよ。あそこの成金おやじ、ご祝儀にって、ウチの支払いもはずんでくれた。クルミは今度は大病院の若奥様だよ」 「落ち着いたら、また、YUKIのとこに遊びにくるってさ。そのときは、わたしも呼んで。それから秀一やSARAも集まって遊ぼうよ、わたし、またクルミを調教したりしてさ」 「そうだね、みんなで集まろう」 そう言ってはじめて、YUKIの心に「みんなで」という言葉が、鐘が鳴るように響きだした。 仲間なんて、と思っていたのに。いつのまにか、何人かが集まって、そうして仲間になっている。野良猫同士の集まりのような自分たちなのに。いつか、みんなで、なんて言っている。 息を潜めるように生きてなんていられない。 仲間がいて、ときに集い、バカなことやって。そんなことを想像するだけで、こうも人生は彩られるのだ。 「あ、スギ、もしかしたら、また、副業の方に行くとこ?」 「あたり。ほんと、キャッツもだんだん仕事が地味になってくるんだから。わたしもちょい欲求不満よ。ま、それを解消するのにアダルトショップやってんだけどね。あんたもさ、こんなとこでくすぶってないで、わたしたちがびっくりするような事、やってみせてよねー」 日々の生活に困らない程度の金はある。 堅実な窃盗でも金は稼げるし、何もしなくたって、しばらくはまったく困らない。 だけど、そんな毎日なんて、クソくらえだ。 「じゃ、今度は。キャッツもタジタジの大事件を起こしてあげるから、楽しみにしてなさいよ」 と答えると、スギが蛇皮のブーツをトンと鳴らした。 「そうこなくっちゃ。あんたが守りに入ると、こっちもつまらなくてしょうがないわ。言ったわね、ぜったい言ったわね。また、どっかの宝石屋で、あんたを裸にして天井からぶらさげて蝋燭たらしてあげるから。そっちこそ、楽しみにしてなさいよー」 そう言って、スギは、夜の仕事へと向かっていった。 YUKIは、もう一度、クルミの写真を見つめる。 不在のさみしさと、それを埋めるものが、交互に騒がしく、胸の中を行き交ってゆく。 その感触をしばらく味わってから。 YUKIは、夕刻の雑踏を、家路へと向かっていった。 「おしまい」 |