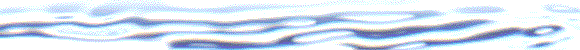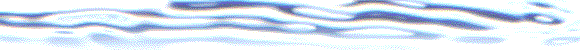
韓国詩のコーナーⅧ
目次
|
金経株 李昇夏 105韓国詩人選 金思寅 黄炳承 高銀(2) 崔正礼(2) 千良姫 呉世栄(2) 金恵順 朴柱澤 朴賞淳 文泰俊 金宣佑(2) 「詩と思想」2006・7月号 高炯烈(2) チョン クッピョル 韓国女性小説家 金ミョンニ 羅喜徳(2) 『今日の詩 韓国詩21人集』 崔泳美(3) |
|
金経株 風の年代記は誰かがすべて記録する 佐川亜紀訳 1 例えば氷河は私の中に風を凍らせ数世紀とうとうと流れる 極点に達した登山家たちが雪山の雪を拾い食べながら相談する 幾百年溶けなかった雪をぼくらは今食べている昨夜 氷の世界に閉じ込められた数世紀 ぼくは風を食べてからこの風に到達しようと 人々は数世紀の間 神聖な人生に遅刻するために 山をさまよった そして時々そこで山彦を鳴らしてから 生が 届かないところだけ 行って 山彦は 浸る 山彦は風の前で人間がする唯一の方式ではないとか ある日鏡を割るやいなや内に入った風が青空に向かって満開だ でも誰かがぼくの顔を手探りしながら噛んだ まず歌から始めようよ 2 風は生きている化石だ 生きているあらゆるものが 消えてなくなった後も自ら生き残り さまよう人々は 自分の世界の中で泣く しかし生きているあらゆるものは 風の世界の中で泣きながら行く 風が吹くよ 鳥たちは 自分の 夢の中で飛び立つ 人間の瞳を持つ鳥たちを眺めながら自分は まっすぐに来る 人の目の中をさまよう それは風の年代記の前で生きながら行った 人々のかすかな笑みかもしれない いわば風にやたらにタメ口をたたくなっていう冗談みたいな ピアノになった木 佐川亜紀訳 1# 夕方になれば水差しを持ってピアノに水をやりに来る男がいる ピアノに花が咲くと信じる男の習性だ 2# 手の爪をかみちぎる女は好きだ 手の爪をかみちぎる男を 理由なく別れる 手の爪は指と 3# 女が自分の家でピアノを盗みに入った 男と女はピアノに鳥籠をつるし海の中に沈めた そして男は女の指を夜中に吸ってやった 4# 海の中 ピアノが今日の昼間ちょっと抱いてやり ピアノが開ける十の穴に話す 男が開ける十の穴はひくひくしながら鳴く これは鳥が生きられない穴に対する習性だ 5# ピアノに花が咲くと信じる これはぼくの悲運でもよく あなたの不滅でなくともよい ピアノになった木がずっと以前 花が咲いたところを思う夜 ピアノは木と別れた ここは因縁に魅惑されたこの星の習性だ ■キム・ギョンジュ 1976年光州生まれ。2003年ソウル新聞(大韓毎日) 新春文芸で当選し登壇。2005年大山創作基金を受ける。 フリーのコピーライター、映画制作などに携わる。 現在、韓国ソウルの大型書店・教保文庫で 第一詩集『ぼくはこの世に無い季節だ』が売り上げ8位(8/11現在。次の週に7位)の人気詩人! ポストモダンの作風ですが叙情性は残っています。 韓国近現代詩は、来年生誕百年を迎え、8月11日から13日まで記念行事が催されました。 韓国現代詩人協会も50周年となり、東アジア詩人フォーラムに 日本からなべくらますみさんと私が招かれました。 中国、台湾、モンゴル、ベトナムの詩人、それにアメリカ、チェコの研究者が参加しました。 アメリカの詩人は、時調(韓国の短歌)風の詩をユーモアこめて作っていました。 この人は25年前に日本で俳句集を出したこともあるというハーバード大学の先生です。 まったく器用で語学力がすごいです。 フォーラムのテーマは「グローバル化時代の東アジア詩の役割で、 会長の呉世栄は、グローバル化で実利主義が進み、地球環境破壊も憂慮される中、 詩人は東洋思想を見直し、禅詩、仏教、儒教、シャーマニズムなどを生かしていこうと提起しました。 韓国では、詩において日本よりずっと東洋伝統思想を重んじてきました。 その成果を今世紀に広めたいという意気込みも感じられます。 金光林、金宗吉、金鐘海、成賛慶、文貞姫、柳岸津、朴柱澤、国際交流担当の権宅明などの 韓国詩人の方々がいらっしゃいました。 行事の合間に、翻訳家でもある韓成禮と一緒に中堅詩人の金基澤、李珍明と会食しました。 その後、ソウルの大きな書店・教保文庫に行きました。 驚いたのは日本の小説の翻訳本が多いことです。 芥川賞・直木賞作品、人気作家は同時出版かと思う早さ。 夏休みのせいか、書店に若者が一杯いました。 この日本小説ブームについて呉世栄は、文化のグローバル化現象で、 韓国でもポストモダンの「未来派」の詩人が現れたが、 思想を重んじる伝統は変わらないだろうと語っていました。 だが、さすがの韓国詩も最近やや求心力が弱まっているようで 詩集の場所も少し狭くなった印象があります。 それでも、新書から近代詩選集まで平積みで、専用棚もいくつもあり、 各出版社は文庫版的シリーズ本をたくさん出し、 日本とは比較にならない量です。 売り上げランキングのコーナーにも詩部門があり、 1、2位は、日本でも翻訳書が出たリュ・シファが独占。 リュ・シファは、18、20位にも昔の詩集が入る圧倒的強さ。 このコーナーでも紹介し、日本語訳が出ています。 本格的な現代詩人は、4位に女性詩人で人気・実力とも高い金宣佑。 8位(8/11現在。次の週には7位)の金経株は、日本のポストモダンの詩に似ています。 本人写真もかっこよく、今までの誠実が前面に出た韓国詩人像とは全く違います。 上記に訳したようにしゃれた感覚を楽しむ詩です。 有名詩人が選ぶアンソロジーが流行り、10位のうち半分を占めます。 総体的に抒情詩、愛の詩が主流です。 12、13日は、ソウルから車で4時間くらいの江原道の万海村で祝典。 万海とは、詩人・僧侶・独立運動家であった韓龍雲の号。 今年の万海大賞・文学部門は重鎮で女性詩人の金南祚が受けました。 夜の野外朗読と歌の会は、詩人ばかりでなく、 お坊さんもたくさんいて、一般参加者も多く、詩を楽しんでいました。 徴兵制の軍事訓練中で、面会のために山から降りた若者もいました。 従軍慰安婦をテーマにした詩を書いた20枚ほどの布も風にはためいていました。 宿泊所のテレビをつけたらアフガンの人質に関する報道をしていました。 韓国詩人は未来志向を強調し、文化創造の活気に満ちていました。 映像文化やIT文化が今後いっそう発展するでしょうが、 百年を経て、さらに新しい韓国現代詩の歩みも始まっています。 (敬称略) 李昇夏 あざ 権宅明・佐川亜紀訳 あなたの首筋と手の甲に残っている 青かびのようなあざを見た 湿布が隠せなかったあざは 殴られていた時間を思い返しているのだろうか あざが代わりに あなたの痛さを語ってくれる あなたは黙って 車窓の漢江の風景を見ているけど 赤黒い夕焼けの沈む漢江を ぼんやりと見ていたあなたの目に ゆっくりと浮かぶ水分を見た 密かに、しかし注意深く見たらあざの色は どんよりして薄黒い いや、濁った青色だ 殴られた妻たちのあざが あの空を濁った 青色のあざだらけにして 空があんなに顔をしかめているのか 痛さに夜は太陽を吐き出したはず 痛さに海は津波で湧き上がり 痛さに人は夜光虫のように光る あざの色を記憶しながら生きる あざができた女よ あなたの皮膚に息をふうふう吹きかけたいのだが 心まであざができていないかと気遣って こっそり、しかし注意深く 盗み見だけしている あの首筋、手の甲の青い痕跡 牛が闘う 李昇夏 佐川亜紀訳 砂原は四方とてつもなく広い 熱い力と力がぶつかる にらむあの牛の目は リングに上がる格闘技選手のようだ 泡を口元にぐっと溜め 前足で豪快に砂原を蹴る 銅鑼よ鳴れ 向き合った力に応じて力が出る 四方八方に砂がはじけ 人々の歓声・・・・牛と人の力がはじける あいつが負ければ俺の力が全部抜ける あいつが勝てばほかの力まで俺の力になる世界 一方の牛の角にもっと大きい怒りが積まれ 別の牛の後ろ足が押され始める 力で突け 力で迎え撃つ 砂原にはじける血 ぱらつくつば ネズミが死んだように静かになる闘いの場 つばきをずるずる流しながら苦痛をこらえる牛が とうとう逃げ出す 銅鑼が鳴り 闘いが終わる 一方はもっと大きい歓声を立て 別の方は罵声を吐く 追われ疾走する牛がこの上なく憎く 勝った牛は残った力をどうにもできずふうふう荒い息をする 勝った牛の主人はカッとつばを吐き出す 青い紙幣と黄色い小切手が行き来する時ごとに 人間の目つきが牛の目つきより もっと殺伐としている さらにもっと怒りに満ちている ※DV(ドメステイック・バイオレンス)は、日本で問題になっていますが、 韓国でも以前から憂慮されてきました。韓国では家庭内暴力というそうです。 詩作品として書かれるのは珍しく、技巧的にも工夫されています。 李昇夏は2007年の素月詩文学賞候補に挙げられている男性詩人です。 詩集に『暴力と狂気の日々』があり、そうしたテーマを追求しています。 ※李昇夏(イ・スン・ハ) 1960年慶北義城生まれ。 中央大学文芸創作科および同大学院博士課程卒業。 1984年<中央日報>新春文芸に詩、1989年<京郷新聞>新春文芸に小説が当選。 詩集、<愛の探求><ヨブの悲しみが分かりますか><暴力と狂気の日々> <生命から物件に><痛恨の星を捜して><人間の村に夜が来る>。 詩論集、<世界を魅惑した不滅の詩人たち><李昇夏教授の詩創作教室> <韓国詩文学の空地を探して><韓国現代詩と諷刺の美学>等。 大韓民国文学新人賞、芝薫文学賞、中央文学賞受賞。 現在、中央大学文芸創作科教授。 105韓国詩人選 韓国村の庭園で 高昌秀 高貞愛訳 秋しばらく 庭園のイチョウは 孔雀が翼を広げるように 目映い金色の葉を広げていた ある日 品のある庭師はイチョウの中ほど大枝に上り しきりに木を揺るがしていた 日を背にした逆光の庭師は 厳しく黒い魔法使いのように 地球の中心にまで及べと しきりにイチョウの葉を落とした その日 庭園は怪しげな笑みを含んでいた それからは わたしが音楽を聞いていても 町を歩いていても 黒イチョウの葉は わたしの存在の暗い深淵に 果てしなく落ちて行った 秋の間中 黒い枝はわたしの意識に クモの巣のように拡がっていた イチョウの木には 戦いで焼き焦がれたブリキ切れのような木の葉いくつかと 黒い枝が空を背にしてか弱く揺れた 見えない風の息遣いに 木は荒んだうら淋しい身振りでわたしを泣かせた いく羽かのカササギも物悲しいらしく いつにでも立ち去る勢いで枝に止まったりした 冬風が吹き雪が降った 雪のリズムで景色は変わって 黒い枝の木はたまゆらに踊りを踊っていた やがて やつれていた枝には 金色絢爛たるイチョウの葉がいっぱい満ち輝いていた 庭師はどこへ行ったか見えなかった *コ チャンス 成均館大 大学院 英文科卒1965年「詩文学」登壇。 英語詩を米国文芸誌に発表。詩集『元暁を尋ねて』など。英訳『韓国 99人選』で韓国翻訳文学賞受賞。パキスタン大使歴任。 SFー露玉の化石 朴堤千 高貞愛訳 化石には 色んなものが入っている 恐竜の足跡が刻まれた 岩の化石 トカゲが嵌まり込んだ 琥珀の化石 5千年の昔 アルプス男が横たわる氷の化石 その中でもわたしは 露玉の化石を ご紹介いたしたく思う カワズが鳴く池があって その池に浮かぶ ハスの葉に 今しも生じた露の玉 陽も月もその中に 入れておいた わたしの恋人の瞳に 生きている 露玉の化石を お見せいたしたい *パクチェチョン 1945年ソウル生まれ。東国大国文科卒。『現代文学』 登壇。『朴堤千詩全集』『荘子詩』『月は千の江に』『木の舎利』など。 『SF-交感』。アメリカ・ベトナム・スペインで翻訳詩選集刊行。 因縁 高貞愛 黄色いバナナ 黄色い袋に カゲロウが住んでいるのを見た 飛び交う羽音 聞こえそうで聞こえない 薄茶色の胴体 見えそうで見えない 補聴器が無ければ聞こえない 虫眼鏡が無ければ見えないほどの生が バナナ袋の中が世界であるらしく 群れながら 思う存分食ったり飲んだり いつの間にか 一日が音も無く傾くのに 右往左往 与えられた生を享受している お前の小さな目としては 前を遮られ 見えないはずの 巨大なわたしも お前と同じ 億劫歳月の中では カゲロウくらいも 1ミクロンにも及ばないちりあくた 今 お前とわたしの出会いは 黄金より 何より 最も貴い 刹那の因縁 まさにそう *コヂョンエ 1934年生まれ。日本の大阪に居住したことがある。 木浦女高卒業。「詩と意識」登壇。詩集『鉛筆削り』『健やかな家』 季刊『文学と創作』に韓国詩の日訳連載。2007年6月に朴堤千・選 高貞愛・訳で『日訳・105韓国詩人選』を出版。1926年から2007年 までの詩人105人の詩を訳出した労作。 金思寅 風景の深み 風が吹いて 低い草がぶるぶる震えるのに 目を留めるものがどこにもない その貧しいものの生の一瞬 心寂しい孤独な震えにして 宇宙の夕べのひとときがようやく暮れてゆく その震えのこちらとあちらの間 その瞬間の始めと終わりの間には 無限に老いた昔の静寂が さもなければ まだ来ないある時間の内の幼い静寂が 見えるか見えないかくらい浅く埋めてあるようで そのけだるい静寂の春の光の中に私は 百年か二百年ほど でなければ 三ヶ月 十日ほどもぐっすり眠りたいものだ そうすれば三ヶ月であれ 十日であれ 名前くらいの私の無限のそばに 蝶やハチやたいして美しくなく捨てられるものが 無邪気によぎって行くこともあるようだが その時は私は夢のように その時は生命の触角や羽や幼い足に 載せられて来たなじみのにおいが ある生が ひとしお深くなった君の目の輝きを見分けるようになるだろう (佐川亜紀訳) 遅い愛 ぼくの空の一方に長く留まる 鳥一羽 飛び立つ 力なく曲がって集まった 赤い足の指 白い額 世を去るものが残して行った 端正な文字のようだ 空ががらんとあいたね かかとがつぶれた靴でも引きずって ぼくはまたいたずらに この家 あの家 しきりにのぞきこみながら年老いてゆくんだろうな (訳・佐川亜紀) ※キム・サイン 1955年忠北生まれ。ソウル大国文科、高麗大大学院 で学ぶ。1982年同人誌「詩と経済」の創刊同人として参加。 詩集『夜に書く手紙』『ひそかに好きな』第6回申ドンヨプ創作基金、 第50回現代文学賞受賞。現在、東德女大文芸創作科、教授。 黄炳承 心でだけ グッバイ 車窓にもたれ美しい姿で寝入ったとき ぼくはおまえがそのまま息 が 絶え 美しさを完成することを願った 長い髪 ワンピース 緑色タイツ の少女よ 汗にぬれた下着が熱気をふき出す夜 ぼく たちは少し近く なって 胸の中の四足けものは狂ったように暴れて いる おまえをどう してやろうか!こんにちは!おまえを自由に してやりたいけれど ワン 声が突然あがるみたいだ おい、紳士さん、もう少しおとなしく行動しなよ!ところでちょっと、こ の 狂った女がむしろ俺の喉をかみちぎるつもりらしい だるいな いやなこの気分 車窓にもたれ おまえのほんのり赤い両頬が悲しげに震えるとき ぼく はおまえがその悲しみの中で心臓を握りしめたまま ばったり倒れ る のを切に願った どうか ぼくのそでを放してくれ しめった靴下 が滑 る夜 胸の中にはうなる歯が寒さに震えている 長い髪 ワンピース 緑のタイツの少女よ おまえをこ んなにしておいてもいいのか! このきたないあま このきたないあま 股の中に臭い毛をいっぱ い かかえていながら!へどが出る いやなこの気分 ごめん ごめんしたいけど獰猛な足の爪が おまえの顔をだめ に してしまうようで寄りたいけど おまえを一口でかみ殺すようで 恐ろしい おまえは柔らかい手の温もり 優しい声 すべてぼくにくれたけど ぼ くはおまえにあげるものが何もないし おまえをおとなしく放してやるの もいやだ めちゃくちゃな髪の毛が火のように燃え上がる夜 おまえを このまま放してもいいのか!長い髪 ワンピース 緑色タイツの 少女よ 心でだけ 心でだけ グッバイ *ファン・ビョンスンは、1970年ソウル生まれ。ソウル芸大文芸創作科 卒業。2003年に「パラ21」詩人文学賞に当選し登壇。2005年詩集 『女装男シコク』を出版し、<未来派>を代表する詩人として注目さ れる。第一詩集の題名「シコク」は日本の四国のこと。このことからも 分るように、意味よりも言葉の自由な組み合わせに主眼を置いてい る。アルファベットがそのまま入ったり、意味ではなく音をハングルで 表している。権威主義を否定し、欲望を表面化させるのは、70年代 頃の日本の詩人、鈴木志郎康、ねじめ正一、正津勉の作品と似てい る。高度経済成長期に欲望の開放が見られるのは、中国とも共通し ている。<未来派>は、詩人・権赫雄が名づけ、解体詩をさらに過激 にしたような詩人たちのこと。殺人や屍姦など異常にグロテスクな場 面を取り上げることが多い。活躍中の翻訳家・詩人・韓成禮は「実践 文学」2007年春号の論文「注目されない日本現代詩から見た韓国 詩の現状」で、<未来派>のような作品は詩の衰退を招かないか心 配している。確かに、伝統的な詩の文化的権威を自ら壊すとオピニ オンリーダーとしての地位を失う。しかし、民主主義が進むとみんな ふつうの人になり、生活も向上し、消費社会で欲望を隠すのは非現 実的に感じてしまう。時代に対応した作品が生まれる必然性もある。 「心でだけ グッバイ」は三大詩賞の「未堂詩文学賞」の候補にも のぼり、詩壇も一定程度認めているようだ。ただ、以前紹介した 1970年生まれの仏教的詩風の文泰俊のほうが詩壇のもっと大 きい期待を担っているので、韓国と日本の詩の違いはまだ続くと 思う。情報化社会で同じ影響を受けることはあるだろうが。 高銀(2) 『高銀詩選集 いま、君に詩が来たのか』 休戦線 金應教・佐川亜紀訳 過去五十五年間に感謝する 韓半島の休戦線六百里 その非武装地帯 昔の持ち主たち 寝て起きては地団駄踏んでやきもきした土地 誰も管理しない草 草虫たち 木 木々 動物たち 小さい生き物 細菌たち 君たちのためにどうか永遠なれ 休戦線 こちら側もあちら側も広げて行きなさい 休戦線 東北アジアの亡霊のような希望よ ここに来い 広げて行きなさい 広げて行きなさい 『南と北』(2000年) ある喜び 金應教・佐川亜紀訳 今 私が思っていることは 世界のどこかで 誰かが思ったこと 泣かないで 今 私が思っていることは 世界のどこかで 誰かが思っていること 泣かないで 今 私が思っていることは 世界のどこかで 誰かがちょうど思おうとすること 泣かないで どんなにうれしいことか この世界で この世界のどこかで 私は無数の私によって作り上げられた どんなにうれしいことか 私は無数の誰かと誰かによって作り上げられた 泣かないで 『まだ 行かない道』(1993年) *3月21日の「21世紀の知識人―フランス、東アジア、そして世界―」のシンポジウムは 今世紀の知識人の役割を問うものでした。高銀は、「私の片方のポケットには、知識人の 役割は消滅したという思いが入っている」と時代に対する鋭い見解を示しました。アジア、 特に、西欧や日本の被害を受けた地域は、歴史意識は危機意識としてうまれ、知識人・ 詩人・作家は独立運動家や民主革命家にならざるえませんでした。しかし、その後の急 速な近代化と世界化、さらに高度情報化社会に突入するにおよんで、今までの知識文化 は劣勢に追いやられています。グローバル化した経済が想像を超えた競争を強いていま す。しかし、それだからこそ、「地球上で最も誇るべき知恵と思索の伝統を持った東アジア の知性の社会が、人文の危機を迎えている今日を、いかに生きていくかという文化血縁 的な悩みが、時代の感性を伴うとき、東アジア知識人の普遍性は実現されるであろう」 と東アジアの知性の復活を呼びかけています。 崔正礼(2) 彼女の唇は温かくて あなたのは冷たいのよ (2007年現代文学賞受賞作品)佐川亜紀訳 だから どうぞ私を放して あなたをもうこれ以上愛せないから だから どうぞ 低脂肪牛乳、サバ、クリネックス、ゴム手袋を積んで トランクをバタンと閉めたとき・・・・・・・・・・・ この上なくやわらかい声で プリーズ リリース ミー が流れてくるのよ 向かい側に止まっている車の中で犬が一匹車窓を引っかきながらほえている この国はダリアがお盆くらいで 桜もこぶしくらいで 散りもしないで 一ヶ月も二ヶ月も咲き続けるのだと ウニョンが電話で話したとき いきなり隣の車が近づいて私の車にバンとぶつけるじゃない 運転手が飛び出して おばさん 俺がこう曲がっているのに そこで飛び出してどうする それでも歌は止むことはない ショッピングカートをもどしに行った人、コインを取りに行って帰ってこない ウニョンは電話を切らないのよ 私が曲がるのに おじさんが急ハンドルを切ったじゃない 聞きもせず男はすばやく白いスプレーを取り出し 地面にスッスッスッと線を引く 10分たって20分がたってもショッピングセンターを抜け出す車 スピーカーではまたあの歌 こんな人生は無駄遣いよね これは罪悪よね 私を放して お願い どうぞまた愛することができるように 私を放して そのナムルに そのご飯 お盆ほどのダリアに こぶしほどの桜 その歌 その節 この前買ったものをまた買って積んだ 隣の車が私の車にぶつかったと騒いでも ウニョンは電話を切らないのよ すすり泣きながら ここはブルーベリーがただで公園に行けば バケツいっぱいに採ることができる ブルーベリーヒルに遊びに行って ブルーベリーケーキを作ろうよ プリーズ リリース ミー あなたをもうこれ以上愛せないから 彼女の唇は温かく あなたのは冷たいのよ だから どうぞ 私を放して また愛することができるように 放してちょうだいってことよ *チェジョンレ1955年京畿道生まれ。高麗大国文科、同大大学院卒業。 1990年「現代詩学」で登壇。詩集『私の耳の中の長竹やぶ』 『日光の中の虎』『赤い畑』『レバノンの感情』 キム・ダルジン賞、イス文学賞受賞。 *韓国でも急速に進む消費社会。無駄遣いを無制限に勧める甘い宣伝。 そんな物質文明で失われる愛情をもう一度回復したいというテーマは 最近よく見られます。日常感覚が日本とだんだん似てきましたね。 千良姫 心の月 権宅明・佐川亜紀訳 いばらの垣根一面に月光がかかっています 心をまた思い尽くして日が暮れます ヒメムカシヨモギの花まで咲き 片方の野原が欠けそうな十五夜です 月光があまりにも明るく 私はもう暗闇を地に置きました 円満に生きることができなかった人たちが 月に向かってしきりにおじぎをします 胸いっぱいの願いをこめて見上げます 何かに傷つけられたことのある人は分かるはずです 月もときに光が折れることを 一月も半分に折れたら十五であるように 折れるのは膝ではなく心です 心をかかげて月光の下に立ちました 吸った息の中に入ってきた月が 心の中に昇ります 月光がいばらの垣根を越えるころ 心はもう満月です *韓国詩誌「詩で開く世」の共訳試み第二回の作品です。 何かに挫折した人たちが月に祈る敬虔な様子が清らか に伝わってきます。 好日 権宅明・佐川亜紀訳 小さい花は ほかの花が大きいからと いつ咲き争うでしょう 鳥たちは 空に道があるからと いつ足跡を残すでしょう 風は 行くあてがないからと いつ止まるでしょう 川は 忙しいからと いつさかのぼるでしょう 稲穂は 実ったと いつ頭を下げないでしょう 子供たちが日の暮れるのも知らず 独楽をまわしています 日差しが子供たちの肩にとまっています とってもとっても良い日です *温かい雰囲気で生きているものを肯定し、人生に、 神に感謝しているような優しい詩ですね。 「日々是好日」に近い内容なので「好日」としてみました。 呉世栄(2) ゴビ砂漠・3 権宅明・佐川亜紀訳 すすり泣くように あざ笑うように 恐ろしいほど沈黙している空間に か細く響く あの口笛の音 行けども行けども地平線は果てしなく遠いばかり 太陽が泣くのか 昼の月が笑うのか 砂丘にラクダを止めて ふと 振り返って見る ニグラミノ草のかげで白く朽ちる白骨 中がからの脛骨ひとつ 風におどけて泣いている 寂莫たる宇宙に投げられた 笛ひとつ *「寂寞たる宇宙」とこの世界の本質をとらえ、白骨が笛になり、 それは孤独な詩人の比喩とも考えられます。 砂漠は文明の果てを想像させ、深い思考の現代詩と思いました。 経歴は以前の項をごらんください。 韓国詩にみる宗教的テーマ 豊かで長い精神文化の流れ (朝日新聞2007・1・9) 佐川亜紀 韓国で年間の最優秀詩作品に贈られる素月詩文学賞に一九七〇年生まれの文泰俊 が選ばれた。九四年に「文芸中央」新人文学賞を受けて以来、〇四年には東西文学 賞と雲雀文学賞、〇五年には唯心作品賞と未堂文学賞と名だたる賞を総なめにし、 今後の韓国詩に大きな役割を果たす詩人と期待されている。第一詩集『ざわめく裏 庭』と第二詩集『素足』がある。 職業が「仏教放送」ラジオ部プロデュサーで、詩の 根本に仏教的な考え方がある。今回の受賞作「その頃には」にも、西欧的な時間の 観念や個人観とは異なる世界がうかがえる。「空にとんぼが消えた/素手だ/一日 をなでまわした/両目をこっそりまた開けてみた/素手だなあ/かたくなな石碑の 横を通ってみた/もろい私は金剛という言葉が分からない/その時が来るはずだ とんぼが空から消えるように/その頃には私もここでするりと解き放たれるはずだ から」とんぼが空に消えるように人間も死と生をくりかえす宇宙の一部だと彼は考え る。自分はもろい存在であり、ある日この世との結び目が解かれて、永遠の源に帰 って行くと。 「素手」という言葉は、韓国の禅僧・法頂の教え「素手で来て素手で帰る」 を思い起こさせる。人間は何も持たずに生まれ、何も持たずに死ぬという悟りである。 法頂のエッセー集『無所有』(金順姫訳、東方出版)はロングセラーを続け、テレビドラ マ「宮廷女官 チャングムの誓い」の主演女優イ・ヨンエもエッセー集で愛読書だと 紹介していた。 韓国は儒教の国だといわれるが、仏教も早くから公的宗教であり、 近現代詩人には韓龍雲や高銀などの僧侶出身者がいる。高銀には大冊の小説『華 厳経』(三枝壽勝訳、御茶の水書房)もある。 また、ベストセラーとなったリュ・シファ の詩集『君がそばにいても 僕は君が恋しい』(蓮池薫訳、綜合社・集英社)の邦訳 が、昨年十月に刊行された。やわらかい感性で生と愛をとらえ、精神的憧れもすが すがしい。彼のユーモアたっぷりのインド旅行記『地球星の旅人』(米津篤八訳、NH K出版)も人気を集める。 詩人の高炯烈は、原爆をテーマにした七九〇〇行を超す 長編詩『リトルボーイ』(韓成禮訳、コールサック社)を上梓し、昨年八月には広島で出 版記念会が催された。その時の講演で、中国の白雲という僧の話を通して人間の傲 慢への戒めを語っていた。 韓国詩は日本の詩より宗教的主題が多く、昨年十月に刊 行された代表的な女性詩人・金南祚の詩選集『神のランプ』(高貞愛・本多寿訳、花神 社)のように、キリスト教詩も盛んだ。精神文化の豊かで長い流れを感じさせる。 金恵順 2006年未堂文学賞受賞作品 砂の女 佐川亜紀訳 砂の中から女を引き上げた 女は髪の毛一本傷んだところがなく清らかだった 女は恋人が去った後眠りも食べもしなかったと伝えられる 女は目を閉じていたけれども 息をしなかったけれども 死んではいなかった 人々が来て女を連れて行った 服を脱がせ塩水につけ股を開き 髪を切り胸を開いたそうだ 女の恋人が戦場で死に 国さえ遠く遠く離れてしまったというのに 女は命を飲み込んだまま この世に自分の息を解き放つことはなかった 体の中に刀をいくど刺し抜かれても閉じた目は開かなかった 人々は女をまた繕いガラス管の中に横たえた 待つ恋人は来ず四方からたくさんの指が集まって来た 砂の中に隠れた女を引き上げ 紙の上に置いた両手を毎日 じっと見下ろした ラクダに乗ってここを去り逃亡したい 夢ごとに女が追ってきて 閉じた目をぱっと見開いた 女のまぶたの中が砂漠の夜空より深く広かった *金ヘスン 1955年生まれ。慶北生まれ。1979年「文学と知性」で登壇。 詩集『また違う星で』『父が立てたかかし』『ある星の地獄』『私たちの陰画』 『私のウパニシャド、ソウル』『哀れな愛の機械』『カレンダー工場の工場長 見てください』『一枚の赤い鏡』。金スヨン賞。現代詩作品賞。素月詩文学 賞。<詩は、もしかすると道を束ねてできたわたしの身体を、ゆっくりほど いて、またあなたに道を作って上げる。そのような言葉の道であるかも知 れない。>(『日・韓戦後世代100人詩選集 青い憧れ』より) 朴柱澤 建物 権宅明・佐川亜紀訳 あの道いっぱいにそびえるものたち 冬のすっぱい土を踏んで生の中心に満ち立ち上がるものたち 北部幹線道路で見た、川辺に向かって立っていた たくさんの建物が自らの淋しさに耐えられなくて互いの肩に 寄りかかりながら、互いの屈辱を見逃してやり がっしりと立っている建物、空に向かって 開かれた窓 そして開心寺や浮石寺のどこかに 数千年まっすぐに立っているたくさんの塔 そのあらゆるものたちの忍耐が傷として立ち上がる夜 川辺の明かりが自分のおなかを川に擦りつけ 吹雪の中に自分の顔を埋めては明け方の 冷たい空気の中へ消え去ったら 夜に耐えた建物は生の中心に満ちわき上がる悲しみと憐みみたいなもの 残雪のように真っ黒な煤煙にこびりつく 凍りつく、その場所の道の上で 取り戻した息をゆっくり吐き出す あれほどどっしり自分の場所に立っていた日のように あれほどまっすぐな夜が崩れるように ためらいもなく真昼の遊覧船が 川を突っ切りながら 自分の動作の誇らしさに汽笛を鳴らす ※朴柱澤については、このコーナーの『詩と思想』7月号でご紹介 しました。権宅明さんとの共訳は、韓国の詩誌『詩で開く世』(おも しろい誌名)の試み。誌上で韓国詩を他の言語にネイテイブと韓 国人両方が訳し、お互いが工夫点や疑問点を出し合ってベストな 訳を目指す取り組みです。ドイツ語訳や英語訳などもあるそうです 朝鮮語と日本語は文法は似ているし、漢字も中に入っているし、と 一見、翻訳が簡単に思えますが、文法的に正しく直訳したら、日本 の読者にはさっぱり分からないということもしばしばあります。 それは、一つの語が持つ意味が多様であり、社会・文化環境や 歴史的経緯が異なるため感性にも特有のものがあるからでしょう。 やはり互いにネイテイブのアドバイスが必要とは、英語詩を多数訳 した英米文学者・故・木島始さんの教えでした。 リュ・シファ 君がそばにいても 僕は君が恋しい 蓮池薫訳 水のなかには 水ばかりがあるのではない 空には あの空ばかりがあるのではない そして僕のなかには 僕ばかりがいるのではない 僕のなかにいる君よ 僕のなかで僕を揺さぶる君よ 水のように 空のように 僕の深いところを流れて 秘かな僕の夢と出会う人よ 君がそばにいても 僕は君が恋しい ※リュ・シファ 1959年生まれ。80年に韓国日報新春文芸詩部門 を受賞。詩誌「詩運動」を創刊。83年から詩作を中断し翻訳活動 に入る。88年以後はインドやアメリカを放浪。日本でもインド旅行記 『地球星の旅人』(日本放送協会2004年米津篤八訳)が出版された。 91年に詩壇に復帰し、詩集『君がそばにいても 僕は君が恋しい』 が100万部を超えるベストセラーとなる。 (日本での発売は集英社。発行は綜合社。1400円+税) 訳者の蓮池薫さんは、拉致被害者。現在、翻訳家としても活動し、訳書に 『弧将』(新潮社)、『走れ、ヒョンジュン』(ランダムハウス講談社)、 『ハル哲学する犬』(ポプラ社)等がある。 あとがきから、韓国詩に真摯に向かい合っていることが感じられ、 さわやかな分かりやすい訳だと思いました。 朴賞淳 綿畑を通って少年は行き 佐川亜紀訳 綿畑があった―― ひとりいた 綿畑があった―― ぼくがいた ひとりいた ―― ひざが破れた白い少年がそこにいた 綿畑を通って少年は行き ひざが破れた白い少年は行き きみは今でも綿畑にいるんだね きみは今でも残っているんだね 綿畑があった ―― 二人がいた 綿畑があった ―― ぼくがいた ぼくたちがいた ―― 頭に綿毛を付けた白い少年がいた 白い花々が呼ぶのだろうか、白い月が呼ぶのだろうか 綿畑を通って少年は行き 君は今でも綿畑にいるんだね 君は今でも残っているんだね 綿畑があった ―― 三人がいた 綿畑があった ―― ぼくがいた ぼくと一緒にいた――ぼくの指を埋めて背を向けた白い少年たちがいた そこにいた。砂漠にも雨が降るだろうか。砂漠にも雨は降るだろう。 綿毛のように芽吹くだろうか。ぼくの指も育って綿になるだろうか 白い花々は呼ぶだろうか 綿畑は呼ぶだろうか 白い月は呼ぶだろうか、もう一度呼ぶだろうか 綿畑があった―― 綿畑だけがあった 綿畑があった ―― 少年たちだけがいた そこにいた ―― 綿畑を通って少年は行き ぼくが引いていったものたち、ぼくが持っていったものたち ぼくが二つの手にしっかり握りしめていったものたち そこにあった、綿畑が呼ぶのだろうか、綿毛が呼ぶのだろうか きみの指を埋めて背を向けた白い少年は行き きみは今でも残っているんだね 綿畑にいるんだね 死んだ馬の夏休み 佐川亜紀訳 死んだ馬が夏休みを発つ まだ生きている馬たちの村を通って 走る 死んだ馬は ずっと前に消えた私の未来 生きている馬たちは私の未来の時間が死んだあと 湧き出たとんでもない未来 今やっと死んだ馬は夏休みを発つ 海に向かって とんでもない未来を通って 走る 走る 死んでも走る 死ぬほど走って また 走って 海に行く 海は すでにずっと前にさし迫った私の孤独 砂粒のような孤独が波に吹き払われ 打ち返しては打ち寄せる 夏は まだ生きている私の死 しっぽに死をつけて死んだ私の馬が 夏休みを発つ 死んだ馬 死んでしまった馬 死んだ馬 また生き返っても 永遠に きっと死んでしまう私の馬 *パク サンスン 1961年ソウル生まれ。ソウル大学校美術大学絵画科卒業。 1991年『作家世界』で詩壇デビュー。1993年『6は木、7はイルカ』、1996年 『マラナ、ポルノ漫画のヒロイン』。1996年現代詩同人賞受賞。2005年 『Love Adagio』。2006年現代文学賞受賞。 朴賞淳の作品はポストモダン的で、通常の意味をはがした文字の組み合わせ により、新しい世界を表出しています。例えば、「死んだ馬が夏休みを発つ」は 旧来の比ゆではなく、意識的に文法を崩すことにより、さらに意識の解体を進 めています。旧来の比ゆよりもっとイメージの広がりをうながし、読者の読解の 自由が増すわけです。と言っても、逆に読解が難しいというのが日本のポスト モダン詩の現状でもあります。読解というより、想像の楽しさを味わうのがいい でしょう。昨今、韓国詩は急速にポストモダニズムに近づき、朴賞淳はその洗 練性の高さでも代表的詩人と言えます。 *なお、もっと詳しくは韓成禮さんが日本の『詩学』10月号で多くの訳詩と批評を 紹介しています。 文泰俊 東京新聞2006・8月4日 若い詩人の優しい抒情詩・佐川亜紀 一九九四年に出版した実売六十万部に上る第一詩集 『三十、宴は 終わった』で一躍韓国のスター詩人となっ た崔泳美(チェ・ヨンミ)が 四月五日に来日した。昨年九月には日本語版 (韓成禮訳)が書肆青 樹社から出版され、さらに十一月 に七年ぶりの第三詩集『豚たちに』 を上梓した。上の世 代や男性社会を痛烈に風刺し、偽善やごまかし をあばく知性は鋭さを増している。来日までに一万部売れたそう だ。 崔泳美ら何人かの有力女性詩人が社会に批判的に立ち 向かってい るのに対し、若い男性詩人には柔らかい抒情 性が目立ってきた。 現前の社会より永遠性や芸術の純粋性を志 向している。抒情詩は 韓国詩の伝統の一つで、急に起こ ったことではないが、かつて社会 政治性が前面に出た時 代から考えれば、格段の違いがある。最も 評価されている若手男性詩人は一九七〇年生まれ の文泰俊(ムン・ テジュン)である。一九九四年に「文芸中央」新人文学賞に当選して 以来、二〇〇四年東西(トンソ)文学賞、二〇〇五年に は有名な未 堂(ミダン)文学賞、二〇〇六年には抒情詩の代表的な素月(ソウオ ル)詩文学賞とたて続けに大きな賞を受け、韓国詩の将来に重要な 役割を果たす詩人として期待されている。未堂文学賞受賞作「誰か が泣いて行く」は「一晩中ちゃら んちゃらんと音がする/雪が止んだ //私は一人寂しく /思いはしばらく止まる//蔦に/小鳥/胸が 赤い鳥/ 来て鳴く/来て鳴いて行く/(略)あのように泣いて/ 去っ た人がいた//胸の中に/赤く/滲んで染みつき/ 今は/誰も引 き出すことができない」(韓成禮訳)と表 され、「誰か」は人間の悲哀を 泣いてくれる大きな存在 とも考えられる。日本で知られている民謡「ア リラン」 も去り行くものへの恨(ハン)と悲しみをこめた歌だ。 文泰俊の 作品も喪失の後に残った余韻を書くことで消え 去ったものや永遠性へ の想像力を呼び起こしている。文 泰俊は仏教放送ラジオプロデューサ ーで、仏様をテーマ にした詩もある。 もう一つの最近の傾向は、子供 時代への追憶である。 二〇〇六年に現代文学賞を受賞した朴賞淳 (パク・サンスン)の「綿畑を通って少年は行き」は、綿畑にいたズボ ンのひざが破れた 白い少年の自分を思い出し、現在もそのまま少 年は綿畑 に残っていると想像する。大人の中にも子供時代の無垢 な 部分があり、それこそ純粋詩だと言っているようだ。 文泰俊の素月詩 文学賞受賞作「その頃には」もとんぼを 追った澄んだ夏の日を回想し ている。 世界的に対立が厳しくなっているが、悲しみや無垢な部分を 忘れまいとする優しい詩が韓国で書かれている。 その頃には (佐川亜紀訳) 2007年素月詩文学賞作品 ムン・テジュン 空にとんぼが消えた 素手だ 一日をなでまわした 両目をこっそりまた開いてみた 素手だなあ かたくなな碑石の横を通ってみた もろい私は金剛ということばが分からない その頃が来るはずだ とんぼが空から消えるように その頃にはわたしもここですっかり解き放たれるはずだから どこに行っただろうか 夏の雷について行っただろうか 夏の雷について行っただろうか ぱらぱら ぱらぱら草の葉に飛び降りた彼らは *私はこの詩に仏教的無我の境地を感じました。 法頂というお坊さんの『無所有』という本が韓国で300万部とも 言われるベストセラーになりました。その無所有が ここでの「素手」の意味に近いと思います。 金宣佑(2) 朝日新聞2006・7・5夕刊 〈海外文化・韓国〉 活躍めざましい女性詩人・佐川亜紀 韓国では、さまざまな分野で女性の進出が 目覚しく、01年には 中央官庁に女性部が設 置された。詩の世界でも有能な書き手 が次々 に登場している。 本紙でベストセラー詩人・崔泳美が紹 介さ れたが、さらに若い1970年生まれの金宣 佑が最近注目 されている。00年に第1詩集 『私の舌が口の中に閉じこもってい るのを拒 否したら』を出版し、イラク戦争を背景にし た「咲け! 石油」で04年度現代文学賞を受 賞。現代文学賞といえば、韓国 詩を代表する 中堅詩人におもに与えられてきた。それが、 30代 前半のいわば新人に授けられたわけで、 詩壇の期待と才能評価 の高さを示している。さらに、やはり有名な素月詩文学賞の 06年 度優秀賞作品に「石には耳がたくさんあ って」が選ばれた。 第1詩集の題名から分かるようにフェミニ ズムが主題の一つで、 「私の舌は、彼の口の 中に、卑屈で素直に閉じこもって」(韓成 禮 訳)いるよう強いる男性文化・儒教文化を拒 み、女性の舌で 語ろうとする。現 在は、映画「猟奇的な彼女」やテレビドラマ 「チ ャングムの誓い」を見れば、かつての物 言わず耐える女性像が 一掃され、いきいきと 自分の感情と知性を表す女性の姿に新し い時 代を感じるが、旧来の束縛も根強くあり、そ れに対する問 題意識は日本より強く、率直。 金宣佑の作品は、歴史上の女性 を織り込んだ 「水の中の女たち」や、韓国でも進む少子化 を文 明批評的に風刺した「無精子時代」など 視野の広さ、鋭い知性、 情念がこもるグロテ スクな幻想も魅力である。「石には耳がたく さんあって」は石の中に多くの耳を感じ、舌 でなめて石を味わう というもの。言論を抑圧 されながらも全身で時代に耳をそばだて てき た人々の歴史を思い起こさせる。呪術や批判精神 を源とする 怪奇な想像力は朝鮮の伝統文化で ある。 一方、昨年9月に呉英珍編・訳でソウ ルの民文社から『最新 日 本女性名詩選』が 上梓され、高良留美子、新川和江、石川逸子、 石垣りん、森崎和江、堀場清子、白石かずこ ら28人が紹介された。 今年亡くなった茨木 のり子の作品「わたしが一番きれいだったと き」など6編が収録されている。巻頭は、中野重治の妹 の中野鈴子 の詩で、巻末解説「日本女性詩の歴史」に至る豊富な知識には驚嘆 するば かり。 こうした動きに刺激されて、日本でも、朝鮮の 女性詩についての 理解が深まることが望まれる。 無精子時代 金宣佑(韓成禮訳) 精子の数が減っている という、クスクス、 実験室のビーカーと 胎児たちの頭が解放されるだろう 四〇年の間平均40%の精子が減った という 最近10年間は年2.6%の減少率 クスッ、私は笑う 2.6%ほど 売春婦たちの家計簿が豊かになるだろう ただ、原罪ではないことに感謝せよ 化学薬品が体の中に蓄積して起きた副作用だ というクスッ、君だけ飲んだのかい? とんでもない平和な終末が来るかも知れない 五大洋六大陸の年寄りどもが集まり 隣り組み会でもするように最後の神前への供え物の息を止めるかも、 受精卵の雲が早く下降してくれるように 幼い人間の泣き声をたった一度でも聞けるように! 肺臓と子宮を持った動物の中で 自分たち同士殺戮し、搾取するのはただ一種類だけだから 甘んじて受けよ 天の門が開き 腐ったヘソの緒が降り下っ腹を刺し抜くだろう 無精子の時代 無精卵の霊魂たちが 冬のキビの茎を染め 次の次の次の年には 赤いキビの花だけ元気に咲くだろう ※韓国の出生率は、日本以上に下がり、2005年はなんと 1.08(日本は1.25)。非婚、シングル化も急速に進んでいま す。大家族を重んじる伝統文化も変わってきました。 社会的に小気味よく風刺しているのが金宣佑の詩の おもしろさですね。 「詩と思想」2006・7月号 雑草取り 金鍾海(権宅明訳) 草取り鎌で土を掘りながら 雑草を取る 雑草はぼくの手により間違いなく抜かれ 抜かれた雑草は外に消え去る 玉石を分けるぼくの手も震える 天はこの雑草を育てられたのに 今日はぼくが抜き出している 畑の半分くらい草取りをしながら ふとぼくは悟った この畑で雑草として抜き出される名簿の中に ああ、いつのまにかぼくの名前も入っているんだ! *金鍾海(キム・ジョンヘ) 1941年釜山生まれ。1963年 「自由文学」誌の作品懸賞募集に詩が当選、京郷新聞 主催の新春文芸作品懸賞募集に詩が当選して詩壇デ ビュー。現代文学賞、韓国文学作家賞、韓国詩人協 会賞、空超文学賞等受賞。詩集に、『航海日誌』『風の吹 く日は地下鉄に乗って』『流れ星』『草』等がある。 韓国詩人協会会長歴任。現在、図書出版「文学世界 社」代表、季刊詩の専門誌「詩人世界」発行人。 ハンドバッグ 慎達子(権宅明訳) 私のハンドバッグは 私の隠れた胸の中の隠れた部屋のようです 他人はよく開けられなくて 開けられないから人が少しは知りたがる私のハンドバッグは 時々私も知りたくて手を入れてごそごそかき回してみたりします 鍵と財布だけつかまえられたら安心ですけど その二つが確かに見えるのに 何かがなくなった感じであちこち心の袋を 手探りして胸がどきんとしたりします 何かが満ち潮のように押し寄せてきては 引き潮のように打ち返していったのか 黄土色の干潟が痛々しく広がっています 今日は捜しても捜しても捜すものがなく 中身を引っくり返してこぼしてしまいましたが 取るに足りない私の品位が みすぼらしい裸身で日差しに露出され 廃墟のような心を素早く拾い入れます 私のハンドバッグの中には 私の心臓の拍動の音が聞こえたりします *慎達子(シン・ダルジャ)慶尚南道生まれ。淑明女子大学 及び同大学院卒業。文学博士。詩集に『長く話し合う間柄』 『矛盾の部屋』『雅歌』『父の光』等十冊があり、散文集に 『白痴恋人』等二十冊がある。大韓民国文学賞、詩と詩学賞、 韓国詩人協会賞等受賞。 木の風 金基澤 (韓成禮訳) 木は固体になった風です。 風がどう生じたのか知りたければ多足類植物の木を見てください。 柱一つに鈴なりについた手足と指を見てください。 一方は堅く釘付けになっており、もう一方は果てしなく 飛んでいく動きを見てください。 空気がじっとしている時でも 木の風は旗のようにだらりと垂れたりはしないのです。 葉は一様に珍島犬のようにぱりっと耳を立て 風の大きさと音と香りと色と味を一つも逃さずに ひったくっています。 木の風は一日中一つの場所に立って踊っているように 見えると言います。 飛んで世の中すべてを歩き回って見ようと 空気になった筋肉で跳躍し、 骨に満たされた水紋で身震いをします。 丸やかな木の風の中に入ると どれほど強い直線も、波紋や渦になってたわんで過ぎ去り どれほどか細い震えも周辺の空気を すべて鳴らしながら去っていきます。 木の風は根から上って来ると言います。 根からほとばしり上がる力のため、 それは噴水や波のような様ですね。 しかし噴水や波のように自分の身を底に流す事はないです。 今も木の風は噴水のある動作、 波のある姿が今ほとばしって 下へ降り注ごうとするまさにその瞬間にあります。 その瞬間の体は はちきれた空気がなくても跳ね上がり、 浮力がなくてもざぶんざぶんとほとばしります。 木の葉一枚一枚は空中に跳ね上がった水玉です。 今は枝に釘付けになっていますが 水玉の性質はそのまま残り 少しもじっとすることができず騒いでいます。 木の風は地に刺さっていても虚空に浮かんでいます。 地の外に身の外に走り出ようとする姿 そのままで浮かんでいます。 日光もそこに触れればすぐ風になります。 刹那の生を生きて行く無数の輝きが葉の波の間で 生じて消え、消えてまた波打つでしょう。 *金基澤(キム・ギテク)略歴 1957年 京畿道安養で生まれる。 中央大学校英文学科卒。慶熙大學校国文学科修士取得。 同大学院博士課程履修中。 1989年 韓国日報新春文芸 詩部門で詩<せむし><日照り>が当選し、文壇デビュー。 1991年 第1詩集『胎児の眠り』(文学と知性社)刊行。 1994年 第2詩集『針穴の中の嵐』(文学と知性社)刊行。 1995年 <金洙暎文学賞>受賞。 1999年第3詩集 『事務員』(創作と批評社)刊行。 2001年 <現代文学賞>受賞。 2004年 <イス(ISU)文学賞>受賞、<未堂文学賞>受賞。 時間の肉体には虫が住む 朴柱澤(韓成禮訳) トラックの行商からイカ十匹を買い 内臓を除いてきれいにした、除いた内臓を廊下のごみ袋に 入れて隅に片付けておいた。明くる日、夏の光が 沈黙する封筒の中に入って行き、血の気のない肉体と混じる間 イカの内臓は臭いで抵抗していた それから梅雨が来て私は屋根の上に忘却を下ろすことができず 近くから聞こえて来る虚しい録音に部屋のドアをかけている時 肉の腐る臭いだけがドアの隙間から染みこんでいた 廊下にはひどい臭いだけがいっぱいだった 私は部屋の中いっぱいに漂って来る臭いを嗅いで臭いにもある分別が あるはずだという思い、もっと正確には汚いゴミをかろうじて出して 捨てねばという思いと争っていた 初めて私は廊下の門を開いた 雨が止み、争った後の不安な平穏が 四方に広がっていた、空気が濡れた肩を乾かしていた 足跡にかびが生えてきていた そしてちょうど鍵で地獄のような門を閉め背を向ける頃 血の気のない臭いが心臓まで食い入った 墓で臭いの根として生まれた数多くのうじたちが 時間の肉体の中に散らばって行った * 朴柱澤(パク・ジュテク)1959年 忠南瑞山生まれ。 慶熙大学国文科、及び同大学院修士・博士卒業。 1986年京郷新聞新春文芸当選。詩集『夢の移動建築』 『放浪はどれほど痛い休息か』『砂漠の星の下で』 『カフカと出会う眠りの歌』。現代詩作品賞、慶熙文学 賞、片雲文学新人評論賞、素月詩文学賞受賞。 高炯烈(2) 長編詩「リトルボーイ」から 韓成禮訳 すべてのものたちがだらりと萎えた 蒸し暑くうっとうしい広島の夜だった。 どこかで小さく硬い鐘の音がした。 この広島の運命と 私たちの運命はどうなるのだろう。 同じ道を行くことになるのではないか。 たとえまっ暗でも李オクチャンは 海が見たかった。 同志たちの顔が浮かび上がった 金ジュホ、ハナ、朴老人、カン・ドス 皆、仮の名を名乗っている同志たちだった。 組織とラインを保護するためだ。 呉鉱山の呉チャンス、燕瓦工場で鉄板に 穴を開ける崔イン、採字工チョコマ、ハナと彼女の娼婦の友達、 海軍施設部測量台の文ジェボク、 関釜連絡船に顔が広い甲板屋の李グァンス、 広島にひかれて来た2千人を超える朝鮮の徴用青年たち。 彼らすべてが山のような人々だった。 李オクチャンは波がしきりにぶつかる防波堤の 水音を聞きながら話のできない海水になった 心情だった。水を打ったように静かな 港湾の中にすこしでも波が立ったらと思った。 (略) *「COAL SACK コールサック 54号」 「リトルボーイ」第3章7より一部分 チョン クッピョル ある跡 どの手が花梨を集めていったのか 私が眺めたのは花梨だけだった ちらっと花梨の葉を見たようでもあり またほんのちらっと花梨の花を見ていたようでもあるが 花梨の葉が芽生える間 花梨の花が咲いている間 そして花梨の実が熟れていく終始 私は花梨だけを見た 眺めれば眺めるほど花梨は私のものだったが ある日一瞬の間に花梨が消えうせた 私の眼差しが花梨のへたを息苦しくさせたのか 私の眼の毒が花梨の肉を傷つけたのか 初めから花梨は無かったのでないのかと疑う間 花梨は消えうせてみぞれが降った ぬれた枝の先へ熱が上った うめき声をあげて花梨が消えうせた 花梨が熟れていった跡に拳一つほどの空が咲いた 花梨が熟れていった跡を見ている 見れば見るほど花梨はやはり私のではあるが 花梨の汁に触れた目のふちがひりひりする 花梨が熟れていった跡で 滑ってゆく縁ある悲しみ この愛の背後 ※チョン クッピョル1964年全南全誕生。 1988年『文学思想』にて登壇。 詩集『白樺わが人生』『白い本』など。 韓国女性小説家
金ミョンニ
羅喜徳
『今日の詩 韓国詩21人集』
崔泳美(3)
| ||||||
メール |
トップ |