| 「もう、いいから」 ぽつりと。かすかに震えた声がこぼれる。
ピンクに染められた前髪がふわりと揺れて、その奥の瞳が真っ直ぐに彼を射抜いた。
「もう、いらない。必要とされてないなら、いらない。全部じゃないなら、いらない」
強気の言葉。けれどその視線はどこか揺れていて、でも。抱きしめようと伸ばされた彼の手をしっかりと拒絶する。
「……ありがとう」
泣き出しそうな顔で、微笑んで。くるりと身体の向きを変えると駆け出した。
「ちょっ、待てよ!」
取り残された彼の顔の、アップ。流れ出すテーマソング――――。
「……はー、やっぱりマリーナ、上手〜」
思わずテレビの前でわたしがそう呟くと、キッチンからグラスを手に戻ってきたマリーナは苦笑した。
「もう、恥ずかしいから見るのやめてって言ったのに」
言いながら、冷たいジュースの入ったグラスを渡してくれる。それを受け取ってわたしは笑った。
「マリーナでも自分が出てるドラマ見るの恥ずかしいんだ」
「うん、こればっかりは慣れないなあ。自分を見てるようないないような、なんかくすぐったい感じがして」
グラスに口をつけながら、わたしの隣りに座るとテーブルの上のリモコンを取り上げた。あっ、と思う間もなく、チャンネルをバラエティ番組に変えてしまう。
「見てたのに」
ソファに背をもたせかけてクッションを抱きこみながら、わたしが上目遣いに言うと。
「もう後は次回予告だけだったからいいでしょ?」
困ったような顔でマリーナは首を傾げた。
月曜九時から現在大人気放映中のドラマ「ラストチャンス」。
失恋して、もう恋なんて絶対にしないと決めていた男女がひょんなことから意気投合し「これで最後の恋にしよう」と約束して付き合い出す、というストーリーで、今ちょうど、最終回に向けて盛り上がりを見せているところだ。
今日放映分ではヒロインを大切に想うあまりどうしても自分を隠してしまう男に、ヒロインが本音を欲しがって困らせ、すれ違ってしまう――というところで終わっていて。
続きがどうなるのか、本当に気になっちゃう。
「次回予告も見たいのー」
「それじゃあ、続き教えてあげようか?」
「……いじわる」
悪戯っぽい瞳で言われて、わたしはジュースを一口飲んで息を吐いた。
そう。このドラマのヒロインを演じているのは他でもないマリーナなのだ。
マリーナは五歳の頃から芸能界入りし、子役を経て現在若手実力派ナンバー1として人気を得ている女優さん。
そしてわたし、パステル・G・キングも。
ついこの間芸能界デビューした、新人女優なのです。
デビュー作(といってもちょい役だったんだけど)で共演したマリーナとは、歳が近いこともあって意気投合して。友達になれたんだ。
わたしみたいな新人がマリーナのような人気女優さんと友達だなんて、ちょっと、いやかなり気が引けるんだけどね。
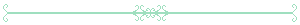
「パステル、次の仕事、入った」
マネージャーのノルがそう言って台本を渡してくれた。
「えっ!?」
受け取って、わたしは突然のことに目を丸くする。
ここはわたしの所属している「フォーチュン・プロダクション」の事務所内。打ち合わせのためにやって来たのだけれど、そこでドラマ出演が急遽決まったことを知らされた。
手にずっしりとくる分厚い台本。表紙には「ホワイト・スノウ」と書かれている。
あまりに綺麗な装丁で、なんだかわたしなんかが読んじゃいけないみたいだ。手に持ったまま表紙を見つめて固まっているわたしに、ノルが優しく笑いかけた。
「クリスマスに放映される、二時間ドラマだ。読んでみろ」
そう言われて、パラパラと台本をめくってみる。
フリーカメラマンの青年が、主人公のようだ。彼と、夢を失った少女が織り成す、クリスマス前の一週間に閉じ込められた切ないラブストーリー。
ざっと流し読みしただけで、ちょっと泣きそうになってしまった。
すごくいいお話。わたしがこれに出演させてもらってもいいのかな、って思ってしまうくらい。
主人公の青年もかっこいいけど、この、ヒロインがすごく良いなあ。微妙な感情の揺れ方がすごく共感できる。マリーナが演じたらはまりなんじゃないかな。うん、すっごく似合いそう。
わたしが演じるのはこのヒロインの親友の女の子、かな。元気がよくっておっちょこちょいで、――。
「気に入ったか?」
ノルがわたしの顔を覗き込むようにして聞いた。ノルの背は高いから、どうしてもそういう体勢になってしまうんだ。
「うん、すごく素敵なお話。ラストシーンのクリスマスツリーの下でのところなんて、映像になったらすごくロマンチックだろうね」
わたしがにっこり笑ってそう言うと、ノルは満足げに頷いて、微笑んだ。
「そう言ってもらえると、良かった。今回のドラマは、パステルにぴったりだと思って」
「……へ?」
その言葉に含まれる「何か」が上手く飲み込めず首をかしげると、ノルは微笑んだままで言ったのだ。
「パステルが演じるのは、このドラマのヒロインだ」
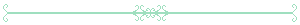
「やったじゃない、パステル」
電話の向こうの声は弾んでいる。そんなに喜んでくれるとなんだかくすぐったいな。
その日の夜。偶然マリーナから掛かってきた電話で、わたしは突然のヒロイン抜擢を報告したのだった。
「ありがとう、マリーナ。でもね、やっぱり不安になっちゃうんだ」
受話器を握ったまま軽く部屋の天井を見上げ、こぼれたのは小さな弱音。
ヒロインに抜擢なんて。不安というよりむしろ、無理なんじゃないかって思ってしまう。
だって、確かに台本を読んだときヒロインに共感できるなあって思ったけれど。でも同時に、実際に演じるにはすごく難しそうな役だとも思ったんだ。
「大丈夫よ」
電話越しでもそんな雰囲気が伝わったんだろうか、ふわりと優しく包み込むような声でマリーナは言った。
「そんなに弱気にならないの。パステルにぴったりだと思われたからこその抜擢なのよ? 誰にだって『初めて』はあるんだもの、完璧にやろうと思わなくったっていいの」
どき、っとした。もう少しで「ヒロインなんて初めてだし無理」って言ってしまいそうだったから。
「……ありがとう。そうだね、始まる前から弱音吐いてちゃだめだよね」
わたしがそう言って笑うと、
「わたし、パステルの演技好きよ?」
マリーナはそう、続けた。
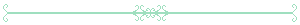
「パステル、急いで!」
普段あまり大声を出さないノルにそう急かされて、わたしは猛スピードで廊下を走る。FUZテレビ局。今日はここで「ホワイト・スノウ」の初めての読み合わせがあるのだ。
車が渋滞に巻き込まれてしまって、時間ギリギリにしか局に入れなかったんだよね。でも共演者の皆さんを待たせるわけにはいかない。
あちこちに、ついこの間まではわたしにとってテレビの中だけの存在だった人たちが歩いている。その間をすり抜けて走っているなんて、なんだか夢みたいで慣れない。
って、そんなことのん気に考えてる場合じゃない!
突き当たりの角を右に曲がる。あとは一直線、と思ったところで。
「うわっ」
どんっ、と衝撃。よろけたところに腕が差し出され、わたしはぽすんとそこに収まる。
「大丈夫か?」
上から降ってきた声に、わたしは慌てて身体を離した。
「す、すみません!」
あ〜、気をつけてたのにな、人にぶつからないように。
彼は笑って、首を振った。
「いや、別に構わないよ。あ、それと」
ちょっと長めの黒い髪に高い背。余計なものを削ぎ落としたような、鋭くて端正な顔立ち。彼はちょっとかがんで、それを拾い上げた。
「台本、落としたよ」
「あっ、すみません」
さっきから「すみません」しか言ってないな、わたし。慌てて受け取ると彼は微笑んだ。
かっこいい人だなあ。俳優さん、かな?
「パステル」
ノルに呼ばれ、振り返る。そうだ、急がなきゃいけないんだ!
「『パステル』? え、ひょっとして――」
「その、本当にありがとうございました!」
彼が何か言ったような気がしたけれど、わたしはぺこりと一つお辞儀をして走り出した。
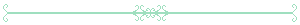
なんとか時間には間に合ったみたいだ、けれど。部屋に入ると共演者の方々が既にスタンバイしていた。
「おはようございます、遅くなって申し訳ありません!」
わたしが頭を下げると、
「ああ、パステル。いえいえ全然遅いなんてことはありませんよ、大丈夫です」
声をかけてくれたのは、演出家のキットンだった。
彼との仕事は二度目になるのかな、わたしのデビュー作を手がけていたのがキットンだったのだ。ちょっと変わった人で、出会って第一声が、
「『さん』付けじゃなくて結構です。そんな他人行儀な呼び方は堅苦しいですからね。一緒に作品を作るのだから、もう家族も同然でしょう?」
それで(演出家の方を呼び捨てというのも気が引けるのだけれど)、「キットン」と呼ばせていただいている。
「パステル、久しぶり」
「やっほー、元気だった?」
そう言ってやって来たのは、クレイとリタ。二人とも共演は二度目だ。
クレイ・S・アンダーソンはわたしより二つ年上の俳優さん。アンダーソン一家といえば芸能界では有名で、お父さんもお母さんも二人いるお兄さんもそしておじいさんも、クレイを含めて全員が何らかの形で活躍していらっしゃるんだ。
そして彼の曾祖父は伝説の「青の俳優」と呼ばれるクレイ・ジュダなんだから。本人はいたって気さくで優しい人なんだけれどね。
「また一緒に仕事できてうれしいよ」
にっこり笑ってクレイは言う。クレイは今回、主人公の青年の親友の役だ。
「わたしも。すごく不安だったから、知ってる人がいるのって心強いし」
わたしが答えると、
「ヒロインだもんね。でも台本読んでてもパステルのイメージにぴったりだと思ったよ。気負わなくって平気だって、わたしたちもいるし」
リタもぽんっとわたしの肩を叩いて笑った。
リタは劇団出身の女優さんで、だからわたしと同じくらいの年なんだけれどわたしよりずっと経験も度胸もあるんだよね。前に共演したときにも随分とお世話になってしまった。そんなリタは今回、わたしの親友の役。
考えてみれば、演出家はキットンだし、クレイもリタもいるし。ひょっとして完全に初対面なのは、わたしの相手役、つまり主人公であるカメラマンの青年を演じる俳優さんだけなんじゃないだろうか?
「今回も色々お世話になると思うけれど、よろしくお願いします」
「いえいえ、こちらこそ」
ぺこぺことお辞儀しあって笑いあっていると、部屋のドアが音を立てて開いた。
「ちーっす」
気だるげな様子で軽く頭を下げて、入ってきたのは赤い髪の男の人だった。
すらっとした身体つき。さらりとした長めの髪を一つにまとめている。
「相変わらず、ギリギリにならないと入らないんだからな」
クレイが苦笑したようにそうこぼした。
「トラップ、遅いじゃないですかまったく」
「遅いっつっても時間には間に合ってるじゃねーか。そんな細かいことでぎゃーぎゃー言うなってキットン」
なおも言い募ろうとするキットンをにやにや笑いながら軽くいなし、そして彼はこっちを向いた。そうだ、彼が。
「クレイ、お前と共演すんのは久しぶりだな。リタとは、去年の映画以来か」
軽く手を挙げて挨拶をして。そして彼はきょろきょろと辺りを見回す。
「で? おれの運命の相手役は、誰なわけ?」
ゴン。わたしは思わず壁に頭をぶつけてしまった。
「トラップ、お前の目の前にいるだろ?」
クレイが軽く額を押さえて言う。リタがわたしの肩をぐいっと抱いた。
「こちらが、今回のヒロイン役のパステルよ」
一瞬、ぽかんとしたようにわたしを見つめ、
「へ? こちら、スタッフさんじゃないの?」
ガン。これは、わたしの頭に降ってきた岩の音。
「……お初に共演させていただきます、新人のパステルです。よろしくお願いします」
ショックから立ち直れず、棒読みになってしまったのは仕方がないと思って欲しい。
そして彼はそんなわたしを見て、あろうことか吹き出したのだ。
「くっくくく、ひゃっひゃっは!」
しかも笑ったままこれがぜんっぜん止まらない。わたしがちょっとだけ顔を引きつらせていると、
「トラップ、いい加減にしろ」
クレイがぱこんっとトラップの頭を叩いた。そしてそのままわたしに向かって紹介する。
「こちらが、今回の主役を演じるトラップだよ」
そうだ。彼が。
「お初に共演させていただきます、俳優やってるトラップです。よろしくお願いします」
まだ笑いが収まらない様子でそう言った彼が、わたしの相手役なのだ。
これがわたしとトラップとの、余りに失礼な出会いだった。
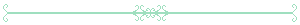
そんなこんなで、読み合わせが始まった。読み合わせというのは台本を持ったまま、動きなしで演技をするもの。
顔合わせも兼ねるこの読みあわせでは、互いに台本を読みながら雰囲気をつかみ、細かい演技の調整や演出などをしていくのだ。途中、演出家の方から注文とかセリフの変更とかが入ったりもする。
さっきまでは和やかだった雰囲気も、一瞬でぴんっと張り詰めたものに変わった。わたしも台本を握りしめる。
「風景写真を撮りたいって言ってたじゃないか。今のままでいいのか?」
クレイの声が普段とは違った響きで聞こえる。冒頭部分。夢を諦めそうになっている主人公を案じて、彼に声をかける親友。
そうだ、ここに今「いる」のはクレイじゃない。主人公を真摯に思いやる、「別の人間」なんだ。そして。
「……いいと思ってんなら、こんなことしてねーよ」
一瞬、どきっとした。
辛そうに歪めた顔、かすかに揺らいだ瞳、諦めたようで、それでも諦めきれない溜息交じりで。
それは本当に何気ないセリフのようなのに、そこに主人公の全てが見えるんだ。
上手い、この人。さっきまでは憎たらしい人だとしか思えなかったけれど。さっきまでの雰囲気とは全然違う。
キットンも、ほう、と息を吐いた。
「いや、さすがですねえ。それでいけるんなら次のセリフ、削りますか。蛇足でしょう」
「ああ、おれもそう思ってよ。おれの演技力、見くびらないでくれる?」
「いやいや、失礼いたしました。ちょっと説明的すぎますからねえ、ここは」
トラップは他にもいくつかキットンと細かく変更点を話し合っていた。
その様子を眺めながら、軽いプレッシャーを感じてしまった。
わたしは、この人と張り合えるだけの演技ができるんだろうか?
考えてみれば、この中で一番の素人はわたしだ。他の皆はもう何年も芸能界にいる人たちだし、演技もわたしよりずっと上手い。
なんだか、自信なくしちゃうな。どうしてわたしなんかがヒロインに抜擢されたんだろう?
「……ル、パステル!」
呼ばれてハッとした。全員がわたしに注目している。
「どうしたんです、パステル。あなたのセリフですよ」
キットンがちょっとだけ苦笑交じりにそう告げた。しまった、考え事してたら!
「す、すみません!」
慌てて台本をめくり出したわたしに、トラップが「おいおい」と呆れたようにわたしを見た。
「何やってんだよ、読み合わせの最中だろ? どうして今がどの場面かもわかってねーんだよ」
冷たい言葉に、びくりと身体が震える。
「トラップ、そういう言い方はないだろ?」
クレイがとりなすようにそう言ってくれたけれど、トラップは険しい目つきでクレイを見返した。
「あのな、甘やかしてちゃダメなんだよ。自分の出番にも気づかないなんて、どう考えても他のこと考えてたに決まってるだろうが。そんなんで演技なんかできるわけねえ」
一言一言が胸に刺さる。本当のことだ、何も言い返せない。
「本当に、すみませんでした。気をつけます」
うつむいたままでやっとそう言うと、トラップは冷たい声のまま、
「ま、それが当然だわな」
短く、そう言った。
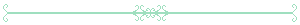
「はい、じゃ、今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした」
「お疲れ様でしたー」
「お疲れー」
長かったような短かったような読み合わせが終わって、それぞれがバラバラに部屋を出て行く。
「パステル、元気だしなよ。トラップは誰にでもああだから」
苦笑交じりに言って、わたしの肩をぽんっと叩いたのはリタだ。
「うん、大丈夫。それに全部本当のことだもん、言われても仕方ないよ」
あれからわたしは、必死でセリフを追って演じていったんだけれど。何かあるたびトラップには怒られ呆れられ。最後には演出家のキットンよりもわたしにダメ出ししていた気がする。はあ。
「パステル、お疲れ」
クレイがそう言って、軽く手を挙げて部屋を出て行く。それまで彼と話していたトラップもこっちを向いて「ああ」と口を開いた。
「おい、パステル、っつったか?」
「はい?」
彼と目が合う。真っ直ぐな目。ああ、と思う。この目をしているときは、彼が真剣に仕事モードに入っているときなんだ。決して妥協を許さない目。
「セリフ追っかけてるだけってのは、演技じゃないぜ」
トラップの淡々とした言葉は、ずしん、と胸に響いた。
「じゃな、お疲れ」
軽く手を挙げて去っていく彼に、思わずわたしは叫んでいた。
「今日は、本当にすみませんでした。でもわたし、頑張りますから! 頑張って精一杯演じますから!!」
目を丸くして振り向いたトラップは、小さく笑った。
「期待してるぜ? 何せ、おれを惚れさせてくれる役なんだからな」
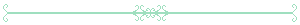
「パステル、今終わったの?」
部屋から出たところで、マリーナと偶然出会った。
「うん、マリーナも撮影だったの?」
「わたしは今日は撮影じゃなくって、顔合わせだったのよ。今終わったところ」
顔合わせ、ってことはマリーナ、また仕事が入ったんだな。さすが人気女優。
「次はどんな仕事なの?」
そうマリーナに尋ねたとき、
「マリーナ、お疲れ様」
そう言う、どこかで聞いた声がした。
「ギア、お疲れ様。初共演、よろしくね」
マリーナがそう答える相手は。
「あっ!」
思わず声を上げてしまった。
「やあ、また会ったね」
そう微笑む男の人は、今日、角を曲がったところでぶつかったあの人だったからだ。
「その節は、どうもすみませんでした」
わたしが頭を下げると、
「いや、そんなに気にしなくてもいいよ」
ちょっと困ったように笑った。
「パステル、だよね? 確か、クリスマスの二時間ドラマでヒロインを演じる」
「え?」
どうして知ってるんだろう? わたしが目を丸くすると、マリーナが教えてくれた。
「あのね、パステル。ギアもほんのちょっとだけ、『ホワイト・スノウ』に出演するのよ」
なんでも、今日あった顔合わせというのはマリーナと彼の共演する映画の顔合わせだったそうで。その映画というのが、いくつかのFUZテレビ系のドラマとリンクしたものになる予定なんだって。
それで「ホワイト・スノウ」もその映画とほんの少しだけリンクすることになっていて、彼がほんのちょい役で出演することになるのだそうだ。いや、「ホワイト・スノウ」ではほんのちょい役扱いでも、その映画――「Calling」というタイトルらしい――では主役級になる役なんだけれどね。
「よろしく。共演できるのを楽しみにしているよ」
にっこりと微笑んで、彼は去っていった。
「ねえ、マリーナ。一つだけ質問してもいい?」
「何、パステル?」
「あの人、誰?」
「え?」
マリーナの顔が、固まった。
「知らないの!? あ、あ〜、でもそっか、最近テレビに出るようになったばっかりだしなあ……」
マリーナがそう言いながら教えてくれたところによると。
彼の名はギア・リンゼイ。もともとは劇団に所属していた舞台俳優だとか。舞台演劇の方面ではかなりの評判で、隠れた天才とも呼ばれていたそうだ。だけど決してテレビには出ようとしなかった。
ところが昨年、たまたま彼が出演した映画が密かなブームになる。単館上映だったその映画は、けれど口コミで広がってじわじわと人気を獲得していったのだ。で、ギアにも注目が集まって。断りきれなくなったからか、最近ではテレビ関係の仕事も受けるようになった。
で、今回、FUZテレビが手がける全国ロードショーの映画での主役級の大抜擢。もちろん彼の実力を考えたら、それも全然不自然なことではないんだって。
「すごい人なんだ」
わたしが思わず呟くと、マリーナは小さく微笑む。
「うん、やっぱり上手いんだよね。それに、人を惹きつけるものを持ってるんだ。彼が立ってるだけで空気が違うの」
「へえ〜」
そんな人にぶつかっちゃったのか、わたし。そんなことを考えて、また今日の出来事を一通り思い出してしまう。
ううん。自信なくしてちゃダメだ。わたしはぶんっ、と頭を振った。
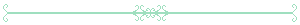
「はい、じゃあシーン32、行きます!」
「はい!」
「ホワイト・スノウ」の撮影は、表向き順調に進んでいる。
今日はロケの日だ。今回のドラマでは夜のシーンが多いから、必然的に夜の街での撮影が多くなる。冬も迫ったこの時期、夜ってすっごく寒いんだよね。でも、カメラの前では震えたりなんてできない。
トラップがすごいと思うのは、どんなに本番前は震えていても「本番!」の声がかかったと同時にすっとその震えが止まって演技の体勢に入ることだ。しかも、わたしみたいにコートやらマフラーやらの重装備でいるわけじゃなく、いつだってウインドブレーカー一つの軽い服装なんだよ。
わたしなんかコート着てても寒くってすぐには声がまともに出ないのに。スタンバイをしながら、わたしは小道具のカメラを確認しているトラップを見るともなしに見つめていた。
「本番五秒前! 四、三、二……」
キューが出され、わたしと彼は街路樹の間の道を歩き出す。
このシーンは、二人が出会って初めて互いのことを話すシーンだ。
主人公の青年は、本当は風景写真を撮りたいのにその機会が与えられず、もっぱらモデル相手に写真を撮る日々。対して少女は、音大を出てピアニストになる、という夢を家庭の事情から捨てなくてはならなくなった。
二人はひょんなことから出会うものの、互いに本音を隠したままだ。本当は少女はピアニストの夢を諦めたくなどないし、青年は風景写真が撮りたい。だけどそれぞれ相手には、夢など諦めたと言っているし人間相手の写真にしか興味ないと言っている。
「別に、叶うはずないって諦めてた夢だもの。気にしてない」
「ふうん、そう」
気のないそぶりで彼はカメラのファインダーから街路樹を覗いているみたいだ。
「諦めた夢、ってのは、夢って呼ぶのかねえ?」
そう言って、不意に足を止める。気に入ったアングルがあったらしい。それがまるでごく自然なことのように、シャッターを切る。
初めて見る。彼が人間以外のものに向けてシャッターを切るのを。
「『人』にしか、興味ないんじゃなかったの?」
そこでやっと、彼はファインダーから目を離して初めてわたしを見るのだ。
「そうだな」
自嘲気味に、唇の片端を持ち上げて。
「多分、あんたと同じなんだよ」
ゆっくりと首をかしげる。彼が近づいてくるから、そのまま顔を見上げたような形になる。
「叶うはず、ないって?」
わたしが聞くと。彼は頷いて、立ち止まる。
「そ。諦めてた夢なんだ」
そしてわたしにカメラを向ける。
「ピントがずれちまったみたいにさ」
苦笑交じりで言いながら、そのままシャッターを切る。
「はい、OK!」
言われて、ふう〜っと息をついた。良かったー、今日初めての一発OKだ。これで今日の撮影は最後だし、早く帰ってお風呂に入ってあったまりたい。
そう思って思いっきり伸びをしていると、トラップと目が合った。何か言いたげににやにや笑っている。
「な、何よ」
撮影が始まって以来、トラップは他のスタッフの誰よりも一番わたしにダメ出しをくれる。まるでわたし専用の演出家みたいに。
また何かダメ出しされるんだろうか、そう思って身構えたけれど、
「いや、別に?」
あっさりと言われて肩透かしをくらってしまった。
「まあ、でもよ」
すれ違い際、丸めた台本でポンッとわたしの頭を叩いて。
「かなり練習したんじゃねーの? セリフ追っかけてるだけじゃなくなってるし。うん、上達してきてると思うぜ」
「へっ?」
思わぬことを言われて、わたしはトラップを振り返った。だけどトラップはそのまま振り向かず、「お疲れさん」と手を振って去っていった。
……トラップに、誉められるなんて思ってなかった。
なんだかちょっとうれしくなって、わたしはあったかい気持ちではたかれた頭をなでた。
|