「おはようございまーす、今日もよろしくお願いします!」
挨拶しながらスタジオに入る。今日は映画、「Calling」とのリンクシーンの撮影だ。 どんな形でリンクするのかっていうと。主人公の青年がたまたま立ち寄るバーのバーテンさんがギアだという、ただそれだけなんだそうな。もちろんいくつかセリフはあるけれど、本当にちょい役。
なんでも、映画の封切が近くなるほど各ドラマとのリンクの度合いも高くなるそうで。今回の「ホワイト・スノウ」とのリンクは映画を製作し始めたばかりの時期のものだから、ちょっとにおわせる程度でいいんだって。
それにしても、ギアをこんなちょい役で使うなんてぜいたくなことだと思うけれどね(って、最近ギアを知ったわたしが言うことじゃない?)。
そして当のギアはというと、わたしがスタジオに入るともう既に入っていた。
「おはよう。今日はよろしく、パステル」
ギアはそう言って笑う。手に持っているのは台本だ。ほんの少しの出番だけど、随分と読みこまれたあとがある。
「あっ、こちらこそ、よろしくお願いします」
わたしはぺこりと頭を下げた。
ギアが出るのは、ほんの二シーンだけ。その両方ともがわたしとトラップ二人のシーンだ。だけど、その二シーン。まったく性質の違うシーンなんだ。
一つはトラップ演じる青年が、わたしの演じる少女に心を開き始めるシーン。
もう一つは、二人の気持ちが完全にすれ違ってしまってけんかしてしまうシーン。
こういう感じに全く時間軸とベクトルの違うシーンを続けて撮ることは珍しくないのだけれど、実はわたし、こういう撮り方苦手なんだよね。感情を切り替えるのが難しくって。うう、またトラップに「さっきまでのシーンの気持ちを残すな!」ってたくさんダメ出しされそうだ。
「パステル!」
突然呼ばれて振り向くと、マリーナが手を振っていた。
「マリーナ! どうしたの?」
「へへ、見学させてもらいに来ちゃった。っていっても、午後から『ラストチャンス』の撮影があるから途中までしか見られないんだけどね」
わたしが聞くと、そう言って笑う。映画とリンクしているから、その繋がりでスタジオ見学に来たみたい。
「えー、でもマリーナが見てると思うと緊張しちゃいそう」
「何言ってるのよ。放映されたら日本中の人が見るのよ? こんなことで緊張しててどうするの」
まあ、そうなんだけどね。
そんなことを言い合いながらマリーナと話していると、他の出演者の方々も次々とスタジオ入りしてきた。そろそろ、撮影が始まるかな。
「はよーっす」
一番遅く入ったのはやっぱりトラップだ。前髪をかき上げながら一つあくびをして、そしてこっちに目をとめる。
「マリーナ!?」
トラップが驚いたように声を上げるから、わたしはびっくりして目をぱちくりとさせた。
「久しぶりね、トラップ」
マリーナがにっこりと笑って答える。なんだなんだ、親しげな様子だぞ。トラップはなんだかうれしそうに笑いながらやってきた。
「何、パステルの知り合いなわけ?」
「パステルはわたしの友達なの。いじめるんじゃないわよ」
「いじめるなんて人聞き悪ぃなあ。面倒見てやってる、って言ってくんない? っつーか何でこんなとこにいるんだよ」
「あれ、マリーナ。なんでここにいるんだ?」
向こうの方から、スタッフと打ち合わせをしていたクレイまでやってくる。
あっという間に三人は盛り上がって話しはじめてしまって、なんだかわたしは自然とはじき出される形になってしまった。なんだか、ちょっとだけ疎外感を感じてしまう。
「三人って、知り合いだったんだ」
ぽつりと呟くと、後ろからポンッと肩を叩かれた。
「リタ」
「あの三人、もともと同じ児童劇団出身なのよ」
わたしの呟きを拾ったのか、笑ってそう教えてくれる。といっても、実際に子役として活躍していたのはクレイとマリーナで、トラップは児童モデルだったそうな。
「あれ、でもトラップって今は俳優一本だよね?」
「うん、数年前に俳優に転向したのよ」
へえ。知らなかった。あれだけの実力なんだし、てっきり子役の頃からずっとやってるものだと思ってたのに。
「それで、わたしはね」
そしてリタはちょっとだけわたしに意地悪く笑いかけてから、
「お久しぶりです、ギア『先輩』」
さっきからずっとわたしの隣りにいたギアに、ぺこりと頭を下げた。
「ああ、久しぶり。リタ」
ギアも微笑んでそう答える。
「え? 先輩、って……」
わたしが訳がわからず頭にクエスチョンマークを浮かべていると、
「わたし、ギアと同じ劇団にいたのよ。舞台演劇からこっちに転向したから。わたしが劇団に入る前からギアはずっと舞台に立ってたから、本当にすごい『先輩』なの」
リタが親切にもそう教えてくれた。へえ、そうだったんだ。
「でもギア、絶対舞台演劇以外やらないって言ってたのに。何かあったんですか?」
リタの素朴な疑問に、ギアはちょっとだけ困ったように笑った。何か言いかけて口を開いたとき、
「リハーサル始めまーす」
そう声が入ったから、ギアはそのまま口をつぐんでしまった。
……何を言いかけたんだろう? 気になって思わず見つめてしまう。
ギアはスタンバイをしながらも、わたしの視線に気づいたらしい。ちょっとだけ笑って、それからわたしの頭にポンッと手をのせた。
「行こうか」
そうだ。今はそんなこと、考えてる場合じゃないよね。軽く頭を振ると、
「そんじゃ、行ってくるわ」
トラップがクレイとマリーナにそう言い残して、こっちへやってくるトラップと目が合った。二人と話しているときに向けていた笑顔が、わたしと目が合った途端にすっと引き締まる。冷たいほどに。
どきりとする。
と同時に、なんだかどこかざらりとした感情が混じった。
なんだろう? これは。
別におかしなことじゃないのに。トラップが撮影モードに入るとこうなるのは、今までもずっとそうだった当然のことなのに。
どうしてだろう?
まるでわたしに向けられたかのような冷たい目は、お前じゃこの役は無理だって言われているような。
いきなりそんな、気がしてしまった。
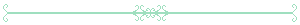
「おかしいだろ!?」
トラップが怒鳴る。これは「セリフ」じゃない。リハーサル中のいつものダメ出しだ、けれど。
わたしはうつむいて身体を強ばらせる。何も言い返せない。
「何でそんなに言葉が薄っぺらいんだよ。だいたい、さっきのシーンの感情引きずってるだろお前。ここでそんなか細い声が出るはずねーんだよ、怒ってるの、泣きたいくらいにいらだってるの、ここでのお前は!! 何度言わせりゃ気がすむんだよ」
普通なら、他の人の役作りにこんなにも相手役が口出したりはしない。カメラの向こうで見ているキットンも困った顔をしているけれど、でも何も言わないのはそれがキットンも思っていることだからだろう。
「悪ぃ、キットン。口出ししすぎだな、オレ」
溜息をついて、トラップはそう吐き出す。
バーカウンターのセットの奥、ギアは黙って腕を組んだままこちらを見ている。その視線までもなんだか痛く感じてしまう。
トラップがここまで怒っているのは、わたしの演技が演技と呼べないほど不安定なものになっているからだ。そのシーンの雰囲気まで壊してしまうほどに。
わかってる。わかってるんだ。それなのに上手く演技が出来ない。
昨日練習したときにはちゃんと出来たのに。どうしちゃったんだろう? 自分でも演技がおかしい、と思うと同時にトラップからの叱咤が飛ぶ。するとますます身体が縮こまって、演技が出来なくなってしまうんだ。トラップはそれを見てまたリハを止める。ダメ出しをする。溜息をもらす。
その、トラップの溜息が怖い。お前じゃ無理だ、そんな声が聞こえてくる気がする。
マリーナだったら、もっと上手くやるんだろうな。
ちらっとそんな考えが頭をかすめる。そうだ、わたしは最初にこの台本を見たときから、ヒロインはマリーナに似合いだって思ってた。
トラップだって、そう思ってるのかもしれない。
思い出してしまう。マリーナと話しているときのトラップの顔。笑顔。
悔しい。
何だか、いろんなことがぐちゃぐちゃになって、出てきたのはその言葉だった。
「一旦、休憩入れますかね」
キットンがそう提案し、しんと静まり返ったスタジオ内の空気がふっと緩んだ。
けれどそれも一瞬のことで、トラップの言葉でまた空気が張り詰める。
「休憩したところで、こいつの演技はまともにならねえよ」
冷たい言葉。何かが溢れ出すように、わたしの中でぐんっと悔しさが強まった。
思わず顔をあげると、こちらを向いていたトラップと目が合う。
「今日は無理だろ? 何考えてるのか知らねーけどな、演技に身が入ってないことくらい簡単にわかっちまうんだよ」
「……入れてる、つもりよ」
何も言い返せないと思いながら、それでもわたしは声を押し出していた。
トラップはハッ、と笑って、
「『つもり』だあ? つもりだけじゃしょうがねーんだよ。ちゃんと演技で示してみなきゃ誰も認めてくれねーのは当たり前だろうが」
「わかってるわよ! 自分でも演技がおかしいっていうのは。でも出来ないんだもの!」
「『出来ない』ですむことじゃねーだろうが!」
「だってわたしにはマリーナみたいに演じるのは無理だもの!!」
――――あ。
思わず言ってしまった言葉に慌てて口を押さえる。
どうして? こんなこと、言うつもりじゃなかったのに。
トラップは不機嫌な表情のまま、静かに言い捨てた。
「馬鹿か、おめーは」
そんなの当たり前だろ。
身体が震えた。わたしは自分の腕をぐっと抱え込む。
「そこまでだ」
静かな、けれど重みのある声がして、わたしは顔を上げた。と同時に後ろから抱き寄せられる。
ぽんぽん、と背中をあやすようになでられて、ちょっとだけ泣きたくなった。ギアだ。
「パステル、頭に血が上ったのかもしれないけれど今のは言っちゃいけない言葉だな。自分でもわかっているだろう?
トラップ、君の言ってることは正論だ。だけど言い方は考えた方がいい。自分でもしまったと思ってる人に対して、ただ叱咤するだけってのは親切じゃない」
トラップはじっとギアをにらみつけていたけれど、何も言わなかった。
ギアは小さく溜息をつく。
「休憩にしよう。そこの彼は、今日は無理だと言っていたが」
「こいつの状態見てりゃ、誰だってそう思うだろがよ」
かみつくようにトラップは言った。けれどギアは動じない。静かに続けた。
「そうかもしれないが、生憎おれには『今日しか』空いていない」
ハッとした。そうだ、今日を逃したらギアとの共演シーンは撮れなくなっちゃうんだ。
「単なる、話題づくりのためのキャスティングだろがよ」
トラップがギアに吐き捨てる。けれどギアは余裕の笑みで答えた。
「それでも、おれの役だからな」
そう言うギアを一瞥し、トラップは一つ息を吐き出すとスタジオを出て行った。とりあえず、ギアの言葉に従うようだ。
スタッフもみんな、休憩だということで落ち着いたらしい。がやがやとそれぞれ動き出す。
「パステル」
マリーナが困ったように声をかけた。わたしは振り向く。
「ごめん、ごめんね、マリーナ」
自分で自分が情けなくって、涙が出そうになる。ギアが後ろから支えるようにそっと肩を抱いてくれた。
「ううん、気にしてないから大丈夫」
やさしいな、マリーナは。甘えてしまいたくなって、わたしはそんな自分を叱咤した。
「ごめん、ちょっと頭冷やしてくるね」
マリーナが何か言いたげに口を開きかけたけれど、気づかないふりでわたしはスタジオを出た。
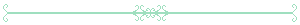
スタジオから出て休憩室に向かう。けれどわたしはすぐに、それを後悔した。
そこの自販機の前に立っているのは他でもないトラップだったからだ。
どうしようかと思っていると、トラップがこちらを見た。どきっとする。どんな顔をしたらいいのかわからない。
だけどトラップは何の気もないそぶりで、たった今自販機からとりだした缶をわたしに投げた。
「へ?」
慌てて受け止める。じわりと手のひらが熱くなった。ホットコーヒーだ。
「やるよ。さっきは、悪かったな」
わたしは今、珍しいものを見ている。そう思った。
「……なんだよ、その妙なものを見る目つきは」
「だって、トラップが謝るなんて。それに、さっきのはわたしが悪いんだし」
そこまで言って、わたしは自分がしなければならないことを思い出した。
「ごめんなさい。トラップが怒るのも、当たり前だよね」
頭を下げる。トラップは苦笑した。そのまま何も言わずに自販機にまたコインを落とし込む。
「あ、あのね、トラップ」
「何だよ?」
訝しげに振り向いたトラップに、わたしは自分の手の中の缶コーヒーを見て言った。
「わたし、ブラックコーヒー飲めないんだ」
手の中の缶コーヒーは、ホットのブラックコーヒーだ。
「……あー、そーですかい!」
わたしの手からコーヒーをもぎ取ってから、トラップは乱暴にホットココアのボタンを押した。
ベンチに二人並んで座る。なんだか、まだドラマの撮影の続きみたいだ。
お互い無言のまま、それぞれコーヒーとココアをすすっていた。
「おれ、さ」
どれくらいそうしていたかはわからない。先に口を開いたのは、トラップだった。
「今でこそ、こうやって俳優やってるけど。前はモデルやってたんだ」
さっき、リタに聞いた話だ。わたしがトラップを見ると、彼はちょっとだけ笑った。
「クレイやマリーナは子役として芝居やってたけど、おれ一人だけモデルでさ。つまんないわけよ、人に言われたようにポーズ決めて、笑って、泣いて。いや、つまんないっつーか、ずっと、おれには向いてないなって思ってた」
一口、コーヒーをすする。
「そんなとき、一度だけチャンスがあったんだ。クレイとマリーナとの共演って形で、芝居やらせてくれるっつって。何だったっけな、何かの二時間ドラマだった気がするけど。まあ、それではりきって行ったわけよ。ところがそこで、大ミスやらかして」
そのときを思い出したのか、トラップは苦笑しながら続ける。
「はりきりすぎてたんだろうなあ、カメラが回った途端、あがっちまって。セリフがぜんっぜん出てこなくなっちまったわけよ。何度も何度もNG出して、それでも上手くいかなくて。クレイやマリーナの励ましも、なんかただのやじみたいに聞こえてさ。それで、言っちまったの」
唇の端を歪めて、トラップはわたしを見た。
「おれにはお前らみたいに演じるのは無理だー、って」
わたしは何も言えず、ただトラップを見つめていた。
「そんときさ、しまったって思って。それでおれは決めたんだ。本気で芝居が上手くなるまで、絶対に芝居はしない。それまでモデル一筋でやっていこう、って」
小さく笑ったその顔が、どこか弱々しくて。わたしは初めて見るそんなトラップの姿に胸の奥を震わせる。
ああ、それでなんだ。なんだか、わかった気がした。
トラップが決して妥協しない理由、揺るぎない瞳である理由が。
「悪かったな、ああやって言われたらつらいのはわかってたはずなんだけどよ」
わたしは首を振った。
「ううん、わたしも他のこと考えてたのは本当だもの。なんだか、頭ごちゃごちゃになっちゃって」
わたしが苦笑すると、トラップは首をかしげるようにしてわたしの顔を覗き込んだ。
「お前さ、気負ってたりしない?」
どきっとしてわたしは一つ瞬きをした。
「図星だろ。なんで気負うの?」
「なんで、って……」
「いいじゃねーか」
缶コーヒーを飲み干して、空き缶をくずかごに投げる。ナイスシュート。
立ち上がりながら、トラップはわたしを見た。
「気負わなくっても、お前の演技で。おれ、パステルの演技好きだぜ?」
ふわりと、なんだかあたたかいものを感じた。胸の辺りに。
「ほれ、そろそろスタジオ戻るぞ」
「あっ、ちょっと待ってよ」
慌てて残り少しだったホットココアを飲み干す。缶をくずかごに捨てて、トラップを追った。
「そうだ、ココアのお金」
「別にいいって、おごりだっつったろ」
「でも」
悪いし、そう言おうとしたらトラップが振り返った。
「そんじゃ、演技で返してくれる?」
笑ってそう言うから、わたしもちょっと困ったように笑い返す。
「わかったわよ、やってやろうじゃない」
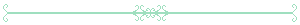
「はい、ラストシーン、本番行きます!」
「はい!」
見上げても一番上の星が見えないくらいの、巨大なクリスマスツリー。イルミネーションがとっても幻想的だ。
色々あったけれど。これで最後の撮影だ。最初に台本を読んだとき、思わず泣きそうになってしまったラストシーン。
向こうでスタンバイ体勢に入ったトラップと、目が合った。にやりと笑って親指を立てるトラップに、わたしも笑顔を返す。
たくさんたくさん、半ば罵倒するかのようにダメ出しされたりもした。でもだからこそ、トラップに誉められると本当にうれしかったんだ。
一つ、深呼吸。よし、絶対に一発OKをねらってやる。
いっぱいのイルミネーション。まるで星空のような。
クリスマスツリーの下で、二人は向かい合う。
「嘘だ、って言っただろ?」
何もかも、全部。彼はそう言う。口にした夢も希望も、そして恋心さえも。
だけどそれは、彼女を思いやってのことで。その本心は届いてしまう。彼女、そうつまりわたしにも。
だから泣き出しそうな顔を無理やり笑顔に歪めて、わたしは精一杯の声で言う。
「わかってるわよ。いっつもそうなんだから」
ツリーを見上げるふりで涙をこらえる。ニセモノの星。
「天の川にもならないね、このツリー。年に一度って約束すら、できない」
恋人として別れるわけじゃないのだ。だから、それは当たり前なのだけれど。
もう会えないのは、当たり前なのだけれど。
「それなのに……なんでだろうな」
彼は言った。
「ファインダーって、本当のことしか見えないんだよな」
かすかに口元を歪めて、カメラをわたしに向ける。その後ろのツリーを撮るふりをしているけれど、でもわたしにはわかってしまう。
だから。彼のカメラの正面を向いて、彼に向かって笑いかける。本当のことが彼に見えるように。
「わたしきっと、ピアノ弾くのやめないと思う。あなたが、好きだって言ってくれたから」
けれどどうしてだろう、こらえたはずの涙が一筋だけ流れるんだ。
「わたしは、あなたが好きなんだと思う」
彼は黙ってシャッターを切る。カメラを下ろす。わたしは「嘘」になる。
「多分、おれもそうだったよ」
わたしは、本当を見ることのできる「ファインダー」を持っていないから。だからこれが嘘なのかそうじゃないのかはわからないけれど彼の目に映る「嘘」のわたしはとにかく笑う。
「わかってるわよ」
「嘘」なのだから、絶対に泣かない。泣いたらそれも嘘になってしまうから。
「……ありがとう」
彼はただそれだけを言って、そっとわたしの頬に触れる。
雪が、降る。白い白い粉雪。
しばらくそのままでいて。そして彼は離れた。わたしは何も言わない。彼も何も言わない。
ただ黙って、そっとツリーから離れる。別々の方向へと。
「はい、お疲れー! OKです!」
そう言われてしばらくは、その言葉の意味が飲み込めなかった。
「おい、何ぼけーっと立ってるんだよ。終わったぜ?」
やってきたトラップがわたしの頭をぱこんっとはたく。
「終わった、の?」
トラップが頷く。そっか、終わったんだ。
「二人とも、お疲れ!」
「すっごく良かったよ〜」
出番は先に終わっていたけれど見に来てくれていたクレイとリタが、そう言いながら花束を渡してくれた。
「特にパステル、すっごく上達したね」
リタにそう言われて、ちょっとうれしくなってしまう。もちろんこれは、トラップのおかげなんだろうけどね。
「トラップ、お疲れ様。それに色々とありがとう」
そう笑いかけると、トラップはちょっと唇の片端を持ち上げた。
「いえいえ、こちらこそ。そうそう、一つだけ注文」
「何?」
トラップはにやりと笑って、
「次に共演するときには、もうちょい色気を出せるようにしといてくれよ」
「なっ!」
わたしが何か言おうとするより早く、トラップはスタッフのところへ行ってしまった。くぅ〜、なんかすっごく悔しいんですけど!
「まあまあ、パステル。頑張ったご褒美にいいこと教えてやるから」
わたしをとりなすようにしてクレイがそう言った。そのまま、耳元に口を寄せる。
「――――嘘」
言われたことが信じられなくて思わず呟くと、クレイは笑いをこらえたような顔で
「ホントだって」
と言う。
だって、そうだとしたら。あれだけたくさんわたしにダメ出しをしてくれたのは、ひょっとして。
――おれ、パステルの演技好きだぜ?――
そう言ってくれた彼の顔を思い出す。
――――このドラマのヒロインにパステルを推薦したの、トラップなんだよ。
次に共演するときにはちょっと聞いてみたい。どうしてわたしをあのドラマに推薦してくれたの、って。
そう聞いたときの彼の顔を想像して、わたしはちょっと笑ってしまった。
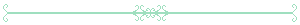
「ホワイト・スノウ」はかなりの高視聴率で、この冬話題のドラマとなった。
マリーナとギアの出演する映画の撮影も順調だとか。前評判も随分と高くて、わたしも楽しみにしている。
トラップとクレイは今度、舞台で競演するんだって。テレビとは勝手が違うってちょっと大変そうだった。もちろん、二人ともすごく楽しんでやってるんだけれどね。
リタは次のクールの連続ドラマの主演が決まった。共演するのは今一番の人気子役であるルーミィ。
そしてわたしも、次のクールから初の連続ドラマレギュラーが決まったんだよ。他にも色々と仕事の話が来てて、今までは想像もしていなかったくらい一気に忙しくなってしまった。
でもこれは、また別のお話だ。
〜END〜
|