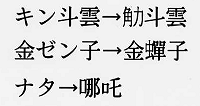
・第1回・
・取り敢えず書いて編集さんに見せたら、「売れ線から外れすぎてボーイズラブでは売れません」と言われた代物(泣笑)。…西遊記ベースじゃどうしたって少年漫画ですね。はっはっは。悟空が書きたかったんですよお(号泣)。
※お断り! 文中に出て来るキン斗雲のキン、ナタ、金ゼン子のゼンは下記が正しい表記です。すっげー悔しいけど、字が無いんだからしょうがない…この悔しさがわかるあなたはお友達だあッ!…それでは本文へどーぞ。しくしく。
(※松田篁 様、白馬の名前を教えて下さって、有難うございます! 多謝!)
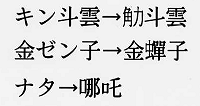
日暮の時刻だった。
取り分け上等でも粗末でもない住宅地。賑やか過ぎることもなく、静か過ぎることもなく。
一人の男子高校生が、長い影を引き連れて、自宅への道を歩いていた。華奢なシルエットだ。学生鞄を提げている半袖の白い制服から覗く腕は、いかにも力仕事には不向きに見える。短く清潔に整えられた髪は、校則ではなく、彼の性格に依るものだろう。小さな頭と狭い肩を繋ぐ首は、やはり細い。
優しい顔立ち。気が弱そうにも見える整った顔は、怒るよりも笑う方が似合うだろう。その中で細い真っ直な眉が、実は強い頑固な気質をこっそりと表している。
いつものように学校から家まで、急ぐでもなく遊ぶでもなく歩く彼を、見つめる者がいた。
いつもとは違う下校風景。彼はそれに気が付いた。
男は、沈みかける太陽を背負って、彼の行く手に腕組みをして立っている。彼とは対照的に、その腕には逆光にもよくわかる実用的な筋肉が確りと纏われている。右の上腕に巻き付けるように嵌められた金輪のアクセサリーは、まるで弾け出す力を封印しているようだ。ぴったりとしたくすんだ赤のタンクトップに、これまたぴったりとした洗いざらしの、元はインディゴ・ブルーだったのであろうジーパン。肩や胸や足の筋肉もさぞしなやかで頑強なのだと、着衣の上からもよくわかる。
何より印象的なのはその髪だ。日に灼けたものかそれとも生来か、紐で括って背中に垂れた赤茶けた髪は、夕日に透けて金にも見える。紐を解けば、軽く波打ち鬣(たてがみ)のようになるのだろう。
男はにやりと笑っている。髪と同じ色をした太くて力強い眉の下の、爛と光る目で、彼を見ている。
瞳の色は茶だ。それも生来なら、日本人ではないのかもしれぬ。
「――よう」
彼は瞬き、立ち止まった。男は、にっと歯を見せた。
獣のような風情の男の顔が、そうすると酷く懐こくなった。
「捜したぜ」
彼は辺りをきょろきょろと見回した。道行く者は自分と男の他にいないと知って、改めて男をじっと見た。男は彼に話しているのだ。
「ええと……」
左手をこめかみに当てた。
「……どちら様でしたっけ?」
「んなっ……」
赤毛の男はあんぐりと口を開いた。そのまま数秒、男の時間は止まったようだ。彼が、あの、と言いかけたところで、男はふっと息を吐き、「……まさかな」と笑って首を振った。
「まさか、クソが付く程真面目なあんたの口から、冗談が聞ける日が来ようとはな。然しもの俺様も予測できなかったぜ……いや、参った参った。大したもんだぜ、時間って奴は!」
さも面白そうに、はっはっはあ! と声を上げて空を向く。
「あのう……」
彼は申し訳なさそうに、申告するのだ。
「すみません、ほんとに、思い出せないんですけど……どこかでお会いしましたか?」
今度こそ男は、落雷の如きショックを受けた。腕を解き、目を見開き。四つ足の獣が後足で立ち上がったような格好で。
「俺を……」
信じられないものを見るように。
「まさか、俺を」
彼に語り掛けているのか、茫然自失に呟くのか。
男の年は十八か十九か。いずれ二十歳前のようだ。
ならば、以前に会ったことがあるとするなら、彼も男も幼い頃だったに違いない。しかし彼には本当に憶えがないのだ。記憶力はいい方だ。それに成長し姿が変わったのだとしても、この男の瞳は余りに強い。忘れることが可能だろうか。
やはり、男の勘違いだ。
無関係なのだと思いつつ、男のショックを受けた様は、気の毒に見えて。
「……誰だと思ったんですか?」
彼は尋ねてみた。
「憶えていねえのか?」
訴えかけるその顔は、子供が駄々を捏ねる様にも似て。
彼の家はすぐそこだ。関わり合いにならずに、逃げ込んだ方が良かったろうか。人違いですよ、と言おうとして、背中から肩を叩かれ、振り向いた。
「貴史(たかし)、何してるんだ?」
背の高い細身の男。水色のシャツのボタンを襟の端まできっちりと留め、グレーのズボンの折り目も正しい。髪に一筋の乱れなく。眼鏡の奥の切れ長な目は、彼を優しく見つめている。
「正臣(まさおみ)……あ、柴(しば)先生」
まるで保護者が現れたかのように、彼は安堵の息を吐いた。
「何でも。そこの人が、俺を誰かと間違えたみたいで」
教え子の肩を抱いたまま、彼はちろりと赤毛の男を見た。その視線は打って変わって、氷のように冷たい。
男は仰天している。歯を剥き出し、貴史の肩を抱く優男を、驚愕と憤慨で睨み付けている。
「てめえ……」
唸るように男は呼んだ。答える声は視線に等しく冷たい。
「俺ですか? 俺は彼の家庭教師だが」
「んなこと尋いてんじゃねえ!」
「さ、貴史、中に入ろう。今日は数学の日だね。宿題はできているかな?」
男の憤慨を受け流し、彼は教え子の背を押して一軒の家へと近付いていく。
「おいおい!」
追いかける男を無視して玄関を開け中に入ると、彼はその場で貴史を抱き寄せた。狙っているのは唇だ。
「えっ、ちょ……正臣」
貴史は赤毛の男を気にしている。男は立ち尽くし、あんぐりと口を開いている。
ゆっくりと閉まっていくドアの向こうで、二人の唇は触れた。やがて貴史はうっとりと目を閉じる。ドアがガチャリと音を立てる寸前、正臣の目は男を向いて、笑っていた。
赤毛の男はふるふると震えて、両の拳を握り締める。
「あんの……」
ドアの向こうどころか、向こう三軒両隣、いや町内中に聞こえる声で。
「……河童野郎―――ッ!!」
*
三蔵(さんぞう)法師は旃檀功徳仏(せんだんくどくぶつ)の仏号を釈迦如来(しゃかにょらい)に授けられたが、私は唐で訳経をせねばなりませんと、天竺(てんじく)は雷音寺(らいおんじ)に留まることを拒絶した。
貞観(じょうがん)十九年正月。三蔵が長安の都を旅立ってから十八年。取経の旅は、終わろうとしている。
「悟空(ごくう)……」
三蔵様お早く、と天竺から運んで来た、大量の経文を乗せた荷車の脇に立つ従者が催促をする。
唐の国境に入ろうという時。三蔵は一人残った弟子に、別れを告げる。
猪八戒(ちょはっかい)と沙悟浄(さごじょう)は、昔の罪を許されて、それぞれ浄壇使者(じょうだんししゃ)、金身羅漢(こんじんらかん)と仏号を授けられ、如来の元にいる。悟空にも闘戦勝仏(とうせんしょうぶつ)の名が用意されていたが、如来のくれる名なぞ断ってくれようか、と考えている悟空だ。
「今まで、世話になりました」
三蔵が戻ったという知らせを持った先触れが、今頃は唐の太宗皇帝の元に届き、三蔵を迎え入れる祭りの準備でもしていることだろう。
「……行けよ。国の連中が待ってるぜ」
「生まれ変わっても、――きっと」
三蔵はそう言って、唇を噛み、微笑んだ。
「お前は、不老不死なのだろう? ……生まれ変わった私を、見付けておくれ」
今生は、これで別れだ。
「緊箍児(きんこじ)を外そう。もう必要のないものだ」
「外さねえでくれ」
三蔵は怪訝に見つめる。あれ程、悟空が厭うていた、まじないの受信機を。
「……何かあったらブツブツやりな。飛んでいくからよ」
悟空は頭の金輪を指で突(つつ)く。
三蔵は最後に、にこりと笑んだ。では達者で、と呟いて、己が国へと戻って行った。
*
沿道の民家も疎らな道を行けるところまで行った後は、車ならばそこで乗り捨てねばならぬ。延々続く石段を登りに登った森の中。古くてくすんだ建物が、へばり付くようにある。
鬱蒼とした山中の寺院。無造作に置かれた石に刻まれた寺の名は西雷寺(さいらいじ)。その境内。
頭に手拭いを巻いた一人の男が、懸命に竹箒を動かしている。
「こりゃ、高昌(こうしょう)」
紺の作務衣を着た和尚が、本堂から姿を現し、掃除真っ最中の男を呼ばわった。
掃除男は勢いよく住職を振り向き、
「うっせえ、クソ坊主! 『こうしょう』って呼ぶな!」
怒鳴り返す拍子に、手拭いの下の束ねられた赤毛が、ぶんと揺れた。
「僧の名は音読みすると決まっとる」
「嫌いなんだよ。『たかまさ』の方がなんぼかましだ!」
大体俺は坊主じゃねえ! と高昌は怒鳴る。
それでも掃除を続ける辺り、存外真面目な性格かもしれぬ。
住職は、がっしがっしと箒を動かす居候に、毎度毎度の苦言を呈す。
「作務衣を着んか、作務衣を。またそんな赤い服で、赤い髪も、剃らんでいいから黒く染めるなり、せめて切れと言うとるに」
この西雷寺は江戸の昔から続く寺で、檀家衆も勿論古くから……と住職の話は続く。
「実質修業に関係はないとわしはわかるが、中にはお前のその格好を厭う方々もおらっしゃるのじゃ。あれはああいう者であれでよう頑張っておるのですといちいち語って聞かせるわしの身にもなってみい」
「うるせえ。語って聞かせるのは坊主の仕事じゃねえのかよ」
高昌はケッと咽で吐き捨てる。
「大体がこんな山の中にそうそう檀家が来るかってんだ」
「そうそう来んから一時(いちどき)に話せず面倒なのじゃろうが」
物臭坊主、と高昌は悪態をつく。
住職はふう、と息を吐く。
「しかしなんじゃな。お前もその<なり>と物言いで、ようあちこちの寺を渡れたものじゃ。『捜し物をしている』と言ってお前がここに現れて一月経つが……この地で、捜し物は見つかりそうかの?」
「……」
高昌は口をねじ曲げた。それを住職は誤解した。
「まあ、気長に捜せ。わしも気長にお前の赤髪を切らせるとしょう」
「……切らねーよ」
かっかっか、と住職は本堂に戻って行った。
高昌はその場にぺたりとしゃがみ込み、両腕を猿のように両膝の間に垂らした。頭をかくりと俯かせ。
呟きは、住職がそこにいても、聞き取れなかっただろう。
「……褒めてくれたんだ。あいつが」
だから、髪(これ)と輪っかは持って行こうと決めていた。
てっきりどこかの寺にいるものと思っていた。坊主以外のあいつを想像することができなかった。
生まれ落ちた気配を感じたその時は、よくぞ今に居合わせたと、己の運を喜んだ。
それが、どうだ。
まさか、忘れられているなどとは、夢にも思っていなかった。
会いさえすれば、廻り逢えさえすれば、昔と今が、すぐにも繋がると、信じていた。
前世の高昌の寿命は長かった。というより不老不死のはずだった。待って待って待って待って……
千三百年、待ったのだ。
あいつが、生まれ変わるのを。
「……クソ坊主」
脳裏に浮かばない日はなかった。
若い学僧が、自分に向かって笑っている。
耳に聞こえない日はなかった。
優しげでありながら、固い意志を帯びた、呼ぶ、声。……
唐代の高僧、
――玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)。
*
「――悟空!」
切り立つ岩の上に立つ悟空を、僧衣を砂混じりの風に棚引かせ、馬上の三蔵が手を翳して見上げている。
砂ばかりの砂漠が、ようやく岩混じりに変わり、目指す町も近付いただろうと、様子見に上った妖猿を呼んでいる。
玄奘三蔵、二十六歳。貞観元年(六二七年)八月、唐の都長安を旅立つ。
旅の途中、五行山(ごぎょうさん)で石猿の孫悟空(そんごくう)、鷹愁澗(ようしゅうかん)で龍王子の玉竜(ぎょくりゅう)、高老荘(こうろうそう)で猪怪の猪八戒、流沙河(りゅうさが)で水妖の沙悟浄を供に加え、遥か十万八千里の西方、天竺国にあるという、大乗仏教の妙文を手に入れんが為の取経の旅に赴いて、すでに数か月。
「どうした?」
ふいと一瞬で馬の隣に降り立った悟空に、三蔵は馬の首を撫でて言った。
「馬が限界だ。町がすぐそこでないなら、この岩陰で少し休もう」
馬は荒い息を吐いている。だが悟空の目には、その三蔵こそが疲れているとよく知れた。三蔵の涼しい眼差しは馬を思い遣るばかりで、きりりとした眉は、ちらとも苦しげではなかったが。
町はもう半日も歩けば辿り着けたが、
「わかった。じゃ、少し休むか」
悟空の言葉に、三蔵の顔は微笑む。よっしゃ、そんなら軽く食事でも、と騒ぐのは八戒だ。悟浄は黙って荷物を肩から下ろす。
馬を下り、八戒から水を受け取った三蔵は、夕日の向こうに目を凝らす悟空を、眩しそうに見た。
砂風に吹き上げられて、悟空の赤い髪がぶわっと広がり、忙しなく舞う。
「……何かいる?」
「ん? いや、念の為に警戒しただけだ」
なびく髪の隙間から目だけで振り向き答える悟空の、気にせず休め、と言外の言葉を聞き取ったのか。三蔵は、ありがとう、と礼などを言う。
後ろ向きに手をひらひらと振った悟空に、三蔵はくすりと笑った。
「……きれいだね」
「……あ?」
ああ夕日のことかと、悟空が納得しかけた時。
「悟空の髪」
手を伸ばした三蔵は、そっと赤い髪の一房を抓んだ。
「な、なん……」
「夕日に透けて、ほら、金色に光っている」
「……」
日に翳して、悟空に示す。悟空は髪も三蔵も見ないようにして、何言ってやがんだか、と吐き捨てた。
兄貴照れてんの? と間抜けな声で尋ねた八戒は、次の瞬間、悟空の拳で泣かされる羽目になる。
*
ぱさぱさに傷んだ猿の赤毛を「きれいだ」などと言われたのは、それが最初で最後だった。
斉天大聖(せいてんたいせい)、孫悟空。それが、高昌の前世だ。
天界の桃を、仙人の金丹を食い、不老不死になった猿の王だ。……のはずであったが、どういう訳か、悟空は死んだ。もっと言うなら、妖猿の命を一旦終えた。
死んだ憶えもないのに、ある日気付いたら、悟空は人間の赤ん坊の姿で籠に入れられ、川を流れていたのである。
赤ん坊の高昌は、首に金輪を掛けていた。
縮れた短い髪の色は、日に灼けたように赤かった。
拾って高昌と名付けてくれたのが、名もない寂れた寺の住職だった。
どうやら妖猿だった頃とは時代も下り、場所も更に東へ移っていると、拾われてから知るに至った。
よもやその間に三蔵が生まれ変わって、あまつさえ生を終えてしまっていないだろうなと気を揉んだが、悟空が人間になって二年後に例の魂の転生を感じた時には、和尚の呆れ訝しむ目など無視して、二歳児の高昌は奇声を上げて踊ったものだ。
会える。逢える!
(生まれ変わっても、――きっと)
千三百年前の約束を!
――よもや、約束を申し出た当人が忘れているとは。
人間の身は不自由だ。石猿時代に憶えた仙術は、何一つ使えなくなっていた。身を分けられもしなければ、雲にも乗れない。辛うじて感じた魂の気配を頼りに、高昌は身一つで、あちこちの寺を尋ね回ったのだ。
……やっと、見つけたのに。
登り来る気配を感じるのがもう一瞬遅ければ、高昌は不覚にも、落涙を許すところだった。はっとして顔を上げ立ち上がる。
墓参りに来た檀家ではない。近付く気配は、高昌を目指している。しかも気配に憶えがある。
境内の外をじっと見据えて、高昌はその姿が見える先に思い至った。
「お前……」
ガサリと木々を分けて現れた顔が高昌を認めると同時に。
「――八戒か?」
「――うわあい!」
高昌が呼ぶ声を聞いて叫んだものか。ふうふうと息をしていた、現れた小柄な丸々とした男は、汗だくのやはり丸い顔の中で目も口も大きく丸くし、喜色満面、どたどたと高昌に駆け寄った。
「やっぱしや! やっぱし悟空の兄貴やあっ!」
高昌に抱き付くや、おんおんと泣き出す。
円な目を糸のようにして、登るん苦労したわ、もう、階段きつうてきつうて、と泣き笑いながら訴える。
「おいおい、階段きつくて泣いてんのか?」
高昌は呆れながらも笑みが溢(こぼ)れる。遠い昔も、こうして豚の化け物に泣き付かれたものだ。
「ちゃいまんがな。もう……まさかこうして同じ時と国に、みんなして生まれて来れるなんて……悟空に会った、いうて悟浄に聞いて、」
「そうだ、悟浄だッ!」
「ひいっ?!」
ごおっと噴き付けた高昌の気迫にあてられたように、人間の小男に生まれ変わった八戒は、びくっと震えて高昌から離れた。
高昌は、忘れられたショックから、憤りを忘れていたのだ。
「あんの野郎……悟浄め……三蔵に……三蔵に……!」
そのことやけど、と八戒は、おずおずと切り出した。吹き出す汗は冷や汗に変わったか。悟空の怒りのとばっちりを受けるのを、心底恐れているようだ。
「悟浄な……一等最初におっしょさん見つけてん。で、おいらは半月程前に二人に会うたんやけんど……」
八戒は言葉を切って、ちら、と高昌を伺い見る。
「なんだ、言え!」
おいら、悪ないで、と言い置いて。
「会うたんやけど……そん時はもう、悟浄とおっしょさん、……恋仲やった」
バキッと、竹箒が高昌の手の中で砕けた。
「あわわわわ……」
兄貴、落ち着いて~、と八戒は宥めにかかる。
「ちくしょう……」
ぎりぎりと歯が鳴る。
「……まさか悟浄が何かしやがったのか? でなきゃ三蔵が全部忘れちまうなんて」
「さあ? 悟浄が言うには、最初っから、いうて……悟浄も忘れられてたて」
「何だそうか」
悟浄が嘘を吐いている可能性は、端から吟味もしない。
「悟浄(てめえ)も忘れられてんじゃねえか。へっいい気味……じゃねえ! 忘れてんのをいいことに、勝手してんじゃねえかッ! 糞ッ!」
一人で嗤ったり突っ込んだり憤ったりしている高昌に、八戒ははあ、とこっそり溜め息を吐く。
怒りはまだ治まらぬ。が、高昌は漸く八戒の格好に気が付いた。
「……そういやその服、三蔵が着てたのと似てるな」
嬉しい話題だったのか、八戒は機嫌良く笑う。
「似てる、じゃなくて、一緒でっせ。今、おいら、おっしょさんと同級生でんねん。へへ。高校生、やねんで」
「一緒の服? また偉く横に広いがな」
高昌は遠慮のない観察結果を告げる。秋生は丸い顔を更にぷうと膨らませ、口を尖らせる。
「制服って奴どす! 今のおいらの名前は、樋口秋生(ひぐちあきみ)、ちゅうねん。おっしょさんは、秋生ちゃん、いうて、呼んでくれんねんで」
「秋生ちゃんねえ……」
かあいいやろ、と秋生ちゃんはくふくふ笑う。
「にしても、お前その言葉、何だあ? 無茶苦茶だな」
えへへ、と秋生は刈り上げた後ろ頭を掻く。
「日本全国、おっしょさん捜して転校繰り返したけんね。ばってん、おっしょさんは、この言葉、面白い、いうて笑ってくれて。もうそれだけで、捜した甲斐があった、いうもんや」
「ふーん……」
「せや、おっしょさんの今の名前な、渡辺貴史、いうねん」
「ああ、そういや貴史、とか言ってたな」
また憤りが蘇る。
「悟浄は、柴正臣。大学生で、貴史はんの家庭教師……」
で、恋人や。最後の言葉は、口の中で呟いた。だが高昌は、確りと聞き取っていた。
「……なあ八戒」
「はあ」
「俺は随分、我慢強くなったと思うだろ」
「う、うん」
「ところがそりゃ勘違いなんだな」
にやあと笑っていく高昌の口元を見て、秋生はぶるると震え上がった。
「ひええ兄貴、頼むから落ち着いてえ!」
「悟浄が住んでんのはどこだ、案内しろ!」
「そ、そやけど多分、今頃、貴史はんと……あわわわ」
慌てて口を塞いだがもう遅い。
ぶちっと高昌の中で何かが切れた。
ひいいいいーという悲鳴が、境内から山を下りる階段に吸い込まれていく。高昌に腕をむんずと捕まれて、風のように飛ぶように、登る時の何倍ものスピードで、秋生は山寺を後にした。
「……何を考えている?」
「あっ……ごめんなさい」
貴史は慌てて参考書に目を落とす。
週に三日、こうして貴史の部屋で正臣に勉強を見てもらうようになってから二か月。二人でいる時に、正臣を忘れて別のことを考えていたのは初めてのことだ。貴史は自分で驚いている。
「謝らなくていい。何を考えていた?」
正臣は静かな声で尋ねる。他の者には冷たく思える程の正臣の声や眼差しが、自分に向けられる時にだけは暖かみを帯びると貴史は知っている。
椅子の後ろに立つ正臣を振り仰いで、貴史は薄く微笑んだ。
「……昨日の人のことを。何だか、印象の強い人だったなあって。……捜してる人に、会えればいいなって」
考えてた、と笑う貴史に、正臣は尋く。
「俺と、どっちがいい男だった?」
「え……」
珍し過ぎる問に、貴史は面食らって瞬いた。その顔を見て、正臣は失笑する。
「……すまん。変なことを尋いた」
「……そういえば、正臣も、初めて会った時に、見つけた、みたいなことを言ったね」
「……そうだったな」
あれは、理想の相手に会えた、と言ったんだ。
冗談だか本気なのだか、判別の付かぬ正臣の声。
「正臣」
断定的に、名を呼んだ。
「ん?」
「さっきの答。正臣のがいい男」
正臣は瞬いて、貴史の肩を抱いた。
正臣はいつも、大事なものを扱うように貴史に触る。貴史が正臣と知り合って、初めて<そういうこと>になった時も、そうっと、そうっと、まるで壊れ物を丁寧に弄るようだった。
「……壊れたりしないのに」
「ん?」
ぽつりと言った貴史の言葉を、正臣は聞き逃さなかった。
「……キスしてって言ったんだ」
照れながら貴史は申告する。優しく笑って触れる唇は、やはり優しい。
――違う唇を、知っているような気がする。
そんな憶えの、あるはずもないというのに。
貴史に正臣は、初めての相手だ。なのに、近頃特にそんな気がするのは、一体どういう訳だろう。
……自分は多分、正臣に、もっと激しくして欲しいのだ。
そんな淫乱な部分が自分の中にあるのだと思い、でも正臣となら、と確かに望んでいる自分を見付けて、貴史は受け入れ、自分から唇を押し付けてみる。正臣は応えてくれるが、結局、正臣が貴史を大事に思っているのだと確認することになる。
触れ合う舌は、あくまで優しい。欲望の権化であるはずのもので、貫く時でさえ、なお。
正臣は、口付ける貴史から唇を離し、何かを感じ取ったかのように顔を上げた。
貴史の親がお茶を持ってくる時など、勉学以外で貴史に触れていた場合、正臣は逸早く察知して、す、と貴史を離れる。今度もそれかと思ったが、どうも様子が違う。
「……正臣?」
「こらあァ――!! 河童ァ!!」
声は、外から聞こえた。
「な、何?」
貴史は目をぱちくりとする。
「出て来やがれェ、唐変木ッ!」
正臣は、ふうー、と溜め息を吐いた。目を閉じ、やれやれ、と呟く。
「貴史、お前は出る必要はない。一寸行って来る」
参考書の続きをやっていろ、と部屋を出た。
「……正臣?」
声に聞き覚えがあった。これは、昨日の。
貴史は開いた参考書をそのままに、立ち上がった。
「出て来いっつってんだ、てめえ!」
「あ、兄貴~」
夜の住宅地、表札に渡辺と書かれた家の前で、高昌は仁王立ちして喚いている。それを秋生は、止めたいのだが、止められずにいる。
寺を出たのはまだ夕方だった。山を下り、汽車に乗り、している間に、すっかり日が落ち暗くなってしまった。たかが隣県、昔はキン斗(とんぼがえり)の間もかからぬ時間で辿り着けた距離である。誠人間の身は不自由だと、高昌は歯痒く思う。
おまけに確かに、この家の二階の一角に、三蔵と悟浄の気配を感じるのだ。しかも、二人ぴたりと寄り添って!
ちくしょう、と高昌は吐き捨てる。
「出て来い、河童ァ!」
ガチャリと、玄関のドアが開いた。出て来たのは、正臣だ。
「……出やがったなこの野郎」
ぎり、と歯を噛み鳴らして、高昌は睨む。正臣は涼しく受け流す。
「近所迷惑だ。話があるならこちらから出向く。立ち去れ」
「んだとう?」
「ほんま堪忍、すぐ連れてくさかい」
「八戒、てめえどっちの味方だ?!」
「貴史はんのどす!」
秋生は真面目に断言する。
「なあ、ここは引いとくれやす兄貴、頼んまっさ」
あちこちの窓やドアの隙間から、秋生に抱き付かれてなお踏み込む勢いの高昌を眺める好奇の視線が注がれている。
「迷惑すんのは貴史はんでっせ!」
「……っ」
高昌が黙り込んだのは、正臣の後ろに貴史を見付けたからだ。
その顔は決して迷惑そうではなかったが、何事だろう、という、<部外者>のものだった。
「……出て来なくていいと言ったんだ」
振り向き、正臣は、責める響きなしに言う。
「うん……でも」
その後ろに、母親でもいるものか、貴史は家の中に、何でもないよ、と優しく言った。
「話は済んだ。さあ、入ろう」
正臣は貴史の背を押して、玄関を戻っていく。
「……あれ? 秋生ちゃん」
気付いた貴史に、えへへ、と秋生は手を振った。
「貴史はん、明日また、学校で」
うん、と貴史は手を振り返す。
「秋生ちゃん、その人と知り合いなんだ?」
「――おい!」
高昌は叫んだ。
「知り合いも何も、こいつもあんたも、一緒に天竺まで行った仲じゃねえか! こいつが八戒であんたは三蔵! そいつは悟浄で、俺は孫悟空だッ!」
言ってもうた、とばかり秋生は目を瞑る。
正臣は高昌に冷たい視線を送る。
貴史は。
「……は?」
ぽかんと、呆気にとられて高昌を見ていた。だからあんたが三蔵で、と高昌が繰り返した時、目をしばたいた貴史は、「……ああ」と得心の声を上げたのだ。
高昌はぱあっと笑う。勢い込む!
「思い出し……」
「なる程『西遊記』か! ふうん、言い得て妙だね」
「―――」
「……あは、俺が三蔵法師って以外は、なんかぴったり。そっか、それで正臣のこと河童って。じゃあ正臣もこの人と知り合いなんだ?」
「……まあな」
正臣に押されて玄関に消えていく貴史は、高昌に「じゃあね。『孫悟空』さん」と手を振った。
「……兄貴、行こ」
秋生に腕を引かれて、高昌は振り払いも留まりもしない。いや出来ない。力なく、引かれるままに、ついていくだけだ。
顔だけ見れば、秋生の方が泣きそうだった。三蔵に破門された時でさえ、悟空はこんな顔をしなかった。高昌は、がっくりと、魂が抜けたような顔で、黙って歩いた。
*
全く誰が言い出したものか、坊主の肉は長寿の薬、三蔵法師程の高僧の肉ならば不老不死を得られるだろうと、寄って来る不心得妖怪には事欠かなかった。
八戒の九本歯の鋤が、妖怪変化の頭を叩き割る。
悟浄の降魔の杖が、魔物の腹を串刺しにする。
悟空の如意金箍棒が、妖怪盗賊共をなぎ倒す!
三蔵はその度、自分を食らおうとした化け物共の為に、経を読む。
「……許しておくれ。今はまだ、小乗の経しか知らぬ。天竺で大乗を手に入れたなら、必ずもう一度読経する故、亡者よ、どうかそれまで、待っていておくれ……」
そもそも如来の経文は、人間の亡者ならともかく、妖怪は端から勘定に入っているのかね、と悟空が言うと、決まって三蔵は悲しげに、命は命です、と眉を寄せた。
一度悟空が、じゃあ俺が死んだら、やっぱり経を読むのか、と尋いたら、三蔵は猛烈に怒って、「読んでなどやるものか!」と叫んだ。
その時は悟空はむっとして、いらねえよ、俺は不老不死なんだぜッ! と言い返した。
それを聞いた三蔵は、ほっとしたような、悲しいような、とにかく怒り以外の表情をした。
*
処西雷寺。天候薄曇り。
高昌は境内の石畳にぺたりとあぐらをかき、砕けた柄に添え木を当てて、竹箒を修復していた。物を大切にする心根は物よりも大切じゃ、と和尚は言ったが、この寺が貧乏なのも本当だ。
ぎり、と巻いた縄を引き絞り、結わえて余った端を千切った。……無論、通常人の力では簡単に出来ることではないから、縄がやわい訳でもない。千切った口が不揃いだが、気に入らなければ和尚が自分で刃物を持って来て切るだろう。
縄の端切れをジーパンのポケットに突っ込んで――ポイ捨てはしない。掃除をするのは自分なのだ。――高昌はふいと顔を上げた。
長い山寺の階段を登って来る、二つの気配。
姿が見える先に、ひいひいと息吐く音がした。
「……かなんて、やっぱ。……ひい」
秋生だ。汗をかきかき、足取りも重い。
来やがったな、高昌は噛み潰す。秋生の後ろから涼しい顔で現れた。正臣だ。
秋生は境内に高昌を見付け、ぱっと笑う。
「あ、兄貴ぃ」
額の汗を腕で拭って、秋生は懐こい顔で歯を見せた。
高昌は立ち上がり、境内に入って来た二人をねめつける。それだけで気の毒に秋生は、「ひっ」と小さく身を竦めた。
「……は、話をしに来たんや、な、そやなあ」
高昌と正臣を交互に見やる。高昌はまるで熱を発しているかのようだ。秋生の言葉に圧する気迫が無言で答える。対する正臣は冷ややかな水鏡だ。長い階段を秋生と同じく登って来たなど微塵も感じさせない涼しい顔で、
「最初に言っておく」
正臣が口を開いた。
「貴史は俺のものだ。譲ってやる気はない」
ガツン! とぶつかる音がしたのは、瞬間ゆらりと赤毛が揺れたかと見えた高昌の、目にも留まらぬ肉迫を、秋生が正面から抱き留めたものである。
「放せ八戒ッ!」
「喧嘩しに来たんとちゃうんや、は、話しよ、話!」
単純な力比べなら、秋生の方が上だ。歯をぎりぎりと噛みながら、高昌は動けぬ腹いせに正臣をなお睨み付ける。
「正臣はんも、穏やかにいかな、穏やかにい」
「俺は至って穏やかだろうが」
ああ、あかん、喧嘩腰やあ、と秋生は泣き声を出した。
「……いいか。よく聞けよ、悟浄」
秋生に抑えられたまま、高昌は<彼なりに>静かに話し始めた。
秋生はそれでも手を放す訳にはいかない。高昌の筋肉はぴくぴくと震え、辛うじて爆発を抑え込んでいるのだと、触れる身に見る目にわかるからだ。
「三蔵はな。この俺、悟空様と約束したんだ! 生まれ変わってもきっと、また出逢おうってな!」
「あ、あんなあ、兄貴……」
秋生が、言いにくそうに口を挟んだ。
「……それ、おいらも約束してもろうたで」
「なに……ッ」
高昌が秋生を見る間に正臣が、
「俺もだ」
「何イ――ッ?!」
ガガーン! とばかり高昌は馬鹿口を開ける。
「そっ……んな馬鹿な……ッてめえらだって知ってんだろうがよ、<三蔵は俺と>……!」
「たった一度の昔の話だ。言ったろう。<貴史は>、俺のものだ」
「……!」
高昌の震えが、怒りとは違うものになっていく。
「俺は……千三百年……」
正確には千三百五十四年、と正臣。
「……待ったのは俺も同じだ。あの方が生まれ変わるのをじっと待った。必死で捜した。八戒も同じだ」
秋生はどこか申し訳なさそうに、高昌にしがみ付いている。
「……大体、お前との一件が、あの方が憶えていたい事だと、本気で思ったか?」
「―――!」
高昌の体から力が抜ける。秋生がそっと高昌を見た。
ふう、と正臣は溜め息を吐く。
「……話は着いたな。行くぞ秋生」
「あ、ま、待ってえな、正臣はん!」
一人さっさと境内を出る正臣を呼んでおいて、秋生はもう一度高昌を振り向いた。
「……兄貴、あ、あんま、気い落とさんといてな。会えただけで十分幸せやん。凄い偶然やねんで? な」
高昌の返事はない。秋生は一寸口を結んで、もう見えなくなった正臣の後を追った。
高昌はその場に立ち尽くしている。烏が鳴いた。それが合図だったかのように、本堂から住職が現れた。
「高昌(こうしょう)。箒は直ったか?」
高昌は応えない。直された箒は、石畳に転がっている。
「……今来ておったのは友達かの」
「……ダチなんかじゃねえよ。あんな奴等」
小さく、答えた。
「一緒に闘った、戦友だ」
「……ほう」
今生の話ではなさそうじゃのう、和尚は、顎を摩ってそう言った。
良かったら聞かせい高昌、と和尚。高昌は振り向いた。
「うるせえ糞坊主。『こうしょう』って呼ぶな」
箒を拾って、本堂の裏へ回った。
*
(続く)