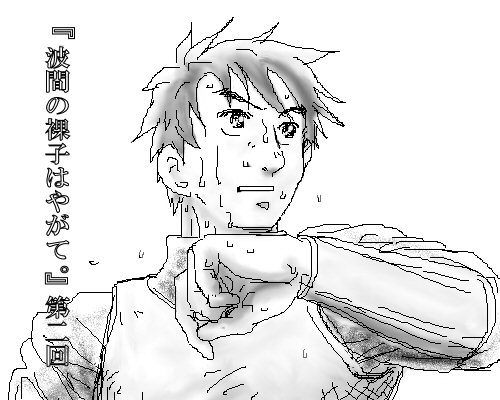
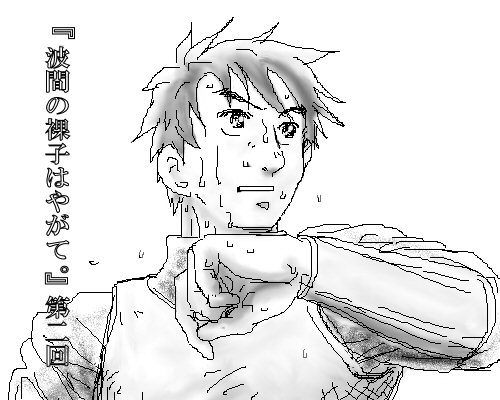
『辿り着いた島は、土豊かにして水湛え―――』
*
訓練場の空には、やがて中天に懸かろうかという太陽が燦と照り輝いている。
タルは剣を持たぬ方の手の甲で、顎まで垂れて来た汗を拭った。
「ふい~あっちー…」
午前の訓練がようやく終了したところである。
「ほんとに慣れんのかな? このあっちーのによ…」
誰にともなく呟いた愚痴を、先まで手合わせしていたケネスが耳聡く聞きつけた。
「着慣れないと、鎧はホントに暑いな。まあ、慣れなきゃ困るだろう。体力だって付くはずさ」
ケネスも、前髪を全て上げた額から、だらだらと汗が流れている。息もやや上がっているようだ。タルに比べたら、確かにケネスは、もう少し体力をつけた方がよさそうだ。
水分取っとけよ、と助言するタルに、ああ、わかってる、とケネスは軽く肯いた。
「お前もな」
そう言ってタルを指差す。
「あ?」
「午前の訓練が終わったってのに、メシって言わない。疲れてるだろ」
ケネスは自分の考えを述べるのに、その根拠になる事柄も常に頭にあるらしい。タルなら「なんとなく」で済むところを、いつもきちんと理由付けるのだ。
しかし、今回のそれは、実は少し違っていた。
今日は、ヒルダを昼飯に誘おう。
タルのその予定は入団以来毎日のことだったのだが、ヒルダはいつも、例のお屋敷の坊ちゃん、スノウにべったりで、騎士団での食事は常に二人一緒らしい。
ところが今日は、訓練途中からスノウが上官に呼ばれていて、訓練の邪魔にならぬよう、隅の方でまだ話の最中だ。
ヒルダは、少し離れた場所で、スノウを見て待っていた。
タルは剣を腰の鞘に収めると、ケネスにひらひらと手を振って、ヒルダの方へと歩み寄った。
「よ、ヒルダ」
ケネスは、ああ、という顔をした。この体の大きな同期生が、余り口を利かない、大人しい同期生にいつも何か言いたそうだと、気付いていたからだ。
「メシ、食いに行かないか」
「……」
言葉を発しないまま、タルを振り向いた後、ヒルダは、ちら、と目線をスノウへ滑らせた。
「……そっか。っていうかよ、おい、それでもわかるこたわかるけど、口で話せ?」
タルに注意されて、ヒルダは身を縮めた。
「いや……あー……参ったな……」
タルはがしがしと頭を掻く。
確かに、昔も、あまり喋る子供ではなかった。だが、ここまで言葉少なだったろうか?
ほんの1、2回会っただけで、判断するなと言われればそれまでだが。入団式で再会した時も、少なくとも、これよりは、ヒルダは話そうとしていたと思う。
まだ、昔の方が、表情があった。
「……せっかく教えた名前も、呼ばねえじゃねえか」
ぼそりと呟いた。ヒルダは、それに反応した。
「……ん?」
ヒルダはタルを見つめて、首を横に振っているようだ。
「なんだ?」
首を振る。
「……呼んでるのか? 名前」
ヒルダは俯いた。いや、頷いたのか。
ぽりぽりとタルは鼻を掻く。
「……そか。じゃ、呼んでみろよ?」
それでヒルダが口を開けば御の字だと、考えたかどうか。タルは腕を組んでヒルダが口を開けるのを待った。
「……」
「……」
「……」
……きりがない。
タルは諦めて、じゃ、また今度誘うわ、と踵を返した。
「……っタル!」
その背に、意外と通る声で自分の名をかけられた。
「……おう」
少し驚いて振り向くと、ヒルダは上気した顔をして、必死に息をしていた。
「……おい大丈夫か?」
こくん、とヒルダは肯く。肯いて俯いたまま。
「……タル。タル……、タル……」
堰を切ったように、名前を連呼する。
自分の腹の前でぎゅっと拳を握り、タル、タル、と繰り返す。
タルはさすがに、いたたまれなくなってきた。
「お、おい、わかった、もう、わかったから」
ヒルダは呼ぶのを止めて、タルを見た。また俯いた、その口が、笑って見える程に、嬉しそうに震えた。
名前を教えてもらったのが、そんなに嬉しかったのか。
「……な、なんか、こっちまで照れるな……」
間に困ったタルの耳に、呆れ声の助け舟がやって来た。
「お前らなにやってんだ……」
「おおっケネス! いいとこきた!」
船もひっくり返る勢いで、タルはケネスの腕を引っ掴む。実際ケネスは、引かれる強さに、踏鞴を踏んで転びかけた。
「おいヒルダ! こいつも呼んでやれ!」
にいっと笑ってタルはケネスを指す。
「はあ?」
ケネスは怪訝にタルを見上げたが、素直に肯き、ケネス、ケネス、とやりだしたヒルダに、面食らうことになる。
「……な、なんか……照れるな……」
「だろ?!」
得たり、と声を上げるタルに、ケネスは冷静に返す。
「お前(タル)に何度も呼ばれても、うっとおしいだけだろうにな」
「……それはあんまりじゃねえか?」
「なになに、なにやってんの~?!」
やってきたのは、同じくペアを組んで剣術訓練を行っていた、ジュエルとポーラである。
この面々が、入団式の時、タルと一緒にいた連中であり、その4人ともが、ラズリル出身ではないと、この数日で互いに知るところとなっている。
よそ者同士、という訳でもないだろうが、以来、よく一緒につるんで行動しているメンバーである。
額にナ・ナル島出身の証を刻んでいるジュエルは、面白そうなことを嗅ぎ付けるのが得意だ。ジュエルの後ろからゆっくりと付いてくるポーラは、この辺りでは珍しいエルフ種で、エルフにしてはまた珍しく、人間と会話するのを厭わないらしい。
呼んでやれ、と笑うタルの指に従って、ヒルダは、ポーラ、と呼び始めた。
「ポーラ」
「はい」
「ポーラ」
「はい」
呼ばれる度、微笑んで返事するポーラと、どうやら返事が嬉しいらしいヒルダの二人が、いつまで続けるのだろうとやや不安になった頃、
「はいはい!あたしもあたしも!」
ジュエルが元気よく挙手した。
「ジュエル」
「は~い!!」
ジュエルの返事の元気よさに、ヒルダが押される形で、一度で済んだ。
その顔がおかしかったのか、くっと笑って、「ヒルダ」とタルは呼んだ。
「はい」
タルは、変な顔をした。
「……お前の『はい』は、どうも痛々しくていねけえな」
顎を親指で擦るタルに、ケネスも同意する。
「同感だ。謂れない無理を強要してる気になる」
「……いやまあ、なんだかわかんねんだけども」
ちらりとこちらを見たケネスが、頭も筋肉か、と目で毒づいた気がした。
タルは構わず、思い付くところを提案してみる。
「おう、とか、なんだ、とか言ってみろよ」
ヒルダは、息を吸ったり吐いたりして、ようよう、真似てみる気になったようだ。
「…………お、お……」
なんだか、吐き気を我慢しているようだ。
「……ま、なんだ、そう構えんな」
「……うん」
「おっそれだ!」
ヒルダが力を抜いたところに、タルが、ばしん! と肩を叩くものだから。
ジュエルとポーラに向かって、ヒルダは堪えきれず、突っ込んでしまった。
「もー馬鹿タル力!ヒルダが壊れるでしょー?!」
ヒルダを支えながらのジュエルの非難に、口を曲げて主張する。
「壊れるかよ。こいつこれで、結構な一撃打つんだぜ、剣術でよ」
ヒルダは、照れくさいらしい。ぶつかった二人にごめん、と謝って、そんなこと、と小さい小さい声で、タルの賛辞を辞退した。
にいっとタルは笑う。
「さっきの、いい感じだぜ。おい、ヒルダ」
あっちのスノウも呼んでやれ、と上官と話しているスノウを指差した。
ヒルダは、途端に困った顔になる。ジュエルは、タルバカ、と決め付ける。
「今、スノウ、先生と話してるじゃん! 呼べったってさ!」
バカ呼ばわりされたことは流して、タルは瞬き、ヒルダに尋ねた。
「……ヒルダ? どうした?」
だーかーらー! とジュエルは腕を振り上げたが、ポーラに宥められ、収めた。横でケネスは、そこは引いてもいいだろうに、と言いたげだったが、黙っていた。
タルは手を膝について、ヒルダの答を待っている。
息を吸って、吐いて、ヒルダは、ぱくぱくと口を動かした。明らかだ。ヒルダは、長く話すことに慣れてない。
「……スノウ……は、同じ訓練生だから、坊ちゃんって呼ばなくていい、って、いってくれてるんだ。……だから、呼びたくなる僕が、いけないんだ」
答え終えて、静かに、長い息を吐いた。そうして、ごめん、と付け足した。
タルは膝から手を離し、体を起こす。にかっと笑った。
「……そっか。ま、じきに慣れるって」
右手で、ぐしゃぐしゃとヒルダの頭を撫でる。手の下で、小さく、ヒルダの頭が肯いたようだった。
「ふ~ん……」
人差し指を顎に当てて、ジュエルは感心したように口をすぼめた。
「そういえば、あんたラズリルに住んでないのに、よくスノウとヒルダのこと知ってたね」
領主の息子と、その小間使い。入団初日からそれを知っていたのは、彼ら4人の中ではタルだけだった。
「あ?」
振り向いたタルに、ジュエルが、すぼめた口を横に引いて、にまあっと笑う。
「その調子で、床屋の親父の浮気相手も知ってたりして」
「……はあ?」
ぽかんとタルは口を開く。ポーラが、薄く微笑んで、感想を述べた。
「少し話して気付きました。ジュエルはゴシップ好きです」
「ゴシップて……知るかよそんなん。俺はただ、ガキの頃ラズリルに来た事があるだけだって」
ジュエルは目をぱちくりとし、矢庭に手をポン、と打った。
「あ! ねえ、あたし、ちっさいあんた、見たことある気するんだけど!」
「おお、父ちゃんと貨物船乗ってたからな。ナ・ナルも行ったぞ」
「やっぱり!」
ケネスが見ていた。ヒルダの顔が、淋しげに翳るのを。
「……混ざりたければ、話せばいい」
ケネスはそっと話しかけたのだが、ヒルダはびくりとして、身を硬くした。
「―――ヒルダ!」
弾かれたように、ばっとヒルダは顔を上げた。いつの間に話が済んだものか、上官はスノウから離れて行って、スノウが遠くから、腰に手を当ててヒルダを呼んでいた。
ヒルダは物も言わずに駆け出した。スノウに向かって、一直線に。
同時にタルが声を上げたのは、スノウに向かってだった。
「おう! お前、いいとこあるんじゃねえか! 見直したぜ!」
走りながら、ヒルダはちょっと振り返った。口の横に添えた手を、高々と上げて、二人に向かって振るところだった。
「……は?」
胡散臭げにスノウは眉を寄せる。
先程ヒルダが言った、同じ訓練生同士だから、坊ちゃんと呼ばなくていい、という発言に対してだと、スノウには知る由もない。
「わけのわからないヤツだな、タルは」
すぐ傍まで来たヒルダにこぼしつつ、スノウはヒルダを従えて、訓練場を後にした。
「……」
「……」
振っていた手を下ろしたタルを、ケネスは観察する目で眺めた。そうして、タルにだけ聞こえる声で、ぼそりと言った。
「また持っていかれたな」
タルはぽりぽりと頬を掻いて、既に消えたスノウとヒルダを見送っている。ケネスも同じものを見るように、タルの隣で腕を組んだ。
「構うんだな、ヒルダのことは」
「……なんか、放っとけねえってか……うん。放っとけねえんだな。……」
「……わかるけどな。難物だぞ、あれは」
「……そうかなあ?」
実は、入団してから数日が経つのに、タルはヒルダと、まだまともに、きちんと話らしい話をした事がない。それでもタルは、スノウを除けば、ヒルダと一番、口を利いている人間なのであったが。
8年前は、どちらも幼い子供だった。それを覚えていて、育った姿を見分けてくれた、十分ではないか、と考えるには、タルは何かすっきりしない。
ジュエルが、ドン、とタルの背を叩いた。
「ご飯いこ! あっはは、ヘンなの! タルがご飯に誘われてる!」
見ると、ポーラとケネスも苦笑している。
「……おい、俺はそんなに食欲魔人か?」
3人一度に肯かれて、タルは反撃の台詞が出なかった。
*
『風、そよと撫で、陽はさんと照り―――』
*
ガイエン海上騎士団の砦の入り口は、大きな石の扉一つである。
昼も夜も、その扉は騎士団員によって守られている。右に1人。左に1人。
本当ならば、タルは明日の夜、朝まで寝ずの扉番のはずだった。夕方になって急に、今夜の当番が代わってくれと言ってきたのである。
一期上の先輩は、後輩のタルに手を合わせて拝んだ。
「ごめん、どーしても帰らなきゃならないんだ。ばあちゃんが、今夜がヤマだって」
いっすよ、とタルは引き受けた。ばあちゃん、山越えるといいっすね、と先輩の肩を叩いた。
もう1人は、訓練生じゃない、騎士様だから、と扉番交代時刻について伝えて、先輩は行った。よほど気が急くのだろう、宿舎に入るまでに、2度こけた。
夜も更け、タルは仮眠を取っていたベッドから降りた。同室の訓練生は高鼾の最中だ。
窓から星を見る。いい夜だ。時刻も、いい頃合である。
見張り番の二人は、同時に交代することはない。まずないことだしあってはならないが、寝こけていたり忘れたりして、交代要員が来ない場合は、迎えに行ってやらねばならない。どちらか1人が、必ず残るようになっている。特に夜は、二人いっぺんに眠くなられては困るのである。異常なし、という報告でも、二人一度に交代するより小刻みに入るのも、メリットである。
よいしょ、とタルは内心掛け声をかけて、砦の扉を押した。軽い扉ではない。守る為の扉だ、簡単に破られては困るのである。夜、人の出入りがなくなる頃に、仕掛けによって扉は一層重くなる。しかし開かなくても困る訳で。中途半端な扉だよな、と開閉する度、タルは常々思っている。だが、道具なしに1人で、しかも片手で夜のこの扉を開けてしまう人間も、そうそういないので、タルの心配は、あまり当たっていなかった。
騎士団の館の扉を内側から開けて外へ出ると、左側に、もう1人の立ち番の相棒が見えた。
あれ、と思ったのは、彼が着ている鎧が、訓練生のものだったからだ。タルに交代を頼んだ先輩は、騎士だと言ってなかったか。さては、もう1人の騎士も、タル同様の代わりを立てたのかもしれない。
松明の明かりが揺れて、立ち番の姿もゆらゆらとする。
「よろしくー、どうっすか、異常……」
扉の開く音でも振り向かなかった彼が、タルの声で振り向いた。
「……ヒルダ」
松明に照らされて揺れているのは、ヒルダだ。2、3度瞬いた後、タル、と呟いた。それから思い出したように、体をぴんと伸ばして、異常ありません、と右手拳を左胸につけた。
タルも、了解、と型通り敬礼を返し、自分の持ち場の右位置につく。そして、にっと笑って、左を向いた。
「なんかよ、やっと、まともに話できるな」
暗くて、松明の明かりは揺れる。俯くと、ヒルダの表情は見えなかった。
「……俺はお前と話がしたいんだけど……いやか?」
首を横に振った。
「そっか。……まあ、話くらい、サボったことにはなんねえだろ。ははは」
「子供の頃に……」
軽く目を開いて、タルは見た。ヒルダがすぐに話を切り出したのは、少し意外だったのだ。ヒルダは、変わらず俯いて、ぽつぽつと話す。
「船に、乗ってる時に会ったのは、僕だけじゃないんだね」
「……おう、そりゃまあ……そうだろ」
ヒルダの意図が読めなかったが、単純に、今近くにいるジュエルもそうだという偶然を語ったのだと思った。
「船であちこち行けばな。知らないヤツに大勢会う。後で、またどこかで会えるかってえと、また違う話だけどよ」
「どうして」
問いかけは、一息の間、途切れた。
「来なかったの」
ラズリルに。
あれから。
……ヒルダには珍しく、責める響きが潜んでいる。
タルは瞬いて、息を吐いた。頭を掻き、ちょっと、唇を噛んだ。
「……わりい。待ってたんだよな」
多分ヒルダは、こんな物言いの仕方を、誰にもしたことがないに違いない。
口にしたことを後悔するように、ヒルダは、どうやって取り消そうかと逡巡して見えた。
タルは、それを見ていなかった。いつかヒルダに会ったら話すつもりで、今までに何度か頭の中で繰り返したことを、初めて口にする。
「父ちゃん死んで、家を長く離れるわけに行かなくなったから、貨物船の仕事もやめて家の近所の鉱石の露天掘りを手伝ってた。船下りちまったから、ラズリルどころか、家と仕事場の往復ばかりで。そのうちチビども(弟たち)も働くようになったし、俺もちゃんとした仕事見つけねえといけなかったし。ただ遊びにラズリルに来る訳にもいかねえし。で、騎士団あるし、ちょうどいいかと思ってよ」
そこまで言って、大息を吐いた。思ったより澱みなく言えた。ちゃんと、ヒルダにも伝わっただろう。
考えることや説明することが苦手なタルは、一つ、大仕事を終えた気になっていた。
「……おとうさん、なくなったの?」
「ん? おう。……で、騎士団て、試験あるじゃねえか、入団に」
「手紙、……」
一瞬、ヒルダが自分に手紙を出したのかと思い、心当たりを大急ぎで漁ったが、よくよく考えれば、ヒルダは自分の名さえ知らなかったのだ。出せる訳がない。……同じく自分も、出せる訳がないのだ。
「……しょうがねえだろ、だって俺、字、書けなかったんだもんよ」
ヒルダは目を見開いた。
「え……」
「今は書けるぞ! 騎士団入るのに、勉強したからな!」
笑うなよ、と言って、タルはその辺の石を拾って、地面に自分の名前を書いた。自覚はある。悪筆だ。
だが、ヒルダの反応がない。笑うなよと言ったが、本当は、笑ってくれることを期待していた。
ひしひしと、罪悪感が、タルを締め上げる。
出た声は、なんとも情けなかった。
「勘弁してくれよ。来ただろ、ちゃんと。……遅くなっちまったけどよ」
「…………。…え?」
ヒルダは目を見開いた。
小石を持って、しゃがみこんで、ふてくされたように、タルはなんと言った?
ラズリルの騎士団に来たのは。
「……ぼ、くが……いたか、ら、……?」
「おう」
あっさりと返事する。
お前も入ってるとは思わなかったけどな。そう言って、タルは笑った。
「―――……」
小刻みに体が震えるのは、夜風のせいではない。海からの風は、然程冷たくはないのだ。
いや、むしろ、火照る体に心地よい。
なんともいえない、初めて味わう感覚だった。
自分だけのために用意された何か。
お前のために来たのだと。
松明に照らされて、ヒルダの顔は、笑って見えただろう。
火が揺れていてよかった。震えているのも、きっとわからない。
タルは再び石畳を見て、今度はヒルダ、と書いた。やはり、悪筆だ。
「……一本多いよ」
「え、マジで?」
「うん」
ヒルダもその場にしゃがんで、手近な石を拾った。そうして、足元にがりがりと自分の名を綴る。
「……お、そう書くのか」
それをタルが真似る。揺れる松明の明かりに目を凝らしながら、右と左のそれぞれの定位置で、二人離れて屈んで、書き取りを始めた。
かり、かり、がり、がり、と石同士が削れる音と、時折漏れる、くすくす、くっくっという可笑しそうな息の音が、ラズリルの海から吹く風に乗って、遠慮がちに響いた。
(続く)