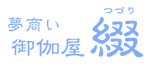
「こんちは」
カラカラと木戸の滑る軽やかな音と共に聞こえてきた馴染み客の声に、綴は吸いさしの水煙管を置いて艶やかな笑みを浮かべる。
「いらせられませ、ラズ様」
今日のラズの出で立ちは、見慣れた市井の若者のそれだ。
その意を正確に汲んで、綴は彼の望む名で呼びかける。
「その後、子供達の様子は如何ですか?」
「おかげさまで、今のところ問題ないよ」
桃花源教に拐かされた子供達は、エルマの夢を辿ったラズの記憶と蜻蛉の夢解きのおかげで無事に救出された。
暗示に使われた呪いの影響が危惧されていたものの、連れ戻された子供等はすんなりと家庭に馴染み、元通りの生活を送っている。
教団の人間も捕縛され、ラピスヴィナ公国での神隠しは一件落着といったところだった。
「生憎、蜻蛉は只今務めに就いておりますが…」
話しながらもきょろきょろと視線を彷徨わせるラズに気を回した綴が、少しばかり笑みを含んだ声でそう告げる。
「あぁ、うん」
ラズは、少々決まり悪げに苦笑しつつ、その日の来店の目的を口にした。
「今日は七星に会いに来たんだ」
「それは失礼をいたしました」
軽く目を瞠った綴が思い込みを詫びたところに、夢招きの匂い袋を並べた盆を手にした七星が現れる。
ラズは、七星の向かう先に歩み寄ると、彼女が商品を陳列し終えるのを待って傍に膝をついた。
そして、片腕に抱えていた飾り気のない桐の函を差し出す。
「七星、これを君に」
それは、先だって七星が桔梗の間に置いていった夢幻燈の入っていた小箱だった。
七星は、ラズに据えた双眸を不思議そうに瞬かせる。
「夢幻燈はラピスヴィナ公国の子供達の為に誂えたモノ。返却には及びまセン」
「うん、だからこれは、子供達から七星に」
そう言って、ラズは函の中から件の夢幻燈と良く似た大きさの灯篭を取り出した。
外張りの白紙に影絵を映し出すのではなく直接壁や天井に映像を投影する仕組みらしく造りはかなり簡素化されているが、夢幻燈と同じ回り灯籠の一種である事は見て取れる。
戸惑う七星の目の前で、ラズは灯篭に収められた蝋燭に火を灯した。
歯車が動き、高く澄んだ自鳴琴の音色に合わせて色とりどりのセロファンを張り合わせたシェードがゆっくりと回りだす。
揺れる炎に照らされた壁に映し出されたのは、子供達の日常だった。
ブランコや滑り台で遊ぶ子供達、母親に手を曳かれて辿る家路、夕餉の団欒、ベッドの中の我が子の額に口づけを落とす父親――他愛のない、けれど、かけがえのない光景。
「この曲は、ラピスヴィナ公国の子供なら誰でも知ってる子守唄なんだ」
自鳴琴が紡ぐ柔らかな旋律の謂れを告げて、ラズは壁の影絵を見つめる七星ににっこりと微笑みかける。
「七星のおかげで、彼等は大切な家族を失わずにすんだ」
だが、七星は、彼の賞賛と感謝を受け容れようとはしなかった。
「邪な術を破ったのは空蝉で、呪いを解いたのは蜻蛉。子供達の居場所を探り出せたのは、胡蝶の力添えがあったから。ワタシはただ器を作っただけに過ぎまセン」
舌足らずな声に似合わぬ素気無さで応える七星の生真面目な頑なさを溶かす為に、ラズは尚も言葉を重ねる。
「それでも、子供達が1番救われたのは、七星の紡いだ夢の優しさになんだよ」
まやかしに囚われていた子供達の心を最初に動かしたのは、夢幻燈の描く景色だった。
眠る事に怯えていた彼等がすぐに安らぎを取り戻せたのも、七星の見せた夢がぬくもりと希望を思い出させてくれたからだと、ラズは言う。
七星は、床の上で回り続ける灯篭に視線を落とす。
張り紙のところどころが縒れたり歪んだりしているのは、それが幼い子供達の手によって作られたものだからなのだろう。
そこから伝わる作り手の想いは、ラズの言葉が偽りでない事を物語っている。
ややあって、七星は、黒目がちの大きな瞳を僅かに細めてぽつりとこう呟いた。
「…ありがとう」
それから、顔を上げてラズに向き直ると、すいと握った拳を差し伸べる。
つられて差し出されたラズの掌の上で、七星はぱっと拳を開いた。
「これは…?」
ラズは、不思議そうな面持ちで首を捻る。
彼の掌に残されたは、雫形の針水晶だった。
「これは、想いと願いの欠片」
小さな結晶を光に透かしてみているラズの問いに端的に答えて、七星は謎めいた言葉を告げる。
「ワタシは、アナタを信じる」
透明な石の中で煌めく銀色の輝きに吸い寄せられるように見入っていたラズは、そこに込められた真意を量りかねたまま、その言葉を胸に刻み込んだ。
※※※
夢解き夢占夢違え、夢見合わせに夢詣で。
凡そ夢に纏わる万象に於いて右に出る者はないと評判の店、夢商いの御伽屋「綴」。
板塀に囲まれた広大な敷地に建つ木造平屋建ての古風な佇まいの、時に取り残されたような風情のその屋敷に、微かな変化の兆しが訪れようとしていた。
|