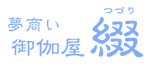
うっすらと霞みがかった木立に、哀感の漂う笛の音が響いていた。
空に焦がれる鳥の啼く声にも似た切ない音色を辿って歩を進めれば、白木造りの舞台が揺らめく篝火に照らされて暁闇に浮かび上がっているのが見えてくる。
「七星は容赦がないな」
口許に薄く苦笑を刷いて、空蝉は謎めいた呟きと共に秘かに嘆息した。
「聖皇様には、七星が紡いだ夢に来て貰うわ」
空蝉をこの夢に送り込んだ胡蝶は、夢訪いの段取りについてそう説明した。
「贈った夢は「幸せな記憶」。心を開く鍵になるものよ」
「綴」の斎子の中で最も幼く純粋な七星は、無垢であるが故に時に意図せずして残酷な事実を突きつける。
優しい筈の想い出がほろ苦い懐古と甘い疼痛を齎す――人の弱さから来るそんな心の機微を七星は斟酌しない。
「くれぐれも気をつけて。空蝉はあたしと同じで「人」に近いから蜻蛉相手の時みたいに神経質にならなくても大丈夫だとは思うけど…それでも、繋いだ糸を手繰れないほど深く他人の夢に囚われてしまえば、こちらに呼び戻せなくなってしまうのだから」
「…解っているよ」
念を押すように忠告して遣した胡蝶のいつになく真摯な面持ちを思い浮かべて、空蝉は気を引き締める。
これは、夢。還らぬ時を模した、偽りの世界だ。
手にした仮面を身に着け、空蝉は己を待つ舞台へと足を踏み出した。
※※※
「あぁ、懐かしいな」
夢現に木々の間を彷徨って来た青年が、目の前に開けた光景に目を細める。
「此処を訪れるのは随分久方ぶりだ」
其処は、鬱蒼と茂る杜の中にひっそりと建てられた神楽殿だった。
四隅に篝火を燈しただけの飾り気のない舞台には四方を囲む壁はなく、四本の柱に支えられた天蓋から下がる浄布以外装飾らしいものもない。
青年は、愛しむように欄干に手を滑らせながら、壇上へと続く階をゆっくりと上っていった。
青年の名は凌霄《リンシャオ》。
だが、今となってはその名を呼ぶ者はない。
鳳鸞教国の聖皇玉鳳――それが、現在の彼を語る名だった。
置かれた立場に相応しく、その装いは典雅なものだ。
立て襟を右脇で合わせた袍には金糸の縁取りが施され、艶やかな漆黒の生地には翼を広げた鳳凰の図紋が浮線綾で描き出されている。
だが、たとえ身に着けているのがありふれた簡服だったとしても、身の内から溢れ出る気品と立ち居振る舞いを見れば卑しからざる人となりは顕かになったことだろう。
絹糸の如き黒髪に縁取られた端整な白皙の面には未だ年若いといって良い年齢を越えた英邁さが見られ、穏やかな双眸には深い慈愛が宿っている。
生まれついての巫覡王、それが当代の聖皇を評して謳われる賛辞だった。
下手に設けられた囃子方の席と対を成す上手の高御坐に上った玉鳳は、懐から横笛を取り出すとそっと口をつける。
目を伏せ、深く息を吸い込んで気を静めた玉鳳は、かつて繰り返し奉じた神楽の曲を奏でだした。
高く澄んだ笛の音は、闇を縫って遠く響き渡る。
どれほどそうしていただろう。
ふと吹き抜けた風に淡い花の馨を感じて、玉鳳は僅かに瞼を上げる。
いつの間に現れたのか、仮面を被り、純白の狩衣を身に纏った少女が、舞台の中央に佇んでいた。
表情らしいもののない白い仮面の左頬には紅梅の枝が一振り描かれており、腰に佩いた太刀の鍔も雪輪に古木梅枝丸の意匠をあしらったものだ。
笛の音に誘われて地上に降り立った梅花の精。
そんな埒もない想像が、玉鳳の脳裏を過ぎる。
少女は、すらりと太刀を抜き放つと、玉鳳の奏でる笛に合わせて舞い始めた。
微かに戸惑いを覚えた玉鳳は、しかし、すぐに演奏に没頭する。
以心伝心、という言葉があるが、玉鳳の笛と少女の剣舞はまさにその域に達していた。
笛の音の強弱と舞の緩急は完全に調和し、円弧を描く動きは旋律をそのままなぞり上げる。
翻る太刀筋は鋭く通る音色と共に浄めの意志を表し、流れるような足運びは美しい調べに乗って荒ぶるものを鎮めていく。
不思議な事に、少女の振るう剣が風を斬る度に、大気までその色を変えていくかのようだった。
何かが劇的に変化したわけではない。
変わらず夜はすぐそこに在る。
ただ、重く蟠る不安と言い知れぬ恐怖が拭い去られ、安らぎだけが残されたような、そんな感触。
この静謐さこそが、夜本来の姿なのだろう…玉鳳は理由もなくそう思う。
終局に向けて、楽と舞いは益々共鳴を深めていく。
最後の音が暁降の空に尾を引いて消えた時には、彼等の精神は別ち難い程に溶け合っていた。
それは、玉鳳にとって覚えのある感覚だった。
太刀を鞘に収め、高御坐の前に膝をついて頭を垂れた少女に、玉鳳が躊躇いがちに声を掛ける。
「…梅琳《メイリン》?」
|