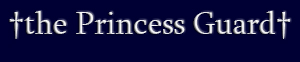|
無防備に佇む彼を絶好の獲物と見て襲い掛かってきた小鬼の群れは、光球に触れるとぱたりと動きを止めた。 一瞬の間を置いて、彼等は弾けて消える泡のように呆気なく姿を消す。 だが、際限なく現れる小鬼に対して、浄化の効力を持つ光の玉は無限ではない。 新たな光が生み出されるまでの僅かな隙を縫って、一匹の小鬼がランの背後に迫る。 それを鞭の一振りで叩き落して、ステラがランを怒鳴りつけた。 「隷属解除なんて悠長な事してる場合かよ!」 彼等を襲っている小鬼達は、元々少々邪で好戦的なところがあるものの、酷く臆病な種族でもある。 魅了を更に強めたアジールの隷属魔法により操られていなければ、彼我の実力差の大きいステラ達相手にこれほど無謀な攻撃を仕掛けてきたりはしないだろう。 だから、隷属命令さえ解除してやれば、大抵は自分達の住む世界へと逃げ帰るのだ。 「この数をまともに相手にするよりはましだろう」 「だからってなぁ!」 「しょうがないよ、ランは優しいもの」 左腕に装着した小型の折り畳み式ボウガンで自身は容赦なく小鬼達を射抜きつつ、ティアラが場違いなほどにほわほわした調子でそうフォローする。 月瑠家の魔導士は争乱を好まない。その事は、ステラも重々承知してはいるのだが。 「それで自分が危ないめにあってりゃ世話ないだろが!」 これで、敵の狙いがティアラやステラ達なら、ランは相手が何者でも躊躇いなく攻撃を仕掛けるのだ。 ちぃっと盛大に舌を鳴らして、ステラはランの背を庇う位置に回り込む。 彼が振るう炎を帯びた鞭と風の魔法を孕むティアラの矢は、正気に返っても尚戦意を失わずに向かってくる小鬼の残党を駆逐していった。 それでも、次から次へと湧いて出る小鬼の数の多さは、彼等を辟易させる。 アジール本人を抑えなくては事態の収拾がつかない事は解っていても、如何せんこう数が多くては雑魚の相手に手間取るばかりで決定打が繰り出せない。 「あなたは戦わないの?」 障壁に護られた結界の内側から戦闘の様子を焦れるような思いで見守っていたエヴァは、斜め前に立つルディの背中にそう問いかけた。 「お友達があんなに危険な目にあってるのに、此処で見てるだけなの?」 彼女にとっては、目の前で繰り広げられている光景は恐ろしく危険なものに見えるのだろう。 実際にはこれ以上の修羅場を何度も経験しているルディは、怯える彼女を宥めるように柔らかな表情で振り返ると、穏やかに応える。 「それが、僕の役目だから」 「役目?」 「戦う彼等の背後を護る事。保護すべき対象の安全を確保する事。僕には、その力がある」 訝しげに問い返すエヴァにそう応じて、ルディは再び戦場に視線を戻した。 甘やかな飴色の双眸は、揺るがぬ毅さを秘めてステラ達の戦いを映す。 「でも、その為には感情に任せて飛び出したんじゃ駄目だ。たとえ目の前で仲間が倒れていっても、最後まで結界を維持するのが僕の役目なんだ」 静かに語るルディの言葉に黙って耳を傾けていたエヴァは、結界を維持するルディの槍の柄を握る手に必要以上に力が込められている事に気づいた。 その手を見つめて、エヴァは我が身を振り返る。 自分の務め。 与えられた力とそれが齎すものに、目を逸らさずに向き合う事。 小さな頃から、エヴァの歌は特別だった。 心の病を癒し、苦悩と痛みを和らげるその声は、時に肉体をも癒す奇跡を惹き起こした。 エヴァの声が、強力な人外の者さえ惹きつけるのだと言ったアジール。 その力を我が物にする為に彼女を為に口説いたのだと…彼の優しさが夢魔の本性と手管でしかないのだと知った今、自分に出来る事は何なのか。 胸に下がった音叉のペンダントを強く握り締めて、エヴァはするりと結界を抜け出す。 ルディは、エヴァを制止しようとはしなかった。 大きく息を吸い込んで、エヴァは歌い出す。 列聖の儀式で歌う、天を讃える聖歌――厳粛な祝詞を理を紡ぐ旋律に乗せたその歌は、小鬼達を束縛する魔法を完全に打ち消した。 聖なる歌声を恐れた魔物の群れは、潮が引くようにその場から消え去る。 後に残されたのは、エヴァとステラ達4人、それに意外そうな表情で立ち尽くすアジールだけだった。 「エヴァ」 この期に及んでも、アジールがエヴァを呼ぶ声は甘い。 エヴァは、ともすれば揺らぎそうになる気持ちを叱咤して口を開く。 「ごめんなさい、先生。でも、私は私の務めを果たします」 それは、事実上アジールの魅了の魔法を打ち破る退魔の一矢となった。 「凄腕の夢魔の面目が丸潰れだな」 最後の最後で標的に拒まれるという予想外の事態に衝撃を受けるアジールに皮肉な台詞を投げつけたステラが、冷たく宣告する。 「消えろよ。もうあんたの出る幕はないぜ」 + + +
|