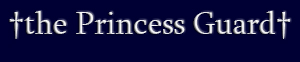|
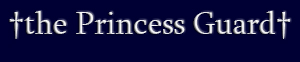
頬に飛んだ滴を拭った手の甲に残った赤い色を、ステラは何か不思議なものを見るように見遣った。
ぼんやりと視線を動かすと、床に倒れ伏したランの姿が目に入る。
彼のシャツの襟元は、溢れ出る鮮血で真っ赤に染まっていた。
白皙の肌は今や透けるように蒼褪め、それと対を成すように床の上には真紅の血溜りが広がっていく。
つい今しがたまでの鮮やかな戦いぶりが嘘のように静かな、それでいてショッキングな光景だった。
ステラの戦慄く唇から、知らず呟きが零れる。
「な…んだよ、これ…」
状況は明確だ。
風に乗って勢いのついた硝子の破片の1つが、防御を失ったランの頚動脈を掠めたのだ。
よろよろと足を踏み出しかけたステラの耳に、ルディの緊迫した声が届く。
「待って、ティアラ!」
ルディの制止を振り切って結界を抜け出したティアラは、振り向いたステラには見向きもせずに真っ直ぐランの許へと駆け寄った。
躊躇いもなく血溜りの中に跪くと、力の抜けたランの身体を胸に抱え起こす。
黒い制服の胸元は、大量の血にじっとりと濡れてすぐに色を濃くした。
「ラン?」
彼女の呼びかけに応えてうっすらと瞼を持ち上げたランが、微かに唇を震わせてきれぎれに何事かを囁く。
次の瞬間、ごぉっという音と共に、資料庫内に火柱が上がった。
「…不死鳥…?」
間近から吹きつける熱気と渦巻く魔力に圧倒されて咄嗟に腕で頭を庇いつつ顔を背けたステラは、呆然と呟くルディの声につられて火元を振り返る。
傷だらけのランの肢体をかき抱いたティアラを中心に、赤々と燃える羽根が火の粉のように舞っていた。
見上げれば、寄り添う2人を包み込むように、炎を纏った美しい鳥が大きく翼を広げている。
その姿は、確かに伝説の不死鳥フェニックスを髣髴とさせるものだった。
飴色の瞳を大きく見開いて呆然と立ち尽くすルディのチョコレートブラウンの髪が、金赤色の炎に照り映える。
「召喚士か!?」
驚嘆に喘ぐステラが見守る中、ティアラの身体から眩い光が放たれた。
視界を灼き尽くす閃光は、しかし、温かな波動となって触れる者を癒す力となる。
致命傷と思われたランの傷も見る間に塞がり、痕も残さず消え去った。
「凄ぇ…」
意識を失ったランの、幾分血色の戻った顔に頬を寄せて目を閉じたティアラをじっと見つめて、ステラは胸を高鳴らせる。
だが、彼の気分の昂揚は、単なる感動から来るものではなかった。
小さく拳を握った彼は、予想外の台詞を力強く呟く。
「…惚れたぜ!」
「は?」
いつの間にか隣に来ていたルディが呆気にとられた様子で訊き返してくるのに、ステラはにんまりと微笑んだ。
それから、収束しつつある光の中で折り重なるようにして眠るティアラとランに歩み寄る。
その頃になって、ようやくシェルアの派遣した救援隊が資料庫内へと駆け込んで来た。
+ + +
翌朝、司令部にある謁見室に呼び出された新入隊員は、各自属性と担当分野を示す紋章と貴石を授与された。
ステラは機知を表す【風】と精霊魔法の【火星】を、ルディは守護を司る【土】と風水術の【土星】をそれぞれ与えられる。
尤も、彼等の場合幼等部隊在籍時から適性も得手不得手もはっきりしていたので、仮の徽章がそのまま本決定になった形だった。
ティアラには、活力の【火】と召喚魔法の【金星】が授与される。
実のところ属性については未だはっきりしない面も多かったが、呼び出したのが炎の幻獣である不死鳥であった事と暴発ともいえるような魔力の発動の仕方から、とりあえず【火】の質と判断されたらしい。
最後に残ったのが、本年の主席入隊者であるランだった。
「君に関しては、我々司令部も少々判断に迷っている。そこで、君自身に選択を委ねようと思う」
新入隊員への徽章の授与を任された年少部隊副隊長のキーラムは、落ち着いた口調で騎士団としては異例の見解を口にした。
「属性は癒しを意味する【水】、これは君自身の本質から見ても決定と考えて良いだろう。問題は担当分野だ。神聖系魔法の【太陽】なら、すぐにでも司の位につける実力がある。何分、神聖魔法の使い手は人手不足なのでね」
そう告げるキーラム自身は、祈りと神聖系魔法を示す【闇の太陽】の徽章を身につけている。
鋼の鞭を思わせる長身痩躯の持ち主である彼が、戦闘を厭う傾向にある聖職系を専門にしているとは思えなかった。
武闘僧や神聖騎士という事も考えられるが、彼の言い分が強ち大袈裟なものではないのだと判断する方が自然だろう。
キーラムは、一瞬浮かんだ柔らかな印象の微苦笑を収めると、硬質な表情で残りの選択肢を提示する。
「だが、君にはもうひとつの可能性がある。単独の分野に偏らず、魔導全般を修める賢者――現在の年少部隊には存在しない【月】の魔導士としての素養だ」
魔法は、属性との相性や生まれ持っての素質に左右される部分が大きい。
一定以上のレベルですべての魔導を使いこなす「賢者」は相当特殊な存在だった。
だが、ランにはその素養があるというのだ。
「月瑠家の魔導士は、霊獣の加護を受けると聞く。それは召喚士としての素質を示すと考えて良いだろう。他の能力については今度の任務でその片鱗を見させてもらった。けして容易な道ではないが、君なら【月】を修める事も可能だと我々は判断している」
慎重に言葉を選んでいる感のあるキーラムの発言に、近くに控えているティアラがほんの少し不安げにランを見上げる。
そんな彼女とは裏腹に、ランは躊躇う事なくこう答えた。
「【月】を」
僅かに瞠目したキーラムは、賛嘆と慈しみの合い混じった眼差しを注ぎつつ務めを果たす。
「了解した。では、ラン=ユエルには【水の月】の徽章を授与する」
「やはり、彼は【月】を選んだか」
謁見室の片隅から徽章授与の様子を見守っていた年少部隊長シェルアは、誰に言うともなくそう呟いた。
「驚かないんだな」
彼女の傍で同じように2人の遣り取りに耳を傾けていたステラが、やけに気安い調子でそう問いかける。
シェルアは、幼等部隊の頃から目をかけている後輩に小さく肩を竦めて見せた。
「神聖系魔法を修めたいなら、何もわざわざLUX CRUXに所属する必要はあるまい。むしろ月瑠の家の方がよほど理想的な環境だろう」
ワケありというヤツさ、と嘯く彼女は、何やら隠された事情を掴んでいるようにも見える。
「ま、今年の新人は優秀で何よりだ」
それでも、それ以上は語らずににこやかに話題を打ち切ったシェルアに、ステラは疑いの視線を投げかけた。
「まさか、昨日の騒ぎはあんた達が仕組んだんじゃないだろうな?」
「私が好んで身内を危険に曝すとでも?」
一転して冷たい一瞥を投げかけられて、シェルアの人となりを知るステラは素直に謝罪する。
「…すまない。失言した」
シェルアは、ステラを責める代わりに彼女の懸念の一端を垣間見せた。
「魔物の中には、魔力の高い人間を殺してその力を我が物にしようとする者もあるらしい」
彼女の視線の先には、ランの隣で無邪気に笑っているティアラの姿がある。
「ただでさえ貴重な召喚魔法の使い手、それも、おそらくは契約を必要としない幻獣使いだ。月瑠家の前当主が守護についてるってのも頷ける」
2人は、暫くの間無言でそれぞれ物思いに耽っていた。
やがて、シェルアが気を取り直すようにステラに問いかける。
「で?わざわざ居残ってるという事は、私に話があるのだろう?」
ステラは、頭を振って思索の名残を振り払うと、真っ直ぐシェルアを見て用件を切り出した。
「パーティーを登録したい」
シェルアは、軽く眉を上げる仕草で先を促す。
「メンバーは俺とルディ、それから、ラン=ユエルとティアイエル=フューの4名だ」
「まぁ、予想はしていたがな」
ステラが挙げたメンバーに、シェルアは苦笑を洩らした。
ティアラはともかく昨日の今日でランがステラ達に気を許したとも思えないが、共に戦う事で互いの力を認めたと考えれば然程意外な話ではない。
ステラやルディの実力は、主席入隊のランと比較してもけして遜色のないレベルなのだ。
部隊全体の戦力を考慮すれば優秀な人材はバランス良く配置したいところだが、だからといて彼の要望を退けるつもりはシェルアにはなかった。
そもそも、LUX CRUXの任務にはパーティー単位であたる事がほとんどなのだ。ひとつくらい飛び切り有能なチームを作らせるのも悪くない。
「コードネームはどうする?」
パーティーの登録を認める事を前提としたその質問には、ステラと同じくその場に留まっていたルディが答えた。
「プリンセス・ガード、なんてどうかな?」
「ティアラが護るべきお姫様か?」
完全に面白がっているのが解る口調で尋ねるシェルアに、ルディは楽しそうに頷いてみせる。
「もちろん。だって、ステラってば彼女に一目惚れしちゃったんだもんねぇ」
「煩いっ!とにかく!幻獣使いなんて滅多にいないし、【月】の魔法使いがいると何かと便利だし、このメンバーなら最強パーティーも夢じゃないだろ!」
ティアラとランの仲を見せつけられる度に感じていたイライラの原因を今更ながら自覚したばかりのステラは、照れ隠しと八つ当たりから語気を強めて理屈を並べ立てた。
だが、ルディは全く意に介さないどころか、おっとりとした調子で更なる波紋を投げかける。
「でも、僕もティアラのコト、気に入っちゃったなぁ」
ぎょっとするステラを尻目に、ルディはにこやかに続けた。
「ランは当然彼女の騎士だし、なかなか的を得た名前でしょ?」
「確かに」
邪気のない表情で小首を傾げるルディに、シェルアは笑みを孕んだ声で同意する。
「尤も、姫君が最強という気がしなくもないがな」
自身も年少部隊最強の名を恣にしている彼女の台詞には、妙な説得力があった。
一瞬、ステラの瞳に早まったかという表情が過ぎる。
そんなステラに、シェルアはくつりと笑みを零した。
それから、シェルアは年少部隊長としてこう宣告する。
「良いだろう。プリンセス・ガードの結成を公認する」
こうして、彼等の運命の歯車は動き出した。
BACK <<< ◆ >>> NEXT
|