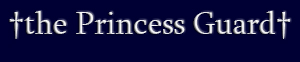|
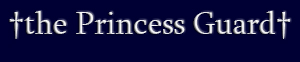
英国最古の学園都市オックスフォードからやや東に外れた緩やかな丘陵地帯に、魔導騎士団LUX CRUXの本部は存在する。
9月の北半球といえば残暑に見舞われる地域も多いが、暖流の影響で比較的温暖な気候に恵まれているとはいえ緯度の高いこの地には、早くも秋の気配が漂い始めていた。
多くの学園で新年度を迎えるこの時期に合わせて、魔導騎士団LUX CRUX年少部隊では入隊式が行われる。
下は13歳から上は19歳まで――実際には教育機関としての色合いの濃い幼等部隊からそのまま年少部隊に繰り上がる者が過半数を占める為、ほとんどが13、4歳の子供だが――の魔導の素養を持つ者が、世界中からこの日の為に集まって来るのだ。
今、慌しく身繕いをしているステラも、幼等部隊から持ち上がりの新入隊員の1人である。
ぴんぴんとあちこちに跳ねる癖の強い赤毛と格闘していたステラは、窓辺から聞こえてきたのんびりとした声にブラシを持つ手を止めて振り返った。
「ターキッシュアンゴラとロシアンブルーだ」
「えっ、どこどこ?」
「あそこ」
やや垂れ目気味の鮮やかなジャスパーグリーンの瞳をぱっと輝かせて窓際に駆け寄ると、声の主の視線を追って大きく身を乗り出す。
が、その先にある光景を目にした途端、ステラはがっくりとその場に座り込んだ。
脱力して窓枠に凭れかかった姿勢のまま、チョコレートブラウンの柔らかな髪を風に遊ばせている友人を上目遣いに見遣る。
「ルディ…俺には人間の女の子と男の子に見えるんだけど?」
「うん」
遠慮がちにそう指摘したステラに、ルディは素直にこっくりと頷いた。
彼が指し示した先では、プラチナブロンドの少女と黒髪の少年が石畳の櫟の並木道をゆったりとした足取りで歩いている。
あまりにあっさりと肯定されて、彼を見上げるステラの眼差しが少々恨めしげな色を帯びた。
だが、ルディはそれに気圧されるでもなく、黒目がちな飴色の瞳を笑みの形に細めて楽しそうに続ける。
「でも、なんとなくそんな感じでしょ?」
あくまでも無邪気に微笑むルディに毒気を抜かれて、ステラは深々と溜息を落として窓枠に突っ伏した。
+ + +
同刻。
「なぁに?」
ふっとすぐ近くで微笑む気配を感じて、ティアラは半歩後ろを歩くランの、頭ひとつ高いところにある瞳を覗き込んだ。
2人が歩いているのは、櫟の並木に挟まれた古い石畳の小道だ。
自然の趣きを残しつつ規則正しく並んだ木々の間からは、長い歴史を持つ名門大学の校舎といった感じの、どこかノスタルジックな雰囲気を醸し出す煉瓦造りの建物が遠く見て取れる。
ランは、青みがかった黒髪をさらりと揺らして小首を傾げると、優しくティアラに微笑みかけた。
「髪、綿菓子みたいだなと思って」
そう言って、眩しそうに目を細めつつ、木洩れ日に煌くティアラの髪の一房をそっと手に取ってみせる。
品の良い端正な顔立ちのランには、ちょっとばかり甘く気障な立ち居振る舞いや古風な景色が良く似合う。
その彼の言う通り、ふわりと風にそよぐティアラの髪は羽根のように軽く雪のように色が淡くて、確かに見る者に綿菓子を連想させた。
だが、本人はどうやらまったく自覚がないらしい。
「そぉかなぁ?」
大きなメイプルシロップの色の瞳をぱちくりとさせて、ティアラはあどけない仕草で首を捻る。
そんなティアラに、ランは秘色と呼ばれる蒼翠の瞳に極上の笑みを湛えてこう告げた。
「蜂蜜がけの綿菓子みたいに、ふわふわできらきらしてる」
「そっか」
向けられた笑顔も、幼い子供に語りかけるような声も、どこまでも優しく柔らかい。
それが嬉しくて、ティアラも幸せそうににっこりと微笑み返した。
+ + +
「…気に入らないな」
未だ窓枠とオトモダチになったまま、ステラはぽつりとそう呟いた。
彼の視線は、遠くから観察されているなどとは知る由もなく仲睦まじく並木道を行く少女と少年にむけられている。
膝の上のペーパーバックに興味を移したルディは、素っ気無い調子で疑問を呈した。
「そう?お似合いだと思うけど?」
確かに、並んで歩く2人は、まるで白と黒の一対として誂えられたかのように似合いのカップルだ。
それが気に入らないと、自分でもはっきりとした理由が解らないままステラは思う。
しかし、悠長に物思いに耽っていられたのもそこまでだった。
パタンと音を立てて本を閉じたルディが、取り立てて急かす風もなくこう尋ねてくる。
「ところで、そろそろ出ないと間に合わないんじゃない?」
「げっ!」
つられて時計に目を遣ったステラは、針の指し示す時刻に呻き声を上げた。
慌てて身支度を再開した彼の耳に、ルディののほほんとした声が聞こえてくる。
「入隊式早々遅刻はやだよね」
「そう思うんなら早く言えって!」
運命の日の朝は、ステラの怒声で幕を開けた。
BACK <<< ◆ >>> NEXT
|