あなたはご存じだろうか、エルドランという島を。
遠い海の遙か彼方に、その島はあるという……。
爽やかな風に乗って、小鳥たちのさえずりが朝のルザイアを抜けていった。四つの小さな影は大通りに沿うように飛び、大きな屋敷の屋根に立つ風見鶏の脇をすり抜け、大空へと舞い上がっていく。
小鳥たちの影は、眩しい朝日にゆっくりと飲み込まれていった。雲一つ無い、まさに快晴の青空である。
夜の闇と静寂は、東からやって来る朝の光と共に西の空へ消えてしまった。
朝は、昇る太陽の光りが告げていく。
朝日に照らされたルザイアの大通りは、一日の始まりを待ちわびたように、人々の息吹が感じられた。
旅籠の若い女将は、箒を手に店の前をシャッシャッと掃いていく。パン屋の太った主人は、出来たての丸いパンを店先の籠に入れていく。庭の花壇に水をやっていたおばさんは、勢い余って通りの方まで水を飛ばしてしまい、ポニーテールの少女と一緒に歩いていた不運な少年の靴に水をかけてしまう。
いつもの朝。変わること無い日常の風景の中を、一台の馬車が石畳の大通りをカタカタと音を立てて過ぎていった。
隊商(キャラバン)が荷物を運ぶための馬車ではなく、貴族が乗るような、豪華に飾られた馬車だった。馬車を引く黒毛の馬にも、どこか気品のようなものが感じられる。
その馬車は、大通りの先にある白い建物の方に向かって進んでいた。
その建物は、この町の若者達が学ぶ「王立アカデミー」である。
その名の通り、「王立アカデミー」はこの島を治めるエルドラン王国が設立した学校である。
もちろんこの王都ルザイアには「王立アカデミー」の他にも学校といえるものはあり、例えば知識人が個人的に開いている私塾などがある。
だが知識人の私塾は限りがあるし金もかかる。そこで王国が、若者にも広く教養を身に付けられるにと設立したのが「王立アカデミー」なのだ。
エルドランは大陸から遠く離れた小さな島国のため戦乱は滅多に起こらず、自然と文化が発達してきたことも背景にある。
この王都ルザイアには街の西と東に一つずつ「王立アカデミー」があり、太陽の昇る東の学校をその神の名にあやかり「アポロン校」、西はその兄妹神である「アルテミス校」と呼ばれている。
馬車が向かっているのは、西の「アルテミス校」である。
「お嬢様、まもなく到着いたします」
馬車の御者を務めていたフランケンシュタインのような大男が振り返り、馬車の中に向かって声をかけた。
馬車の中からは、「分かったわ」と少女の声が帰ってくる。お嬢様と呼ばれる割には、どこか上品さが欠ける言葉遣いであった。
馬車の中の少女は、小さな宝石を散りばめた値の張りそうな手鏡を片手に、眉の辺りまでおろした前髪の具合を確かめていた。
少女の名前はエレウシアという。この街の大商人、ゲイルードの一人娘である。
「お嬢様」
外からフランケンが続けて声をかける。
「夜は大切なパーティーが開かれます。忘れてはいらっしゃいませんよね?」
「忘れるわけないでしょ。あたしだって楽しみにしてるんだから」
その言葉通り、鏡に映るエレウシアの眼が一層輝きを増し、すうっと細くなった。
「今年は優勝できるとよろしいですね」
「あったり前じゃない」
手鏡をパタンと音を立てて閉じたエレウシアの瞳には、闘志が溢れていた。
「そのために毎日お稽古を続けてきたんだから。今度こそ優勝して見せるわ」
今夜、エレウシアの屋敷ではダンスパーティーが開かれることになっていた。
そのダンスパーティーは、ある双子のダンサーの命日に開かれる。今なおその名が伝えられるその兄妹にちなみ、パーティーでは同じく男女がペアとなってダンスを披露し、どのペアが一番のダンサーかを決めるのだ。
この街では、年に一度行われる最大のダンスパーティーである。
ちなみにエレウシアは、まだ優勝したことがなかった。伝説の兄妹の再来とまで言われる兄妹に、いつも優勝を奪われているからだ。
「今回は招待したダンサーも増やしたと聞いていますから、まだ世に隠れたダンサーも出てくるかも知れませんよ」
「ふふっ、面白いじゃない」
「自信満々ですね。狙いは優勝の賞品のみですか?」
「賞品より名誉よ。ルザイア一のダンサーの称号は、必ずあたしが貰うわ。なんたってあたしのお屋敷で開かれるんですもの。優勝すれば、きっとお父様も喜んでくれるし」
「左様ですね。わたくしも陰ながらお嬢様の優勝を祈っております」
そんな会話を続けているうちに、馬車は校門の前までたどり着いた。大きく開け放たれた校門から、校舎に向かってに一直線に道が延びている。登校時間を迎えた校門は、制服を着た学生達で賑わっていた。
そしてその途中に、一つの大きな石像があった。ちょうど生徒達の背と同じぐらいの台座の上に立つその石像は、大人がゆうに二人分はありそうな程の高さである。
その石像は、一羽の羽根を広げた鷹であった。その姿は、今まさに大空に飛び出そうかという鷹の勇姿と躍動感を備えている。
そしてその頭上には、アルテミスを表す丸い月を戴いていた。東のアポロン校の鷹は、言うまでもなく太陽を頭上に戴いている。
鷹は「王立アカデミー」のシンボルであった。アカデミーで学び、鷹のように羽ばたいて欲しいという意味が込められているという。
この学校の制服にも、意匠化して鷹が刺繍されている。
「じゃあ、行ってくるわね」
フランケンに声をかけ、エレウシアは馬車から降りた。朝の日差しを浴びて、エレウシアの金髪が輝きを増す。
(さあ、今日も面白くなりそうね)
心の中でエレウシアは呟く。そんな彼女の表情は、自慢の金髪よりも一層輝いていた。
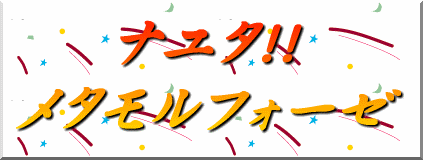
第4笑・一流ダンサーに……なれるかな(^^;①
1
「ひどいよ、あのおばさん……」
教室に入るなり、ナユタの第一声がこれだった。
「相変わらずナユタも運がないわねぇ。朝から水をかけられるなんて」
同情するようにサヤカが答える。
一緒に登校してくる途中で、大きな花壇のある家の側を通ったのだ。その花壇におばさんが水をやっていたのであるが、手元が狂ったのか、たまたま花壇の側を通りがかったナユタの方まで水を飛ばしてしまったのである。
「ホントだよ。この靴、買ったばかりだったのに」
と言って、ナユタは新品の靴を見やった。水に濡れて足に張り付き、グショグショと気持ち悪い。
「あのおばさんも悪かったかも知れないけど、ナユタだってボ~っとしてたじゃない。朝から話しかけてもあくびしか帰ってこないし」
「仕方ないだろ、朝早くから起こされるんだから」
「起こされるって、ナユタは独りで住んでるじゃない。誰に起こされるよ?」
「誰って……」
ナユタは言葉を詰まらせた。頭の中には、寝ている最中にボディアタックを見舞ってきたナインテールの顔が浮かんでくる。ナインテールのせいで、いつも中途半端な時間に起こされるのだ。
「うちにはタチの悪い妖怪が住み着いてるんだよ……」
ナユタはため息混じりに答えた。
「妖怪って、この妖怪?」
そう言って、サヤカは両肘を曲げて手をぶらぶらとさせた。いわゆる、ヒュ~ドロドロと現れるお化けのポーズである。
「まあ、そんなもんかな。うちに住み着いてるのは動物の妖怪だけど」
「ナユタ。人生捨てちゃダメよ。いくら運がないからって、妖怪のせいにするなんて」
「い、いや。別に捨てちゃいないよ。実際に僕には見えてるし」
「ああ…、おかしなキノコをやけ食いして幻覚を見ているのね。ナユタがそこまで悩んでいたなんて……」
「冗談だよ、冗談。うちに妖怪なんているわけないじゃないか。ははっ……」
心配してくれるのは有り難いのだが、サヤカの心配は時として突拍子もなく飛躍することがある。まるで我がことのように悲痛な表情を浮かべるサヤカに苦笑いを浮かべ、ナユタはカバンを机の上に降ろした。
教室には長い机が横に3列になっていくつか並んでおり、生徒は好きな場所に座って授業を受ける。だから自分の席というものは基本的にないのだが、それでも自然とよく座る場所というのは決まってくるものである。
ナユタとサヤカは、廊下に面した右側の列の、前から5番目にあるいつもの席についた。
教室の中には、すでにほどんどの生徒が登校していた。
机に座って一時間目の授業を始める生徒、友達同士集まっておしゃべりをする生徒、教室で飼っているエリマキトカゲに餌をあげる飼育係の生徒など、いつもと変わらない休み明けの教室の光景が広がっていた。
そしてまた一つ、日常の光景が繰り広げられることになる。
「やばっ、一時間目の宿題忘れた!」
悲鳴を上げたのは、’ミスター不運’ことナユタである。
「えっ!? 一時間目の授業って、フェルマー先生の授業じゃない」
横にいたサヤカが驚きの声を上げた。
フェルマー先生は、生徒指導も担当しているひじょ~に厳しい先生である。おまけに筋肉ムキムキマンで頭はツルピカハゲ丸君なので、生徒達の間では’金剛’と呼ばれ、同時に恐れられている。
「どうしよう、もう授業が始まるまであまり時間がないし……」
「もぉ~、しょうがないわねぇ……。どうしてすぐにやっておかないのよ?」
「いや、まだ時間があると思って……」
人間とはそんなものである。宿題なんて、直前になってやればいいと。しかしドジ男の場合は直前になっても宿題をやることを忘れ、このザマだ。
「昨日はお休みだったんだから。宿題を忘れたなんて言ったらなおさら怒るわよ」
「でも、昨日はピクニックに行ってたわけだし。サヤカだって知ってるだろ?」
そう。ナユタとサヤカは、前の日にピクニックに行っていたのだ。そこで様々事件に巻き込まれたのだが、ナユタのドジぶりとサヤカの勇敢な姿は前回の物語に譲るとしよう。
「そんなことフェルマー先生に関係あると思う?」
「…………関係ない」
ノミのため息ような声だった。
「たぶん、罰は決定ね」
「…………」
前に宿題を忘れたときは、中庭にある鷹の石像を掃除させられた。あの大きな石像を、たった一人でだ。
命綱一本で石像の上から吊され掃除をしたのであるが、さすがは’歩く災難’の異名を持つナユタである。やってくれる。
バケツに入った汚れた水をこぼすわ、どこからかやって来た鳥にフンをかけられるわで、せっかく綺麗にした部分をまた掃除しなくてはいけなかったんだ。
終いには命綱に絡まって身動きがとれなくなり、様子を見に来た金剛がいなかったら、無様な姿のまま朝の登校時間を迎えていたことだろう。
全身の血が抜けていくような感じがして、ナユタはミイラになって固まってしまった。
と、二人の後ろから何やらハミングが聞こえてきた。
「ルン、ルル、ル~ン♪ ラン、ララ、ラ~ン♪ タ~リラ~リ、ルレル~ル~♪」
リズム感も結構あって、なかなかのハミングであった。その声に気が付き、サヤカが振り返る。
「あっ、エレウシア。おはよう」
「おはよう……」
ナユタもミイラ化したまま振り返る。
「おっはよう、お二人さん」
エレウシアがカバンを持った右手を上げて挨拶をする。彼女が持っていたカバンは、まるで測ったかのように一人の男の顔面に向かっていった。
そして……
ドオッ!
タイミング、音、勢い、すべてが申し分なく、見事なまでにナユタの顔面にクリーンヒットした。
「な~に朝からミイラになってるのよ、ドジタ。素晴らしい一日の始まりよ、シャキッとしなさいよシャキッと」
鼻っ柱を押さえるナユタを気に留めることもなく、エレウシアは二人の前の席にカバンを降ろした。そこが彼女のいつもの席なのである。
ちなみにエレウシアは、ナユタのことを「ドジタ」と呼ぶ。
理由は言わずもがなであるが、ナユタが初めてエレウシアと会ったときに、ナユタは制服のボタンを一つずつ掛け違えていたのである。それ見た彼女の第一声が、
―ナユタ? 変な名前ね。ドジタって言う名前の方がよっぽど面白い。
だった。
以来エレウシアは、一度もナユタの名前を言ったことがない。
「今日はずいぶん機嫌がいいじゃない。何かあったの?」
なおもハミングを続けるエレウシアに、サヤカが訊ねた。
「ふふっ、よくぞ聞いてくれたわね」
待ってましたとばかり、エレウシアは満面の笑みを浮かべる。
「今日の夜、あたしのお屋敷でダンスパーティーが開かれるのよ。ある双子の兄妹の命日にちなんで行われるダンスパーティーなんだけど、え~っと、名前は何て言ったかな……」
名前を思い出そうと必死に頭を回転させるエレウシア。そんな彼女の横から、まるで神の啓示のように突然声がした。
「兄の名はナユラ。そして妹の名はリサ」
いとも容易く名前を答えた少女は、いつの間にかナユタの席から通路をはさんだ隣の席に座っていた。
「あっ、レア」
彼女の名前はレアという。栗色の髪を肩の辺りまで伸ばし、伏し目がちに本を読んでいるその表情には、どこか影のようなものがあった。
「今から二十年も昔、その兄妹はあるダンスパーティーに参加しようとしていたわ。当時は『神の踊り手』とまで称賛された最高のダンサーだった。でもその途中で盗賊に襲われ、彼等は殺されてしまたの。悲劇のダンサーとして、今なおその名が伝えられているわ」
「さっすがレア先生。そうそう、兄の方がなんか間抜けな名前だったのよね。誰かさんに似て」
感心するように何度も頷くエレウシアの言葉にも、レアは何事もなかったかのように難しそうな本に視線を落としたままであった。
「で、そのダンスパーティーで誰がルザイアで一番のダンサーか決めるの。これがワクワクせずにいられる?」
まるでお祭りの朝の子供のように、エレウシアは瞳を輝かせた。
「へぇ~、パーティーと一緒にコンテストもやるだ」
サヤカの頭の中には、きらびやかなドレスを身にまとった貴婦人と、黒いタキシードに身を包んだ紳士が、軽やかに踊る姿が浮かんできた。
「いいなぁ~、女の人はみんな素敵なドレスを着てるんでしょ?」
憧れるような視線で、サヤカはうっとりとする。
「まあね。サヤカだってお化粧してドレスを着れば十分通用するわよ」
「えっ? わ、私なんかどんなに高いドレスを着たって似合わないし」
サヤカは激しく右手と首を振った。
「あのね、高いドレスを着たって要は中身よ。どんなに高価な物で着飾ったって、それが本人と合っていなかったら綺麗だとは言えないわ。サヤカに一番似合うドレスを着れば、絶対綺麗になれるって」
「そ、そうかなぁ」
頬に手を当てて顔を赤めながらも、サヤカはまんざらでもない表情だった。
「サヤカだったら、落ち着いた色のドレスの方が似合ってそうね。水色のドレスなんてどう?」
「水色ねぇ…」
頭の中の自分に、まず水色のドレスを着せてみる。
「サヤカだったらあまり指輪とかは付けない方がいいかもね。胸元の目立つところにブローチでも付けてみたら?」
「うんうん…」
「ポニーテールは解いてそのまま後ろに流してみたら? サヤカはストレートも似合いそうだし」
「うんうん…」
頭の中の自分が、どんどんとお嬢様に近づいていくような気がした。それからも二人は、ああでもないこうでもないと話を続ける。
一方のナユタといえば、そんな女の会話には付いていけるはずもなく、二人の話をぼんやりと聞きながら授業の準備を続けていた。
しかしそんなナユタの耳に、ふと次のような言葉が聞こえてきた。
「でも、コンテストなら賞品とかもあるの?」
サヤカの声だった。
「まあね。優勝者には賞品が贈られるわ」
(んっ、賞品?)
その言葉に、ナユタは即座に反応した。
「そ、それって本当!」
「な、なによ急に」
突然話に割り込んできたナユタに、エレウシアは思わずたじろいだ。
「賞品が出るって、本当?」
「本当よ。たぶん高価な宝石なんじゃないかな」
「高価な宝石かぁ……」
’超’という文字が神輿(みこし)を担いで行列を作りそうなほど金持ちのエレウシアが高価というぐらいなのだから、きっとぶっ倒れるほど高価な宝石に違いない。ナユタは意を決し、どれほど高価なのか聞いてみることにした。
「ちょっ、ちょっと聞いてみて良いかな? 値段にするとどれぐらいなの?」
「値段? そうねぇ……」
エレウシアは顎に手を当てて、考え込むように天井を見上げた。
ややあって、エレウシアが僅かな笑みを浮かべてこう答える。
「ふふっ、ざっと一千万ゴールドぐらいかしら」
一千万ゴールドといえば、ルザイアでは曾孫の代まで遊んで暮らせるほどの金額である。
「いっ、一千万…うわあっ!」
途方もない金額に、ナユタは椅子から「ガタン!」と転がり落ちた。更にその途中で足を机に引っかけ、用意していた教科書がバタバタとナユタの頭の上に落下してくる。
「痛ててて……」
床の上で、ナユタは顔をしかめて頭の上を押さえた。そんなナユタに、サヤカの緊張した声が飛ぶ。
「ナユタ、上っ!」
「へっ?」
サヤカの声に、ナユタは上を見上げた。
ナユタの視線の先にあった物は、堅い角を下にして落下してくる自分の教科書だった。
「マジで……」
ガツッ!
声にならない悲鳴を上げ、ナユタは一瞬固まる。そして、ボロボロと崩れ去っていった。
「はははっ、じょ~だんに決まってるじゃない。珍しい宝石って聞いたから、高価な物なのかなって思っただけ。どれだけ値打ちがあるのかは、あたしだって知らないわよ」
「で、でも賞品がでることは間違いないんだよね?」
ひっくり返った椅子を元に戻し、ナユタはおでこをさすりながら座り直した。
「らしいわね。それがどうかしたの?」
「いや、別にどうしたってわけじゃないけどさ。ところでもう一つ聞きたいんだけど、パーティーっていうぐらいだから、豪華な食事も出るんだよね?」
「さっきから何なの? それはお食事だって用意するわよ。ダンサーだけじゃなくて、貴族や富豪だって来るんだから」
「そうか。ふふっ、ありがとう」
またとないチャンスであった。そのダンスパーティーとやらに参加して賞品の宝石を手に入れれば、膨大な借金の返済の足しになるだろう。一番の問題は、あのわがままな妖怪がはたしてダンスパーティーに興味を示すかどうかであるが、乗り気にさせるためのエサも先程確認した。少々ひねくれてはいるが単純な性格だから、必ずやうまく行くことだろう。
「あんた、もしかして今夜のダンスパーティーに参加したいなんて言わないわよね?」
「誰でも参加できるんじゃないの?」
「ははっ。そうねぇ……、一つだけ条件があるんだけど」
エレウシアが目を細めてニタリと笑う。
「えっ、何?」
例え賞品が出ようが、参加できなければ意味がない。一体どのような条件なのか、ナユタにとっては大いに気になるところであった。
「ドジで間抜けな男は参加できませんっていう条件があるの。あははっ」
「…………素晴らしい条件だよ。まるで僕のために作られた条件だ」
快晴だったナユタの表情が、一気にどんよりと曇った。
「ちゃんと招待状を配るのよ。なんたってルザイア一のダンサーを決めるコンテストですもの。ちゃんとしたダンサーにしか招待状は送ってないらしいわよ」
今夜のダンスパーティーは、貴族も参加するそれなりに格式のあるものなのである。ど素人が気安く参加できるようなコンテストではないのだ。
「それにあんたみたいにトロい男がダンスなんて踊れるわけないでしょ。ステップを間違えて、躓いて、転んで、無様にひっくり返るのがオチじゃない」
「いえ、きっとそれだけじゃないわ」
エレウシアの言葉に、サヤカが口を挟んだ。
「躓いた拍子に足首をひねって、転んだ拍子におでこをぶつけて、ひっくり返った拍子に相手の女の人のヒールでお腹を踏まれるかも知れないわ。ナユタ、やめておいた方がいいわよ」
サヤカなりに心配しているのだろうが、ナユタの心には十本ほどの矢が突き刺さった。
「そういうこと。諦めなさい、ドジタ」
「うう~」
エレウシアがクルリと背を向けて席に座る。遠くで始業のベルが鳴り始めていた。
何とかしてダンスパーティーに参加できないものだろうかと、ナユタは考えた。変身すれば自分だってダンスを踊れるであろうが、問題は招待状がなければダンスパーティーに参加できないことである。自分のところに招待状が来ることなんてまずあり得ないだろうから、自分で手に入れるしかない。
しかし良いアイデアを出そうとしても、蜘蛛の巣がはったナユタの脳味噌では、耳から埃を出すのが精一杯であった。
(しょうがない。とにかくナインテールに相談してみよう)
そんな風にナユタが諦めかけた時、チャイムが鳴り終わるのとほぼ同時に、教室の後ろのドアから何かが投げ込まれた。その白い塊は一直線に飛んでいき、
バフッ!
とナユタの後頭部に直撃した。
「痛てて。何だぁ?」
床の上に落ちていたのは、四角く折り畳まれた白い胴着だった。名前のところには、”クリス”と書かれている。
クリスとは、彼もまたナユタのクラスメートである。剣術部に所属し、アカデミーでも随一の剣技を誇る。だがアカデミーでも随一の遅刻常習犯であり、またアカデミーでも随一にナユタの災難を喜ぶ。
「へへっ、ギリギリセーフだぜ」
安堵の表情を浮かべてクリスが教室の中に駆け込んできた。
クリスは炎のように赤い髪をツンツンに逆立て、制服の袖を肘の辺りまで捲っていた。彼のいつものスタイルである。
なんとか遅刻せずにすんだと安心し、クリスはエレウシアの隣の席に着いた。そこが彼のいつもの席なのだ。
だがそんなクリスのもとに、教室の床を踏み抜かんばかりの勢いで金剛が歩み寄っていった。岩石のようないかつい顔が、まるで溶岩のように真っ赤になっている。
「何がギリギリセーフだクリス! チャイムはもう終わっていたぞ! 完全に遅刻だ!」
「なっ、何だと~!」
クリスの叫び声は、まるで雷鳴の轟きのようであった。隣のエレウシアが迷惑そうに耳を塞ぐ。
「どこ見てんだ金剛! 俺の胴着はちゃんと教室の中にあっただろうが!」
「お前自身は教室の中にいなかっただろうが!」
「なに言ってやがる! あの胴着は俺の命に次に大事なものだ! いわば胴着と俺は一心同体! 胴着があったっつ~ことは、俺が教室にいたのと同じだ!」
「屁理屈ぬかすな! 校則にも席に着いてなければ遅刻とあるだろうが! 一心同体とやらの胴着は床に落ちてたじゃないか!」
「あ、あれは……」
クリスが床に落ちている自分の胴着に視線を落としたとき、彼の後ろにいたナユタの視線とぶつかった。
「…………」
「ん??」
クリスが何も言わずにじっとナユタを見つめる。
運動神経は抜群だかおつむはからっきりダメという典型的なスポーツ馬鹿のこの男だが、唯一頭が猛烈に回るときがある。それは、ナユタをからかう時だ。
「あれはナユタが邪魔したからだ! あんなところにナユタの頭がなきゃ、俺の胴着はちゃんと席に着いていた! 悪いのはナユタだ!」
「ええ~!」
いきなり罪をなすり付けられ、ナユタは目玉を飛び出さんばかりの勢いで驚く。
「なに? ナユタが悪いのか?」
金剛がギロリとナユタの方を睨んだ。物語で見る悪魔よりも恐ろしい眼光だった。この睨みで泣かした女生徒の数は、千人を下らないと言われている。
「ちょっ、ちょっとフェルマー先生ぇ~」
あんな理不尽な理由で罪なったら、冤罪もいいところである。
「は~はっはっ、嘘だ嘘。悪いのは全部クリスだ。お前に罪はない」
「は、はい~……」
ヘナヘナと全身の力が抜けていくナユタの肩を、金剛は「がははは」と笑いながら叩いた。
まるで山賊の頭のような笑いだと、ナユタは心の中で思った。豪快に笑い続ける金剛の姿が、熊の毛皮を纏った大男の姿とダブっていく。
「クリス! お前は罰だからな! 後で生徒指導室まで来い!」
「ちぇっ」
クリスは小さく舌打ちし、渋々従った。
「お~し、それじゃあ授業を始めるぞ。宿題を忘れてきたなんて勇気ある奴はいないだろうな?」
山賊の頭は目玉をギロつかせながら教室の中を見渡した。頭の怒りに触れたときの罰がどれだけ厳しいか心得ている生徒達は、宿題を机の上に広げる。
だがたった一人、頭のそばで悲鳴を上げる勇者がいた。
「あっ、宿題忘れたんだ!」
その言葉を、頭が聞き逃すはずがない。
「おお、そうかナユタ。見掛けに寄らず肝が据わっているんだな、お前は」
金剛は笑っていた。顔全体は笑っているのであるが、たった一つ、目だけは悪魔になっていた。こういうときの金剛が一番恐い。
「お前もクリスと一緒に罰を受けるか? 今回の罰は、『絶体絶命! お前は地獄を見ることができるか!? 恐怖に耐えることができるか!? 絶望をうち破ることができるか!? 漢なら根性だ! 勇気だ! 希望だ! 負け犬になるな! この試練を乗り越えたとき、天界への扉が開かれるであろう大作戦・激辛モード』だ。楽しみにしてろ」
「…………
ツッコミどころ満載の金剛の言葉に、ナユタはただ言葉を失うだけだった。
2
小高い丘の上に続く坂を、ナユタは夕日を背負うようにしてとぼとぼと歩いていた。
ナユタの家は、その小高い丘の上にある。良く晴れた日ならルザイアの街を広く望むことができ、遠くにはお城の影も見ることができる。
眼下では、橙(だいだい)色に染まった街並みが流れていく。朝の眩しい景色とはまた違う、どこか落ち着いていて、そして哀愁を感じさせる光景だった。
時は夕暮れ。光りと闇のはざまに訪れる、黄昏のひととき。
夕暮れは、沈む夕日が告げていく。
「あ~あ、すっかり遅くなっちゃったよ」
金剛から罰といて与えられた『絶体絶命! ……(面倒臭いので中略!)…… 大作戦・激辛モード』は、結局のところ金剛が顧問を務める剣術部の部室の掃除だった。
ではなぜあれほどご大層な名前が付くのかと言えば、部室の汚れが想像を絶するものだったからである。
部室のロッカーを開いた瞬間、ナユタはおぞましい光景を間に当たりにした。ロッカーの中にかかっていた胴着に、ピンク色のカビやら、暗くすると不気味な緑色の光りを発するキノコやらが繁殖していたのである。
ナユタが悲鳴を上げると、剣術部に所属するクリスは平然とこう答えた。
「そのロッカーは部から逃げ出した奴のだよ。金剛に見つかるのが恐くて、逃げ出した奴らはみんな胴着とか片づけにこないんだ。胴着には汗が染みついているから、今みたいな湿っぽい時期になるとカビとかキノコとかが生えるんだよ。なかなか綺麗なもんだろ? 俺達は『天使のお茶目なプレゼント』って呼んでるんだけど」
クリスがなんと言おうと、ナユタにとっては確かに地獄以外の何物でもなかったし、バイオハザードを起こしているロッカーの中は恐怖であった。根性や勇気、そして希望という言葉を総動員しなければ、おそらく絶望感に打ちのめされたことだろう。犬にならなくて本当に良かったと思う。嗅覚に優れているという犬になっていたら、埃とカビと汗の匂いが程良くミックスした部室の空気に気絶していたかも知れない。掃除が終わって部室から出たときは、本当に天国への門をくぐったような喜びと感動に満ちていた。
何はともあれ、あの秘境から無事に生還できただけでも喜ぶべきかも知れない。
「まっ、いいか。今夜はお楽しみがあることだし」
疲れを帯びていたナユタの表情が、パッと明るくなる。立ち直りが早いのもこの男の特徴だ。
「うまくアイツが話しに乗ってきてくれるといいんだけどね」
我が家の前にたどり着き、ナユタはドアのノブに手をかけて呟いた。
今夜エレウシアの屋敷で開かれるダンスコンテンスに優勝すれば、珍しい宝石が手にはいるという。膨大な借金を抱えるナユタにとっては、またとないチャンスだった。
だがそのダンスコンテストに優勝するには、ナインテールの力が必要なのである。九尾の狐が持つ変化(へんげ)の能力を使って一流のダンサーにならなければ、運動神経がまるでないナユタなど、奇妙な踊りを披露するだけである。
「ただいま~。ナインテール、実は話しが……んん?」
いざナインテールを説得すべくドアを開けたナユタの目には、木のテーブルの上に乗って何かをむさぼっている、ナインテールの姿が飛び込んできた。
部屋の中には、少し空きかけたお腹を刺激するよな、いい匂いが満ちている。
「おお、帰ったかナユタ。今日は遅かったな」
振り向くナインテールの口のまわりには、白いソースのようなものがこびり付いていた。
「ナインテール、何やってるのさ?」
「何って、こいつを」
ナインテールが差し出したのは、縁が高くて底が平べったい白い皿である。
「ああ~! もしかして!」
カバンを放り出し、ナユタはテーブルに駆け寄る。何か食べ物が入っていたであろうその皿は底まできれいに舐められ、残りカスの一つも残っていなかった。
ふとナユタは、テーブルの上に紙切れがあるのに気付いた。その紙切れには、女の子が書きそうなやや癖のある字で、次のように書いてあった。
マカロニグラタンを作ったんだけど、たくさん作り過ぎちゃったからナユタにもあげるね。
今日は生クリームの量を増やしてみたから、タバスコを少しかけると美味しいかも。
試してみてね。
それから、またドアの鍵が開けっぱなしになってました。
家を出るときは、ちゃんと鍵を閉めたか確かめるように。
サヤカ
「さっきオレ様がテーブルの上で毛繕いをしていたら、サヤカが来て食い物を置いていったんだ。お供えかと思って、オレ様が食った」
サヤカには、ナインテールの姿を見ることはできない。だからサヤカは当然ナユタのために置いていったわけであるが、ナインテールの食い意地を考えれば、焦げたチーズの匂いが香ばしいマカロニグラタンをみすみす見逃すわけない。
「いや~、やっぱりサヤカの作るメシは旨いなぁ」
至福の笑みを浮かべるナインテール。ナユタはこめかみの辺りを引きつらせながら、そんなナインテールの目の前にサヤカの書いた紙を突き出した。
「ナインテール……、この紙が見えなかったのかい?」
「あん?」
食後の満足感に浸るのを邪魔され、ナインテールは投げやりにサヤカの文字に目を走らせた。
だがやがてご満悦ぎみだったナインテールの表情が、一気に凍り付いた。
「い、いやぁ~、妖怪のオレ様に人間の字は読めないなぁ……」
「嘘付け~!」
「百一年も生きとると、目が悪くなってのぉ……ゴホゴホ」
「そのうち百年は死んでるだろ~!」
「こんな言葉を知っているか? オレ様の物はオレ様の物。ナユタの物もオレ様の物……」
「知るか~!」
「まあまあ、これでも飲んで落ち着けよ」
と言ってナインテールが差し出したのは、サヤカがご丁寧にもマカロニグラタンに添えて置いたタバスコだった。
「いるか~!」
「はぁ~」と重いため息を付き、ナユタはガックリと肩を落とした。
サヤカの作ったマカロニグラタンは、さぞ美味しかったことだろう。ナインテールが皿の底まで舐めていることからも、それは分かる。もはや匂いしか残っていないのが、余計に悔しかった。
「ところでナユタ、オレ様に話しがあるんじゃなかったのか?」
「あっ、そうだ!」
いつまでもマカロニグラタンを惜しんでいる暇はない。食べられなかったのは残念だが、どうせ今夜はダンスパーティーに参加するのだ。美味しい食べ物は、向こうでもいくらでも食べられる。
ナユタは気を取り直して椅子に座り、今朝学校で聞いた話を切りだした。
「実はね、ナインテール。また大金が手に入る情報を耳にしたんだよ」
「ほう、そうか」
「エレウシアの屋敷って覚えているだろ? あのシャドウを捕まえに行ったお屋敷だよ。そこで今夜ダンスパーティーがあるんだけど、一緒にダンスのコンテストも行われるんだ。そのコンテストに優勝すれば、なんと珍しい宝石が賞品として貰えるんだよ」
珍しい宝石という言葉を強調し、ナユタはナインテールの反応をうかがう。
「ふ~ん、ダンスパーティーねぇ……」
ナインテールはあまり関心がないのか、またテーブルの上で毛繕いを始めた。だがナユタにとっては、予想通りの反応である。勝負はこれからだ。
「ナインテール、ルザイアでも1,2を争う大商人の屋敷で行われるダンスパーティーだよ。きっと美味しい物、珍しい物が腹一杯食べられるさ。そんなチャンス滅多いないよ」
ナインテールの食い意地を突く作戦である。ナユタの言葉にも自然と力が籠もっていた。
ナインテールの反応はどうかというと……。
「珍しいメシねぇ……。でももう、マカロニグラタンを食って腹一杯だし」
ナユタの作戦は脆くも潰(つい)えた。悲しいくらい、あっさりと……。
(な、なんてこった……)
頭を抱えて、ナユタはテーブルの上に突っ伏した。
(何か、何か他に方法は……)
ナユタは激しく脳味噌を回転させた。学校の授業ではほとんど機能しないナユタの脳味噌であるが、ことナインテールを調子に乗らせる方法なら、驚くべき性能を発揮する。
ナインテールをその気にさせる方法。食い意地を突く作戦がダメだとしたら……。
「ナインテール……」
一つの答えをはじき出し、ナユタはおもむろに口を開いた。
「今夜のダンスパーティーには、貴族や富豪も来るんだ。そこでもし、あのナインテール・ブラウンの衣装を身につけた僕が優勝してご覧よ」
ナインテール・ブラウンとは、要はきつね色である。自分が持つやや黄みがかった茶色の毛並みから、ナインテールが勝手に命名したのだ。ナインテールがナユタを変身させると、何故かこの色の服を必ず着ている。
「優勝したら、どうなるって言うんだ?」
「決まっているじゃないか。ナインテール・ブラウンは一気に上流階級の間でも大流行、注目の的になること間違いなしだよ!」
「な、なに!」
ナユタの言葉に、毛繕いを続けていたナインテールの動きがピタリと止まった。
「上流階級の間でも大流行」、「注目の的」という言葉が、ナインテールの心を激しく揺さぶる。
「ふっ、ふふふ……」
ナインテールが不気味に微笑む。ナインテールの頭の中では、社交界の席で貴族全員が、ナインテール・ブラウンの衣装に身を包んでいる光景が浮かんでいた。
恐ろしい光景である。
「は~はっはっは、そういうことだったか! このオレ様のナインテール・ブラウンを、貴族連中にも売り込もうっていうわけだな。そのためにダンスパーティーを選ぶとは、ナユタにしてはなかなか頭が回るじゃないか。ダンスパーティーに出席する貴族なら、きっとファッションセンスもあるに違いない。そんな連中の目に留まれば、このオレ様はファッションリーダーだ。素晴らしい!」
「……と、とにかく力を貸してくれるんだね、ナインテール?」
何やら目的をはき違えているようだったが、とりあえずそれは置いておくことにした。要はダンサーに変身して、ダンスパーティーに参加できればいいのである。
「もちろんだとも」
「ありがとう」
ようやくのところでナインテールの力を借りることができ、ナユタはホッと一息ついた。
ナインテール一人を説得するのに、なにゆえにこれほどまで疲れないといけないかと疑問もわき上がってくる。が、このひねくれた妖怪と付き合うには、そんなことでいちいち疲れていては身が持たない。
間違いなく忍耐力は付きそうだなと、ナユタは心の中で思った。
「ところで一つ問題があるんだけど……」
「問題? そりゃナユタがダンサーに変身するんだ、問題なんて軽く百個はあるぞ。まずは……」
「……いや、そうじゃなくてさぁ」
指折り数える仕草をして問題を並べていこうとするナインテールを、ナユタは嘆息しながらとめる。本当に百個言えるか、聞いてみたくもあったが。
「ダンスパーティーに参加するには、招待状が必要なんだよ。でも僕は、貴族がお金持ちの出席するダンスパーティーの招待状なんて持っているわけない」
「うむ、当たり前だな」
「…………」
妙なところで相づちを打たれ、ナユタの言葉が一瞬止まった。
「……でだね。何とかして招待状を手に入れないといけないんだよ」
「なるほど。ダンスパーティーに参加できなければ、ナインテール・ブラウンを貴族連中に見せることもできないからな。それは一大事だ」
納得するように、ナインテールは大きく頷く。
「よし、それは任せろ。オレ様が何とかしてやろう」
「えっ、本当に!?」
「ああ、オレ様なりのやり方でな。ひっひっひっ……」
何か企んでいるとしか思えないような笑みを浮かべるナインテール。そんな彼を見ながら、ナユタは大きな間違えをしたのでないかと、激しく後悔するのであった……。
3
夜―。
月が雲に隠れ、その道は暗い夜の闇に包まれていた。
人の声はしない。側を流れる用水のために作られた小さな川からも水の流れは聞こえず、虫の音もしなかった。
完全な静寂の世界である。
この道を進めば、この街の貴族や富豪達が屋敷を並べる大通りに行き当たることになる。だがガス灯に照らされたその大通りの光りも、ここまで届くことはない。
華やかな通りも、一つ裏道に入れば、そこには別の世界が存在している。それが「街」というものである。
王都ルザイアとて、例外ではなかった。光りのあるところに闇があるのは、自然なことなのである。
だがそんな場所でこそ、本当の夜を感じることができる。
夜は、月が導く闇と静寂が告げるのだから。
その暗い裏道に、二つの眼が浮かんでいた。細長くやや吊り上がったその眼は、何かを探すようにチラチラと動いている。
「ちっ、来ねえなぁ」
細い目が、苛立たしげに更に細くなる。
「ねぇ、いったい何をしようっていうんだよ?」
と、細長い眼の上にもう一組みの眼が現れた。こちらの眼は、不安げでどことなく頼りない。
「何って、見れば分かるだろ?」
「分からないから聞いてるんじゃないか。早くエレウシアの屋敷に行かないと、ダンスパーティが始まっちゃうよ。招待状だってまだ手に入ってないのに」
「その招待状とやらを、このオレ様が手に入れてやろうとしてるんじゃないか」
「だからどうやって?」
「しゃ~ないなぁ、説明してやろう」
吊り上がった眼の方が、やれやれと真っ平らになる。
「パーティーに参加する奴から招待状を奪うのさ」
「う、奪うだって!?」
頼りない眼の方が、弾けるように丸く大きくなった。
「まあ強引に奪ったら強盗になっちまうからな。さすがに犯罪はしたくないし。ちょっと脅して、招待状をいただくだけだ。何も問題はなかろう?」
吊り上がった目の方が、ニタリと再び細長くなる。
「……君は『恐喝』という言葉を知らないのか?」
「だが、大通りでそれをやったらさすがに目立つ。そこでだ、この裏通りに潜んでいるわけさ」
「聞いちゃいないな……」
ため息混じりのかすかな声と共に、今度は頼りない眼の方がやれやれと真っ平らになった。
「パーティーに遅れてくる奴だって、一人や二人いたっておかしくない。そいつを脅かして、招待状をいただくのさ。完璧だろ?」
「もしかしてその脅かす役って僕?」
「もちろん」
「やっぱり……」
また一つ、頼りない眼がため息を付く。
「でもどうやって脅かせば良いんだよ? ただ脅かすだけじゃ、招待状なんて貰えないじゃないか」
「ふふっ、そこはオレ様に考えがある。人間を脅かすには、あれに変身するのが一番だ」
吊り上がった目が、暗い闇の中で不気味に紅く光った。
「ちょ、ちょっと待って! 何に変身させようって言うんだよ!?」
そんな叫びも虚しく、紅い光りは一瞬大きく弾けた。頼りない眼の方が、モクモクと煙に包まれ見えなくなる。
やがて月を覆っていた雲が晴れ、暗闇に包まれた裏道に月明かりが差し込んだ。
頼りない眼のまわりから、一つの人影が浮かんでくる。
「何なんだよコレ?」
その人影は、全身血にまみれ、ボロボロの服を身に纏い、死人のように蒼白の顔をしたナユタの姿であった。
「見りゃ分かるだろ。そんな格好をしたバーテンがいると思うか? 全身血まみれでブラッディーマリーを出された日にはシャレにならんぞ」
「ま、まあそうだけど」
「どこから見ても幽霊に決まっているじゃないか」
「姿はそうみたいだけどね……」
ナユタは近くにあった民家の窓を覗いてみた。確かに無惨な死に方をした幽霊のようにも見えるが、月明かりを受けておぼろげながら映る顔はどこか自分に似ている。
「顔はもしかして僕のままじゃない?」
「その通りだ。今回の変身のコンセプトは、この道でパーティーの招待状を風に飛ばされ、それを追いかけてつかみ取ろうとジャンプしたら勢い余って小川に落ちて溺れ死んだ不運な男、だからな」
「川で溺れてどうして血まみれなんだよ……」
ナユタはため息混じりに呟いた。
更に付け加えるなら、側を流れる小川はむしろ溺れる方が難しいぐらい浅いのである。この小川で死人が出る要素なんてどこにもない。
「幽霊が出るのはこんな暗い夜と決まっている。お前はここで待ちかまえ、遅れてきた奴にさりげなくこう言うんだ。『パーティーの招待状をよこせ~』、とな」
「おもいっきり不自然じゃないか~! どこの世界にパーティーの招待状なんて欲しがる幽霊がいるんだよ!」
「それをカバーするのはお前の演技力だろうが」
「そんなぁ…。人を脅かすなんて僕には無理だよ。ナインテールの方がよっぽど得意じゃないか」
「何だその『得意』っていう言葉は。忘れたか? オレ様の姿はお前以外の人間には見えないんだぞ。オレ様にできるのならいちいちお前に頼まん」
「いや、頼むというより問答無用で変身させられたんだけど……」
「おっ、噂をすれば何とやらだ。誰か来たみたいだぞ」
ナインテールの言葉通り、薄明かりの向こうの方からガタガタという馬車の音と共にランプの明かりがこちらに向かってきた。馬車の速度から、だいぶ急いでいるようである。
「しっかりやれよ、ナユタ。オレ様のナインテールブラウンが宮廷で流行るか流行らないかは、お前の頑張りにかかってるんだからな」
「そ、そんなこと言われてもねぇ……」
いきなり幽霊の真似をしろと言われても、役者でもないナユタにできるわけがない。だがナユタがたじろいでいる間に、馬車はナユタの目の前までやって来た。
「むっ、どうどう!」
道の真ん中に突っ立っている人影に気が付き、御者が慌てて手綱を引いた。かなりスピードを出していた栗毛の馬は、嘶きと共にナユタの目の前で前脚を高く上げる。
「う、うわあ!」
悲鳴を上げたのはナユタの方であった。驚かすために現れた幽霊が先に悲鳴を上げるなど、あまりにも滑稽である。
「ひゃあっ! で、出たあ!」
出血大サービスなナユタの姿を見て御者も悲鳴を上げる。
とはいえナユタも馬車を止めたまでは良いが、それからどうすればよいのか分からない。脅かすために現れた幽霊がオドオドするという奇妙なシチュエーションのまま、ランプの明かりに照らされた生々しい鮮血だけが、ナユタの姿をさらに気味悪くしていた。
「どうしたんだ?」
外の異変に気付いたのか、馬車の中から若者と思える男の声がした。
「あ、ああ…」
だが御者は歯をガチガチとさせたまま、金縛りにあったように動かなくなってしまっていた。
「いったい何事だ? 急がないとパーティーに遅れるぞ」
馬車の扉が開き、中から一人の若者が姿を現した。年の頃は、ナユタとほとんど変わらないだろう。
赤い派手なシャツに、ピッタリとした黒いズボンを履いたその若者は、一目でパーティーに参加するダンサーと分かる。
「あ、あそこに…」
御者が指さす先には、幽霊のくせに戸惑っているナユタの姿があった。
「き、君は?」
さすがに全身血だらけにして相手を驚かすという趣味を持ち合わせているのは、幽霊しかいない。幽霊との初めての遭遇に緊張を隠せない若者であったが、ナユタはナユタで頭の中が真っ白になるほど緊張していた。
「え、え~と、その~。しょ、招待状を……」
「招待状?」
「は、はい。僕はパーティーの招待所が欲しくて……」
ここまで腰の低いの幽霊がいるだろうか。
「何でパーティーの招待状なんて欲しがるんだ?」
「そ、それはですねぇ……」
「パーティーの招待状を奪われてしまったからです」
突然ナユタの横から少女の声がした。
ナユタが慌てて振り向いてみると、そこにはいつの間にか一人の少女が立っていた。こちらも見た目には十五、六歳頃で、ナユタとさほど変わらない印象を受ける。
だがその少女の姿は何故かぼんやりと透き通っており、そして何よりも目を引いたのは、その胸に短剣が突き刺さっていたことであった。胸の部分に広がった鮮血を、白いドレスが一層際だたせている。
「二十年前の今日、まさしくこの場所で、私たち兄妹はダンスパーティーに出席する途中で盗賊に襲われました」
ふと眼を閉じた少女の表情に哀しみが浮かぶ。紛れもなく、その少女は本物の幽霊であったのだ。
「ダンスパーティーに出席する途中で盗賊に襲われて命を落とした兄妹って……。ま、まさか君の名は?」
馬車から出てきた若者は少女に訊ねた。
「はい、リサと言います」
「あの『神の踊り手』と言われた双子の兄妹のリサなんだね。と言うことは隣にいる君は…」
若者がナユタの方に視線を移す。
「ぼ、僕はナユ…、じゃなくて」
「やっぱり君は兄のナユラなんだね! ずいぶんひどい姿になってたからよく分からなかったけど、前に一度見た肖像画とそっくりだよ」
「えっ、僕とそっくりなの?」
「信じられないなぁ。幽霊とはいえ、あの伝説の兄妹に会えるなんて」
「いや、違うんだけどなぁ……」
小声で呟くナユタであったが、興奮している若者の耳には届いてはいなかった。
「兄さんどうしたの?」
と、今度は若者が出てきた反対側の窓が開き、一人の少女が姿を現した。
彼女もダンスパーティーに参加するのであろう。若葉のような薄いグリーンのドレスに身を包んだ彼女は、赤いヒールをコツコツとさせて兄の元に歩み寄る。
「見てご覧よ、エリサ。『神の踊り手』と言われたあの兄妹の幽霊が僕の前に現れたんだ」
「えっ、本当に?」
エリサは彼女の前に立つ二人に目をやった。
「ほ、本当にあなた達はナユラとリサ兄妹なのですか?」
一人は全身から血を流し、もう一人は胸に短剣が突き刺さっている姿に一瞬驚き、彼女は僅かに声を震わせて訊ねた。
「はい…」
リサが静かに答える。
「私たちが招待されたダンスパーティーは、私たち兄妹の誕生日を祝って開かれたものだったのです。あの時はどんなに楽しみにしていたことか。でも盗賊に襲われ、持っていたものはすべて奪われてしまいました。パーティーの招待状も、そして命さえも……」
よほど無念であったのだろう。リサの丸く大きな瞳は、涙がこぼれそうなほど哀しみに包まれていた。
「今もそのパーティーは私たちの誕生日の日に開かれていると聞きます。だけど、その招待状はもうありません。あなた方もパーティーを楽しみしていることでしょう。でも一度だけで構わないから、パーティーに参加したいのです。お願いします。私たちに招待状をいただけないでしょうか」
リサの言葉には自然と力が込もっていた。訴えかけるよな視線を、馬車から出てきた二人に送る。
「兄さん……」
エリサは横目に兄の様子をうかがった。
兄は小さく頷くと、考える様子もなくこう答えた。
「この二十年の間、パーティーに参加できなかったことがずっと心残りだったんだね。他ならぬ伝説の兄妹の頼みだ、喜んで招待状をあげるよ」
「本当ですか」
彼の答えに、リサはパッと晴れやかになった。幽霊であることを忘れてしまいそうなほど、少女らしい明るい笑顔である。
「いいよな、エリサ?」
「ええ、もちろん。なんたって憧れの兄妹の頼みですもの」
エリサは「待っててね」と兄に声をかけると、馬車の方へとって返す。
ややあって、エリサが馬車から戻ってきた。その手には、2枚の紙が握られている。
「通りがかったのが私たち兄妹でよかったですね。一人で参加する人だったら、二人でパーティーは行くことができなかったから」
エリサはニッコリと微笑むと、リサとナユタに招待状を手渡した。
「本当にありがとうございます」
「ど、どうも……」
リサは言葉を弾ませて、そしてナユタは相変わらずあたふたしながら、エリサから招待状を受け取った。
「もし良かったら、あなた達の名前を教えて貰えないでしょうか?」
「僕たちの名前を?」
リサの意外な言葉に、兄は自分を指さしながら訊ね返した。
「ええ。二十年もの間ずっと思っていた願いを叶えてくれたあなた達の名前を、是非知りたいんです」
「分かった。こっちの妹の名前はもう知っていると思うけど、エリサっていうんだ。そして僕の名前はナユラス。二人とも君たちの名前を貰ったんだよ」
「まあ、そうだったのですか」
「父さんが言っていたよ。君たちのようなダンサーになって欲しくて付けた名前なんだって。人からはあの伝説の兄妹の再来何て言われてるけどね」
ナユラスは「へへっ」と照れ笑いを浮かべる。
「風の噂で耳にしたことがあります。この街で誰よりも素晴らしいダンスを踊る兄妹がいると。それがあなた達だったのですね」
「僕たちなんてまだまだだけどね。……あっ、そろそろパーティーが始まる頃だ。早く行かないと遅れる」
ハッと思いだしたように、ナユラスは遠くの空を見上げた。その先には、エレウシアの屋敷にある大時計が、淡い光りに包まれてぼんやりと浮かび上がっている。
エレウシアの父ゲイルードが、街の人たちが一目で時刻が分かるようにと立てた時計台である。その意向に添って、夜になると明かりが灯されるのだ。十二個刻まれている文字盤の一つ一つに宝石が埋め込まれており、明かりに照らされてその宝石が小さな輝きを放っている。
’エルフの涙’というその緑色の宝石をめぐってナユタがシャドウという盗賊と対決したのは、まだほんの数日前のことである。
「本当にありがとうございました。あなた達のこと、ずっと忘れません」
最後に一つ深々とお辞儀をすると、リサはくるりと振り向いて走り出した。エレウシアの屋敷のある、大通りに向けて。
「あっ、待ってよ……うわっ!」
リアを追いかけようとしたナユタであったが、小石に躓いて無様に転倒する。
「痛ててて……」
鼻っ柱を押させて振り向くナユタを、二人の兄妹がポカンとしながら見つめていた。
「あはっ、あはははははは……」
転んだ後に顔中血だらけで笑われると、よけい恐い。
「招待状ありがとう」
一言声をかけると、ナユタは脱兎のごとく駆けだした。
そんなナユタを、二人の兄妹は目を点にしながら見送っていた。
ナユタの消えた闇の向こうからは、「ミ゛ャー!」という鳴き声と共に、彼の悲鳴が聞こえてきた。野良猫の尻尾でも踏んづけて、引っ掻かれたのであろうか。
「……意外とおっちょこちょいだったんだな、ナユラって」
「伝説のダンサーの意外素顔ね」
二人の心だけに刻まれた、新しい伝説であった。
「はぁ、はぁ、はぁ。もう大通りかな?」
暗い夜道をダッシュし、気が付くと大通りに出ていた。きれいに並んだガス灯が、広い道を点々と照らしている。
「あれ、あの女の子はどこに行ったんだろう?」
まわりを見渡してみても、リサはおろか人っ子一人いなかった。
もっともその方がよかったのかも知れない。血だらけの男が急に現れたら、通りはパニックになっていたことだろう。
「成仏したんだろうよ」
「ナインテール」
いつの間にやら、ナユタの足下にナインテールがやって来ていた。
「念というものは、強ければ強いほどそこに残るもんだ。パーティーに行きたいという気持ちが、あいつの魂をずっとあの場所に縛り付けていたんだろうな」
「じゃあ招待状が手に入ったから、あの女の子は成仏できたってこと?」
「ああ。パーティーに参加したくても、その招待状はなくなっちまったからな。だが招待状が手に入ったことで、パーティーにも参加することができる」
「彼女の願いが叶ったってわけだね」
「だからあいつの魂は、あの場所から解放されたんだ。もしかしたらあいつの魂は、今夜のパーティーをそっと影から覗いているかも知れないな」
「でも驚いたな。急に本物の幽霊が現れるんだもん」
「恐らくお前を自分の兄と間違えたんだろう。名前も顔も似ていると言っていたから。兄と似ている男が招待状を貰おうとしている姿に誘われて、あいつの魂が幽霊となって現れたんじゃないのか」
「ふ~ん、そうなんだ。でも良かったよ。あの女の子のおかげで招待状が手に入ったようなものだし」
満足げに頷くナユタの言葉に、ナインテールはハッとした。
「そういえばお前! オドオドしてただけで何にもやってなかったじゃねぇか!」
「だから言ったじゃないか。僕には人を脅かすなんて無理だって」
「何のために変身させてやったと思ってる! 自分の方が先に驚く幽霊なんて見たのは初めてだぞ!」
「仕方ないだろ。急に目の前で馬が足を上げてご覧よ、誰だって驚くに決まってるじゃないか」
「そりゃお前がいつもボケボケっとしてるからだろうか! どうしてお前はそこまでドジなんだ!」
「し、知らないよ……」
「はぁ~、せめてそのドジが治ってくれたらなぁ。オレ様も苦労はしないんだが」
「よく言うよ、自分だって間抜けな死に方をしてるくせに」
「な、なに!?」
「確かナインテールの最期って、お腹が空いて死にそうになりながら食べ物を探しているときに、ようやくキノコを見つけて食べたんだけど、それが毒キノコで死んじゃったんだよね」
「くっ、くく…」
それが事実なだけに、さしものナインテールも反論のしようがない。
「他人のことを間抜けなんて言えないじゃないか。ははははっ。」
「う、うるさい!」
ボカッ!
ナインテールが思いっきりジャンプして、ナユタの脳天にげんこつを落とした。
「ちょっと立場が弱くなったらすぐこれだ。ヒドイよ……」
頭を抱えてうずくまりながら、ナユタは呻いた。
「……い、いつまでへたばってる。パーティーに行くぞ。オレ様のナインテール・ブラウンが一躍脚光を浴びる、その舞台へとな」
かくして招待状を手に入れたナインテール達は、ナインテール・ブラウンを上流階級に広めるべく、エレウシアの館へと向かったのである。
あれ、そんな話しだっただろうか……。