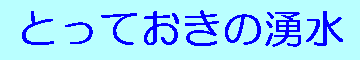
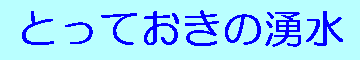
各地には、人々に親しまれている湧水が数多くあります。各地で出会った、とっておきの湧水を紹介します。
美々川源流 北海道 千歳空港から程近い平原を南向きに流れ、ウトナイ湖に
注ぐ美々川。その始まりは小さな湧水から。土でできた小さな壁にあいた左右2つの穴の奥から、
こんこんと冷たく清らかな水が湧き出してきます。
源兵衛川 静岡県三島市 静岡県三島市の源兵衛川。約1万年前、富士山の噴火で
流れ出した三島溶岩流。その境目から、多量の伏流水が
湧水となって湧き出しできます。清冽な流れ、源兵衛川の
始まりです。
遊歩道、せせらぎルートには、川中にウッドデッキや
飛び石が配置され、とっても気持ちがいいです。
楽寿園内にある小浜池は、水の湧出量により毎日水位が
変わります。源兵衛川は、に選ばれています。