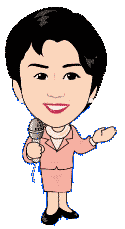 |
朗読の部屋 ナレーター・平野美保の語りの世界。 語りと音楽の融合した作品を、随時紹介していきます。 ナレーター:平野美保の紹介はこちらへ 完成したCDを希望の方に、お分けします。 申し訳ありませんが、実費として、送料梱包費込みで、900円をご負担下さい。 CDご希望の方はこちらまで |
第2弾 宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』 CD制作中
第1弾 音楽物語『ピーターと狼』 CD完成
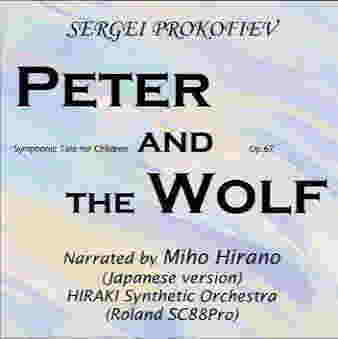 プロコフィエフ作曲 プロコフィエフ作曲音楽物語『ピーターと狼』(日本語版) 語り:平野美保 演奏:ヒラキ・シンセティック・オーケストラ(SC88Pro) ←写真をクリックするとサンプル音声が聞けます。 |
||
| <内容> 「ピーターと狼」はロシアの作曲家・プロコフィエフの作った子どものための音楽物語です。 劇的なオーケストラ音楽と巧みなナレーションで、物語が展開します。 今でも世界中の子供たちに親しまれています。 このCDでは、日本語の美しさに親しんでもらうために、言葉遣いと発音に特にこだわりを持って作成しました。 演奏は、シンセサイザーです。 原曲の雰囲気を損なわないように努めながら、その魅力をくっきりと浮かび上がらせるために、独特の演出がほどこしてあります。 従来の「ピーターと狼」とはひと味違う作品が完成しました。 |
 |
|
| <音楽制作メモ1> 現在発売されているCDを聴き比べてみると、 ナレーションの編集が粗雑なものが、なんと多いことか! 音楽のタイミングと合致してなかったり、 台詞の挿入場所が悪くて音楽が間延びして聞こえたり。 テープのヒスノイズが目だってて、編集のつなぎ目がもろ分かりだったり。 これは、日本語英語ドイツ語にかかわらず、同じ。 有名な俳優による語りがほとんどだけど、その値打ちがだいなしだなぁ。 指揮者自ら語ったものもあるけど、これは論外。 発音に難がありすぎて、鑑賞に堪えられない! 有名な指揮者の肉声が聞けるというメリットだけ。 せっかく演奏が一流で、録音状態も最高なのに、 2度と聴く気にならなくなってしまう。 <音楽制作メモ2> 最初に小鳥が登場する場面。 フルートの軽快なパッセージが続くところ。 楽譜を見ると、速度指定が176となってる。 (1分間に四分音符が176拍ってこと) これは、かなり速い。 実際に、フルートをこの速さで演奏するのは、相当難しい。 実演奏では、たいてい120ぐらい。 正確に演奏できる速さまで落としてるのかな。 でも、プロコフィエフが要求したのは176の速さ。 シンセサイザーなら、どんな速さでも簡単。 楽譜指定の速さで演奏させてみると、 小鳥の生き生きとした姿が浮かび上がってきたではないか。 なるほど、プロコフィエフはこれを期待してたんだね。 <音楽制作メモ3> プロコフィエフの没年は1953年。 ということは、この曲は著作権保護期限が切れるのが2003年ってこと。 あと、もう少しだったのに、残念。 仕方ない、JASRACに使用許可を申請するとしよう。 期限切れまで待ってられないから。 <音楽制作メモ4> JASRAC中部支部の池上さんがHPを見て間違いを教えてくれた。 プロコフィエフの著作権保護期限切れは2003年だと思ってたら、違ってた! 普通、没後50年で期限切れになるはずなんだけど、例外がある。 それが、戦時加算。 第2次大戦中、日本は連合国側の著作権の保護を怠ってたから、その分を加算して、日本だけ著作権保護期間を延長するってことが戦後処理で決まったらしい。 (これに関しては日本人として言いたいことがいっぱいあるけど、省略) でも、プロコフィエフの出身はソ連(ロシア)。 ソ連はサンフランシスコ講和条約に調印してないぞ。 戦時加算対象外のはず。 でもでも、プロコフィエフは、なんと、フランスの著作権協会と契約を結んでいた! (なんで、こんなことするんだよ。) だから、プロコフィエフは戦時加算の対象。 計算すると、『ピーターと狼』は、2014年5月21日まで保護期間内。 詳しくは、JASRACのHPへ。http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a3.htm#01 <音楽制作メモ5> アヒルがドボンと池に飛び込む音。ホルンがちゃんと描写してるんですが、普通の演奏では、ほとんど無視しちゃってますね。ナレーションがかぶってたり、全然聞こえなかったり。でも、この演奏では、しっかり強調してます。 小鳥とアヒルの喧嘩の場面。小鳥が池の淵をチョンチョン駆け回るのを描写して、フルートの音が右へ左へと動きます。こういう表現は、実演奏では無理ですね。 おじいさんがピーターを家に引きずってく場面、アヒルが狼に追われて逃げ出す場面、小鳥が飛び回る場面でも、動きをつけました。 ピーターがおじいさんの言うことを聞かずに駆け回っている場面。軽やかなピーターのメロディーの陰で、ファゴットの重低音が鳴り続けます。これは、おじいさんがかなり怒ってる描写なんです。少し強調していれてあります。 猫が木の上でガタガタ震えている場面。プロコフィエフは芸が細かくて、これもちゃんと描写してます。でも、従来の演奏では、あっさりやり過ごしているものがありますね。この演奏では弦のトレモロも合わせてガタガタ感が伝わってくると思いますよ。 それから、狼が捕まって激しく暴れまわる場面。普通の演奏だと、のたのたした感じで、全然「激しく」ありません。というのも、楽譜の指定がこうだから。ここでは、動きを速くして、緊迫した雰囲気を作り出しました。プロコフィエフさんごめんなさい。 狼が棒に結び付けられて運ばれていく場面。気を失ったまま大口を開いていびきをかいている音が聴けます。もちろん実演奏では聞こえませんよ。 <音楽制作メモ6> おじいさんがピータを連れて帰り、門に鍵をかけてしまう場面。 ガチャンとしっかり閉めてしまうイメージを強調するために、ティンパニーに前打ちを加えました。 うまく効果が出ているでしょうか。 <音楽制作メモ7> 弦楽器の配置。 現在のオーケストラ配置は、プロコフィエフの時代にはありえない形式でした。だから、現在の配置で演奏すると、音が一方に偏ってしまって、バランスの悪いところが出てくるんですよ。 今回の演奏では、次のようにパンを設定しています。 左にビオラ。 左中間に第1バイオリン。 中央にコントラバス。 右中間に第2バイオリン。 右にチェロ。 |
<ナレーション制作メモ1> ピーターが狼を捕まえたあと、狩人たちにお願いをする場面。 今までのナレーションでは、たいていこんな台詞になってましたね。 「撃たないで! 狼は動物園に連れていこうと思うんだ。一緒に手伝ってー」 友達の小鳥さんに話しかけるのと同じ口調。 大人に向かってタメグチで話す子どもって、いけませんよね。 最近の童話はこれで許されてるみたいですが、あまり好ましくない傾向ですよ、教育上。 ピーターの年齢設定にもよりますが、今回は、きちんと丁寧な言葉を話せる子どもにしてみました。 「撃たないでください! 狼は動物園に連れていこうと思うんです。おじさんたちも手伝ってください」 <ナレーション制作メモ2> 登場人物の性格付け。 ピーター:10歳ぐらいの元気のいい男の子。 小鳥:よくしゃべるお姉さん。ちょっと高ビー。 あひる:気の強い太っちょのおばさん。 猫:こずるい奴。いざとなるとびびって何もできない。 おじいさん:いつもぶつぶつ、頑固じいさん。 声の表情だけで、人物の性格を描きわけるのは大変ですね。 納得いくまで何度もとりなおして、喉が痛くなっちゃいました。 今回、いいトレーニングになりました。 <ナレーション制作メモ3> ほぼ完成。 で、音楽と合わせて完成品を聴いてみると、作品として、生き生きとした感じに聴けます。 やっぱり、プロコフィエフの傑作ですね。 でも、冷静に聴きなおしてみると、ところどころ気になるところがいくつか出てきました。 音楽の雰囲気と合わないところ、音楽がうるさくてナレーションの聴き取れなくなってしまったところなどなど。 部分的にナレーションの入れ替え。 <ナレーション制作メモ4> 仕上げで、手直しをしていくと、その他のところがまた気になりだしてしまいます。 完璧を目指したら、きりがない。 でも、この作品は、一過性の流行りものとは違う。 10年後20年後にも確実に残るはずです。 ちゃんとしたものを作れば、きっと、貴重な財産になる、と思い、もうひと踏ん張り。 <ナレーション制作メモ5> 最後に狼をどうやって動物園に連れていくのかは、解釈の分かれる場面。 「ピーターと狼」を描いた絵本などを見てみると、尻尾を縄で縛られた狼が狩人たちに連れられて歩いている図が多いですね。 でも、これではラストシーンのどんでん返しがうまくイメージできないんですよ。 このCDでは、気を失った狼が棒に括りつけられて狩人に担がれていくという状況設定にしました。 <ナレーション制作メモ6> ラストシーンのどんでん返し。 ちょっと工夫しました。 ここまでやらないと、普通、納得できないでしょう。 23分の音楽物語を終わるのにふさわしいハッピーエンドになったと思いますよ。 |
|
<今後の予定>
第3弾 「シェヘラザード」 原作:アラビアンナイト 音楽:リムスキーコルサコフ
第4弾 「ドン・キホーテ」 原作:セルバンテス 音楽:R.シュトラウス