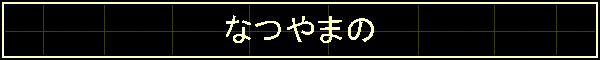夏
夏日見る遠山雲
9 なつ山の をちにたなびく しら雲の たちいでてみねと なりにけるかな
くひな
10 たたくとも しばしとぢなん あまのとは あくればかくる くひななりけり
ほととぎす
11
ゆふやみに なきてすぐなり ほととぎす かへらんときも 道なたがへそ
あるところにて、詠木下風
12 なつの夜は このしたわたる 風のおとも いふかげにこそ すずしかりけれ
なかをかにて、ほととぎすをまつといふことを
13 ほととぎす きなかぬさきに あけにけり などなが月に またずなりけん
ほととぎすをききて
14 ひとこゑの おぼつかなきに ほととぎす ききてののちも ねられざりけり
月よほととぎす
15 さみだれは おぼつかなきを ほととぎす さやかに月の かげにききつる
【校異】
●たゝくとも(島・類)……たゝ○とも(三)、た○○【ゝく】とも(山)
●あくればかくる(島)……あくればかへる(類)
●なかをかにて(島・山・御・三・清)……なかをかにして(類)、なかをかにして【○無イ】(仲)
●さやかに(島・類)……さやけき(東)
●きゝつる(島・類)……なかなむ(東)
【通釈】
夏
夏の日、遠くの山の雲を見る
9 夏山の向こうに層をなして薄く引く白い雲は、立ち上って峰となっていることだ。
くいな
10
叩いても、しばらくは天の戸を閉じたままでいてほしい。なぜなら、戸を開けて
夜が明ければ、隠れてしまう水鶏だからだ。
ほととぎす
11
夕闇の中を鳴いて通り過ぎてゆくらしいほととぎすよ、帰る時も、道を間違えるなよ。
ある所にて、木の下風を詠んだ歌
12
夏の夜は、木の下を吹き渡る風の音も、夕方の光の中では涼やかに聞こえるなあ。
中岡にあって、ほととぎすを待つということを詠んだ歌
13
ほととぎすが来て鳴かないうちに、月が隠れて夜が明けてしまった。どうして長い月
という意をもつ九月の月が、待ってくれなかったのだろう。
ほととぎすを聞いて
14
ほととぎすの一声が待ち遠しくてならなかったからだろう、その声を聞いた後も、
眠れないことだ。
月夜のほととぎす
15
五月雨が降ると、ほととぎすの姿ははっきりと見ることができない上、声も定かには
聞こえないが、月の光のおかげで、紛れもなくその姿を見、声を聞いたことだ。
【語釈】
●をちにたなびく……(山の)向こうに薄く層を成して引く。
●くひな……鴫に似た鳥。くちばしが黄色く、背面に茶褐色の黒斑がある。腹面は白い。水辺のくさむらなどに生息。秋から冬にかけて渡来する。
●たたくとも……鳴き声が戸を叩く音に似ていることから、くひなの声は「たたく」と表現することが多い。
●あまのと……「天から地への戸」が原義。くひなが叩く戸という縁語として詠まれるが、夜が明ける、明け方を導くほどの意味しか持たない。
●あくればかくる……夜が「明ければ」と戸を「開ければ」を掛ける。
●木下風……木の下を吹き渡る風。
●なかをか……具体的にどこか不明。長岡のことか。
●きなかぬ……来て鳴かない。
●なが月……陰暦九月のことだが、夜の長い月、という意味を持たせて詠まれることが多い。
●ひとこゑのおぼつかなきに……ほととぎすの一声が待ち遠しい。
●さみだれはおぼつかなきを……五月雨のせいで、ほととぎすの姿ははっきりとは見えず、鳴き声もはっきり聞こえない。
●さやかに月のかげにききつる……月明かりの下では、紛れようもなく見、聞くことができた。
|