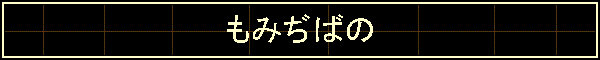ふゆ
十月一日、山ざとに人人いきて、もみぢを見てかはらけとりて
85
もみぢばの ちりしのこれば 山ざとに あきをとどめて みる心ちする
かやうゐん殿のいけにふねにのりて、月秋といふだいを
86
あきごとに さやけきつきは こよひこそ わがみつるよの ためしなりけれ
栖霞寺にて、もみぢころもにおつといふだいを
87 もみぢばは わがころもでに かかれども きて見る人の あかずもあるかな
88 けさ見れば かはべのこほり ひまなくて かはせにのみぞ なみはたちける
いかだ
89
かはみづに まかせておとす いかだしは さしてゆくへも しられざりけり
ゆきふりたるひ、大納言の家に、うたよむひと人よびて、松雪といふだいを
90 ゆきふれば まつこそいたく おいにけれ ちとせのふゆを つみやしつらん
十月卅日、殿のあまうへ、はせにまうでさせたまひて返らせたまひしに、
うぢ殿に御むかへにまゐれる人人、あじろにまかりて、あじろにて
月を見るといふだいを
91
月かげも いはなみたかき あじろには うすきこほりの よるかとぞ見る
遍照寺にて、人人月前紅葉といふ題よみける
92
いとどしく もみぢちりしく にはのうへに ひかりをそふる ふゆのよの月
落葉如雨
93
このはちる やどはききわく ことぞなき しぐれするよも しぐれせぬよも
落葉旧苔上
94 うちかさね いくよの風か たちつらん この葉ぞこけの ころもなりける
【校異】
●もみちをみて(島・類)……もみちけをみて(三)、もみちけ【×】をみて(山)
●(改)かやうゐん殿の(類)……かやうゐん殿のの殿の(島)
●(改)ひと人(類)……ひと八人(島)
●十月卅日(島)……十月廿日(類)
●させたまひて(島・類)……させたまて(三)、させたま【ひ】て(山)
●(改)遍照寺(類)……道願寺(島)
●もみちちりしく(島・類)……もみちりしく(三)、もみち【ち】りしく(山)
【通釈】
冬
十月一日、山里に人々が行き、紅葉を見て土器を取って、
85
ここ山里にはもみじの葉が散り残っているので、まるで秋を留めて
見ている心地がする。
高陽院殿の池の舟に乗って、「月秋」という題を
86
秋ごとに、澄み切った月は今宵こそ、わたしが見た世の、夜の月の例と
なったことだ。
栖霞寺にて、「紅葉、衣に落つ」という題を
87
紅葉の葉はわたしの衣に落ちかかるけれども、ここに来て、この衣を着て
見る人は飽きることがないよ。
筏
88 今朝見てみると、河辺の氷は隙間もなく、川の瀬にだけ、波が立っていたことだ。
89
川の水に任せて落とす筏師は、棹を挿しても、これといってその行方を
知ることはないのだなあ。
雪の降った日、大納言の家に、歌を詠む人々を呼んで、「松雪」という題を
90
雪が降ると、松は白髪をいただいたようにたいそう老いてしまうことよ。
まるで千年の冬を積んだかのように。
十月三十日、殿の尼上が長谷に詣でなさって、お帰りになるのに、
宇治殿にお迎えに参上する人々、網代に行って、
「網代にて月を見る」という題を
91
岩波の高い網代には、月の光も薄い氷が張っているように見える夜である。
遍照寺にて、人々が「月前紅葉」という題で詠んだときの歌
92
紅葉がますます一面に散っていく庭の上に、光を添えて投げかけている、
冬の夜の月よ。
落葉如雨
93
木の葉が散る家では聞き分けることもできないことだ。時雨が降る夜とも、
時雨が降らない夜とも。
落葉旧苔上
94
幾晩も吹いた風が立ったのであろう。うち重ねた木の葉は、
実は苔の衣だったのだなあ。
【語釈】
●山ざと……山里。本来は山の中にある人里、そのような里にある家を指した。平安時代、貴族の間で山里に別荘を建てたり、山里の雰囲気を出した造りの邸を建てたりすることが流行し、侘びしい、寂しい所として多く詠まれるようになった。中国の隠遁思想や山居思想の影響かと思われる。
●かやうゐん殿……高陽院殿。藤原頼通が高陽院(かやのいん)を所有していたことから、頼通を指す。高陽院はもと賀陽親王(桓武天皇皇子)の邸宅跡地と伝えられ、賀陽院とも書かれる。頼通は治安元(1021)年、中御門大路の南、堀川小路の東の四町に及ぶ広大な敷地に豪華な邸を建造、ことに庭園が美しいことで有名であった。長暦3(1039)年3月16日に焼亡したが、翌長久元(1040)年10月には再建された。天喜元(1053)年ごろからは、後冷泉・後三条・白河天皇の里内裏ともなった。承暦4(1080)年焼失、寛治6(1092)年に藤原師実が造営している。天永3(1112)年再度焼失したが、新造の高陽院に後鳥羽上皇が元久2(1205)年移御している。
●我みつるよのためし……「夜」と「世」を掛ける。わたしが見てきた世の、夜の月の例。
●栖霞寺……現在の清涼寺。京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町。もとは源融(嵯峨天皇皇子)の山荘・栖霞観があった場所で、融の没後に寺となり、阿弥陀堂が建てられ栖霞寺と呼ばれた。のちに奝然が三国伝来の生身の釈迦如来を安置したのが、清涼寺の始まりとされている。現在の堂宇は江戸時代の建立。多宝塔の裏に源融の墓である宝篋印塔や嵯峨天皇檀林皇后などの碑がある。
●遍照寺……37番歌参照。
●きてみる人……「来て」「着て」を掛ける。
●かはべ……河辺。川のほとり。
●かはせ……河瀬。川の中の瀬(川の流れは早いが水が浅く、人が徒歩で渡れるところ)。
●ひまなくて……隙間がない。
●大納言の家……長元8(1035)年より権大納言であった源師房を指すと考えられる。
●いかだし……筏師。筏に乗り、棹をさして川の上を流すのを生業とする者。
●さして……副詞。下に打ち消しの語を伴い、これといって~ない、格別~ない、という意を表す。ここは棹を「挿して」と掛ける。
●殿のあまうへ……頼通の母、源倫子を指すか。倫子は治安元(1021)年、58歳のとき出家した(「入道太相府北方昨日於無量寿院出家」『小右記』2月29日条)。一説に長暦元(1037)年とも(「長暦元年三月十四日於法成寺西北院、有御出家、先度垂尼歟」『婚記』)。
●はせ……長谷。大和国の歌枕。今の奈良県桜井市初瀬町。初瀬山、巻向山、三輪山の連山、天神山、鳥見山の連山の三方を山に囲まれた峡谷。古くは伊勢に向かう交通の要衝であり、長谷寺の観音信仰が流行し始めてからは、女婿の長谷寺詣は盛んに行われた。和歌では「初瀬」とも呼ばれる。桜の名所とされ、花と共に詠まれたり、秋は入相の鐘と共に詠まれたりした。
●あじろ……網代。川に杭を並べて打ち、その杭に簀を渡して簀に堰かれた魚を捕る仕掛け。初冬、宇治川や田上川で氷魚を捕るのに用いられた。「夜」と「寄る」を掛けることは多くなされた。
●いは浪……岩波。岩にうちかかる波。
●遍照寺……37番歌参照。
●いとどしく……さらにいっそう、ますます。
●もみぢちりしく……「ちりしく(散り敷く)」は一面に散らばること。
●ききわく……聞き分く。聞いて判別する。
●しぐれ……晩秋から初冬にかけて降るにわか雨。
●うちかさね……「打ち」は動詞の前に付けて、語調を整えたり意味を強めたりするのに使う。
●いくよの風……幾夜の風。
【参考】
『後拾遺和歌集』第十七、秋下、382
「落葉如雨といふ心をよめる
このはちる やどはききわく ことぞなき しぐれするよも しぐれせぬよも」
『袋草紙』
「源頼実は術なくこの道を執して、住吉に参詣して秀歌一首詠ましめて命を召すべきの由祈請すと云々。その後西宮において、
木の葉散る 宿は聞きわく 方ぞなき しぐれする夜も しぐれせぬ夜も
と云ふ歌は詠むなり。当座はこれを驚かず。その後また住吉に参詣して、同じく祈請す。夢に示して云はく、「秀歌は詠み了んぬ、かの落葉の歌に非ずや」と云々。その後秀逸の由謳歌せり。また其の身六位なる時夭亡すと云々」 |