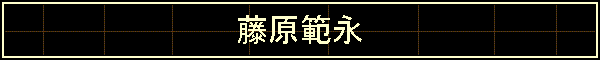事跡:
正暦3(992)年、出生
寛弘6(1009)年1月10日、蔵人所雑色
寛弘8(1011)年6月25日、一条帝崩御、御法での焼香が決定
7月8日、天皇御葬送の際、所衆四人の中に加わる
長和3(1014)年以前、正六位
長和4(1015)年、非蔵人
長和5(1016)年11月25日、任六位蔵人・この頃勧学院学頭
寛仁元(1017)年6月26日、丹生・貴布祢二社の奉幣で、貴布祢使となる
8月20日、修理権亮に任ず
寛仁2(1018)年3月13日、石清水臨時祭で陪従を勤める
寛仁3(1019)年1月23日、式部大丞
4月7日、叙従五位下
寛仁4(1020)年3月28日、甲斐権守
治安2(1022)年7月24日、法成寺供養に弟永禅と参会
治安3(1023)年2月12日、春宮少進
万寿2(1025)年2月20日、伯耆守見任、この年任官か
8月7日、上京
8月11日、前司資頼不与状を右大臣実資に提出
長元3(1030)年1月28日、叙従五位上(治国賞)
長元4(1031)年11月25日、叙正五位下(春宮御給)
長元6(1033)年2月16日、白河院子日遊に参加
長元8(1035)年3月27日、上東門院法華八講に参会、頼通の御捧物を献進
長元9(1036)年7月17日、叙従四位下
長暦元(1037)年1月23日、尾張守
長暦2(1038)年2月19日、典薬允源致親、隠岐国に配流、贈答す
長久元(1040)年、能因の初度伊予下りの際に離別歌を詠ず
長久2(1041)年2月12日、『弘徽殿女御十番歌合』出詠
長久4(1043)年1月24日、叙従四位上(造安福殿賞)
寛徳2(1045)年4月28日、大膳大夫
永承2(1047)年ごろ、『左京大夫道雅障子絵合』に参加
永承2(1047)年ごろ以降、『橘俊綱伏見亭歌会』開始
永承4(1049)年11月9日、『内裏歌合』で子息良綱の代作
永承5(1050)年6月5日、『祐子内親王家歌合』
11月、『修理大夫俊綱歌合』
天喜元(1053)年、8月19日、但馬守
天喜4(1056)年2月22日、正四位下(自四条宮幸一条院左大臣家司賞)
4月30日、『皇后宮寛子春秋歌合』但馬守見任
康平元(1058)年2月5日、外記政あり、禄を賜る
8月、『右近少将公基歌合』
康平2(1059)年2月11日、前但馬守見任
10月12日、関白頼通、法成寺無量寿院および五大堂供養、
範永子息良綱と参会
康平4(1061)年11月22日、頼通、法成寺にて七十賀、参会
康平5(1062)年1月30日、阿波守
春、高階経重陸奥守下向に際し贈答
康平6(1063)年10月3日、
『公基朝臣歌合』判者
康平7(1064)年6月13日、摂津守に遷任
治暦元(1065)年6月13日、紀伊守補任(『勅撰作者部類』)
治暦3(1067)年2月、これまでに紀伊守辞任か
延久3(1071)年ごろ、出家するか。津入道と称す
延久4(1072)年ごろ、家集が完成するか
承保2(1075)年ごろ、没するか
津入道と号する。小式部内侍との間に娘をもうけている。後一条朝〜後冷泉朝に至る頼通の関白時代に歌壇で活躍、和歌六人党の中心的人物として受領層歌人の間で重鎮であった。相模など女流歌人らとの広範な交流も知られる。後拾遺集以下勅撰集に28首入集、続詞花、万代集に6首ずつ、玄々集、後葉集に1首ずつ入集。
家集:
伝本は宮内庁書陵部に甲乙2本が現存。
甲本(501・305) 188首
乙本(501・185) 56首
巻頭より28首はほぼ一致するが、それ以降は乙本で大部分が欠落。
『袋草紙』
道雅三位は、帥大臣殿の息なり。八条の山庄の障子の絵に、歌合に読ましめて撰びて書かしむ。作者は、兼房・家経・範永・経衡・頼家等なり。
「江記に云はく、「往年六人党あり。範永・棟仲・頼実・兼長・経衡・頼家等なり。頼家に至りては、かの党頗るこれを思ひ低(かたぶ)く。範永曰はく、「兼長は常に佳境に入るの疑ひ有り」。これ経衡の怒る所なり」。また云はく、「俊兼の曰はく、「頼家またこの由を称す。為仲、後年奥州より歌を頼家の許に送る。『歌の心を遺す人は君と我なり』と云々。頼家怒りて曰はく、『為仲は当初(そのかみ)その六人に入らず。君と我と生き遺るの由を称せしむるは、安からざる事なり』」」と云々。
『十訓抄』第一、57
但、遍照寺にて山家秋月と云ことをよみけり。其中、範永朝臣蔵人たる時のうた、
住人もなき山里の秋の夜は月のひかりもさびしかりけり
とあるを、件の懐紙の草案どもを、定頼中納言とりて、公任卿の出家して籠居させたまひける、北山長谷といふ所へ見せにつかはしたりければ、範永がうたをふかく感嘆して、此歌のはじめに、「範永何人にや。和歌其程をえたり。」と自筆にて書付られたりけるに、範永聞て感にたへず、其懐紙をとりて錦袋に入て、宝物として持たりけり。これこそ称美のかひありてきこゆれ。かやうのことは、よく至たる人のすべきとぞ。
|