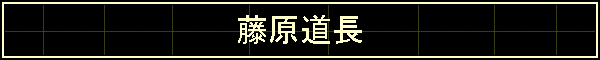藤原兼家の五男。母は藤原中正女時姫。
若年のころは父兼家の威光により昇進しているが、兄の道隆・道兼らに比べて影が薄かった。30歳のとき、父や兄の相次ぐ死により政界のトップの座を手に入れることとなった。甥の伊周との政争に勝ち、娘の彰子と中宮定子の一条天皇をめぐる争いも定子の死によって終わりを告げ、以後30年の長きにわたって政界の頂点に立ち続けた。
後宮政策においても、彰子を初めとする娘たちが皇子を生んだことで、確固たる外戚の地位を築くことに成功した。有名な「この世をば我が世とぞおもふ望月の欠けたることもなしと思えば」の歌は、晩年の道長の満足を十分に言い表している。
自身は関白には就かなかったが、日記に「御堂関白記」がある。
ここに着目!
 | 稀代の幸運児の業績 |
道長は、平安王朝時代を代表する政治家と考えられている。娘3人が后となったときに詠んだ上の歌はつとに有名だ。しかし、道長の政治家としての業績は何なのか、改めて挙げようとするとはたと困ってしまう。
道長は幸運児だったと言われている。藤原兼家の五男だから、上には摂関になり得る兄が二人いた(あとの二人はいわゆる庶腹のような存在で、問題にならなかった)。にもかかわらず、兄は二人とも長徳元(995)年、ふた月のうちに亡くなった。その年は疫病が流行しており、公卿は全部で8人死んでいる。若い道長が浮上するのは当然のことだが、姉の詮子の後押しで、甥の伊周を抑えて内覧の宣旨を受けてしまった。
おもしろくないのは、道隆の子らである。父亡き後、自動的に長子の伊周が座るものと思っていた内覧の地位が、叔父の道兼、道長とスライドしてしまったのである。それでも、伊周が来るべきときを待って堪えていればよかったかもしれない。妹の中宮定子は3年後に皇子を生んだのだから。若い伊周は待ちきれなかった。叔父にしてやられたという思いもあったろう。翌年、同じ家の女に通っていた花山法皇に矢で射かけるという事件を起こし、それがもとで左遷されることとなる。伊周が中宮定子の後見として関白になる夢は、断たれたわけである。道長が幸運だったのは、自分の地位を脅かす者が勝手に自滅してくれることだった。父祖たちは陰謀を仕組まなければ(異論はあるが、一般にはそう考えられている)政敵を葬ることができなかったのに、道長の場合は自分の手を汚す必要がなかったのである。伊周らは赦されて都に帰ってくることはできたが、もはや昔の勢いは戻らなかった。道長は娘彰子を一条天皇のもとへ入内させ、中宮定子は若くして亡くなり、彰子は皇子を生む。偶然はほとんど道長に微笑んだことになる。
そうした権力闘争とも言えないようなことどもの合間に、道長はオリジナルの政策らしいものを出して、それを積極的に押し進めようとしたか? 悲しいことに、平安時代の中でも最も栄華に満ちた生涯を送ったこの幸いびとは、自分を取り巻く貴族のためにも、貴族社会を支える庶民のためにも、目新しいことをしていない。
ふつう公卿たちは、陣定と呼ばれる会議に出席して、国政上の事柄を審議する。即位・大嘗会・改元、対外関係、年中行事の執行、叙位・任官・除目、神事・仏事、諸国申請雑事など、あらゆることがこの会議で裁定されたという。だが、これらは貴族たちがみずから発案しているわけではない。儀式的なことは時期が来れば段取りを考えるというだけのこと、叙位や任官でさえ時期は決まっている。そうでないのは、対外関係と諸国申請雑事くらいである。
その対外関係も、遣唐使を中止して以来、正式に中国(宋)と国交が開かれていないために、政府が率先して貿易を行うということはしていない。宋の商船などが到着すると、その扱いを審議するといった程度のことをしていたにすぎない。諸国申請雑事はどうか。これは地方にいる国司たちの要望書などを議題として審議するもので、たしかに儀礼的ではない分、ほかの案件よりはましであろう。ただ、これも国司の要望に許可を与えるというような受け身が基本形で、道長が音頭をとって全国の国司に命令する、という類のものではない。
結句道長は、娘の入内や立太子のことなど、権力の根本に関わること以外は何もしていないと言わざるを得ない。中年以降、神事や仏事に精を出しているが、これはどうやら体の不調のせいらしく、単なる個人の救済を求めてのことである。寛弘四(1007)年、道長が金峰山に埋めた経筒は江戸時代に出土して現存しているが、そこに刻まれた文字は、簡単にすれば極楽浄土へ行きたいということである。皇子を生まない彰子のことも念頭にあっただろう。道長の頭の中に、一国の長としての自覚はない。こういう人が政治を行っていて、よく戦乱にならなかったものだと感心させられるだけである。 |